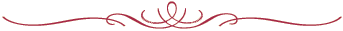
| リクルート事件の経緯考 |
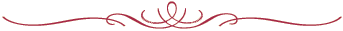
(最新見直し2009.3.15日)
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
| 「★阿修羅♪ > Ψ空耳の丘Ψ55」の吐息でネット右翼氏の2009.1.28日付け投稿「〔メモ〕怪死した朝日新聞論説委員と神奈川県警の接点(低気温のエクスタシー) 」、たむたむ教授の「リクルート事件の概要」その他を参照する。 リクルート疑獄事件は、神奈川県警の捜査ニ課の警部が、神奈川県警の盗聴事件を取材していた朝日新聞の鈴木啓一・社会部記者に”「川崎駅前のリクルート・テクノピアを調べた方が、盗聴事件より大きなスキャンダルがものに出来る」”とリークし、以下のように進展していったものである、と判明しつつある。 藤原肇著「平成幕末のダイアグノシス」は次のように述べている。
2009.1.29日 れんだいこ拝 |
| 【事件の概要と歴史的意味考】 |
| 江副浩正氏が創業したリクルート社の関連企業リクルートコスモス(現 コスモスイニシア)社の未公開株を政財官の役職者が賄賂的に受け取っていたことが暴露された汚職事件である。中曽根康弘、竹下登、宮澤喜一、安倍晋太郎、渡辺美智雄など大物政治家が群がっていた。東京地検特捜部は、1989年、政界・文部省・労働省・NTTの4ルートで江副浩正リクルート社元会長ら贈賄側と藤波孝生元官房長官ら収賄側計12名を起訴、全員の有罪が確定した。だが、政治家は自民党の藤波議員、公明党の池田克也議員が在宅起訴されただけで、中曽根や竹下をはじめ大物政治家は誰一人立件されなかった。 この事件は、ロッキード事件に比してダグラス・グラマン事件同様に司直のメスが入らずうやむやにされてしまったことを確認することに歴史的意味がある。いずれも中曽根が深く絡んでいるが、中曽根はいつも免責される。なぜこのようになことになるのか、これを思案せねばならない。誰か国際金融資本の意図を嗅がずに説明できる者が居るだろうか。 |
| 【事件の伏線】 |
| 事件の伏線は次の通り。1983.12月、藤波孝生被告が第2次中曽根内閣の官房長官に就任する。1984.1月、日経連専務理事(当時)が就職協定無用論を打ち出す。3月、各省庁の人事担当者会議で就職協定順守を申し合わせ。1986.9月、リクルート側が藤波被告にリクルートコスモス株を譲渡。10月、コスモス株店頭公開。 |
| 【事件勃発】 |
|
1988年(昭和63)6月、朝日新聞横浜支局のスクープ記事から発覚した。戦後最大級の構造汚職疑惑となり、問題の多い日本の株式市場のゆがみを利用して政・財・官界など特権階級の人々の金儲け主義(錬金術)が白日の下にさらされた。
事件の発端は、川崎市テクノピア地区へのリクルート社進出にからみ、同市助役へのリクルート社の子会社であるファーストファイナンス社の未公開株融資付き売買疑惑であったが、まもなく、リクルート・コスモス株の疑惑譲渡先として元閣僚を含む76人が発覚(小松秀煕・川崎市助役への株譲渡が発覚)。7月、中曽根康弘前首相、竹下登首相、宮沢喜一蔵相ら側に株が譲渡されていたことが発覚。9月、社会党楢崎弥之助代議士が、松原弘・リクルートコスモス社長室長からの贈賄申し込みを公表。スモス社の松原社長室長から、この事件追及をすすめていた社会党(当時)楢崎弥之助議員に500万円の贈賄工作があったとの代議士自らの告発という事態に発展した。この模様はテレビで放映され、世論は沸騰した。10月、藤波被告へのコスモス株譲渡が発覚。真藤恒・NTT会長、高石邦男・前文部事務次官ら側への 株譲渡が発覚した。 1988(昭和63).10月、東京地検特捜部は、リクルート社などを強制捜査、松原室長を贈賄容疑で逮捕。12月、宮沢蔵相が辞任。翌1989(平成元).2月、東京地検特捜部が、リクルート社江副浩正前会長ら2名を贈賄容疑で、日本最大の企業NTT式場、長谷川の両元取締役を収賄容疑でそれぞれ逮捕。2月、鹿野茂・元労働省課長を逮捕。 疑惑が持たれた高級官僚や閣僚たちは、「妻が株をもらった。私は知らない。」とか「家族がもらった、秘書がもらった」と釈明し、当時「妻が、妻が…。秘書が、秘書が…」という言葉が小学生の間にまで流行した。 こうして事件は元閣僚、元代議士、事務次官2名、NTT元会長らをリクルートコスモス社未公開株収受による収賄容疑で起訴及び宮沢大蔵大臣辞任、竹下内閣崩壊というスケールに拡大した。 特に、疑惑のコスモス株を秘書または家族名義を含めて9人の閣僚級政治家が密室の財テク的収受をしていた政府自民党幹部、中でも中曾根前内閣中枢に強い疑惑が集中した。当然、国会の証人喚問などでも追及されたが、多くの「灰色高官」たちの立件は行われないまま、事件は幕引きとなり、結局、戦後の他の大疑獄同様、核心の解明なしで終結、国民の間には、「政治不信」だけが残ることとなった。 |
| 【裁判の様子】 | ||||||||||||||||||
リクルート裁判は、政界ルート、文部省ルート、労働省ルート、NTTルート、リクルート社ルートの5本立てで行われた。 「リクルート事件にかかわる検察捜査の総費用は合計1億5000万円(人件費を除く)」(法務省根来刑事局長の参院法務委員会での発言)とされている。リクルート事件と規模や内容面でしばしば比較される1976(昭和51)年に発覚したロッキード事件の場合は1億7000万円。
費用面では、リクルート事件の方がロッキード事件を下回ったが、両事件発覚時の物価水準を考慮すると、2000万円の差は逆転し、さらに開くことになる。
|
| 【藤波氏の裁判闘争】 | ||||||||||||||
藤波氏は、裁判闘争に向かった。次の経緯を見せている。
|
| 【藤波氏の裁判闘争】 | |
|
2003.3.5日付け毎日新聞の小林雄志記者の「リクルート裁判:事件から14年 政界の金権体質変わらず」を転載する。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)