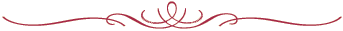
| �y�ё\�p�h��k��b�A�p�h�̔ߌ����\���z |
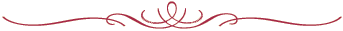
�@�i�ŐV�������Q�O�O�V�D�T�D�X���j
| �y�ё\�p�h��]��k�̔�b�z | ||||||||||
| �@�Q�O�O�Q�D�P�P�D�Q�V���t���ōu�k�Ђ��ؒ��l����c���p�h�Ɩё�������ł���Ă���B�����������ē��o�a�o�o�ł��O�Y�N�V������ɗ��āI�c���p�h�ƃj�N�\����E��������ł���Ă���B��������A���b�L�[�h������ʂ��Č����ɂ߂Ĕᔻ����Ă����c���p�h�̌������Ɏ�����Ǐ��ł���B�{�������ƒ��ڂ���Ă��ǂ����A�䂪�Љ�ɘS�Ƃ��Č`������Ă��颊p�h��͖ԣ�̌��e�ɉЁi�킴�킢�j����ă}�X�R�~�ɓo�ꂷ��@����Ȃ��B�܂��Ƃɐɂ��܂�邱�Ƃł���B�@ �@���āA��c���p�h�Ɩё�́A��ё\�p�h��]��k��̓��e���A���͐��Ԃɗ��z����Ă��錭����ł͂Ȃ��A�^���͋ɂ߂đ�_�����x�Ȑ����I��������g�b�v�E�V�[�N���b�g�I�Ɉׂ��Ă������Ƃ�\�I���Ă���A�ɂ߂ďՌ��I�ł���B����݂ł��A���̖�̉�k���e�̏ڍׂ͓�ɕ�܂�Ă��飂Ɖ]���B �@�ȉ��A�ؒ��l����c���p�h�Ɩё�����~���ɂ��Ȃ���A��������ɓZ�߂�B�i���ǂ݂₷���悤�Ɋ����ϊ��A��Ǔ_�A�i���ς��A��������폜�A���ӂ�ς��Ȃ��͈͂ő����̈Ӗ�����Ă���܂��\������j |
||||||||||
| �@���a�S�V�D�X�D�Q�V���ߌ�V�����A�k���̌}�o�قł��낢�ł����c����s�̂��ƂցA�����O�������̊��O������d�b���������Ă����B���{�O���Ȃ̋��{�����ے�����莟���ƁA�u�ё�Ȃ�������܂��B�c�������Ƒ啽�O����b�ɂ��z���������������v�Ƃ����d�b�̓��e�ł������B��������c���́A�����ɉ]�����B�u��l�����Ƃ����̂̓_���ł��B��K�����[�������ꏏ�ɗ��Ă���̂�����A�s���̂Ȃ�ꏏ�ɎQ��܂��B���������Ă���v�B �@�ߌ�W���A���������u��قǂ͎��炵�܂����v�Ɖ]���āA�P�Q��O���Ƌ��Ɍ}���ɗ����B���̎��A������Ƃ����㒅���N�����B�c���̌�q�����A�K���̌`���ŁA�u����A��čs���Ă��������B�����łȂ��ƁA���{������ė������̐E�ӂ��ʂ����܂���v�Ɠc���̑��ɂƂ肷�����čĎO���肵���B�c���́A�u������v�ƌy���U�蕥�����Ƃ��邪�A��q���͂����͂������Ɗ撣�����B�c���́A�ނ̊��^���ʂ��猩�����A�T�v�u������B�������Ă���B�����܂ŗ���ΎςĐH���悤�ƁA�Ă��ĐH���悤�ƁA��������Ȃ����v�Ɖ]���āA�j�b�R���Ə����B�������ĎO���݂̂��o���������A�ˑR�̗\��ύX�ł������ׁA��K���̎Ԃɂ̓z�X�g���s�݂������B �@�ߌ�W�����A���{����]�Ɩё�ȁi�V�W�j�Ƃ̉���Z�b�g���ꂽ�B���{���͓c���E�啽�E��K���A�������͖сA���A�P�A��傤�A����ɒʖ�E�L�^�W�Ƃ��ĉ������i�O���ȃA�W�A�Ǐ����j�Ɨї�蹁i���Y�}�����A���������j�̓�l�̏�������������B���{���̎������͏o�Ȃ��Ă��Ȃ��B��͖�P���Ԃɂ킽�����B�c������������Ƃ��A�т͗p�ӂ��Ă�����^���W����努�����B �@�ؒ��l����c���p�h�Ɩё�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@��k�̖`���A�т́A����Ƃ̌��܂͂��݂܂�������Ɛ�o�����B����܂͂��Ȃ���ʖڂł���B�݂��ɉ]���ׂ����Ƃ��咣�����܂��Ă������ǂ��Ȃ����̂ł���Ƒ������B�c�������ĞH���A������A�������Ɖ~���ɘb�������Ă���܂��B�����������Ƃ́A��c�����ɘb��������ł���B�ўH���A������A����Ō��\�A���܂����Ă������ǂ��Ȃ�܂��B�{���̗F����܂�܂���̌����肪�ׂ��ꂽ�B �@�c���̃X�s�[�`�ɂ������u����Ȗ��f�v�������Ƃ̏ⓖ���b��ɂȂ�A���̂悤�Ɍ����肳��Ă���B��������A���ݘR�k����Ă�����ސ����čČ����Ă݂�B
�@�����ĎG�k�����X�����A�т́A�����́A�A�C�E�G�I�B�������ƃJ�^�J�i��n��o�������{�����͈̑�Ȗ����ł��B�����{��̕������Ă��܂��B���{�ɗ��w�������Ǝv���Ă���̂ł��棂Əq�ׂĂ���B�啽���A��ł́A�������͂ǂ�����Ă��Ȃ��̐��b�������炢���̂ł����B����ł���B��͂葼�̍��ɗ��w���Ă���������ƒ������A�ўH���A��啽�搶�͗F�D�I�łȂ��ł��ˣ�Ɖ������B��k���̗F�D���[�h���`����b�ł���B �@���̑��A�����̓`���n��I���Q�A���{�̑I�����x���X�ɂ��b�肪�y�Ɠ`�����Ă���B |
||||||||||
�@�Ђƒʃ��̈��A�ƎG�k���I���ƁA�ё͓c���p�h�̖ڂ̑O�ŁA�₨��E���ɂ������B���̎�����E�ɂ������ƐU��B�c���B�̑O�ʼn��x�����������Ԃ�����A�ނ͎������j������悤�ɂ��Ȃ�������J�����B
�@���̔��������ɂ��āA�c����焈Ղ��A���S�ł͂��lj߂���Ǝv�����Ɖ]���B��l�̓G��Ƃ������t�́A������K�₷��O�ɍs��ꂽ�O���Ȃ̃u���[�t�B���O�ŁA���x�������Ă������t���������炾�B�����A�������Y�}�͓��{�ɑ��Đ���ɢ�A�����J�鍑��`�A�\�A�C����`�A���{�R����`�A���{���Y�}�{�{�C����`��̢�l�̓G��Ɛ키�悤�i���Ă����B����A�����v���O���̃L�[���[�h�������B�������A���{�̌R����`�ɂ��ẮA�����K��̓������炳��������A�������̗����������͂��̃e�[�}�ł���B �@�����A�т̌�����o����l�̓G��͓c���̑z���𗠐���̂������B�т͉E��̎w����{���܂�n�ߎ��̂悤�Ɍ�����B
�@�����͎l�{�̎w��܂�Ȃ��������̉E��Ɍ�����ꂽ�܂܁A�c��������悤�Ƃ����Ȃ��B���̎p���ґz�ɒ^���Ă���悤�������B��Ȃ����l�̒�����͊P����������Ȃ��B�c�������ł͂Ȃ��B�啽����K�������̌��t�ɒ��ق��Ă����B�Î�̒��A�т̐������������ɋ������B �@�т͍X�ɘb��i�߂��B�ӊO�Ȑl���̖��O���т̌����甭����ꂽ�B
�@���ɑ��ʂɋ��������̂��A���{�̓����p�@�������B
�@�ނ�̖��O�������āA�т͓c���ɂ����������B
�@���������́A���������b�𐄗�����B�ё͎��̂悤�ɏq�ׂ��̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�ё̘b�͑������B
�@��̑卑�����{�ƒ����̐ڋ߂̍s���𒍎����Ă���B�т͂����]���̂������B
�@�\�A�������ڋ߂��x������͕̂�����B���{�ƒ����Ƃ����A�\�A�ɑ��ėF�D�I�ł͂Ȃ��A�W�A�̓�卑���W�𐳏퉻���邱�ƂɃ��X�N���͐_�o���点�Ă����B�A�����J�͂Ȃ��C���������̂��B
�@�т͏��Ȃ���A�����J�ƃ\�A�̐S����������Č������̂������B
�@�ё̌�����o���͓̂��������_�������B�����ł���悤�Șb�ł͂Ȃ������B �@�������ĉ�k�͏I������B�Ō�̌��t�ŁA�������𐳏퉻���̐����͖��ꂽ�����O�������B���Ԃɂ��Ĉꎞ�ԁB�������ʖ���̂Ŏ��ۂ̉�b�͎O�\���ɂ����Ȃ�Ȃ������B�т̎�����������c���͑傫�������z�����B���������Ɠ`����ꂽ������]��k�́A�O���O�������I�Ȃ��̂������B�i�ȏ�j |
||||||||||
|
�@���̢��b��͋ɂ߂ďd�v�ȃ��b�Z�[�W�������Ă���悤�Ɏv����B������ςɂ��ƁA�H��̐헪�ƁE�ё́A�c���p�h�ɓ������������o���A�������u�I���ĂȂ������Ă��邱�ƂɋC�t���ׂ��ł���B���̏�ŁA��g�b�v�E�V�[�N���b�g�I�S�N�̌v��������悤�Ƃ��Ă���A�Ɠǂݎ��ׂ��ł���B���̎��_�ɂ���Ă�����ё\�p�h��k��̐����������ė���B��p�h�̍��h�I������\�����ɃL�[���[�h���B����Ă���A�Ƃ�����͊ς�B |
| �y�ё̊p�h�ɑ�����X�Ȃ�ʊS�z |
| �@�ё́A�c���p�h�ɑ�����X�Ȃ�ʊS�����������A���̌���p�h�̓����Ɏ����𒍂��ł����l�q����c���p�h�Ɩё�Ŗ��炩�ɂ���Ă���B �@�P�X�V�U�i���a�T�P�j�D�Q�D�S���A�˔@���b�L�[�h���������o�����B���̎����ɖт͍Ō�̓��a�̓��X�𑗂��Ă����B���̌���{�̐��E�͖��\�L�̐�����@�ɒ��ʂ��Ă������ƂɂȂ����B���N�V���A�т͒�����K�ꂽ�^�C�̃N�N���b�g�ɁA��������ۂɉ���ĖJ�߂��l�́A���ɋA��Ƃ݂ȍГ�ɑ����Ă��飂Ɖ]���Ȃ���A�E�H�[�^�[�Q�[�g�����Ɋ������܂ꂽ�j�N�\���Ƌ����Njy�Ŏ��C�����c���p�h�̖����������A�Ƃ���B �@������̃G�s�\�[�h�����̂悤�ɖ�������Ă���B�т͍ŔӔN�܂Őg�ӂ��珑�Ђ𗣂����Ƃ��Ȃ������B�a���ɂ����Ă��ӎ��͂܂��͂����肵�Ă����B�g�ӂ̊Ō��S�����Ă������l�̒��ʖP�́A�т��I�{��N�ǂ��邱�Ƃ����ۂɂȂ��Ă����B�ł́A�т��l���̍Ō�ɐڂ������Ђ͉��ł��������B�������邪�u�O�ؕ��v�v�ł������Ƃ�����������B����͉����������Ă���̂��B�ǂ݉����̂ɁA�т́A�c���p�h�ߕ߂ƂȂ������{�̃��b�L�[�h�����ɕ��X�Ȃ�ʊS�������A�p�h�i�ǂ̋}��N���߂鐭���ƎO�̕��͂Ɍ��������Ƃ��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B �@�؎��̌������̂܂��A�u�т͓c�������b�L�[�h�����Œǂ��l�߂Ă���O�Ƃ��������Ƃ̌o����v�z���烍�b�L�[�h�������ꎩ�̂̐����I�\���𐄗������������̂��낤���v�Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂪ���̑O���̃G�s�\�[�h�ł���A�т͗����̂P�X�V�U�D�X�D�X���ɐ��U����Ă���B |
| Re:�y�ё\�p�h��]��k�̔�b�z | ����� | 2003/03/31 |
| �@�X�q������F���킟�B�ёI���E�ςɂ��Ăł����A�v���Ƃ���������t���Ă݂܂��B�ё́A���̎��_�ɂ����āA��������\�����������Ă���܂��B����𐄑�����̂ɁA�����ȗ��\���̎w���ɏ]��������̂��Ƃ��Ƃ������s�ɋA���A���̑����X�̂��Ƃ��v�Ă������ʁA�{���I�Ƀ��V�A�卑��`�ł����Ȃ��̂ɍ��h�I������M�ԍł����f�̂Ȃ�Ȃ��Љ��`�I�鍑��`���Ƃł���ƈʒu�Â��Ă����̂ł͂Ȃ��ł������B �@����̂ɁA���̎��_�ł́A�\�A�m�ɓG�����ƂƂ݂Ȃ��Ă���܂��B��������ƁA���̃\�A�ƑΗ����Ă���A����Ƃǂ̒��x�܂ŊW�C������̂��A���ꂪ�ۑ�ƂȂ�܂�����͂�C�f�I���M�[���Ⴂ������̂œ���B�������A�J�[�h�Ƃ��Ă͂��̐�D���n�߁A�L�b�V���W���[�̖K���A�����ăj�N�\���K�����������܂��B���̌��ʁA�ł��e���Ȗ��F�ѕV�h�����̍��h���䂦�ɏl������邱�ƂɂȂ�܂��B �@�ނ���A�ё́A��Ղ̕����𐋂����������{�ɔM�������𑗂�܂��B�A����Ƃ̌R���������ɂ���Ȃ���A���a�I���ۋ����I���@���_�ɑ���v�C�f�I���M�[�I�Ɍo�ϔ��W�𐋂�������{��A�]���Ă�����������܂��B���j�I�Ɍq������[�����̓��{�ƒ�g���Ă������Ƃ��A�����̂��߂ɂ��Ȃ���{�̂��߂ɂ��Ȃ�Ƃ������ƕS�N�̌v�ɂ�镶���I���f���m�����Ă����悤�Ɏv���܂��B�v����ɁA�����u���b�N���`�����Đ��������ƌނ��Ă����Ƃ����ʐ^���\�z���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�������A���̃V�i���I�͓��̒����ł��䂪���{�ł��������܂����B���̌�̗��������ƁA�����Ƃ����̃V�i���I�̓O��I�j������Ɍ����������Ƃŕ�����܂��B�������͂��̃V�i���I�̍��_�҂ł������A�������ȍ~�������Ɏ���n���͐e�Ĕh�Ōł߂��Ă����܂��B���{�������ł��B����A�����̓A�����}����ɂ͉����肪�łĂȂ��Ƃ���܂Ş���ł����܂�Ă���܂��B �@�b��߂��܂��B�V�O�N��O���̂��̎��A���{�ɓc���p�h���t���o�ꂵ�܂����B�E�p�h�A�O���E�啽�A���[�����E��K���̕z�w�ł����A�����{�����j��n�g�h�n�����_�ɒB���Ă����̂����̎��ł����B�l���Č���A���ɂ���Ă�������n�_�o�g�̐�㒁���Ȃ�ł͓��p���������Ƃ̏o�����D�l���ł��������Ƃ�������܂��B�F�Ȑ����l���ǂ��ł��ˁB �@������́A���̐��͂���{�̓y���^�Љ��`�ҏW�c�ł͂Ȃ����Ɛ��肵�Ă���܂��B���̊ϓ_������j�����Ă����ƁA�����̐����j�Ƃ̊w��ł͂����ς���ɗ����Ȃ����Ƃ�������܂��B�ǂ�ȓ}�h�̂��̂ł��낤�Ƒ�䏊�̂���ł��[���ł�����̂�����܂���B �@����͂���Ƃ��āA�ё[�p�h��k�Ƃ́A�����̓y���^�Љ��`�҂Ɠ��{�̓y���^�Љ��`�҂��琂�����ɂ���ɂ��Ȃ��������̗��j�I�Ӌ`�[�����̂ł������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ْ������ٔ��������ɂ����m�̊ԕ��̊̒_���Ƃ炷���u�I���͋C���Y���Ă����Ɛ�������܂��B �@�ʔ������ƂɁA���̃j�Z���m����������ɔ@���ɑΉ��������B�j�Z���m�x�̋����ɉ����ċ��萺���グ�l�|���Ă���A���邢�͉A�ɗz�ɉ��l���Ȃ߂�������Ă���l�������Ă܂���܂��B��������������b�L�[�h�����ŒN���ł����X�ɔ��p�h�I�������������A�\���܂ł�����܂���B���̊ϓ_���瓖���̗��Â�������Ƃ����Č������̂ł����A���Ԃ�����܂���B >�u�����v�ȂǂŒ��������钆�����{�́A�E�h�ɂ͕]���������ł����A�v����ɂ��̊ϓ_���炷��u�Ȃ��A���v�̗�����点��悤�ȓ����Η��Ɏ������݂����̂��H�v�Ƃ����^�O������̂ł��傤�ˁB �@������j�ςɂ��A�u�����v�ȂǂŒ��������钆�����{�́A�����Ă̖ёI���E�ςƂ͔��ڂ̌n���ł��B�����{�R���̏��Ƃ�ᔻ����ϓ_�́A�ё���ɂ����R����܂������A�������̖ڐ����Ⴂ�܂��B�����̒������{�̊C�O���炷�鉽�ł�����ł��ᔻ�́A�ʂ̐l��B�ɂ����j�ӔC�Njy�ł���A����͂��Ȃ蓾�菟��Ȃ��̂�����Ǝv���Ă���܂��B���������̘A���Ƌ{���[�s�j�n�����Ƃ͎v�z�������悤�ŁA�ŋ߂͏������菵���ꂽ�肵�ď����̑̐��C���^�����^���������ċ���܂��B��قǃE�}�������̂ł����ˁB |
||
| �@�y�u�����̐헪�I������N�����ё� �c���p�h�Ɩёv �z | |
�@�u���C���@���Ɣj�Y�R�W�v�̂Q�O�O�T�D�P�D�R�O���t���}���̓��e�����u�Q�P���I�W���[�i���v���u�����̐헪�I������N�����ёv�̈ꕶ���Љ��Ă���B�����]�ڂ��Ă����B
|
| �y�u���̖�A�V���ȗ��j���Ђ炩�ꂽ �с\�c����k���Č����� (���x�@����)�v�z | |
�@�u���C���@���Ɣj�Y�R�W�v�̂Q�O�O�T�D�P�D�R�O���t���}���̓��e���ʼn��x���Ȏ����u���̖�A�V���ȗ��j���Ђ炩�ꂽ�@�с\�c����k���Č����������̐헪�I������N�����ё��v�̈ꕶ���Љ��Ă���B�����]�ڂ��Ă����B
|
|
�@�����Ɉ�̈�b������B�p�h�͎A�C���ɢ���f�Ǝ��s����f���A���̌��t�ʂ�����������Ɏ��g�ݖk���ւƔ�B�����̌��ۂ������������Ȃ��ē��X�ƋA�������̂͏O�m�̒ʂ�ł���B�Ƃ���ŁA�����Ō����Ƃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��G�s�\�[�h������̂ňȉ��L���B �@����A���̖ё̓c���p�h�ɑ���u�^���W���v�v���[���g�̈Ӗ���l�X�ɉ��߂��Ă���B������S��������̂͂Ȃ��B������́A�ю�Ȃ��u�^���W���v��n�������ӂ����̂悤�ɉ����B
|
| �y�^���ɂ��āz | |
�@�^���ɂ��āu�w�^���x�`���ؕ������t�����`�v�ihttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/cozy-p/soji.html�j���Q�l�ɂȂ�̂ł����]�ڂ���B
|
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)