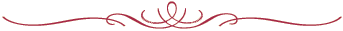
(最新見直し2005.6.12日)
| イタリア政界通信その5 |
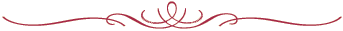
(最新見直し2005.6.12日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「イタリア政界通信その5」を確認しておく。 2005.6.3日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 | ||
| 2021.6.16日、「『鉛の時代』: イタリアのもっとも長い1日、ブラックホールとなった1978年3月16日」。 | ||
| 1978年3月16日、イタリアが歴史の重要な断片を喪失する、『モーロ事件』が起こる2日前のことです。キリスト教民主党のリーダーであるとともに、ローマ大学サピエンツァの教授だったアルド・モーロに、「次の卒業論文の採点が最後になりますね。共和国大統領になられたら、大学にはいらっしゃれなくなるでしょうから」と、助手だったフランチェスコ・トリットが、何気なく話しかけたそうです。するとモーロは「愛情のこもった言葉をありがとう」、といつも通りに微笑んだあと、「しかしわたしは、大統領にはならないと思うよ。おそらくジョン・ケネディと同じ最期をたどることになるだろう」と付け加え、トリットをギョッとさせた、というエピソードがあります。アルド・モーロはその頃、最有力の次期大統領候補とみなされていました(ジェーロ・グラッシ)。当時、モーロの授業を受けていた学生たちの証言によると、事件が起こるしばらく前から、モーロの護衛であるカラビニエリ、オレステ・レオナルディは、殺気だった緊張感に包まれ、普段、学生たちと和気あいあいと冗談を言い合う、気さくな人柄のレオナルディとは別人のようだったそうです。
レオナルディは15年間、モーロの傍を片時も離れない、誠実で、優秀な人物で、モーロだけでなく、モーロの家族からも厚い信頼を寄せられる人物でした。
さて、前項、「蛍が消えた」イタリアを駆け抜けた、アルド・モーロとは誰だったのか、に続き、『モーロ事件』を追いかけたいと思います。以前に書いたことと重複する部分、あるいは割愛する部分があるかと思いますが、お許しいただければ幸いです。 以前の項に繰り返し書きましたが、遥か遠くに過ぎ去った『鉛の時代』の事件の数々を、堂々たるキャリアを持つ、夥しい数の検察官、研究者、司法官、歴史家、ジャーナリスト、作家、政治家、さらにその時代を経験していない若い世代に至るまでが、「絶対に忘れてはいけない」と、情熱と義務感を持って調べ上げ、意味を問い続ける執念は、わたしにとっては脅威的な現象でした。 それは外国人が持つであろうイタリアの人々の、「呑気で陽気でいい加減」という一般的なステレオタイプにはない、黙々と根気強く、精密で鋭い、複雑な一面でもあります。 その中でも、特に『モーロ事件』に関しては、虚無が広がる過去の時間枠に、丹念に調べあげた事実を、多くの人々がひとつひとつモザイクのようにはめ込んでいく有り様が、細密で描かれる巨大な絵画を思わせ、芸術的というか、バロックというか、あるいは集合知というか、ここにイタリアの魂、ひとつの文化の形があるのではないか、とも考えるようになりました。確かに、過去を振り返り続けることは、あまり機能的で合理性のあることではないかもしれません。しかしながら、数多くの犠牲者と衝撃を受けながら、司法の判決に明らかな異常を残す事件の連なりからは、2000年の時を超え連綿と続く歴史に、空白が生まれてしまいます。諸刃の剣(グラディオ)の連続テロという「恐怖」に支配されたイタリアの『鉛の時代』(1969年から1984年あたり、あるいは1992年あたりまで)は、司法が認めたオフィシャルな歴史と、現在に至るまで捜査され続ける歴史、というアンチノミーで構成されたままなのです。おそらく、このような歴史の二重構造はイタリアだけでなく、多かれ少なかれ、どこの国でも見られる現象かもしれませんが、イタリアの場合、その時代に起こった血塗られた事件の数々の、社会に与えた衝撃があまりに大きく、悲劇的でもある。『モーロ事件』に関して言えば、民主主義下にある西側で、『選挙』によって最も大きな勢力を誇った『イタリア共産党』の政権参画が、事件の勃発で事実上反故となったことで、パルチザンたちがレジスタンスで勝ちとった、民主主義の理念は暴力的に破壊され、モーロという人物とともに、歴史そのものが闇に葬られることになりました。 「国よりも人」と言い続けたアルド・モーロがデザインした、『イタリア共産党』と『キリスト教民主党』の『歴史的合意』が実現していたなら、冷戦の緊張下、民主主義における画期的な実験となり、国際社会にも影響を及ぼすイノベーションとして、平和的な解決策になった可能性がありました。ひょっとすると10年ほど早く、『ベルリンの壁』は崩壊していたかもしれない。反対に、結局何も起こらなかったかもしれませんが、それにしてもその実験の結果から、何らかの学びがあったはずです。いずれにしても『モーロ事件』は、検察の捜査、裁判の記録をはじめとする公文書をはじめ、その時代の政治家、軍部関係者、さらには国内外のシークレットサービス=諜報の一挙一動まで、細部の細部にわたって調査され、書かれ、語られ、ネット上にびっしり刻み込まれ、壮大なパノラマとなっています。その膨大な情報量を有するリサーチは、とても『dietrologia(背景論ー陰謀論)』と片づけてしまえるレベルにはありません。そしてその現象こそ、グローバリズムの発端ともなる大航海時代、クリストフォロ・コロンボ(コロンブス)、アメリゴ・ヴェスプッチを生んだイタリアの、誇り高きレジスタンス、と言ってもいいのではないか、と思っています。5月9日(アルド・モーロが亡くなった日)に定められた、今年の「テロリズムで亡くなった方々のメモリアルデー」にちなみ、マフィアの銃撃によって、かつて自らの目前で実兄を亡くしたセルジォ・マッタレッラ大統領は、「テロリズムは68年、69年(の学生と工場労働者の共闘)から生まれたという人々がいるが、わたしはそうは思わない。発展的な議論が行われた重要な時期だった」「極左グループ(赤い旅団)のテロリズムは、レジスタンスで勝ちとった民主主義の自由を、再び重い専制に引き戻そうとする行動だった」と明言したうえで、「忘れないことがモラルである」「鉛の時代の完璧な真相(が明かされること)こそが、イタリア共和国にとって本質的に必要なことである」という主旨の発言をしました。 この発言の背景には、1885年に制定され、2002年まで効力を持った「ミッテラン・ドクトリン」で、亡命者としてフランスに保護され(イタリアは専制国家ではなく、民主主義の自由な国であったにも関わらず、なぜ?)、逃亡していた『赤い旅団』(モーロ事件に関わった)、『継続する闘争』(ルイジ・カラブレーゼ殺害主犯)のメンバーを含めるテロリストたちが、30年以上経った今年2021年5月、改めてフランス当局に逮捕された、という直近の事情があります。そしてその逮捕が象徴的なものに終わらず、彼らがそれぞれの事件に関して、何らかの真実を語ることを、誰もが期待しているところです。 さて、『モーロ事件』に関しては、十分にリサーチを終えた、と自分自身、まったく納得できないのですが、これ以上情報を入れると、消化できない状況に直面するため、ここでいったん整理しておきたいと思います。 まず、事件に関する書籍や犯人たちのインタビューを読んだり、限りなく制作されるドキュメンタリー、講演など、情報を入れれば入れるほど、いよいよ闇が深まり、収拾がつかなくなる、というのが率直な思いです。というのも、テロリストたちをはじめ、当時政権を握っていた政治家たち、目撃者たち、その他のあらゆる当事者たちの証言の詳細に整合性がなく、『薮の中』というか、『密林の中』というか、全体を物語として再構成するロジックが浮き彫りにならないからです。たとえば、モーロ事件が起こった当日から、内務大臣としてタスクフォース(Comitato politico-tecnico-operativo)の総指揮を執ったフランチェスコ・コッシーガ(のち首相を経て共和国大統領)が、『モーロ事件』を語る76分のインタビューがネットにアップされているのですが、彼はもちろん、2021年の現在まで繰り返されるリサーチと捜査、そして細部の検証を、「Dietrologia(背景論ー陰謀論)」と一蹴しています。『モーロ事件』は『赤い旅団』が起こした事件でしかなく、それ以外には何の要素もない、と強調するのです。しかし、インタビューがはじまった途端に「あれ?」と首を捻る発言をしている。「わたしは『モーロ事件』に関わったすべてのテロリストたちに会っている。ただひとりだけ、モーロの殺害犯には会っていない。ごく最近亡くなった人物だ」と、コッシーガは、さも当然のように、さらりと断言しました。この発言の何が問題なのか、というと、司法の場において、モーロを殺害したのは、当時の『赤い旅団』幹部、マリオ・モレッティということになっているのですが、モレッティは2021年現在も元気にセミリベルタ(一応、監視を受けながらの通常生活)を謳歌しており、主要メディアでは、ほとんど取材されることはなくとも、小規模なネットニュースで、時々近況が報告されることがあります。 ではコッシーガは、当初、殺害犯とされ、2013年に亡くなった『旅団』コマンドのプロスペロー・ガリナーリと勘違いしているのだろうか、とも思ったのですが、コッシーガご自身が2010年に亡くなっており、インタビューがネットにアップされたのは2012年ですから、モレッティとガリナーリを間違った、というわけではなさそうです。あるいは2001年に亡くなったジェルマーノ・マッカーリのことを言っているのかもしれませんが、殺害に最後まで反対したマッカーリが、自分の武器をモレッティに手渡したことは、すでに他のメンバーの供述で明らかになっています。また、『モーロ事件』に関わり、殺害現場にも立ち会った、と自ら主張する他の『旅団』メンバーは、現在も皆健在で、かなりリラックスした様子であらゆるメディアのインタビューに答え、テレビのドキュメンタリー番組に出演することもありますから、「じゃあ、その殺人犯とはいったい誰なのか?」という大きな疑問となるわけです。むしろ「背景論」として、モーロを殺害した、と仮説をたてられている、すでに亡くなった、カラブリア・マフィアと近い関係にあった極悪非道の殺人鬼、ジュスティーノ・デ・ブォノに符号するかもしれません。そういう経緯ですから、事件後43年もの間、多くの人々が何年もかかって執拗に調べ上げた事件の詳細を、たった一言で「すべては陰謀論」と片づけてしまおうとする人物にしては、不用意な発言をネット上に残してしまったわけです。 なお、コッシーガは、当事者がほとんど亡くなっていることをいいことに、「イタリア共産党のエンリコ・ベルリンゲルは、3月16日のキリスト教民主党との『歴史的合意』となる信任投票の朝(すなわち『モーロ事件』が起こった日)、首相であるジュリオ・アンドレオッティに、自分たちは野党に残りたいので、投票しないと宣言した」であるとか、「アルド・モーロこそ『グラディオ』の父のひとりである」など、言いたい放題に、このインタビューで発言しています。しかし、この元イタリア共和国大統領は、「都合が悪い質問ははぐらかす、論点をすり替える」として、信用できない人物と見なされ、この長時間に及ぶインタビューも信頼に足らず、と判断され、「殺害犯には会っていない」発言以外、あまり注目されることはありませんでした。ちなみに『モーロ事件』において、「すべては背景論ー陰謀論」と言い放ち、『赤い旅団』の背後には、件の『赤い旅団』しか存在しない、と言い続けるのは『赤い旅団』のメンバーたちも同様です。 |
||
| 明かされても、ミステリーであり続ける秘密 | ||
| ところで、「背景論ー陰謀論」に関してですが、さまざまな事象に絡んで、日常的にSNSに流れてくる、裏付けがなく、あるいはあったとしても、それが信頼に値するとは思われない情報源の場合は、どんなにまことしやかに構築された「陰謀論」であっても、わたし自身はまったく信用しません。ウンベルト・エーコが亡くなるまで言い続けた、ネット上に溢れ、繰り返し語られる、脅威的な「ミステリー」としての偽の情報(虚構)は、権力が人心を撹乱し、誘導するための手段になりうる、というロジックに共鳴するからです。 そのウンベルト・エーコは、2015年にラ・レプッブリカ紙に寄稿した記事で、「本物の謀略は、謎のままに残ることなく、たちまちのうちに暴かれる」と定義しました。その例として、ジュリアス・シーザーの暗殺、フェリーチェ・オルシーニのナポレオン3世の暗殺未遂とともに、1970年のイタリアで企てられたユニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼのクーデター未遂、そして1982年にリーチョ・ジェッリの邸宅で発見された、『秘密結社ロッジャP2』のメンバーリスト(962人)を挙げています。 しかしながら、意外なことに『モーロ事件』に関しては、『旅団』の背後に『Grande Vecchio(黒幕)』がいることを語り続ける人々を、エーコはその記事で批判的に論じてもいるのです。これはおそらく、司法で判決が出ているにも関わらず、何十年にも渡ってリサーチが続くことには発展性がない、とエーコが見なしているからでしょうし、『モーロ事件』に深く関わったとされる『秘密結社ロッジャP2』や、国内外の諜報が、そもそも本人たちが進んで真実を明かすことのない秘密組織であり、その、明かされることがないであろう秘密を追い続けることは徒労である、という意図かもしれません。ただし、ロッジャP2の支配者であったリーチョ・ジェッリは、意外と秘密主義でもなく、亡くなる数年前のイギリスメディアのインタビューで、遺言ともいうべき『モーロ事件』に関する多くの暗示を残しています。晩年のジェッリは、国内外の政治経済権力の、謀略の中枢に存在し、指揮をとった自らの人生をハリウッドに売り込みたい、と考えていたそうで、モーロがデザインした『歴史的合意』に関して、強い反意を明かし、『モーロ事件』を巡る、それこそ「背景論ー陰謀論」をフィクションに仕立てた映画、『Piazza delle cinque lune(5つ月広場)』に、好意的に言及していることは、興味深いことです。 | ||
| さて、2021年の段階で「もはや何ひとつ謎はない」と言われる『フォンターナ広場爆破事件』同様、『モーロ事件』の各シーンの詳細も、ほぼ明らかになっている、と考えてもいいかもしれません。「この事件にはミステリーはない。あるのは秘密だけだ」とも言われますが、謎だと思われていた背景は堂々と語られ、知ろうと思えば、誰でもアクセスできる膨大な資料が残されているにも関わらず、真実は相変わらず秘密のまま、時の向こうに置き去りにされたままです。しかも、その各シーンの詳細をひとつに繋ぐ糸は、肝心なところでプツンと切れてしまう。
現在、司法の場において、オフィシャルとされる事件の再構成は、79年、まず最初に逮捕された『赤い旅団』のメンバー、ヴァレリオ・モルッチ、アドリアーナ・ファランダ(CIA、モサドとも付き合いがあったKGBの元スパイの教授の娘の家で、自首とも思われる不自然な経緯で逮捕)の自白が元になっています。その自白は、『キリスト教民主党』の機関紙、イル・ポポロ紙主幹の協力で、獄中で書かれた『メモリアル・モルッチ』と呼ばれる300ページほどの原稿が元となっていますが、さまざまな状況証拠と齟齬を起こすうえ、モルッチの供述記録を聴くと、最も重要なシーンの事実関係を尋ねられると「覚えていない。記憶にない。分からない」を繰り返しているのです。
そのモルッチを含め、ほとんどの『旅団』主要メンバーたちが何冊もの本を出版しており、「弱者のために」と多国籍資本による帝国主義に支配された国家を転覆することを企てた若者たちが、自らの思いを饒舌に語る、それぞれの革命物語は、その専制指向、暴力性を強く否定したとしても、それなりにドラマチックです。しかしその、一種ロマンティックで南米の小説を彷彿ともさせる情緒的な感性は、『モーロ事件』の精度、完成度、残虐性とかけ離れすぎています。
レオナルド・シャーシャは、事件のわずか3ヶ月後に脱稿された『Affaire Moro(モーロ事件)』で、「自虐ではあるが、(わたしは)すべてが正確で、時間通り(に動く)、効率的なイタリア人を知らない。正確さ、几帳面さ、効率性は、一般的なイタリア人にとっては関係ない、あるいは価値のない、異質の、あるいは何かを保護するための異民族の性質と見なされている」と書きました。 「機能しない研究所、ひどい扱いを受ける、あるいはベッドが足りない病院、遅れる汽車、離陸しない飛行機、実現しないフェスタ。『これがコーザ・ノストラ(われわれなのだ)!』と叫ばれることになる。にも関わらず、少なくともたったひとつ機能する『コーザ・ノストラ』があり、いまやこの別称的な『コーザ・ノストラ』に(注意が)向けられるわけだ」(中略) 、「『赤い旅団』は、完璧に機能する。しかし(ここでは、「しかし」が必要だ)彼らはイタリア人なのだ。これは7つの革命を遂行するか、諜報や外国の援助で成し得ることができる、コーザ・ノストラ(われわれの事件)でもある。また、個々人の付き合いはともかく、より伝統的で、効率的な、もうひとつの『コーザ・ノストラ』との(事件の)関係性における疑惑を深めたいわけではないが、このふたつには類似点がある」と、マフィアと『赤い旅団』の類似点をも指摘しています。 現代では、『モーロ事件』に、まさにマフィアの介入が存在していた可能性が、ほぼ明らかになっていますから、シャーシャの直感的分析には驚嘆するより他ありません。 ともあれ、この項では、前項から続けて、レオナルド・シャーシャの『L’Affaire Moro(モーロ事件/1978年)』、マルコ・ダミラーノの『Un Atomo di verità(真実の核心/2018年)』、コラード・グエルゾーニの『Aldo Moro』に加え、セルジォ・フラミンニの『Patto di omertà(沈黙の合意、2015年)』、ロッサーナ・ロッサンダ、カルラ・モスカによるマリオ・モレッティインタビュー『Brigate Rosse(赤い旅団)ーイタリアの物語(1994年)』、エンマニュエル・アマーラによる、事件の期間にイタリア政府と共同で作戦を練った、当時、米国のアンチテロリストのスペシャリストであったスティーブ・ピチェーニックのインタビューを含む『われわれがアルド・モーロを殺した(2008年)』などの書籍を参考にしました。 さらに上院下院議員で構成された『政府議会事件調査委員会』が2017年に全公開した資料の一部、その委員長で下院議員のジュゼッペ・フィオローニの講演、さらにネットに参考資料をアップしている、副委員長の下院議員、ジェーロ・グラッシの講演、各種ドキュメンタリー、『赤い旅団』メンバーのインタビューなども参照しています。 なお、それぞれのシーンにおける詳細は調べ上げられてはいても、それらをひとつに紡ぐ糸が曖昧なことから、気持ちよく、すっきりとしたシナリオの物語が形成されることはありません。研究者やジャーナリスト、歴史家たちが、それぞれに「こうではないのか」、と、有力な証拠、証言を集めて、ひとつの流れを形成したとしても、それらはやはり、すべて可能性、あるいは仮説でしかなく、『赤い旅団』のメンバーが自白を翻す、あるいはフランスに逃亡中だったメンバーが、突如としてその経緯を語らなければ、真実とはならないのです。 そういうわけで、事件を追いかける多くの人々が、「Io so. Ma non ho le proveー僕は知っている。しかし確証がないのだ」と、1974年11月14日に、ピエールパオロ・パソリーニがコリエレ・デッラ・セーラ紙に書いた「このクーデターが何なのか、僕は知っている」という、あまりにも有名な記事の言葉を引用します。そして、パソリーニが「知っている」と書いた、そのクーデターこそが、ウンベルト・エーコが「たちまちに暴かれる陰謀」と定義した、イタリア軍部森林警備隊の支援を受け、ユニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼが率いる極右武装グループ「Xmas」が核となり、イタリア国営放送Raiを占拠。あわや「クーデター成立」寸前に、闇の中からストップがかかったクーデター未遂事件のことでした。余談ですが、パソリーニが記事で言及した、グラディオ作戦下における無差別大規模テロの黒幕のひとりとされ、裁判ともなった(無罪)SID(防衛省諜報局)の局長、ヴィート・ミチェッリ(P2メンバー)は、1974年の段階で「これからは極左グループがテロの中心となるだろう」と語っていたそうです。 |
||
| 『モーロ事件』の背景に蠢くもの | ||
| さて、『赤い旅団』が工場労働者の敵である資本家から、執行部が変わった75年を境に、司法官、ジャーナリストへと攻撃のターゲットを変えたことは以前の項で述べた通りです。しかしなぜ突然、まさしく「国家の心臓部」である『キリスト教民主党』のリーダー、アルド・モーロというヒエラルキーの頂点にまで、そのターゲットを飛躍させる決断をしたのか、という問いに、『旅団』のコマンドたちは「モーロをターゲットとしたのは、いわば偶然の成り行きであり、最も攻撃しやすかったからだ」と供述しています。そもそも彼らは、党のメンターであるモーロ、あるいは党内で権力を振るいはじめたジュリオ・アンドレオッティ、さらにアミントーレ・ファンファーニの3人に攻撃の焦点を絞っていたと言い、「そのうちのひとりであれば、誰でもよかった」と言うのです。しかしモーロとアンドレオッティ、ファンファーニでは、事件の意味が根本的に変わり、国際政治に与えるインパクトも大きく変わります。
それでも『旅団』のコマンドたちは「ファンファーニの家は見つからず、アンドレオッティはあまりに警護が固く、誘拐事件をプログラムできなかった」ため、モーロにターゲットを絞り、「行動を監視していた」、と全員が口を揃えて言い張るのです。
その、『赤い旅団』の攻撃の動機は「国家に戦争をしかけ」「武装政治勢力として、国家に認めさせる」ことであり、「決して『キリスト教民主党』と『イタリア共産党』の『歴史的合意』を妨害するつもりはなく、むしろ自分たちには、あまり関心のないことだった。目的は、すでに逮捕され、裁判がはじまろうとしていた『旅団』創立メンバー(レナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニら)を含む仲間たちと、誘拐したアルド・モーロの交換を、政治勢力と認知された『武装政党』として、国家と対等に交渉することだった」、と供述しています。
つまり、大物であるならターゲットは誰でもよく、やみくもに社会を錯乱させ、その混乱に乗じて革命のきっかけとなる支配権を握りたかったのだ、と「マルクスーレーニン主義」を標榜する『革命家』たちにしては、緻密なストラテジーがまったくない、「ただ暴れて、注目されたい」山賊集団のような供述を繰り返すのです。彼らに言わせれば、犯行を起こした日は、たまたま『歴史的合意』の議会信任投票の日に重なっただけでした。
しかしながら、そのとき刑務所に入っていた『旅団』創立メンバーであるフランチェスキーニは「違う! われわれは、あくまでも『歴史的合意』に反対していたのだ」と語り、さらにはモーロが誘拐された直後に、イタリア政府(フランチェスコ・コッシーガ内務大臣)の要請を受け、ローマを訪れた米国政府のアンチテロリストのエキスパート、スティーブ・ピチェーニックも、冷戦下、「米国はどんなことがあっても、『歴史的合意』を阻止しなければならなかった」とはっきり語っています。さらに、『秘密結社ロッジャP2』のリーチョ・ジェッリは『モーロ事件』が起こったのは、「人々が『歴史的合意』に反対だったからだ。『キリスト教民主党』も『イタリア共産党』も、米国もソ連も、誰ひとり『歴史的合意』を望んでいなかったから起こったのだ」、と「当たり前じゃないか」とでもいうように、インタビューで言及していますから、事件の核に存在する『旅団』コマンド以外の『旅団』メンバーを含め、『背景論』として事件に関わる要素となる人々は、口を揃えて『歴史的合意』の妨害こそが事件の理由、動機だ、と述べているのです。
そこで、以前の項といくぶん重複することになりますが、ここでもう一度、イタリアの1978年の時代背景と、『モーロ事件』に関連する『背景論』の要素を要約しておきたいと思います。
グラディオー冷戦下、欧州各国はCIA 、NATOによる共産主義勢力を水際で堰き止めるグラディオ作戦のターゲット(1948年から)となっており、欧州で共産主義勢力が最も強かったイタリアが、グラディオに賛同する軍部諜報、内務省諜報、極右ネオファシスト勢力共謀の、「オーソドックスではない戦争」に直面していたことは以前の項に書いた通りです。 些少残る公文書によると、NATOにおける共産主義排斥アクションに関わるグループは、1. 心理戦争グループ(新聞、ラジオなど)2. 政治戦争グループ(共産主義国内のレジスタンス支援、民主主義国内の反共産主義者の支援など)3. 経済戦争グループ(貿易の妨害、市場妨害、ブラックマーケット、投機)4. 防衛活動グループ(戦闘員の支援、妨害、破壊、潜入)と、4グループに別れて機能していたそうです。「すべての活動は、複数の国家の反政府グループ、あるいは互いに対立するグループが、複数の国家やグラディオに関わる者たちの支援を受けて遂行されるが、米国のあらゆる機関は(オペレーションの)責任を負う義務はない。もし、その存在が発覚したとしても、尤もらしく、その責任を否定することができる」 、「なお、その秘密オペレーションには、破壊工作、反破壊工作、プロパガンダ、経済戦争、破壊活動、スパイ(潜入)活動、対立する国家の転覆、(その土地の戦士たち、自由主義グループたちの)レジスタンス活動の支援、自由主義の国家における反共産主義者たちへの支援が含まれる。このオペレーションは軍部による武装攻撃ではなく、軍事作戦としてのスパイ活動、防諜、隠蔽、謀略として遂行される」 当時、グラディオのオフィスであった機関は、そう定義しています(エマニュエル・アマーラ)。 秘密結社ロッジャP2ー上記グラディオの非合法網に、イタリアでは『秘密結社ロッジャP2』が全面的に協力し、あらゆる政治ー軍事的性格を持つ謀略の中心となるオペレーションの采配を振るうことになります。支配者であったリーチョ・ジェッリは、72年あたりにこの秘密結社に参入したとされ、69年『フォンターナ広場爆破事件』から実行された、「社会の安定化のための不安定化」を目的とする、連続的な大規模テロにより社会を混乱させる『緊張作戦』ーステイ・ビハインドにおいて重要な役割を担った、と考えられています。 大統領府、シークレット・サービス=諜報、政府、及び内務、防衛、外務、司法などの各省、さらに各政党、銀行、メディアなど、各分野で権力を振るうメンバーが集う『秘密結社ロッジャP2』が、グラディオーCIA、NATO、国内外のファシスト(特にアルゼンチン)、マフィアグループと深い絆を結び、『モーロ事件』のみならず、『鉛の時代』のあらゆる政治暗殺事件、80年に起こった『ボローニャ駅爆破事件』、さらに92年に起こったマフィアによる『検事ファルコーネ暗殺爆破事件』『検事ボルセリーノ暗殺爆破事件』などの事件の背景に暗躍していたことは、現在ではほぼ明らかです。なお、フランチェスコ・コッシーガが率いた『モーロ事件』のタスクフォース(Comitato politico -tecnico-operativo)のメンバーすべてが、P2メンバーで占められていたことが発覚した際、ジェッリは「P2メンバーは軍部、Sismi、Sisdeを含む 諜報局、カラビニエリなどの幹部らがメンバーであったのだから、その幹部で構成されたタスクフォースが、皆P2メンバーになるのは当たり前だ」という、よく分からない言い訳をしています。 ヒペリオンーさらに、『モーロ事件』で重要な役割を果たしたと見られる要素として(のち、検察官フェルディナンド・インポジマート、裁判官ロザリオ・プリオーレが追求)、フランス、パリの語学学校『ヒペリオン』があることを忘れるわけにはいかないでしょう。この語学学校こそが、69年に結成された、『赤い旅団』の前身である、CPM(Colettivo Politico Metropolitano)時代、レナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニ、マラ・カゴールに、「世界を揺るがすような、インパクトのある事件を起こさなければならない」と大胆な武装闘争を煽り、NATOの要人秘書や海外の諜報機関との繋がりを誇示した、金満家らしき謎の人物、コラード・シミオーニがドゥーチョ・ベニオ、ヴァンニ・ムリナリスらとフランスに渡って設立した語学学校です。フランチェスキーニによると、シミオーニはオイルショックが起こることまで予言していたそうです。 このシミオーニという人物を、クルチョ、フランチェスキーニ、カゴールは、信用ならない「スパイ」と見なして、短期間付き合っただけで決別し、その後改めて『赤い旅団』を創立しています。その際、のちに『モーロ事件』の主犯となるマリオ・モレッティ、プロスペロー・ガリナーリ(彼らはシミオーニが秘密裏に構成していた革命戦士「スーパークラン」のメンバーでもありました)も、シミオーニととも消えていた時期があり、いずれも『赤い旅団』がプロパガンダに成功し、その名が極左武装グループとして認識されはじめた頃に、ふらりと舞い戻ってきました。 なお、フランスのレジスタンス運動の英雄であり、有力な慈善家であったアベ・ピエールの孫、フランソワ・トゥッシャーを学長に冠した「ヒペリオン」は、実はヨーロッパのテロリストグループ、たとえば、Eta(バスク祖国と自由)、Ira(北アイルランド共和軍)、Raf(ドイツ赤軍)をはじめ、PLO(パレスティナ解放機構)の一部が情報を交換する、欧州の極左武装集団の一種の国際ロビーとなっていたとされ、欧州の西側諸国、東側諸国の諜報と連帯し、米国、ソ連から独立した『第3の欧州』について話し合いがなされる場になっていたと見られています。しかしながら、同時にCIA、KGB、モサドとの関係が指摘され、実はCIAの管理下にあった、と言われてもいて、『ヒペリオン』はフランスのシークレット・サービスに、常に強力に保護され続けることになりました。実際、イタリア当局者が学校内部で交わされる会話を盗聴しようとしてもガードが固く、まったく埒が開かなかったそうです。 ところで、『冷戦』というイデオロギーの二項対立の時代において、この『ヒペリオン』という語学学校の節操のない有り様が、長い間理解できなかったのですが、ある時「ウォーラーステイン」(川北稔編)を読んでいた際、多少合点がいく、次の一節に出会うことになりました。 「米ソ対立とはいわば見せかけの対立にすぎない」「米ソ対立は、根本的にはアメリカのヘゲモニーを承認した上で、そのヘゲモニーを政治的に安定化するために、他のあらゆる政治的、経済的利害対立を全て米ソ対立、東西対立、資本主義対共産主義の対立へと還元する体制に他ならない」(小論:敵としての友) 。なるほど、そう考えれば、『モーロ事件』の後、79年に殺害されることになる、ロッジャP2のメンバーでもあったジャーナリスト、ミーノ・ぺコレッリが「モーロはヤルタに殺害された」と自ら創刊した軍事雑誌『OP』に書いた内容にも合致するかもしれません 。なお、クルチョ、フランチェスキーニが逮捕された75年以降、『旅団』の執行幹部となったマリオ・モレッティは、身分を隠しての「クランデスティーノー非合法活動」のため、偽のドキュメントを携帯していたにも関わらず、飛行機に乗っても一回も怪しまれることなく、頻繁にパリに通っていたことが明らかになっています。 ロッサーナ・ロッサンダによる獄中でのインタビューで、モレッティは「パリにはしょっちゅう行っていたが、1回もシミオーニには会っていない。彼とは相性が悪かった」と言っていますが、「モレッティはシミオーニが苦手だったかもしれないが、シミオーニはモレッティという人物を高く評価していた」との証言もあるのです。また、シミオーニには会っていなくとも、この謎の人物とともにフランスへ渡った、かつての同志、ヴァンニ・ムリナリス、ドゥーチョ・ベニオには会っていたかもしれません。 その『ヒペリオン』は、78年になって『モーロ事件』の直前、交換留学のオーガナイズを理由にローマに事務所を設立(軍部諜報のオフィスと同じ建物内に)しながら、事件が終わると間もなく、静かに閉鎖しています。『モーロ事件』を追い続けた、『赤い旅団』メンバー捜査の主任検事だったフェルディナンド・インポジマートは、何度もフランス側へ「ヒペリオン」の捜査を要請していますが、シミオーニに近づくことは出来ず、フランス警察の協力を得ることもできなかったそうです。なお、1978年3月16日、『モーロ事件』直後の10:45、校長であるフランソワ・トゥッシャーの夫、サルヴォーニ・イノチェンツォが、『旅団』のコマンド2人とバールで会っていたところを目撃され、裁判に召喚されています。しかしアベ・ピエールの『キリスト教民主党』への圧力(推測)で、イノチェンツォは、ただちに放免となりました(ロザリオ・プリオーレ、シルヴァーノ・デ・プロスペロー)。この、元々は『イタリア社会党』の有力メンバーだった(米国諜報機関との関係が疑われるなどして、党から排斥)コラード・シミオーニについて、のちに政界を席巻した、同じく『イタリア社会党』のベッティーノ・クラクシーが、「彼こそ『赤い旅団』のグランデ・ヴェッキオ(黒幕)だ」と発言しましたが、裏付けが取れないまま、シミオーニは2008年に他界。なお、クラクシーは『秘密結社ロッジャP2』について、「イタリアのメディアの50%を牛耳っていた」など、かなり踏み込んだ内容の発言をも残しています。 |
||
| Petrolioー原油 | ||
| さらに、もうひとつの背景として注目したいのが、『モーロ事件』を追いかけ、『パズル・モーロ』など多くの著作があるジャーナリスト、ジョバンニ・ファッサネッラの、英国機密書類のリサーチでしょうか。そもそも戦後のイタリアは、英国政府の監視下にあったと言われ、『フォンターナ広場爆破事件』の直前、今後イタリアで繰り広げられるであろう「安定化のための不安定化」「オーソドックスではない戦争」としてのストラテジーである「Strategia
della tensioneー緊張作戦」「ステイ・ビハインド」を、イタリアのギリシャ大使館から得た英国情報局の機密情報として、いちはやく報じたのも、英国のThe
Observer紙でした。ファッサネッラは、戦後の英国のイタリア監視の目的を、中東、北アフリカの資源、主に『原油』をコントロールするためであったと考え、1970年「われわれは、イタリア政府が独立し、地中海諸国、中東諸国と交渉することを阻止しなければならない(海外オフィス内文書)」、1976年「イタリアのクーデターを支援するアクション、あるいは破壊(アルド・モーロの政治に対する英国政府トップシークレット文書)」、1977年「モーロとベルリンゲルの海外政治に及ぼす影響は強大。重大な反応を及ぼす可能性がある。イタリア政府は適正な道を歩まなければならない(ローマ、英国大使レポート)」などの機密文書を上げ、詳細を分析しています。中東、アフリカへ続く欧州の玄関にあたるイタリアは、原油政治において、地政学的に重要な位置にあり(もちろん米軍、NATO基地としても重要な位置ですが)、『原油』を巡るイタリアの国際政治に関しては、モーロ以前に遡る必要があるのです。なお、イタリア語でPetrolioは『石油』と訳されますが、ここでは通常、取引市場で使われる『原油』、と訳したいと思います。
戦後のことになります。現在のイタリアの主要エネルギー会社のひとつ、ENIの創立者であり、政治家であった、元パルチザンのエンリコ・マッテイ(1906-1962)が、アングロアメリカンの独占市場であった原油市場を打破すべく、イラク、リビアなどの中東諸国、地中海諸国と直接交渉。産油国にとって有利な歩合を提示することで、市場のモノポリーを切り崩すことに成功し、イタリア独自の原油市場を構築した、という経緯があります。もちろん、マッテイのこのスタンドプレイを、アングロアメリカン勢力は強く警戒していました。そのマッテイが1962年、突然「飛行機事故」で亡くなることになるわけですが、当初から爆弾による暗殺説が囁かれてはいても、当時の捜査では不運な飛行機事故と断定されることになります。それからなんと32年の時を経た、1994年に再捜査が開始され、ようやく飛行機に故意に仕掛けられた爆弾が原因の墜落ということが判明しました。
また、飛行機爆発事件の詳細を追い、スクープとして発表しようとしていたパレルモのジャーナリスト、マウロ・デ・マウロは1970年、1本の電話を受けて出かけたまま、行方不明になっています。そして、やはりこちらも40年後の2011年、「コーザ・ノストラ」のビッグ・ボス、トト・リーナの分身と言われ、のちに検察の協力者となったロザリオ・ナイモが、「デ・マウロがマフィアに殺害されたこと」を明らかにしました。動機としては、エンリコ・マッテイの死の真相を明らかにしようとしたデ・マウロが、掴んだ情報を元に「ある人物のキャリアを破壊する証拠がある」とマフィアをゆすったため、「コーザ・ノストラはゆすりに動じない」と殺害されたと見られます。
なお、マッテイ、そしてデ・マウロ殺害の主犯は、マッテイ亡き後、ENI総裁となったマッテイの長年の宿敵、エウジェニオ・チェフィスと推測されていますが、このチェフィスこそ、『秘密結社ロッジャP2』の真の改革者と目され、75年に殺害されたピエールパオロ・パソリーニ事件の主犯なのだ、と仮説をたてる人々が多く存在するのです(イタリア語版ウィキペディア)。 というのも、パソリーニが亡くなる直前、既存の小説や詩、あるいはジャーナリズムとはまったく違うスタイルで、ライフワークとして書こうとしていた小説『Petrolioー原油』が、ENIを舞台に『権力』と『巨悪』を中核に置いたストーリーだったからです。
『原油』は現在、522ページのメモ・草稿のみが出版されていますが、パソリーニは、カールとカルロという主人公を並行して描き、多国籍企業による国際ロビー、独占市場と闘ったマッテイ、マフィア、ファシストグループ、フリーメイソン(チェフィス)の権力構造を、既成の文章表現にはない、奇抜な、いわばジェイムズ・ジョイス的とも言えるスタイルで書こうとしていました。また、その草稿からは「Eniの閃光(稲妻)」という章がごっそり抜けていることから、「盗まれた」という説が拡がり、その章に「殺害にまで及ぶような、衝撃的な事実が書かれていたのでは?」という憶測が渦巻きましたが、そもそもその章は、はじめから書かれなかった、とも言われます。ただ、マフィアとの癒着で有罪判決を受け収監された、ベルルスコーニ元首相の盟友であるマルチェッロ・デルウトゥリが2010年、「パソリーニの『原油』の盗まれた章を読んだ。チェフィスを強く糾弾する内容だった」と騒いだこともありました。しかしメディアに証拠を求められ、いつの間にかうやむやになっています。
ここで、少し横道に逸れますが、文芸評論家のカルラ・ベネデッティによる、パソリーニの『原油』批評に、次々に衝撃が訪れ、悲劇的な物語が過剰にひしめくイタリアの『鉛の時代』についての、検察官カルロ・パレルモの、次のような興味深い発言が引用されています。
「68年の5月革命に影響を与えた、フランスの著述家、ギー・ドゥボールの「スペクタクルの社会」では、「スペクタクルの社会には、たったふたつの形しかない。ひとつはスペクタクルを拡大するタイプ(米国型)、もうひとつはスペクタクルを凝縮するタイプ(全体主義国型、ソ連型、ドイツナチズム型)であり、前者は「メディアコミュニケーションを中心に置き」、後者は「秘密を中心に置く」と定義している」
。その定義からパレルモは、イタリアを3番目のタイプとし、スペクタクルの拡大と凝縮が融合し、「秘密を含むメディアコミュニケーション」という、非常にソフィスティケートされたスタイルが生まれた、と考えるのです。実際『鉛の時代』は、真実は秘匿されながら、うむも言わせぬダイナミックなメディアコミュニケーションで、市民を断続的な緊張と恐怖へと誘導しているわけですから(意識的な誘導ではないにしろ)、イタリアの市民は、90年にグラディオの存在が明らかになるまで、20年近い月日を、その「拡大と凝縮が融合する、秘密を含むメディアコミュニケーション」に日常を侵食されながら生活していたということです。また、この批評でベネデッティは、パソリーニは『原油』に、パレルモの言う「プロット(拡大と秘密)の権力」、爆弾や飛行機事故だけでなく、「権力のトポス」を表現しようとしていた、と言います。パソリーニが生きた時代、まさに『原油』こそが「権力のトポス」であった、という納得のいく分析です。
さて、『モーロ事件』に話を戻しますが、ファッサネッラは『モーロ事件』の背景にも、『原油』を巡る英国を含める諸外国とイタリアの葛藤が存在していた、と見ています。モーロはマッテイの原油政治を引き継ぎ、外務大臣時代には、その時期を「地中海時代」と名づけ、特にリビアを中心に(当時はリビアの産油量のほぼ100%をイタリアが輸入)、産油国である中東諸国を勢力的に外遊していました。その結果、アングロアメリカンの独占市場において、『sette sorelle(7人の姉妹)』とエンリコ・マッテイが呼んだ、イタリアを第三世界国と見なす、原油大企業の国際ロビーというグレーゾーンを通さずに、マッテイが確保したイタリア独自の原油ルートを維持することに、モーロは成功しているのです。 さらにモーロは、1973年の外務大臣時代、パレスティナ人5人のテロリストが起こした、『ローマ・フィウミチーノ空港爆破事件(34人死亡)』ののち、『パレスティナ解放機構』のメンバーで、当時欧州でテロ組織と認定されていた『パレスティナ人民解放戦線(PFLP)』との間に、『Lodo Moro(ロード・モーロ)』と呼ばれる密約を交わし、イタリア国内での武器の移動を許可することを条件に、イタリア国内では交戦しないことを約束させる、という意外ときめ細かい、アンダーグラウンドな政治をしています。 そうこうするうちに第四次中東戦争が起こり、世界を揺るがした第一次オイルショックに突入することになるわけですが、ここからイタリアは、69年からはじまった「緊張作戦ーステイビハインド」のテロの緊張に加え、2桁(16%~18%)のインフレという経済混乱に陥り、天井知らずに『原油』価格は上がり続けます。街には失業者が溢れ、工場では毎日のようにストライキが起こり、特にイタリア南部の経済打撃は深刻な状況となって、人々は既存の政治にも、経済構造にも信頼を失っていきました。 その時期、ユーロコミュニズムという融和路線を打ち出し、反対し続けていたNATOへのイタリア参加にも譲歩して、飛ぶ鳥を落とす勢いで支持を伸ばしたのが『イタリア共産党』でした。しかし73年に起こった、チリのアジェンデ政権を襲ったクーデターのような状況が、イタリアに訪れることを危惧したベルリンゲルは、党を守るためにも『キリスト教民主党』との『歴史的合意』、というモーロのデザインに身を委ねていくことになるわけです。 その『歴史的合意』に「裏切り!」、と怒り狂った極左グループ、さらには敵対する極右グループの学生たちは、『赤い旅団』が繰り返す殺害やガンビザッツィオーネ(足を銃撃し障害を残す独特の攻撃)に煽られ、大学構内や街の広場、大通りに毎週のように大挙して押し寄せ、絶え間なく挑発してくる警察隊やカラビニエリを相手に乱闘。火を放ち、投石し、銃口を向けるヴァイオレンス・カルトの中、「革命」を連呼します。 このように、77年の学生運動は、市民戦争とも呼べる常軌を逸した騒乱となり、68年の運動とは大きく異なる、闘争の本来の主人公であった工場労働者の現実とは隔絶した、学生たちの欲動と自意識が主役となった運動となりました(たとえばウンベルト・エーコは、拳銃を握る学生が、カメラ写りを意識してポーズをとっていることを喝破)。しかしこの時、平和的に運動した学生たち、文化人たちの価値観が、フェミニズムにしても、献身的に弱者を支援する各種社会運動にしても、現代のイタリアに大きな影響を与えているには違いありません。また、「Né con lo stato Né con le BR(国も、『赤い旅団』も支持しない」という『モーロ事件』の間中、他の極左グループ、あるいは学生たちに叫ばれたスローガンは、この時代に生まれたのだそうです。一方、それまで北イタリアのミラノ、トリノ、そしてジェノヴァを活動の拠点としていた『赤い旅団』はといえば、『キリスト教民主党』、すなわち国家への戦争を仕掛けるために、75年からローマに拠点を作りはじめ、まず、事件の主犯となる、マリオ・モレッティが移動しています。モレッティは74年ごろ、秘密裏にモーロの自宅の近くに住んだこともある、とも言われますが、この説には確実な裏付けが見つけられませんでした。 なお、そのころローマで、偽のドキュメントを8つほど持ちながら、「クランデスティーノー非合法活動」をしていたのはマリオ・モレッティだけだそうで、のちに『モーロ事件』のコマンドのひとりとなるバルバラ・バルツェラーニの家に厄介になりながら、隠れ家となる拠点を探しています。その後、ヴァレリオ・モルッチ、アドリアーナ・ファランダが、トニ・ネグリ、フランコ・ピペルノをリーダーとする『ポテーレ・オペライオ』から『旅団』へ移動。フランコ・ボニソーリがミラノ拠点からローマに移動しています。欧州最大の極左テロリストグループと言われる『赤い旅団』ですが、この頃、身分を隠して完全な非合法活動をしていたのは十数人であり、その執行部の周囲で活動していた仲間たちは、昼間は別の仕事をしながら、夜半に活動を手伝うというスタイルだったそうです。たとえばマルコ・ヴェロッキオの映画、『夜よ、こんにちわ』のモデルとなった、モーロが捕らえられていた人民刑務所だった(と言われる)、モンタルチーニ通りのアパートの所有者であったアンナ・ラウラ・ブラゲッティも、昼間は普通に仕事に出かける二重生活を送っています。 こう書くと、まるで手作りの武装サークルのようにも思えますが、仏ジャーナリスト、マルチェッレ・パドヴァーニは「一種、マフィアのような機構を『赤い旅団』は持っていた。内部のコミュニケーション網は十分に確立され、非合法活動をするメンバーは毎月サラリーを受け取り、それで日常の費用を賄っている。『赤い旅団』は、国家との戦争状態を継続していたが、(他のグループも含め)極左テログループだけで、その時代、だいたい1万人存在し、1000人ほどがレギュラーに活動し、3000人ほどが出たり入ったりするイレギュラー要員だった。その他、極左グループの共鳴者は5000人ほど存在し、グループが必要とする際に、手を貸していた。その構成は、Raf(ドイツ赤軍)に酷似している」とも言っています(エマニュエル・アマーラ)。しかし『赤い旅団』がパドヴァーニが言うように、もはや思想とかけ離れた暴力犯罪集団として、無軌道に、残酷になるのは、『モーロ事件』あたりから名前が現れる、フィレンツェ大学、シエナ大学で教鞭を執り、犯罪学者としてイタリア内務省でも働いた経緯のある、ジョヴァンニ・センツァーニが『旅団』のリーダーのひとりとなってからです。 |
||
| 事件前夜 | ||
| ファーニ通りで事件が起こる直前、『イタリア共産党』が戦後はじめて(正確には戦後から1948年まで続いた連立大政府以来)、政府の信任投票で賛意を示す1978年3月16日の『歴史的合意』を控え、社会には期待とともに、『キリスト教民主党』を支持する保守派、『イタリア共産党』を支持する急進派の間には、不信感、激しい対立による緊張が高まっていました。それでも合意が成立し、状況に慣れることで、その敵対が少しずつ解消されれば、市民の73%の支持を得る、安定した政府が樹立する予定でした。
しかし問題は国内の緊張よりむしろ、連合国からの反意であり、1月12日には、ワシントンから「われわれは欧州の国政にコミュニストが参加することには、まったく賛成できない」とオフィシャルに遺憾が表明されることになります。そしてその翌日の13日には、なぜか諜報機関、Sismi(軍部諜報局)、Sisde(内務省諜報局)の幹部が、コッシーガ内務大臣の腹心である人物に総入れ替えとなりました。
なお前述したように、その時に任命された諜報局幹部たちが、『モーロ事件』のタスクフォース(Comitato poritico-tecnico-operativo)を担う、のちに発覚した『秘密結社ロッジャP2』のメンバーでもありますが、このタスクフォースは国家が運営していたにも関わらず、議事録は結成時のみ、とたったひとつしか残していないそうです(セルジォ・フラミンニ)。また、モーロが教授をしていたローマ大学サピエンツァには、学生としてKGBのスパイが潜入していたことが判明しており、その人物は事件の当日に、ふわっと消えることになります。そのスパイの身分証明書は、のちに検察官フェルディナンド・インポシマートの著書で明らかにされることになりました。
さらにはベイルートに駐在していた、モーロと親しかったSisde(軍部諜報局)の大佐、ステファノ・ジョバンノーネが、事件の1ヶ月前から、「最重要である政治家を狙った、『赤い旅団』及び国際テログループの攻撃予定がある」と注意を喚起していたことに、2017年、『政府議会事件調査委員
会』の委員長ジュゼッペ・フィオローニが言及しています。 ジョバンノーネはパレスティーナと強い繋がりを持ち、ローマのPFLPメンバーから密に連絡を受ける、国際テロ情報を熟知する中東エキスパートでしたから、信憑性の高い情報でしたが、イタリア当局は具体的な対策をとってはいないうえ、この情報を受け、機密文書を廃棄しなかったカラビニエリの大佐が自殺(暗殺?)するという事件も起こっています(ジェーロ・グラッシ)。このときパレスティーナ側は、モーロと交わした密約を維持するためにも、モーロの身柄を保護する意図があったようです。
ところで、レオナルド・シャーシャの82年のレポートには、この頃からモーロの周囲には緊張が高まっていたことが明らかにされています。モーロの運転手であったカラビニエリのドメニコ・リッチ、そして警護責任者のオレステ・レオナルディは、その心配を家族にたびたび話していたそうで、尾行されることが多くなったレオナルディは、事件の前には痩せるほどに心配し、「以前とはまったく違う状態だ」と夫人に漏らしていたそうです。その状況を、たびたび上司に相談していましたが、その上司は相談を無視し続けました。 モーロ夫人も、「警護を担う若者たちには、特別な訓練ができておらず、軽機関銃は車のトランクに入れたままで、咄嗟の攻撃には対応できなかった。警護に関しては、いつも議論されていて、訓練を受けた人材を警護に加えるべきだということを何ヶ月も話し合っていた」と証言しています。 防弾車に関しては、以前からモーロがリクエストしていたにも関わらず、一向に届く気配はなく、一方、ジュリオ・アンドレオッティの車はすでに防弾が施されていたそうです。 事件前夜には、サヴォイア通りにあるモーロの個人事務所に、警察幹部、検察官、Digos(特殊警察)幹部ドメニコ・スピネッリが訪ねており、3月17日(事件の次の日)から、さらに警備を厳重にすることを、モーロに約束しています。 なお、ここで大きな疑問として強調しておきたいのは、16日の朝、前日にモーロを訪れて警護の強化を約束したDigos幹部、スピネッリが、事件現場に9:20にはすでに到着していたことでしょうか。当局に事件が報告されたのは、どんなに早くとも9:05より以前ではないはずですが、Digos幹部はその朝、8.8km離れた場所にいて、しかも交通量が多い渋滞の時間、そんな短時間に現場に急行することは、どう考えても不可能にも関わらず、誰よりも早く現場に到着しています。 この疑問に関しては、2017年の『政府議会事件調査委員会』で、「スピネッリの要請で、われわれはすでに8:40から8:45あたりに、トリオンファーレ(ファーニ通り方面)に向かって出発した」と、スピネッリの当時の運転手が証言することになりました。ファーニ通りの急襲は9:02に起こっていますから、その時間にはもちろん、まだ何ひとつ事件の予兆はありませんでした。(マルコ・ダミラーノ)。 ちなみにスピネッリは、「モーロを安心させるために自宅へ行くつもりだった」という理由でトリオンファーレ方面に向かった、ということですが、モーロは毎朝教会に礼拝に出かけますから、8時40分に出発しても、モーロはすでに家にいないことは分かりきったことでもありました。 つまり、最もシンプルに考えるならば、ジョヴァンノーネの注意喚起ののち、攻撃に備えた武器が使える特殊訓練を受けた警護官を加え、ただちに防弾車が用意されていたならば、イタリアの歴史を変えてしまうような、こんな衝撃的な悲劇は起こらなかった、ということです。モーロが使用していたエレガントなフィアット130 blueはたった120秒の間に蜂の巣になっています。 また、『イタリア共産党』のエンリコ・ベルリンゲルも、イタリア独自のユーロコミュニズムという融和路線に軌道を修正し、政権に近づいたことで、米国だけではなく、ソ連からも危険人物と目されていました。 1973年にはブルガリアのソフィアで暗殺未遂と考えられる自動車事故に巻き込まれ、その際、運転手と通訳が亡くなり、ベルリンゲルは奇跡的に一命を取り止めます。その場で病院に運び込まれそうになりましたが、東の病院が、一種の「墓場」控室であることをよく知っているベルリンゲルは、ソフィアでの入院を拒み、外務大臣であるモーロに直接国有機を要請。そのままイタリアへ戻っています。この自動車事故の一件は、現在でも事故説、暗殺説と意見が分かれますが、このような事件もあった、ということを記しておきたいと思います。 戦後から30年、長期政権を担っていた、その頃のキリスト教民主党内部は、政治システムが錆びつき、右、中央、左と分裂して、互いが互いを憎み合うような状況でもあったそうです。モーロがイタリア共産党との連立政府をデザインしたのは、自らが率いるその政党に生命を与え、イタリア共産党をさらに民主主義システムに近づけながら、まず第一に、市民の主権を守るためでもあった。『歴史的合意』は、経済的にも、心理的にもエマージェンシーだった、当時のイタリア社会にとっては、どうしても必要な平和的再構成だったのです。マルコ・ダミラーノによると、『歴史的合意』政権の首相として、閣僚を率いることになったジュリオ・アンドレオッティは「モーロに、わたしは閣外でも閣内でもいいので、あなたが首相をしてくださいと何度も言ったが、断固として拒否された。閣外にいた方が、貴重な支援ができたと思うのだが」と1978年、3月6日の日記に綴っているそうです。 他方、『歴史的合意』政府の閣僚リストを見たイタリア共産党の議員たちには、その顔ぶれが、前政府からまったくイノベーションされていないことに「エリートによる少数独裁政治になるのではないか」との不満が渦巻き、「われわれはもちろん、有権者たちも許すはずがない」と造反が起こりそうな雲行きとなっています。イタリア共産党最後の書記長となったアキーレ・オッケットも、2018年のインタビューで、「賛成票を投じない予定であった」ことを明かしていました。誰もが、最後の最後に騙し討ちにあうことを警戒していたのです。他に例のない、冷戦下における『イタリア共産党』の政権参画という『歴史的合意』を前に、騒然とした状況下、最後の自由な1日となった3月15日、モーロはサヴォイア通りの個人事務所で、1ヶ月前、極秘で約束を取り交わしたベルリンゲルと連絡を取り合い、さらには不穏な空気に包まれる『イタリア共産党』幹部に、その合意を保証することを誠実に約束し、16日の信任投票が無事に通過するよう、全力を尽くしています。 |
||
| 3月16日 9時2分 | ||
| 薄曇りの、いつもより温かい朝だったそうです。アルド・モーロは、その日樹立する『連立政府』の信任投票のため、5人のカラビニエリ、警察官に警護され、2台の車で下院議会へと向かっていました。その車の中でモーロは、午後の予定となっている、ローマ大学サピエンツァでの卒業論文のディスカッションのため、それぞれの卒論に目を通していたようで、事件現場には、血に染まった卒論が散らばっています。ファーニ通りとストレーザ通りの交差点を通り過ぎようとした9:02のことでした。運転手とレオナルディ、モーロが乗っていたフィアット130blueと、モーロの後に続く3人の警護官が乗ったアルファ・ロメオ(アルフェッタ)は、その2台を追い越し、交差点で突然停車した『赤い旅団』のマリオ・モレッティが乗るフィアット128
biancoに行く手を遮られ、まったく身動きが取れなくなった。『旅団』は、反対車線を走って他の車の通行を遮断するため、あるいはモーロを連れ去るため、と全部で4台の車で犯行に及んでいます。そこに、進行方向左側にある『バール・オリヴェッティ』前の、鬱蒼と茂った生垣の陰から、アリタリアの乗務員のユニフォームを着た、4人の『旅団』のコマンドが突然現れ、凄まじい勢いで発砲。たった120秒の間に、93発の銃弾が発射され、4人の警護のカラビニエリ、警察官はその場で惨殺され、ひとりの警察官は重症を負い、間もなく病院で亡くなっています。その93発の銃弾のうち、モーロの警護官から防御のために発砲されたのは、たったの2発でした。それほど激しい銃撃が繰り広げられたにも関わらず、その時無防備に歩いていた通行人は巻き添えを食うこともなく、モーロは手の甲をかすっただけで、ブルーノ・セゲッティが乗りつけたフィアット132blueに乗せられ、そのまま誘拐されることになったのです。車にはモーロの鞄が5つ積まれていたそうですが、『旅団』のメンバーは、なぜか重要な鞄を知っていて、薬が入ったカバン、そして機密重要情報が入ったカバンのみを瞬時に選んで、モーロと共に持ち去っています。さらに、事件を知って急行した当局、メディアの騒乱のなかで、誰もが「見た」と証言した、置き去りにされた3つのカバンのうち、もうひとつの機密重要書類が入ったカバンのみが、いつの間にか消えて無くなることになりました。現場検証によると、コマンドの中には、93発のうち49発、さらにもうひとり、22発を打ったスーパーキラーが存在したそうですが、そのオペレーションは、きわめて洗練された特殊訓練を受けたプロフェッショナルなコマンドが存在したとしか考えられない、異常とも言える完璧さでした。のちに自白した『旅団』のコマンド、ヴァレリオ・モルッチ、ラファエッレ・フィオリ、プロスペーロ・ガリナーリ、フランコ・ボニソーリによると、彼らが携帯したミトラー軽機関銃は、いざという時に詰まってしまい、たとえばモルッチは、「一時まったく発砲できず、急いで弾丸を入れ替えた」と言っています。しかし120秒の間に、そんな猶予はあったのか。見張りや移動の車の用意を含め、『モーロ事件』に実際に関わった9人(現在では11人、12人と言われます)の『赤い旅団』のコマンドの名前は1990年まで明らかになりませんでしたし、オフィシャルな『事件』の再構築は、マリオ・モレッティ、ヴァレリオ・モルッチ、アドリアーナ・ファランダの自白、つまり犯人側からの供述のみでなされています。そして全員が、実際に銃撃した4人のコマンドのなかに「特殊訓練された者はいなかった」「メンバーで武器を上手く扱える者はいなかった」と強調し、コマンドのひとりであったロベルト・フィオリは「山で何回か銃弾を打ったことがあったが、人を撃つのははじめてだった。怖かった」とまで語っているのです。
たとえば『旅団』創立メンバーのフランチェスキーニは、「われわれがマリオ・ソッシ事件を起こした時は、警護がまったくついていないソッシを市電から誘拐するために(のち、解放)、18人のコマンドが必要だったのに、5人もの警護がついているモーロを誘拐するために、たった9人のはずがない」「だいたい72年の段階(カラビニエリのスパイが『旅団』に潜入し、その時多くのメンバーが逮捕されています)で『旅団』全員が逮捕されていてもおかしくなかったのに、行動を監視しながら、わざと見逃したのではないかと思うふしがある」と語っています。
また、75年にクルチョ、フランチェスキーニが囮捜査に引っかかって逮捕された際、なぜかマリオ・モレッティだけが約束の場所に来なかったことで、「その囮捜査を、モレッティは知っていたのではないか」との疑いを、フランチェスキーニは繰り返し述べ、2017年の『政府議会事件調査委員会』の聞き取りでは、レナート・クルチョが「モレッティはスパイではないだろうか」と先に言い出した、と答えているのです。
このような『旅団』側の発言があるうえ、事件の一部始終を見ていた目撃者(住宅街の朝9時、多くの人々が道を歩いていました)も、キラーは7、8人いたと証言し、現場に駆けつけたDigos(特殊警察)さえも、事件の1時間後「キラーは8人だった」と発表しています。それにも関わらず、時間が経つうちに人数は修正され、5人の警護の方々を銃撃したのは『赤い旅団』の4人のコマンドのみ、ということになったのです。アルド・モーロの実弟であるカルロ・アルフレド・モーロ検察官(パソリーニ事件の担当検察官でもありました)は、あまりに素人離れした、この銃撃の異常を執拗に追求し、検証に検証を重ねて本も出版なさっていますが、やはりオフィシャルには、ファーニ通りには『旅団』のメンバーしかいなかったことになっています。しかし、どんなに「犯人は『赤い旅団』だ! それ以外にはありえない」と連呼され続けても、事件の状況に、それこそありえない疑惑と謎が残るため、それからの43年間というもの、検察官、司法官をはじめ、ジャーナリスト、歴史家、政治家の方々に、詳細の詳細に至るまで根気強く背後関係が調べ上げられることになるわけです。『モーロ事件』の調査をし続ける、『政府議会事件調査委員会』の副委員長、下院議員であるジェーロ・グラッシは、「あの朝、現場は超満員だった。通行人、居住者、証言者、カメラマン、シークレット・サービス、マフィア、軍部関係者・・・。そこに『赤い旅団』もいた、ということだ」と、たびたび発言しています。
さて、詳細に入り込むと、あまりに複雑なため、なるべく細部は省略したいと思いますが、ファーニ通りを巡る検証結果が衝撃的で、それが本当であるならば、手の込みようが理不尽きわまりなく、関係のないわたしまで怒りが込み上げてくるほどなので、断片のみではありますが、ざっと記しておきたいと思います。なお、ファーニ通りの襲撃に関係したと推測される人物の名前、出自は、その場にいたとされるスーパーキラー以外は明らかになっています。また、いずれの仮説も、すべて捜査記録、裁判記録などの公文書、あるいは『政府議会事件捜査委員会』のレポートとなって残る資料、検証から導かれたものです。
まず、前日3月15日の夕刻、ベイルートからジュネーブへ向かう予定とされていたリビアの飛行機が、人知れずローマ、フィウミチーノ空港に着陸しています。4人の人物が乗っていたとされるその飛行機がコンタクトをとったのはSismi(軍部諜報局)の局長で、コッシーガ内務大臣が率いるタスクフォースにも名を連ね、83年に逮捕された(健康上の理由で即刻釈放)、ジュゼッペ・サントヴィート大佐(P2メンバー)でした。この飛行機に誰が乗っていたのか、明らかな情報はありませんが、きわめて高度な軍事特殊訓練を受けた戦闘員、あるいは海外諜報員、テロリストが乗っていた可能性が指摘されています。つまり、ファーニ通りのスーパーキラーたちは、このリビアの飛行機に乗ってやってきた、との仮説です。飛行機は事件の直後、3月16日の10:05に離陸しています(イル・ファット・クォティディアーノ紙)。
さらに事件の当日、モーロと警護官5人を乗せた2台の車がファーニ通りを通過したのは、当局の無線オペレーターから、「ファーニ通りを通るよう」指示があったからだそうです。その日8:05にモーロは家を出て、いつも通りサンタ・キアラ教会で礼拝を捧げ、それから下院議会へ向かっていますが、ローマの中心部にある下院議会に向かうには、多少回り道となるファーニ通りを通ることは不自然な指示ではありました。それでも運転手であるカラビニエリのドメニコ・リッチは、指示通りにファーニ通りを通過することになります。のち、当時オペレーターを務めた人物から「わたしが指示した」、との確認が取れたにも関わらず、その指示がどこから来たものか、記録一切が廃棄されていたことが判明しました(ジェーロ・グラッシ)。 ところで、事件現場となったファーニ通りとストレーザ通りの交差点には、毎朝花売りのトラックが停車していたのですが、朝、起きるとトラックのタイヤがナイフで切られており、花屋の主人はいつもの時刻に出かけることができなかったそうです。その代わり、いつも花屋のトラックがある場所には、近所の人には馴染みのない、ブルーのオースティン・モーリスが停車されていました。この花屋のトラックについては、アクションの邪魔になるため、前夜にトラックのタイヤをパンクさせに行ったことを、『旅団』が供述しています。また、事件が起こった場所の反対車線側にある『バール・オリヴェッティ』前から、事件の直後、軽機関銃で武装した男女が乗った、ホンダの大型バイクが、逃亡する『旅団』の車を追って、発車したのを見た目撃者が3人存在します。しかし彼らが誰であったのか、いまだ判明していません。 なお、『バール・オリヴェッティ』があった建物は、それこそ作り話のようですが、シークレット・サービス、つまり諜報局の基地であったことが2014年に判明し、事件が起こる以前の数年間閉鎖されていたにも関わらず(閉鎖されてはいても、誰かが常駐し、植物は手入れされていました)、『モーロ事件』の後に再開しています。 ちなみに『バール・オリヴェッティ』は、事件が起こる以前に倒産して閉店した、ということでしたが、「事件当日は開いていた」、とする証言が複数あり、『政府議会事件調査委員会』は、実は『バール・オリヴェッティ』で『旅団』を含めるキラーたちが待機していたのではないか、と推測しています。生垣に隠れていた、という『旅団』コマンドの中には、180mあるプロスペロー・ガリナーリもいて、身を隠すことは困難だったはずだ、との仮説です。しかも事件後の調査により、この『バール・オリヴェッティ』が、長らく武器類の重要な取引の場となっていたことが明らかになり、ペッピーノ・インパスタート(映画『ペッピーノの百歩』の主人公)を殺害した「コーザ・ノストラ」メンバー、同じく「コーザ・ノストラ」のボス、フランク・コッポラ、グラディオーステイ・ビハインドの戦闘員だった大佐、『赤い旅団』メンバー、NAR(極右武装グループ)、ローマのマフィアグループ『バンダ・デッラ・マリアーナ』のメンバーが通っていたという証言があります(ジェーロ・グラッシ)。 |
||
| 見え隠れするグラディオの影 | ||
| 生涯、『鉛の時代』を調査し、機密書類、モーロ夫人が集めたモーロのパーソナルな記録を含める、公文書、裁判記録、マフィア、諜報関係のあらゆる資料を集めたセンター「アーカイブ・フラミンニ」を創設した、元イタリア共産党上院議員、セルジォ・フラミンニは、その朝、事件現場の反対車線(バール・オリヴェッティ側)に、逆進行方向に駐車されていたミニ・クーパーに注目しました。 現場の検証結果から、フラミンニは、このミニ・クーパーの影に隠れ、『旅団』コマンド以外の複数のキラーが存在していた可能性に言及し、現場で通行者によって目撃された、弾倉が長いミトラー軽機関銃を持っていた男が、120秒の間に49発を撃ったのではないか、との仮説をたてているのです。「正確に、落ち着いて武器を操り、(その男が)銃撃の完全な主導権を握る様子が強く印象に残っている。手袋をした左手で銃身を抑え、右手に軽機関銃を抱え、やるべきことがすべて分かっているかのように、狙いを定めていた」 。事件直後、目撃者はカラビニエリにそう証言していますが、その男が誰だったのか、その武器がどこへ消えたのか、現在も正体が分かっていません。つまり、『旅団』の4人のコマンドが犯行時、わざわざ飛行機の乗務員のユニフォームを着ていたのはショー・アップするためや、彼らが供述するように、仲間同士で間違って銃撃するのを防ぐためではなく(彼らはもちろん顔見知りであり、当日は顔を隠していませんでしたから)、『旅団』以外のキラーから間違って銃撃されないためだった、と考えられるのです。このことについては、カルロ・アルフレド・モーロ検察官も指摘しています。しかし2017年の『政府議会事件委員会』で、改めて現場の科学的な検証が行われた結果、49発を打ったスーパーキラーとされた男から発射された弾丸は、ほとんど向かいの住宅に飛び込んでおり、6発のみがアルファロメオに乗っていた警察官に当たった、という結論が出されました。また、この検証で、モーロが乗っていたフィアット130blueの運転手リッチと、レオナルディは、モレッティの車に遮られる前、車が動いている時に銃撃された、という新たな可能性にも言及されることになりますが、いずれにしても、特殊訓練を受けたプロフェッショナルなキラーが存在したには違いありません。ところで、フラミンニが言及したミニ・クーパーは、現場からほど近い、ファーニ通り109番地の建物の住人の所有で、70年にクーデター未遂を起こしたユニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼの極右グループ「Xmas」の元幹部という経歴を持つ、そもそもパラシュート部隊に属していたモスカルディという人物の車でした。この人物はグラディオーステイ・ビハインドの戦闘員としてフィレンツェに派遣されていた、という経緯もあるそうです。そのうえ、この人物が住んでいた建物は、軍部諜報局の社宅としても使われており、その98%を、NATO基地でグラディオ戦闘員を訓練していたストッキという大佐の妹が所有。残りの2%をその夫が所有していました。モスカルディが、なぜ事件当日、自宅付近の道路ではなく、自宅バルコニーから見下ろすことができる、『バール・オリヴェッティ』前に、わざわざ逆方向にミニ・クーパーを駐車していたのか、捜査されることはありませんでした。 「ありえない」奇遇は続きます。ちょうど事件があったその時間、現場をSismi(軍部諜報局)の大佐(P2メンバー、NATO基地でグラディオの戦闘員を指導していた経歴を持つ)が歩いていたことが、かなり時間が経ったのち、明らかになりました。大佐はその理由を聞かれて、「同僚の家に昼ごはんを食べに行く途中だった」と答えていますが、いくらなんでも朝9時から昼食に出かける人は非常に稀なうえ、同僚という人物も「自分はそんな時間に昼食などしないが、突然やってきたので一緒にコーヒーを飲んだ」と答えたそうです。 また、いつも花屋のトラックがあるはずの場所に駐車され、モーロの車の行く手を遮るために、故意に駐車されていた(と見られる)ブルーのオースティン・モーリスは、ふたつの役割を持っていた、と考えられています。ひとつはモーロと警護官たちが乗る車2台が咄嗟に歩道に乗り上げて、前方へ逃げるのを遮るため、もうひとつは別のキラーを隠すためであり、銃撃と同時に大きく振り返り、モーロを守ろうとしたカラビニエリのレオナルディ、そして後方の車に乗っていた警護官ひとりは、このキラーに右側から射殺された、との仮説があります。しかし『旅団』コマンドは皆、左側から銃撃した、と供述しているのです。 もちろん、このオースティン・モリスにも驚愕する背景があるわけですが、所有者はSisde(内務省諜報局)の不動産を運営する(諜報局には財産所有が認められないため)不動産会社(Sisdeのオフィスがある建物の同じ階にある)であり、なんと、その会社が、のちに発覚することになる『旅団』のマリオ・モレッティの隠れ家であった、グラドリ通り96番地のアパートの建物の、ほとんどの不動産を管理していたのだそうです。しかも、その不動産会社は当時、P2のメンバーでもあった警察分署長の恋人であった女性が運営していました。 さらに事件の直後、アパートの窓から急いで写真を撮ったカメラマンが存在しましたが、そのフィルムを恋人である通信社で働くジャーナリストの女性に託したところ、人から人へと渡るうちにいつの間にか消滅することになっています。ところがそれから38年経った2016年に、その時の写真が、文化、政治、経済、地政学ニュースなどを深く掘り下げるサイト、Formiche.netに突然現れることになりました(マルコ・ダミラーノ)。そして公表されたその写真には、マフィアグループ「ンドゥランゲタ」と近しい、冷酷非常な殺人鬼として恐れられたジゥスティーノ・デ・ヴォノに非常によく似た男が写っていたのです。 軍事ジャーナリストのミーノ・ぺコレッリは、1978年、3月28日(モーロの誘拐中に)、自身が創刊した軍事ジャーナル『OP』に「ファーニ通りで殺戮を行った犯人たちは、さらに酷いことを行うだろう。アルド・モーロを誘拐したのは、最高レベルの戦闘特殊訓練を受けたプロフェッショナルたちだ。『キリスト教民主党』のリーダーの車を襲撃するキラーとして送り込まれたのは、広場でリクルートされた肉体労働者たち(『赤い旅団』)かもしれないが、これは心に留めておく必要がある」と書いています。 あわせて、モーロが殺害された後には、「殺害者は、『デ』と肉屋のマウリッツィオとは言わずにおこう」と、ペコレッリは、まるで暗示のような言葉を残してもいます。マウリッツィオが、マリオ・モレッティの非合法活動における戦闘名であることは、すでに周知のことですが、『デ』というのは、実はデ・ヴォノを指していたのではないか、とダミラーノは推測しているのです。 というのも、モーロの解剖写真を見た司祭を含める、何人かの証言者が、遺体に残された、特殊なサインを認めているからでもあり、それは心臓の周囲にバラの花のように弾丸を打ち込んで、出血多量によって、少しづつ命の灯火を消すデ・ヴォノ独特の暗殺の方法で、この殺人鬼が残すサインとして知られていました。 しかしながら、デ・ヴォノは、すでに1994年に病死していることを『政府議会事件調査委員会』が明らかにし、裏付けが取れない状況となっています。なお、別の事件後の現場写真には、2015年に亡くなった、アントニオ・ニルタという『ンドゥランゲタ』のボスに非常によく似た人物も写っており、おそらく彼らは『バール・オリヴェッティ』の常連だったと見られます。 また、これは事件当初から言われていたことですが、現場でドイツ語、あるいはドイツ語アクセントの英語を聞いた、という多くの証言があり、ファーニ通りの急襲に、Raf(ドイツ赤軍)と思われるドイツ人テロリストが関わっていた可能性が指摘され続けています。 事実、『旅団』と明らかに繋がりを持つ何人かのドイツ人テロリストが、事件の数日後、3月21日に、ローマ近郊のヴィテルボで逮捕される、という経緯があり、しかしそのテロリストたちは完全に黙秘権を行使して、ひとことも喋ることなく釈放となっています。いずれにしても、『赤い旅団』が、Raf、PFLPなど、海外のテロリストたちともコンタクトがあったことは明らかなのだそうです(ジュゼッペ・フィオローニ)。こうして現在では、「これは9人とか11人のレベルではない。現場には、おそらく関係者が40人ぐらいはいたはずだ」と考えられている現場は、いわば「グラディオエリア」とでも言うべき状況で、もちろんこれらすべての調査の結果は、もしかしたら本当に、ただの偶然なのかもしれませんが、ここまで偶然が重なるのはやはり異常事態です。 では、以上の調査の方向性が間違っていなかった、と考えて、アルド・モーロという国家の頂点にある人物の誘拐事件の中核に存在し、国家に戦争をしかけ、革命を起こすはずだった『赤い旅団』という欧州最大のテロリストグループとはいったい何だったのか、という、きわめて大きな疑問が残ります。 創立メンバーたちも、マリオ・モレッティも「赤い旅団は、真正である」と強調しますが、知らないうちに操られ利用されたのか、スパイが紛れ込んでいたのか、それとも謀略を知っての共謀だったのか、『赤い旅団』の存在意義が問われる局面です。そもそも『モーロ事件』のコマンドたちは、それぞれが農民の息子であったり、工場労働者であったりと、その時代、甚だしい格差を生んだ多国籍資本帝国主義経済システムに義憤を募らせ、『武装革命』を起こそうと非合法活動に身を投じた若者たちです。その若者たちが、それから43年を経て、十分に年齢を重ねても、いまだに説明のつかない証言をし続けている。 ただひとり、アドリアーナ・ファランダが、「だいぶん時間が経って、ひょっとしたらわたしたちは操られているのかもしれないと考えた」と語っていますが、彼女の証言にも齟齬があり、どの部分が真実なのか釈然としません。 『旅団』メンバーは当初、モーロが毎朝礼拝に行くサンタ・キアラ教会での犯行を考えていたと言いますが、他の市民を巻き込む可能性があるため計画を変えた、と供述しています。しかし人通りはファーニ通りのほうが断然多く、しかも教会の中ならレオナルディのみの警護だったため、本人たちも危険を犯しながら、5人もの警護の方々を犠牲にする必要もなかったのではないか、との疑問が残ります。 考えられるのは、目撃者が多いであろうファーニ通りの方が事件のインパクトが大きく、ショッキングなシナリオとなった、ということでしょうか。 『旅団』のメンバーがアルド・モーロを連れ去って、ストレーザ通りを左折して逃亡したのち、現場に当局者、メディアが急行し、9:28、テレビ、ラジオで第一報が流れた途端、イタリア全土が今までに体験したことがない異様な緊張と恐怖に包まれました。その時代を生きた人々なら、その瞬間の衝撃を覚えていない人はいないほどです。 9:23には、犯人が乗り捨てたフィアット132が、現場から100mしか離れていないリチアーノ・カルヴォ通りで発見され、武装した男女の若者が徒歩で逃げるのを目撃されています。このリチアーノ・カルヴォ通りのすぐ傍のマッシミ通りには、ヴァチカン(P2と強固な絆を持つ、ポール・マルチンクスが総裁をしていたL’Istituto per le Opere di ReligioneーIOR)が所有する建物が存在し、なぜか『モーロ事件』の後、『旅団』のコマンドのひとり、プロスペロー・ガリナーリがその建物内に寄宿していたことが判明しています。 『旅団』のコマンドたちは、ヘリコプターが飛び交い、あらゆる街角で尋問がはじまる中、要所要所で車を乗り換えながら、人民刑務所として準備していた、モンタルチーニ通りのアパートまでモーロを運んだ、と供述しています。しかし、朝の渋滞時間に誰にも見られることなく、車を交換しながら逃げた、というこの供述もいたって不自然で、実は、現場のすぐ傍にあるマッシミ通りのヴァチカン所有の建物内に、諜報の支援を得て、いったんモーロとともに滞在したのではないか、という言説が後を断ちません。 レオナルド・シャーシャは、モーロが誘拐された55日間、ローマで6296ヶ所(全国で72460ヶ所)が封鎖され、6933件(全国で6413713件)が家宅捜査され、167409人(全国では6413713人)が監視下に置かれ、96572件(全国で3383123件)の車が捜査され、150人逮捕され、400人が勾留されたことに触れ、このオペレーションのために、毎日ローマに4300人(全国で13000人)の警官、カラビニエリが動員され、大仰な捜査が行われたことを、まったく意味がなく、間違っていたと糾弾しました。モーロ事件が起こった日は、ローマだけではなく、イタリア全国、シチリアからヴァッレ・ダオスタまで、何が目的なのか判然としないまま道路が封鎖され、しかも、ローマに4300人もの警官、カラビニエリを動員したにも関わらず、尾行調査ができるエージェントをリクエストした警察には、たったの12人ほどしか増員がなかったそうです。当時、ローマの検察局長であった大佐の「あの時のオペレーションは大捜査というよりも、パレードだった」という発言にも、シャーシャは触れています。 そしてこの、「パレード」と表現された、まったく効果がなかったそのオペレーションはつまり、『旅団』に見せつけるためではなく、事件を強調し、新聞、TV、ラジオというメディアで拡散するためだった、と言うのです。 11:30には、内務大臣フランチェスコ・コッシーガの采配のもと、防衛省、警察、軍部安全保障諜報Sisde,、Sismiなどの幹部が招集され、内務省内に事件を解決するための、件のタスクフォース(Comitato politico-tecnico-operativo)が、P2メンバーで構成されましたが、今までアンチテロリストのエキスパートとしてテロリストの捜査に関わっていたメンバーが、その時すべて排除されたことに、多くの人々が疑問に感じた、と答えています。なお、このタスクフォースに米国から招かれたのが、日本の連合赤軍を含む極左国際テロリストによる誘拐事件に関わった経緯がある、当時アンチテロリストのエキスパートであり、のちにベストセラー作家ともなった、優れたストーリーテラーのスティーブ・ピチェーニックでした。 夕刻、コッシーガは22人のテロリストたちの手配写真をメディアに公表しますが、そのうちの2人はすでに収監されており、ひとりはフランスの住人(ここで唐突に現れるのが『ヒペリオン』校長フランソワ・トゥッシャーの夫、サルヴォーニ・イノチェンツォの写真です)、もうひとりは何も関係のない人物だったそうで、早速捜査を撹乱しています。 事件の1時間後には、イタリア最大の労働組合CIGLがストライキに入ると同時に、断固としてテロを糾弾する大集会を開き、ローマの街中にイタリア共産党の赤い旗とキリスト教民主党の白い旗が同時に舞ったそうです。『歴史的合意』が決定したのちも、常に反目しあっていた、イタリア共産党とキリスト教民主党の支持者は、皮肉なことに『モーロ事件』を通じて、はじめて団結することになりました。同時に、ローマ大学サピエンツァでは、『旅団』を支持する学生たちが100人ほど集まって、シャンパンを開けて祝杯を交わしています。 夕刻、アンドレオッティは、イタリア共産党を含む過半数を得て政権を樹立させ、テロリストとの交渉には一切応じないFermezza(断固とした拒絶)における一致団結を確認しました。しかしRaiのニュースで報じられた、この『断固とした拒絶』は閣僚の賛意を得ないまま、アンドレオッティ首相の、ほぼ独断で発表されたものでした。 そしてこの『歴史的合意』は、事件が終わった後、レオーネ大統領の辞任とともに、事実上崩壊することになります。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)