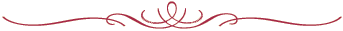
更新日/2021(平成31.5.1栄和元/栄和3).9.7日
| イタリア政界通信その4 |
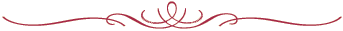
更新日/2021(平成31.5.1栄和元/栄和3).9.7日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「イタリア政界通信その4」を確認しておく。 更新日/2021(平成31.5.1栄和元/栄和3).9.7日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 | ||
| 2020.1.21日、「『フォンターナ広場爆破事件』から50年、『鉛の時代』がイタリアに遺したもの」。 | ||
| 社会に渦巻いた憎悪、恐怖と不信。15年間で377人の犠牲者を出すに至った、イタリアの『鉛の時代』の原点となったフォンターナ広場爆破事件は、2019年12月12日に50年のメモリアルを迎えることになりました。それを機にジャーナリストや検事、歴史家が次々と本を出版。TVでは複数のドキュメンタリーが放映された。半世紀を経てもなお、公正な審判を求め、調査を続行するイタリアの執念を感じると同時に『100000サルディーネ』の出現に遭遇し、『鉛の時代』に打ちのめされた『革命』の魂は、その形を変え、静かに、ゆるやかに生き延びたのではないか、と思うようになりました。 | ||
| はじめに | ||
| このサイトをはじめたころ、現代イタリアに強い影響を及ぼし続ける『鉛の時代』の火蓋を切って落とすことになった、フォンターナ広場爆破事件について考察を試みたのですが、今思い返すなら認識がきわめて甘く、わたし自身、その意味と背景をよく理解できていなかったように思います。この事件における、歴史的に最も重要な要素は、布告されなかった緊急事態宣言と民主主義における市民の力であったということに、今回の50年のメモリアルを経て、ようやく気づくことになった。現在のイタリアの政況は相変わらず波乱含みで、1月26日に予定されているエミリア・ロマーニャ州、カラブリア州という重要な地方選挙の結果如何で政情が大きく変化する可能性があります。その選挙を間近に控え、『サルディーネ』のメンバーたちが、極右政党勢力を水際で食い止めようと、目覚ましい活躍を見せてもいます。そのような動きを背景に、もう一度、フォンターナ広場爆破事件のパノラマを俯瞰し直すことにしました。かつて投稿した内容と異なる部分、あるいは重複する部分が多々あること、そして長い投稿になることを、お許しいただければ幸いです。 ともあれ、60年代後半から80年代のはじめまで続いた『鉛の時代』を生きた学生、工場労働者である青年たち、元パルチザンたちが熱狂した『プロレタリアートによる専制』『武装革命』という理想は、戦勝国が牽引する多国籍企業による自由資本主義経済の支配下にあったイタリア共和国では、当然のごとく打ち砕かれました。当時『革命』を夢見た急進派の青年たちは、繰り返される当局との騒乱にピストルを片手に応戦、騙し討ちにあい、謀略に利用され、激しい非難に晒されると同時に、厳しい社会的制裁をも受けている。もちろん、彼らとは違う時代を生き、生理的に暴力をまったく受けつけないわたしにとって、『武装による共産主義革命』は、現実離れした無謀な野心としか思えませんが、いまだ手練れなく、大人の世界を知らない青年たちが欲動に突き動かされ、世の中に蔓延する不平等と不正に「許しがたい。『革命』しかない」という思いにかられる心理プロセスは、十分に理解できます。また当時、イタリア共産党の目覚ましい躍進のせいで、『冷戦』における欧州のひとつの戦場となったイタリアを生きた当時の青年たちの周囲には、「いずれ訪れる革命の日のために」と、野山に武器を隠し持っていたパルチザンたちや、カストロやチェ・ゲバラとも親しい、大金持ちの『革命家』ジャンジャコモ・フェルトリネッリという、頼りになるパトロンが存在し、国際背景を含めた時代そのものが『革命』を後押ししていた。そして厄介なことにその時代、『革命』という言葉が放つロマンチシズムには、抗えない強い魔力がありました。国境を超えて瞬時に飛び交う、多方向からの情報で窒息しそうな現代とは違い、閉ざされた共産圏のライブな情報がまったく入ってこなかった50年前、かつてソ連や中国で成功した『革命』こそが、労働者たち、貧しき者たちの華々しい勝利、とロマンかきたてられ、「共産主義こそ、この世のユートピア」なのだと青年たちの神話となったことは想像に難くありません。彼らはキューバ革命の栄光と、ほぼ同時代を生きていたのです。 |
||
| はじめから余談なのですが、このところずっと香港の状況を気にかけているわたしは、『鉛の時代』に学生運動をしていた人物と香港について話すうち、ちょっとした口論になりました。「学生たちが大学を占拠して武装で抵抗しなければならなかったのは、当局があまりに非道な挑発を続けるからだ」と全面的に学生たちを擁護するわたしに、自らも過激な学生運動に身を投じていたはずのその人物が「挑発されて、暴力的になるのは過ちだ」と主張するのです。「では、されるがままに、どんなに間違っていても、当局のいいなりにならなければならないのか」と反論するわたしに、「このような事態に陥れば、当局は必ず挑発してくる。それはカンサス大学(68年、非武装学生デモに警察隊が発砲。2人の学生が亡くなった事件)からの決まりごとだ。計算づくの挑発に暴力で抵抗してしまったら、『革命』はそこで終わる。いいかい。どんなにわれわれが武装しようが、現代社会の国家警察、軍隊には絶対に勝てない。武力のレベルがまるで違う。そんなことは、すでに歴史が語っているじゃないか」と彼は言ったのです。
「香港の学生たちと、あなたたちの『革命』は質が違う」と激昂すると、「基本的に、革命はすべて同じだ」と念を押したあと、「僕らの住む世界では、『革命』には時間がかかる。長い時間がかかるんだ。暴力を使ったらそこで終わりだということを、僕らはよく知っているからね。今となっては『非暴力』の闘争を、場合によっては何世代にも渡って継続するしかないと考えている」と、かつての闘士は答えました。
その時の会話はその後も印象に残り、しばらくの間、考えさせられることになりましたが、『6000サルディーネ』の青年の初期の頃のインタビューを見ていた際、「僕らはこの状況における、ヴェトコンのようなものなのだ」というフレーズがサラッと語られ、ハッとしたわけです。
『サルディーネ=イワシ運動』というまったく新しいスタイルをとる、イデオロギーに裏打ちされない、非暴力の市民ムーブメントの中心にいる30歳代前半の青年から、『ヴェトコン』などという言葉を聞くことになろうとは正直、思いもよりませんでした。
なるほど、かつての闘士が言っていたことは、こういうことだったのかもしれない。イタリアにおける『革命』の遺伝子は『非暴力』という形で、現代の若者たちに脈々と受け継がれているのかもしれない。 もちろん、かつての学生運動の極左思想の流れを受け継いだ反議会主義のチェントロ・ソチャーレや、住居を失った人々のために公共スペースの『占拠』をオーガナイズするグループが、イタリアには多く存在します。 しかしイデオロギーからは随分遠い、若い年代の青年たちにまで、パルチザン、『鉛の時代』から続くアンチファのスピリットは受け継がれているようです。 戦後から70年代までの政治的な動きは、敗戦国である日本とイタリアはとてもよく似ていると感じます。イタリアと日本で大きく違うのは、日本は学生運動の終焉を迎えたとほぼ同時期にバブルへと突進をはじめ、イタリアは68年の『フランスの5月』をきっかけに学生と労働者の共闘が生まれ、やがて極端な極右、極左テロリズムが社会を覆う『鉛の時代』に突入したことでしょうか。 しかしよく考えてみると、バブルを経た日本も、『鉛の時代』から一転、ベルルスコーニ政権を経たイタリアも、あまり建設的ではない心理的『喪失感』へ向かった、と言えるのかもしれません。特に2008年のサブプライム金融危機の後は、貧富の格差が広がり、社会が苛立ちはじめた。 わたし自身は、学生運動は悪、政治思想は恐ろしい、政治なんか関係ない、という日本の論調のなかで過ごしたのちにイタリアに住むようになり、若い女性も含めて、誰もが日常的に政治を語るだけではなく、当時の学生運動について肯定的な意見が多くあることに驚きました。 そのうちに、たとえ社会にとっては不快な時代であっても、頭ごなしに『悪』と決めつけず、柔軟性を持って時代の背景を直視することこそ、未来への展望を抱くためにも大切なのではないか、という考えに至った次第です。歴史のあらゆる動向には、善悪では評価できない尊い側面があるのだと考えるようになりました。 そういうわけで、『鉛の時代』の原点、50年前のイタリアを恐怖に突き落とした『フォンターナ広場爆破事件』を再考しなければ先へ進めない、と思うようになり、資料を探しに書店に立ち寄ると、予想通り事件関連の新刊が山積みになっていることに軽い目眩を感じました。 『鉛の時代』の諸々の事件に関する、イタリアの人々の執念は常軌を逸しており、今回、メモリアルを機に出版される予定の本は15冊を超えるのだそうです。この50年の間に、『フォンターナ広場』だけでも100冊はくだらない膨大な数の本が出版されていますから、「すべてを網羅することは不可能」とフェルトリネッリ出版から出版された本を1冊のみ購入した次第です。50年という気が遠くなるような長い年月に渡り繰り広げられた、『フォンターナ広場爆破事件』に関する捜査、裁判調書は数百万ページにも上り、細部に渡って事実上、ほぼ何もかもが明らかになっています。にも関わらず、確実に犯人とみなされる人物たちはすべて『無罪』となっている。CIA、NATOの国際諜報に加え、内務省、軍部、一部の政治家などイタリア国家の中枢が、多くの一般の市民が巻き込まれ生命を落とした重大無差別テロのシナリオを創り上げ、伏線を張り、極右グループがテロリストとして実行したという事実が調査上明らかになっていても、司法が効力を発揮することはできませんでした。何十年も続いた裁判で、ことごとく敗訴となった遺族の方々はどこに怒りをぶつけたらいいのか、50年という歳月を必死に闘ってこられた。現在、遺族の会の方々は、イタリア各地の学校や機関を訪ね、事件と経緯を語り継いでいらっしゃるそうですが、今回のメモリアルでは、遺族が望むのであれば、もう一度上告できるのでは?という声も上がりました。何よりこの事件からはじまる『鉛の時代』は、冷戦下という特殊な時代ではあっても、『国家』というものが、表面からは窺いしれない背景を秘めることもありうる統治機構であることを物語っているかもしれません。いずれにしても大雑把に見るなら、冷戦後の世界が中東諸国の葛藤へと動いていったことも、流れとしては、なんとなく理解できるように思います。 |
||
| 事件の背景 | ||
| ●極左、急進派の動き | ||
| フォンターナ広場爆破事件が起こった1969年のイタリアが、欧州の他の国には類を見ないイタリア共産党ーPCIの目覚ましい躍進のために、冷戦下における欧州のひとつの戦場となったことは前述した通りです。イタリア共産党は、その1年前の1968年の国政選挙で上院30%、下院26.90%と、議会の3分の1近くを担う重要な勢力にまで発展しています。こうして国家機構に食い込んだPCIは、のちにユーロコミュニズムとして展開される穏健姿勢をとりはじめ、戦後掲げた武装革命の旗を徐々に下ろしていくことになったわけです。そしてその姿勢こそが、あくまでも武装革命を目指し続ける元パルチザン、知識人、学生たち、そして工場労働者たちという共産主義急進派から、「共産党は軟弱!」と大きな反感を買うことになった。武装革命の理想を捨てきれない共産主義急進派は、同年、チェコスロバキアに侵攻したソ連軍を厳しく非難、ソ連から一定の距離を置いたイタリア共産党にとことん失望し、たとえば69年の11月に党と衝突し脱退した『マニフェスト』(アルド・ナートリ、ロッサーナ・ロッサンダなど
/ マニフェストは現在も左派の中核を担う新聞として継続しています)のメンバーをはじめ、共産党と袂を分かつ決意をした人々が続出しています。しかし今になって思えば、冷戦下のイタリアが『グラディオ』という国際謀略の真っ只中にあることを、薄々は気づいていたであろうイタリア共産党の中枢は、ソ連との絆を完全に断ち切らないまま、米国をはじめとする戦勝国とも協調の素振りを装う、どっちつかずの穏健路線以外にイタリアを守る方法はない、との判断があったのではないか、とも考えます。イタリア共産党は米国からとことん憎悪されながらも、そのときすでに国民の支持を背景に、国政への影響力を持ちはじめていました。
なお、68年といえば、マルチン・アーサー・キングが暗殺され、世界が震撼した年でもあります。米国ではヴェトナム戦争に反対する学生たちが大規模集会を繰り広げて騒乱となり、欧州では『フランスの5月』が勃発。ほぼ同時に、イタリアにおいても、かつて類をみないほどに学生たちが荒れ狂い、火を放ち、ローマをはじめとする各地の大学で、当局と大きな衝突を起こしています。また、その頃のイタリアには、『保守』富裕層と『革新』貧困層がまっぷたつに分裂する、経済格差が存在していたのだそうです。戦後のイタリアは、米国が推進する欧州復興計画『マーシャル・プラン』の恩恵を受け、『奇跡』とも言われる急速な復興を遂げており、日本同様、冷蔵庫、洗濯機といった家電製品が、『豊かさ』の象徴となっていました。そして、それらの家電を揃えることができる裕福な家庭が多い都市の生活は飛躍的に便利になった。しかし、と同時に富が行き渡らないイタリア南部はいっそうの貧困に見舞われることになり、イタリア南北に、大きな貧富の格差が生まれることになりました。現在のイタリアで難民と呼ばれる人々は、アフリカや中東から、紛争による生命の危険、飢饉や干ばつから誘発される貧困を逃れてイタリアを訪れる人々のことですが、当時の移民、難民と呼ばれる人々は、南イタリアの極度の貧困から逃れ、イタリア半島を北上する家族でした。 南イタリアから、仕事を求めて各都市を訪れる移民の人々は、同じイタリア人でありながら、言葉も伝統も風俗も違う移住の地で、非正規労働の安い賃金でようやく食いつなぐという状況だったと言います。当時の写真を見ていると、住居を持たない移民の人々が、ローマの郊外に違法に建てたバラックが立ち並ぶ、ボルガータ=新開地の風景に出くわすことがあります。 このような社会を背景とした68年から69年にかけて、正規の『労働組合』に加入できない不定期採用の工場労働者、農民、失業者たちが、自らの権利と保障を求め、学生たちと共に立ち上がるわけです。当時イタリア全国の大学を占拠し、警官隊と大規模な衝突を繰り返した学生たちと、工場でサボタージュを繰り広げていた労働者たちは「多国籍企業による、米国型帝国資本主義経済に占領された」社会を、共闘で根底から破壊する『革命』を目標とした激しい抗議運動を、イタリア全土で拡大させていきます。68年を駆け抜けた学生たちにとっては共闘する工場労働者こそが、『革命』における『聖なる階級』でもありました。この大規模な抗議活動から、続く『鉛の時代』の主人公となる『労働者の力(トニ・ネグリ/フランコ・ピペルノ)』『継続する闘争(アドリアーノ・ソフリ)』『赤い旅団(レナート・クルチョ)』の前身となる『CPM』が誕生したことは、以前の項に書いた通りです。実は最近、ジャーナリスト、エンリコ・デアリオの新刊『La Bomba(爆弾)』のプレゼンテーションの際、フォンターナ広場爆発事件の主人公のひとりである、『継続する闘争』のリーダー、アドリアーノ・ソフリの講演を聴いたのですが、クールで知的で唯物論的な無神論者、というイメージに反して、とても人間的で、胸を打たれる発言が多くありました。話を聞きながら、なぜ彼が、当時の学生たちや労働者のリーダーとして人々を魅了したのか、なんとなくわかったように思います。話の内容については事件を追いながら少し後述しますが、一種カリスマ性のある、誠実な印象。しかし激しい一面をも垣間見せる人物でした。 |
||
| ●『グラディオ』と緊張作戦 | ||
| もちろんその時代を生きた人々は、第二次世界大戦以後のイタリアが、共産主義勢力の拡大を食い止めるという目的で、着々と進められてきた国際謀略の管理下にあるなどとは考えてもいませんでした。強いていうならば、ギリシャのようにクーデターが起こるかもしれない、と危惧していた知識人やジャーナリストが、若干存在していたぐらいでしょうか。冷戦下のイタリアに繰り広げられた、NATO、CIA、イタリア軍部諜報、内務省、イタリア国家の中枢の政治家、極右グループ、のちに秘密結社P2、コーザ・ノストラなどマフィアグループが深く関わった国際軍事謀略であるStay behind(ステイ・ビハインド)ー『グラディオ』については、以前の項で触れたので、この項では詳細を省略します。ただし、このグラディオと呼ばれる『安定のための不安定化』『オーソドックスではない戦争』を仕掛けるため、戦後間もない時期からイタリア軍部が米国、英国と秘密裏に通じ、特殊訓練を受けていたことが明らかになっており、その存在がオフィシャルに証言されたのは、『鉛の時代』からはるかな時間を経てベルリンの壁が壊れたのちの1990年、アンドレオッティ首相の国会スピーチであったことは、明確にしておきたいと思います。 ヤルタ会談以降、戦後の欧州に、網の目の如く周到に準備された、この国際謀略『グラディオ』を背景に、イタリア国内ではフォンターナ広場爆発事件を出発点とする『Strategia della tensione(緊張作戦)』が実現されるわけですが、その衝撃がきっかけとなり、極右グループ、極左グループともに荒れ狂い、イタリア国内にテロ、騒乱、衝突が頻発。普通の学生たちまでが過激派と化し、カリブロ35を手に銃撃戦を繰り広げるという流血の混乱、『鉛の時代』の幕が開かれることになります。そもそも『緊張作戦』の当初の目的は、といえば、欧州で最も共産主義勢力が躍進する当時のイタリアで、緊急事態宣言を発令。クーデターを起こし、ギリシャ同様に、一気に軍事政権を樹立することでした。したがって『グラディオ』下の『緊張作戦』は、東欧から国境を越え押し寄せる共産主義勢力を、水際で抑え込む国際謀略であると同時に、ファシスト政権回帰を悲願とするイタリア国内の極右勢力、また戦後、国外追放となったサヴォイア家を連れ戻し、君主専制主義を実現させようとする極右一派の利害をもカバーしていたわけです。 つまり、日本同様、第二次世界大戦の敗戦国であるイタリアは、こんな謀略が政府関係者の協力により実現するほど、米国をはじめとする戦勝国の管理下に置かれていたわけで、表向きは民主主義を政体としながら、現実にはその国民主権は、著しく制限されていた、ということです。 フォンターナ広場事件の翌年の話ですが、イタリア共産党の影響力がますます増大する1970年、米国大統領リチャード・ニクソン、大統領補佐官ヘンリー・キッシンジャーは「もしこのままイタリアが共産主義へと向かうならば、軍事攻撃をも辞さない」と、時のイタリア外務大臣に釘を刺したと言います。そしてその外務大臣こそが78年に『赤い旅団』に誘拐され、殺害された『キリスト教民主党ーDC』のリーダー、制限のない純粋な『民主主義』、『国民主権』を理想とし、イタリア共産党との連立政府を実現させようとしたアルド・モーロでした。 モーロは、米国の威圧的な脅しに激怒して、訪問を途中で切り上げ、さっさと帰国したそうですが、モーロが『グラディオ』の存在を知らなかったはずはありませんから、イタリアの民主主義に介入してくる米国の圧力を強硬に阻止しようと抵抗し続けていたのでしょう。なお、オフィシャルには『赤い旅団』が「単独で」企てたとされる、イタリアの戦後政治の一時代を終焉させたアルド・モーロ誘拐、殺害事件は、フォンターナ広場爆破事件ほどには詳細が明らかになってはいませんが、現在に至るまで、米国、イスラエル、ソ連などの国際諜報、さらにはドイツ赤軍の関与の可能性も含めた詳細が、根気よくリサーチされ続けています。 |
||
| ▶︎爆弾までの経緯 | ||
| さて、この項の本題であるフォンターナ広場爆破事件ー緊張作戦のルーツは、1965年に遡ります。その年、イタリアにおける『緊張作戦』に先立つ実行計画会議が、ローマの老舗ホテル、パルコ・ディ・プリンチピで行われたことは、のちの捜査の過程での極右テロリストの証言から明らかになりました。会議にはCIA諜報メンバー、イタリア軍部諜報SIDメンバー他、極右グループ『オルディネ・ヌオヴィ』を率いるピーノ・ラウティ、『アヴァンガルディア・ナチォナーレ』のステファノ・デッレ・キアイエ、右翼軍事ジャーナリストでSIDメンバーとして活動したグイド・ジャンネッティーニ、決起に逸る極右青年たちなど、その後『緊張作戦』として繰り広げられた一連のテロ事件に関わるメンバーが一堂に会し、その主旨を共有したのだそうです。 ところで、フォンターナ広場爆破事件』の主軸となるオルディネ・ヌオヴォ』は、極右政党『イタリア社会主義運動(MSI)』から派生した極右グループで、その『オルディネ・ヌオヴォ』から、『アヴァンギャルディア・ナチョナーレ』が枝分かれしています。そしてこのふたつの極右グループのメンバーが前線部隊となり、その後の十数年の間に繰り広げられた無差別テロを実行していくことになったのです。 急進派の学生たちと工場労働者が共闘で、乱闘にまで発展した抗議デモやサボタージュ、ストライキを繰り広げ、当局とエンドレスの衝突を繰り返すその裏で、たとえば70年代にCIAが関与し、アルゼンチンやチリで実現されたクーデターと似たような計画が、イタリアでもひそやかに、着々と進んでいたというわけです。 1967年にはイタリア同様、欧州における共産主義封じ込めの国際謀略のターゲットであったギリシャに、実際にクーデターが起こり、「まさか、あのギリシャに」と、それまで誰も予想していなかった軍事政権が樹立していますから、イタリアが同じ轍を踏む可能性は、非常に高い確率で存在していました。 そしてこの頃、当時の『革命』急進派の中核に存在していたジャンジャコモ・フェルトリネッリが、すでにその状況を見透かしていたことは特筆すべきことです。イタリアには、●ギリシャの軍事クーデターのような、総合的なクーデターが起こる可能性がある。● 最も可能性が高いのは、軍部とNATO、さらに、世論、及び国際世論を味方につけて、過半数(共産党を破壊して)を得て、権力を強化しようとする動き。あるいは社会的に対極にある動き(極左学生運動)と労働者たちが起こす広場での抗議運動を重大化させようと、何人かの政治家が、非武装のデモ隊に発砲するなどしながら、自分たちを正当化することだ。フォンターナ広場爆破事件が起こる以前から、フェルトリネッリはそう予言しています。 |
||
| 69年になると、学生と共闘する労働者たちによる攻撃的サボタージュ、ストライキ、デモ、政治集会など抗議運動は拡大するとともにますます激化。『熱い秋』と呼ばれる大きなムーブメントへと成長し、警官が労働者たちに銃口を向ける事態にまで発展しています。しかしその激しい闘争の結果として、欧州で最も低かったイタリアの工場労働者のサラリーはやがて賃上げに成功し、労働条件も着実に改善されることになっていますから、彼らの闘いは決して無駄になったわけではありません。ちなみにフォンターナ広場爆破事件以前を振り返るなら、それまでに起こった極左、極右グループによる暴行、爆弾事件は145件に上るのだそうです。しかし69年4月、ミラノの見本市のフィアットのスタンドで起こった爆発(20人が怪我)、8月、イタリア全国で起きた、列車に仕掛けられた10個の爆弾爆発事件以外はいずれも規模がちいさく、負傷者も出ず、それぞれのグループによるプロパガンダの域を超えてはいなかった。このミラノの見本市、列車爆破事件という際立つ破壊力を誇示した、ふたつの爆破事件に関しては、当時、アナーキスト・グループの犯行と捉えられましたが、のちにいずれもフォンターナ広場爆破事件に関与した極右グループ『オルディネ・ヌオヴォ』メンバーによる『作戦』開始のシグナル、前哨戦であったことが明らかになっています。フォンターナ広場爆破事件前夜、社会にみなぎりつつある『緊張』が、人々の不安をかきたて、しかしまだ形を持たないまま、曖昧に膨れあがりつつありました。事件の数日前にはフォンターナ広場にごく近い通りで、若い警官のひとりが、労働者たちの抗議運動の乱闘で死亡するという事件も起こっており、この事件に関しても『緊張作戦』の一環ではないか、と根強く語られ続けています。さらにこの時期、英国紙『オブザーヴァー』が、『ステイ・ビハインド』という言葉をはじめて用い、MI6の機密書類を引用しながら、ミラノの見本市の爆発の裏にはギリシャ大使館と軍部諜報が関与していたことを報道しましたが、当時のイタリアでは、その記事に注目が集まることはまったくなかったそうです。 「僕らは『国』を創造するのではなく、国を解体したいと思っていた。マルクスやレーニンが書いたように、国を解体したいと思っていたんだ。レーニンの、クールで、科学的で、計算された唯物的な著述に心酔し、僕らは押しつぶされるような倫理的『責任感』を感じていた。僕らは若く、無知で、傲慢で、そして『責任』を感じていた。つまり国際的な階級闘争に責任を感じていた」、「僕らの目標である『革命』を実現するためには、絶対的に武装する必要があり、したがってその闘争は暴力的なものだ。だから僕らがまったく無実であったとは言わない。しかし『フォンターナ広場』は、その時の僕らの想像をはるかに越えた事件であり、僕らの存在そのものをも超えてしまった。そして『フォンターナ広場』こそが『Perdita dell’innocenza(無垢/無邪気/無実の喪失)』だったのだ」 。これは、一貫して『無実』を訴えながら、フォンターナ広場爆破事件の特別捜査本部長、ルイジ・カラブレージ警部殺人事件の主犯とされ、2011年の恩赦まで15年間服役した『Lotta Continuaー継続する闘争』のリーダー、現在77歳のアドリアーノ・ソフリが語った言葉です。 1969年12月12日。その日を境に、『若さ』という抑えようのない傲慢に駆り立てられ、『革命』を目指した多くの青年たちの人生は大きく変わることになりました。いや、イタリアの近代史そのものが大きく変わらざるを得ない時代へと突入した。冒頭で書いたように、事件から遂に半世紀を迎えた2019年12月12日を挟み、イタリアが決して忘れることがないフォンターナ広場爆破事件に関する多くのドキュメンタリーやドキュフィクションがTVで放映され、報道番組、各新聞が特集を組みました。そしてそのメモリアルは、ジェネレーションが変わったイタリアで、そして世界で、再び極右政党や極右グループの台頭が著しく、世界の分断が進行する現在の状況に対する警鐘となったようにも思います。 1969年といえば、68年に続き、日本も世界も激動した1年です。東大安田講堂では攻防戦が繰り広げられ、米国ではニクソン大統領が就任、三島由紀夫VS東大全共闘の公開討論が開かれ、南ベトナム解放民族戦線が臨時政府を樹立、アポロ11号が月面に着陸し、NYではゲイの人々のストーンウォールの反乱が起こっている。 中国がはじめての地下核実験を行い、国際反戦デーの新宿では新左翼と機動隊が衝突して1594人の逮捕者を出し、大菩薩峠では共産党同盟赤軍53名が逮捕されています。ジョン・レノンとオノ・ヨーコがLove & Peace『ベッド・イン』(平和活動パフォーマンス)で世界を騒がせたのも69年でした。 クリスマス・シーズンのその日のミラノは薄暗く、小雨が降りしきっていたそうです。一方ローマは、冬だというのに、なぜかとても暑かったと言います。 2019年の12月12日、 SNS上にシェアされたフォンターナ広場爆破事件の記事に、その頃階級闘争のまっただ中にいた、かつての『革命家』たちが「その日、自分がどこで何をしていたのか、昨日のことのように思い出す。覚えていない者はいないはずだ」、とのコメントを残しているのを、多く目にしました。 |
||
| 12月12日、16時37分 フォンターナ広場 | ||
| その日、ミラノとローマの2都市では、5つの爆弾が炸裂しています。ローマでは、ヴィットリオ・エマニュエーレ講堂の『国家の祭壇』など3カ所、ミラノではスカラ座前の全国労働銀行に仕掛けられた爆弾で、軽傷を負った人が16人出ましたが、それほど大きな被害を及ばすことはありませんでした。その場に居合わせた人々の身体が粉々に吹き飛ぶ大爆発を起こしたのは、ミラノのフォンターナ広場にあるBanca
Nazionale dell’agricoltore – 全国農業銀行に仕掛けられた爆弾です。銀行に訪れていた人々17人が生命を奪われ、88人が重軽傷を負うという大惨事でした。世界が9.11を体験した今、米国、欧州をはじめとする世界中のあらゆる場所、特に紛争が絶えない地域では、『自爆テロ』を含む大規模な無差別テロが繰り返され、わたしたちは50年前に比べると、テロの『恐怖』と『悲しみ』にいくぶん鈍感になっているかもしれません。そしていつの間にか忘れた頃、どこかで新たなテロが起こって、再び恐怖と嫌悪に襲われる。
しかし第二次世界大戦から24年が経ち、その傷がようやく癒えようとしていた当時のイタリア、しかもミラノのような平和な大都市での無差別テロは、社会そのものを絶望に突き落とす、人々の記憶から決して消すことのできない事件となりました。 事件が起こった当時はいったい何が起こっているのか、誰が、何の目的にこんなにひどい無差別爆破事件を起こしたのか、もちろん誰も理解できませんでした。しかしながらその後50年をかけ、テロ事件の背景と動機、そして犯人について、何ひとつ分からないことはない、もはやフォンターナ広場爆破事件にミステリーは存在しない、と言われるほどにまで詳細が調べ上げられていることこそが、誇り高きイタリアの威信であり、静かな復讐と言えるのではないか。それにも関わらず、司法に裁かれて『有罪』となった人物は誰ひとり存在しないのです。フォンターナ広場爆破事件、ボローニャ駅爆破事件を経た1969年から1984年までの間に、イタリアの各地では60個の爆弾が炸裂し、16件の大規模テロが起こっていますが、それら無差別爆破事件の主要テロリストたちのほとんどが、現在も自由に人生を謳歌しています。そして前後の文脈からは『無罪』ではないのか、と推測される者たちのみが、実刑を受けることになったわけです。 その日、爆弾が仕掛けられたBanca Nazionale dell’agricoltura – 全国農業銀行は、他の銀行が通常は閉まる金曜日の午後でも、手形の換金などで訪れる、中小企業、農業関係者や商店を営む人々のために開かれており、クリスマスを目前に控えた12日の午後も、多くの人々で混雑していたそうです。銀行の用事を済ませ、その足でクリスマスの買い物に行くため、子供を連れている人もいました。つまり、『緊張作戦』を牽引する国際諜報、そして軍部諜報、内務省、イタリアの国家の中枢にいる政治家と極右グループらは、戦後のイタリアの経済を支えてきた、何の罪もなく、政治にも思想にもまったく関係ない『一般の市民』をターゲットにしたのです。1980年代の終わりから捜査を再開し、1990年代から再び裁判を開くことに成功したグイド・サルヴィーニ裁判官が、最近出版した本によると、銀行爆発の直後に銀行の建物の外部、さらに内部にまでシークレット・サーヴィスが侵入し、一部始終を撮影した映像が存在すると言います。 そしてその時に使った2台のトラックは、証拠隠滅のためにローマで木っ端微塵に爆破されているそうです。爆破直後の銀行内部、ということは、爆弾に吹き飛ばされた人々が、助けを求める状況に、手を差し伸べるどころか、無慈悲に淡々と撮影して立ち去った、ということでしょうか。 |
||
| 作為に満ちた捜査と30万人の葬列者 | ||
| 爆弾以前に、すでに物語は形成されていました。つまり犯人は捜査をする前から極左『アナーキスト』グループと決められており、事実、捜査は一直線に、アナーキストへのみ向かっていきます。当時、ミラノ警察署長だったアントニオ・アレーグラに至るまで、謀略サイドの司令が行き届いており、たった一夜にして、何も事情を知らないアナーキストたちは、許されざる非人間、恐るべき怪物に仕立てあげられることになったのです。爆発の直後、ミラノ中央警察署には、ルイジ・カラブレージ警部を部長とした『特別捜査本部』が設置され、何の証拠も動機も上がっていないにも関わらず、ジュゼッペ(ピーノ)・ピネッリ、そして『3月22日グループ』のアナーキストグループ14人を、ただちに連行することを、署長に命じられています。カラブレージは、ミラノの見本市のフィアット・スタンドにおける爆破の捜査を担当した経緯で、そもそもピネッリと付き合いがあり、アナーキストたちも顔見知りでしたから、彼らもまさか犯人に仕立てあげられるとは考えもせず、「軽い取り調べ」という気分で警察署を訪れたそうです。ピネッリに至っては、警察がアナーキストたちを連行する車の後ろをバイクで追いかけており、重大事件の犯人が、自ら警察の車についていく、ということは、まずありえないことでしょう。また警察も、それほど危険な犯人なら、こんな緩い連行の仕方はしないはずです。 実際はこの時点で、すでにアナーキストグループには内務省からスパイが仕込まれており、ジュゼッぺ・ピネッリが主犯とされたのち、15日早朝、実行犯として逮捕されるピエトロ・ヴァルプレーダの動向は、随分以前から『友人』により監視され続けていました。そしてその『友人』は、事件当日、ローマからミラノにやってきたヴァルプレーダがアリバイが作れないよう、巧みに行動を制限。他との接触を妨害しています。事件のずいぶん以前からヴァルプレーダに張り付いていた『友人』は、イタリア軍部諜報SID の協力者である『オルディネ・ヌオヴォ』のメンバーで、パルコ・ディ・プリンチピの緊張作戦会議にも参加していたマリオ・メルリーノでした。謀略サイドがアナーキストに目をつけたのは、グループそのものが解放的で人の出入りが多く、グループの構成が曖昧で自由だったからだそうです。 また、主犯とされた41歳のピネッリは、ジャンジャコモ・フェルトリネッリとも親交があった元パルチザンで、労働組合、イタリア共産党の会議や政治集会をオーガナイズする『ギソルファ橋アナーキストクラブ』のメンバーでした。彼はイタリア国内のアナーキストたち、極左グループの若者たちからも一目置かれる温厚な鉄道員で、抗議運動における暴力を強く否定していたため、彼が首謀者となって爆弾を仕掛けるなどということは、誰ひとり想像できなかったと言います。 彼らが連行された際、「アナーキストは確かに爆弾を仕掛けるが、政治的にターゲットを絞った犯行であり、無差別殺人を計画するとは思えない」と疑問を呈する複数の知識人、ジャーナリストの発言もありましたが、ミラノ警察署長は、ピネッリ及び22人のアナーキストを連行した瞬間から、まったく確証がないままにプレスを開き、「アナーキストの犯行」と断言する性急さで事を進めています。当然翌日の新聞は、アナーキストたちを『恐るべき怪物』と書き立て、その様子はTVでもセンセーショナルに実況されました。 そして12月15日の深夜、『主犯』ジョゼッぺ・ピネッリの身に痛ましい悲劇が起こることになったのです。その経緯はその後小説、映画、演劇(ダリオ・フォー)、数々の歌、そしてドキュメンタリーとなり、『フォンターナ広場爆破事件』の不当を象徴する出来事となりました。 法律で定められた30時間を超え、深夜にまで及んだ取り調べの途中、突然ピネッリはミラノ中央警察署の4階から中庭に転落して死亡。その際、取り調べ室にはカラビニエリ、警察官と5人の捜査官が同室していたとされますが、現在ではそのなかに軍部諜報が含まれ、部屋にいたのは10人以上だったことが確認されています。 一方、ピネッリとも旧知の仲であったカラブレージ警部は事件が起こった際、警察署長アレーグリに緊急に呼び出され、現場には不在でした。この時、捜査室の外でピネッリを待っていた 3 月22日グループのひとりであるヴァレトゥッティは「カラブレージは部屋から出てこなかった」と証言していますが、ヴァレトゥッティが座っていた場所からは、捜査室からの移動がすべて見えるわけではないことが、のちに証明されています。ヴァレトゥッティは捜査室から喧嘩のような怒号と大きな音が聴こえたとも証言しています。 このピネッリの転落事件を巡って、警察側は当初、自らのアリバイが崩れた瞬間「ことの重大さ」を悟り、絶望のための突発的な『自殺』説を主張しましたが、のちの捜査でピネッリのアリバイが実証された際「飲まず食わずのうえ、睡眠も取れず、疲れ果てていたピネッリは、吸った煙草で気持ちが悪くなって窓際へ寄り、そのまま転落した」と『事故』説を主張。 会見での発言を二転三転させる、このあやふやな警察サイドの対応が、人々の疑惑を深めることになりました。ピネッリが亡くなった12月15日は、その後のイタリアにとって、重要なイベントが起こった日ともなりました。というのも、ミラノのドゥオモ大聖堂で全国農業銀行の爆発で犠牲になった人々の葬儀が行われたその日、広々とした広場を隙間なく埋め尽くす途方もない数の人々が、自発的に集まったのです。人々は、誰からも指図されることなく自らの意思で、爆発で亡くなった犠牲者、そして遺族への湧きあがる想い、悲しみと憤りを、広場に集まることで静かに分かち合った。その数は、30万と言われます。 そして、この夥しい数の市民たちの沈黙の団結こそが、『緊張作戦』謀略サイドを怖気づかせ、その後の『緊張作戦』のシナリオを大きく変えることになりました。 ドゥオモ広場で遺族の悲しみと憤りを分かち合った30万人の市民たちに自覚なく、無意識ではあっても、戦後、人々の精神に根づいた『民主主義』のシンボルとして、「こんな無差別テロをわれわれは決して許さない」 声に出さずにそう訴えた。主権は国民にあるのです。 | ||
| 布告されなかった『緊急事態宣言』 | ||
| 『フォンターナ広場爆破事件』はそもそもクーデターを目的に構築された作戦ですから、『キリスト教民主党ーDC』のマリアーノ・ルモール首相は、事件直後、当然『緊急事態宣言』を発令することを詮議していました。しかし結局それが発令されることはなく、いまだにその理由は明らかになっていません。最も信頼がおけるのは、ドゥオモ広場で、沈黙しながら犠牲者と遺族に寄り添う30万人の市民の姿に心を動かされたルモール内閣が、『緊急事態宣言』の発令を中止した、という説でしょうか。つまり葬儀に集まった市民たちが、クーデターからイタリアの『民主主義』を守ったということです。また、これものちになって発覚したことですが、1970年には大戦中のファシストの英雄、『黒い君主』と呼ばれたジュニオ・ヴァレリオ・ボルゲーゼが森林警備隊とともに蜂起、内務省、国営放送Raiを占拠するというクーデター未遂事件を起こしています。それも、あと数分でクーデターの告知放送をはじめる、というところまで危機が迫っていましたが、ボルゲーゼはなぜか突如としてクーデターを中止。森林警備隊を引きあげ、それからの1年間というもの、このクーデター未遂事件は秘密にされることになりました。しかしなぜ突然、もう少しでクーデターが実現する、というタイミングで、ボルゲーゼが森林警備隊が引き上げることになったのか。中止されたクーデターが発覚したのちに開かれた裁判で、ボルゲーゼは『無罪』になっていますが、詳細は謎に包まれたままになっています。一説によると『フォンターナ広場事件』で『緊急事態宣言』が発令されなかったことで、その後の『緊張作戦』シナリオが大幅に変更されたにも関わらず、軍事政権樹立の夢を捨てきれずクーデターに走ったボルゲーゼに、米国かイタリア軍部か、いずれかの司令塔から『即刻中止』の命令が下されたと言われます。このクーデター騒ぎは当初、金満家のボルゲーゼのちょっとした演劇的反乱=オペレッタと見なされましたが、現在では「あわや成功」という緊急レベルにまで迫っていたことが明らかになりました。 なお、ドゥオモ大聖堂での葬儀の朝には、当初のシナリオ通りに、『友人』の監視が奏して、当日まったくアリバイがなかった、前述のアナーキストのダンサー、ピエトロ・ヴァルプレーダが実行犯として逮捕されています。 ヴァルプレーダの逮捕は、犯人を乗せたタクシーの運転手の証言が決め手となったそうですが、『面通し』で運転手が見せられた数葉の写真は、背広姿でネクタイを締めた男たちの中、たったひとりカジュアルな服装、長髪のヴァルプレーダの写真が混ざっているという、どう見てもアナーキスト然としたヴァルプレーダしか選びようのない怪しい検証でした。 しかも爆発の現場まで、犯人はたった100メートルほどの距離をわざわざタクシーに乗っており、この不自然な行動は、運転手を無理やり証人に仕立てあげるための工作だったと見られます。 50年を経た現在、全方向からの捜査の末、「共産主義の侵攻を食い止め、恐怖で社会を支配する新しいパノラマ」を目指し、爆弾を仕掛けた主犯は、極右グループ『オルディネ・ヌオヴォ』のメンバー、パドヴァ出身のフランコ・フレーダ、ジョヴァンニ・ヴェントゥーラ、ヴェネト出身のデルフォ・ゾルジ、カルロ・マリア・マッジであることは確実ですから、ピーノ・ピネッリ、ピエトロ・ヴァルプレーダは計画通りに無実の罪をなすりつけられ、連日、憎むべき『アナーキストの恐るべき怪物』としてメディアに報道され続けたということです。 事件直後のことですが、真犯人であるジョヴァンニ・ヴェントゥーラの友人であったトレヴィーゾの『キリスト教民主党』メンバー、フランス語教師、グイド・ロレンツィンが「彼は爆弾のことを話しており、実際にそれを見せてくれたこともある。友人であるヴェントゥーラが真犯人だと思われる」と弁護士に届け、警察に通報しています。しかしこの証言はたちまちのうちにもみ消されました。 ロレンツォンはドゥオモ広場に集まった30万人の葬列者の悲しみの沈黙にいたたまれなくなって届け出た、と語っていますが、ロレンツォンのこの勇気ある証言が、のちにヴェントゥーラ、フレーダを逮捕する際の重要な決め手のひとつとなりました。さらに同年、8月に起こった列車爆発事件(イタリア国内の列車に10個の爆弾が仕掛けられた)からフレーダ、ヴェントゥーラに疑いを持ち、ふたりの会話を盗聴し続けたパドヴァ警察署のパスクワーレ・ユリアーノ警部は、確証を得たと同時に警察内で不当な非難を浴び、イタリア南部へと更迭されています。このユリアーノ警部は、『フォンターナ広場事件』以前に、その後20年が過ぎて自白する、爆弾のエンジニアであったCIA及びイタリア軍部諜報の協力者、後述するカルロ・ディジリオの存在まで突き止めていたそうです。 また、爆弾が仕掛けられた5つのドイツ製の鞄をフレーダに売ったことを、パドヴァの鞄店の主人が警察に届けていますが、この事実も69年の時点ではうやむやになっています。 加えて、弁護士でジャーナリストのヴィットリオ・アンブロジーニは、「MSIから脱会した、ギリシャの軍事政権に深く繋がる、ピーノ・ラウティ率いる『オルディネ・ヌオヴォ』が爆破事件の犯人だ」という手紙を、当時の内務大臣フランコ・レスティーヴォに送っていますが、この手紙が問題にされることもありませんでした。 このアンブロジーニは、フレーダ、ヴェントゥーラ、ピーノ・ラウティが逮捕された71年に心臓発作で入院。病院の窓から飛び降り『自殺』しています。しかし転落した際の姿勢が不自然なうえ、当時勤務していた看護師がひとり行方不明となって追跡不能となる、いや、そんな看護師はもともと存在しなかった、など諸説あり、不可解な点が多く指摘されています。 | ||
| なお現在、極右グループの犯行である、一連の『Strategia della Tensione(緊張作戦)』テロとして認識されている事件は、以下の通りです。 1969年4月25日、ミラノ見本市のFIATのスタンドの爆発で20人が怪我。8月9日には、イタリア全国で列車に仕掛けられた爆弾が爆発して12人が怪我。 1969年12月12日 「フォンターナ広場」及びローマの5カ所で爆発。 1970年7月22日、ジョイアタウロ駅に爆弾が仕掛けられ、6人が死亡、60人が重軽傷。 1972年5月31日、北イタリア、ゴリツィア、サグラード地方のペテアーノで、置き去りにされフィアット500が爆破される。電話でおびき寄せられた3人のカラビニエリが死亡。2人が重傷。 1973年5月17日、アナーキスト、ジャンフランコ・ベルトリがミラノ警察署前に爆弾を投げる。その日は1972年に殺害されたルイジ・カラブレージの一周忌が執り行われていたが、同席したルモール首相は、すでに立ち去っており爆発から免れている。市民4人が死亡、40人が重軽傷。なお、ベルトリは、アナーキストではなく極右グループと深いつながりを持つSIFAR(イタリア軍部諜報)のメンバーだったことが、のち明らかになった。1969年12月にルモール首相が『緊急事態宣言』を布告しなかったことへの制裁だったことを、ペテアーノ事件の犯人、ヴィンチェンツォ・ヴィンチグェッラが告白。 1974年5月28日、ブレーシャのデッラ・ロッジャ広場で行われていた労働組合の集会で、ゴミ箱に隠されていた爆弾が爆発。8人が亡くなり、100人が重軽傷を負う大惨事となる。 1974年8月4日、列車イタルクスがボローニャのサンベネデット・バル・ディ・サンブロで爆発。12人が死亡、105人が重軽傷。この列車には、アルド・モーロ首相が乗る予定になっており、直前に連絡を受けてキャンセルしている。 1980年8月2日、ボローニャ駅の待合室で爆弾が爆発。85人が死亡、200人が重軽傷を負う大惨事となる。 1984年12月23日、急行列車904が、やはりボローニャのサンベネデット・バル・ディ・サンブロで爆発。17人が亡くなり、260人が重軽傷。 |
||
| このように、CIA、NATOの国際諜報、イタリア国家の軍部、政治家、極右グループが起こしたテロのほとんどが、無差別に市民をターゲットにした大量殺人です。しかも爆弾は、まさしく『冷戦』という戦争のために隠されていたNATOの武器庫から調達されていたことが明らかになっています。このほかにも、1973年シシリア、トラパニのカラビニエリの詰所で起こった銃殺事件『アルカモ・マリーナの殺戮』、さらに1977年の急進党主催のファミニスト・デモで警官に銃殺されたジョルジャーナ・マーシ殺害事件、極右グループにより殺害された1976年、検事ヴィットリオ・オッコルシ殺害事件、1980年、検事マリオ・アマート殺害事件も『緊張作戦』の一環であったと言われます。(イタリア語版:ウィキペディア参考)
さらには、たとえばジャンジャコモ・フェルトリネッリの事故死、あるいはルイジ・カラブレージ殺害事件、ピエールパオロ・パソリーニ殺害事件など、いまだに謎が解けない事件が数多くあり、そのどれもが「国家による殺害」と、主張され続けてもいる。 極左グループ『赤い旅団』によって引き起こされた1978年の『アルド・モーロ誘拐・殺害事件』もまた、その不条理な展開から、国際諜報、国家の中枢の政治家、秘密結社P2、マフィアグループの関与の可能性について、いまだに調査が継続されていることは、前述した通りです。 |
||
| Perdita dell’ innocenza 無垢/無邪気/無実の喪失 | ||
| 再び69年に戻ります。「爆発を知った時は、ひどい衝撃だった。こんな冷酷で、非道な犯罪が起こったことに恐れをなした。ピネッリ? アナーキスト? 僕らの仲間がこんなことをやったのかと、誰もが言葉に表しようがないほどのショックを受けたんだ」。デアリオの新刊のプレゼンテーションに同席した極左グループ『継続する闘争』のリーダー、アドリアーノ・ソフリは事件当時の衝撃を、そう語りました。グループは違っても、60年代、特に68年から69年にかけて、工場労働者や農民たちと共に、熱く激しく闘争し『革命』を目指したピネッリは、学生たちの同朋だった。その口ぶりから、ソフリは実際にピネッリと親交があったように見受けられました。当時『継続する闘争』は、工場労働者たちに最も近い位置にあり、毎日工場に通って、早朝から共に議論していたそうです。ソフリに言わせると、68年に世界中に巻き起こった学生たちの抗議活動は『よい家庭の子供たちの反乱』に過ぎず(パソリーニもそう指摘していますが)、69年こそが、労働者が真の『労働者』となり、労働者と辛苦を分かち合う学生たちと共闘しながら、それぞれの個が全体と呼応するCollective(集合的)なアイデンティティを持った年だった。その頃、共に過ごした工場労働者や闘争に加わった、生きるために売春婦にならざるをえなかった女性たちの名前や彼らのパーソナルな物語を、ソフリはひとつひとつ覚えているようでした。「僕らにとって、最も素晴らしい時期だった」と晴れやかに語るソフリに、講演会場(ローマ3区庁)は満場の拍手に包まれ、その明朗な表情からは、カラブレージ警部殺人事件の犯人として22年の実刑を受け、恩赦になるまで15年間服役した人物とはとうてい思えなかった。工場労働者たちが中核となり、ソフリをはじめとする学生たちと繰り広げた『熱い秋』は、前述したように、その後労働法の改正として結実し、現在の労働法の基礎となっています。「僕らが築いた流れ、特に69年の工場労働者たちとの強い連帯が、作戦のターゲットとなった。69年は「熱い」どころではなく沸騰していたからね。アナーキストが狙われたのは、彼らが最も脆弱だったからだ。そしてわれわれが共に築いた69年の流れで彼らが標的となり、犠牲になったことに、僕らは強い『責任』を感じていた」ソフリは、何度も『責任』という言葉を強調した。同朋ピネッリが亡くなった後、ソフリが『継続する闘争』が発行する新聞で、「ピネッリを殺害したのは、警察の責任者、カラブレージだ」と大々的に攻撃的なキャンペーンを繰り広げたのは、その強い『責任感』からなのでしょう。このキャンペーンをきっかけに、世論はカラブレージ警部、警察署長アレーグラへの強烈な非難へと動き、ピネッリの死の真相究明を求めて、700人の知識人、アーティスト、政治家、ジャーナリストなどがレスプレッソ紙に署名を発表する運びとなっています。
そのレスプレッソ紙のマニフェストには、オリヴィエロ・トスカーナ、ナタリア・ギンズブルグ、ウンベルト・エーコ、フェデリコ・フェリーニ、ピエールパオロ・パソリーニ、ベルナルド・ベルトルッチという、イタリアの一時代を代表する錚々たる文化人たちが署名し、『ピネッリの死を巡るカラブレージ警部の責任』『国家組織、検察、シークレット・サービス(諜報)部門の不透明性の解除』を訴えました。
また、ここで問題となるのは、殺人予告が来るほどに、カラブレージへの強い憎しみが社会に満ちていたというのに、警察サイドが警部にボディガードがつけることもなく、あまりにも無防備だったことでしょうか。状況を鑑みるなら、その無防備さは、確かに不自然でもある。Sky
news24のドキュメンタリーによると、脅迫と嫌がらせの毎日に「どうしてこんな目に合わなくちゃならないのだ」と、カラブレージはその苦しみを友人に打ち明けてもいたそうです。
いずれにしても、1970年の5月には、弁護士エドゥアルド・ディ・ジョヴァンニ、ジャーナリストであるマルコ・リジーニ、エドガルド・ペリグリーニらが共同で調査した『Le Stragi di Stato(国家による虐殺)』が匿名で出版され、『フォンターナ広場事件』の背後に存在する軍部諜報、国際諜報、国家の中枢による謀略の存在が明らかにされていましたから、目の前で繰り広げられた無差別の殺戮が、国家が絡む『オペラ』であることを、運動に関わっていたほとんどの労働者や学生たちは認識していました。『鉛の時代』は、イタリアのジャーナリストの独自捜査の原点となった時代とも言われますが、事件から、たったの5ヶ月しか経っていないというのに、ここまで真実に近い内容を調べ上げていた人々がいたことは驚愕すべき事実です。もちろんそれは、匿名で出版しなければならないほど危険な真実でもあり、事実、弁護士ディ・ジョヴァンニの事務所には爆弾が仕掛けられたこともあるそうです。 また、現代イタリアで活躍する多くの著名ジャーナリストを輩出した『継続する闘争』は、ピエールパオロ・パソリーニの発案で『12 DICENBRE』という長編ドキュメント映画をも制作しています。ピネッリ夫人や、当日爆弾が入った鞄を持った犯人を銀行まで乗せたタクシーの運転手にインタビューを撮り、独自に事件を検証。パソリーニのバックアップも得て全力で、あらゆる事実を調べあげようとする彼らの『責任感』を謀略サイドが邪魔に思わなかったはずはありません。 一方、すでに議会の一部を形成していた『イタリア共産党』は、パソリーニが1974年に新聞記事で非難したように、残念ながら『緊張作戦』について、何ひとつ語ることはありませんでした。しかしその頃の『イタリア共産党』は、イタリアが1973年にチリで起こったクーデターと同じ轍を踏むことを強く危惧しており、『フォンターナ広場爆破事件』に関しては集会もスピーチも行わず、沈黙を保つことが最善だと考えていたようです。 やがて、強烈な世論の後押しで「ピネッリの死」を巡る一件は再捜査となりましたが、ピネッリの取り調べが続く部屋に居合わせた(と見なされた)警官、カラビニエリなど全員が『無罪』となったのは、カラブレージ警部が自宅付近で何者かに射殺された1972年の3年後、1975年のことです。 そして、このカラブレージ警部の殺害についても、いまだに多くの謎が残る事件のひとつとなりました。まず殺害当時のカラブレージは『赤い旅団』『継続する闘争』『マニフェスト』『労働者の力』など極左グループのリーダー的存在であり、パトロンでもあったジャンジャコモ・フェルトリネッリの事故死について捜査を進めている最中だった。 また、カラブレージ警部は、殺害1ヶ月前に、なぜかヴェネトへ赴いており「そこで隠されていたNATOの武器倉庫を存在を知ったのでは? カラブレージは非常に有能な警部だったのだから、疑問を持たなかったはずはない」という説が根強く語られます(Skynews 24)。 結局、カラブレージ警部殺害の犯人としては、アグレッシブに攻撃キャンペーンを繰り広げていた『継続する闘争』のアドリアーノ・ソフリ、ジョルジョ・ピエトロステーファニが主犯、レオナルド・マリーノ、オヴィディオ・ボムプレッシが実行犯として逮捕されることになり、マリーノが『ソフリから命令された』と自白したことになっています。 しかし、そもそもドラッグ漬けで、常に妄想状態であったマリーノが捜査中に酷い拷問を受け、無理やり自白させられたとの疑惑が付きまとい、「ソフリの『沈黙』を命令であるとマリーノが受け止めたのだ。それならもはや検証不可能」とソフリの『無罪』を一貫して主張した人々は言い続けた。 ソフリの『無罪』を主張した、あるいは恩赦を大統領に要求し続けたのは、ジュリアーノ・フェラーラ、ガッド・レイナーという『継続する闘争』出身のジャーナリストだけではなく、ダリオ・フォー、ウァルター・ヴェルトローニ(PD創立者、元ローマ市長)、マッシモ・ダレーマ(元首相)、レオナルド・ジャーシャ、フェルディナンド・インポシマート(アルド・モーロ事件を担当した検事)、フランチェスコ・コッシーガ(モーロ事件の黒幕のひとり?とも言われる元大統領)、ベルナルド・ベルトルッチ、アントニオ・タブッキ、マッシモ・カッチャーリなど、やはり各界の錚々たるメンバーがズラリと並びます(イタリア語版ウィキペディア)。 『無罪』を主張し続けながらも、長い裁判を経た1997年、最終的に『有罪』が確定したソフリは、「ピネッリの死」を巡って『継続する闘争』紙に「カラブレージは自殺することになるだろう」という記事を掲載した経緯も含め、時代を担ったひとりとして『責任』をとるとし、さらにカラブレージの家族にも、当時の攻撃を謝罪しています。確かに『継続する闘争』が率先してキャンペーンを繰り広げなければ、事件当時、カラブレージ警部がこれほど世間の注目を浴びることはなかったはずです。12月12日のメモリアルには、ピネッリの死を巡るソフリが書いたイル・フォリオ紙のコラムに、新刊を出版したばかりのジャーナリストが反論するという一件が起き、つまり50年経った今もなお、ピネッリの死を巡る議論は続いているということです。 |
||
| 極右グループへと大きくシフトした捜査 | ||
| 現在から振り返るならば、事件当時、ドゥオモ広場に集まった30万の人々の沈黙の抗議、そして『継続する闘争』をはじめとする極左グループ、学生たち、イタリア共産党に反旗を翻した知識人、事件に疑問を呈する司法官、警察官、ジャーナリストたちが大きな声をあげ、『闘いだ!』と強い姿勢を見せたことで、謀略サイドはクーデターのシナリオ変更を余儀なくされたのだと確信します。
さもなくば、『緊急事態宣言』が発令されると同時にイタリアにクーデターが起こり、冷戦が終わるまで、市民は武力で完全に抑圧され、集会、表現の自由どころか、軍部の専制主義下で怯えながら暮らさなければならなかったかもしれない。いずれにしても、クーデターが起こるはずだった『フォンターナ広場爆破事件』では『緊急事態宣言』が発令されることなく、やがて各方面から次々に疑問の声が沸き起こり、遂にはアナーキストから一転、極右グループ『オルディネ・ヌオヴォ』のリーダー、ピーノ・ラウティ、そしてパドヴァのネオファシスト、フランコ・フレーダ、ジョヴァンニ・ヴェントゥーラに捜査のメスが入っていくことになります。
その方向転換の最も重要なきっかけとなったのは、ヴェネトの田舎家の修理を頼まれた大工が、隣の廃屋で、偶然見つけた大量の爆発物と武器でした。それらはNATOレベルでなければ所有できないような、実際に『戦争』で使われる爆発物と武器でしたが、『フォンターナ広場爆破事件』の数日後にヴェントーラが持ち込んだもので、事件で使われた爆弾の構成物質と成分が、廃屋で発見されたものと一致しています。
また、取り調べの途中、フレーダ、ヴェントゥーラの犯行をさらに裏付けることになったのが、ヴェントーラの母親と叔母の共同貸金庫からSID(軍部諜報局)の機密書類のコピーが見つかったことでした。それは54枚からなる書類で、米国CIAエージェントのリストと共に、市民を巻き込む『緊張作戦』を実行するための具体案が記されたものでした。さらには爆弾に使われたタイマー50個を、フレーダが調達した事実が証言された。見つかった書類は、1967年、ヴェントゥーラ、ルーマニアのスパイ監視担当の諜報、そして右翼ジャーナリストであり、SIDのエージェントでもあったグイド・ジャンネッティーニが密会した際、ジャンネッティーニにより作成されたもので、この右翼ジャーナリストが家宅捜査された際にも、同様の書類が見つかっています。
ところがこの捜査の途中、ジャンネッティーニは軍部諜報SID「オフィスD」の局長、アントニオ・ラブルーナのオーガナイズで闘争資金を得て、パリに高飛び。1974年にはラブルーナにも逮捕状が出たにも関わらず、拘束されることもなく、自由に任務を遂行していたそうです。
ジャンネッティーニは、パリからブエノスアイレスへと逃亡しようとしたところで遂に逮捕され、この時ジャンネッティーニの逃亡を幇助し続けたSIDにも捜査の手が入りましたが、SIDは「軍事機密のため、何ひとつ明かすわけにはいかない」と全証言を拒絶しています。
こうして捜査の核が『極右グループ』へと移るなか、アナーキスト、ピエトロ・ヴァルプレーダは条件付きながらも、ようやく釈放されることになりました。当時ヴァルプレーダは、『マニフェスト』紙のバックアップを受け、獄中から国政選挙に立候補するなど、『国家に仕組まれた冤罪』の被害者として、極左グループのシンボル的存在になり、彼が書く『詩』も、当時の若者たちに人気を博したそうです。釈放後も執筆活動を続け、ジャーナリストと共著で3冊の小説を出版したのち、2002年に69歳で亡くなっています。
なお、パドヴァで小さい右翼出版社を運営していたナチ・ファシストのフランコ・フレーダ、右翼書店、及び出版社を持つジョヴァンニ・ヴェントゥーラ、そしてピーノ・ラウティ(ただちに釈放)の公判は72年、ミラノではじまりましたが、4日後にはローマ、さら8ヶ月後にはイタリア半島最南部のカタンザーロへと法廷が移動するという、作為的とも思える異常な動きを見せています。ミラノで起こった事件の裁判をカタンザーロで開くこと自体、前代未聞のことでした。したがって犠牲者の遺族の方々はカタンザーロまで、何回も列車を乗り換える長時間の旅で通わなければならならず、父親や夫を失い、ただでさえ困難な状況に見舞われながらも、遺族同士で強く団結、互いに励まし合って通ったのだそうです。それも10年を超える気が遠くなるほど長い時間、裁判のたびにミラノからイタリアの最南端まで通い続けなければならなかった。 極右グループ『オルディネ・ヌオヴォ』と軍部諜報の動きを中心とした捜査のもとに進められた裁判は、場所が変わるたび、ミラノやローマの検事、捜査官が解雇されたり、移動となったり、さらには裁判が中断されたりと、司法側は大きく混乱しています。つまり、裁判の間じゅう、どのような力が働いていたかは判然とはしなくとも、常に妨害が入り続ける、という状態でした。 ジャンネッティーニがSIDの諜報メンバーであることをサラっと告白した、時の内務大臣ジュリオ・アンドレオッティ、SID高官ジャン・アデリオ・マレッティ、ジャンネッティーニを逃亡させたラブルーナなど、当局側も出廷し、芝居がかった裁判が繰り広げられるうち、刑務所に入っているはずのフレーダ(SIDの手引きでコスタリカへ逃亡)、ヴェントゥーラ(同様にアルジェンティーナに逃亡)が失踪し、裁判が中止となったこともあったそうです。 こうしていったんは、フレーダ、ヴェントゥーラ、ジャンネッティーニに『無期懲役』、SIDのラブルーナに懲役2年が求刑され、アナーキストグループに潜入していたマリオ・メルリーノも含め、二審、三審と、フレーダ、ヴェントゥーラ、ラブルーナ、ジャンネッティーニらの『有罪』『無罪』が繰り返され、遺族の一喜一憂が続いています。事件から15年が経過した84年には、72年に起きたペテアーノのカラビニエリ爆破殺害事件の犯人、『オルディネ・ヌオヴォ』のメンバー、ヴィンチェンツォ・ヴィンチグエッラがグラディオの存在、さらに『緊張作戦』のために、ローマのパルコ・ディ・プリンチピで計画実行会議が開かれた事実を自白していますが、その自白が『フォンターナ広場』の爆発と関連づけられることはなかった。 そして遂に迎えた1985年の最終公判では、事件の犯人、及び協力者として名前が上がった全員が、『証拠不十分』で『無罪』となるという、信じがたい判決が下りたのです。つまり、17人の無実の市民が亡くなり、88人の人々が重軽傷を負う戦後最大の重大爆破事件が現実に起こり、十分すぎる証拠、証言、証人が存在するにも関わらず、司法上、この事件に『犯人』は存在しないということです。十数年の間、ミラノからわざわざカタンザーロまで、出廷し続けた犠牲者の遺族の方々の、このときの失望は計り知れません。 |
||
| 継続され続けた『フォンターナ広場爆破事件』捜査 | ||
| ところが、ここで捜査は終わることはありませんでした。いったん『無罪』となった被告たちに新たな裁判で『有罪』を科すことはローマ法以来の法律で不可能ではあっても、イタリアはこのまま、この事件を歴史の闇に放り捨てるわけにはいかなかった。
1990年、国際謀略である『グラディオ』の存在がオフィシャルに確認され、一部の軍部諜報の資料が公開された際、ミラノ裁判所の裁判官グイド・サルヴィーニは、『フォンターナ広場爆破事件』が独立して存在する事件ではなく、一連のテロとリンクしていることを突き止めます
。事件から20年近くの時が過ぎるまで『緊張作戦』の存在は公には認められていなかったのです。サルヴィーニ裁判官は各事件の細部をもう一度調べ上げると同時に、『オルディネ・ヌオヴォ』から脱退したメンバー、マルティーノ・シシリアーノから50000ドルと引き換えに、新事実を掴むことに成功した。
その新たな捜査で浮かび上がってきたのが、フレーダ、ヴェントゥーラと深い関わりを持つ、日本でも有名になったヴェネト出身のテロリスト、デルフォ・ゾルジでした。『オーディネ・ヌオヴォ』の主要メンバーだったゾルジは、フレーダ、ヴェントゥーラ同様、ミラノ、ローマで起きた『フォンターナ広場爆破事件』一連の爆破に関わっていたことが明らかとなっています。
さらには74年に起きた、ブレーシャの『デッラ・ロッジャ広場爆破事件』、遡って69年の夏に起こった列車連続爆破事件との関わりも指摘され、ローマの軍部諜報局と強い絆を持っていたことも証言されました。
ところが、デルフォ・ゾルジはブレーシャの爆破事件後、74年に奨学金を得て、日本に移住して結婚。異例のスピードで日本の国籍を獲得しています。「イタリア政府が何度も日本政府に引き渡しを要求していますが、日本政府は、それを強く拒絶した」と、イタリアでは報道されたにも関わらず、実はイタリア政府が日本にオフィシャルにゾルジの引き渡しを求めたことはなかったそうです(ピオ・デミリア)。
この経緯については、当時の日本でもさまざまな記事になっていますが、裁判がはじまってもデルフォ・ゾルジ(日本でハーゲン・ロイと改名)はイタリアへの帰国を拒絶。結局法廷に出廷することなく、本人不在のまま、『無期懲役」を受けるも、2005年の公判で、やはり証拠不十分で『無罪』となりました。
またもうひとり爆破に関わった極右テロリスト、カルロ・マリア・マッジは、2014年、『デッラ・ロッジャ広場爆破事件』の犠牲者たちが原告となった再審の最中、2018年に84歳で亡くなっています。
1992年には、サント・ドミンゴに逃亡中だった『オルディネ・ヌオヴォ』元メンバーであり、爆弾制作のエキスパートであったカルロ・ディジリオが逮捕され、CIAとのコンタクトを自白。その後、サルヴィーニ裁判官の捜査に協力し、『フォンターナ広場事件』唯一の受刑者となりました。
この人物は父親の代からCIAとコンタクトをとる役割を担い、CIAが「イタリア国内政治の不安定化を狙い、緊張作戦に加担していたこと。また、ルモール首相が『緊急事態宣言』を発令しなかったことで作戦は失敗した」と考えていた、と語ったそうです。ディジリオはしかし、捜査中に心筋梗塞で倒れ、捜査継続不能の身心喪失に陥り、2005年に死亡。
1994年には、前述のマルティーノ・シシリアーノが『フォンターナ広場爆破事件』の爆弾の準備に関わっていたことを告白しています。その際、事件で逮捕されたアナーキストたちがスケープゴートであったこと、『鉛の時代』に起こった極右テロ爆発事件のうちの2件が、ディジリオが調達した爆弾だったことも語りました。
さらに1995年、サルヴィーニ裁判官が率いたカラビニエリ特殊部隊捜査では、元SID諜報メンバー、ニコラ・ファルダの証言を得ることに成功。1969年にSIDを辞めたファルダは、数々の爆破事件が、内務省内部の特別オフィスとともに準備されたこと、SIDがその爆破事件の実行者をオーガナイズしたことなどを告白。また、内務省がアナーキストグループにくまなくスパイを送りこんでいたことが明らかになりました。
1998年、サルヴィーニ裁判官はCIAメンバーを書類送検、NATO諜報メンバー、さらに極右グループ『アヴァンガルディア・ナチョナーレ』の創立者、ステファノ・デッレ・キアイエを裁判へ召喚しています。
|
||
| 裁判ののち、南アフリカに移住したSID「オフィスD」の長官ジャン・アデリオ・マレッティは、ラ・レプッブリカ紙のインタビューで、一連の極右グループによる爆破事件にCIAの協力があったことを認め、政府はそれらすべての情報を得ていたにも関わらず、SIDに介入することはなかったと発言。またSIDがイタリア、ドイツの極右グループを連動させるために政治活動に潜入し、CIAの協力者として活動したことについて言及しました。
なお、『フォンターナ広場爆破事件』で罪を問われなかったテロリスト、フランコ・フレーダは現在も自由の身として、新聞に署名原稿を書いたり、書籍を出版したりと普通の日常を送っています。最近では「マテオ・サルヴィーニ(極右政党『同盟』党首)こそがイタリアの希望だ」と発言し、物議を醸したこともありました。こうして、サルヴィーニ裁判官の粘り強く、執拗な捜査により、『無』から取り出された物語の断片、証言、証拠が、モザイクのようにひとつひとつはめ込まれ、グラディオ下の『緊張作戦』という巨大な『オペラ』が、長い時間を経て姿を現した。したがって、司法に裁かれることはなくとも、その事実とともにイタリアの近代史に刻み込まれることになり、『フォンターナ広場爆破事件』からはじまった『鉛の時代』は、末代まで語られ続けることになったわけです。
爆破事件が起こった『フォンターナ広場』で、2019年12月12日に開催されたメモリアルセレモニーに参加したセルジォ・マッタレッラ大統領、ミラノの市長は、事件の犠牲者の遺族、事件で亡くなったアナーキスト、ピーノ・ピネッリ夫人、殺害されたルイジ・カラブレージ警部夫人と面会し、無実の罪を着せられたアナーキスト、ピエトロ・ヴァルプレーダを含む被害者に、謝罪の言葉を述べました。 「『フォンターナ広場爆破事件』は、ミラノ、そしてイタリアが『無垢/無邪気/純粋性』を失った事件だった。国家の一部が謀略に関わった事実は、二重に罪深い」。イタリア共和国の大統領が『フォンターナ広場事件』のメモリアルに参加したのは、今年がはじめてのことでした。いつの間にか、世界中でナショナリズムによる排外主義、分裂、ファッショ化が進もうとする不安定な現代、あの時ルモール内閣が『緊急事態宣言』を発令しなかった理由は、犠牲になった方々の葬儀のためドゥオモ広場に集まった30万人の群衆の沈黙の力だと信じます。時の首相、内閣はその夥しい群衆ひとりひとりの尊い眼差しに「怖気づき、あるいは感銘を受け」、国民が主権を持ち、自発的に、自由に集まって思いを表現する『民主主義』、そして戦後のイタリアが築いてきた『共感』の力を、国際謀略によるクーデターで破壊することができなかった。 ならば、われわれ普通の市民がどんな国際謀略にも立ち向かうことのできるパワーを潜在させている、ということを明確に再認識できます。 |
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 | ||
| 2021.5.4日、「『鉛の時代』: 「蛍が消えた」イタリアを駆け抜けた、アルド・モーロとは誰だったのか」。 | ||
| 1978年に起こったアルド・モーロ誘拐・殺害事件は、イタリアの「ダラス」、あるいは「9.11」として、イタリアの近代史における大きな転換点となった事件と言われます。今のイタリアからはまったく想像できない、常軌を逸したテロが、凄まじい勢いで荒れ狂った『鉛の時代』。その悲劇は55日もの間、イタリアの社会を恐怖と緊張に陥れ、人々を絶望の淵に突き落としました。のち、犯人たちは逮捕され、司法で裁かれましたが、事件の詳細の辻褄が合わず、現代に至るまで全方向から調査が継続されるとともに、アルド・モーロという人物が、イタリアにとって、どれほど重要な人物であったかが、繰り返し語られることになる。その事件の重大さを理解するため、アルド・モーロとはいったい誰で、何をしようとしていた人物であったかを、まず知っておきたいと思います。
イタリアにおける『鉛の時代』に起きたそれぞれの事件に関して、夥しい数のジャーナリストや研究者たちがひたすらリサーチし続け、書籍、映画、芝居、ドキュメンタリー、TVプログラム、講演、講義として、次々に発表される事実については、以前の項でも幾度となく触れてきました。 そのなかでも、ひときわ群を抜いているのが、何といっても『アルド・モーロ誘拐・殺害事件』なのですが、まさに無限を彷彿とする、尋常ではない情報の多さで、ロックダウンをものともせず、絶え間なく書籍が出版されるのみならず、ネット上にも動画がアップロードされ、「それらすべてを網羅するには一生でも足りない」と意気消沈するほどです。わたし自身、少しずつではあっても、数年前から『アルド・モーロ事件』関連の書籍を読んだり、ドキュメンタリーや動画を見はじめたにもも関わらず、その情報が、まるで有機体であるかのように留まることなく増殖するため、「これじゃ追いつかない」と焦燥に駆られる次第です。このように、『アルド・モーロ事件』の背景に、ひっそりと息をひそめる不条理という底なしの闇を、白日の下に晒そうと徹底的にリサーチを重ねる人々の情熱は、ただごとではありません。それもジャーナリスト、研究者に留まらず、検察官、裁判官、政治家、大学教授、作家、歴史家、と老若男女を問わず、それぞれがそれぞれの視点で、まるで昨日の出来事のように事件を追い、細部を調べ上げ、その意味を世に問うのです。 いずれにしても、もはや43年前という遠い過去の事件であり、すでに犯人とされる者たちは司法で裁かれています。それにも関わらず、その事件をオンタイムに経験していない世代を含め、多くの人々が追い続け、政府議会では「事件調査委員会」が繰り返し形成され続けるわけですから、その執念には頭が下がるとしか言えません。 と同時に、アルド・モーロを衝撃的に喪失した事実が、イタリアにとっては決して忘れてはならない、重要なテーマを孕んでいることは疑いようがなく、言い換えれば、このテーマを解読しなければ、イタリアの現代は理解できないのではないか、とも思うのです。そういうわけで、先で追う予定にしている事件の詳細を前に、当時、イタリアの戦後の政治を掌握した、『キリスト教民主党』(現在は消滅)のリーダーであったアルド・モーロという人物が、いったい誰で、何を考え、何をしようとしていた人物なのか、総体として知っておきたいと思います。 なお、アルド・モーロ誘拐・殺害事件は、極左武装集団『赤い旅団』を、血に飢えた狼の群れ、狂気のテロリスト集団として、はじめて世界に名を轟かせた重大事件です。以前の項に書きましたが、創立メンバーである3人の若者たち、レナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニが逮捕され、マラ・カゴールが銃撃され亡くなったのち、マリオ・モレッティが執行幹部となった76年から、『赤い旅団』は大きく変質しています。74年に企てたマリオ・サッシ誘拐事件で、『旅団』の要求を退けた司法官フランチェスコ・ココを、その報復と称して殺害した76年からは、一切タブーが無くなり、影響力のあるジャーナリストや弁護士の脚に銃弾を打ち込んで、一生歩けないようにする「ガンビザッツィオーネ」を多発するなど、『旅団』は次第に凶暴化。ターゲットを国家の心臓部に向けはじめました(参考▶︎『赤い旅団』の誕生、フェルトリネッリ出版と『赤い旅団』、『赤い旅団』の変質と77年学生運動)。 あわせて、スターリニストを標榜する他の極左グループ(『マニフェスト』、『継続する闘争』、『ポテーレ・オペライオ』など)と大差がない、つまり小規模な放火騒ぎ、誘拐を繰り返してはいても、殺人に手を染めることはなかった『赤い旅団』が、普通の学生までが拳銃を手に荒れ狂った77年の学生運動あたりから、堰を切ったように過激になるにつれ、学生たちからは喝采が湧き、大きな支持を集めています。実際、『モーロ事件』の犯行メンバーとなった多くは、ボローニャ大学での大集会などでリクルートされ、77年に『旅団』に参加した若者たちです。 ちなみに、現在ネット上で公開されている、『赤い旅団』のメンバーたちの、当時の取り調べの経緯やインタビューを見たり聴いたりすると、執行幹部はともかく、その他は学生政治集会でよく見かける普通の若者たちのようでもあり、とても「血に飢えた、凶悪なテロリストたち」とは思えない、拍子抜けするような単純さです。もちろん、彼らが事件の中核にいたことに疑いの余地はなく、さらにグループの幹部であった人物たちは事件を巡る真相を語ってもいない、と思われますが、それにしても彼らの発言の数々は、あまりに日常的で幼く感じます。立居振る舞いも意外に礼儀正しく、彼らが犯した罪を知らなければ、むしろ世間知らずな善人と呼べそうな若者たちでもある。つまり、折に触れ、いかにも邪悪そうな人相のモノクロの写真とともに報道される、陰惨な「テロリストたち」という一般化されたイメージとはギャップが甚だしい、というのが正直な感想です。 78年の3月16日の事件当時、アルド・モーロを護衛していた警察官、カラビニエリ5人の方々が、数十秒のうちに次々に射殺され、時代を大きく動かす55日間の誘拐という、国家的悲劇がはじまったファーニ通りの現場には、現在、「確かに『赤い旅団』もいた」という表現(つまり他の何者かの関与があった)が定説となり、2018年の政府議会事件調査委員会のメンバーたちも、そう発言しています。『モーロ事件』を『赤い旅団』が単独で起こした事件だと考えているのは、わたしの知る限りでは、歴史家のアレッサンドロ・バルベーロぐらいでしょうか。前述したように、のちに逮捕された、当時の執行幹部マリオ・モレッティをはじめ、バルバラ・バルセラーニ、ヴァレリオ・モルッチ、アドリアーナ・ファランダらは簡単に自白し、司法で裁かれ服役もしていますから、確かにオフィシャルな犯人は『赤い旅団』であるには違いありません。ただ、歴史を変えるほどの重大事件を起こしたにしては、あまりに受刑期間が短く、創立メンバーであるクルチョ、フランチェスキーニが、殺人を1度も起こしたことがないにも関わらず、20年近く収監されたのに対し、事件を起こしたメンバーは数年で出所して、今も自由を謳歌している、という状況には、誰もが疑問を呈しています。事件から43年が経った現在、『赤い旅団』による単独の犯罪とされた、この事件の背景は、ほかの『鉛の時代』に起きた事件の数々と同様に、国家の中枢、SIFER、SIDら軍部、内務省諜報、秘密結社ロッジャP2、CIA、NATO、KGB、モサドなどの国際諜報、マフィアが網の目のように絡まる、謀略のモザイクとして、パズルのように解き明かされようとします(dietrologia)。しかし、証拠が上がらず、どうしても明らかにならない箇所がいくつも残るのです。もちろん、それぞれのリサーチ、着眼点は確かに興味深く、納得する部分もあります。それに、事件のあらゆる側面に手がかりが残されているにも関わらず、物語が複雑すぎて全体が見えない、決着のつかない謎を追うことは、わたしを含める人々を夢中にもします。しかしながら、あれこれと情報を集めるうちに、ただ謀略の断片のみを追いかけるだけでは、事件の本質は見えてこないのではないか、と考えるようにもなりました。 そこで、レスプレッソ誌主筆であり、近代歴史家でもあるマルコ・ダミラーノの『Un atomo di verità(真実の核心ーアルド・モーロとイタリア政治の終焉/2018年)』をガイドに、レオナルド・シャーシャの『Affaire Moro(モーロ事件)』、長年、モーロのスポークスマンだったコラード・グエルゾーニの『アルド・モーロ』などの書籍、映画『Todo Modo』(トド・モド/エリオ・ペトリ)、ピエールパオロ・パソリーニの『権力の空洞化、すなわち蛍の記事』(75年/コリエレ・デッラ・セーラ紙)、Youtubeにアップされている講演、インタビューなどを参考に、アルド・モーロという人物が時代に与えた影響を、まず考えてみたいと思います。 ダミラーノは、かつて「ここにイタリアで最も重要な人物がいる」、と父親に連れられて行った教会で祈りを捧げるアルド・モーロの姿に出会い、そのイメージが脳裏に焼きついたまま、事件直前には、小学校のスクールバスでファーニ通りを通った、という稀有な経験をしています。そして、その幼少時代の記憶とともに、レオナルド・シャーシャとパソリーニの分析から『真実の核心』を書きはじめました。 事件の経緯とともに、人間アルド・モーロの政治家としての軌跡を、自分の足で歩いて現場をリサーチしながら時代を俯瞰しており、ジャーナリズムというよりは文学的ともいえる、他の『モーロ事件』に関する書籍とは異なる、読み応えのある一冊です。また、常にモーロのそばにいたコラード・グエルゾーニの著作は、ジャーナリスティックではありながらも、モーロへの深い尊敬が垣間見え、権力の座にぶら下がる、モーロの同僚政治家たちの、怪物的とも言える冷酷非情な対応も赤裸々に描いており、ある意味ぞっとした次第です。 何より、事件の3ヶ月後に脱稿された、レオナルド・シャーシャの『モーロ事件』の分析と疑問は、彼自身がこの政治家の敵対者であったにも関わらず、当時の誰よりも尊厳ある、人間的な同情で事件の本質が語られ、43年経った現在も、ほんの少しも色褪せてはいません。むしろ、短期間での執筆でありながら、事件の背景をすべて見透かし、真相を暗示するかのような驚くべき内容で、その後のすべての捜査、リサーチはシャーシャのこの分析を基盤にしているのではないか、と勘ぐるほどでもありました。1982年に『モーロ事件』政府議会調査委員会のメンバーであったシャーシャは、そのレポートに、「これらの疑問には、後年の歴史家たちが決着をつけていくであろう」とも書いています。 |
||
| 冷戦という時代とアルド・モーロ | ||
| 1916年、南イタリアのプーリアで生まれたアルド・モーロは、第二次世界大戦後に形成された、イタリア共産党を含む、あらゆる全ての党が参加した大連立政府を経たのち、1948年の国政選挙で第1党に躍り出てからの30年間、イタリアで揺るぐことのない権力を誇った『キリスト教民主党』政治初期の象徴とも言える人物です。
1959年にわずか33歳で党の一等書記官となり、1963年から1968年の5年間、イタリアで最も長く持続した中道左派政権を担い、さらには1972年から1974年にも首相を務めています。 1947年からは憲法制定議会に加わり、イタリア共和国憲法第1条の「イタリアは労働に基づく民主主義共和国である」部分の論議にも関わった経緯があるそうです。レジスタンスそのものには参加していないモーロは、その際、「憲法はファシスト、アンチファシスト、いずれであってもならない」、共和国憲法は、確かにレジスタンスを出発点として制定されるが、それは「思想とは関係がない」とし、「Felice convergenza di posizioniー(国は)それぞれ違う立場の者たちの幸福な集合体であり、共和国としての国家機構は撤回できない」との論点を提示し、制定議会で採用されたことを、グエルゾーニが指摘しています。「自由と公正こそが、われわれの国の民主主義における、人間の条件として最も相応しい、本質的で、それぞれが相関するアスペクトだ」と考えるモーロは、常にその実践を目指していました。以前の項にも書いたように、イタリアの『民主主義』における個々の市民の権利、社会の相互扶助のアイデアは、ファシズムの圧政に立ち向かったパルチザンたちが勝ち獲ったものです。したがってイタリア共和国憲法は、確かにパルチザンたちのレジスタンスから生まれたものですが、「憲法は思想とは関係なく、国はそれぞれ立場が違っても、幸福な集合体であるべきで、それぞれの個的な生活、社会的相互扶助、集団の独立性は侵すことはできない」とモーロは考えていたということです。しかしながらモーロは、ファシズム思想、右翼思想は憲法に反するエゴイズムだとして、自らが政権にある間は、右派勢力を遠ざけたため、『キリスト教民主党』内の右派やMSI(イタリア社会主義運動)など極右政党からは、「敵」とみなされていました。 また、モーロは政治家であっただけではなく、大学教授でもあり、1951年からはプーリアのバーリ大学で法哲学教授として教鞭を握り、63年からはローマ大学サピエンツァ、政治学科へ移動。政権にある間も含め、刑事法・刑事訴訟法の教授として、政治の状況がどれほど厳しくとも、授業を休むことはなかったそうです。 のちに『赤い旅団』の人民裁判にかけられ『死刑』となるモーロは、その授業では「復讐と罰は異なるものである」とし、「法で定められた殺人は、民主主義の社会、政治にとって考えられないほど恥ずかしいこと」、と『死刑』には絶対的に反対しています。さらに学生たちとの交流にも活発に参加し、学生たちを連れて刑務所に慰問に訪れるなど、生涯に渡って受刑者の人権についての働きかけも継続。1978年3月16日、ファーニ通りで誘拐された際、乗っていたフィアット130に残された鞄のひとつが、学生たちの卒業論文でいっぱいだったことは有名な話です。このように、モーロという人物は、若者たちとの対話に熱心で、68年(激しい学生運動が巻き起こった時代)の若者たちの討論会をテレビで観た際には、「あの若者たちに会いたい」とのモーロの要望で、69年、実際に両者の討論会が実現し、その中には極左グループに属していた青年もいて、彼はのちに政治家になっています。 なお事件当日、幻の『歴史的合意』として語り継がれることになる、ジュリオ・アンドレオッティを首相とする『キリスト教民主党』の政府に、戦後の大連立以来はじめて、イタリア共産党がApoggio esterno(外部からの過半数参加)として政府に参入する、議会における記念すべき投票に参加したのち、モーロはいつも通りにローマ大学へ向かい、卒論の懇談会に立ち会う予定でした。 モーロがキリスト教民主党、つまり政治の中枢にいた時代は、もちろん冷戦のまっただ中です(参考▶︎ 諸刃の剣『グラディオ』)。 のち、90年になってアンドレオッティが「公表」したグラディオ作戦のもと、CIA、NATOの国際諜報、イタリア軍部SIFER、内務省SIDなどの諜報、カラビニエリの幹部、君主制を目指す右翼分子、そして国家の中枢の一部、さらには秘密結社ロッジャP2が加わり、東欧からイタリアに迫る共産主義を水際で堰き止め、国内で勢力を拡大するイタリア共産党の躍進を阻止する目的で、何度もクーデター未遂が起こっています。さらに、長期モーロ政権が崩壊した翌年の69年(キリスト教民主党右派の嫉妬によるとされますが)には、「安定のための不安定化」を目的に、社会を劇的な大混乱に陥れる『Strategia della tensione(緊張作戦)』『Stay Behind(ステイ・ビハインド)』と名づけられた謀略が、『フォンターナ広場爆破事件』の凄まじい極右テロで幕が落とされました。その衝撃に煽られた、極左グループをはじめとする若者たちの反発は次第に激化し、イタリアはやがて、市民戦争にまで発展する、『鉛の時代』に突入するわけです。 つまりモーロが生きたイタリアは、ある意味、南米の状況に近い、冷戦における「オーソドックスではない戦争」が繰り広げられたひとつの戦場でもあり、西側諸国が悪魔と見なすイタリア共産党が、『民主主義』における『選挙』によって、欧州の国々の中で、市民の支持を最も多く集めた国でもありました。そのイタリア共産党は、『選挙』のたびに支持率をじわじわと伸び続け、70年代中盤からは国政に手が届きそうな勢いとなります。しかしながら、こう言っては何ですが、イタリアという国そのものが、米国から支援された共産主義パルチザン(カトリック僧や君主制主義のパルチザンも存在しますが、きわめて少数です)の、レジスタンスから建国された国でもありますから、そのパルチザンの流れを汲むイタリア共産党が、市民の支持を集めるのは、当然といえば当然の流れです。 ちなみに、現在でも4月25日の解放記念日の前後には、必ずといっていいほど『ムッソリーニ最後の日々』という映画が放映されるため、外国人のわたしにも、パルチザンの重要性が叩き込まれています。イタリア市民は基本、祖国が敗戦国だとは決して認識せず、胸を張って、ファシズムからの解放を祝いますから、おそらく当時の米国にとっては憎らしい存在ではあったに違いありません。しかも戦後は、といえば、ヤルタ会談における大国の勢力圏合意など、まったく無視して、イタリア共産党が勢力を伸ばし続けていたのです。なお、長年のスポークスマンであったグエルゾーニは、モーロはNATO誕生のきっかけとなる北大西洋条約には、なんら関係がなかった、と断言しています。つまり戦後のイタリアの背景にある、NATOが全面に支援した一連の謀略『グラディオ』を、政権の中枢にある人物として、おそらくうすうす知ってはいても、決して加担した人物ではなかった、ということです。むしろその謀略を、「薄暗い何か」として忌み嫌う発言を、周囲に漏らしてもいたようです。 そしてモーロを語る際に、まず重要なのは、冷戦という時代を生きる国を担う政党のリーダーとして、同盟国から敵視され続ける、イタリア共産党と積極的に手を結ぼうとしたことでしょう。現代から俯瞰するならば、バイオレンスカルトに満ちたその緊張の時代、キリスト教民主党のモーロも、イタリア共産党のエンリコ・ベルリンゲルも、対立ではなく対話、思想を超えた和解、多様性を認める共生こそが、社会の緊張を和らげ、イタリアだけでなく、世界の発展をもたらすのだと考えていました。この、モーロとベルリンゲルが、交渉に交渉を重ねてきた『歴史的合意』としての連立政府が、もし実現していたならば、イタリアがいち早く『ベルリンの壁』になった可能性すらあるのではないか、と語る歴史家も存在します。おそらく、両者ともに、時代に張り巡らされた危険な謀略の数々の、その背景を知っていたでしょうから、国内外からのさまざまな妨害に屈することなく、憲法に認められたヴィジョンに向け、交渉を重ねた姿勢は、当時の世界を覆った「ヤルタ体制」に真っ向から挑む、まさにレジスタンス、とも呼べる勇断であったと思います。加えて、このレジスタンスの魂こそが、現代に至るまで、人々の情熱を掻き立てながら『モーロ事件』を連綿と生かし続ける、最も重要な要因ではないか、とも思うのです。 さて、演説が「長く、ゆっくりとしていて、難解で退屈だった」と、その複雑な言語表現を指摘されることも多いアルド・モーロという人物を、あらゆる説明を飛ばしてシンプルに表現するならば、血塗られた時代の背後にうごめく「薄暗い何か」と、深い絆を持つ者も存在するキリスト教民主党の中枢にあって、彼らからは距離をとり、「左右の思想で分裂し争うのではなく、ともに認め合いながら市民のよりよい生活を取り戻そう」と静かに、ゆっくりと、しかし信念を曲げることなく対話し続けた人物というところでしょうか。ファシズム時代に青年期を送ったモーロは、自らをファシストともアンチファシストとも表明しておらず、そもそもアンチファシストを旨とする『キリスト教民主党』の結党メンバーになる際には、その出自を疑われたというエピソードもあるそうです。そのモーロを強く推薦したのはカトリック司教だったそうですが、つまりモーロの政治の中核は思想ではなく、キリスト教への深い信仰であり、その信仰に基づいて熟慮された『民主主義』のあり方、憲法だということでしょう。そしてその姿勢は、最後まで貫かれることになりました。 |
||
| 禁断の共生へ向けて | ||
| 同盟国が一斉に敵と見なす『イタリア共産党』と、『キリスト教民主党』が手を握る決断をしたのは、「憲法こそがすべての法律の上位に存在する」と考えていたモーロが、憲法に明記される『民主主義』における自由と公正を、市民の意志にしたがって実現しようとしたからです。また、『イタリア共産党』への接近と対話を、当時のイタリアを覆っていた『Strategia
della tensione(緊張作戦)』を皮肉ったのか『Strategia dell’attenzione(心遣い作戦)』と名づけています。そしてその、時代の空気を読まない(ふりをする)、揺るがぬ態度が、同盟国を逆撫でしました。そもそもソ連からはスターリニストと定義されていた、当時の『イタリア共産党』は、多くの同志や知識人から激しい反発を受けながらも、ゆるやかに武装革命の旗を降ろし、やがてソ連とはさらっと距離をとり『民主主義』における『選挙』での躍進を目指していました。これが、ソ連からは独立した『イタリア共産党』独自のユーロコミュニズムという穏健路線です。 77年の国政選挙では(投票率93.40%!)、下院『キリスト教民主党』38.71%に対し『イタリア共産党』34.37%、上院『キリスト教民主党』38.88%に対して『イタリア共産党』33.83%と肉薄。70年代に入ってアルド・モーロとエンリコ・ベルリンゲルによって模索されていた『歴史的合意』は、ここで一気に加速します。この時期、合意が成立する最後の最後まで、いずれの党にも「騙されるのではないか」と疑心暗鬼に陥る反対派が多く存在し、緊張がみなぎっていたそうです。 当然のことではありますが、モーロが若く、勢いがあるベルリンゲルに両手を開いたのは、真の『民主主義』を実現すると同時に、支持を失いつつある、自らが長きに渡って率いてきた『キリスト教民主党』の威信を守るためでもあったことは、疑いの余地はありませんし、グエルゾーニもそう分析しています。さらにこの時期、イタリアでも『ロッキード事件』が勃発していますが、メディアから一斉に攻撃されても、モーロは収賄で糾弾された同僚を議会で徹底的に弁護し、『キリスト教民主党』を守っています。もちろん、イタリアの共産主義化を恐れていた同盟国及び党内右派、極右政党、極右グループは、際限なく左傾化し、『イタリア社会党』を政府に迎え入れるのみならず(63年〜68年の長期政権時代に、モーロは『イタリア社会党』と連立しています)、さらには次第に『イタリア共産党』に近づくモーロを激しく警戒。何度も脅しをかけ、連立を阻止しようとしています。後年、レスプレッソ誌によってすっぱ抜かれた、64年、カラビニエリ大佐、デ・ロレンツォが画策したクーデター「ピアノ・ソロ」では、当時首相であったモーロの殺害計画まで組み込まれていたそうですし、72年に起こったイタルクス列車爆発事件の目的は、その列車に乗っていたモーロの殺害であったとされます。ネオファシストによって爆弾が仕かけられ、12人の方々が亡くなる大惨事となったイタルクス事件では、列車が出発した直後、モーロは秘密裏に連絡を受け、次の駅で下車。九死に一生を得ています。 政権を率いていた74年(72年〜74年)には、レオーネ大統領の渡米に同行したモーロに、当時、国務長官だったヘンリー・キッシンジャーが「もし、わたしがあなたのようにカトリック教徒ならば、無原罪懐胎の教義を信じるだろうが、わたしはカトリックではないから、そんな教義も、『イタリア共産党』の民主主義的進歩も信じない」と言ったそうです。おそらくキッシンジャーが言ったのは、そんなメタフォリックで上品な言葉だけではないと思われますが(米国は、このまま『イタリア共産党』が躍進を続けるのであれば、軍事行動も辞さない、と発言したこともあるそうですから)、その後、教会のミサに参加していた際に具合が悪くなったモーロは、予定を切り上げて帰国しています。モーロはイタリアに到着するや否や、「少なくとも2年間、わたしは政治の世界から消える。各メディアにそう伝えてほしい」と、グエルゾーニに連絡。いくつかのメディアが、モーロを批判するとともにそのニュースを書き立てました。しかし結果的には諸事情が許さず、モーロはそのまま政治の世界に留まることになります。一方キッシンジャーはその後、その発言を否定し、後年には「アルド・モーロ? 誰?」とまでとぼけますが、モーロとキッシンジャーの間に激しい葛藤が繰り広げられたことは明らかです。なお、71年には、モーロがモスクワを訪問し、『ソビエト最高会議』を見学。ブレジネフと会談した、というエピソードもありました。モーロが首相の座を降りた75年ごろからは、米国大使館、企業家、姿が見えない策士たち、各国の諜報が、モーロをおだてたり、すかしたり、脅迫したりという攻撃や暗示が多くなり、右派のメディアがフェイクニュースを拡散するなどして、モーロを『キリスト教民主党』内で孤立させようと仕向ける動きが目立つようになったそうです。またアンドレオッティがワシントンに招かれ、『キリスト教民主党』の勢力を蘇らせる作戦を伝授された、との情報もあります。なお60年代、モーロが米国デビューした際、米国の政界では「モーロは踊らない」と囁かれたと言います。というのも米国では、イタリアの政治家は文字通り(ダンスができる)にも、メタファー(1歩進んで2歩下がる)としても、「バレリーノー踊り子」と表現されていたからだそうです。つまりモーロが、従来のイタリアの政治家のイメージとはまったく違う、踊らない、つまり意見を変えない、空気を読まない異例の政治家だ、という意味なのでしょう。 |
||
| パソリーニの『蛍の記事』とシャーシャの『Todo Modo』 | ||
| では、その時代の左派知識人たちの目にアルド・モーロはどう映っていたのか、と言えば、残念ながら、その多くが批判的なものばかりです。 というのも、マーシャルプランの恩恵を受け、「奇跡」と呼ばれる復興が進んだ戦後のイタリアの政治を担った『キリスト教民主党』は、確かに都市部を裕福にはしましたが、富が行き渡らなかったイタリア南部、都市部周辺の郊外に、甚だしい貧困を生むことにもなり、社会には不満が渦巻いていたからです。
この時代、南イタリアから仕事を求めて都市部へと移民する人々は、ボルガータと呼ばれる郊外の新興地で不法バラックに住まざるを得ず、非正規労働でようやく食いつなぐという状況でした。
国内の産業化が進み、貧富の差がいよいよ開いた69年には、不定期採用の工場労働者、農民、失業者たちが自らの権利と保障を求め、68年(フランスの5月と同時)にイタリア全国に巻き起こった学生運動と共闘し、「多国籍企業による、米国型資本主義経済に占領された」社会を破壊する『革命』を目指す「熱い秋」が勃発します。
78年の『アルド・モーロ事件』の実行犯となる『赤い旅団』も、この学生運動から生まれるわけですが、イタリア共和国建国の経緯同様、彼らの思想もまた、パルチザンのレジスタンスの流れを汲んでいるという事実は興味深いことです。実際、この時代の学生運動のモデルは、野山を駆け巡ってファシストと闘った、荒くれたパルチザンたちであり、フィデル・カストロやチェ・ゲバラとも親交があったジャンジャコモ・フェルトリネッリという、若き日にレジスタンスに加わった大富豪が、学生たちを資金面でも精神面でも支えるパトロンでもありました。 なお、イタリアには基本、共産主義に負のイメージはなく(右派を支持する人々はともかく)、時代とともに消滅した『イタリア共産党』に並々ならないノスタルジーを抱き、アントニオ・グラムシ、そしてエンリコ・ベルリンゲルを英雄視する若者たちが、非常に多く存在することは注目すべきことです。
もっとも68年の学生運動の主人公たちは、『キリスト教民主党』のみならず、穏健路線へ向かった『イタリア共産党』までをも、ファシスト、右翼と捉える極端な武装革命思想を持っていたわけですが、まったく庇うつもりはなく、その暴力性を強く否定したとしても、イタリア建国の流れや時代背景を鑑みたうえで、「あまりに不平等で不正に満ちた社会を破壊し、再構築したい」という欲動に駆られた10代、20代の青年たちの想い、そのユートピア幻想を理解できないでもありません。
一方、その68年の学生運動を「中産階級の子供たちの革命ごっこ」と手厳しく批判したピエールパオロ・パソリーニは、1975年、自身の殺害事件の9ヶ月前、コリエレ・デッラ・セーラ紙に「権力の空洞化、すなわち蛍の記事」と題された、まさにその時代の政治を分析した記事を書いています。その記事でパソリーニは、『キリスト教民主党』を「戦後10年間、純粋に、そして単純にファシズム体制を持続させた」とし、それから「何か」が変わり、その後「完全に新しい何かが生まれた」、「60年代はじめから、水の汚染のせいで蛍が消えはじめ、それはあっという間の出来事だった。それから数年の間に蛍はすっかり消えてしまった。『何か』は10年前に起こったのだ。それを私は『蛍の喪失』と呼ぼう」と書きました。パソリーニは、戦後から75年までの『キリスト教民主党』が政治を掌握した社会の状況を「蛍が消える前」、「蛍が消えつつある時代」、そして「蛍が消えた後」と分けて分析しているわけですが、「蛍が消える前」の『キリスト教民主党』による政治は、完全にファシズム時代の継続であると定義。そしてこの定義が、当時の左派知識人、そして学生たちと労働者に共有される『キリスト教民主党』への評価でもありました。「教会、祖国、家族、服従、規律、秩序、節制、道徳」という、アルカイックなイタリアの農村の価値観を国の価値観とした、『キリスト教民主党』の「順応主義におけるエリートたちの田舎臭さ、無教養、無知は、ファシズム時代と同質である」とし、「蛍が消えつつある時代」は、イタリアの中に『イタリア共産党』が率いる労働者と農夫たちが、もうひとつの大きな国を創りはじめていた時代であったが、「前衛的で批判的な知識人でさえ、この時、蛍が消えつつあるのに気づいていなかった」と、パソリーニは言うのです。そして、『イタリア共産党』率いる労働者たちが、イタリアに実現しなければならない、(産業の)発展による「よりよい生活」のために声を上げたその時代が、マルクスの『共産党宣言』を大量虐殺した「蛍が消えつつある時代」だと断言します。つまり、この「蛍が消えつつある時代」は、アルド・モーロが『キリスト教民主党』のリーダーとして、63年〜68年の長期政権を率いていた時期、そして『イタリア共産党』が大きく躍進した時期と重なるということになります。さらにパソリーニはこの時期、『イタリア共産党』の議員たちの、まるでブルジョアのような振る舞いや言動、また69年以降、イタリアを襲った連続テロに、何の意思表示もしない状況を非難していました。「蛍が消えた後」は、アルカイックな農村の価値観である「教会、祖国、家族、服従、規律、秩序、節制、道徳」の偽造はもはや意味のないものとなり、「農村や手工業とはまったく異なる新しい文明の価値観へと置き換えられた」と続き、60年代に強烈に進んだ産業化で、「少しの期間に、人々は滑稽で異様に、犯罪的になった」、「その人々を愛すべきだとは思うし、ー残念ながらー今までその人々を真剣に愛してきたが、人々の良識は消費され、取り返しがつかないほどに悪化している」と社会を痛烈に批判します。『キリスト教民主党』の権力者たちは、「この数ヶ月の間に有権者が好みそうな、信用できない誠実さで、常に瞳を輝かせて微笑み、陽気に振るまうという、いかにも不吉に思えるマスクを被るようになり、行動することなく、ただ、だらだらと無駄話をするだけで、彼らはもはや骨と灰の塊と化している」と酷評。「今日のイタリアの現実は、権力の悲劇的な空洞化だ」と断じます。産業化が進んで「蛍が消えた後」の『キリスト教民主党』は、『消費』に権力を奪われ、国民投票における『離婚法』(70年)の成立で敗北し(カトリックは本来離婚を認めていませんでしたから、完全な敗北です)、もはや何者でもなくなっている、とパソリーニは分析しているのです。 そして、ここではじめてパソリーニはアルド・モーロの名を出します。「権力者たち、特にアルド・モーロは完全に新しい表現(ラテン語のような理解できない表現)を使いはじめた。現在まで、とりあえず権力の座にいるモーロは、69年から今日まで(75年)オーガナイズされた、数々の酷い出来事すべてにはまったく関係がないように見えるが」と、直感的にモーロの立ち位置を見抜き、それでもパソリーニにとっては「謎めいた存在」であるモーロを含む『キリスト教民主党』全体を、まったく効力のない権力と捉えている。つまりパソリーニは「蛍が消えた後」、イタリア中に産業化が進んだ10年というもの、顕在化されない真の権力は彼らなしで進行している、と政治不在を糾弾しているわけです。その頃のパソリーニは、真のファシズムは『消費主義』であり、ファシストたちすら変えることができなかったイタリアの風景を、『消費主義』はあっという間に破壊した、と訴えてもいます。もちろん、戦後の短期間での産業化による、この環境破壊が、現在の地球温暖化にも通じる、熟考すべき歴史であることに、疑問の余地はないでしょう。 一方、レオナルド・シャーシャは、「パソリーニとともに、パソリーニのために」書いたという78年の『モーロ事件』の序文に、この「蛍の記事」を引用して、もはやこの世には存在しないパソリーニへのレスポンスとして、事件後明らかになった『キリスト教民主党』におけるモーロの存在とその動きを分析します(後述)。そのシャーシャは、といえば、自らの同名の小説『Todo Modo』を、エリオ・ペトリ監督とともに1976年に映画化。共産主義を感染病と捉える(さらにはその時代に吹き荒れたテロリズムをも暗示)『キリスト教民主党』とアルド・モーロ、そして聖職者たちを、うしろ暗く、病的で、徹底的にグロテスクなストーリーで表現しました。その『Todo Modo』は、『アルド・モーロ事件』直後、まるで事件を予言していたようだと糾弾され、長期に渡って上映禁止となっています。地下教会のカルトな儀式に集う、ダークスーツに身を包んだ権力者たちの秘密結社的な群れ(ロッジャP2をも彷彿とします)の、謎に満ちた相関関係と非人間性を描いた、その政治ノワールを観たのは、ごく最近のことですが、パソリーニの映画監督デビューとなった『アッカットーネ』で、ルンペンプロレタリアートの青年を演じたフランコ・チッティが、ストーリーの重要な役柄を演じたことにも、時代のメッセージを見出しました。延々と続く、不安と苦悶と血みどろのシーンに「これはひどい」と思いながらも、『キリスト教民主党』を巡る、左派知識人の怨念を、何となく理解できたように思います。 なお、シャーシャが「死の世紀」、「シロッコの世紀」と呼ぶ、テロの嵐がイタリアに吹き荒れた『鉛の時代』、真相はいまだ闇の中でも、当時の左派知識人、若者たちは、当局、すなわち『キリスト教民主党』の関与を深く疑っていました。そのような時代に、政党の中枢にあり、象徴的な役割を担い続けたアルド・モーロが、矢面に立たされ批判を浴びる対象となったのは、ある意味、しかたがなかったのかもしれません。それに、まだこのときは、『モーロ事件』の予兆は何ひとつなかったのです。マルコ・ダミラーノによると、シャーシャは『Todo Modo』の制作について、「70年代、戦後30年もの間、政権の座に居座る、滑稽で収賄に満ちた政党が国であるかのような状況を破壊したいという欲動に突き動かされた。カタルシスとしての表現であった」と語っていたそうです。いずれにしても、シャーシャは『モーロ事件』ののち、「アルド・モーロが人生を変えた」とまで言っており、『Todo Modo』の原作者としての責任を感じ、事件を徹底的に、正確に分析しています。そして『キリスト教民主党』を、あれほど暴力的な表現で糾弾したシャーシャが、事件が起こった際、モーロの「友達」であるはずの同僚政治家たちの誰よりも、モーロの尊厳を守り、人間的な、そしてどのメディアより、卓越した視線で経緯を捉えることになるわけです。また、証拠が何もないままに想像をたくましくすることが許されるならば、ー『モーロ事件』が巷間で断言され続けるように、プランニングされた事件であると仮定してーそのテーマである「滅びゆくべき古い権力」をモデルにプランされたのかもしれない、と思うほど、『Todo Modo』の抽象性は、事件の経緯を彷彿とさせます。さらに、やはり何の証拠もないままに、想像をさらに逞しくすることが許されるならば、パルチザンである『ガリバルディ旅団』がムッソリーニを人民裁判にかけて『死刑』に処した、イタリア解放のきっかけとなったイベントを、パルチザンをモデルとして形成された『赤い旅団』に踏襲させるプランが練られたのかもしれない、とも、ふと考えました。ただしアルド・モーロが、ファシストとは真逆の考えを持つ人物だったことを、時代はまだ、まったく理解していませんでした。 |
||
| 時代を覆う不安に共鳴したパソリーニとモーロ | ||
| レオナルド・シャーシャは、『モーロ事件』の序文で、「昨晩、散歩に出ようと家を出たとき、壁の裂け目に蛍を見つけた。少なくとも40年間、この田舎ではそれを見ることはなかったから、はじめは石、あるいは鏡の欠片が混ざった壁の漆喰かと思ったのだ」と、長らく見なかった蛍が戻ってきたシーンからはじめ、パソリーニの『蛍の記事』へのレスポンスであることを明らかにします。「蛍。政府(il Palazzo)。政府による審判。コリエレ・デッラ・セーラにパソリーニが書いたこの記事(75年)のように、誰もいない部屋を、すでに一掃され空洞化した部屋を、アルド・モーロだけが駆けずり回っていたのだ。その部屋は、もっと安全で、新しく、重要な他の誰かのために、すでに一掃されていた。(ここでわたしが)もっと安全な、というのはさらに劣悪な者たち、という意味である。つまり(モーロは)遅れていて、孤独で、『最も巻き込まれないまま』、自分がガイドであるということを信じていた。そして遅れていて、孤独だったのは、『最も巻き込まれていない』からだった。『最も巻き込まれていない』からこそ、さらに謎めく、悲劇的な相関性へと運命づけられたのだ」。シャーシャが『モーロ事件』をパソリーニに捧げた時点で、このシチリアの偉大な作家が、2年半の時を置いて起こった、あまりに衝撃的なふたつの事件に、ある種の関連を認めていたことは明らかと思われます。いずれにしても、2021年現在、75年の『ピエールパオロ・パソリーニの殺害事件』、78年の『アルド・モーロの誘拐・殺害事件』のいずれの悲劇も、証拠が多数残されているにも関わらず、検証が曖昧なまま犯人が断定された、『鉛の時代』に画策された謀略の一環と見られています。 また、パソリーニの殺害事件で唯一犯人として逮捕された少年、ピーノ・ペロージの少年犯罪裁判は、モーロの実弟である検察官カルロ・アルフレド・モーロが担当したという経緯があり、「あらゆる明白な証拠を鑑みるならば、明らかに集団による犯行であり、ペロージひとりの犯行とは考えがたい。共犯者が存在する犯行」とペロージ単独犯を否定する一審判決を下している。しかしその後4年に渡る裁判で、その判決は却下され、のちにロッジャP2のメンバーであったことが明らかとなった少年側の弁護人の控訴で、「最終的には共犯者の可能性はありえず、ペロージひとりの犯行」と断定されることになりました。おそらくシャーシャは、何ひとつ具体的な証拠はなくとも(のちに多くの証拠が提示されることになりますが)、ふたつの事件の背後に横たわる、深い、底なしの闇を見据えていたのでしょう。なお、シャーシャの『アルド・モーロ事件』の分析で、誠実に感じたのは、事件が起こった2日後から、それまで各種メディアがモーロを表現する形容詞であった、「重要なリーダー」から「偉大な政治家ーGrande Statista」へと、突然に変わった、という観察でした。Statista=Uomo dello stato は国政に手腕のある政治家という意味です。シャーシャはメディアが一斉に、突然大袈裟な表現を使いはじめ、悲劇を煽りはじめたことに違和感を感じた、と率直に述べている。これは、シャーシャにとってモーロは政治家ではあっても、決してStatistaではない、という主張でもあり(敵対者でしたから)、と同時に、メディアが一斉に「偉大な政治家」の悲劇として、国中を巻き込む絶望的で壮大なメロドラマに仕立てあげようとしたことを指摘しているのです。『モーロ事件』は、確かにイタリアの歴史を変えるほど、国中に衝撃を与える事件だったには違いありませんが、一般論として、突然大仰に論調を変えながら、市民の日常を飲み込むメディアの違和感は、わたしもたびたび感じます。メディアの大袈裟な表現による過剰報道は、人々を簡単に集団ヒステリーに陥れますし、リアリティ・ショーの原点はここにあるのかもしれない、と思うぐらいです。 さて、ダミラーノによると、シャーシャとパソリーニは共に互いを尊敬しあい、距離は遠くとも「兄弟」のような気持ちを抱いていたそうです。「わたしが感じている深い恐れはパソリーニと同じだ」「イタリアの政治と知性は解体からはじめるべきだ」とも語り、パソリーニの死の知らせに、シャーシャは「心から話すことができる唯一の人物だった。わたしたちはすべてを殺してしまった」と号泣しています。なお、パソリーニが予期せぬ死を前に、最後に読んだ本は、シャーシャの「マヨラーナの失踪(75年)」であり、「素晴らしい!なぜならシャーシャはミステリーを見たからだ。彼はそれを語ってはいないが、君にはわかったかい? この本が素晴らしいのは、分析のせいではなく、シャーシャが絶対に明らかにならないことを凝視しているからだ」と絶賛したそうです。そのパソリーニの言葉に、わたしはハッとすることになりました。『マヨラーナの失踪』を読んだ時、その時代背景をまったく考えていませんでしたが、つまりシャーシャは、突然消えたマヨラーナの、決して明らかにならない真実に、真相が明らかにならない時代の事件の数々をクリプト化した、ということなのでしょう。そしてシャーシャを絶賛したパソリーニは、それから時を置かず、自ら「絶対に明らかにならない」時代の闇のなかに消えて行くことになってしまう。それが忌まわしい時代の運命でした。マルコ・ダミラーノは、『真実の核心』を書いた動機として、歴史の記憶として『モーロ事件』にあまりにも強くイメージ付けられたアルド・モーロを、「人間として、政治家として、そして教授として、『赤い旅団』の人民刑務所、人民裁判から解放したかった。それが執念になっていた」と書いています。事件現場からはじまり、シャーシャが『モーロ事件』を執筆したシチリアの小さい街ラカルムート、モーロが生まれ、青年時代を送ったプーリアを自分の足で歩き、それぞれの足跡を克明に調べ上げ、55日間もの間、人民刑務所に囚われたモーロが書いた多くの手紙、メモリアルに実際に触れ、インクの色や筆跡を確かめ、事件の背景とモーロの心理を見据えています。 特に感銘を受けたのは、事件当時、『イタリア共産党』の上院議員で、モーロ事件政府議会調査委員会、ロッジャP2政府議会調査委員会のメンバーであったセルジォ・フラミンニが集めた公文書、印刷物、極秘文書などを管理するアーカイブセンターを訪ね、膨大な数のアルド・モーロの写真や日常の手紙、いつもダブルのダークスーツを纏っていたモーロの、カジュアルな服装の写真などを一枚一枚選んで対峙しながら、人間としてのモーロの人物像に迫ったことでしょうか。モーロがどの写真も大勢の人々と写っており、ひとりだけ目立つような仕草をしている写真が一枚もないことを、ダミラーノはまず指摘。その大量の写真や、忙しい中に丁寧に書かれた日常の手紙の数々から、SNSで攻撃し合い、ナルシシスティックなプロパガンダにいそしむ、現代の多くの政治リーダーたちとは人間の器が違う、と強調しています。イタリアにおいて『モーロ事件』は、第1共和国=戦後政治の終焉のきっかけ、デカダンのはじまり、と定義されますが、事実、もはやモーロのような、生真面目すぎるほど実直な政治家は見当たりません。また、大量の写真の中には、79年に射殺されることになるジャーナリスト、ミーノ・ペコレッリや、やはり80年にコーザ・ノストラによって射殺されるシチリア州知事、ピエールサンティ・マッタレッラ(現大統領セルジォ・マッタレッラの年長の兄弟で、モーロ派として、シチリア州議会でいち早く『イタリア共産党』と連帯)とともに写った、「死の鎖」とも呼べる時代の運命の予兆のような写真もありました。なお、1969年から1993年までのあらゆるテロリズム、秘密結社ロッジャP2、マフィア関連資料、政治収賄事件など、極秘書類をも含む資料を集め、60のテーマに分けたアーカイブセンターを設立したセルジォ・フラミンニ元上院議員は、膨大な資料を背景に『モーロ事件』のみならず、『グラディオ』『秘密結社ロッジャP2』について、『鉛の時代』に関する多くの著作を書いています。 現在もご健在でいらっしゃるフラミンニは、1925年生まれの元パルチザンであり、記事を書く際に、文書をアーカイブすることの重要さを学び、上院議員時代を通して各メディアで報道された記事も含み、あらゆる文書をアーカイブしていたのだそうです。現在では、95歳で亡くなったモーロ夫人が生前集めていた、モーロに関するパーソナルな資料「Chi è Aldo Moro(アルド・モーロとは誰だったのか)」が、アーカイブに寄贈されており、センターは歴史家やジャーナリストのリサーチのための貴重なハブとなっています。そのアーカイブの資料は、後年の研究者のために、デジタル化されつつあるそうです。アルド・モーロという人物は、あまりにゆっくりとしていて、演説は回りくどく、難解であったというのが定説ですが、その内面は活力に溢れる、情熱的な人物だったのではないか、とダミラーノは考え、パソリーニがラテン語のようだと表現した、回りくどいモーロの言葉を、(国内にも、国外にも)敵ばかりの状況で、何かを隠しながら話さざるをえなかったからではないか、とシャーシャは分析しました。そしてダミラーノは、正反対の立ち位置にいたモーロとパソリーニは、時代を覆う不安に共鳴しており、共に「新しい動力は政党だけでなく、政府と左派との合意のみならず、市民を含めすべてを巻き込んでいく」、つまり真の民主主義をイメージしていたのではないか、と言うのです。このダミラーノの分析には、両者が時代を覆う不安に共鳴していたこと、アルド・モーロが真の民主主義をイメージしていたことには賛成しますが、パソリーニの政治観に関しては、わたし自身は少し異なる印象を抱いています。こうして、『鉛の時代』には、憲法、自由と公正、和解と共生という、民主主義においてはあたりまえの主張をした重要な政治家、影響力があるオピニオンリーダーたちが、大量殺戮事件の被害者となった無辜の市民たちとともに、時代の不条理に飲まれ、次々と消えていくことになります。アルド・モーロに関する、さまざまな情報を調べていくうちに、暗い時代の最も過激な革命家は、極左武装集団ではなく、実はアルド・モーロだったのではないか、という思いが浮かび上がってきた次第です。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)