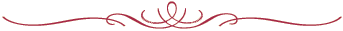
(最新見直し2005.6.12日)
| イタリア政界通信その3 |
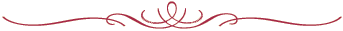
(最新見直し2005.6.12日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「イタリア政界通信その3」を確認しておく。 2005.6.3日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 |
| 2018.10.2日、「『鉛の時代』拳銃とパンと薔薇、’77ムーブメントと『赤い旅団』」。 |
| 何回かこのサイトでも書きましたが、イタリアに慣れた頃、最も非常識に思ったのは、日本では1970年まで続いた学生運動以後、すっかり廃れてしまった『占拠』という現象が、あちらこちらで日常茶飯事に起こっていたことでした。荒れ果てたまま置き去りにされた古い劇場や映画館、営業を停止したホテル、広大な工場跡や廃屋となった議員宿舎が、文化スペースや住居として、ある日突然有志たちに『非合法』に、しかし堂々と『占拠』され、当然のように普通に機能する。もちろん、『非合法』ですから強制退去の危機と常に背中合わせではありますが、退去になればまた占拠、と人々は『占拠』を諦めない。そしてこの現象のルーツは、武装学生たちが発砲しながら荒れ狂い、『市民戦争』レベルにまで発展した’77のムーブメントにありました。 ※この項は▷『赤い旅団』の誕生、▷フィルトリネッリと『赤い旅団』、▷『赤い旅団』と謀略のメカニズムの続きです。(写真は「77年の若者たち」doppiozero.comより引用) 既存の議会政治の流れとは一線を画した、反議会主義グループが運営するチェントロ・ソチャーレと呼ばれる『占拠』文化スペースが、ローマの中心街周辺に(極左ーアナーキズムやフェミニストグループを含み・極右ーカーサ・パウンドなど)パッと思いついただけでも8つ、9つは存在し、いずれも独自のチョイスによる音楽やアート、芝居を上演、その他知識人を招いての講演会、市民集会など、プロフェッショナルなレベルでアウトノミー(完全自治)に運営されています。「まさかここでこんな作品が観れるとは」と驚く国際的著名アーティストの作品展示に出会うこともあり、ふと隣のテーブルを見ると、観客として訪れているのが、カンヌ映画祭常連監督だったり、人気俳優だったり、重鎮の美術評論家だったりと、表現者たちのちょっとした社交場にもなっている。そういえば、神父さまや伝説の左派政治家を見かけたこともありました。これらの『占拠』スペースは基本、商業利益を完全に無視、入場者のカンパ、メンバーシップ・フィー、あるいは自主制作刊行物やグッズの販売で経費を賄いながら、アーティストたちに自由でクリエイティブな表現の場を提供。さらには難民・移民問題、貧困格差問題、住居問題など、巷に渦巻く過酷な社会問題にも鋭く切り込み、たちまちのうちに有志によるボランティアグループが形成される。難民・移民の人々、ロムの人々のための語学学校や法律相談、就職相談所、健康相談所などを完備するチェントロ・ソチャーレも存在し、占拠スペースによっては自治区役所のようでもあります。 また、経済危機や失職などで住居を追われた人々が団結し、廃屋となった建物を、怒涛のように『占拠』するケースも非常に多く、ローマだけで、なんと92の建物 (2018年 8月時点:コリエレ・デッラ・セーラ紙)が占拠され、12000人の人々が『非合法』に暮らしているのだそうです。 『占拠』という現象を知った頃は、強制退去のリスクをものともせず、住む家を失ったから『占拠』、自分たちの表現を追求する場がないから『占拠』という、簡単に世の中の仕組みを無視するアウト・ローなメンタリティがまったく理解できませんでしたが、イタリアの『鉛の時代』を紐解いていくにつれ、その現象が意図するイデオロギーが、だんだんに理解できるようになりました。 いまさらではありますが、『占拠』はベルリンの壁が崩れ、ソ連が崩壊してもなお、世代を超えてイタリア市民の底流に根づく『プロレタリアート』の遺伝子、イタリアの77年のムーブメントを席巻した『アウトノミー(自治)』のコンセプトをルーツとする『プロレタリアート闘争』の一形態。当時の極左の若者たちを熱狂させたイングリッシュ&アメリカン・パンク魂が、現代まで営々と引き継がれているものです。もちろん『非合法』ですから、常に当局からは勧告を受け続け、突然の暴力的『強制退去』とも背中合わせの日々、そのギリギリの緊張感に立脚しながら、世俗の干渉を押しのけ、呑気に好きなように運営を続けている。 しかしこれほどまでに世界中にグローバリズムが行き渡り、街じゅう監視カメラで埋め尽くされ、消費活動までネットですっかり管理される時代に、『占拠』という行為が可能な、管理されずに忘れ去られたスペースが、まだまだ存在するイタリアの現代社会の余裕と緩みを、個人的には「とても面白い!」と思います。さらには『占拠』スペースから、社会に影響力を持つミュージシャンやアーティストが輩出されるケースも多くあり、最近では、少年の頃からローマのチェントロソチャーレでうだうだしていたZero calcare (カルシウムゼロ)という漫画家が、左派のオピニオンリーダーのひとりとして躍り出ています。 |
| とはいえ、『同盟』『五つ星運動』の連帯政府になって120日、今までの緩い方針が大きく変わり、人気のある『占拠』スペースが強制退去となったり、裁判で途方もない金額の賠償請求判決が下されることも多くなりました。しかしそのたびに、歴史ある『占拠』スペースに賛同する市民が強制退去に猛反対、市庁舎で大がかりなデモを繰り広げたり、SNSで署名を募ったりと、抗戦姿勢を崩しません。個人的には、イタリア名物『占拠』スペースは、予期せぬ才能を開花させる、自由でクリエイティブな実験の場として消滅して欲しくない。「国や地方自治体が何もやってくれないのなら、自分たちでなんとかする!」という人々の心意気が押しつぶされないことを、願ってやみません。 さて、『占拠』はさておき、冷戦下に張り巡らされたグラディオの謀略のもと、毎年毎月爆弾が炸裂、多くの無辜の市民が命を奪われ、ターゲットを絞った政治殺人が繰り返された、緊張と悲しみの『鉛の時代』。『革命』の機運はいよいよ高まり、若者たちは熱病に浮かされたように常軌を逸していった。イタリアの戦後、最も大きな市民の騒乱となった、’77ムーブメントに迫ってみたいと思います。まず1977年は冷戦下、文化的に言えば、前述したパンクが世界のミュージック・シーンを席巻し、過激な動きが各地で起こっている年です。イタリアの’77のムーブメントに関していえば、極左、極右過激派グループだけでなく、ごく普通にデモに参加していた学生たちが、突如としてピストルを構え撃ちまくり、当局も銃を乱射、流血の騒乱にまで発展した。と同時に、武装しない平和主義の若者たちが、世間のあらゆる約束事を逸脱しながら、歌い、踊り、盗み、奪い、愛し合う、お祭り騒ぎで反抗した時代でもあります。その時代を生きた世代の人々は、「社会全体が、まるで伝染病にかかったみたいだったよ。それがなぜだか僕らには分からないんだけれどね」と口を揃えますが、その口調からは、自らの逸脱に後悔はないようです。 |
| ドイツ赤軍RAFと日本赤軍の77年 |
| さっそくですが、ここで脱線します。冷戦下、イタリアの『鉛の時代』を追ううちに、「その頃の日本ではいったい何が起こっていたっけ」と年表を見て、ふと思ったのは、西側において(日本も含め)、パレスティナ人民解放戦線(PFLP)と思想的に強い絆を結んだ極左武装革命集団が、次々と極端な殺戮事件を起こしたのは、イタリア、ドイツ、日本という三国同盟、第二次世界大戦の敗戦国だけだ、ということでした。もちろんアメリカでもフランスでも英国でも、「公民権運動」「フリースピーチ」、「フランスの5月」「ヴェトナム戦争反対」など、時代を揺るがす大きなうねりが起こっていますが、『日本赤軍』や『ドイツ赤軍』、『赤い旅団』のように、人々を恐怖ーテロで打ちのめし、時代のメンタリティを変えてしまうほど衝撃的な事件を起こした武装集団は、わたしが知る限りにおいて他の西側諸国からは生まれていない。 先の項でも書いたように、イタリアには現代でも、40年も昔の『鉛の時代』の数々の事件の謎に挑み、証言、証拠をもとに真実に光を当てようと調査し続ける多くの司法官やジャーナリストが存在。それぞれの事件のメモリアル・デーに寄せて、膨大な数の書籍や映画、新聞記事、ドキュメンタリー番組が発表されます。また、それぞれの事件の詳細に新たな情報が浮上すると、主要メディアがただちに報道。かつて人々を奈落に突き落とした虐殺事件の数々を、決して記憶の彼方へと置き去りにしようとはしない。したがって、普通に新聞を読んだり、テレビを見たり、ネットを覗いたり、日常を過ごすだけで、『鉛の時代』の事件の断片に出会うことになります。ドイツに関しては、まったくドイツ語が分からないため、冷戦下に過激派が起こした事件を題材にしたいくつかの映画を観るぐらいで、その時代が、現代社会においてどれほど重要視されているのか見当がつかないのですが、かつて『ドイツ赤軍』が起こした事件の数々をWikipediaや年表で見てみると、『日本赤軍』や『赤い旅団』の動きに酷似していることに強い印象を受けます。3者の相違点はといえば、それぞれの活動に多少のタイムラグがあることだけで、テロのアプローチは、誘拐が『赤い旅団』と『ドイツ赤軍』、飛行機のハイジャックが『日本赤軍』と『ドイツ赤軍』、と共通点が多い。現在、当時グラディオ下にあった『旅団』と『ドイツ赤軍』は交流が指摘されていますが、『日本赤軍』に関して詳細を知らないわたしには、残念ながらその関係をうかがい知ることができません。共通項であるPFLPを通じて、互いが互いに影響しあっていたということでしょうか。 いずれにしても77年という年には、日本赤軍が9月28日、ドイツ赤軍を代行したPFLPが10月13日、と1ヶ月も開けずに大がかりなハイジャック事件を起こし、世界を震撼させている。日本赤軍が起こした日本航空472便ハイジャック事件では、時の首相、福田赳夫が「人の命は地球より重い」という後世に残る言葉を残し、70年に起きた共産主義者同盟赤軍派「よど号」ハイジャック同様、運輸政務次官らが「身代わりになる」と決死の覚悟でダッカに乗り込んでいる。結局、政務次官らが人質の身代わりとなることをテロリスト側から拒絶されましたが、一滴の血も流さないで武装集団の要求を呑み、莫大な身代金とともに受刑中のテロリストたちを解放、数十人づつ乗客を飛行機から降ろし、最終的にはアルジェリアで全員解放に成功。「テロには屈した」という形にはなっても、乗客141名、乗員14名の生命を最優先した人道的な政府の采配は、今から思うなら、たとえ批判の波に晒されて時の首相が辞任せざるを得なかったとしても、国民の『政府』への信頼を強固にしたように思います。と同時に人々は、完全に極左思想に恐怖と嫌悪を覚え、政治的な議論から、いよいよ遠ざかったかもしれません。 一方、ドイツ赤軍と緊密な関係を結ぶパレスチナ人民解放戦線(PFLP)が10月13日に起こしたルフトハンザドイツ航空181便ハイジャック事件は、日本赤軍が起こした事件とは結末が大きく異なり、中東各国に着陸を拒否され、空港をたらい回しになった挙句、犯人全員が射殺されるというショッキングな結末で幕を閉じている。その際、乗客と交換に解放を要求された獄中のメンバー3人が自殺(自殺と見せかけた非合法の処刑という説が根強く語られますし、『赤い旅団』創立メンバーのアルベルト・フランチェスキーニも逮捕ののち「僕らもいずれRAFのように消される」と考えていたと言います)、そののちRAFに誘拐されていた実業家も惨殺され、鬱々と重い悲劇に終わっています。そこで、ドイツ赤軍に関して少し情報を得たいと、イタリアの『Anni di piombo – 鉛の時代』という呼称の語源となった81年の映画、西ドイツのマルガレーテ・フォン・トロッタ監督がヴェネチア映画祭で金獅子賞を獲得した『Die bleierne Zeit – 鉛の時代』を改めて観てみました。かつて、ナチスによる強制収容所で繰り広げられた、非道な残虐を脳裏に焼きつけられた少女(モデルはドイツ赤軍前身のバーダー・マインホフ・グルッペの創立メンバー、ウルリケ・マインホフ)と、フェミニストであるジャーナリストの姉の物語が静かに語られる、哀しみに満ちたフィクションです。冷戦下、アメリカ型資本主義が怒涛のように流れ込み激変する時代、マルクス・レーニン主義『革命』にユートピアを夢見、理想と救いを求めた、いわば歪んだ『正義』と、主人公を取り巻く不条理、何度かシーンに現れるキリストのイコンが印象に残った。また、この映画で表現される厳格な刑務所のあり方は、われわれが生きる、いつのまにか「管理」までモダンに、より精密になる、世界の有り様をも暗示しているかもしれません。「キリストは歴史上はじめて現れた共産主義者である」と断言した『赤い旅団』のレナート・クルチョ(パソリーニもそう表現していますし)といい、ドイツ赤軍といい、戦後、ルーズベルトのマーシャル・プランに組み込まれ高度成長を遂げた、欧州におけるマルクス・レーニン主義革命思想の拡大は、「貧しき者は幸いである」と福音書に刻まれるキリスト教文化という背景が、切り離せない要因のひとつと考えます。 では、日本で当時爆発した極左運動のルーツとなる精神性とはなんだったのか。何が彼らを『革命』に駆りたてたのか、敗戦国ゆえの単純なルサンチマンと捉えていいのか、日本という国で『連合赤軍』『日本赤軍』『東アジア反日武装戦線』いう極端な過激派が台頭した背景にあるのは何なのか、いまだに具体的な動機に至った背景が掴めないまま、多少もやもやしています。いずれにしても今となっては、イタリアにおいても、日本においても、夢のような時代です。77年の日本は、というとイタリアとはまったく違う意味での『狂乱』ー記号の集積であるポストモダンな都市、『中流階級』を自認する人々の『消費』という闘争へと、次第に突入していった。一方、グラディオ下にある当時のイタリアはといえば、自らを『プロレタリアート』と認識する学生、若者たちが大挙して、過激度を増した『赤い旅団』の方向性に賛意を示す年となりました。 |
| 『赤い旅団』と女性たち |
| ところで、本題に入る前にさらに脱線することになってしまいますが、こうしてドイツ、イタリア、日本の極左武装集団を改めて眺め、まず注目することは、いずれのグループでも、女性がリーダーとして重要なポストに就いてグループを牽引していることでしょうか。日本赤軍は重信房子、ドイツ赤軍はウルリケ・マインホフ、『赤い旅団』に関しては、創立メンバーである、レナート・クルチョのパートナーであり、初期の重要な幹部として『旅団』の中心人物となったマラ・カゴールが存在する。イタリアでは、68年に爆発した労働者と学生たちによる大きな抗議ムーブメントの頃から、60年代に米国に起こったウーマン・リブの流れを受け、女性たちが団結して、旧態依然とした父権社会に断固抵抗。「女性の権利」を強く訴えるフェミニズムの息吹は、70年代に入った途端に大きく発展しています。また、77年のムーブメントでは、フェミニストの存在が政治闘争の重要な核ともなっています。ともあれ『赤い旅団』のマラ・カゴールという女性は、メンバーの誰からも慕われ、頼りにされる女性だったようです。たとえば『アルド・モーロ誘拐・殺人事件』の主犯マリオ・モレッティは、『Una
storia italiana (イタリアのひとつの物語)ーカルラ・モスカ、ロッサーナ・ロッサンダによるインタビュー)』で、「マルゲリータ(マラは通称)は僕にとっても、組織にとっても、仲間達にとっても、非常に重要な存在だった」「僕の中に残っている彼女のイメージは、とてもノーマルな女性だというものだ。それなのに彼女のイメージは、(テロリストのイメージが焼き付けられ)まったくつまらないものになってしまっているけれどね。彼女は僕らのジェネレーションの女性が持つ、すべての問題を考えている本物の女性だった」と手放しで称えています。
「僕は彼女のことを(モレッティがかつて技師として働き、仲間たちと共同生活をしていた)シット・シーメンス時代から知っているが、誘惑し合うようなこともなく、緊張する必要のない、気楽でいながら、深く分かり合える友人だったんだ。こんな感覚は女性との関係においてはとても珍しいものだと思うよ。僕らは内面的なことも含め、何でも、恐れなく、誤解なく話し合えたし、彼女には嘘をつく必要もなかった」「彼女は非常に難しい問題を抱えているときでさえ、非常に賢く、陽気だったよ」。『モーロ事件』の主犯として、『赤い旅団』のグランデ・ヴェッキオ(黒幕)と言われるコラード・シミオーニとの緊密な関係を強く疑われるモレッティは、事件の核心に触れるような質問に対しては、きわめて饒舌に、さらりとはぐらかす。しかし資本家の誘拐のために用意した隠れ家を急襲され、カラビニエリとの銃撃戦で死亡したマラ・カゴールの話をする際は、声をつまらせ、痛みを露わにしています。インタビュアーであるロッサンダが「カゴールの話をするときのあなたは、とても苦しそう」と言葉をかけるくらいです。また、そのモレッティを「真実を話すべきだ」と糾弾し続ける元幹部アルベルト・フランチェスキーニも、カゴールについてはモレッティ同様、絶対の信頼と親愛を表明。自分の姉のような存在だったとも語っています。いずれにしても、75年にカゴールがカラビニエリに銃撃された際、共に行動していたはずの『旅団』メンバーが誰であったのか、現在まで明らかになっていないことも、フランチェスキーニがモレッティへの疑惑を募らせるひとつの原因ともなっているようです。
もちろん『赤い旅団』は創立以来、マラ・カゴールだけではなく、多くの女性をメンバーに持ち、バルバラ・バルゼラーニ、アンナ・ラウラ・ブラゲッティのように『モーロ事件』の主要メンバーとしても多くの女性が関わっている。興味深かったのは、ロッサンダの「 ロンコーニやマントヴァーニ(共に女性メンバー)は『旅団』のストーリーでは、どんな役割を占めていたのか。平等に仲間だったのか。それとも『俺たちの(所有する)』仲間だったのか」との質問に、モレッティが次のように答えていることです。「僕らが、男たち同様に、あるいは、幹部であったマルゲリータ (マラ)と同じように、バルバラ・バルゼラーニやマルッチャ・ブリオスキ、アウロラ・ベッティ (共に女性メンバー)を扱ったか、と聞くのかい? バルバラはローマ・アジトのリーダーとして指揮を執っていたんだよ。非常に繊細な女性だったが、その繊細さは、いわば鋼鉄の繊細さだった。マルゲリータは2年間、フィアットの労働者たち、彼らと深く関わるメンバーたちをまとめるという、『旅団』においては最も権威あるトリノの指揮を執っていたんだ」、「いいかい。工場労働者たちから尊敬されるには、とても美しい緑の眼を持っているだけじゃだめなんだ。それ以上のエネルギーを当然必要とし、マルゲリータはそれを持ち合わせていた。個人的には、女性メンバーたちは巷で言われるよりもずっと大きな役割を担っていた、と確信している。マスキリズムのイメージがマスメディアを席巻し、男性だけが政治ができる、あるいは告発できる、と考えられ、(政治に関わる)女性はただ熱に浮かされただけだ、と解釈されているようだが、『赤い旅団』においては、女性は男性以上でも以下でもない。まったく同等だ」。その答えに、ロッサンダは「フェミニストたちも、あなたたちとまったく同じことを言うと思うわ」と答えています。 |
| クルチョ、フランチェスキーニが逮捕されたのちの『赤い旅団』の動き |
| ▶︎ここからは、セルジョ・サヴォリの『共和国の夜』書籍/TV番組、シルヴァーノ・ディ・プロスペーロ、ロザリオ・プリオーレの『赤い旅団を操ったのは誰なのか』、カルラ・モスカ、ロッサーナ・ロッサンダによるマリオ・モレッティインタビュー『イタリアのひとつの物語』、ジョルジョ・マンゾーニ著『赤い旅団メンバー、ウァルター・アラシア捜査』を中心に、Rai
Storia、Wikipedia、Youtubeなどを参考にまとめていきたいと思います。
74年にレナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニが逮捕されたのち、『赤い旅団』のメンバーたちは、末端のメンバーまで続々と逮捕されています。残された幹部マリオ・モレッティ、マラ・カゴールは、今後の『旅団』のオーガナイズをどうすべきか、戦略はどうすべきか、窮地に陥り途方に暮れた、とモレッティは語っている。当時の極左思想を持つ学生たち、工場労働者たちは、73年のオイルショック以来、長く続く2桁のインフレと就職難、不平等な社会の有り様に怒りを募らせ、未来を信じることができなくなっていた。さらにイタリア共産党、労働組合が次第に国家機構の歯車になりつつあるように見え、まったく頼りにならないと落胆もしていました。「ならばユートピアは僕たちの手で掴むしかない。今こそ革命の時」若者たちのリビドーの沸点はすぐそこまで迫っていた。『旅団』のメンバーはバラバラになり、このままでは統制が取れなくなることを案じた矢先のこと、マラ・カゴールが、「じゃあ、獄中の仲間をひとり解放しようよ」と提案。そもそも冷静で実務的な彼女は、自らのパートナーであるクルチョ解放を計画し、モレッティを含む5人の仲間とともに、即戦力でもあったレナート・クルチョの脱獄幇助を敢行することにしたのです。75年の2月18日、クルチョが収監される刑務所を訪れたカゴールは、夫に差し入れをする心優しい妻を見事に演じて看守を欺き、すでに調べ上げていた刑務所で、ちょっとした銃撃戦を繰り広げながら、仲間とともにクルチョの脱獄幇助に成功。計画で使った刑務所の地図は、クルチョの弁護を引き受けた弁護士エドアルド・ディ・ジョヴァンニ(『フォンターナ広場爆破事件』から間を置かず、70年前半に国家と極右グループの共謀による犯行だと見抜いた、当時の極左思想支持の若者のバイブル『国家の虐殺』の著者のひとり)が作成しています。73年以降執行幹部であり、『モーロ事件』の主犯とされるモレッティのこの時の役割は、といえば、外を歩く通行人から中の様子が分からないように扉の付近に立っているだけ、という意外に控えめなものでした。しかも冷酷にアルド・モーロ元首相を殺害した人物とはとても思えないほど、慌てふためいて、おろおろしています。いずれにしても、娑婆に出たクルチョは、獄中で練っていた「多国籍巨大企業を増補するために存在する、帝国主義国家(イタリア)をバラバラに解体するため、また、キリスト教民主党と『歴史的合意』へと向かっているイタリア共産党を、再び(本来のマルクス・レーニン主義思想と)統合するための戦争」というコンセプトを提示、アントニオ・ネグリ同様、改めてイタリア国家を敵とみなし、工場労働者をアンタゴニスト(反体制者)と位置づけました。さらにクルチョは、73年以降の経済危機によるインフレは「多国籍企業グループの帝国主義者たちにより指揮されたもの」と断定、イタリアがアメリカ、ドイツモデルの産業行動を踏襲したことで経済危機が起こり、安定雇用を失った、と考えた。注目すべきは、この時点のレナート・クルチョによる『赤い旅団』の思想の核は、創立時から引き続き、伝統的共産主義思想を受け継ぐ『工場労働者』であったということです。 ここで『赤い旅団』は、それまで継続してきた工場における階級闘争革命に加え、反帝国主義としての武装共産主義闘争を再確認、「戦後の政治を担ってきたキリスト教民主党が、社会的平和を約束するのは、資本家たちの仲介をやりやすくするためである。一方、イタリア共産党は、工場労働者たちの闘争を破壊するのみならず、資本家を保護し、NATOが機能しやすいように配慮し続けるキリスト教民主党のプロジェクトに組み込まれてしまった」と定義した。この時代の『赤い旅団』はスターリニズムの影響があまりに強く、共産党のベルリンゲルがデザインしたユーロコミュニズムに、フェミニズム、エコロジーというコンセプトが反映されていることに気づいてはいませんでした。また、この状況を打破するには、『国家へ戦争を挑む』アクションのみであると結論づけ、アバンギャルドな武装プロパガンダによる『市民戦争』を起こしたのち、資本家から労働者を解放、国を再建する復興の過程に、経済活況を期待した。そしてその計画を実行し、キリスト教民主党を倒すことを目的として『闘争する共産党』創立を宣言。このときクルチョが作成したドキュメントが、その後の『旅団』のストラテジーとなり、学生、工場労働者、各地域に配布され『赤い旅団』共鳴者のバイブルともなっています。しかしこのドキュメント配布の前後、マラ・カゴールは銃弾に倒れ、レナート・クルチョは再逮捕されることになりました。そしてこの76年あたりから、トニ・ネグリとも連絡が途絶えたと考えられている。刑務所からいったん『赤い旅団』に戻り、1年余りをアルファロメオの工場労働者たちとともに過ごしながら今後の戦略を構築したクルチョですが、その間、自らが創設した『赤い旅団』の質とメンバーがいつのまにか大きく変わってしまい、大きな孤独を感じたといいます。『旅団』は死んでしまったと思った、とものちに語っている。68年のムーブメントで共に立ち上がった労働者たちは、もはや極左運動の核ではなくなっていたのです。 |
| 『赤い旅団』、はじめての政治殺人とウァルター・アラシア |
| こうして初期のメンバーが完全に消失した76年、検察官フランチェスコ・ココを『赤い旅団』が殺害。ココはマリオ・ソッシ誘拐事件の際、人質との交換に『旅団』が要求したアナーキストたちの解放を、最後まで拒んだ検察官でした。この事件は、MSI(極右グループ)の事務所に忍び込んだ際、たまたま訪れたメンバーに見つかって、慌てて銃で応戦。ふたりのMSIメンバーを『旅団』が殺害してしまった事件ーいわば意図せず、偶発的に起こった74年の殺害事件とは異なり、明確にターゲットを定めた『国家への攻撃』となった『旅団』はじめての政治殺人と位置づけられています。さらに76年には、かつて『赤い旅団』が誘拐を計画準備中に、忽然と姿を消したキリスト教民主党右派の弁護士、マッシモ・デ・カロリス(のちに秘密結社ロッジャP2メンバーであったことが明らかになる)のオフィスに『旅団』が押し入り恐喝。デ・カロリスのふくらはぎを狙って負傷させる(ガンビザッツィオーネ)事件をも起こしている。初期幹部アルベルト・フランチェスキーニによると、この「ガンビザッツィオーネ」という技は、「ミラノの魚屋」という触れ込みだった優秀なテロリスト、フランチェスコ・マラ
(のちに諜報として潜り込んでいた、カラビニエリのパラシュート部隊の一員と判明)がメンバーに訓練したもので、このあと次々と犠牲者が増えることになります。
ところで、このデ・カロリス狙撃の実行犯のひとりは、『赤い旅団』の新しいメンバーになったばかりのウァルター・アラシアという20歳の青年でした。アラシアはミラノの郊外、セスト・サン・ジョヴァンニの出身。両親ともに工場労働者という家庭に生まれています。両親が支持する共産党文化で育った、明るく外交的な、ごく普通の青年でもありました。その彼が成長過程で、『旅団』の創立メンバーたちと同じように、国家機構の一部となりつつあるイタリア共産党に反発、家族もまったく知らないうちに『継続する闘争』に通いはじめ、さらに過激な『赤い旅団』へと移動しています。76年の12月15日、そのアラシアを巡る悲劇は起こりました。当時、ほぼクランディスティーノ(偽装身分証明書で非合法に活動)として武装政治闘争に加わり、仲間内を転々としていたアラシアが、久しぶりに両親の家に帰った日の早朝5時のことです。いまだ闇に包まれた静かなミラノの郊外、ガンガンと銃で扉を打ち叩き、乱暴に足蹴りしながら「扉を開けろ。さもないと強行突破する」と警察隊が叫ぶ声に、アラシアの両親は驚いて飛び起きた。母親が寝巻きのまま、おそるおそる扉を開いたと同時に、なだれ込んできた警官のうちふたりを、すでに自室で起きていたアラシアは、隠し持っていた銃で射殺。窓から逃げようと、飛び出したところに無数の銃弾を浴び即死した。 |
| その一部始終を目にした、アラシアと同じ部屋に寝ていた弟は「ウァルターは、まるで高度な訓練を積んでいたように、極めて冷静に行動した。顔色ひとつ変えずに、警官に銃口を向け発砲したんだ。僕は彼のそんな顔をまったく知らなかった」とそのときの衝撃をのちに語っています。早朝、このように暴力的に実家に突然乗り込んで、軽機関銃で扉を叩き、何事が起こっているのか分からないまま、うろたえ怯える両親と弟の目前でアラシアを射殺したことは、当時、若者たちの大きな非難を浴びました。咄嗟に銃を構え、警官ふたりを射殺したアラシアを英雄視する若者たちも現れ、『赤い旅団』はその名を記憶を残すため、ミラノ・アジトを「ウァルター・アラシア」と名づけている。当局は、といえば、アラシアは初期の幹部がすでに逮捕されたあと、『赤い旅団』に生き残った過激派で、この事件を最後に『旅団』はほぼ壊滅した、と考えていたといいます。しかし、当局の推測とは裏腹に、この時期、モレッティが新しい主軸となった『赤い旅団』は再構成されつつあり、極左武装グループNAP、Prima Linea(プリマ・リネアーローマの極左武装グループ)とも絆を結んでいました。また、この時期にフランコ・ボニソーリ、バルバラ・バルセラーニらの『アルド・モーロ誘拐・殺害事件』の中核となるメンバーが合流、ローマ・アジトを固めている。トニ・ネグリ、フランコ・ピペルノが創立した『労働者の力』からは、アドリアーナ・ファランダ、ヴァレリオ・モルッチが流れてくるなど、メンバーが総替わりしながら、新しい動きがはじまっています。 なおこの頃は、68年から70年代にかけて主役だった極左グループの編成が大きく変化した時期でもあります。たとえばLotta Continua『継続する闘争』は武装闘争から平和主義的に変遷を遂げたことでメンバーが離れ、機関紙のみを残して事実上解散。Potere Operaio (労働者の力)は発展し、さらに解散した『継続する闘争』から流れてきたメンバーも加わって、イタリア全国に共鳴者を持つColletivi autonomi di lavoratori e di studente ( 工場労働者と学生による集合的自治)を形成、 Autonomia Operaia (労働者によるアウトノミー)として拡大を遂げています。一方、76年のイタリア総選挙では、イタリア共産党が下院議席228、上院議席116、とキリスト教民主党に肉薄するほどに躍進。国政において、その影響力を無視できない勢力に成長しました。 特筆すべきことはこの76年、「コンピューターで計算してみると、73年、74年が大きな不況(実際にはオイルショックが起こっている)に見舞われるので、74年に大きな事件を起こし、その後、あらゆる右翼グループに忍び込み、そこで市民戦争を起こそう」と、まるで予言でもするかのように言っていた(フランチェスキーニ談)、件のコラード・シミオーニが、ヴァンニ・ムリナリス、ドゥーチョ・ベニオ、フランソワ・トゥッシャーら『スーパークラン』のメンバーとパリへ移り、語学学校『ヒペリオン』を創立していることです。フランソワ・トゥッシャーが、フランスの良心とも言われる慈善事業家、アベ・ピエール神父の孫であったことから、シミオーニはフランス社会から、大きな信用を得ることになった。 さらにこの年には、イタリアでも日本同様、世界規模の汚職事件『ロッキード事件』が暴露されています。 (『市民戦争』にまで発展した、武装した若者たちの騒乱の経緯、時代に流れたメンタリティは、次のページでたどります) |
| 77年の『市民戦争』、若者たちの騒乱はどのように発展したのか |
| 連綿と続くテロ事件、オイルショックから極端に落ち込んだ経済、ワァルター・アラシア事件、ロッキード汚職事件の暴露。不穏に満ちた70年代を過ごした若者たちの革命マグマは、ここで遂に噴火することになった。グラディオ下のイタリアが、緊張作戦(Strategia della tensione)の真っ只中にあった時代です。77年1月24日、『労働者のアウトノミー』の共鳴者による大規模な大学『占拠』がはじまったのは、シチリアのパレルモからでした。この『占拠』からトリノ、カイアリ、サッサリ、サレルノ、ボローニャ、フィレンツェ、パドヴァ、ピサと急激に波紋が広がり、イタリア中に学生たちの抗議活動が拡大していきます。2月1日には70名のネオファシストグループが、『占拠』中のローマ大学サピエンツァの文学部になだれ込み、銃を乱射、爆弾を投げるという暴動を起こし、対抗して極左の学生たちも乱闘で応戦。この時ひとりの学生が、ネオファシストにピストルで頭を射抜かれ、重体に陥るという痛ましい事件が起こっている。そこに警察隊も加わったため、火炎瓶、石(石畳を剥がした)が飛び交い、爆弾が炸裂する騒乱が翌日まで続きました。この時点で、ネオファシストグループも極左グループ『労働者によるアウトノミー』も、共に挑発的なテロリストと当局に見なされ、イタリア共産党は学生たちの政治闘争と完全に袂を分かつことを確認しています。時をおかず2月17日、イタリア共産党のシンボル、CGIL(労働組合)総長ルチアーノ・ラマが、後述する『メトロポリスのインディアンたち』、『労働者によるアウトノミー』が占拠するローマ大学サピエンツァに訪れ、「君たちはただちに『占拠』を終了し、勉学に戻るべきだ」と呼びかける集会を開きました。ところがラマが登壇した途端、占拠学生たちは大挙して棒を振り回し、暴動を起こしてラマの演説を妨害。学生たちは、結局大学からルチアーノ・ラマの一団を追い出すことに成功し、今度は学生側が、イタリア共産党、労働組合を『敵』だと明確に認識している。大学の壁には「新しい警察(イタリア共産党、CGIL)は出て行け!ラマはチベットにいるものだ」というスローガンが貼られたそうです。その後ローマでは、平和闘争である『フェミニスト』『メトロポリスのインディアンたち』と、武装派の『労働者によるアウトノミー』、そのほかの過激派との間で亀裂が生まれ、『武装による革命』か、『自由でクリエイティブな革命』か、方向性がまっぷたつに別れている。ボローニャでは、過激な学生運動の主導者が続々と逮捕されはじめました。そして3月11日、学生たちを、さらに憤らせる決定的な事件が起こることになります。ボローニャの学生デモの最中、『継続する闘争』の共鳴者である学生、フランチェスコ・ラルッソがデモに参加していた最中、丸腰であったにも関わらず、背中に警官の銃弾を受け亡くなる、という事件が起こった。暴力的な衝突が繰り返された学生デモではあっても、警官が丸腰の学生を背中から打つ、という過剰な介入はそれまでに起こったことがなく、学生たちは当局による明らかな『挑発』と捉えた。その事件を知ったイタリア中の学生たちは怒り狂い、各地で抗議活動がはじまりました。翌日3月12日からは、ラルッソ殺害事件を機に、ボローニャとローマで大がかりな抗議集会が開かれ、狂乱する学生たちが持ち込んだ爆発物、投石、飛び交う銃弾で、街中が火の海になっています。この日ローマには、全国から10万人が集まったと言われ、学生たちによる街の『侵略』とも言える様相となり、その参加者からは150人が逮捕されることになりました。同日、トリノでは警官が極左武装グループ『プリマリネア』から銃殺されるという事件が起こり、ボローニャでは学生たちの情報源であり、議論の場として重要な役割を担ったインディペンデント・ラジオ、『ラジオ・アリーチェ』が強制退去となっています。この騒乱を受け、14日には当時の内務相、フランチェスコ・コッシーガが、ボローニャ大学を占拠していた学生全てを強制退去、大学の門を閉ざす、という乱暴な措置を取り、学生たちをさらに怒り狂わせることになった。その数日後、歯止めが効かなくなった極左過激グループNAPが、ローマで警察官を殺害。 なお、時の内務省、コッシーガが強行した、このボローニャ大学閉鎖というアカデミックな場に当局が介入したことに関しては、フランス人を中心に知識人たちが声をあげ、『継続する闘争』の機関紙に署名を残す事態となっています。署名にはジャン・ポール・サルトル、ジル・ドゥールーズ、フェリックス・ガタリ、ロラン・バルト、シモーヌ・ド・ボーヴォワールなど錚々たる名が並び、毎年、休暇をとってローマを訪れるサルトルとボーヴォワールは、『継続する闘争』の若いジャーナリストたちのロング・インタビューを受け、イタリア共産党の方針を強く批判しました。しかし大学が閉鎖されてもなお、学生たちの騒乱は一向に収まる気配はなかった。この時期、街中で繰り広げられるデモにおける、学生たちと当局の混乱は熾烈を極め、過激派でもない普通の学生、若者たちが、警官、カラビニエリに向かって銃口を向け発砲する事態にまで発展。学生を含む、警官、ジャーナリストら負傷者は膨大な数にのぼります。Youtubeで、その時代の大学教授などのインタビュー動画を見ると、たとえば500件近い暴行事件が起きたパドヴァでは、そのうち160件が若者たちによる襲撃事件で、日常的に脅迫、無言電話、嫌がらせが続き、「大学関係者たちは大変な緊張状態で毎日を過ごしていた」と怯えた様子で語っている。 |
| このように、あまりに緊迫した状況が続いたため、コッシーガ内務相は、遂に「公共のスペースにおける一切のデモを禁じる」と通達しましたが、集会の権利は『民主主義』の基本だ、と火に油を注ぐ結果となりました。コッシーガがデモの禁止を通達した5月12日、『離婚』の合法化を議会へ持ち込み成功した『急進党』のマルコ・パンネッラは、『離婚』合法化3周年を記念して企画した集会を中止せず強行。ローマの心臓部にあるナボナ広場まで、平和的にデモ行進をしていた『急進党』の群衆に機動隊が大挙して攻め込み、デモ参加者たちと長時間の激しい衝突が続いた。その混乱のなか、フェミニストグループの19歳の学生、ジョルジャーナ・マーシが無抵抗のまま銃殺されることになります。このジョルジャーナ・マーシ事件を、当局側は、ネオファシスト過激派の仕業と断定しましたが、「銃を打ったのは、間違いなく群衆に紛れていた私服警官である」と、長きに渡りパンネッラは主張し続けた。事実、セーターを着た青年が銃を手に、警察官と何やら話している証拠写真が捉えられながら、結局犯人は逮捕されることはなかったのです。この事件は『鉛の時代』において、学生たちの間にさらなる緊張を創出するため、軍部諜報に企てられた『挑発』の一環と見られています。さらに、その2日後の5月14日にも、ミラノで大きな衝突が起こり、学生たちと当局が銃撃戦を起こしました。そしてこの時たまたま撮影された、まさにテロリスト、という姿勢で銃を構えるジゥゼッペ・メメオの写真が、『鉛の時代』のシンボルとして後世に残ることになった。メメオは『労働者によるアウトノミー』の共鳴者であり、その後『武装プロレタリア共産党』へと加入。当初、この騒乱で銃弾を浴び死亡した警察官殺害の犯人と見なされましたが、のちに別の人物の犯行だったことが明らかになっています。
9月20日には、ローマで『継続する闘争』の、道でビラ配りをしていた学生、ウァルター・ロッシがネオファシストの銃弾に倒れている。この一件については、以前『永遠の革命家』としてインタビューをさせていただいたパオロ・グラッシーニの項に詳細を記しました。 以上のような経緯を経て、78年に起こった『アルド・モーロ誘拐・殺人事件』の前奏となる’77のムーブメントの核、『国家圧力と闘うための全国学生大会』が9月23日から25日の3日間、ボローニャで開かれることになった。この大会の間じゅう、イタリア全国から集まった10万人を超える学生たちが、市庁舎、大学、広場など街中を占拠、演劇やパフォーマンスで、平和的に抗議活動を繰り広げています。この集会には多くのアーティストたちが参加しましたが、のちにノーベル文学賞を受賞し、最近まで『5つ星運動』の強力な支持者であったダリオ・フォー、フランカ・ラメが参加していた事実は、注目すべきことです。そして、そのボローニャの大集会で確認されたのが、学生たちによる『赤い旅団』の武装革命への共鳴だった、というわけです。「Rosse, Rosse, Rosse, Brigate Rosseー赤、赤、赤、赤い旅団』というシュプレヒコールを、集会の最終日に集まった何万人という学生は口々に叫び、『赤い旅団』による『国家との戦争』を支持。このように、学生たちが明らかに『赤い旅団』への共感を表明するのは、はじめてのことでした。 一方、77年の『赤い旅団』はといえば、影響力のあるジャーナリスト、ヴィットリオ・ブルーノ、イタリアで最も有名なジャーナリストだったインドロ・モンタネッリ、Raiのエミリオ・ロッシなど、ジャーナリストばかりを狙い、ふくらはぎに銃弾を打ち込む『ガンビザッツィオーネ』で重傷を追わせています。 2月にはミラノでカラビニエリ、リーノ・ゲディーニ、3月には警官ジウゼッペ・チオッタを殺害。4月には、予定されていたレナート・クルチョ、フランチェスキーニら『赤い旅団』創立幹部のはじめての公判を前に、弁護士フルヴィオ・クローチェを殺害して、公判を阻止している。 12月にはスタンパ紙の主幹、カルロ・カッサレンニョを殺害。76年の判事フランチェスコ・ココの殺害からタブーがなくなり (モレッティ談)、ターゲットを絞った攻撃が、際限なくエスカレートしていた。ボローニャの10万人の学生たちは、その凶暴化した『赤い旅団』に賛同、支持したというわけです (時系列:Wikipedia参考) |
| ’77ムーブメントとふたつの魂 |
| この’77のムーブメントはもちろん、68年に団結した学生と工場労働者で構成された、プロレタリアートの絶大な権力を誇る資本家たちとの階級闘争の流れを汲み、それがモデルともなっていますが、77年の極左運動の中核にいた青年たちは、68年のムーブメントは「豊かなアイデアがあったが、プロジェクトが足りなかったために失敗した」と考えていたそうです。一方、現代の研究では77年のムーブメントには「知性が欠如し、より卑俗であった」と評論されることもある。プロレタリアートのムーブメントの核から、いつしか工場労働者が後退し、主人公は学生や職のない若者たちとなった時代です。
この時代、『労働者の力』から発展して支持を拡大した 『労働者によるアウトノミー』は、学生たちに人気の雑誌『Rosso (赤)』を発行。工場労働者たちにはネオファシストである資本家の下、予告なくストライキ、あるいはサボタージュを敢行するなど、攻撃的な労働闘争を推奨していました。彼らにとって「暴力を諦めることは新しい世界を諦めること」であり、武装闘争による政治、つまり戦争を超えずにはユートピアへは行き着かない、と考える『赤い旅団』と同じ方向性を維持していた。若者たちの間に、このような『武装革命』の機運が高まる中、’77ムーブメントのもうひとつの重要な側面は、『人権』というコンセプトに大きなスポットが当たった、という事実でもあります。
そして、その『人権運動』で大きな役割を果たしたのが、前述のイタリアの『人権の父』と呼ばれるマルコ・パンネッラが率いるPartito Radicale 『急進党』。『急進党』は74年に国民投票で『離婚』を、77年には『中絶』合法化など、非暴力主義 (ガンジー主義)を貫いて『人権』の保護、『選択の自由』を強く訴え、女性の権利、ホモセクシュアルの権利、安楽死問題、大麻の合法化、難民問題など、多岐にわたる『人権問題』に署名運動やハンストで徹底的に闘っています。この『急進党』のシンボルであったパンネッラが生涯をかけて取り組み、訴え続けてきたマイノリティの権利の保護が、現在のイタリアの『人権』に関する議論の基盤になったと言っても過言ではありません。 さらにこの頃になると、『武装革命』を目指す極左グループとは一線を画す、77年ならではの重要なユートピア・ムーブメントが起きています。これはイタリアにブリティッシュ&アメリカン・パンクが流入したと同時に巻き起こった現象で、フリークス( frichettoni:ヒッピー)、フラワーチルドレン、ゲイの人々、アナーキスト、自由主義者、疎外された人々、フェミニストなど、てんでばらばらに多様な人々が集まって、コスプレで街を練り歩き、歌ったり、踊ったり、芝居をしたり、パフォーマンスをしたり、と自由にクリエイティブにデモを行う『Indiani Metropolitani (メトロポリスのインディアンたち)』と呼ばれる若者たちによるカウンターカルチャーの出現でした。この現象は、そもそもはミラノの雑誌『裸の王様』が主催したフェスティバルで繰り広げられた、平和的な乱痴気騒ぎがイタリア全国に広がったもので、ウッドストックのコンセプトからも大きく影響を受けているそうです。 その、『メトロポリスのインディアンたち』は、好き勝手なコスチュームを纏って集会に参加、と思えば、ピエロのメイクで裸で踊ったり、広場や路上で芝居やパフォーマンスをはじめたり、と突飛な方法で自分たちの権利を主張。スローガンとして『Pane e Rosa (パンと薔薇) 』を叫び、『革命』はサラリーや食べるものだけではなく、自分たちに歓喜をももたらさなければならない、と訴えた。この『インディアンたち』にはリーダーが存在せず、すべての行動に個人ひとりひとりが責任を負わなければならない、という暗黙の約束事があったのだそうです。 彼らの特徴は、といえば、まずクリエイティブであり、非合法をものともせず、自然発生的に集まって、ほぼ非暴力を貫いた。さらにその表現は、どこか皮肉っぽく、毒のある笑いを特徴としていました。考えてみれば、体裁は大きく変わっても、彼らの精神性、皮肉っぽいセンスは現代イタリアで活動するストリートアーティストたちの性格に、かなり近いかもしれません。 この『メトロポリタンのインディアンたち』のアイデアは、共産主義と個人的な欲求をミックスして構築された独自のもので、既成概念に囚われない表現による『スペースの占拠』の精神は、やがてイタリア共産党のローマ文化評議委員レナート・ニコリーニがプロジェクトして一世を風靡した、ローマの街中がストリートパフォーマンスの劇場と化した『エスターテ・ロマーナ(ローマの夏)』に受け継がれ、現在では、MAAMやAngelo maiなど『文化スペース占拠』のコンセプトとして引き継がれています。 また、郊外のスラムと化した地区では、国家に見放され、数々の犯罪に手を染めながら、ヘロインなどの強い麻薬に溺れるルンペンプロレタリアートを助けるために、『労働者のアウトノミー』や『継続する闘争』の極左グループメンバーが、荒れ果てるままに放ったらかしにされている廃屋を、次々に『占拠』していた。若者たちは困窮者の住居を確保したのち、近くの電線から電気を不法に引いたり、人が暮らせる状態に修復したりと、ヘロインなどの強い麻薬から彼らを引き離すために腐心しています。極左グループの若者たちは本来、弱者を助けるべきイタリア共産党が、国政の場で存在感を示すことに躍起になり、その役割を怠っていると感じ、資本家より国家よりキリスト教民主党より何より、イタリア共産党こそ憎悪すべき敵、とみなしていたそうです。そういうわけで77年は、武装によって国家を攻撃することによって『ユートピア』を実現しようとする流れと、ほぼ平和主義を貫きながら、自由でクリエイティブに自分たちの権利を主張して『ユートピア』を実現しようとするふたつの大きな流れに大きく分かれていた。しかし、その根底に流れる共通の理念は「(サラリーだけを目標に奴隷のような)仕事の拒絶」「再び我々の手にすべてを取り戻す」「自分自身で、自分自身を評価する(僕らには価値がある)」というものでした。 自らを「プロレタリアート」と自認する彼らは、プロレタリアートにも贅沢をする権利がある、とスーパーマーケットで、高級食品、キャビアやシャンパン、あるいは本屋でも万引きをして欲しいものを確保。さらには映画館、劇場にもチケットを買わずに忍び込み、バス、汽車、電車など交通機関もタダ乗りという具合でした。それを『Spese Proletarieープロレタリア経費』と呼んで、ちゃっかり正当化。また、映画館まるごと占拠して、無料で映画を市民に解放する、というアクションも度々起こし、現在、ローマで大きな支持を得る、占拠した広場で無料映画上映を企画するチネマ・アメリカのルーツともなっています。さらにこの時代を代表すべき新しいメディアとして、インディペンデント・ラジオの発展があります。これは76年に地上波が自由化されたことで、学生たちが次々にラジオ局を創設。地区の若者たちの気持ちを音楽とパンクな議論でひとつに結んだ、ボローニャの伝説のラジオ・アリーチェ(77年に当局に踏み込まれて解散)をはじめ、ラジオ・オンダロッサ、ラジオ・チッタフトゥーロ、エピチェントロ、ラジオ・ラディカーレ(『急進党』のラジオ部門)などがあり、現在でも継続。このインディペンデント・ラジオの登場で、市民は初めて議会の質疑を自分の耳で聴けるようになり、政治をライブで知ることができるようになりました。 |
| 『赤い旅団』マリオ・モレッティが語る’77ムーブメント |
| ロッサーナ・ロッサンダは、マリオ・モレッティへのインタビューで、「77年のムーブメントは、あなたたちの誰かが武器を使って激化させたんじゃないのか」「ムーブメントの指揮を執ったのは誰なのか」と、76年を境にアクションを先鋭化させた『赤い旅団』に疑問を呈し、学生たちのムーブメントに『旅団』の介入があったのでは、と厳しく質問をしています。しかしモレッティは「指揮をした人間などはいないよ。誰もがメトロポリタンで闘う反体制者、『プロレタリアート共産党』のメンバーだったんだから」と曖昧に答えている。興味深いのは、モレッティが77年のムーブメントを「68年のムーブメントとは明らかに違う若者たちによる抗議運動であった」「70年代中盤に入ると、ムーブメントの最もラディカルな存在は、『工場労働者』ではなく、ウァルター・アラシアのような『学生』や、区域の若者たちへと変わっていった」とも断言していることです。「では『赤い旅団』は、工場での闘いは捨ててしまったのか。そもそも工場が『赤い旅団』の核ではなかったのか。72~73年までは、アンタゴニストー反体制者は、労働階級のアヴァンギャルドな過激派という位置づけで、それがイタリアの極左集団の伝統的な特徴だったが、77年になると他のヨーロッパの武装グループと全く同じになってしまったのでは?」という問いには、「工場は闘いの場としては狭すぎるようになった。世の中に緊張を生むことで権力を解体させ、機能を麻痺させようという目標が、僕たちのストラテジーに変わっていったんだ」とモレッティは答えている。さらに「自分には77 年のムーブメントはまったく掴み所がなく、理解できない」とも言っています。確かに『メトロポリタンのインディアンたち』をモレッティが理解して、共感したとは到底想像できません。 クルチョ、フランチェスキーニが逮捕され、マラ・カゴールが死亡したあと、『赤い旅団』のメンタリティも大きく変わり、『市民戦争』にまで発展した過激な’77ムーブメントから大きな支持を得て、多くのメンバーをリクルートしてもいる。68年のムーブメントとは世代が違う多くの若者が『赤い旅団』に参入することになりました。 77年を境に、もはや『赤い旅団』は戦中戦後、ファシズムを相手に闘い続けた共産主義パルチザンの伝統からは、遥かにかけ離れた存在、ただのテロリスト集団に変遷した、ということです。 |
| 2019.11.9日、「貧しき者たちに寄り添い、『インテグラルなエコロジー』を世界に訴えるフランシスコ教皇」 | ||
| 最近のイタリア政治には少し暗雲が漂っていますが、まもなく教皇が日本を訪問されるので、キリスト教やローマ・カトリック教会のこと、そしてフランシスコ教皇が日頃おっしゃることなど、改めて考えたり、調べたりしてみました。なにより深く感銘を受けるのは「貧しき者たちによる、貧しき者たちのための教会を」とおっしゃって、社会で最も弱い立場にある人々に常に寄り添い、消費主義=『廃棄文化』に誘発された環境破壊と気候変動が、地域社会、ひいては世界の均衡を大きく崩している、とご指摘なさることです。わたしはカトリックの信仰者ではありませんし、一神教には懐疑的ではあっても、教皇のおっしゃることには強い共感を覚えています(写真は、いつの頃からかローマの地下鉄スペイン広場駅に描かれたグラフィティ)。 | ||
| カトリック文化をルーツとするローマの人々 | ||
| もうずいぶん昔のことになりますが、ローマの人々と知り合いはじめて、我が身を振り返ることになったのは、彼らから「自然に湧き出る、自分より弱い立場にある人々へのやさしさ」でした。そしてその「街に漂うなんとなくやさしい空気」が、たとえば一部の極右勢力の台頭や、ときどき巷を震撼させる差別主義に失望しながら、いつまでたってもマイノリティである外国人のわたしをローマに留める大きな理由のひとつです。 もちろんローマには、大雑把に言うと「何が何でも自分の意見を主張する」とか「感情の起伏、迸る思いをそのまま言葉、態度に表現しないと気がすまない」とか「空気をまったく読まない」「僕、あるいはわたしが主人公主義」など、コミュニケーションに慣れるまでに時間がかかった独自の精神性もありましたが、普段はかなりお調子者の輩であっても、重い荷物を抱えたお年寄りが側を通ると「持ちましょう」と、ちょっと気取りながら申し出て、世間話をしながら駅まで送る姿には感動したりもしました。ローマの人々は意外に繊細です。また天気のいい日には、必ず近所の広場にたむろして、詩であるとか、ポストモダンであるとか、あるいは突然過去に遡り、ギリシャ哲学などを紐解いて喧々諤々と議論する、当時はまだ若かった芸術家の友人たちが、いつの間にかふらっと現れた物乞いのおじさんが手を差し出すと、「お、今日はいいTシャツ着てるね。誰かにもらったの?」と、何気なくポケットからピーナッツの皮にまみれた小銭をザラッと出して、その掌に乗せる様子にハッとした。客を探して何回も広場を横切る薔薇売りの青年には、「薔薇はいらないから、とっときな」と、少ないながらも小銭を渡し、哀しい旋律を奏でるジプシー青年の流しのアコーディオンには「ブラヴォー」と拍手しながら「いつ聞いても素晴らしいね。少なくて申し訳ない」とチップを弾んでいました。「資本主義反対!」「グローバリゼーションのせいで、僕らには居場所がない。お金もない。困った、困った」といつも文句ばかり言っているわりには、彼らはずいぶん気前がいいので「さっきまで、お金がないって言ってなかった?」と尋ねると、「お互いさまだからね」と涼しい顔でニヤッと笑い、再び「芸術」について、ああでもない、こうでもない、と語りだすという具合です。その彼らは現在でも「お金がない。お金がない」と言いながら、相変わらず芸術の険しい道のりを巡礼者のように歩いています。もちろんローマの人々全員が、このように「弱者への温かい眼差しを持っている」というわけではなく、凶悪犯罪も起こりますし、詐欺も多発します。最近では、SNSの差別主義に感化された若者が壁に外国人を侮辱する落書きをしたり、アンチファのお店を放火したり、すれ違いざまに悪態をついたり、さらにはマフィアまで暗躍していますから、旅先での甘言には徹底的に気をつけなければならないのが、外国滞在の鉄則です。が、バスに乗ればお年寄りにはもちろん、妊婦さんにも必ず誰かが席をゆずるし、ベビーカーの上げ下ろしを手伝う若者たちを見かけます。洒落たレストランで子供が泣き叫んでも、誰もが若い夫婦に「困ったね」ぐらいの感じで微笑みかけ、なかには子供をあやしに席を立つご婦人もいるくらいです。 そして、信仰の有無に関わらず、プライベートの時間を徹底的に削って、行き場を失った難民の人々や、住居を追われた人々など、苦難にある人々を支援するNGOグループや社会活動が周囲にたくさん存在する。イタリアは欧州の他の国に比べて、最もボランティア活動が盛んである、という統計もあります。互助精神が失われつつある時代、極東アジアから訪れたわたしには、さまざまな困難が日常茶飯事で、人々の動きに、のびのびしすぎる無駄な時間がやたらに多いことにはうんざりしながらも、そんなヒューマンなローマが居心地よく、開放的に感じました。「しかしいったい何が彼らをやさしくさせているのか」そう思いを巡らすうちに、やはり長きに渡って人々の日常に根づくキリスト教文化のせいなのだろう、と思い至ることになった。また、大部分のローマの人々の考え方に切迫感がなく、どこか人間的な緩みがあるのは、「ローマという街は聖母に抱かれている」というぼんやりとした宗教的な安心感が無意識に働くからではないか、とも思います。 ところが、わたしの周囲の2、3人を除いて、教会に通う人は見当たらないのです。 「教会のミサには行ってないようだけど、あなたはキリスト者?」と知り合いに尋ねてみると、驚いたような顔をして「当たり前じゃないか。僕は世界中の宗教、スピリチュアリティには敬意を表するが、あらゆるすべての基本はイエス・キリストだよ。たまには福音書だって読むんだ。でも教会には行かないよ。いいかい、教会とイエス・キリストはもはや何ら関係ない。新聞を読んでごらんよ。ヴァチカンはスキャンダルばかりじゃないか」と断言したのです。それが、かれこれ10年ほど前の話です。そして「もし、本当にイエス・キリストのことを知りたければ、この映画を観るといい」と勧められたのがピエールパオロ・パソリーニの『奇跡の丘/Vangelo secondo Matteo(マテオによる福音書)』でした。 | ||
| 『奇跡の丘』とフランシスコ教皇 | ||
| 前述したように、わたしはキリスト教の信仰者ではありませんが、プロテスタントのミッションスクールに通っていたせいで、福音書にもいくらか親しみがあり、ある一定の「慈しみ深きキリスト像」を抱きながら青春期を過ごしています。ところが、パソリーニの『奇跡の丘』を観て、それまでのイエス・キリストへの理解が一転したと言っても過言ではありません。それはある意味、衝撃と言ってもいいほどでした。それまでのわたしは、イエス・キリストが、当時のユダヤ社会(腐敗した権威が豪奢を極める格差社会として表現されており)の変革者として現れ、今の言葉で言えば、「マージナル」に押しやられた人々に、奇跡と希望をもたらした、いわば『革命家』なのだ、という認識を持ったことはなかったのです。もちろん、パソリーニの背景には、欧州の中で特にイタリアに根を下ろし、のちにユーロ・コミュニズムへと発展するマルクスーグラムシの共産主義思想があったわけですが、『マテオによる福音書』を読み返すたびに、『貧しい出自の弟子たちとともに、荒地を黙々と、厳しい眼差しで放浪しながら教えを説き、貧困に喘ぐ、あるいは病んだ人々に奇跡(希望)をもたらすイエス・キリスト』というパソリーニの解釈が最もしっくり来るように思うのです。そして相当な大人になってはじめて「なるほど、これが何度も革命や変革が起こるキリスト教世界の普遍の価値観なのかも」と思い至った次第です。と同時に『赤い旅団』のレナート・クルチォが言ったとされる「イエス・キリストは歴史上最初の共産主義者だ」という言葉にも、妙に合点がいきました。いずれにしても当時、不品行とされたホモセクシャルであることや強烈な共産主義者であること、そのうえ数々のスキャンダルを巻き起こし、いくつもの訴訟を抱えていた『聖人』パソリーニ(モラヴィアは、パソリーニを100年に1度現れるかどうかの『詩聖』だ、とオマージュを遺しています)は、ヴァチカンから忌み嫌われ、厳しく糾弾されていました。時が経ち、多くのカトリック信仰者や修道士、そしてちいさな教会の神父さまたちやカリタスが、貧窮した人々や困難な状況にある人々に、たゆみなく支援の手を差し伸べることには感銘を受ける一方、本体の教会ではIOR(ヴァチカン銀行)の資金洗浄スキャンダルや、聖職者による小児性的虐待というニュースが駆け巡り、権力欲とお金と肉欲に塗れた『聖域』の腐敗を思わずにはいられなかった。時代時代に、多くの優れた聖人が存在するにも関わらず、ヴァチカンという複雑なヒエラルキーで構成される権力機構を流れる遥かな時間が紡いだ歴史物語から、そして現状から、もはや神の子の福音を聞くことは困難でした。そんな気分のときにコンクラーベで教皇に選ばれたのが、『カトリック教会の改革者』となるアルゼンチンから訪れたホルヘ・マリオ・ベルゴリオ枢機卿、現在のフランシスコ教皇だった。そして2014年には、そのフランシスコ教皇を頂点とするヴァチカン(オッサルヴァトーレ・ロマーノ)が、(なんと!)「キリストを描いた映画の中で最も優れているのは、ピエールパオロ・パソリーニの『奇跡の丘』だ」と発表する運びとなり、「ヴァチカンがパソリーニの映画を賞賛するとは!?」と誰もが驚くことになったのです。
ヴァチカンが、パソリーニの『奇跡の丘』を選んだことは、教皇が持つイエス・キリスト像、そしてキリスト者としての姿勢を確認できる重要な出来事でした。『貧しき者たちによる、貧しき者たちのための教会を』と、困難にある人々、難民の人々を助けるために全力で立ち向かい、宗教を超えユニバーサルな環境保護、社会問題の解決を訴え、難しい状況に陥った教皇庁の改革に挑む教皇を、人々は『急進的』と呼びます。
しかし原始キリスト教そのものが、腐敗した権威が牛耳るユダヤ世界における、神の子による革命だったと考えるのならば、フランシスコ教皇の、誰にでも分かりやすく、シンプルで明確な言葉と姿勢こそが、キリスト教の原点ではないのか。もちろん、教会には時とともに積み上げられ、洗練された神学が存在するわけですが、刷新というアプローチこそがキリスト教を現在まで継続させた大きな理由のひとつではないか、とも考えるのです。 「福音のあるところ、革命があリます。福音は静止を許さないのです。われわれを革命に追い立てます」これは2019年初頭の謁見での、教皇の言葉です。 さらには『共産主義再建党』の前書記長ファウスト・ベルティノッティが、「イタリアの左派政治はもはや死んでいる。一方、フランシスコ教皇はわたしたちの住む荒れ果てた社会に、非常に深い問いを投げかけられる。良心はまだ生きていたのだ」と発言しました。とはいっても、もちろんフランシスコ教皇は、政治思想にはなんら関係はありませんから、むしろイタリアで発展したユーロ・コミュニズムが、キリスト教の影響を大きく受けていると考えるのが自然ではありましょう。 わたしの周囲の人々は、信仰からは程遠い唯物論的なリアリスト、あるいは非常に政治的な人々を含めて、ほぼ全員が、フランシスコ教皇のファンです。しかし教皇庁の中枢を、厳かに徘徊する古い魂たちにも、教皇はさらっと厳しく対応するため、ヴァチカン内部、そして外部に、多くの敵が多くいるのも事実です。これについては後述したいと思います。 なお、イタリア語ではフランチェスコ教皇と呼びますが、ここでは日本語表記に合わせてフランシスコ教皇に統一しました。 |
||
| ※『奇跡の丘』から。マタイによる福音書 第5章3節から「こころの貧しい人たちは、さいわいである。天国は彼らの慰められるだろう。柔和な人たちは、さいわいである。彼らは地を受けつぐであろう。義に飢えかわいている人たちは、さいわいである。彼らは飽き足りるようになるであろう。あわれみ深い人たちは、さいわいである。彼らはあわれみを受けるであろう。心の清い人たちは、さいわいである。彼らは神を見るであろう。平和をつくり出す人たちは、さいわいである。彼らは神を見るであろう。義のために迫害されてきた人たちは、さいわいである。天国は彼らのものである」 わたしのために人々があなたがたをののしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々の悪口を言うときには、あなたがたはさいわいである。喜べ、よろこべ。天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。第7章9節、第5章17節、第5章13節から、さらには奇跡のシーンへと進むクリップ。すべての台詞が『マタイによる福音書』に忠実に再現されています。 | ||
| フランシスコ教皇の人柄を語るエピソード | ||
| さて、教皇の経歴については、日本語のウィキペディアにも詳細が書かれているので、ご覧になっていただければと思いますが、アルゼンチンの枢機卿時代は、ワンルームのアパートで、ご自分で夕食を作るという質素な生活をしながら、地下鉄やバスなどの公共交通機関を使って、貧窮した人々の救済に尽力していらっしゃったことは、今でも語り草になっています。イタリア、ピエモンテ州から移民した、決して裕福ではない労働者階級の家族に生まれた教皇は、幼い時から会計士事務所に働きに出かけ、聖職者になる以前には、工場の清掃やナイトクラブのボディガードなどの仕事(イタリア語版ウィキペディア)まで経験されているそうです。つまり、教皇が『貧しき者たち』に深い共感をもって尽力され、祝福されるのは、移民であるご自身が、世の中の現実を実感としてご存知だからだと思います。教皇になられてすぐには、カトリック教会の高位聖職者が、高級車を乗り回す贅沢な生活をしていることを厳しく批判。ご自身はこじんまりとしたファミリーカーで移動され、たとえば、さまざまな儀式の際にも豪華な法衣をまとわず、教皇の普段着である白い法衣で人々の前に現れることがほとんどです。そういえば、街の眼鏡店に、突然ご自身の眼鏡の修理を頼みにいらして、腰を抜かした店主が「あ、新しい眼鏡を献上します!」と申し出ても、「この眼鏡の修理でいいのです」とおっしゃり、5ユーロほどの修理代を払って帰られた、というエピソードもあります。また、サン・ピエトロ寺院の始祖である聖人ペテロの後継者としての教皇の証、『漁師の指輪』に関しても、歴代の教皇のようなゴージャスなものではなく、銀製に金メッキの指輪を選ばれていますし、住居として選ばれたのもまた、教皇のために用意された豪華アパートではなく、コンクラーベが開かれる際に枢機卿たちが宿泊するカーサ・サンタ・マルタのレジデンスの1室で、他の客室よりは少々広い50㎡ぐらいのお部屋だそうです。ヴァチカンには、自らの権威を象徴するように、ローマの一等地の300、400㎡もある豪華絢爛な邸宅(もちろん無料)で、優雅な暮らしをする高位聖職者も存在します。とある枢機卿は、自宅を大幅に修復するために、子供病院の基金を横流しした、という嫌疑がかけられるという有り様でした。さらにはなぜか『戦争に使うような高額な武器』を収集していた高位聖職者も存在していたそうです。
繰り返しになりますが、教会を担う聖職者、真摯なキリスト者の方々が、困難にある人々のために骨身を削って尽力され、高邁な志を持って、カトリックの病院施設や大学で、日々勉学、研究に励んでいらっしゃることを知ってはいても、法衣をまといながら世俗的で豪奢な生活を謳歌する、ひと握りの高位聖職者たちの存在が、人々を失望させ、教会から足を遠のかせていたことは事実です。
残念ながら、税金を納める必要のない宗教組織のヒエラルキーにおいては、頂点、あるいは頂点にほど近い聖職者(僧侶、聖者でもいいのですが)が、腐った権力欲と世俗的な欲望に心を奪われ、救いを求める衆生がすっかり欺かれるケースが後を絶たない。このような現象は、古今東西、宗教組織と呼ばれるものの、悪しきアーキタイプと言えるかもしれません。そういえば、『マタイによる福音書』にも「にせ預言者を警戒せよ。彼らは羊の衣を着てあなたがたのところに来るが、その内側は強欲なおおかみである」という一節があります。いずれにしても、人間とお金が集まるところには、それが世俗であろうと、聖域であろうと、必ず権力欲と欲望が渦巻く、と考えておいたほうがいいのだと思います。ただし世俗では普通のことでもその舞台が、人々が絶対真理を求める聖域となると、失望は一段と深まり、非難が大きくなる。
さて、コンクラーベでベルゴリオ枢機卿が教皇が選出された夜、荘厳な「ハベームス パパム(我ら、教皇を得たり)」の宣言に、サン・ピエトロ広場に集まった大観衆の喝采が起こりました。ついでアッシジのサン・フランシスコの名を継ぐ教皇の誕生を告げられるや否や、さらなる大喝采が起こった。「兄弟、姉妹たち、こんばんわ」と、白い法衣のまま(通常、教皇は赤いマントを羽織って現れますが)の教皇がにこやかに、緊張のない軽やかさで現れた時は、広場全体に轟きが起こりました。 そしてその軽やかさで、フランシスコ教皇が教会の改革に乗り出されてから、「ヴァチカンの空気が変わった」、と人々の教会への期待が日々高まっていったのです。 フランシスコ教皇が現れて、ちょっと驚いたことは、『パルティート・ラディカーレ : 急進党』、イタリアの人権の父とも言える、マルコ・パンネッラが教皇を賞賛したことでした。パンネッラは、信仰者には厳格な倫理観を押し付けるにも関わらず、噴出する数々のスキャンダル、漏れ伝えられる高位聖職者の豪奢な生活を軽蔑し、それまで強力なアンチヴァチカニストとして、厳しく教会を批判していました。当時、難民の人々が大勢訪れたギリシャのレスボ島を訪れ、難民の人々を温かく抱擁するフランシスコ教皇に、歴代の教皇に反発していたパンネッラは感銘を受け、「ありがとう。わたしはあなたのことが大好きだ」と締めくくる手紙を送っています。 また教皇も、長年ヴァチカンを批判し続け、カトリックの教義を無視し続けたパンネッラが亡くなった2016年、「寛大な政治家として、特に弱者と貧しい人々の権利に貢献する、大きな遺産とスピリテュアリティを遺した」と異例の表明を出しました。 ちなみに、カトリック教会の倫理観が一般市民の倫理観と重なっていた70年代のイタリアで、『離婚』と『中絶』を議会で発議し、法律化することに成功した『ラディカーレ』は、現在ではLGBTの人々の家族の権利の保護やマリワナの解禁、『安楽死』を強くプロモートしています。一方、ヴァチカンは『中絶』はもちろん、『安楽死』、『LGBTのカップルによる家族』を認めてはいません。どれほどフランシスコ教皇がわれわれ庶民、そして弱者に寄り添ってくださる教皇であっても、カトリック教会には違いありませんから、行きすぎた政治的幻想を抱いてはいけません。それでも教皇が、何度もハンストを繰り返し、マイノリティの権利を保護するために、生涯、峻厳な『ガンジー主義』を貫いたパンネッラを称えたことは、両者に共感があったからに他ならないでしょう。ヴァチカンと『ラディカーレ』が共通するのは、『死刑』『拷問』の廃止を世界に訴えていることでしょうか。 その後、フランシスコ教皇はカトリックの教義を緩め、「離婚、あるいは再婚した信仰者」の聖体拝領(キリストの肉を表すパンを神父から拝受する秘跡のひとつ)を許したのですが、これが教会内の保守宗教右派から大きな反発を受けることになりました(後述)。 さらに、LGBTのカップルによる家族形成を決して容認はなさいませんが、「ゲイであるという形容詞よりも、人間であるという主体の方が大切」と述べられ、それぞれの人を、まず「人間」として教会が受け入れる姿勢を示されています。また、ゲイの人々についてどう考えているのか、と質問された際は「裁くのはわたしではないからね」とおっしゃったこともありました。 |
||
| これはちょっと余談になってしまうのですが、ごく最近、「宗教と環境問題の融合」を議題に、アマゾンが跨る南米の国々の司祭を中心に、各国の聖職者が集まって開かれた特別なシノドス(教会会議)の期間のことです。たまたま知り合いの誘いで、ヴァチカンのパオロ6世記念ホールのロビーで開かれた、ボリビアから訪れた人々のコンサートを聴きに行ってみました。当然、彼らの民族音楽だとばかり思って出かけたにも関わらず、民族衣装に身を包んだ彼らが演奏したのは『バロック音楽』で、しかも半端なく、熟練された本格的な演奏でした。
その日、同時に開かれたカンファレンスによれば、ボリビアの人々のバロック音楽との出会いは、欧州各国が南米を侵略した大航海時代、布教に訪れた宣教師が地域の人々に当時の音楽を教えたのがはじまりだそうです。そもそも彼らは優れた音楽性を持つ民族で、欧州の音楽をすぐに覚えた。しかしそうこうするうちに宣教師たちはその地を去らざるをえない状況となり、その後その地域には、カトリックの宣教師が存在しないまま、数百年という時間が流れていきました。時は変わって現代。改めてボリビアのその地域に布教に訪れた宣教師は、音楽好きの彼らが気ままに奏でる音楽を聴いて驚愕します。「欧州にはもはや存在しない、こんなバロック音楽の旋律が、ボリビアに残っていたとは!」。ボリビアのその地域の人々は、宣教師たちが去ったあと、かつて訪れた彼らが教えた音楽を、何代にも渡って受け継いでいたというのです。
その事実に感動した宣教師の人々は、彼らの音楽性の豊かさをさらに発展させたい、と先代の教皇『ベネディクト16世』の名を冠した基金を募り、今ではボリビアに音楽学校を設立し、その地域の多くの若者たちが音楽を学んでいるそうです。ところで、そのコンサートスペースの後ろの席に座って、その透明で柔和なコーラスを聴いていたときのことです。急に傍を、ひとりの枢機卿が入り口の方へ小走りに移動されたので、ふとその背中を追って後ろを振り向いて、えええ!と驚くことになりました。移動の途中に、ちょっと様子を見に立ち寄られた、という風情で、白い法衣をまとった教皇が無防備に入り口あたりに立って、微笑みながらコンサートを聴いていらした。そして2言3言、枢機卿と言葉を交わされると、コンサートを聴いている誰もが気づかないうちに、またふっといらっしゃらなくなったのです。警備員たちも必要以上に緊張した様子はなく、なごやかで温かい空気が入り口あたりにたちこめていました。ちなみに今回行われたシノドスでは、カトリックの聖職者が少ない地域において、「その人物に適性があり、地域で認められた人物であれば、妻帯者であっても聖職に就くことを認める」という議題が賛成多数で議決され、フランシスコ教皇の今後の決断を仰ぐことになったそうです。
「カトリックの聖職者が少ない地域において」という条件があったとしても、いままで聖職者の妻帯を認めなかったカトリック(過去、ベネディクト16世が妻帯者であるイングランド国教会聖職者のカトリックへの改宗を認めたことがあり、アジア地域には妻帯者の神父も多くいるようですが)にとって、今回の議決が教皇に受け入れられれば、歴史的な改革となります。また、今回のシノドスでは女性の助祭司を認める、という議決もされました。フランシスコ教皇が、そもそもイエズス会のミッショナリーであることもまた、教会にこのような変革が起きる理由のひとつではないか、との意見があります。かつて日本を含め、世界の各地を訪れたカトリックの宣教師たちは、その地域が持つ風習や精神性を否定することなく、それぞれの風土に順応しながら福音を布教していったわけですし(たとえばアフリカにはアフリカ的なカトリックの礼拝があり、アラブ世界にはアラブ世界的な礼拝があります)、さらにはローマ・カトリック教会そのもののあり方も、歴史の変化に適応しながら、現代まで継続してきたわけです。その事実を思うなら、フランシスコ教皇は、激動し、大きく変化しながら、数々の問題が山積みの現代に、カトリック世界が選出したユニヴァーサル・レベルのミッショナリーなのかもしれません。実際、フランシスコ教皇が提言される内容の数々は、カトリックの倫理を超えた、人類共通の大きな課題です。だからこそ教皇の姿勢は、わたしのような一神教に懐疑的な人間をも魅了し、納得させるのだと思います。
いずれにしても、「妻帯者が聖職者となり、女性が助祭司を務める」ことが可能となるかもしれない今回の議決には、「まさかこの枢機卿が!」と驚くハイ・キャリアの保守派高位聖職者から反発が生まれており、コリエレ・デッラ・セーラ紙のインタビューでは、教皇がそれを認めないことを公にリクエストしています。さらにあろうことか、その高位聖職者は、「ヴァチカンはサルヴィーニが率いる極右政治勢力と交流を持つべき」とも発言し、かねてから表面化している教会内の分裂を再び露呈する形となった。怪しい国際背景を持つ、極右政治勢力がカトリック内部の保守宗教右派にがっつり食い込んで、教皇を目の敵にしていることは心配なことです。 |
||
| 現代社会への提言でもある、回勅『Laudato si’ mi signore nostra(ラウダート・シー・ミ・シニョーレ・ノストラ)』 | ||
| さて、フランシスコ教皇が、教皇になられて以来、強く訴えていらっしゃるのが、自然環境破壊と世界に広がる経済格差への危機感から導かれた『インテグラルなエコロジー』、『貧困が是正される、公平な社会』、そして教会そのものの『倫理観のイノベーション』でしょうか。教会のあり方としては、人々の苦難の叫びを聞き分け、『misericordiaー神の憐れみ、慈しみ』をもたらす場であるべきこと、そして常に開かれた場所であるべきことを改めて確認されています。また、2015年から2016年にかけては、『misericordia』の特別聖年と定め、貧窮にある人々や、排斥された人々、難民の人々、隣人への憐れみを訴えられました。さらには、われわれはみな同じ『人間』であるにも関わらず、世界中で政治が権力を乱用し、排外主義的な政策が助長されている状況に、インテグラル=総合的に『公正』と『友愛』と『環境』のバランスをとる最も重要な手段として、国際的な対話を促すことを訴えていらっしゃいます。 イタリアにおいては、マテオ・サルヴィーニが内務大臣時代に、難民の人々を乗せた船を一切着港させない、という暴力的な『国家安全保障』の決定の裏で、難民の人々を無条件に受け入れることを訴え続けた教皇に、サルヴィーニが謁見をリクエストしたことは、今まで1度もありませんでした。 もちろん、世界中に拡大する貧困問題がただちに解決することがないように、たちまちに新しいヴィジョンを持った人々や、キリストのスピリットで刷新されたキリスト者が現れるわけではありませんが、長い時間をかけた繊細な教育によって、人々に良心と新しいヴィジョンをもたらすことが、教皇のお考えなのだそうです。 また、国際的な「公正と平和」を実現させるのは、「インテグラルなエコロジー」という枠組みでのみ可能だと、教皇はおっしゃいます。イタリア語で、「インテグラーレ」という言葉は、「総合した、無欠の、完全な、全てを含む」というのが第一義ですが、自然環境、生物多様性、全人類の健全な生活、経済発展など、あらゆるすべてが均衡を保ち、循環しながら、必要なものが平等に行き渡る状況、というコンセプトなのだと、わたしは解釈しています。 わたしたちが『環境』を保護しなければ、正しい進歩のための『家』はいよいよ荒れ果てていき、よりよく生きようとどんなに懸命に努力しても、まったく無意味である。デジタル時代と同時に、われわれの間にエコロジーと公正な社会への意識が目覚めようとしており、効果的にエコロジーな生活を送りたいならば、より公正で友愛に満ちた社会のために貢献しなければならないと、教皇はおっしゃっているのです。 アッシジのサン・フランシスコの『太陽の賛歌』の一節がタイトルに掲げられた、192ページ、6章246節に及ぶフランシスコ教皇の2番目の回勅(教皇から世界中の司祭に送られるカトリック教会の公文書ー2015年6月18日)『ラウダート・シー』は、もちろん聖職者の方々への宗教的な公文書ではありますが、宗教の枠を超え、今後、ユニヴァーサルに立ち向かわなければならない環境問題、社会問題が核となっています。 この『ラウダート・シー』は一般的に、環境保護:グリーンを推進する回勅と捉えられることが多いのですが、むしろ社会問題:ソーシャルな回勅であることが、何度も強調されました。 | ||
| 行き過ぎた個人主義、消費主義、浪費により、水、自然など、世界の共有財産がリスクにさらされ、経済格差、貧困が広がり、不公平の度合いがいよいよ増す現代に必要なのは、あらゆるすべての人々との連帯を共有する経済、環境、そして社会であり、刹那的な満足を追求するのではなく、未来の世代のためによりヒューマンな経済システムを構築しなければならないと、回勅は詳説している。 わたしたちが生きている先進国と呼ばれる国々の、長いスパンで状況を判断することのない近視眼的な政治と、ライフスタイルをなかなか変えることができないエゴイスティックな消費主義が核となった社会の有り様、そして場当たり的な地下資源及び森林資源の過剰利用、搾取に対し、科学的な分析とともに警鐘が鳴らされています。事実、資源の過剰採掘や森林伐採で地球レベルで環境は破壊され、干ばつや飢饉が起こり、気候が大きく変動し、さらに資源に群がる国々が引き金となる戦争、紛争が絶えません。 そしてそれらの戦争で、突然に日常の生活を奪われた人々が、難民となって他国へ救いを求めようとすると、その原因となった紛争や資源の争奪に加担しておきながら、『国粋主義』、『排外主義』という自分勝手な思想を掲げた先進国から国境を閉ざされ、路頭に迷わざるをえない。これはどう考えても異常で、非人間的な状況です。 その状況に回勅は、人類が『自分たちが共有している家』を大切にするという責務を負うようになるに至るまで、カトリック教会の『エコロジカルな改心』『方向変換』を求め、さらに世界から不幸を根絶し、貧困に注意を払い、すべての人々に、地球上の資源が公平に行き渡ることを求めています。もちろん、それはカトリックの信仰者だけでなく、現代を生きるわれわれひとりひとりに、ライフスタイルを見直す必要があることを確信させる内容です。 『ラウダート・シー』の全文をわたしは読んではいないのですが、日本語にもすでに翻訳されています。ここでは「ヴァチカン・ニュース」、そして週刊誌として、イタリアで最も部数を誇る雑誌のひとつ「Famiglia Cristiana(クリスチャン・ファミリー)」の概要記事を参考に、教皇の回勅のポイントを、この項の末尾に簡単にまとめました。 カトリックの門外漢としてまとめた概要なので誤認があるやもしれません。間違いや問題などご指摘いただければ、大変ありがたく思います。なお、クリスチャン・ファミリーは、マテオ・サルヴィーニの『国家安全保障』についても、厳しく批判する記事を掲載した経緯がある雑誌です。 ところで、反教皇派の教会内部の保守宗教右派(極右政党とも絆を持つ)と、緊密に繋がる米国カトリック教会は、この回勅の存在を認めようとせず、『環境問題』や『社会問題』が、まるで存在しないようなふりをしているらしいのですが、その理由を次のページで考えてみたいと思います。 | ||
| 教会内外からの攻撃にも、揺るがない教皇の信念 | ||
| 教会スキャンダルとして、記憶に新しいところでは、米国人聖職者らのおぞましい実態を暴いたボストン・グローブ紙の小児性的虐待の一連の報道を映画化した『スポットライト』の公開で、世界の注目を集めた一連のスキャンダルでしょうか。その後も各国から、たびたび聖職者の『ペドフィリア』のニュースが流れてきて、そのたびに非常に幻滅したのも事実です。しかしヴァチカンは、ベネディクト16世前教皇の時代から、次々に明るみに出るカトリック聖職者小児性的虐待に対して、厳罰を下すと言う方針を貫いています。もちろん、フランシスコ教皇もベネディクト16世同様、神父、そして枢機卿という聖職者の『ペドフィリア』を厳しく監視され、暴かれると同時に、厳罰に処していらっしゃる。たとえばニューヨーク・タイム紙に暴かれた、子供から大人に至るまで、長きに渡って性的虐待を繰り返していた米国人枢機卿の高位を、発覚後、教皇はただちに剥奪されました。『枢機卿』という高位聖職者がそのタイトルを剥奪されることは、前代未聞のことでした。また今年の2月には、「子供たちの保護は、現代の緊急の課題」であり「神に仕える者として、重責を担う行動」を取らなければならない、と教皇が全世界の司教のトップを招聘してサミットが開かれ、ペドフィリアの悲劇にいかに立ち向かうか、徹底的に話し合われています。 そしてヴァチカンには、厳格に監視しなければならない、もうひとつの課題としての、資金洗浄や不正投資などの金銭スキャンダルがある。いまでもときどき、不意に表面に浮き上がってくる不正の舞台とされるのは、「教会関係の芸術、建築の修復のため、信仰者の献金を管理する」、実質的には銀行の役割を担うIORや、教会が保有する不動産の管理を担うApsaと呼ばれる機関で、数週間前にもレスプレッソ紙が、海外への不正投資、資金洗浄があったのでは?と追跡した記事を掲載したところです。さらにはごく最近(アマゾンに関わる教会会議の最中に)、「ヴァチカンは世界から集まった献金を管理できていない。不正で膨らんだ赤字でデフォルトの危機にある」、「フランシスコ教皇の最期の闘い」とセンセーショナルな見出しがついた『最期の審判』という本が出版されました。この本を書いたジャーナリストは、『ヴァチリークス』とも呼ばれるヴァチカンのスキャンダルを追った本を何冊も出版しており、ヴァチカンで裁判にかけられた経緯もあります。 この本では、金銭スキャンダルの出所として、実質的な銀行の役割をするIOR、Apsa、そして教皇庁国務長官事務所、という3つが上げられ、本来門外不出である3000もの書類を元に、ヴァチカン内の収賄、二重口座、不正投資など、教皇の教会改革を妨げるブラックホールを検証。近い将来、ヴァチカンがデフォルトを起こすかもしれないほどの赤字を出す可能性が述べられています。しかし読み進むうちに、ストーリーがあまりに出来すぎで、むしろ不自然に思え、結局途中で読むのをやめることになりました。 つまり、この本の内容が何を意図しているのか、教皇は教会の支出を管理できていない、というイメージを膨らませて、教皇を攻撃しているのか、単純に教皇庁のスキャンダルを暴いて耳目を集めたいのか、ヴァチリークス裁判への報復なのか、はっきりとは掴めないため、額面通り信用するわけにはいかないと感じた、と言うのが正直なところです。 すると、最近になって、ラ・レプッブリカ紙が、教会改革のための枢機卿評議会の議長、マラディアガ枢機卿の次のようなインタビューを報道しました。「ヴァチカンがデフォルトに陥るというのはフェイクです。教皇庁は、とりわけ使徒職も管理しており、さまざまな方面からの収入があります。献金だけが収入源ではないのです。さらにヴァチカン美術館からの収入も教皇庁を助けています。わたしにしてみれば、(この本の出版は、教皇への)不信を募らせるための戦略的な行動のように思えます」(2019/10/21) また、2018年からApsaの責任者となった、ガランティーノ大司教も、「2018年は2200万ユーロが利用可能でした。しかし危機に陥った病院施設とそこで働く人々を保護するために、特別な支出があったことは確かです」「この本は、『ダヴィンチ・コード』と同様、小説のようなアプローチがされているのではないでしょうか」と、現在のApsaという機関の状況と詳細を、アヴェニーレ紙に語ってらっしゃいます。『貧しき者たち』に寄り添い、社会問題の解決を訴え、教会の改革を進めるフランシスコ教皇は、就任した当初から米国カトリック教会と繋がる保守宗教右派グループから、次から次へと攻撃を受け、教会内に分裂があることは周知のことでした。確実なところは、わたしには判断できませんが、「デフォルト」などという、あまりにセンセーショナルな内容のリサーチは、「ドラマチックだけれど、ありそうにもない」と考えたほうがよいと思う次第です。 | ||
| いずれにしても、ヴァチカンに根づいてきた、これまでの隠蔽体質こそが、さまざまな不正の温床になり、教皇の教会改革を妨げていることは、想像に難くありません。厚い壁に覆われたヴァチカンという『聖域』を隠れ蓑に、外部巨額資本のマネーロンダリングや、IOR=ヴァチカン銀行に集まった世界中から集まった献金を資金に、海外に投資して巨額の負債を負った、というような事案に捜査が入り、過去には責任者が辞任することも多々ありました。
しかも、それらのオペレーションには、絶大な権力を持つ数人の高位聖職者が関わり、銀行で働く職員すらまったく知ることができないように、徹底的なバリアが張られて行われると言われます。そして、それらの不正がいつからはじまったのか、元をたどるならばイタリアの『鉛の時代』、悪名高い、かの米国人大司教ポール・マルチンクスがIORの総裁を務めていた70年代にまで遡ることになる。マルチンクスといえば、『コーザ・ノストラ』と強い絆を結んで、一躍時代の寵児となった銀行家ミケーレ・シンドーナや、のちに暗殺されたロベルト・カルヴィが総裁だったアンブロジアーノ銀行と結託し、マフィアの大がかりなマネーロンダリングだけでなく、その後のカルディ暗殺事件、教皇ヨハネ・パオロ1世の暗殺疑惑、ヴァチカン職員の娘、エマヌエーラ・オルランディが突然失踪した未解決の事件、教皇ヨハネ・パオロ2世暗殺未遂事件などに関わったとされ、秘密結社『ロッジャ・P2』及びCIAの一員として、当時のヴァチカンに激震を走らせ、同時にその信頼を失墜させた人物です。
マルチンクスはあらゆる事件の捜査上に名が浮かび、その都度、逮捕状が出たにも関わらず、何の罪にも問われず1990年までヴァチカン銀行の総裁を務めています。ちなみにマルチンクスの父親は、アル・カポーネの運転手をしていた、という話もあり、最近米国で出版された、ラッキー・ルチアーノの息子の自伝には「ヨハネ・パオロ1世をシアン化合物で暗殺したのは、マルチンクスだった」と告白する記述があるそうです。マルチンクスが亡くなってしまった現在では、その確証を得ることはできませんが、グラディオ下の『鉛の時代』、緊張作戦からはじまったイタリアの流血の騒乱は、つまりヴァチカンの暗部にまで、深く侵食していたわけです。 そしてその時代のヴァチカン銀行のシステムが現在でも継続している、と『最期の審判』の著者は言います。かつてはイタリアの魔王、ジュリオ・アンドレオッティも利用していたという、存在しないファンデーションの名を冠した名義不明の口座は、廃止されることなくIORで利用され、それがマネーロンダリングの温床になるケースがあると言うのです。今まで明るみに出たヴァチカン銀行と大手金融機関が関わった資金洗浄を思い起こすなら、そういう事情はあるのだろう、とは思います。
ただ、教会内部における反教皇の動きは、前述した米国カトリック教会を中心とする、マテオ・サルヴィーニら極右政党が深く関わる、福音とは真逆な贅沢な暮らしを謳歌する保守宗教右派の高位聖職者たちとされます(Agi分析記事より)し、銀行、あるいは不正投資にまつわる記事にも、その聖職者たちの名前が見え隠れしますから、今までの流れから考えて、マラディアガ枢機卿がおっしゃることが最も信用に足る、と考える次第です。前述したように、教皇が『再婚した人々にも聖体拝領を許可』、つまりカトリック的には罪を犯した人々に教会の扉を開いたため、大反発したお年寄りの4人の枢機卿が『神学的な疑い』を主張し、シノドス=教会会議を巻き込んで大きな議論となったこともありました。さらには大規模な小児性的虐待で糾弾された、件の米国人枢機卿の手下のように振舞っていたとされる、前米国ヴァチカン使節が、フランシスコ教皇の辞任を要求するなど、反教皇派が声高に騒ぐ事態がときどき起こります。
フランシスコ教皇が、自分の生まれた国、そして家族と離れ離れになり、難民として生きて行かねばならなくなった人々の尊厳を強く訴え、『受け入れ、守り、支えながら、たどり着いた土地に馴染んでもらう配慮』を主張していることで、難民の人々が逃げ出した国に投資し、資源を持ち去り人々から搾取している国、そして大企業は、教皇への敵意を露わにしているそうですが、アマゾンに関わる環境問題に関する教会会議の最中に、『最期の審判』が出版されたのも、このような事情があるからかもしれません。また、教皇が今までに任命した13人の枢機卿は、質素な暮らしをしながら、弱者を救済するために尽力してきた、シンプルな聖職者ばかりだということも、教会内部保守宗教右派の敵意の的となっていると言われます。
「回勅をまったく無視する米国カトリック教会のある一部の者たちは、原油及び石炭関係会社との政治的な繋がりを持つ巨額の寄付金のドナーたちの方に興味があります。そういう意味で、アマゾンに関するシノドス、そして回勅『ラウダート・シー』が推進する繊細な発展と公正な社会という教皇の方針は、お金にしか興味のない者たちには邪魔でしかないのです」(2019/10/21
前述のラ・レプッブリカ紙によるマラディアガ枢機卿インタビューより) 教皇になられた当初から、『貧しき者たちによる、貧しき者たちのための教会を』と、フランシスコ教皇が断言された背景には、そんな背景もあったのだと思います。 ところが教皇は、米国カトリック教会から大きな批判を浴びていることをどう思うか、とジャーナリストに聞かれた際には「批判はいつでも誇りに思います」とにこやかに答えられています。 このように、われわれには想像もできない巨大な妨害に遭遇しても、教皇は常に人々に寄り添い、エネルギッシュに世界を旅し、人々を祝福される。繊細でありながら、揺るがぬ信念を貫く豪腕でたくましい教皇です。 日本でどのようなお話をされるのか、楽しみにしているところです。 |
||
| 回勅『ラウダート・シー』概要 | ||
| ※ヴァチカン・ニュース、クリスチャンファミリーを参考にまとめました。 『主よ、あなたを称えます』 第1章 廃棄文化を拒絶し、飲料水の権利を保護する 現在、われわれの家(地球)で起こっている深刻な状況を、教皇は、環境における科学的なデータを元に分析され、公害と『廃棄文化』の結果として、地球そのもの、つまりわれわれの『家』が、巨大なゴミ収集所に変化しようとしていることを指摘されます。また、リサイクルできない資源の利用を制限しながら、リサイクル、再利用を基盤にした、今までとは異なる生産モデルを構築する原動力の必要性を説かれています。グローバルな問題となっている気候変動のせいで『人権の本質的要素として、ユニヴァーサルな基本』である、生命を維持するために必要不可欠な飲料水を、貧困者が得ることができないような状況(地球温暖化による干ばつなどで)は、『譲ることができない尊厳の根幹』である人権を否定することであるとおっしゃいます。さらに、人為的な気候変動により、未来の子供たちが知ることができないであろう、毎年、何千という種類の植物、動物が地球上から絶滅している現実から、生物多様性の保護を強調されています。また、教皇は、世界には『エコロジカルな負債』があることを明らかにされています。特に南北、つまり先進国が集まる北半球の経済発展のしわ寄せとして南半球の国々が貧しくなる、不均衡なビジネスの有り様で『貧しい国々が外国に借金をせざるを得なくなり』、そのせいで、裕福な国が貧しい国を管理するという結果になっています。しかし本来、そんなことは起こってはならないことです。環境と社会環境の毀傷は、地球上の最も弱い者たちに、付随的損害という特別な形で降りかかってくることになります。ですから、真のエコロジカルなアプローチは、社会問題そのものを解決するアプローチでなければなりません。世界の(先進国の)一部の人々に極端に選択されたライフスタイルである『消費主義』が、エコロジカルなアプローチの障害となっています。現代を生きる人間たちのある種の麻痺状態と無頓着な無責任に対して、生態系:エコシステムの保護を確実にする『システムの基準』を創ることが急務です。 |
||
| 第2章 環境は神からの贈り物であり、破壊できない共有遺産。 「環境は、集合的(collettivo)な神からの贈り物であり、人類の財産であり、共有遺産」であり、破壊すべきではなく、ケアしなければならないものです。神の創造物は全て、それぞれの役割を持ち、何ひとつ余分なく、神の愛を持って触れられるものですから、あらゆるすべての被造物を虐げることは、人間の尊厳という考え方とは対極にある行為です。すべての生きとし生けるものは、『憐れみと気がかり』をもって大切にされるべきであり、そのためには、ユニヴァーサルな聖体拝領(キリストの血、肉を分かち合う)という認識が必要になります。 |
||
| 第3章 テクノクラシー(技術万能主義)の拒絶と被造物の保護責任 技術、人間中心主義、仕事、遺伝子組み替え(GMO)という、この4つのテーマに関して、詳細が述べられています。特に、継続的な発展のための技術の進歩の恩恵を認めながらも、世界中くまなく蔓延する、その技術の知識を悪用する経済権力が主張する技術万能主義に警告を発されています。同時に現代の人間中心主義では、自然の法則を無視して、人間のあるべき場所を認識して『宇宙を管理する責任』という役割を失ってしまうと説いていらっしゃいます。 『使い捨て』のロジックで、あらゆる廃棄を正当化し、『(技術的な)知識を持つ者たち、特に経済権力を持つ者たちが、人間と民族だけではなく世界そのものを支配している』というのがテクノクラシーの論理であり、自然環境を破壊し、特に弱い立場にある人々から搾取しようとします。さらには経済、政治を支配しようとし、『市場だけが総合的な人間の成長や社会への参入を保証するのではない』という認識を否定するのがテクノクラシーです。 テクノクラシーのロジックでは、子供たちから搾取し、お年寄りを放棄し、新たな奴隷を生み出そうとします。市場経済の自動調節機構(神の見えざる手?)を過信して、人身売買、動物の毛皮の売買、さらには血塗られたダイアモンド(シエラレオネ)の売買をする。多くのマフィアの論理同様に、人間の内臓器官、麻薬を売買し、両親の意に沿わない胎児を放棄しようとします(カトリックは中絶に強く反対しているので)。また教皇は、すべての人々が『この地における生存意義の一部』として、人間性の成熟と発展の道のりとして従事できる仕事の保護の必要性を強調。『ただちに巨額の利益を得る目的のために、人々に投資しないことは、社会にとって最悪のビジネス』として、誰もが恩恵を受けられる、真に解放された経済が形成されるまで、『巨大な資本を持ち、経済的な力を持つ層』を制限することが明らかに必要だともおっしゃっています。 GMOに関しては、非常に複雑な問題を孕んでおり、経済的な困難を解決する可能性もありますが、一方ではごく少数の限られた者たちにのみ生産が集中することを指摘。この問題を解決するために、教皇は特に小企業や農村の労働者、また生物多様性、エコシステム網について考えていらっしゃり、広義における責任を負って、すべての情報にアクセスできるように透明性のある、科学的で社会的な議論の必要性を説いていらっしゃいます。 |
||
| 4章 インテグラルなエコロジーは共有財産と切り離せない この章で教皇は、公平性及び政治のテーマとしてのインテグラル・エコロジーに言及されています。自然環境は、わたしたちの人生の単なる背景ではなく、人間と密接に繋がる新しい公平性の基準であると説かれ、『環境と社会が直面している危機を、分けて考えてはいけないーつまり、社会ー環境は、たったひとつの複雑な危機』、と見なされています。教皇は、国家機構のエコロジーについて『すべてが相互に関連しあっているのであれば、社会を管理する国家機構の健全性が、環境や人々の生活の質に影響する。支援や市民的友愛が損なわれると、環境破壊が誘発される』ともおっしゃっている。 また、現代における文脈では、『多くの不均衡があり、見捨てられる人々が数多く存在し、基本的な人権を奪われている』が、共有財産に専心することは、つまり『最も貧困にある人々を優先するオプション』を基本にした選択をすることを意味する、と教皇は述べられています。 |
||
| 第5章 期待していた環境を巡る国際サミットへの失望 「われわれが向かっている自己破壊的なスパイラルから脱する』ために、教会は科学領域の問題だから、とか政治問題だ、と定義してはならないと回勅は続きます。教皇は『特に重要なことや思想は、共有財産を損なうことはないので、誠実で透明な議論』をすべきである、とおっしゃっている。さらに『近年の環境問題を話し合う国際サミットでは、政治的な決断が下されないため、心待ちにしているような結論が何も出ていない。グローバルな環境問題に、現実的で意義があり、効果的に対処するための国際合意は何もなされていない』とも言及。『緊急で差し迫った状況である今日、動くキャパシティのない権力を、なぜわれわれは継続させる必要があるのか』。われわれに必要なのは『グローバルな共有財産の全域をガバナンスすることができる制度への合意ではないのか』『環境の保護は、いくら利益が上がるか、という財政的な計算をベースになされるのではない。環境を市場メカニズムのひとつの資産と考えていたら、保護することも、均衡を推進することもできない』。この章で教皇がこだわっていらっしゃることは、政治と企業が『真にインテグラルな発展』を環境にもたらすことができるかどうかを見定めて、正直で透明な決断による発展を促していかなけばならない、ということです。特に、新しいプロジェクトは、どれほど環境に衝撃を与えるかを研究し、『透明な政治と対話』というプロセスを要する一方、透明性なく、対話の義務をおろそかにして曖昧な合意に迎合するプロジェクトこそが、真に環境を破壊する収賄』とされています。特に鋭い部分は、現代を支配する『効率的な速攻性という論理』に逃げる、政治的立場への批判です。 |
||
| 6章 節制と自由 善く、正直であることは価値がある
6章では、『あらゆる変化は、そのための動機と、教育の歩みが必要だ』と、あらゆる教育機関、特に学校、家庭、メディア、カテケーゼ(キリスト教の入門教育をする教理教授)に、環境教育とエコロジカルな霊性について、指導することを、回勅は要請しています。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)