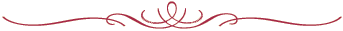
(最新見直し2005.6.12日)
| イタリア政界通信その2 |
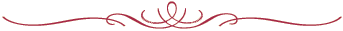
(最新見直し2005.6.12日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「イタリア政界通信その2」を確認しておく。 2005.6.3日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 |
| 2018.4.5日、「『鉛の時代』 イタリアの知の集積 フェルトリネッリ出版と『赤い旅団』の深い関係」。 |
| 2018年3月16日、戦後イタリアの民主主義の構築を根底から覆した、と言われる『アルド・モーロ元首相誘拐・殺害事件』の40年目のメモリアル・デーを迎えました。長い時間をかけ、重要なポジションにいる検事、数々のジャーナリストたち、歴史家たちにより、あらゆる側面から、この大事件の詳細、背景が調べあげられ、もはやどこから手をつけたらいいのか分からないほどの、幾万の情報が積み上げられています。 (この項は、『赤い旅団』誕生の背景 からの続きです。写真はジャンジャコモ・フェルトリネッリとフィデル・カストロ。movieplay.it 、feltrinellieditore.itより引用) さて、1970年に誕生する『赤い旅団』のそれからの経緯を追う前に、その事件を境に、それまでは他の極左武装革命グループとほとんど変わらない評価だった『赤い旅団』(有名ではあっても)を、世界に名を轟かす極悪テロ集団へと変貌させた『アルド・モーロ事件』のメモリアルデーに寄せて、ここで少しだけ、事件の輪郭をまとめてみたいと思います。 |
| 『アルド・モーロ事件』のラビリント、そして終わりなき追求 |
|
現代イタリアにとっての『アルド・モーロ事件』は、まさにゴルゴダの丘、と言っても過言ではないかもしれません。というのもアルド・モーロが最後に書いた、自分の片腕であったキリスト教民主党書記長ザッカニーニに宛てた壮絶な手紙は、マタイによる福音書に描かれた、ゴルゴダの丘のシーンを彷彿とする内容でもあったからです。「あの男(イエス)を十字架にかけよ」と叫び、狂乱する群衆に向かって、総督ピラトは「この人の血について、わたしには責任がない。おまえたちが自分で始末するがよい」と言います。すると群衆全体が「その血の責任は、われわれとわれわれ子孫の上にかかってもよい」とエキセントリックに口々に叫ぶというのが福音書の物語です。アルド・モーロの手紙は、「わたしの血はおまえたち、政党(キリスト教民主党)、そして国の上に降り注ぐだろう」と、悲劇的な予言、呪詛ともいえる言葉で締めくくられていました。敬虔なカトリックの信者であったモーロは、「あの男を十字架にかけよ」と口々に叫ぶ同僚たちの裏切りを聞き、ゴルゴダの丘のすさまじい、そして不条理な殉教ー『パッショーネ』を、おそらく示唆したのだと思います。
この『アルド・モーロ事件』に関して、すべての資料を網羅し理解するには、控えめに言っても数年かかるのではないか、と思われる膨大な情報が残されています。40年の間、オフィシャルな犯行当事者である『赤い旅団』のメンバーたち、犠牲者となった方々の遺族の告発を含め、『モーロ事件』に関する詳細を語る書籍が、とどまることなく出版され、何本も映画が撮影され、ドキュメンタリーが作られ、主要メディアだけでなく、ネット上にも(フェイクも含めて)記事が溢れている。あらゆる背後関係の分析、証拠、考察が、まるでバロック装飾のように隙間なく、細密に積み重ねられながら、しかも日々、増殖し続けているという様相です。当時のイタリア全国民が強烈なショックを受け、深い傷を負いながらも、決して真相が明らかにはならなかった40年前のこの悲劇を、忘れることなく、執拗に追求する司法官、政治家、ジャーナリストたちの姿勢は、現代イタリアに根づく、いわばパルチザンの『レジスタンス』精神の現れとも言えるかもしれない。あるいは、「どんなに時間が経とうとも、イタリアはこの事件を絶対に忘れることはないのだ」という表明を、目には見えない彼方の次元へ向けて発信しているのかもしれません。 1. 外国諸国の関与ーグラディオ。2.『赤い旅団』による国家機構への戦争宣言、クーデターとしての政治テロ。3. 国内軍部諜報と秘密結社ロッジャP2、及びマフィアの関与。緊張作戦。 4. 国内政治権力闘争。 『アルド・モーロ事件』を現代から俯瞰するなら、大きく分けて、以上の4つのアスペクトが見えてきます。そして、膨大な資料から、これらのアスペクトが見え隠れするにも関わらず、「確かに、どうしても解けない謎が数多く存在し、国内外シークレットサービスの痕跡、秘密結社ロッジャP2のメンバーの名前がいたるところに現れて、謎は深まるばかりだが、極左テロリスト『赤い旅団』が犯した政治犯罪であるには間違いない」というのが、主要メディアのオフィシャルな見解です。それはもちろん、当事者である『赤い旅団』のコマンドたちが「わたしたちがやりました」と自白し続け、その証拠も多く残っているからですが、現在は刑期を終え、自由の身となっているその犯行グループの何人かは、今回も主要メディアのメモリアル特集のインタビューに答えていました。そして、彼らの話す『政治テロとしてのアルド・モーロ誘拐・殺害』の物語は、40年前からほぼ同じ内容で、新しい情報が語られることは、何ひとつありませんでした。彼らの背後にイタリア国家中枢、諸外国を含めるあらゆる共謀の可能性が、証言とともに存在するにも関わらず、当事者がすでに亡くなっていたり、嫌疑をかけられた『赤い旅団』以外の人物が起訴され裁判となっても、最終的には『無罪』となっていたりと、真相に近づこうと進められる捜査は、ある瞬間からブラックホールに吸い込まれて、確証がまったく取れなくなってしまいます。そしてそのブラックホールこそが、イタリアの『鉛の時代』のあらゆる事件に共通するリアリティでもある。『アルド・モーロ事件』に関しては、「確かに『赤い旅団』も関わっている可能性があるね」などと、皮肉めいた痛烈な評価をするジャーナリストもいるほどです。 また、次のような尋常でない告白もあります。当時、緊急設置されたヴィミナーレー内務省の危機管理委員会に加わって、『モーロ事件』に関するストラテジーを指揮した米国CIAのシークレット・サーヴィス、スティーブ・ピシェーニックが「わたしがやりました」と、その理由とモーロ元首相殺害に至るまでの状況を、延々と述べるというインタビューが出版されている。77年まで米国の国務長官であったヘンリー・キッシンジャーの片腕だったというこの人物の告白は、しかし腑に落ちない部分もあり、結果、イタリア社会においては、それほど重要で決定的な証言だとは見なされてはいないようです。もちろん、78年の武装グループ『赤い旅団』側から見るならば、当時のイタリア政治の要であり、次期大統領と目されていたアルド・モーロという重要人物を『政治誘拐』することで、55日もの間、共和国全体を恐怖に陥れ、機能不全に陥れた事実は、彼らが狂信したマルクス・レーニン主義思想に基づいて遂行した『武装政治の実現』であり、『クーデター』であり、背後にあらゆる複雑な謀略があろうとなかろうと、『政治』行為であったことは疑いようがありません。国家機構を麻痺させることで、彼らの『極左武装革命戦士』としての矜持は、瞬間的には満たされたであろうと考えます。マルコ・べロッキオ監督の映画、『Buongiorno Notteー夜よ、こんにちわ』は、アルド・モーロが監禁されていたモンタルチーニ通り8番地1Fの名義人、イレギュラーの『赤い旅団』メンバーであった(というのも、彼女は毎日事務所に通う職業を持ち、身元を隠してフルに極秘活動をしていたメンバーたちとは違うため)、アンナ・ラウラ・ブラゲッティ(のち、『アルド・モーロ事件』の中核メンバーのひとりであり、『スーパークラン』としてシミオーニとも強いつながりを示唆されるプロスペロー・ガリナーリと結婚)が書いた告白書『Il prigionieroー囚人』が原作の、『事件』を描いた数々の映画の中でも異色の視点を持つ、珠玉の作品です。ベロッキオは、どこにでもいる、言ってみればテロリストの顔がまったくそぐわない、女性主人公の『思想』と『迷い』、葛藤で揺れ動く心情に、ヒューマンに寄り添いながら『事件』を捉えています。少なくとも女主人公の『革命』は、学生の延長のようで子供っぽく、覚悟なく、国家に戦争をしかけた武装グループとはとうてい思えないものでもある。 実際、彼らのしかけた国家への『クーデター』そのものが、グラディオに利用された茶番と呼べるものかもしれず(彼らが決してそれを認めなくとも)、あの時のアルド・モーロの犠牲が『夢』であったらよかった、モーロが生きて解放されていれば、あのときイタリアは『希望』を失わずに済んだのに、とベロッキオは暗示しているようにわたしには思えます。ラストシーンの、『赤い旅団』の要求を決して受け入れなかったジュリオ・アンドレオッティ、フランチェスコ・コッシーガ、エンリコ・ベルリンゲル、ベッティーノ・クラクシー(唯一モーロ解放に大きな働きを見せた)をはじめとする当時の政府議会の面々、さらには教皇が醸すものものしい『現実』に、この映画の意図である「イタリアの悲劇」が集約されているのかもしれません。第二次世界大戦の枢軸国であり、敗戦ののち、戦勝各国から、常に政治、経済をコントロールされ続けた戦後のイタリアは、冷戦下の40年前、イタリア共産党と連立組閣することで、そのコントロールを突き破ろうとしたアルド・モーロ元首相の死とともに、ひょっとしたら訪れていたかもしれない『新しいイタリア共和国の未来』をも失った。イタリアの戦後は『アルド・モーロ事件』を境に、キリスト教民主党が第1党として長期政権を維持した、第一イタリア共和国の終焉を迎えることになりました。そういうわけで、3月16日のメモリアルデーを迎え、『アルド・モーロ事件』に少し触れましたが、『赤い旅団』の経緯を追うこの項では、まだまだその詳細までには到達しません。アルド・モーロ事件に関しては、机の上に積んだままの新刊を、少なくとも何冊か読んでから、詳細を追って行きたい所存です。そこで、ここではまず、『赤い旅団』が結成された70年まで再び遡り、いまや、イタリアの都市には必ずいくつかある大型書店チェーン、フェルトリネッリ出版の創立者、ジャンジャコモ・フェルトリネッリと『赤い旅団』の深い関係、『赤い旅団』のそれからの変化を追ってみようと思います。ジャンジャコモ・フェルトリネッリというイタリアでも指折りの富豪の家族を出自とするこの人物は、出版界においては時代が生んだ天才であり、と同時に情熱に満ちた『革命家』でもありました。 ※なお、この項では主に、70〜72年代の、時代を反映するイタリア映画のクリップを記事の間に挟んでいこうと思います。 |
| クラシックな共産主義者『赤い旅団』と、100リラ硬貨でデザインされた、いびつな形の五芒星 |
|
「CIAのスパイかもしれない」と件のコラード・シミオーニと決別し、CPM( Colletivo politico metropolitano)
を解散してレナート・クルチョ、マラ・カゴール、アルベルト・フランチェスキーニ、さらにはシット・シーメンス(大手通信会社)、ピレッリの工場労働者たちが共闘で、『プロレタリアートによる専制』を実現する革命戦士集団として、『赤い旅団』を創立したのは1970年のことでした。いったん『赤い旅団』の前身となったCPMから姿を消し、71年あたりに『赤い旅団』に舞い戻ってきたマリオ・モレッティ(78年の『アルド・モーロ事件』の主犯)をインタビューした『Una
Storia Italiana イタリアのひとつの物語(1994)』を編集したのは、創刊時のマニフェスト紙の主幹、ロッサーナ・ロッサンダという、現在も健在のカリスマ的な女性ジャーナリストですが、彼女は『赤い旅団』、さらに当時のイタリアの極左運動について興味深い分析を残しています。『赤い旅団』が、たとえばドイツ赤軍RAF、南米の革命グループやパレスティナ解放機構PLOと明らかに違うのは、それが60年代前半から続く、工場労働者たちの大きな抗議運動の波のうねりと同時に生まれた極左グループであるということ。『赤い旅団』は、ドイツやその他の国では見られなかった『労働者』というエレメントを持つグループだ、とロッサンダは言います。そういえば、確かにイタリアでは、いまでもOperaio(オペライオ)ー工場労働者は社会の『聖域』であり、工場で事故が起こるようなことがあれば、大問題に発展する。また、2018年、今年の選挙の『5つ星運動』の大躍進は、彼らを初期から支えてきたネットユーザーや若きインテリだけではなく、Operaio(オペライオ)ー現代では、工場だけでなく、あらゆる職種の人々ですがー労働者層の票を多く獲得したことが、大勝へ結びつきました。
現在も主要紙の左派の一角をなす新聞、マニフェスト紙(Il Manifesto)は、そもそもイタリア共産党の煮え切らない姿勢を激しく批判した、ヴァレンティーノ・パルラート、ロッサーナ・ロッサンダらが共産党を脱退したのち、1969年に創立した極左グループが刊行する新聞を起源としています。思想的には『赤い旅団』ともほとんど距離のない極左に位置し、したがってロッサンダは『赤い旅団』をイタリアの左翼政治のひとつの歴史だと捉え、工場労働者の抗議運動の、いわば『希望』のなかで生まれた、イタリア共産党の協調ストラテジーとは一線を画すムーブメントであった、という評価をしている。またロッサンダは、68年あたりに形成された学生ープロレタリアートという共闘に由来を持つ『赤い旅団』を「クラシック」な「労働者」を核とした「共産主義者」たち、つまり真性の共産主義とも定義しています。当時のイタリアのマルクスーレーニン主義者たちは、工場を闘いの場として偏愛し、外部で起きるアヴァンギャルドなコンセプトには反対、政党や労働組合の一部として機能するよりは、自由気ままで自発的な闘いを自ら管理、自己完結するアウトノミーな活動を選んでいたのです。
さらに、アルベルト・フランチェスキーニもまた、『赤い旅団』は、何もない『無』から国際諜報たちが作り上げた集団などではなく、イタリアの長い左翼政治の歴史に根を持つ、ひとつの果実であるとも断言している。時代の背後で国内外のシークレット・サービスが暗躍し、結果、『赤い旅団』が謀略に巻き込まれたことより何より、「最大の問題はイタリアの左翼政治の軟弱さと、イタリア共産党が犯した過ちだ。CIAだけに罪をなすりつけるのは簡単なことだ。KGBにべったりだったイタリア共産党もまた、好き放題に『赤い旅団』を利用した。問題はイタリアの左翼政治そのものだった」、と糾弾しています。実際、イタリア共産党は『赤い旅団』のメンバーすら知らなかった『赤い旅団』そのものの特殊な動きを、実は全て把握していた、とも言われている。いずれにしても『赤い旅団』と思想的に共鳴するロッサンダは、イタリアの極左運動に関して、グラディオは過大評価されすぎている、労働者の権力への闘い、レジスタンスは起こるべくして起こったのだ、と考えているようです。レナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニ、マラ・カゴールたちが『赤い旅団』を正式に創立したのは、イタリアが、それから10年以上に渡って続く『鉛の時代』に突入した年で、各地では大規模抗議集会が開かれ、数々の衝突が起こり、次々に爆弾が炸裂していた時代です。レッジョ・カラブリアでは、軍部が出動するほどの労働者たちの大規模な抗議活動で死亡者も出る騒乱となり、イタリア中から多くの労働者たちが、続々と加勢に集まった。また、ジョイア・タウロでは、列車が (犯人は極右テログループとされる)爆破され、6人が死亡、70人が重軽傷を追う大事故となっています。さらにはレッジョ・カラブリアの騒乱の際の軍部の挑発行為の証拠書類を輸送していたアナーキスト6人が、原因不明の事故で亡くなるなど、毎日のように大事件が起こり社会の緊張が高まるなか、青年たちが「決起するのは今しかない」と、興奮状態に陥ったことは容易に想像できます。青年たちはグループを結成すると、ファシスト政権への激しいレジスタンスでイタリア共和国建国に貢献した、尊敬する『ガリバルディ旅団』からその名を借り、自分たちの武装革命グループに『赤い旅団』と命名。「革命家は、あれこれ無駄なことを考えてはいけない。必要な物をリュックサックひとつにまとめ動くのがパーフェクトな革命家」というチェ・ゲバラの信条をそのまま模倣して、生活必需品をリュックひとつにまとめて素早く行動する、という生活をはじめています。その後、『赤い旅団』の存在をシンボライズすることになった、いびつな形の五芒星は、ヴェトコンやティパモラス(ウルグアイ)の『レジスタンス』のシンボルをメタフォライズ。100リラ硬貨を使って、クルチョとフランチェスキーニがデザインしています。何度やり直してもいびつになってしまうので、正確な五芒星をデザインすることを途中で諦めて「これでいいだろう」と、不規則な形のままシンボルマークにすることに決めたのだそうですが、青年ふたりが気楽な気持ちでデザインしたその五芒星が、のちに人々を恐怖と絶望の淵に陥れることになるわけです。また、本格的なClandestino(クランデスティーノ:正体、居場所を隠して秘密裏に行動)として活動するため、犯罪組織から偽の身分証明書を調達、シット・シーメンス、ミラノのピレッリや、トリノのランチアやフィアットの工場に多くの仲間を持つというシステムを作り上げました。この頃の『赤い旅団』には100人近いメンバーがいて、さらに、そのメンバーそれぞれが10人から15人のグループを持っていたため、1000人から1500人ほどの『旅団』共鳴者がいたと言われます。資金集めは、パルチザン以来の伝統に従って「強盗」で稼ぎ、アクションに必要な爆薬、ペンキ、シンナー、ニトロなどは、全て街の薬局で揃えていたのだそうです。そんな風に、どことなく素人っぽくはじまった『赤い旅団』ですが、はじめて起こした行動は、ピレッリの工場で8つのダイナマイトを爆発させ、8台のトラックを一度に放火するというものでした。そしてこの、当時としては仲間内の度肝を抜く派手なアクションに、他の極左グループやメディアが一気に注目し、武装グループ『赤い旅団』初のプロパガンダとしては大成功しています。「その頃、自分たちよりも、カリスマ的なリーダーを持つ、もっと暴力的な極左グループがいたが、彼らはコミュニケーションが下手だった。僕らの名前が一気に有名になったのは、マーケティングがうまかったからだ」と、フランチェスキーニは語っている。実際、その放火事件の成功をきっかけに『赤い旅団』は一躍革命シーンへと躍り出ています。 その後の長い間、アクションとともに発表されるいびつな五芒星をロゴにした声明文のビラ、さらに、この時期クランデスティーノ(身元を隠して行動)の武装革命グループは『赤い旅団』だけでもあり、そのミステリアスな存在感もインパクトとなりました。 |
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 | ||
| 2018.7.18日、「『鉛の時代』国家の心臓部へとターゲットを変えた『赤い旅団』と謀略のメカニズム」。 | ||
| 現在、イタリアが置かれた政治状況から、共産党の大躍進と共に生まれた70年代『鉛の時代』の騒乱を俯瞰すると、感慨深い気持ちになります。もちろん思想、インターネットを含む情報環境や時代背景などはまったく異なりますが、昔『共産党』、今『5つ星運動』と市民が一丸となり、既存の政治にNOを突きつけるという有り様は、大戦中のアンチファシスト・パルチザンを経て60~70年代に育まれ、現在に至るまでイタリア市民に根づく『反骨精神』とも言える。ああ言えば必ずこう言う、権力への服従にはほど遠い、この『予定不調和』こそが特筆すべきイタリアの精神性のひとつです。
※この項は▷『赤い旅団』の誕生、▷フェルトリネッリと『赤い旅団』の続きです (タイトルの写真はDiacronimotiveから引用。「子供たち、反乱を起こそうじゃないか」Milano, anno incerto tra il 1966 e il 1976 © Tano D’Amico)。 そういえば、当時はまだまだ脇役ながら、それでもいつの間にか『鉛の時代』を跳梁しはじめていたベルルスコーニ元首相は、『5つ星運動』の大躍進を「彼らはまるでプロレタリアートみたい」と、かつてのイタリア共産党の有り様を彷彿としている様子でした。 現在の『同盟』と『5つ星運動』の連帯によるイタリア契約政府の、盛りだくさんの市民優遇政策が成立するかしないかはともかく、普通に日常を暮らしていると、巷に流れる空気が少し緊張して、対立の兆しが膨らんでいることは肌感覚で実感できます。『5つ星運動』のディ・マイオ副首相は、大勝した選挙後ただちに「イタリア第3共和国のはじまり」と宣言しましたが、それは未来の歴史家たちが判断することでもあり、わたし個人としては『同盟』色があまりに濃い、ありきたりで古色蒼然とした『極右』政府になってしまうのでは、と危惧するのが正直なところです。いずれにしてもここに来て、『同盟』が『北部同盟』だった時代の4800万ユーロ(!)の使途不明金の存在が暴かれ、検察の調査が入るというスキャンダルが起こりました。また最近になって、遭難しかけていた難民の人々を助けたアイルランド軍の船が、大きな騒ぎもなくメッシーナに着港したことで「それが他国の軍用船であってもイタリアは全ての港を閉ざす。欧州連合に掛け合う」と声高に連呼するマテオ・サルヴィーニに、「それは防衛省、外務省の仕事で、内務省の仕事じゃない」とエリザベッタ・トレンタ防衛大臣が真っ向から異を唱えています。 |
||
| さらに警備の途中、難民の人々を助けたイタリアの沿岸警備隊のシチリアへの着岸を、サルヴィーニが阻止しようとしたところに、マッタレッラ大統領が介入して実現した、という出来事もあった。そういうわけで、多少勢いを削がれる形となったサルヴィーニを巡るイタリアの政局の今後は、いずれ別項で追って行くことになるかもしれません。
さてこの項は、現在から振り返ってイタリアがいまだ「第1共和国」と呼ばれ、キリスト教民主党が戦後の政権を独占しながらも、イタリア共産党が与党に肉薄する勢いで支持を伸ばした70年代に再び遡ります。
大戦直後から米英仏、イスラエルなどの国と密な連携を結ぶイタリア軍部諜報機関( SIFAR、SID)により、時間をかけて周到に、複雑に張り巡らされた、共産主義侵略に対抗する「オーソドックスでなく」「伝統的でない」戦争のための謀略『グラディオ(諸刃の剣)ーステイ・ビハインド』の一環として、イタリアが「 Strategia della tensione – 緊張作戦」下におかれ、混乱し、激動した流血の時代です。街角では極右、極左グループが仕掛けた爆弾が炸裂し、権利を主張する工場労働者、学生、アーティストたちが毎日のように当局と激しく衝突。一種の市民戦争とも言える紛争が繰り広げられた。 現代から振り返れば、トニ・ネグリなど国際レベルで影響を与える多くの知識人、また、現代のイタリアメディアを担う優秀なジャーナリストたちを生んだ極左運動ですが、その一角でありながら「国の未来を変えた」と言われるほどの影響力を持つに至り、イタリア中を恐怖と悲しみに突き落とした欧州最大の極左武装集団『赤い旅団』の変遷、そして背景に見え隠れする多くの謎を再び追いながら、時代を追体験していこうと思います。 イタリアの現代の政治、文化の有り様、精神性、そして風俗は、この時代を知らなければ掴めないようにも思っています。 |
||
| 68年のムーブメントとアルド・モーロ | ||
| 前項の続きに行く前に、ほんの少しだけもう一度、68年あたりまで遡ります。イタリアにおける極左グループ台頭の顕著な動きは、世界を席巻した大がかりなムーブメントが飛び火した『フランスの5月』より少し前にはじまり、その運動の中核を担った若者たちが、70年を代表する主人公となっていったという経緯は前述の通りです。また、イタリアの極左ムーブメントにおいて特筆すべきは、マルクス・レーニン主義の知識人、学生たちだけではなく、労働組合、大勢の工場労働者、農民たちが『革命』の主人公として躍り出たことでしょう。つまり階級闘争におけるプロレタリアートの台頭という、伝統的共産主義のあり方を当時のイタリアの極左運動は踏襲しています。 それから40年を経た今年は、イタリア現代社会の民主主義の基盤ともなるそのムーブメントの深層に迫り、分析、考察する書籍が驚くほどたくさん出版され、主要新聞各社も特集を組みました。時代の核を担った革命家、ジャンジャコモ・フェルトリネッリが基礎を築いたイタリア大型書店チェーン『フェルトリネッリ』をはじめ、たいていの一般書店では『68年』コーナーが設けられ、新刊がズラリと並んでいます。68年は、イタリアにとって、それほど大切な変換期となった1年であったということです。 ところで68年は、イタリア共産党が総選挙で躍進を遂げ、戦後単独与党であったキリスト教民主党に、大きな危機感をもたらした年でもあります。もちろんイタリア共産党は1943年から存在する伝統ある政党ですが、60年代からは選挙のたびに市民の支持を集めてエネルギッシュな躍進を遂げる新しい勢力となった。その新勢力と融和を計ろうと、67年あたりから動きはじめたのが、キリスト教民主党の『頭脳』と言われたアルド・モーロです。モーロは2度の首相を含む、閣僚経験が豊富な人望の厚い人物でしたが、その10年後の78年、『赤い旅団』+αの犯行により『元首相アルド・モーロ誘拐、殺人事件』の犠牲者になってしまいます。 いずれにしても67、68年の、この「イタリア共産党との対話」というモーロの方向転換の背景には、ローマ・カトリック教会の方針の変化がある、と考えられています。60年代のローマ教皇であったジョバンニ23世、また78年まで続くパオロ6世のもと「より大衆的で開かれた、時代が要求するカトリック世界」というヴィジョンをカトリック教会は打ち出し、教会のその変化にキリスト教民主党が従っていくことになった。モーロは「時代とともに世の中に生まれた課題に、緊急に対処するために政府は動かなければならない」と強く党内に働きかけました。 | ||
| まず、モーロが的を絞ったのは、「新しい形の資本主義」「現代的ダイナミズムの構築」「新しい形の社会」を創生することでした。イタリア共産党との対話こそが、イタリア社会において最重要だとモーロは考えていましたが、この『中道左派』的なモーロの態度は、キリスト教民主党の中で大きな亀裂を生んでいます。 余談ですが、モーロのこのイタリア共産党への接近は「Strategia dell’attenzione (配慮作戦)』と呼ばれます。この言葉の並びと音感から、すぐに連想するのは、グラディオにおけるイタリア撹乱作戦、「Strategia della tensione (緊張作戦)」。グラディオの存在を当然知っていたであろうアルド・モーロの作為的な命名、一種の牽制だったのかもしれません。 モーロの柔軟なアプローチが、『武装革命の魂』を内に秘めながら躍進し続けるイタリア共産党の強行姿勢を、やがて軟化させることになったわけですが、前項にも書いたように、イタリア共産党の武装の放棄、与党との融和姿勢への方向変換が、パルチザンを含む、すべての伝統的マルクス・レーニン主義者たちを激怒させることになった。彼らはいつか共産党が労働階級を率いて武装革命を繰り広げ、プロレタリアートによる専制を実現するのだ、と夢見ていました。 ともあれ、それから40年後のいま、思想もプラットフォームも主張もまったく違っても (イタリア共産党は途中、思想の方向転換をしたとしても、マルクス・レーニン主義は本来、民主主義を容認しないわけですし)、主な労働組合層が支持する『5つ星運動』という、直接民主主義による平和革命を謳うオンライン市民運動が、悲願であった政権の一端を担う、という現象が起こったことは興味深いことです。 | ||
| フェルトリネッリを失ったのちの『赤い旅団』 | ||
| イタリアにとっては忌わしい、血塗られた時代の思い出が刻み込まれた、『赤い旅団』という極左武装集団の動きを追って行くことで、世界には、普通の日常を送るわれわれが「預かり知ることができない、そして直接的には一生関わることもないであろう」秘密の謀略の存在があることが、何となくぼんやりと浮き上がってきます。と同時に、そのオペレーションの複雑なメカニズムにも光が当たる。それはもちろん、イタリアの多くの司法官、ジャーナリスト、政治家や学者たちが長い時間をかけて書類を調べあげ、多数の容疑者の公判記録を綿密に照らし合わせながら、執拗に追ってきたからに他なりません。そして少しづつ、内容が明らかになるにつれ、このような謀略は、イタリアの『鉛の時代』だけに限定される特殊なオペレーションだとは一概に言えないのではないだろうか、という感想を持ちます。
もちろんわたしは、あらゆるタイプのテロ集団が謀略で操られている、とはまったく考えていませんし、『赤い旅団』は冷戦下、東西謀略合戦における格好の前線部隊として利用された特殊な例ではあるだろう、と思います。しかしながら時代が変わり、状況が変わり、情報のあり方が大きく変化したことで、工作のテクニックや潜入のタイプが変わっても、混乱のある国、地域には、権益が絡む勢力の工作が施される可能性がおおいにあるのではないか。出来すぎたストーリーは、まず疑うのが常識ではないだろうか、とイタリアの近代史を知るうちに考えるようになったことをも告白しておきたいと思います。
とはいえネットに蔓延する、科学的な調査なく、根拠も証拠もまったく提示されない、誰の利益になるのかわからないような陰謀論には、ちょっと辟易もしています。何らかの謀略を語るのであれば、やはり確固とした証拠が必要になる。いまだに謎に包まれる部分が多くあるにしても、『鉛の時代』に関するリサーチのように、何百人という司法官、ジャーナリスト、政治家が挑んだ『芸術的なパノラマ』とでも表現できるような緻密なリサーチ、証言、証拠の集積を、注意深くアナライズ、結論を導こうとする試みが必要なのではないでしょうか。さて、それはさておき、本題を追っていくことにします。
前項でも書いたように、『赤い旅団』の場合には、結成される以前から、元イタリア社会党員であったコラード・シミオーニという謎に満ちた人物がメンバーたちを懐柔していた、という経緯があります。シミオーニは『赤い旅団』がいまだその名を持たない68~69年、『ジエ・ロッセ(赤いおばさんたちー女性による精鋭武装集団)』『ラ・ディッタ』『スーパークラン』と名づけられた秘密精鋭武装グループを、選り抜きのメンバーたちから構成していた。 後述しますが、この『スーパークラン』のメンバーの一部(ヴァンニ・ムリナリス、ドゥーチョ・ベリオ、フランソワ・トゥッシャーなど)が、76年にシミオーニとともにパリへ渡り、74〜75年以降の後期『赤い旅団』の真の黒幕と考えられるパリの語学学校『ヒペリオン』を創設している。また、イタリアに残り、後期『赤い旅団』の執行幹部として『モーロ事件』の主犯となった、マリオ・モレッティ、プロスペロー・ガリナーリもまた『スーパークラン』のメンバーでした。 この項は、70年初頭に「やつはきっとCIAに違いない」とコラード・シミオーニと決別し、自分たちだけで『赤い旅団』を創設した初期の執行部、レナート・クルチョ、マラ・カゴール、アルベルト・フランチェスキーニの同志、経済的支援者であるとともに精神的支柱であった大富豪の革命家、ジャンジャコモ・フェルトリネッリを突然失うことになった『赤い旅団』の、72年以降を追っていこうと思います。 ジョヴァンニ・ファサネッラによるアルベルト・フランチェスキーニのインタビュー『赤い旅団とはなんだったのか』(BUR)、ロッサーナ・ロッサンダ、カルラ・モスカによるインタビュー『赤い旅団ーマリオ・モレッティ ひとつのイタリアの物語』(Oscar Storia 改訂版)、シルヴァーノ・デ・プロスポ、ロザリオ・プリオリ共著の『誰が赤い旅団を操っていたのか』(Ponte Alle Grazie)、セルジォ・ザヴォリ『共和国の夜』(Oscar Mondadori)を軸に、過去の新聞記事、信頼できるネット上の情報、ドキュメンタリー、ウイキペディアなどを参考に時代を遡ります。 この項では途中、その年にイタリアで流行った国内外の曲の動画をリンクすることにしました。また、文末にはBBC1992年制作の『グラディオ』に関するドキュメンタリーをリンクしています。 |
||
| 歯車が狂いはじめた1972年 | ||
| フェルトリネッリを失った72年は、『赤い旅団』にとって非常にデリケートな、彼らを巡る環境が一変した年です。フェルトリネッリの死とともに、革命家たちは方向性を見失い、海外の社会主義国、革命グループとのコンタクトをも失うことになりました。 一方このころから、『赤い旅団』は極左武装グループ『Potere Operaio – 労働者の力』のメンター、トニ・ネグリとも密に交流するようになり、理論構築を協力しあうようになっています。トニ・ネグリは『赤い旅団』の思想形成に影響を与えたと糾弾され、のち有罪判決を受けましたが、イタリアの『人権の父』、急進党のマルコ・パンネッラの援助に支えられ、ドラマティックな展開を経てフランスに亡命。その後イタリアに戻って受刑し、現在も活躍しています。 なお、前述したように72年には、シット・シーメンスのディレクター、イダルゴ・マッキアリーニの数時間の誘拐によるプロパガンダ成功ののち、マリオ・モレッティが初期執行幹部レナート・クルチョ、アルベルト・フランチェスキーニと同格のリーダーに昇格している。もちろんこの時は、クルチョもフランチェスキーニも、モレッティがシミオーニと密に通じている、とは考えてもいませんでした。しかしフランチェスキーニが、自分たちの周囲を巡る何かがおかしい、と感じはじめたのも72年のことでした。「総選挙」を控えたその頃、『赤い旅団』ではフランチェスキーニが核となり、キリスト教民主党右派であるマッシモ・デ・カロリスを誘拐、選挙を混乱させようと計画し、人質を監禁する家(彼らが「人民刑務所』と呼ぶ)もすでに借りて準備万端だった。ところが誘拐を計画した日の1週間前、デ・カロリスは忽然と行方がわからなくなってしまいました。そうこうするうちに、『フォンターナ広場爆破事件』、『フェルトリネッリ事件』を捜査していたルイジ・カラブレージ警部が自宅付近で射殺される、という事件が起こり、極左グループに一斉の捜査が入ります。そのときに逮捕されたマルコ・ピセッタは、そもそもフェルトリネッリの死後、GAPから『赤い旅団』へと流れてきた、マリオ・モレッティの大きな信頼を得る青年だったそうです。そのピセッタは、逮捕された瞬間からまったく抵抗することなく、あらゆるすべての経緯を白状、即刻警察の協力者として働きはじめた。『赤い旅団』のメンバーたちは、ピセッタはおそらくGAP時代から軍部諜報SIDの協力者として紛れ込んでいたスパイだったのでは?と考え、情報が事前に漏れ、デ・カロリスが誘拐計画を知って姿をくらましたのだろうと推測しました。さらにのち、デ・カロリスは秘密結社ロッジャP2のメンバーだったことが明らかになっています。 | ||
| モレッティもまた、この捜査の際、異様な動きを見せている。一斉捜査が入ったデ・カロリスを監禁する予定の家の付近まで、モレッティは自身のパートナーが所有するフィアット500で乗りつけましたが、警察が群がっているのを見ると、何故か車を付近に駐車して、歩いてその場を立ち去っています。のち、そのパートナーの車から住所が割り出され、モレッティ家族 (ちいさい息子も含め)が住んでいたのは、『フォンターナ広場爆破事件』の捜査責任者であるミラノ警察署長、アントニオ・アレーグラが自宅を構える通りだということが判明しました。この経緯から当然、車の所有者であるモレッティのパートナーは取り調べを受けましたが、モレッティ自身は20日間ほど行方が分からなくなったのちに、逮捕されることもなく再び『旅団』に舞い戻っている。もちろん、ミラノ警察署長と同じ通りに家族で住んでいた、ということだけで、モレッティという人物の背景を疑うのは行き過ぎた推測ではありますが、モレッティが住所に選ぶところ、あるいはモレッティの関係者が住む場所の近所には、必ずと言っていいほど、軍部諜報の有力者や、警察関係者が住んでいるのは不思議なことです。その事実についてはその都度、後述していくつもりです。しかもこの一斉捜査の際、モレッティが他のメンバーたちから処分を依頼されていたはずのクルチョの写真(身分証明書偽造のための)や、マッキオリーニ誘拐の際の写真(ピストルを頬に突きつけた)など、絶対的な証拠がアジトから見つかり、モレッティは「馬鹿かスパイかのどちらかだ」とメンバーから一斉に非難されます。しかしモレッティは「間違った」「不注意だった」と繰り返すだけでした。この件に関してモレッティは、パートナーの車が見つかったことで、ふたりの関係に大きな溝が生まれ、逮捕されるまでの何年もの間、息子にも会えず辛かった、とだけしか語っていません。いずれにしてもこの一件を機に、それまで家族と暮らしていたモレッティは、完全にClandestino( クランデスティーノ・身分を明らかにせず、非合法で活動)に突入します。さらにこの一斉捜査で逮捕されたマルコ・ピセッタは『赤い旅団』メンバーの詳細を知っていたので、この青年がすべて話せば、全員逮捕以外にありえない、とメンバーの間に危機感が満ち、色めきたちました。しかし結果としては執行部の重要メンバーが逮捕されることはなかった。もしこの時点でメンバー全員が逮捕されていたならば、『赤い旅団』は完全に消滅していたはずです。この件についてフランチェスキーニは、『赤い旅団』の共感者であった裁判官(デ・ヴィンチェンツォ)に「保護されていたように感じる」と述懐しています。なお、ミラノ警察署長アントニオ・アレーグラは「スーパークラン」の存在をすでに知っていた、ということが、のちに明らかになったそうです。 | ||
| ☆ペテアーノ・カラビニエリ爆破事件 | ||
| 72年5月31日、カラブレージ警部が殺害された2週間後(極左グループLotta continuaー『継続する闘争』の幹部アドリアーノ・ソフリらが主犯として逮捕され、無罪を主張しながら長期懲役となるが、真相は明らかにはなっていない。現在は出所)には、のちに『鉛の時代』の背景を検察が知る決め手となる『ペテアーノ・カラビニエリ爆破虐殺事件』が起こっています。これは極右グループが、北イタリア、サラガードの田舎道にカラビニエリを電話で呼び出し、カラビニエリ5人が急行したところで、駐車されていたフィアット500が爆発。3人が爆死、2人が重症を負うという凄惨な事件でした。この事件は当初、フォンターナ広場爆破事件同様、国家権力(カラビニエリという軍部)を敵と見なす極左グループの犯行と疑われましたが、捜査が進むうち、Ordine Nuovo (オーディネ・ヌオヴォーネオファシスト・テログループ)のメンバー、ヴィンツェンツォ・ヴィンチグエッラ、カルロ・チクッティーニによる犯行ということが明らかになりました。ペテアーノ事件は、フォンターナ広場からはじまる一連の極右グループによる虐殺事件で唯一、実行犯に『終身刑』という実刑判決が下った事件です。というのも、実行犯として逮捕された「極右革命闘士」ヴィンチェンツォ・ヴィンチグエッラが、1984年のボローニャ検察による取り調べで、フォンターナ広場爆破事件からボローニャ駅爆破事件まで、10年という歳月に渡る大規模爆破事件及び殺人事件の背景に、『極右テログループーOrdine Nuovo』が関わっていること、さらにCIA、NATOに、イタリア軍部諜報SIFAR、SIDというイタリア国家の中枢が関わる『緊張作戦』の一環であったことの詳細を暴露しているからです。 さらに、ペテアーノにおける爆破事件を含み、多くの無辜のイタリア市民を巻き込んだ爆破事件には、NATOがグラディオの作戦実行のために隠していた極秘武器倉庫NASCO の武器が使われたことが、のちの捜査から明らかになっています。ペテアーノの爆破事件には、72年に偶然発見されたアウリジーナ(オーストリアとの国境)のNASCOの武器が使われた、と見なされている。NASCOは発見されるまで、北イタリアの139箇所にありましたが、72年に偶然に発見されたのち、急いで撤去されたのだそうです。 | ||
| 「ペテアーノの事件は、突発的に一日で決定されたものではない。69年のフォンターナ広場事件が終了したのち、長い時間をかけて分析されたアクションだ。ネオファシスト世界の価値観と、僕自身の経験が抱合された分析。国家との前線における闘いとして結論づけられるであろう、という分析だ。ペテアーノはひとつのシグナルとなる事件だった」。ヴィンチグエッラはそう語っています。つまりヴィンチグエッラ自身は、国家や諜報の手先としてではなく、純粋に『極右革命闘士』として国家に戦争を仕掛けた、と言っている。ヴィンチグエッラは現在もペテアーノの事件に対して、後悔を表明していません。 このように、72年は次から次に目まぐるしく重大事件が起こったうえ、極右、極左グループのいずれからも犠牲者が出る衝突が覆った年でした。まさに『緊張作戦』の目的通りに、極左の若者たち、工場労働者、極右グループの間に殺気が満ち、その殺気を縫って諜報が蠢き、さらに焦燥感、危機感を煽り立てるアクションを仕掛けていった、というところでしょうか。 | ||
| ☆ミュンヘン・オリンピック『黒い9月』 | ||
| また、この年はイタリア国内だけでなく、海外でも重大なテロが起こった年でした。8月から9月にかけて開催されたミュンヘンオリンピックでは、パレスチナ武装グループ『黒い9月』が選手村に潜入、ユダヤ系米国人選手を含む2人を射殺。9人を人質にとって攻防が繰り広げられ、結果、テログループ、人質全員、さらに警察官が死亡するという惨事が起こりました。この時武装グループがイスラエル刑務所からの解放を要求した受刑者たちの中には、『赤い旅団』と対比され、交流があったと考えられるRAF『ドイツ赤軍』のメンバー、また『日本赤軍』岡本公三の名(ウィキペディア日本語版より)もあったそうです。 この72年頃から、メンバーの数が急激に増え続けた『赤い旅団』は、資金難を解決するために、手当たり次第強盗(パルチザン以来の伝統的資金稼ぎ)をはじめています。また、多くのメンバーがクランディスティーノー非合法活動へ突入、正体を偽装し、アジトとするアパートは借りると足がつくため、すべて購入したのだそうです。トリノのアジトはレナート・クルチョ、マラ・カゴール、ミラノをフランチェスキーニ、モレッティが仕切るようになりました。インタビューを読みながら少し意外に思ったのは、この時『赤い旅団』のメンバーは、給料制 (!)だった、ということでした。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)