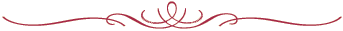
(最新見直し2005.6.12日)
| イタリア政界通信その1 |
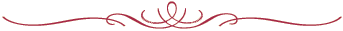
(最新見直し2005.6.12日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「イタリア政界通信その1」を確認しておく。 2005.6.3日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 |
| 2017.9.22日、「『鉛の時代』パソリーニ殺人事件の真相と闇:「唯一」の犯人の死」。 |
| 地中海の明るい太陽輝く、陽気で美しいイタリアには、絶望と悲しみに彩られた深い闇も同時に存在することを、ふいに感じることがある。米国CIAとイタリア国家の一部により、戦後画策された『グラディオ作戦』、『フォンターナ広場爆破事件』からはじまった『緊張作戦』に煽られエスカレートした政争で、イタリアを血の色に染めた『鉛の時代』。ピエール・パオロ・パソリーニの無残な死もまた、確実な証拠は上がらなくとも、『緊張作戦』の一環と捉える人々が多く存在します。その事件の真相を知るであろう、パソリーニ殺人の犯人として、たったひとり刑に服した当時17歳の少年、ジュゼッペ(ピーノ)・ペロージが今年7月20日、59歳でひっそりと病死しました。奇しくもピーノ・ペロージが死亡した日は、近年のローマを揺るがし、市民の『市政』への信頼を完全に失墜させたマフィア・カピターレの容疑者たちの判決の日でもありました。マフィア・カピターレは犯罪組織とローマ市職員、政治家たちの共犯で、市民の税金である莫大な市の予算を食い物にしていた大収賄事件。そのマフィア・カピターレの主人公、マッシモ・カルミナーティは、『鉛の時代』の真っ盛り、70年代後半にメキメキと頭角を現したローマのローカル犯罪集団、Banda della Magliana(バンダ・デッラ・マリアーナ)の主要メンバーであり、かつ極右グループNARの構成員でした。象徴的に言うならば、ピーノ・ペロージにしても、カルミナーティにしても、『鉛の時代』のバイオレンスな空気を、そのまま現代に継承した人物と言えるかもしれない。『鉛の時代』の残影が、こうして時々イタリアの、40年以上経った現代に、ぞろりと浮き上がって、人々をあの時代に引き戻す瞬間があります。いや、マフィア関係のニュースなどを読むうちに、緻密に計算された非道、そのやり口の周到さに「表向きは『毎日カオスな政治祭り』でも、イタリアの政治、社会、そして経済を管理しているのは、実は戦後から『鉛の時代』までに綿密に組織化され、暗躍し続ける地下犯罪ネットワークに密かに循環するブラック・マネーなのではないのだろうか」と、疑いも湧くほどです。『カモッラ』、『ンドゥランゲタ』、『コーザ・ノストラ』・・次々にボスと呼ばれる人物たちが暴き出され、捕えられても、決して消え失せることのない犯罪ネットワークが、イタリアには明らかに存在し、ときおり世間を揺るがせます。
さて、詩人、小説家、映画監督、批評家、ジャーナリストとして、イタリアの一時代を駆け抜けたピエール・パオロ・パソリーニが、イタリアの多くの人々にとって『自由と反逆のシンボル』『時代のヴィジョナリー』として絶大な人気を誇る『英雄』とも言える人物であることは以前に投稿しました。しかしながら、『英雄』であると同時に、その強烈な生きざまと個性、背徳的な重いイメージを、今でも憎悪する人々が存在するのも事実です。53歳という若さで、猟奇的な殺人事件に巻き込まれ、この世を去って42年、この、偉大な詩人の死を巡る真相は明確にならないまま、さまざまな憶測が今日まで語り続けられてきた。おそらくパソリーニ殺人事件の真相を知る、数少ない人物のひとりであろうピーノ・ペロージの死が報道されたその日、各メディアは再び、パソリーニ殺人事件の真相の謎に迫りました。実際、この詩人の死の背景を調べるほどに、Doppio stato(二重国家)と呼ばれた国家中枢の一部を含む、当時のイタリアの闇に蠢いた、極秘ネットワークの片鱗が浮き上がるのは確かです。パソリーニ殺人事件の真相を探ることで、『鉛の時代』を構成した権力システムの全体像と精神性を、なんとなく俯瞰できる、と言っても過言ではないかもしれません。パソリーニについては、小説『パッショーネ』のみならず、このサイトでも何度か触れているので、いくつかの重要と思われるエピソードを除いて、ここではなるべく重複しないようにするつもりでしたが、随所を省略すると、脈絡がなくなるため、結果、網羅せざるを得なくなりました。また、できるだけ新しい情報を中心に、パソリーニ殺人事件を巡る隠された真相を探るとともに、ピーノ・ペロージという人物についても、改めて考えてみたいと思います。 |
| 不都合な詩人、P.P.パソリーニと『蛙のピーノ』 |
|
ピーノ・ペロージは、パソリーニ殺人事件における「唯一の」犯人として刑に服した後も、強盗や、ドラッグの売買、窃盗などの罪で、娑婆と刑務所を行き来、人生の約半分である26年を刑務所で過ごしたという、結局最期まで、犯罪社会から足を洗うことができなかった人物です。そのペロージが、パソリーニの殺害からちょうど30年が経った2005年、突如としてイタリア国営TV、Raiに出演、まことしやかに「あの夜」の真相を語り、自身の『無実』を強く訴え、物議を醸した。それ以降、ペロージは、合間合間にちょっとした犯罪を繰り返しながらも、弁護士や協力者に支えられ、自叙伝風告白本を出版したり、ドキュメンタリーフイルムに出演したり、新聞のインタビューに応えたり、と、ことあるごとにメディアに露出しはじめる。また、いまや5つ星運動のリーダーとして名高いベッペ・グリッロのブログの初期にも、インタビューに応じています。しかし、ネット上に残されているどの動画を見ても、またペロージが書いたと言われる書籍を読んでも、彼がきわめて重大な告白をしているにも関わらず、その『真実』は、どこか風のようで掴みどころなく、詳細の記述も二転三転、核心と思われる質問には、うまくはぐらかして決して明確に答えていない。わたし自身は、彼の言葉を部分的に信用しないわけではなくとも、その告白を聞きながら、何かうしろ暗い印象を常に抱いていた、と言うのが正直なところです。彼はかつて、自分に投げつけられた「ユダ」(キリストを裏切った弟子)という言葉に激怒したことがありましたが、出版された自伝的な2冊の本の内容が微妙に異なり、以前告白した内容を「昔のことだから、記憶が曖昧」と言って平然と翻すペロージの印象は、彼が嫌う「ユダ」のイメージに、やはり近いかもしれない。 ピーノ・ペロージは、その正体がどうにもはっきりしないまま、『パソリーニ殺人事件の唯一の犯人』という重い十字架を背負いながら、かつて、ケチな犯罪で小遣い稼ぎをしていた不良少年だった頃からの刑務所仲間と馴れ合う犯罪社会しか、生きる場所がなかった。ペロージには微塵も同情はしませんが、ひょっとすると彼もまた、『鉛の時代』の犠牲者のひとり、『使い捨てられた人間』と言えるかもしれない、とは思います。事件当時、泣き腫らして膨れた瞼のせいで『蛙のピーノ』とメディアに命名されたペロージは、その名を拭うことなく、生涯を終えました。いずれにしても、人間離れしているというか、神がかっているというか、強いカリスマを持つ、詩人パソリーニの残した作品の数々と、その生きざまが、その死から42年を経てもなお、問題を提起し続け、世代を超えるイタリアの人々に影響を与えている事実は驚異的でもある。殺害当時、多くのパソリーニ映画の助監督を務めたベルナルド・ベルトルッチは「イタリアを代表する芸術家を失った」と悲痛に訴えましたが、現在でも「パソリーニの死」が、偶然であれ、作為的であれ、その後のイタリアにおける、真の左翼芸術の息の根を止めた、と評論する人々が多く存在します。また、かのアルベルト・モラヴィアは『本物の詩人は一世紀に数人しか出ないものだ。詩人とはSacro:『聖なるもの』だ」と絞り出すような口調で、パソリーニへの弔いの言葉を残している。そしてパソリーニの作品、人物像に繰り返し触れるうちに、モラヴィアが選んだ、Sacro:『聖なるもの』という言葉の意味が、だんだんに実感できるようにも感じています。パソリーニが生きた時代に比べると、社会の倫理、自由の幅が広がった(パソリーニが、フリウリでの教員時代、ホモセクシャルであるため激しく糾弾され、告訴され、職を奪われ、イタリア共産党のメンバーからも除外された、というようなことは、もはや現代では起こらなくなりました)現代から見ても、詩や小説はともかく、彼のいくつかの映像作品には、凝視を躊躇する問題作があるのも確かです。しかし本来、芸術は『善悪』、『美醜』という価値観、世俗の枠には収まらず、無限の領域、つまり聖域を内包する。また、『聖なるもの』だからこそパソリーニの作品、言論は時空を超越し、イタリアの現代にまで影響し続けているのでしょう。その、聖人パソリーニは、発表した作品の数々、さらに自身の素行により、当時のカトリック教会や市民団体から大きな反発を受け、生涯に33件の訴訟を抱え、100件以上も告訴されています(いずれも無罪となっていますが)。自らにタブーを課すことのなかったこの詩人は、米国CIAがらみの政治案件も含め、権力機構の不都合な真実を次々に暴き出し糾弾、熱狂的な支持を受けると同時に、執拗な攻撃をも受け続けた。賞賛と憎悪が常に騒がしく渦巻く、その極限の緊張状態の中、パソリーニは死の直前まで、止まることなく問題作を発表し続けました。まさにVitalià desperata ー絶望した生命力、活力に溢れた晩年でした。 |
| Ragazzi di Vita (生命ある少年たち) |
| 無名の高校教師だったパソリーニを一躍スターダムにのし上げ、モラヴィアとの知古を得るきっかけとなったのが、映画『アッカトーネ』の原作でもある、小説『Ragazzi di vita ( 生命ある少年たち)』。この表題をそのまま「生命ある少年たち」という日本語にすると、曖昧な感触しか伝わらないのですが、「はらわたで生きる人間そのもの、生命力迸る野生の少年たち」の意、とわたしは解釈しています。小説の主人公たちは、道端にたむろし、盗みや詐欺、ゆすりなどの犯罪と、ちょっとした暴力沙汰で日々を暮らすルンペンプロレタリアート、つまり社会から完全に見放された、しかしそれでも生き抜かざるを得ない少年たちです。パソリーニは、それまで小説のテーマとして、誰からも見向きもされなかった、プロレタリートのさらに下層に位置すると見なされる少年たちの、狡く、卑怯でケチな犯罪とバイオレンスに満ちた貧しい日常をそのまま、慈しむように哀しく、詩的に描き大好評を得、と同時に、早速イタリア国家の内務省から「要注意人物」とマークされています。また生涯、自らの『英雄たち』として愛し、親交を深めた、『Ragazzi di vita』である、道端でたむろする不良少年たちの中から、フランコ・チッティ、セルジォ・チッティ(パソリーニの映画助手から監督へ)、ニネット・ダヴォリという、のちパソリーニ映画の顔となる、多くのスターたちを生み出している。そして『パソリーニ殺人事件』の唯一の殺人犯となったピーノ・ペロージもまた、パソリーニが愛した『Ragazzi di Vita』のひとりであったことは、皮肉な運命というか、あまりにもシナリオめいているかもしれません。一作ごとに社会的影響力を増し、左翼思想のオピニオンリーダーとして不動となった、そのパソリーニが、一目では誰か見分けがつかないほどの酷いダメージを受け、血塗れの轢死体で見つかったのは、1975年、11月2日の早朝。ローマの海岸線の地域オースティアの、ゴミが打ち捨てられ閑散とした荒地、イドロスカーロ:水上機停泊地帯でのことでした。パソリーニの轢死体が見つかったあと、即座に白状したペロージの『自白』は、ちょっとした悪事で小遣い稼ぎをしていたこの少年を誘った、詩人の性的な乱暴のせいで、激しい口論となった挙句、殴り合いの喧嘩に発展。隙を見て車を盗んで逃亡しようと焦った少年に、パソリーニは誤って轢き殺された、というものでした。このペロージの自白から『共産主義の忌まわしい男色野郎』の自業自得、因果応報とでもいうかのごとき侮蔑的な物語が、たちまちのうちにオフィシャルに構成され、当時の人々はそれを真に受け、未だにその説を信じる人々がいるほど強烈な印象となって残っています。古今東西、どういう形であっても『自白』に裏付けられた、マスメディアによる一斉の『真相』の報道は、人々を簡単に欺きます。 |
| 小説『原油』と事件の背景に蠢く『鉛の時代』の役者たち |
|
殺害当時のパソリーニは、大きな問題作となった『サロ、あるいはソドムの120日間』を公開したばかりでした。また、72年から開始した、『Petrolio
: 原油』というタイトルの小説を、未完ではあっても、ノートとしては、ほぼ完成させた時期でもあった。522ページに上るそのノートは、21とナンバリングされた「Lampo
del’Eni:Eniの閃光』の一章だけを除いて、現在そのまま出版されています。そして、そもそも書かれていない(パソリーニの親族はそう主張)、いや、何者かによって密かに盗まれた、と言われる、この21章『Eniの閃光』こそが、パソリーニ殺害の動機となる、当時のイタリアに大きな衝撃を与える重大な真実が書かれていた、との仮説が現在の通説ともなっている。小説『原油』が完成、出版される前に、パソリーニを完全に口封じしようと大きな力が働いたと考える人々が、多く存在します。ではその章にはいったい何が書かれていたというのか。 現在、そのストーリーとして最も有力なのは、1962年に起こった、イタリア主要エネルギー会社、Eniの総裁であり、イタリアの産業界で極めて大きな影響力を持っていた、元パルチザンのエンリコ・マッテイが巻き込まれた、あまりに不自然な飛行機事故、またその事故の異常をきめ細かく調査していたジャーナリスト、マウロ・デ・マウロの失踪を巡る『真実』が調べ上げられ、書き尽くされていた、というものです。エンリコ・マッテイという元パルチザンの人物は、もちろん、良心的なだけではない野心家、策略家でもある人物でしたが、アングロ・アメリカンのエネルギー関係企業が独占する原油業界に風穴を開けるべく、産油国と単独協定を結び、油田を確保、原油価格を一気に推し下げようと画策し、当時、多くの支持を集めていました。マッテイの飛行機墜落事故は、その原油価格破壊の過程の最終段階で起こっている。事故に疑惑を抱き、「飛行機は故意に爆破されたのでは」、とその背景をくまなく探っていたのが、ジャーナリストのマウロ・デ・マウロでした。しかしそのデ・マウロは、マッテイが乗った飛行機墜落事故の調査中、何者かに電話で呼び出され、自宅の玄関を出たまま失踪し2度と戻ることはなかった。当時、マッテイの飛行機墜落事故は、偶発的な事故と結論され、早々に捜査は打ち切られましたが、のちの最新の科学調査による再捜査で、仕掛けられた爆弾による爆破事故であったことが明らかにされています。また、デ・マウロに関しては、別件でのマフィア事件の捜査の途中、デ・マウロを殺害したことを自白した犯人が存在しています。パソリーニは、この飛行機事故の黒幕が、マッテイの死後、Eniの総裁となった、アングロ・サクソン原油勢力と緊密な交流のあったエウジェニオ・チェフィスだった事実まで把握していた、とも言われている。エウジェニオ・チェフィスはフリーメーソンのセクト、秘密結社ロッジャP2のアイデアを出した真の創立者、とほぼ断定されている人物です。もちろん当時は誰ひとり、秘密結社ロッジャP2の存在など、予想もしていなかった時代のことです。ちなみに62年に起こったこの飛行機事故は、その後の『鉛の事件』のあらゆる事件と同様、いまだに真相が確定されず、司法によって誰ひとり、裁かれることはありませんでした。ところで、ごく最近のことですが、盗まれた、いや、書かれていない、と議論され続けるこの21章のノートが、ある日、忽然と姿を現すことになりました。しかも、その出どころはいかにも怪しげな人物の、怪しげなルートからでした。「パソリーニの未完の小説、『原油』の21章を手に入れた」と声高に吹聴したのは、マフィア犯罪組織との緊密な連帯が暴かれ、現在刑務所に収監されている悪名高い政治家であり企業家、ベルルスコーニ元首相の長年の盟友でもあるマルチェッロ・デル・ウトゥリだった。デル・ウトゥリは意気揚々と「自分は確かにそれを読んだ。仰天する事実が書かれていた」と発言し、途端、イタリア中が蜂の巣を突いたような大騒動になりましたが、時間が経つうちに、デル・ウトゥリは口を閉ざし、やがてうやむやに誤魔化しながらフェードアウト、『原油』21章の行方は再び分からなくなった。そうこうするうちに、ベルルスコーニ絡みのマフィア案件で、デル・ウトゥリは逮捕されてしまったという経緯です。なお、マッテイ、デ・マウロ、そしてパソリーニ殺人事件の背景に存在していると囁かれるエウジェニオ・チェフィスが創立したとされる秘密結社ロッジャP2は、軍部諜報幹部、国家機関中枢の人物、さらにはジャーナリスト、裁判官、検察官、企業家と、多様な有力者で緻密なネットワークを構成し、『鉛の時代』の事件のほぼ全ての要所にメンバーの名前が挙がります。後述しますが、パソリーニ殺人事件の背景にも、やはりP2メンバーの名が、なにげなく、ふっと現れ驚くことになりました。痩せてはいても、鍛錬を積んだ屈強なスポーツマンでもあったパソリーニの、その血塗れの亡骸に刻まれていた極端なダメージから、171cmのひ弱で華奢な少年による単独犯行と考えるには、最初から無理があった。しかも車の窃盗で逮捕された時、ペロージはパソリーニ殺害直後だったはずなのに、返り血を一滴も浴びていませんでした。さらに、供述が途中で次々と変化して、全く確証が掴めない、などペロージの単独犯説には多くの疑惑が残されたままでしたが、4年間続いた裁判を経て、ピーノ・ペロージのみが有罪の判決を受けることになった。このパソリーニの死を巡る謎はマルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督、95年のドキュフィルム『パソリーニ・イタリアの殺人』をはじめ、数かぎりないドキュメンタリー、テレビ番組、書籍となり、現在も途絶えることなく、毎年続々と新作が発表されています。 |
| ジプシー・ジョニーから贈られたU.S.ARMYの指輪 |
|
ではここで、事件の経過を簡単に追うため、1975年、事件当日の11月1日、0時を跨いだ11月2日の午前1時30分に遡ることにします。当時17歳、無免許のピーノ・ペロージは、パソリーニの愛車、アルファロメオGT2000で、オースティアの一方通行の海岸通りを猛スピードで派手に逆走しているところをカラビニエリに停められ、その場で逮捕されました。この時点でカラビニエリは、車に残された身分証明書から、その車がパソリーニ所有のものであることは把握していても、まさかその持ち主がすでに殺害されていることを、もちろん知らなかった。ところがその晩のペロージはといえば、留置場で他の拘留者に「あの有名なパソリーニを殺した」と、事件発覚前にわざわざ語ったそうです。また、このときペロージが「指輪を失くした」と盛んに訴えたため、カラビニエリが、アルファロメオの中をくまなく探しています。翌早朝、オースティアでパソリーニの無残な亡骸が、イドロスカーロの住人に発見されたという衝撃的なニュースに、当局、パソリーニの関係者が続々と現場に急行。捜査中、ペロージが失くしたと言っていた指輪が、パソリーニの亡骸の傍に落ちているのが見つかり、ここでペロージの容疑は一転、パソリーニ殺人事件の容疑者として逮捕されることになりました。この指輪は、ペロージがパソリーニ殺人事件の直前に入所していた少年刑務所で友達となったJohnny lo Zingaro:ジプシー・ジョニー(シンティ・ジプシーのジュゼッペ・マスティーニ)から贈られたと主張する、United
States Armyの印が刻まれたものでした。一方、ペロージが友人だと主張した、ジプシー・ジョニーは「ペロージなど知らない、指輪を贈った覚えもない」と言っています。
ジプシー・ジョニーという少年(当時)は、11歳の頃から盗みを働き始め、14歳で警察と犯罪グループの銃撃戦に参加するほどの根っからの犯罪人生を送っていて、ペロージが少年刑務所で知り合った、と主張する頃は、すでに犯罪者仲間の中で名を轟かせていた。のちに残虐非道な凶悪犯罪者として、窃盗、強盗、誘拐を繰り返しながら、最終的には警官の殺人を含む、2件の殺人事件で無期懲役となっています。このジプシー・ジョニーは、パソリーニ殺人事件の共犯者のひとりとして、当初から現在まで、疑いを持たれ続けている人物です。余談ですが、2017年の今年、つい数ヶ月前のことです。現在ジョニーは、恩赦を受け、刑務所から通って外部で働くことのできる「セミリベルタ:半自由」の身となっていましたが、6月30日、朝、仕事に行ったまま、フォッサーノの刑務所に戻ることなく失踪、大騒ぎになりました。しかし毎回、このような脱獄事件が起こると決まって不思議に思うのは、イタリアの刑務所の施設状況は過酷で有名ではあっても、凶悪犯罪者の処遇が意外と緩やかで自由なこと。無期懲役のジプシー・ジョニーは、今まで3回も脱獄した前科があると言うのに、刑務所が自宅とはいえ、外部に出かけ、ほどほどに自由が認められる緩やかさは、甘すぎるとも感じます。結局、ジプシー・ジョニーは、1ヶ月後の7月27日に再逮捕され、脱獄の理由も明らかになりました。それは14歳の時に恋に落ち、両親の大きな反対で引き離されても、「必ず迎えに来る」と片時も忘れたことがなかった『ジョヴァンナ』という女性と駆け落ちするためにトスカーナに逃げた、という、どうにも信じがたいロマンティックなものでした。ジョニーはそれまでストイックに孤独を過ごしたわけではなく、色恋沙汰も多くあり、かつては恋人である女性を相棒に、誘拐事件をも起こしている。もちろんひとりの人間に、残忍とロマンチシズムが共生する有り様には異存はなくとも、凶悪犯罪者として名高い受刑者を、脱獄後、1ヶ月も野放しにしてしまうとは、当局のかなりの落ち度と思わざるを得ない。ジプシー・ジョニーが娑婆にいる間に、ピーノ・ペロージが死亡したことも、何か因縁めいているような、奇妙な感覚を抱きます。ペロージの当初の証言によると、パソリーニは午後10時30分ごろ、ペロージとその仲間である『Ragazzi di Vita』の少年たちがたむろするテルミニ駅、チンクエチェント広場にアルファロメオで現れ「ドライブをしよう」と少年たちを誘ったと言います。他の少年達はその誘いを断り、このときひとりだけ、アルファロメオに乗り込んだのが、ピーノ・ペロージでした。その後ふたりはサンパオロにほど近いトラットリア Lo biondoで食事をし、23時30分にそのトラットリアを出、そのままオースティアのイドロスカーロ、水上機停泊地へと向かっている。ちなみに事件後、ふたりが寄ったトラットリアの主人は「確かにあの晩、パソリーニが寄ったが、一緒にいたのは黒髪のペロージではなく、金髪の少年だった」と証言していますが、この証言は捜査の対象にはなっていません。ペロージは、パソリーニが要求する性的関係を結んだ際、さらなる関係を迫られ、激しい口論となり、怒り狂った詩人からひどく殴りつけられたため、身を守るために近くにあった『イドロスカーロ』と書かれた立て札、つまり木片で詩人を殴った、と言い張っている。ペロージは、供述の間中、一貫して「すべて自分ひとりの犯行で、他に仲間はいなかった」、とひたすら強調していますが、パソリーニのアルファロメオの車内には、ペロージのものでもパソリーニのものでもない、医療用の靴底、緑のプルオーバーなどが残されており、共犯者が存在する可能性が歴然と残っていました。 |
| 秘密結社ロッジャP2メンバーの裁判関与 |
|
ところでピーノ・ペロージの、「未成年裁判」を当初から担当した裁判官が、奇しくも、のち78年、『赤い旅団』に誘拐、殺害されるキリスト教民主党の党首、元首相でもあるアルド・モーロの兄弟、カルロ・アルフレド・モーロだったという事実も、『鉛の時代』の、予言的なサインなのかもしれません。モーロ裁判官は当初「あらゆる明白な証拠を鑑みるならば、明らかに集団による犯行であり、ペロージひとりの犯行とは考えがたい。共犯者が存在する犯行」とペロージ単独犯を否定する一審判決を下しますが、その後4年に渡る裁判で、その判決は却下され、最終的には共犯者の可能性はありえず、ペロージひとりの犯行と断定された。しかしこの4年の裁判に次々に関わった人物たちの存在により、パソリーニ殺人事件が『鉛の時代』の他のあらゆる事件と同様、国家が絡む『緊張作戦』の一環と考えられるようになり、詩人とごく親しかったニネット・ダヴォリ、ダッチャ・マライーニが現在でも主張し続ける『国家による殺害』、という説を裏付けるような、さまざまな要因が浮上してきます。まず、ピーノ・ペロージの弁護士を務めたロッコ・マンジャという人物には、いったい誰から費用が払われたのか、まったく不明となっています。ペロージの家族はこのマンジャに費用は払っておらず、ペロージ自身も、費用の出所は知らないと言っている。しかもこのロッコ・マンジャという人物は、秘密結社ロッジャP2のグランドマスター、リーチオ・ジェッリと懇意だったことが、のちに明らかになっています。また、弁護士顧問としてロッコ・マンジャから任命された犯罪心理学者アルド・セミナーリは、少年には計画的に詩人を殺害する能力はなく、また殺人を犯そうという意思もなかったと、ペロージを庇う訴状を提出している。しかしこの訴状は、カルロ・アルフレド・モーロ裁判官により却下されました。なお、のち秘密結社ロッジャP2のリストが発見された際、このアルド・セミナーリもまた、P2メンバーであったことが発覚しました。セミナーリは非常に有力な極右勢力シンパで、犯罪心理学者として『鉛の時代』のあらゆる未解決の事件、例えばピコレッリ殺人事件、ボローニャ爆破事件、アルド・モーロ誘拐・殺害事件の背景に名前が上がる、疑惑に満ちた人物です。ローマで組織され、70年代後半にあっという間に勢力を増し、現代でもマッシモ・カルミナーティなど、その残党が暗躍していた犯罪集団、Banda
della Magliana (バンダ・デッラ・マリアーナ)とも非常に強い絆を持ち、彼らの裁判の際も、偽の精神鑑定提出による犯罪者擁護を幾度となく行なっています。さて、パソリーニ殺人事件のミステリーのひとつに、以下の有名な写真があります。パソリーニの亡骸発見直後の殺人現場で撮られた写真の一枚にたまたま見つかったもので、のちにバンダ・デッラ・マリアーナの主要メンバーとなる、あるいは『鉛の時代』に暗躍する(このころは、まだその名も持たない少年犯罪グループだった頃ですが)幼い少年たちが5人も現場検証の様子を伺っている様子が写っている、という写真です。しかしいったいなぜ、パソリーニ殺害現場に、まったく関係がなさそうなこの少年たちが集まっていたのか。ペロージの裁判に関わっていた、バンダ・デッラ・マリアーナと関係が深いロッジャP2のセミナーリが、その謎の鍵となるのかもしれませんが、写真の真相は未だに解き明かされないままとなっています。 さらに事件が発覚した当日、ラ・スタンプ紙の著名ジャーナリスト、フリオ・コロンボは、イドロスカーロ:水上機停泊地に並ぶバラックのひとつに住む漁師、エニオ・サルヴィッティにインタビューし、驚くべき証言を得ている。このインタビューが、重要証言として捜査の対象にならなかったのは、きわめて不思議なことです。「可哀想なやつだよ。虐殺されたんだ。少なくとも4、5人でやられていたよ。殴られている間、ずっと『ママ、ママ、ママ、ママ』と叫んでいた」とコロンボのインタビューにサルヴィッティは答えている。「あなたはそれを警察に通報したのか」と驚いたコロンボが問うと、「まさか、俺はそれほど馬鹿じゃない」と吐き捨てるように言い、報復の恐怖からか、漁師はそのまま口を閉ざしてしまいました。したがってこのエピソードは、マルコ・トゥリッロ・ジョルダーナの映画の冒頭で、ちらっと触れられてはいても、深く追求されることはありませんでした。後述しますが、この漁師の発言が40年の時間を経て、近年、さらなる深い闇へと我々を導くことになります。 |
| 詩人を殺ったのは俺じゃない。俺は無罪だ。 |
| ピーノ・ペロージが突然、パソリーニ殺人事件の犯人は「自分ではない。自分は全くの無実である」と、75年当時、パソリーニの親族が雇った弁護士、ニーノ・マラッジータ弁護士 (生涯をかけてパソリーニ事件の背景を追求)に伴われテレビに登場し、まるで冤罪被害者のように『無実』を訴えたのが、2005年のことでした。「もし真実を言えば、お前の家族を皆殺しにする、と刑務所にいる間じゅう、他の受刑者たちに事あるごとに、耳打ちで脅迫され続け、仕方なく今まで沈黙していたが、両親も亡くなり、さらには殺人に関わった仲間も死んでしまった(全員ではなくとも)。もはや何も怖いものがなくなったので、真実を告白することにした」ペロージはそう言って、そのTV番組を皮切りに、少しづつ、『真実』を語りはじめます。とはいえ、2005年の告白時は、3人の共犯者が存在すると言っていたのに、近年になって5人、さらに6人が関わったと発言するなど、内容の詳細が次々に変わり、今や死亡している2人の犯人については名前は明かしても、その他の犯人は、見たこともない知らない人物であった、と主張している。また、このRaiのTV番組に出演した際にペロージの告白を得て、マラッジータ弁護士は事件の再捜査を要求したにも関わらず、ペロージがRaiから出演料を受け取っていたという理由で、当局に却下されています。ペロージが特に庇い続け、最初から最後まで現場には存在しなかった、と言い続けたのは、件の指輪を贈ったという(のちにペロージは他の人物から、その指輪を買ったとの捜査結果が出ていますが)ジプシー・ジョニーでした。しかし詩人のアルファロメオで見つかった医療用靴底は、ジョニーが足裏の矯正のために使用していた靴底と同種の上、サイズが一致する、またパソリーニ殺害前日に少年刑務所から出所しアリバイもないなど、殺戮に参加したことが強く疑われながら、確証は得られないまま、今に至っています。では、実際のところ、1975年11月1日、午後10時30分からペロージが逮捕された翌日午前1時30分の3時間のあいだに、いったい何が起こったのか。ペロージの発言を追い続け、本人にも幾度となくインタビューし、パソリーニ殺害事件に関する優れた記事を多く書いているジャーナリストに、イル・メッサジェーロ紙のクラウディオ・マリンコラがいますが、そのマリンコラの過去の記事、またその他の文献を参考に、真相とされる仮説をざっと追ってみたいと思います。マリンコラの記事については、パソリーニ殺人事件の真相を明らかにしようと、再捜査を繰り返しリクエストし続けるローマ市元市長、パソリーニの若き友人でもあったウォルター・ヴェルトローニも言及しています。 |
| ボルセリーノ兄弟と盗まれた『サロ、あるいはソドムの120日間』のフィルム |
| 事件当時は、「怒り狂った狂気の詩人に殴りかかられた挙句の正当防衛」と主張していたペロージは、2005年以降、「パソリーニはいたって紳士的な人物だった」と発言を180度、翻しています。また、事件当初、パソリーニには事件の夜にはじめて会った、と語っていたペロージですが、そもそも2人は以前からの顔見知りで、事件が起こった年の夏ぐらいから、他の少年たちとともに時々会っていたそうです。映画『サロ、あるいはソドムの120日間』のエキストラとして出演した、という説がありますが、それについては定かな裏付けが見つけられませんでした。事件当日、なぜパソリーニがテルミニ周辺でたむろする少年のひとりを自らの車に乗せることになったのか。その伏線として、パソリーニ殺人事件の直前に公開された問題作『サロ、あるいはソドムの120日間』のオリジナルフィルムを含む何本かのフィルムが、盗難に逢い、一時消失していたという事実があります。のちのペロージの告白によると、パソリーニの殺害に加わった、当時15、6歳の少年たちであったシチリア出身の、フランコとジュゼッペという札付きの不良、犯罪仲間では有名だったボリセリーニ兄弟が、『サロ』のフィルムをスタジオから盗み出し、返却の条件として、パソリーニに5億リラを要求していたといいます。そしておそらくパソリーニは、少年たちが要求する金額を支払ったか、あるいは支払う約束を交わしている。ピーノ・ペロージ、ボルセリーノ兄弟、クラウディオ・セミナーリ、アドルフォ・デ・ステファニス、サルヴァトーレ・デイッダの少年たちと、パソリーニはそもそも事件前日の10月31日に会う約束をしていましたが、その日都合が悪くなったパソリーニは、わざわざテルミニ駅まで律儀に出向いて、「明日会おう」と少年たちに告げていますから、11月1日にふらりと少年たちの元を訪れたわけではなく、彼らと確実に、何らかの用事があって待ち合わせをしていたに違いないのです。この経緯については、パソリーニの映画の助手を長く務め、本人も監督としていくつかの映画を残したセルジォ・チッティが、パソリーニが少年達に会おうとしたのは、盗まれたフィルムの、ボルセリーニ兄弟を含む少年たちへの約束の支払いに関する話し合いをするためだった、と主張しています。なにしろセルジォ・チッティは、かつて道端でたむろしていた元『Ragazzo di Vita』ですから、その世界のことは知り尽くし、少年たちとの接点となるルートも持っていた。チッティの知人によるとフィルムを盗んだのは、ランチャーニ通りにある場末のバールに出入りしていた少年達で、彼らは「パソリーニに申し訳ないことをした」と後悔、そのフィルムを返したがっている、とチッティに伝えたそうです。パソリーニはそれを聞き、「ほら、彼らは僕に好感を持っているんだよ」と喜んでもいたらしい。なお、フィルムを盗んだのはボルセリーニ兄弟だったと断言したピーノ・ペロージもまた、そのバールにたむろする少年のひとりでしたから、ひょっとするとフィルムの窃盗に無関係ではなく、その返却の算段を理由に、詩人の車に乗り込んだのかもしれない。パソリーニがペロージを車に乗せる直前、広場にたむろする少年達と雑談をする間、ペロージは30分ほどその場から消えています。詩人とペロージが乗ったアルファロメオが走り出すと、バイクに乗ったボルセリーニ兄弟ふたりがアルファロメオの後について同行したとペロージは言っている。さらにオースティアに向かう途中には、ボルセリーニ兄弟が乗ったバイクだけではなく、カターニャナンバーの青い車も加わり、アルファロメオの後について走っていた(これはナンバーを取り替えた盗難車とみられています)。そしてアルファロメオがイドロスカーロに到着した途端、パソリーニはペロージの目前で5、6人の少年達に車から引きずり出され、執拗で残忍な暴行を受けた挙句、自身の車で轢き殺された。最近になって、ペロージは犯行に加わらず、むしろパソリーニを庇ったために顔に傷を負った、などとも発言しています。具体的にペロージの口から名前が明かされた、このボルセリーニ兄弟は、もともと極右グループMSiに出入りしていた経緯がある。また、当時、ローマの犯罪グループに潜入していた警察のスパイに、それとも知らず、「パソリーニを殺ったのは俺たちだ」と漏らしたこともあった(そのあと取り調べを受けた際、『あの時は適当なことを言った』と翻していますが)。つまり彼らの背後を洗ううち、殺害に極右グループが関わった可能性をも浮き彫りになってきます。その後のボルセリーニ兄弟は、ふたり揃ってドラッグに溺れ、最終的には90年代にAIDSで死亡。ペロージは、すでに死亡したこのボルセリーニ兄弟のことは雄弁に語っても、共犯が強く疑われるジプシー・ジョニーについては、「彼は現場にいなかった」と、やはり頑なに否定している。現場で見つかった件の指輪については、見たことのない大柄の男に指から無理やり抜き取られて、その場に捨てられた、と語っています。「こんな殺人を犯すのは、ただの狂人の仕業じゃないだろう。明確で強い動機があったに違いない。真の殺人者たちは、30年以上、司法の網をくぐり抜けているんだよ。彼らが犯した殺人には、重要な動機があり、今まで誰もそのことには触れなかった」「あの晩、フランコとジュゼッペ(ボルセリーニ)がいることはすぐに分かったよ。そこで、すぐに俺は言ったんだ。俺は虐殺には参加しない。何も知りたくない、とね」「その後ボルセリーノ兄弟は、ネオファシストとして、政治活動をするようになったんだ」「パソリーニは誰かの邪魔だったんだろう」「そして俺だけが罪に問われることになったわけだ」(リプッブリカ紙 2009年2月24日、ピーノ・ペロージ談) さらに「ホモセクシャルな性犯罪と暴力に対する正当防衛」という動機は、誰からも費用を払われなかった弁護士ロッコ・マンジャに勧められて作り上げた話だともペロージは告白している。このロッコ・マンジャは、「ジュゼッペ叔父さん」から依頼されて、ペロージの弁護を引き受けたと言ったそうですが、そんな人物をペロージは知らなかったといいます。ペロージにパソリーニ殺害犯として白羽の矢が立ったのは、未成年者で刑期が少なく、比較的軽い罪で済むため(判決は10年9ヶ月と10日)。また裁判でのペロージの発言は、すべてマンジャが指導していたのだそうです。 |
| 全てを知っていたイドロスカーロの住人たち |
| 2005年以降、ペロージは本を書いたり、インタビューに答えたり、ドキュメンタリーを作ったりと精力的に真相を語る告白者として活動し、近年ローマ中が大騒ぎになったマフィア・カピターレの主人公のひとりとして、19年の刑期を言い渡されたサルバトーレ・ブッチの運営する、元受刑者たちで構成するゴミ収集プロジェクトで働いていた時期もある。2010年に再び収監され、出所したのちパートナーを得てからは(死亡する2週間前に結婚しています)、テスタッチョの老舗のバールを友人と経営していたそうです。ペロージの死を知った、元パソリーニの親族の弁護士、ニーノ・マラッジータは、「ペロージは唯一の犯人のまま、死んでしまった。これで彼だけが知っている秘密は、闇に葬られることになった」と深く落胆しています。
ところがペロージの最近の弁護士であるアレッサンドロ・オリビエロは「私はペロージが『無罪』であることを心底信じている。真実を言うならば、彼が明らかにした情報以外に、さらに重要な情報が存在することをも私は知っているからだ。そしてその情報は、金庫の中に厳重に隠されている。なぜなら、あまりにも強烈な内容だから・・・。彼はその情報を流布することを拒絶して、沈黙することを選んだ。何が起こるかわからない、という恐怖に駆られたからだ。実は私も彼と同じように恐怖を感じていることを正直に言っておきたい。その書類にはペロージのサインがあるが、それを保管しているのは私なのだから。そのうち何者かが私の元にやってくるかもしれないじゃないか。したがって、真実はペロージとともに死んだわけではないのだ。今後のことはペロージの家族とも相談して決めようと思う」(ラ・レプッブリカ紙)と語っている。 確かにペロージは生前、「真相が分かることで、困る何者かが未だに存在するのか」という問いを肯定するような素振りを見せている。しかし正直なところ、オリビエロ弁護士のこの発言に、どれほどの信憑性があるのか、わたしには全く判断がつきません。 最後に、ひょっとしたらペロージの言うように、彼は『無罪』なのかもしれない、と思いながらも、どうしてもこの人物から、ある種のうしろ暗さを取り去ることができない理由となったエピソードを紹介して、この項を終わりたいと思います。これは、イル・メッサッジェーロ紙、クラウディオ・マリンコラが2010年に書いた記事に絡む話です。 パソリーニの亡骸発見の直後、ラ・スタンパ紙のジャーナリスト、フリオ・コロンボが、イドロスカーロ:水上機停泊地のバラックに住む漁師、エニオ・サルヴィッティから取ったインタビュー証言については前述しましたが、マリンコラは、2010年、現場となった地域に住む人々にフリオ・コロンボと同じように、再度インタビューを試みています。その中にはコロンボが取材したエニオ・サルヴィッティの孫という人物がいました。 「あの晩のことは、この地域に住む、すべての住人の家族みんなが何もかも知っていながら、誰もが沈黙を保ったんだ。家族中であの晩のことを話したものだよ。僕はまだ5歳の子供だったが、通報で警察が駆けつける前に、パソリーニの亡骸を皆で観に行った」という驚愕すべき事実を、サルヴィッティの孫はイル・メッサッジェーロ紙に証言している。パソリーニ事件の再捜査が再開された直後のことです。つまりイドロスカーロに並ぶバラックに住む人々は誰もが皆、1975年の11月1日の深夜、少年たちに囲まれたパソリーニの残忍な暴行殺人の成り行きを、耳を澄まして聴き、こっそりと覗き見し、全てを知っていながら40年もの間、まったく声を上げず、証言もしなかった。イドロスカーロに住む人々は報復を恐れたのか、あるいは独特の仲間意識からか、地域の家族内だけでひそひそ確認し合うだけで、外部への沈黙をひたすら保ったというのです。 その後、不可思議な事故が起こったのは、マリンコラのインタビュー記事がイル・メッサッジェーロ紙に掲載されて2ヶ月も経たない頃でした。2010年の7月20日、1975年の11月1日の晩の様子をマリンコラに語った、漁師のエニオ・サルヴィッティの孫、オリンピオ・マロッキは、チヴェタヴェッキアのレストランに友人と食事に出かけている。ところがその帰り、彼の乗っていた車がガードレールにぶつかって大破。そのとき運転していたマロッキの友人という男は、事故直後に車を飛び出して、歩いて近所のショッピングモールへと逃げ込んでいます。男はのちに警察に捕まりましたが、マロッキは車の外に放り出され、重症。運ばれた救急病院で死亡した。 サルヴィッティの孫、マロッキが乗っていた車を運転し、事故を起こした途端に逃げ出した男、それはピーノ・ペロージだったのです。マロッキは強盗や盗みで逮捕歴のある人物で、ペロージの友人でもあったため、主要各紙は、Malavita(犯罪者仲間)の喧嘩をきっかけとした、ペロージのいつもの怪しい素行と捉え、マロッキがパソリーニ殺人事件の目撃者であり、イドロスカーロの証言者であったことにーそれが重要な事実であるにもかかわらずー全く触れず、ちいさい記事として扱っただけでした(Alessandro Calvi)。 次から次に証言を翻した、パソリーニ殺人事件の唯一の犯人「蛙のピーノ」は、こうして、まったく掴みどころのない人生を送り、辻褄の合わないことを告白したのち、遂に完全に沈黙することになりました。パソリーニの死の周辺には、やりきれない、いっそう深い闇だけが広がり、明かされない答えを探して問い続ける人々は、大きなジレンマを抱えながら、どうにも忘れることのできない詩人の死を追いかけることとなったのです。 |
| 【イタリア政界のアルド・モーロ誘拐・殺害事件】 | ||
| 2018.2.15日、「機が熟すとき: 『鉛の時代』の幕開け、そして『赤い旅団』誕生の背景」。 | ||
| イタリアの70年代、つまり『鉛の時代』へと遡るうちに底なしの闇に迷い込み、「このまま先に進むことで何かが見えて来るのだろうか」、そして「これらは果たして本当のことだろうか、もし本当なら、こんなことが許されるのか」という不信感が交互に湧き上がり、なかなか踏み込んでいけなかったのが、欧州最大の極左テログループ『赤い旅団』にまつわるエピソードでした。一方で、自分とはまったく関係なさそうな遠い次元の話に思えても、わたしたちの生活そのものが、個人、社会、世界、と多次元のレベルで構築されていて、それを認識するしないに関わらず、実はあらゆる次元を同時に生きている、ということを再確認した次第です。1974年を境にエスカレートしはじめ、1978年の『元首相アルド・モーロ誘拐・殺人事件』という、イタリアにおいては『JFKの暗殺』に匹敵するショッキングな事件の後、メンバーによる常軌を逸したテロ事件が連続。現代イタリアでも『赤い旅団』と言えば、「節操なき狂った狼たちの群れ」として、社会を恐怖に陥れたテロリストたち、と認識されています。しかし調べれば調べるほどに、違う側面もあれこれと浮き上がってくる(タイトルの写真はBlog
di Carmelo AnastasioのAlbumより引用させていただきました)。2015年の2月15日のWSJ紙日本語版は、「イスラム国と『赤い旅団』、西ドイツの『赤軍』RAFには驚くほどの類似点がある」と指摘しています。「当時の共産主義思想―実際の共産主義国家では生命の恐怖があったにもか
かわらず―はより良い、より公平な、より純粋な社会を約束していたように 見えた。イスラム国のプロパガンダの最大の力は、今日の独自のユートピア的ヴィジョンでかつての共産主義と同じような感覚を与える能力で、欧州全域のうんざりした理想主義者、不適応者、冒険主義者らを引きつけている」という記事を掲載(ママ)。しかしこの指摘は、イタリアに暮らし、イタリア人の見地から捉えた70年代の歴史を、ほんの少し知っているだけのわたしでも、やや「こじつけ」に感じられた。 網の目のように張り巡らされた国際諜報の『東西スパイ合戦』が繰り広げられた冷戦下、イタリアでは当たり前のように語られる『グラディオ』、ステイ・ビハインドの存在をまったく無視しながら、したり顔で『赤い旅団』やRAFと『イスラム国』を比較するのは、あまりに安易な分析、片手落ちだ、と正直なところ思います。そもそも『赤い旅団』とはどのような極左グループだったのか、そんな若者たちが現れた時代にはどんな背景があったのか、時代と場所の空気を体感していないわたしにはよく分かりません。しかしデモやストライキを繰り広げる学生運動や労働者たちの闘争に、突如として、映画にでも出てくるような極端にプロフェッショナルな精鋭武装グループが現れる、という現象は考えがたい不自然なことのように感じられた。そんな疑問もあって、『赤い旅団』を理解するには、その誕生以前を追わなければ分からないのではないか、と考えるようになりました。なお、普段は記事の間に写真や動画を載せることが多いのですが、今回はその時代を少し共感したいと思い、1968~70年に流行り、当時の若者たちも、多分聴いたことがあるであろう音楽を載せていくことにしました。 |
||
| いまさら『鉛の時代』を掘り起こすことについて | ||
| わたしがローマに住みはじめたのは、今よりは幾分真摯な態度で政治を語るベルルスコーニ元首相が、その勢力をみるみる増大させていた頃でした。そしてその頃のわたしはといえば、馴染みのお肉屋さんをはじめ、周囲の人々が日々、政治の話ばかりしていることに驚きはしても、かつてイタリアに深く刻まれた時代の傷跡を、彼らのなかに見出すほどの鋭さはなかった。イタリアの70年代の騒乱も、日本を含めて世界中で起こった学生闘争から生まれた混乱、ぐらいにしか考えが及びませんでした。確かに日本の60年、70年代にも衝撃的な事件がいくつも起こりましたが、市民の銃撃戦にまで発展するようなことはなかった。ですからやがて時が経ち、たまにドキュメンタリー番組や、新聞で特集される70年代、『鉛の時代』のひとつひとつの事件が、大きなひとつながりの物語として全貌がぼんやり浮かび上がってくると同時に、「ええ!?」と大きな衝撃を受けたのです。あれこれ語られる、世界の『陰謀論』の数々をうすうす知ってはいても、基本的には『裏』の取れない話は信用しない、という方針であったわたしの、それまで抱き続けたイタリアのイメージは、多少おおげさに言えば「崩壊」、いや、イタリアだけではなく、『世界』に抱いていたイメージも同時に崩壊した、と言ってよいかもしれません。「そんな説は陰謀論、フェイク、幻想だ」では片づけられない、社会そのものを動かす緻密な国際『オペラ』が、わたしたちの住む世界に存在するケースがある。そしてその、日常からはまったく見えない危険水域に、イタリアの多くのジャーナリストや司法関係者は果敢に飛び込み、何十年もかけて(そしていまだに)、過去に散らばりながら置き去りにされた欠片を拾い集める作業をしています。もちろんイタリアにも、「すでに終わった時代だよ。いまさら『鉛の時代だ』なんて」と笑う若人たちも存在しますが、50年の歳月を経てもなお、その時代を描く映画や書籍、テレビのドキュメンタリー番組で当時の事件の詳細が語られ、新たな真実、告白が明るみに出る、という執拗な探求の理由も、今なら理解できるように思える。冷戦下のイタリアが巻き込まれたグラディオという理不尽な状況や、秘密結社ロッジャP2の存在、国際諜報の暗躍、その時代の真っ只中からはまったく見えない、人工的に創出された大きな流れにいつの間にか巻き込まれてしまう、わたしたちが暮らす社会というものは、意外と脆く、危ういものです。世代が変わリ、社会が変わり、テクノロジーが変わっても、現在のような激動の時代はなおさら、現象を冷静に判断するためにも、いろいろな過去の例を振り返る作業が必要なのではないか、と考えます。 イタリアの『鉛の時代』では、その時代に起こったあらゆる重大テロ事件において、綿密な捜査が行われたにも関わらず、最終的には司法が機能せず、長い年月の裁判を経てもなお、主犯と目された、国家軍部とも通じる極右テロリストたちがことごとく『無罪』となりました。その時代を生きた人々にとっては、何が「真実」で「正義」なのか判然としないまま、誰もが前を向いて懸命に生きるうちに、多くの重大事件は、遠い昔に起きた夢のような現実となってしまった。あらゆる事件の背景に諸説あり、いずれも確証がないために焦点が定まらず、多くの死傷者が確かに存在するにも関わらず、すべてが幻のように、遙か時の彼方の向こう、黒雲のように浮かんでいるという印象です。そして、たった50年前の戦後の歴史だというのに、誰にも「真実」が把握できないことは異様にも思う。しかしさらに考えるなら、実はわたしたちが『歴史』と呼ぶ物語そのものには、そもそも「真実」などないのかもしれません。『歴史』というものは、後世の誰かが、自身の信条に基づいて、現存する文献や証拠品から、それぞれの時代の思想や倫理、文化や風俗を推測し、出来事の断片を巧みに紡いだ、もはや検証しようのない『物語』と言えるかもしれない。イタリア語では、『歴史』、『物語』、『筋書き』を、すべてStoriaと言いますが、語源学を調べると–もちろんそのあとに、それぞれの意味に沿った説明があっても– 第一項に、「人間の営みとそれに相互に関わる事柄を、リサーチ、探求し、ひとつの筋道に統一して再構築、その関連を評論すること」とあります。 |
||
| さて、本題の『赤い旅団』。イタリア全土を震え上がらせた、この欧州最大の極左テロリストグループについては、数限りない書籍が出版され、映画が創られ、ドキュメンタリー番組が放映され、国際諜報の関与も含んでのあらゆる背景が研究され続けていて、誰の、どの説が真実なのか、あるいは真実に近い物語であるのか、わたしにはまったく判断がつきません。出版されている元メンバーのインタビューを読んだり、ドキュメンタリーをも観てみましたが、もちろん、何らかの核心を把握しているメンバーがいたには違いなくとも、おそらくメンバーの大勢は、当時自分たちが何をしようとしているのか、何処へ向かっているのか、皆目分からないままに時代に押し流されたのではないか、とも考えます。ともあれ、彼らとは世代が違うわたしは、全体主義を強いる古いタイプのあらゆる政治思想には興味がなく、また、戦争、テロリズムを含めるあらゆる『暴力』というものを、倫理的、宗教的、というよりは生理的に、まったく受け入れることができない。したがって、60年代の工場労働者階級の人々の闘争、学生運動のカオスを心情的には理解しても、『赤い旅団』をはじめとする当時のイタリアの新左翼グループが標榜した『武装革命』にまったく賛意を示すことはできません。70年代の後半から彼らが起こした数々の事件に、市民たちは喝采をあげるどころか恐怖と絶望に突き落とされたわけですから、市民の同意なき『革命』は、ひとりよがりなユートピア幻想にしかすぎない。しかしながら、その、『ユートピア』を追い求めた彼らの理想主義の闘いが、時代を形成する劇的な『オペラ』のひとつの要素として巧みに使われた、あるいは利用された、という疑惑があるのであれば、「利用される方が悪い。彼らが馬鹿なのだ」とは決して思えません。戦後の急激な日本の復興同様、第一次世界大戦の敗戦ののち、ルーズベルトが打ち出したマーシャルプランの恩恵を受け、物質的な見地からいえば、イタリアの市民生活は豊かに一変しています。パルチザンたちはともかく、『学生革命家』たちの親の世代である、戦争を終えたばかりの当時の社会を担う市民たちは、いまさらの『革命』など欲してはいなかった、と捉えるのが自然だとも考える。ゲバラ、カストロが少数のゲリラ隊を率いて、道なき道を行き、ジャングルを駆け巡り、市民たちを親米独裁政権から華々しく解放したキューバの、権力機構のコントロールの網をくぐり抜けられるほどの緩みがある、市民たちの大きな不満と嘆きが充満していた状況と、イタリアは(そして日本も)大きく異なっていました。 | ||
| さて、大変長い前置きになりましたが、その後のイタリアを大きく変えた『赤い旅団』というテーマを扱おうという気持ちになるまで、わたし自身、長い時間がかかったし、それでもまだ充分に咀嚼できたわけではなく、多くの謎が残ったままです。しかし、極左武装テロの道のりを通らなければ、先へ進めないのも事実であり、グラディオー諸刃の刃の一方の刃は欠けたままになる。そこでとりあえず、実験的に、という気持ちを抱いて、イタリアを揺るがしたテロリストたちの物語を探しはじめようと思います。この項では、まず、『赤い旅団』が生まれる背景を、ジャーナリスト、ジョヴァンニ・ファサネッラが、創立メンバーのひとりであるアルベルト・フランチェスキーニをインタビューした書籍、『Che cosa sono Le BR (赤い旅団とは何なのか): 2006』を軸に、イタリアの著名ジャーナリスト(94歳で現在も健在の)セルジォ・ザヴォリの『La Notte della Repubblica (共和国の夜)TV番組及び書籍』、ネットに上がっている『鉛の時代』のドキュメンタリー映像の数々、ロッサーナ・ロッサンダ(マニフェスト紙)、カルラ・モスカによる、モーロ事件の主犯として服役中 (とはいえ、最近はほぼ自由なようで、フランス制作のドキュメンタリーでは、車に乗ってインタビューを受けたりしていました)のマリオ・モレッティのインタビュー『Una Storia Italiana(イタリアのひとつの物語)1994年初版』を参考に、Storia − 歴史、物語を追っていこうと思います。「テロリストの話なんて信用できない。小説じゃないんだから、こんな馬鹿げた話が現実にあるものか」と、一笑に伏されるかもしれませんが、このような証言もあるほど混乱し、不信に満ちた時代だということが少し伝わればいい、とも考えます。また、フランチェスキーニが物語るほとんどの内容、人物は、いまやWikipediaイタリア語版にも根強い疑惑として、多くの証言とともに挙げられている。さらには2016年、『モーロ事件に関する政府議会捜査委員会』でフランチェスキーニが証言した内容を、ラ・レプッブリカ紙が報道していることを付け加えておきたいと思います。 | ||
| フランスの五月革命 そしてイタリアの68年 | ||
| 『赤い旅団』が誕生する背景の最も重要なファクトとして、冷戦下、欧州各国のソ連と連帯する共産主義勢力の拡大を阻止するために綿密に計画されたグラディオの下、イタリアにおいては、すでに1965年から、CIA、SIFAR、SIDなどの国内外の諜報機関と、マフィアを含む有力極右グループ、また主要政党の政治家たちが『緊張作戦』と名づけたオペレーションを実行しはじめていたのは、先の項で書いた通りです。つまり共産主義勢力が欧州で最も強かったイタリアは、冷戦におけるシンボリックな『戦場』のひとつであった、と考える。65年には軍部カラビニエリ大佐によるクーデター、Piano Solo(ピアノ・ソーロ)の計画が、エスプレッソ紙にすっぱ抜かれたこともあり、ギリシャに軍部独裁政権が樹立したこの時代、イタリアもまた、何度もクーデターの危機に晒されていた。また、第二次世界大戦以来、君主専制主義を支持する極右勢力のパルチザンと共産主義を支持するパルチザンの間には、常に微妙な緊張状態が続いてもいました。 この時代の世界の動きを見るなら、1963年にジョン・F・ケネディが暗殺された翌年、東京でオリンピックが開かれた1964年には、カリフォルニア大学、バークレー校で爆発した、学生たちのFree Speechムーブメント、激化の一途を辿るヴェトナム戦争への激しい批判、人種差別に反対する大規模なストライキ、そしてデモが米国中に広がり、やがて欧米や日本にも拡大、多くの知識人、若者たちが反戦を訴えるようになります。また、その頃、既存の常識を完全に覆す新しい価値観、自由と平和を求める「フラワーチルドレン」と名づけられた若者たちによるヒッピーカルチャーが出現。若い世代の『旧体制』への抵抗が、あらゆる形でグローバルレベルで高まっていきます。先進国と言われる国々の、反体制の若者たちの間で、時代の英雄と称えられたのは、まずチェ・ゲバラ、そしてヴェトナムの武装共産主義ゲリラであり、パレスティーナだった。このように世界の若者たちの沸騰が次第に広がる68年、フランスで、当時の大統領シャルル・ドゴール体制に大きな反発が起こりました。大学自治権を巡りソルボンヌ大学の学生が校舎を占拠し、フランス当局と学生たちは、かつてなかったほどの暴力的な衝突に発展、その学生たちを応援する労働組合や市民が続々と集まり、それまでに類を見ない規模の大きい抗議デモがパリを席巻することになります。 5月革命とも呼ばれる、この「フランスの5月」が、パリからフランス全土へ、そして欧州、世界各地へと広がっていった。怒涛の時代でした。1967年にはチェ・ゲバラが敵の銃に倒れ、1968年にはマーティン・ルーサー・キングが暗殺され、当時の若者たちの心理はいよいよ反発へと向かい、旧体制への攻撃へと動いて行きます。しかしネットがない時代に、世界中の若者たちが一斉に立ち上がったという事実は、今から思うなら非常に感慨深い現象です。媒体になったと言われる音楽や文学のパワーの大きさには驚かざるをえません。 |
||
| そして、この「フランスの5月」が起きた68年から69年、イタリアでも、その頃 本格的に大学を占拠しはじめた学生たちと工場労働者の共闘による極左グループが次々に創立され、その後のイタリアの十数年を決定的に方向づけることになります。1968年3月1日には5月革命より一足早く、ローマ大学建築科の学生と警察隊とが激しく衝突するデモがローマで起こっている。これは警官隊148名を含む600名という負傷者を出した、当時の左翼系知識人たちもまったく予想していなかった大規模な衝突で、イタリアではそれまでに例を見ない暴力的な過激デモへと発展しました。この時、ピエールパオロ・パソリーニは「中産階級の金持ちの出身である学生たちが反乱を起こして怪我をさせたのは、真の労働者階級の貧しい家庭の出身である、学生たちと同じ年頃の警察官だ」と、学生たちを強く非難。しかしこの時の騒乱が学生たちを昂ぶらせ、後戻りできない方向へと向かわせるのです。学生たち、そしてフィアット、ピレッリなどの大企業の工場労働者たちによる激しい抗議活動は、社会を根底から変革する開かれた市民の闘争、すなわち『革命』を目標にした共闘という形で、イタリア全土へと拡大していきました。「Vogliamo
prendere la vita ( 生活をこの手につかむ)』のスローガンを掲げ、この年の労働者共闘運動、騒乱のリーダーであった若者たちが、まさに1969年に火蓋が切られる『鉛の時代』、国家が絡んだ『Strategia
della tensione -緊張作戦』に巻き込まれる時代の主人公と重なってゆく。トレント大学の学生運動のリーダーであったミラノのレナート・クルチョ、マラ・カゴールが『赤い旅団』の創立メンバー(70年の創立)として、パドヴァではアントニオ・ネグリが『Potere
Operaio(労働者の力)』(67-68年創立)を率い、ピサのアドリアーノ・ソフリ『Lotta Continua – 継続する闘争)』(69年創立)が、ヴィアレッジョの騒乱を指揮しています。『毛沢東語録』が学生たちの間で爆発的な人気を博し、刷っても刷っても、あっという間に売れ切れた時代です。ちなみにこの時代の渦中を生きた世代のイタリアの人々は、日本の『全学連』のこともよく知っていて、驚かされた経験があります。 また、69年の秋は『Autumno Caldo (熱い秋)』と呼ばれ、労働組合が中心となった大規模な工場労働者たちの激しいストライキ、デモが繰り広げられ、警察官が労働者たちに銃口を向ける、という事態にまで発展した重要な時期です。しかしその闘争の結果、欧州では最も低かったイタリアの工場労働者たちの給料は上がることになり、労働条件も着実に改善され、その改善が法律として定められることとなりました。つまり労働組合の闘いは実を結び、資本家による搾取を徹底的に糾弾することには成功している。当時、学生として極左運動に関わった人々からは、当時の工場労働者たちの多くは学生たちよりも知的で洗練され、勉強も怠らず、優れた戦略で抗議活動をしていた、という証言があります。同時に69年は、『緊張作戦』に関わった極右グループの存在もまた社会の表面にその姿を現し、その活動が活発化しはじめた年でもある。フォンターナ広場爆発事件の主犯と目される『Ordine Nuovo』(新しい秩序)のジョバンニ・ヴェントゥーラ、フランコ・フレーダが計画した(この計画は10年ののちに明るみに出たのですが)イタリア国内鉄道、8カ所の爆破事件で12人が負傷するという出来事も起こってます。そして遂にその後10年以上イタリアを混乱に陥れ、市民戦争のレベルまで紛争を拡大させる『鉛の時代』の幕を開く『フォンターナ広場爆破事件』が、突如として起こるわけです。 |
||
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)