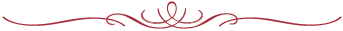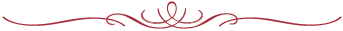| 『栄光なき天才たち』第6巻・第26話 |
|
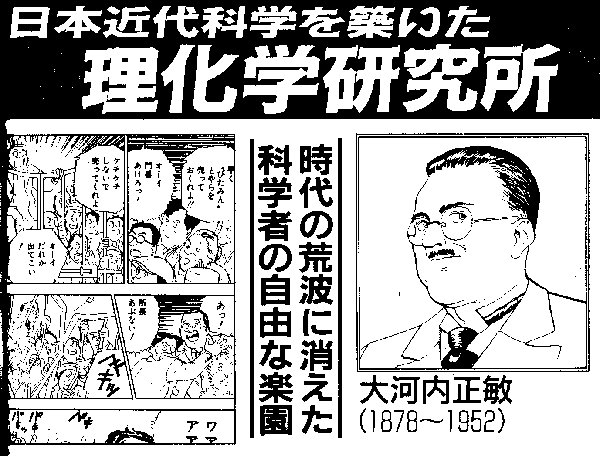
原作
①所長 大河内正敏
②寺田寅彦
③日本の原爆製造計画(ⅰ)
④日本の原爆製造計画(ⅱ)
⑤日本の原爆製造計画(ⅲ)
⑥日本の原爆製造計画(ⅳ)
⑦敗戦
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ① 所長 大河内正敏 ―作.伊藤智義
「かつて、少資源国日本を憂い、科学立国をめざして、科学者が、自らの手で作りあげた研究所が、あった」。財団法人「理化学研究所」(大正6年設立)
高橋譲吉(1854-1922)
タカ・ジアスターゼの創製、アドレナリンの結晶単離により世界的に有名な化学者、実業家。「国民的化学研究所」の必要性を説き、「理化学研究所」の創設に尽力した。「それは、経営を含むすべてが科学者の手による、まさに科学者たちの王国であり、近代日本科学の青春時代に生じた、奇蹟の産物であった
― 」。
三代目所長 大河内正敏(44)。造兵学主任研究員。貴族院議員。子爵。
「日本将来のことを考えて設立された理化学研究所だったが、政財界の反応は極めて冷たかった。期待していた寄付金は思うように集まらず、またたく間に財政危機に陥っていた。その危機を打開するため、最期の切り札として登場したのが、科学界のプリンス大河内正敏であった」。
農芸化学主任研究員・鈴木梅太郎(51)。N「ビタミン学の大家。1910年(明治43年)、当時猛威をふるっていた脚気の病因(ビタミンB1の欠乏症)を発見したが、医学界から不当な扱いを受け、認められなかった。以後10数年を経て、ようやくこの頃(大正11年)、医学界もその正当性に気づき始めていた」。鈴木「(助手たちに)毎年人口が増加していては、将来、必ず食料が不足するときがくる。それなのに日本人は主食物の米を毎年400万トンも酒に変えている。いまのうちに米以外のものからつくる酒の研究をやろう」。N「理研での鈴木は、ビタミンの研究と並行して、合成酒の研究にも打ち込んでいく」。
「大河内は、経営者である前にまず自らが第一線の研究者であった。研究に対しては最大限の自由が与えられるよう、新しい制度を次々に導入していった。しかし、これは見方を変えれば放漫財政であり、貴族の楽天主義と陰で言われたりした。そして、この年の予算は、90万円と当初の3倍にも膨れあがってしまうのである」
長岡半太郎(1865-1950: 磁気歪(ひずみ)の研究及び土星型原子模型で有名。日本物理学界のボス的存在)、池田菊苗(1864-1936: 化学調味料“味の素”の発明者。当時の日本を代表する化学者)、鈴木梅太郎ら研究者の代表と理事たちが顔をそろえている。それに所長の大河内。
理事1「つまりは、予算を縮小して健全財政とするか、それとも基金をさらに食いつぶしても積極的に研究を推進するか…」。長岡「金がなくなったら、自分は紙と鉛筆だけでも研究は続ける」。池田「物理の人はそれでいいかもしれんが、化学から実験をとったら何も残らん。それに所員に払う給料はどうするつもりだ」。鈴木。理事2「財界があまりに冷たすぎるんだ。日露戦争で日本が勝てたのも下瀬火薬の開発があったればこそなのに、今じゃ東郷元帥や乃木大将の武勇伝ばかりがもてはやされている。このままじゃ日本の将来は…」。理事3「ここでそんなことを言っても、しかたあるまい。問題は、この危機をどう乗り切るかだ」。理事1「所長はどうお考えです?」。見る一同。鈴木。大河内「私は長岡さんの意見に賛成です。基金のなくなるまで思いきって積極的にやる。いよいよお手上あげになっても、研究成果さえあがっていれば、政府も放ってはおくまい、そう考えています」。
*
N「大河内には一つの目算があった」。N「所内で研究によって生じる発明を資金源にしようと考えていたのである。それはつまり、自活への道であった」。
高橋(助手)「鈴木先生!ビタミンAの分離に成功しました!」。鈴木「うちの高橋がね、肝油からビタミンAを分離したんですよ」。N「当時の死亡原因第一は結核であった。しかし治療法が確立されていない時代である。栄養補給に努めるしか手はなかった。その結核患者にとって、ビタミンAを豊富に含む肝油は重要な“薬”であった。ところが、これはすこぶるまずく、鼻をつまんでやっとのめるほどのもので、患者に苦痛を強いていた」。鈴木「つまり、この成功によって、患者は無理して肝油を飲む必要はなくなり、ビタミンAの錠剤をのめばすむということになるわけだよ」。大河内「いやいや鈴木さん、これだけのものをみすみす他社に譲ることはない。工業化は理研(うち)でやる」。N「商品名“理研ビタミン”は、すさまじい成功であった。つくれば売れる、うなぎのぼりの売れ行きで、ついには年間100万円(現在の15億円に相当)の売り上げを記録、理研全体の赤字部分の過半を帳消しにしたという」。N「この後、理研から続々と研究成果があがる。大河内はそれを次々と工業化し、理化学研究所は、アッという間に、産業界にも一大勢力を築くまでに膨れ上がる。それはまさに、科学者たちが自らの力で動き始めた瞬間であった。もちろん、鈴木の合成酒はその中でも主力商品の一つであった
― 」。
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ② 寺田寅彦 ―作.伊藤智義
N「大河内の才覚によって自活の道を歩き始めた理化学研究所は、まさに研究の楽園であった」。「十分に使える予算に加え、研究所としての規則はほとんど皆無で、出勤、退出も自由であったという。研究者はただ自分の研究に専念すればよいわけで、当時としては前代未聞の画期的なシステムであった」。
寺田「原子物理ね…まあ、ヨーロッパに目がいくのも無理はないけど、原子物理だけが物理じゃないですよ。例えば、これ」茶菓子として置いてある金平糖を取り上げる寺田。寺田「君たち、不思議だとは思いませんか?」寺田「(うなずき)金平糖はどろどろに溶かした砂糖水に芥子粒(けしつぶ)を入れてかきまぜるだけでできるんだが…つまり、芥子粒が核になって、そのまわりに砂糖が凝固して、段々に大きな塊に成長するわけでね、」寺田「そうするとだよ、対称性を考慮するとだね、金平糖は丸く生長しなければならない」寺田「ところがだ、実際はホラこの通り、ニョキニョキと角が生えている」
寺田寅彦。
名言“天災は忘れた頃にやってくる”など。
N「『吾輩は猫である』の中の理学士水島寒月、『三四郎』に出てくる理学士野々宮宗八のモデルとなった寺田寅彦は、夏目漱石の最も信頼していた弟子であり、自身も文学史上に不朽の名を残しているが、本職の物理学においては、それにもまして重要な人物である」
寺田の業績。
N「著名な物理学者として地震などの地球物理学の分野で偉大な足跡を残しただけでなく、『尺八の研究』で学位を取った寺田は、一生を通じて奇抜な研究テーマが多かったことでも知られている」
大河内「(ニヤリとして)隠さなくてもいいよ。ぼくは寺田と同期だよ。彼のことはぼくの方がよく知っている。昼はきまって銀座へ出て竹葉亭か三越で昼食をとり、風月堂でコーヒーを飲んで、ついでに…おっと、そんなことより、君はもう聞いたか?寺田が東大に辞表を出したこと」大河内「もう東大じゃ大騒ぎだよ。ぼくのところに駆け込んできて、何とか慰留してもらいたいって…今や寺田は東大の物理学教室の看板だからな。学生にも圧倒的な人気があるし」寺田。「ぼくは今度いよいよ決心をして大学を止めるよ。ああいうところに居たら、ぼくは死んでしまう。大学の事情もあるだろうが、生命(いのち)にはかえられないから」と、はにかんだ笑みを見せる寺田。
N「1917年(大正6年)、寺田は、イギリスのブラッグとほぼ同時期に、独立に、ラウエ斑点のX線解析の先駆的な研究を行っている。それは、当時ヨーロッパの主流であった原子物理学において、重要な仕事の一つであった」。大河内「あの時も寺田はまわりに遠慮ばかりして、最後には医学部で不要になったX線管を苦心して使っているんだ」。大河内「まあ、それであれだけのことを成し遂げたんだから、それは寺田のスゴさを示してもいるんだが…」。大河内「その研究でブラッグはノーベル賞をもらい、寺田はそれ以上深入りしなかった。ヨーロッパと同じことをしていても勝負にならないと思ったのか、単に興味がなかったのか、それはわからないが、それ以降、明確に独自の物理学を試行し始める。いわば日本物理学とでも言うのかなあ、寺田は…」
N「昭和2年、地震研究所教授を条件に、寺田の東大理学部辞職は受理された。そしてこの時期は寺田にとって、理研、地研、そして航空研究所の三ヶ所を拠点として、気象学、地震学など広い意味での地球物理学に力を注ぎ、多くのすぐれた弟子たちを育てていく、いわゆる“寺田物理学”の開花期となっていくのである。
一方その頃、ヨーロッパでは、新たな興奮が巻き起こっていた。量子力学の誕生である」。ハイゼンク(独)とシュレーディンガー(オーストラリア) ― 量子力学 1926年(大正15年) ―原子物理学の二大中心地、ラザフォードのいたケンブリッジ大学キャベンディッシ研究所と、ボーアを所長とするコペンハーゲン理論物理学研究所。 N「吹き荒れる物理革命のまっただ中、一人の日本人がいた」。コペンハーゲン理論物理学研究所。その中にいる一人の日本人。仁科芳雄。
N「“クライン・仁科の公式(1928年)”を創出して世界的にも知られた仁科は、ヨーロッパの興奮をそのまま伝え得る唯一の日本人として、昭和3年、帰国する」。N「仁科を迎え入れる大学はなかった」。「仁科が物理学科の出身ではなく、電気工学科(東大)の出身者だったからである」。大河内が誘う。大河内「ああ。今度、仁科君が理研(うち)にくることになったんだ」。N「理研に腰を落ち着けた仁科は、昭和6年京大に招かれて『量子力学』の特別講義を行う」。「そしてこの講義に魅了された多くの学生が後に仁科のもとに集まり、仁科グループを形成していくことになる。そしてそこには後のノーベル賞物理学者湯川秀樹と朝永(ともなが)振一郎がいた」。
N「寺田寅彦がその絶大な人気により東大の門弟を多く集めて、東大物理学の一つの源であったとすれば、仁科芳雄は、湯川秀樹の『中間子論』を経て、戦後の『素粒子論』へと大きく開花する京大物理学の、まさしく源流であった」。
N「そして仁科は、寺田とは対照的に、懸命に欧米を追いかける」。人口加速装置の完成(コックロフト、ウォルトン)、中性子の発見(チャドウィック)、陽電子の発見(アンダーソン)、重水素の発見(ユーレイ)・・・続々と到着する新事実に、仁科「諸君!我々は欧米より郵便がくる二週間しか遅れていない。ガンバロウ!」 その言葉に奮いたつ一同。
18.寺田研 N「一方、寺田の自然観はいよいよ鳥瞰的になり、生物を含めた全自然現象に物理学の方法を及ぼそうとし、それとともに研究テーマは奔放の度を加えていく」。線香花火の研究、墨流しの研究、割れ目の研究、・・・N「さらに寺田の助手であった中谷宇吉郎は北大に移り、一生のテーマとなる“雪の研究”を開始し、見事に寺田物理学を継承していた」
19.イメージ
中谷宇吉郎と雪の結晶の各種。
世界初の人工雪。
“雪は天からの手紙である”(中谷宇吉郎)
*
N「しかし、寺田と仁科のこの対照的な違いは、後に、『東大の物理学が地球物理学にかたより、京大に遅れをとってノーベル賞が出なかったのは、寺田の文人趣味のせいだ』という批判を生み出すことになる」
N「寺田の死後、セキを切ったように寺田批判は噴出する。しかし、原子物理学が原子爆弾を生み出し、重い十字架を背負っていくのに対して、寺田の成した先駆的な仕事の数々は、時代がたつにつれ、文明が高度に発達するにつれ、各分野で再評価されていくのである」
N「昭和10年(1935年)12月31日、寺田寅彦は57年の生涯を閉じた」
N「寺田の死と前後して、仁科は日本で初めての加速器の建設に着手する。この時期、物理学は、個人の学問から、巨大科学へと、大きく変貌(へんぼう) しようとしていたのであった
― 」
|
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ③ 日本の原爆製造計画(ⅰ) ― 作.伊藤智義
昭和12年、日本初のサイクロトロン(直径26インチ)の完成。仁科「さあ、次は大サイクロトロン(直径60インチ)を作るぞ」。仁科「もちろん、これも使うよ。しかし、世界は日進月歩の勢いで進歩している。我々も先を急がなければ…。これを叩き台にして、巨大なサイクロトロンを作る。…そのためにはまず金がいるな…」。N「この頃の仁科研は国内の原子核研究のメッカとして、大きく膨れ上がっていた。研究者は100人を超え、その勢力は、ビタミン、合成酒などで理研の屋台骨を支えていた鈴木梅太郎研究室と二分するものとなっていた。それは量だけでなく、質的にも日本最高級の頭脳集団を形成していた」
仁科研究室(1943年度)
主任研究員 仁科芳雄
(1)原子核並びに中間子の理論(研究員に朝永振一郎(1965年ノーベル物理学
賞受賞)・湯川秀樹(1949年ノーベル物理学賞受賞))
(2)固体の量子論・宇宙線の研究
(3)大サイクロトロンの建設・他
(4)同位元素の研究
(5)サイクロトロンによる高速イオンの分光学的研究
(6)原子核物理学の金属学に対する応用
(7)人工放射能の生物学に対する応用並びに影響
(8)中性子並びに宇宙線の遺伝的作用
(9)中性子の植物に対する作用
N「理化学研究所を支えるために大河内によって形成された理研産業団は、昭和9年を境に著しい膨張を示す。昭和2年から8年までは理化学興業一社だけだったのが、昭和14年には、わずか5年で63社にも増えていた。それは、日中戦争のぼっ発、時局の不安と無関係ではなかった」
N「理研産業団の急激な膨張は、日産、日空、森(昭電)、日曹とともに新興コンツェルンの一角に数えられ、一見華やかであったが、その内実は、急激な膨張に財政がついていかず、経営は極度に悪化していた」。
5.大河内のプロフィール
明治11年 東京生まれ
明治36年 東京帝国大学工科大学造兵学科を主席で卒業
同時に同学科講師に就任 以後助教授(明治37年)、教授(明治44年)
明治38年 火兵学会を創設
明治39年 子爵
大正 4年 貴族院議員に初当選 以後、工政会を結成(大正7年)、一貫して工業
育成に尽力する。
大正 7年 理化学研究所研究員
大正11年 同 所長
昭和 2年 理化学興業創立
・
・
・
N「日本人として初めて造兵学科の教授となった大河内にとって、最大の問題は国防であった。それは兵器の製造のみを意味しない。工業基盤の充実である。そのための理化学研究所であり、理研産業団であった」
― 昭和14年(1939年)9月 ドイツ ポーランド進攻 ―N「時代は、風雲急を告げていた」
大河内、一人の軍人を紹介する。大河内「陸軍航空技術研究所長、安田武雄中将だ。君に話があるらしい」。大河内「軍人といっても、安田中将は東大の電気科を出ているから、君と同窓ということになる」。安田「仁科博士、単刀直入におききします。原子爆弾は可能でしょうか?」「原子核物理学の第一人者としての意見をおききしたい」。N「日本の原爆研究は安田武雄により昭和15年4月に始まる(理研に依頼は昭和16年4月)。それは、オットー・ハーンの核分裂の発見から二年半、アメリカに遅れることわずかに半年たらずであった」
*
仁科「爆弾になるか動力用の原子炉になるか、それはわかりませんが、原子核エネルギーを取り出すことは非常に興味あることです」
安田「(うなずき)よろしくお願いします。それでは」
大河内「安田武雄か…軍にも、あれほど先の見える男がいたとは…」
N「この時期を境に、世界中の学術雑誌から、原子力に関する論文が、ピタリとなくなる。
― 昭和16年12月8日 ハワイ真珠湾 ―N「ついに太平洋戦争、ぼっ発」
10.撃沈する英国プリンス・オブ・ウエルズとレパルス ― 昭和16年12月10日 マレー沖海戦 ―
12.快進撃の日本軍
― 昭和17年2月15日 シンガポール陥落 ―
14.議会
大河内「この戦争に勝って勝手勝ちぬくには、五重要産業を始めとし、何処までも生産を増強しなければならない。そのためには…」
その力強い表情。
寺田寅彦と中央公論。
「具体的にいうことができないのは遺憾であるが、自分の知っている多数の実例において、科学者の目から見れば実に話にもならぬほど明白なことがらが、最高級な為政者にどうしても通ぜずわからないために国家が非常な損をし、また危険を冒していると思われるふしが、決して少なくないのである。中にはよくよく考えてみると、国家国 民の将来のために、実に心配で枕を高くして眠られないようなことさえあるのである。(中央公論 4月号 昭和10年)」
18.同・鈴木研究室
鈴木梅太郎が弟子たちにこぼしている。
鈴木「日本人、とくに青年将校は戦争が好きで困る。日支事変などやらなくてもすんだものを、戦争好きと外交下手のおかげでこんなことになってしまった。この華々しい戦果も、最後まで継続できるとはかぎらない。彼らが本腰を入れて立ち上がると、日本のように軍人だけに頼る国家と違って、経済力のバックがある。つまり、物質の点では比較にならないからなあ。負けなければよいが、心配だよ」
19.海戦
爆撃大破する日本の空母。
― 昭和17年6月5日 ミッドウェイ海戦 ―N「ミッドウェイ海戦で連合艦隊は大打撃を受け、ここに戦局は急転する」
*
― 8月7日 米軍ガタルカナル島上陸 ―N「東京市では、家庭用野菜の登録制販売まで始まった」
*
N「戦局が急速に悪化の度を加えていく昭和18年5月、陸軍航空総監兼航空本部長に昇格したばかりの安田武雄中将のもとに、一通の報告書が届く」
20.陸軍航空本部 報告書を開く安田。
N「こうして日本の原爆製造計画、陸軍最高機密“二号研究”はスタートするのである」
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ④ 日本の原爆製造計画(ⅱ) ― 作.伊藤智義
N「原爆の理論は極めて簡単である。ウラン235で、ある一定の大きさ(臨界量=純度にもよるがおよそ数㎏程度)のかたまりを作ればよいだけである。そうすれば中で自然に核分裂反応が進み、大爆発を起こす」
解説図。
(ウラン235の原子核に中性子を打ち込むと、原子核は2個または3個に分裂し、2×10の8乗eVという莫大な量のエネルギーが解放される。と同時に、この時、核分裂にともなって2個ないし3個の中性子も放出される。この中性子が再び核分裂反応を起こす。臨界量以上の大きさにすれば、この連鎖反応は自然に起こる。)
N「しかし、この核分裂をおこすウラン235は天然のウランの中にわずか0.7%しか含まれていない。これをいかに分離して取り出すか、これが非常に大きな問題であった」
・天然のウラン 99.3% U238 0.7% U235
両者は化学的性質が全く同じで、重さだけ違う。これを同位元素という。同位元素を分離するには、そのわずかな重さの違いを利用するしか方法がない。
N「この方法として、四つが考えられた」
(1)電磁法
イオン化したウランガスに電磁場をかける。軽い方がよく引っぱられる。
(解説図)
(2)超遠心分離法
ウランガスを円筒に入れて回す。遠心力で重い方が外側に、軽い方が内側に残る。
(3)気体拡散法
気体はほうっておくと拡散する。その時、軽い方が先に広がっていく。
(4)熱拡散法
気体に熱を加えると、対流により、軽い方が上に、重い方が下にたまる。
N「いずれの場合でも、まずウランを気体状にしなければならない。ウラン化合物で気体のものは唯一、六フッ化ウランのみであった。この六フッ化ウランの合成も難航が予想された」
*
N「こういう理論は、アメリカのマンハッタン計画と全く同じであった
―
」
2.理研― 昭和18年 ―
武谷「現在のわが国の技術力を考えると、電磁法はまず無理であり、超遠心分離法、気体拡散法は何年で装置が組み立てられるかわかりません。結局残ったのは、熱拡散法ということになります」。
4.イメージ
4人の研究者たち。
― 玉木英彦・臨界量の計算担当 ―
― 武谷三男・熱拡散法の理論計算担当 ―
― 竹内柾・熱拡散法装置製作担当 ―
― 木越邦彦・六フッ化ウラン担当 ―
N「この4人を中心に、アメリカとは比較にならない程小規模ながら、日本でも原爆製造計画が本格的に始動する。当時、陸軍の極秘研究はイ、ロ、ハ、ニというカタカナの符号がつけられていた。そこで、原爆研究は仁科の名をとって“二号作戦”と名付けられた」
5.研究室B(熱拡散法分離筒製作室)
N「昭和18年9月20日、日本の将来を心配しつつ、理研の大黒柱の一人鈴木梅太郎は他界する」
10.イメージ
雨の神宮外苑競技場。
― 10月21日 出陣学徒壮行大会 ―N「その一ヵ月後、学徒出陣が始まり、この頃から喫茶店などが次々と閉業し始める」
大河内「ピッチブレンドの中にはウランもまじっている。そしてチェコスロバキアにはその鉱山がある。さいわいそこはドイツの占領地だ」。
安田「(ハッとなり)ピッチブレンドですね?わかりました」。市谷・航空本部。安田「駐独の大島大使からの返事は?」。軍人3「はい。『何に使うのか』と」。安田「ふん、ドイツ(むこう)もピンときたというわけか…」。軍人4「(来る)大島大使から第二報。『ドイツ政府は分けられない』」。
安田「大島大使にすぐ打電しろ!『われわれがピッチブレンドがほしいのは、原子力の開発に使うためだ。われわれは、いま日独同盟のもとに、米英を相手に食うか食われるかの戦争をしている。その一方のわが国が原子力の開発をやろうというのに、それに協力しないというのは何事であるか』と」。大島「こうなったら直接ヒトラーと交渉するか…」。N「大島大使の交渉の結果、ドイツは日本に2トンのピッチブレンドを送ることとなった」。世界地図
N「しかし問題はドイツからの輸送方法だった。当時は独ソ戦の最中でシベリア経由というわけにはいかないし、輸送船で運ぶというわけにいかない。結局、ドイツの潜水艦で日本まで運ぶということになった」。N「しかし、ドイツを出航した潜水艦が日本に到着することはなかった。途中で撃沈さ
れてしまうのである ― 」。
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ⑤ 日本の原爆製造計画(ⅲ) ―作.伊藤智義
1.雪の降りしきる東京の街並
N「明けて昭和19年、元旦は大雪であった」2.理研・49号館。N「その中で試行錯誤を続けながらも、日本の原爆計画は一歩一歩前進していた」
3.研究室C(六フッ化ウラン研究室)木越、ついにできた六フッ化ウランの結晶を見せる。それはわずかに米粒大の大きさでしかなかったが、仁科「やったな、木越君!」。木越「はい」。N「昭和19年初頭、ついに待望の六フッ化ウランの合成は成功した。そして三月には
― 」
4.研究室B N「熱拡散法分離筒が完成」みんなにたたえられる竹内。天井をぶち抜く形で完成した分離筒。仁科「六フッ化ウランはできた。分離筒もできた。さあ次はいよいよウラン235の分離実験だな」。そこに玉木(臨界量計算担当)、飛び込んでくる。玉木「仁科先生、大変です!武谷(熱拡散法理論計算担当)が、特高につかまりました」。玉木「武谷は学生時代(京大)、左翼思想の研究をしていたことがあるんですよ」。N「ここでも明らかになるのが、日本の組織の統率のなさである。陸軍と海軍の仲の悪さは有名であるが、この時武谷は、軍と警察が全く別個の組織であるということを感
じたという」。N「こうして武谷は珍妙な“特高研究室”で研究を続けることになった」
9.研究室B
N「一方、理研では分離実験が始まっていた」
*
仁科と話をしている武谷。仁科「つまり、分子間力を詳しく計算すると、熱拡散法では分離できないということか?」
武谷「はっきりはしていませんが、われわれはこの重要な問題を軽く見のがしていたん
です。一度、初めからチェックし直さないと…」
仁科「もうここまで来てしまったんだ。後戻りはできん」
武谷「わかっています。しかし万一のために、もう一つ別の方法を並行して研究するべ
きだと思います」
仁科「残念ながら、もはやそんな余裕はどこにもないよ。資材も、時間も
―
」
見る武谷。
仁科「もし、熱拡散法以外でやるとしたら?」
武谷「電磁法と気体拡散法は技術的にとても無理です。しかし超遠心分離法なら、ある
いは…」
仁科「超遠心分離法か…」
11.市谷・陸軍航空本部
N「その頃、陸軍航空本部に海軍の技術関係者が訪れていた」
「海軍でも原爆をやりたいが、第一歩からやるのでは間に合わぬし、むだだから、これ
まで仁科研でやったデータを教えてほしい」
振り返る係官。
安田「この段階にきて陸軍と海軍の区別をうんぬんしている場合でもないだろう。すべ
てのデータを渡してやれ」
12.京都大学
N「海軍の原爆研究は京都大学荒勝研究室に一任された。それは仁科研の“二号研究”
に対して“F研究”(由来は定かではない)と呼ばれた」
13.イメージ
荒勝文策。
“理論の仁科、実験の荒勝”といわれ、日本に原子物理学を定着させたパイオニアの一
人。
14.研究をしている人々
N「F研究の最大の特徴は、二号研究とだぶらないように超遠心分離法を採用したこと
にあった」
(図:「昭和史の天皇4」(読売新聞社)196ページより)
N「超遠心分離法では、少なくとも一秒間に10万回以上の回転が必要だった。しかし、
そんなものは当時の極度に物資の不足していた日本では到底不可能であった。結局、
京大のF研究は理論研究のみで終わる」
15.仁科研・研究室B
分離実験をくり返している竹内。
そこに仁科、来る。
仁科「どうだね?調子は」
竹内「はあ、どうも思うような結果がでなくて…」
仁科「そうか…やっぱりダメか…」
竹内「今、武谷さんに詳しく計算してもらっています。何とか改良して、また実験を続
けます」
仁科「うむ。がんばってくれ」
16.研究室A
研究を続けている玉木。
N「一方、玉木ら理論グループは、原爆開発にかかる時間を計算していた。それは、竹
内の分離筒がうまくいったとしても、それ一基では、一発の原爆を作るのに50~
100年かかると見積もられた」
17.懸命に研究を続けている研究者たち。
竹内。
木越。
玉木。
そして取り調べ室の武谷。
N「そして、さらに致命的に思われたのが、それに要するだけのウランのメドが、いま
だに全くたっていないことであった
― 」
(⑤・終)
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ⑥ 日本の原爆製造計画(ⅳ) ― 作.伊藤智義
1.空襲を受ける東京
N「昭和19年11月1日、B29一機の偵察以来、毎日のように、東京の空には警報
が鳴り響いていた。
そして昭和20年に入って3月9日夜から10日にかけて東京大空襲。下町は壊滅
的な打撃を受けた」
炎上する下町。
N「末期症状を呈してきた軍は、極秘であるはずの原爆計画をこの時期、士気高揚のた
めに利用し始めていた」
2.イメージ
特攻隊として出撃する若者たちに
―
上官「まもなく一発で大都市を吹き飛ばすくらいの威力のある新兵器ができる。君たち
は、それができるまでの間、国を守るためにいのちを投げだしてくれ」
3.イメージ
防空壕の中で
―
「大丈夫。今、マッチ一箱で軍艦を吹き飛ばす爆弾を作っているそうだ」
*
N「しかし実際は ―
」
4.理研・研究室B
竹内のもとに研究者A、来る。
研究者A「ダメです。分析結果は、ウラン235の濃縮は認められません」
落胆する竹内。
竹内「そうか…ダメだったか…」
N「竹内の熱拡散法分離筒による分離実験は、一年に及んでいた。しかし、結果は思わ
しくなかった」
研究者B「どうしますか?竹内さん」
竹内「なあに、研究とはこういうものさ。いつも一度ですらっといったためしはない。
だめならもう一度やり直すだけだ。ただそれだけ
―
」
疲れた体に気合いを入れる竹内。
と、突然、空襲警報が鳴り渡る。
竹内「チッ、またか…」
見る研究者たち。
竹内「かまわん。続けよう」
その時、
ドーン!というものスゴイ音。
窓にかけよる竹内たち。
理研の建物が炎上している。
B「2号館がやられた!」
C「理研が狙われてるんだ!」
竹内「避難…急いで避難だっ!」
5.同・表
火の粉の降る中、逃げ出す人々。
「あ、データが…」
「そんなものはいいっ」
*
「危なーいっ!4号館が崩れ落ちるぞっ!」
6.東京の夜景に
―
次々に上がる火柱。
N「4月13日の大空襲は、ついに理研を直撃した」
7.防空壕
入ってくる竹内たち。
すでに避難してきている人々。
仁科がいる。
仁科「無事だったか、竹内君」
竹内「先生もご無事で」
仁科「残りの人たちは?」
竹内「無事だと思います。しかし、ついに理研が…」
8.街に
―
再びサイレンが鳴って、
声「空襲警報解除―っ」
9.理研
ほとんど壊滅状態。
所々に燃え残りの火がくすぶっている。
各所で絶望的なタメ息。
「3号館は全焼だ」
「6号館も」
その中を、先を急ぐ竹内。
― 49号館は…分離筒は… ―
10.同・49号館
来る、竹内。
ホッとなる。
竹内「無事だったか…」
罹災をまぬがれて無傷の49号館。
木越「(来る)助かりましたね、竹内さん」
竹内「あ、木越君。うむ、本当に良かった。今、分離筒を失えば、文字通り元も子もな
くなっちゃうからな。アイツにはまだまだ…」
その時、
木越「あっ」
思わず声を上げる木越。
見る竹内。
49号館がメラメラ燃え出す。
みるみる血の気が引く竹内。
思わず行こうとする。
それを必死で止める木越。
木越「危ないっ!竹内さん!」
アッという間に燃え上がる木造二階建て。
竹内、ボー然。
― 分離筒が… ―
天をつく炎。
竹内。
― 燃える… ―
音をたてて崩れ落ちる49号館。
竹内
―
。
*
N「熱拡散法分離筒炎上。
“日本の原爆”の夢は、こうして砕け散ったのである」
11.理研(翌日)
焼け跡を見て回る大河内。
その表情は、ひどく淡々としている。
*
復旧作業をしている仁科と研究者たち。
そこに大河内、やって来る。
大河内「やられたもんだねえ」
仁科「(見る)ええ。六割がた焼けてしまった感じですね」
大河内「うむ。で、君はどうするつもりです?」
仁科「は?」
大河内「多くの研究室では、これを機に疎開の準備を始めている。君は?」
仁科「幸い大サイクロトロンが残りましたんで、私は残ろうと思います」
大河内「そうか…。しかし、竹内君の分離筒は焼けてしまったらしいね」
仁科「ええ」
大河内「二号研究はどうするつもりですか?」
仁科「…続けますよ」
大河内。
仁科「少なくとも、二号研究を続けていれば、若い研究者を戦場に送らなくてすむ。そ
れに…」
大河内。
仁科「一時たりとも基礎研究を中断するわけにはいきません。戦争が終わった時、日本
には科学はなかったと言われたら、それは私たちの責任ですからね。たとえ紙とエン
ピツだけになっても…」
大河内「(思わず苦笑)紙とエンピツか…」
仁科「?」
大河内「いや。私が所長に就任したての頃、理研はひどい財政難でね、その時、長岡さ
んが同じことを言ってたんだ。たとえ紙とエンピツだけになっても、ワシは研究を続
ける、とね」
仁科。
大河内「(つぶやくように)しかし今度は本当に紙とエンピツだけになってしまうかも
しれんなあ…」
仁科「…」
*
焼け跡と化した理研全景
―
。
12.イメージ
アメリカの原爆製造現場。
大工場。
大勢の作業員が働いている。
N「その頃、アメリカの原爆製造計画、マンハッタン計画は、大詰めの段階を迎えてい
た」
13.イメージ
白熱している会議。
N「連日、原爆の日本への使用をめぐって、激しい議論がたたかわされていた」
14.山中
トンネルを掘っている大勢の作業員たち。
― 長野県松代 ―
N「一方、敗色が決定的ともなった日本軍は、それでもなお、徹底抗戦を叫んでいた。
長野県松代の山中に長大な地下要塞を築き、そこに天皇家と大本営を移し、」
15.日本地図に
―
N「本土を二分して東部を第一総軍(司令官 杉山元元帥)、西部を第二軍総軍(司令
官 畑俊六元帥)の担当とし、予想されるアメリカ軍の九州上陸オリンピック作戦に
備える体制を整えていた。それは“決号作戦”と呼ばれた」
第一総軍本拠 ― 市谷。
第二総軍本拠 ― 広島。
その他に航空総軍(司令官 河辺正三大将 ― 市谷)。
(解説図)
16.イメージ
皇居。
N「しかし肝心の天皇家が、頑として、空襲にさらされている東京を、動こうとはしな
かった」
17.イメージ
大本営。
N「あわてた軍部は、急遽、B29が毎日飛来する中、皇居地下の吹上防空室の補強に
奔走する」
18.イメージ
作業している第一近衛師団。
“一号演習”と名付けられたその補強工事は、のべ12万人を動員して行われた。
19.イメージ
政府。
N「一方、日本政府は、終戦への糸口を懸命に模索し始めていた」
*
N「そうして迎えた8月
―
」
20.イメージ
せん光とともに、わき上がるキノコ雲。
― 広島 昭和20年8月6日 ―
21.理研・研究室
仁科の所に将校A、来る。
将校A「仁科博士、すぐ来て下さい!」
驚いたように振り返る仁科。
(⑥・終)
|
理化学研究所 ⑦
|
|
「栄光なき天才たち」特別シリーズ ~ 近代日本の科学者群像Ⅱ ~「理化学研究所」 ― ⑦ 敗戦 ― 作.伊藤智義
1.壊滅した街
― 広島 ―
仁科ら視察団が、声もなく立ち尽くしている。
将校A「仁科博士…これはやっぱり…」
仁科「間違いありません。原爆です…」
2.新聞見出し
N「新型爆弾により広島壊滅
―
その報は日本中を駆けめぐった」
3.海軍技術研究所
N「その日、竹内は目黒の海軍技術研究所にいた。戦時研究員の肩書きが残っていたた
め、電波兵器の研究をさせられていたのである」
広島第一報を見てガク然となる竹内。
― そんなバカな… ―
そこに将校B、来る。
将校B「お前はこの前まで理研で原爆の研究をやっていたそうだが。われわれの得た情
報では、アメリカは月産二発のペースで原爆を作っているという。そんなにたくさん
出来ると思うか」
竹内「そんなベラ棒なはずはない。わたしたちのやり方では、100年ぐらいはかかる。
いくらアメリカだって、そんなに出来るはずはありません」
N「ところが広島投下の3日後
―
」
4.イメージ
わき上がるキノコ雲。
― 8月9日 長崎 ―
5.海軍技術研究所
ひどく叱られている竹内。
将校B「お前たちが先日いったようなありさまだから、かくのごとき状態になったのだ!」
竹内「…」
その悔しさのにじみ出た顔にかぶって、
― どうやってアメリカは… ―
6.高校
― 旧制山形高校 ―
N「木越は山形にいた」
食い入るように新聞を読んでいる木越。
N「山形に疎開して、なおも六フッ化ウランを作っていたのである」
木越「やられたか…」
*
N「そして武谷は、巣鴨の東京拘置所で検事の取り調べを受けていた」
7.東京拘置所
N「いよいよ裁判にかけられるというところであった」
8.同・取り調べ室
検事1、来る。新聞を広げ、
検事1「お前が研究していたというのは、この爆弾のことか」
武谷「そうです」
検事1「検事をみんな集めるから話してくれ」
*
検事たちに説明する武谷。
*
武谷「…と、これが原爆というものです」
何がなんだかわからずポカンとしている検事たち。
武谷「(一つ息をして)それでは、具体的にどれくらいの威力があるか説明しましょう」
うなずく検事たち。
武谷「ある地点で一発の原爆が爆発したとする。すると太陽が約17時間照射するのと
同じエネルギーが10分の1秒くらいに加わったことになる。いま吸収率を10%と
して
― 」
さらさらと計算する。
武谷「1000mさきの1mmの厚さの鉄板が溶けることになる。人間を木材と同じと
し ―
」
また計算していく。
武谷の表情から、次第に血の気が引いていく。
武谷「十分に焼けどをし ―
」
検事たち。
武谷「つまりみんな死んでいる」
息をのむ検事たち。
武谷「広島は死に絶えている ―
」
検事たち「…」
武谷「アメリカはまだ数発持っているかもしれません。ボヤボヤしているとまた落ちて
くる。飛行機が単機でくるときは危険だから深い穴に入っていた方がいい」
検事1「(真っ青になって)お前、もういいからさっそく、仁科研へ帰って研究を続け
てくれ」
武谷「え?(と見る)」
検事たちのあまりに真剣な表情に、
思わず苦笑する武谷。
検事2「何がおかしいんだ?」
武谷「帰って研究してくれって?こりゃいいや。ハハハ…」
声をたてて笑い出す武谷。
検事たち。
*
N「昭和20年8月15日、敗戦
―
」
9.理研
みんなが集まっている所に、武谷、来る。
武谷「どうしたんだよ、みんな。しょぼくれちゃって。負けちゃったもんはしょうがな
いじゃないか」
玉木「いや、違うんだよ。仁科さんが、まだ帰ってきてないんだよ」
武谷「え?広島に行ったっきり?」
玉木「うん。連絡もない」
研究者A「まさか先生…」
見る一同。
研究者B「まさかってなんだよ?」
研究者A「いや、出て行く時、ひどく責任を感じてるみたいだったから…」
玉木「(否定)まさか」
一同。
N「しかしリアリストの仁科は、豹変して帰ってきた」
ひょっこり帰ってくる仁科。
すこぶる元気で、第一声は、
仁科「サイクロトロンの修理はどうなっている?」
あっけにとられる一同。
仁科「(ニコニコして)世の中が変わったのだよ」
10.大サイクロトロン
補修工事の指揮をしている仁科。その顔には生気がよみがえってきている。
N「湯川の中間子論(昭和10年発表、昭和24年ノーベル物理学賞)に始まる素粒子
物理学は、戦後、飛躍的な発展を遂げ、現在にまで到っている。その素粒子物理学で
主役となるのが、サイクロトロンなどの加速器であった」
玉木「(来る)しかし良かったですね先生。この大サイクロトロンが残って…」
仁科「本当だよ。戦争が終わって、長い間のムダをとりかえさなくちゃならないからな。
10年かけて作ってきたコイツがやっと使えるんだ。本当に良かった」
しみじみとなる仁科。
そこにGHQがドカドカやってくる。
米兵1「危ないからどきなさーい!」
「?」
と研究者たち。
仁科「何ですか?あなたたちは」
米兵1「これは廃棄します」
仁科「(ビックリ)えっ!?」
米兵1「原子爆弾の研究は一切禁止だ」
米兵1、合図を送る。
騒音を響かせ、解体作業を始めるGHQ。
仁科「やめてくれっ!サイクロトロンは原爆とは関係がないっ!」
しかし
―
、
N「5日間にわたって破壊しつくされたサイクロトロンは、昭和20年11月29日、
東京湾に投棄される」
11.イメージ
東京湾に捨てられるサイクロトロン。
12.理研
サイクロトロン跡地。
ボー然と立ち尽くしている仁科。
N「こうして理化学研究所は、核物理学のメッカとしての使命を閉じる。戦後の日本は
田無の東大核物理学研究所に加速器をつくるまで17年の長い冬眠期を迎えることに
なったのである」
13.仁科家
病床についている仁科。
大河内が見舞いに来ている。
大河内「あれほどタフだった君が胃をやられて倒れるとは、よほどサイクロトロンのこ
とがこたえたんだねえ」
仁科「仕方ないですよ。ぼくはすっかりあきらめています。将来、何年後になるかわか
らないけれど、よしふたたび建設を許されても、そのときにはもう一度つくろうとす
る気力は、ぼくにはもうなくなっていることでしょう」
大河内「何を弱気なことを言っている。我々にはまだやらなければならないことがたく
さんあるじゃないか。とにかく日本の科学界を再建しなければ…」
そこに、
「仁科先生、大変ですっ!所長が…大河内先生が…」
と玉木、入って来る。
大河内「どうしたんだね、そんなにあわてて…私がどうかしたのかね?」
玉木「あ、大河内先生…。ニュースは、お聞きになりましたか?」
大河内「ニュース?」
玉木「先生が…」
14.新聞見出し
“理研所長大河内正敏、戦犯指名”
“科学陣で逮捕命令を受けた最初の人”
(昭和20年12月16日)
15.巣鴨拘置所
大勢の記者に囲まれて大河内、来る。
大河内「(インタビューにこたえて)別に心の動揺を感じませんが、私などがこの列に
入ることは、実に意外でした。東條内閣顧問という肩書も経済顧問というだけで何ら
発言権も与えられず馘(くび)になりましたし…まあしかし、そんなことはどうでも
よいでしょう」
そこに秘書A、来る。
秘書A「先生」
見る大河内。
秘書A「(涙ぐみ)何不自由なく育った先生が、ろうやに入れられてしまうなんて、私
はふびんでふびんで…」
大河内「私なら大丈夫。心配はいらないよ」
入っていく大河内。
16.文理大学(のち東京教育大→筑波大)
N「すべてを失い途方にくれる実験家に対して、文字通り“紙と鉛筆”でできる理論グ
ループは、軍事研究から解放され、生気を取り戻しつつあった」
― 朝永ゼミ ―
N「その核となったのが朝永振一郎(仁科研研究員・文理大教授)であった」
朝永のもとに30人近い若い研究者が集まっている。
N「この荒涼たる環境の中で朝永は、坂田(阪大)、武谷らの提唱したC中間子仮説を
容れて、“くりこみ理論”を確立していく。やがて、アメリカでもややおくれて、の
ちにノーベル賞を共同受賞(1965年)するシュウィンガーが同じ研究を進めてお
り、つばぜりあいが演じられていることが判明すると、朝永は」
17.イメージ
朝永「まさか、こちらはサツマ芋を食べながらやっているとは思わないだろうね。むこ
うはビフテキなんかで馬力をつけているんだから…」
N「そう笑って言ったという」
18.理研
仁科、元気に姿を現わす。
仁科「さあ、バリバリやるぞー!」
N「昭和21年に入ると仁科の健康は回復、そして4月
―
」
*
所員の喜びで迎え入れられる大河内。
N「疑いが晴れて大河内が釈放される」
「どうでしたか、中の様子は。ずい分ご苦労されたでしょう」
大河内「なに、窮すれば通ずるでちっとも困らなかったね」
「どんなこと、考えてました」
大河内「トンカツでビールが飲みたかったね」
笑いがもれる一同。
N「理研復興へと、すべてが大きく動き始めようとしているかのように思えた。
しかし
―
」
仁科、ふと見ると、
GHQがじっと大河内を監視している。
仁科「…」
19.所長室
大河内「理研(ここ)に出入りするなと!?どういうことだ?」
仁科の立ち会いのもと、吉田茂(当時外相)が来ている。
吉田「これはGHQの意向なんです。どうもGHQは大河内さんのことを良く思ってい
ない…」
大河内「自分がこの敗戦日本の再建のために努力するのは国民として当然のことだと思
っている。それが悪いということであれば、ふたたび巣鴨に捕えられても悔いはない」
吉田「しかしそれでは…」
そこにGHQ、入ってくる。
「話し合いはまだ終わらんのかね?」
見る一同。
大河内「…」
N「11月、大河内、所長を辞任」
20.正門
大河内「(仁科に)あとのことは、よろしくお願いします」
無言で頭を下げる仁科。
*
寂しく去っていく大河内。
―
その後姿。
*
N「さらにそこに財閥解体の嵐が襲いかかる。コンツェルンを形成していた理研は、集
中排除法にふれるから解体せよという指令が発せられたのである。これこそ致命的な
衝撃だった」
21.イメージ
財閥解体を伝える各紙。
N「こうして、科学者たちの自由な王国、栄光の理化学研究所は、時代の荒波の中に消
えてしまうのである
―
」
*
N「その後理研は、仁科を所長とし、一研究機関として再出発を図る。
一方、理研を追われた大河内は、その後、公職も追放され、昭和27年8月29日
不遇のうちにその生涯を終える」
22.イメージ
現在の理研。
N「現在、特殊法人理化学研究所は埼玉県和光市に、一研究機関として存続している。
しかし、かつての理化学研究所のような存在は、現在はどこにも存在しない。そし
て、今後も二度と出現しないだろうといわれている」
23.イメージ
理研と、大河内、鈴木、寺田、仁科らの研究者たち。
N「それはまさしく、近代日本科学の青春時代に突如として出現した、奇跡の産物だっ
たのである
― 」
(完)
解説
|
|