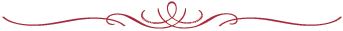
| 田中角栄の政治論政策論 |
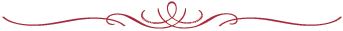
(最新見直し2011.9.14日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、田中角栄の政治政策論を一括しておくことにする。れんだいこツイッターに「田中のような利益誘導型政治の歴史は古く(以下、削除され不明)」なるツイートが寄せられ、これにコチンと来たれんだいこが、「田中のような利益誘導型政治の歴史は古く」とあるが、。どこがどう利益誘導型政治なのか説明して下さいとリツイートしたところ、返答の代わりに「推薦文書の読書の薦め」なるものをいただいた。こんなのありかよ。 未だに返事がない。この御仁に悪意はないのだろうが臭い。おまけに、いつのまにか当該ツイートが消されていると云うお粗末なことになった。この御仁を仮に「推薦文書の読書の薦め氏」(略して「推薦氏」)と命名する。「推薦氏」よ、れんだいこは「推薦氏」が憎いのではない、そこは分かってほしい。質問に答える代りに読書を薦める自称インテリが多過ぎるので、そういう傾向の右代表としてバッシングしているに過ぎない。とんだ被害者であろうが、今時珍しいそういう作法の矯正師としてのれんだいこを拝せ。 せっかくのついでに、転んでもタダでは起きぬれんだいこは、この機会に「田中角栄の政治論政策論」をサイト化し「れんだいこの角栄論」に追加しておくことにする。ネット検索したところ、「ふじむら掲示板」のバード氏の投稿文を目にした。早坂茂三氏の「田中角栄回想録」(小学館:1987年)を書き写し(その労を謝したい)、これに秀逸なコメントを付している。これを転載させていただく(多少編集替えした)。これにれんだいこの私見私論を加えた。味わってほしいと思う。 2011.9.14日 れんだいこ拝 |
|
[6008] 田中角栄の基本思想 投稿者:バード 投稿日:2007/10/28
● 経済についての基本思想
● 国土総合開発についての基本構想
● 農村政策についての基本思想
● 都市政策についての基本思想
[6003] 田中角栄の「行政改革」論 投稿者:バード 投稿日:2007/10/24(Wed) 21:45:19◆ 日本にはもう希望はないのかも 連日、「税制改革」が論議されているらしい。このところ毎年の恒例行事になった感すらある。これが今後も毎年、延々と続くのだろう。先の大東亜戦争の敗因は、一言でいえば日本の指導者の無能であった。現代も同じく指導者の無能によって、日本経済(日本の暮らし)はどこまでも崩れていくのだろう。経済をゼロサムとしか考えられない、あわれな人たちだ。小室直樹氏に一言、相談すればいいものを。 (転載貼り付けはじめ:NIKKEI NET より) ● 田中角栄の「行政改革」論 早坂茂三『田中角栄回想録』(小学館:1987年)を読むと、角栄の「行政改革」は次の四項目であると思われる。
[6002] 田中角栄の国鉄改革 投稿者:バード 投稿日:2007/10/22(Mon) 21:45:47 田中角栄は生前、政治をやっていなければ、自分は財閥になっているだろうと言っている。
以下、田中角栄の国鉄改革論です。中曽根康弘が行った味も素っ気もない国鉄改革とは、全く違います。 ● 地方の赤字線は廃止すべきではない
● 国鉄は、多角経営を許して民営化すべき
● 国鉄再生には、地域、農村、僻村開発(列島改造)をすべき 国土の有効利用のためには、すなわち過疎の農村に人々が住めるためには、農村地域に工業を導入する必要がある、ということだ。
● 分離は北海道と四国のふたつとし、それ以外をひとつの会社とする ● 国鉄改革と列島改造は一体
● 国鉄改革は列島改造に連動し、さらに内需拡大にも連動
● 実際の国鉄改革はどうだったか。
「国鉄分割民営化」 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)