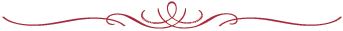「今太閤」と呼ばれた立身出世の人から、汚職事件の罪人へ。政界の頂点から犯罪の奈落に一気に叩き落とされた故・田中角栄の元秘書として、その人柄を知り尽くす早坂茂三氏が若い人を対象に書いた「おやじ説教集」。この世の酸いも甘いも噛み分けたおやじ様の言葉に耳をかたむけて。
捨てる神に拾う神 もっと無器用に生きてみないか (集英社文庫)
§ 早坂茂三の言葉
『若い者はしくじる。右も左も分からないのだから、失敗は当たり前だ。老人の跋扈は国を滅ぼす。しかし、青年の失敗は国を滅ぼさない。私はそう思う。だから、若い者はやりたいことをやったらいい。ウジウジして、周りに気兼ねする必要はない。そして、どつかれ、こづかれ、けつまずき、ひっくり返り、糞小便を浴び、人に裏切られ、だまされ、カスをつかみ、「われ誤れり」と歯ぎしりをする。それを繰り返しやって、たくましい、しなやかな知恵を身に付けることができる。この修羅の巷で生きていけるようになる。出来上がりのワンセット、ワンパッケージの知恵など、この世には存在しない』
悪評を恐れることはない。人の口に戸は立てられない。世の中はやきもちの大海だ。目立つやつは目障りになる。態度のでかいやつには風当たりが強い。ところがまた、この世間の悪評ほど移ろいやすいものはない。一匹のいぬが吠えれば、ほかの万匹の犬が、わけも分からずにいっせいに吠えたてる。日本はそういう国だ。そして風向きが変われば、犬の鳴き声は一気にとまる。世間は手のひらを返す。世評、何ぞ気にすることあらん。顔を上げて吾が道を行く。頑固でもいい。妥協せず、自ら恃むところさえあれば、自分の本心だけは譲らないという気構えでやれば、何とかやれる。そうして私は生きてきた。
国乱れて忠臣現れ、家貧しくして孝子現る。
失敗はイヤというほど、したほうがいい。死にさえ至らなければ、何回も繰り返しひどい目に遇ったほうがいい。やけどもしたほうがいい。五針も十針も縫うような大怪我をしたほうがいい。そうするとバカでないかぎり、骨身にしみる。次回から不必要なリスクを避けるためにどうしたらいいか、反射神経が身についてくる。判断力、分別ができてくる。これが成長の正体だ。人間にとって一番大切なのは情だ。世の中には志を果たせない人、運が悪くてチャンスに乗れない、つかめないという人が溢れ返っている。こういう人たちに対して、本当にいたわり、優しさ、侍でいえば『惻隠の情』が持てるかどうか、これで人間の上等と下等とが分かれる。
人はどういう話に感動するのだろうか。嘘はダメだ。作り事の話をしても、人はすぐ嘘を見破る。世の中はそれほどバカばかりではない。やはり、自分の実体験を下敷きにして、そこから話を進めたらいい。理屈をあまりくどくど言わないことだ。抽象的な話は整合性があり、起承転結もきちんとしている場合が多い。後で速記録を取り寄せてみても、非のうちどころが少ない。そういう話は確かに存在する。だが、それを言葉として聞く時、聞くほうはなかなか大変だ。たとえ話の筋道が整っていても、理屈というものは左の耳から右の耳に流れていく。感性に響いてこない。心に訴えるものがない。なるほど、はい、わかりました。話が終わって、ヨイショと立ちあがり、たまっていた小便を便所でシャーっとやって、ドアを開けて建物の外に出ると、九割は忘れている。
人をとらえる話は、そうした性質のものではない。自分はこういうことでトチったという失敗談とか、こういうことを誰かに教えてもらった、そして、それは真実であったというエピソード、事実を中心にして話す。そうすると相手はとても覚えやすい。記憶のひだのどこかに止まりやすい。自分が胸打たれた話を家や職場に土産として持ちかえる。家族や仲間に伝えて、一緒に感動を反芻する。いい話、本当の雄弁とは、もともと、そうしたものだ。
「宮沢喜一に衆議院の予算委員会で質問する。すると、彼はあの小さな身体をチョコマカ動かして出てくる。答弁席に両手をつき、噛んで含めるように答えてくれる。役所の資料を一切、見ないで、面倒な法律でも数字でも自在にこなし、こともなげに答弁する。ニコニコしながらね。聞きながらオレは、この人は何とできる人かと思う。この人は何でもかんでも実によく知っている。オレはこの人に比べたらいかに不勉強で、いかにボンクラで、いかに至らないか、いやというほど思い知らされる」。
ただ、自分も代表質問を終わって、自席に戻り、そして彼の顔を見てつくづく思うことがあるという。「おい、宮さん。今夜十時ごろ、オレの知っている小さな赤提灯の店に来ないか。おかみは懇意にしているし、口も固い。おかみの部屋が二階にある。布団が置いてあるようなところだ。あそこじゃ、どんなことをしゃべったって、絶対に大丈夫だ。あそこで今晩、二人で上着を脱いで、ネクタイをはずして、時間を気にせず、とことん話そうや。自民党をどうするか。社会党をどうするか。本当の話を徹底的にしゃべろう。宮さん、都合をつけてくれ――。だが、こういう電話をかける気には絶対にならない相手だ」
私は、それが宮沢氏の責任だとは思わない。相手にそういう印象を与えるということが、宮沢喜一の罪咎とは思わない。しかし、相手も感情を持った人間だ。質疑応答していれば、当然、何かを感じるし、この感じることがいけないとは言えない。とすれば、相手にそういう思いを抱かせるということは、やはり、その人にどこか至らない面があるという証明ではないか。
この世には、他人に対して無遠慮に聞いてはいけないことがある。「出身校はどこか」、「今、どこで何をして働いているのか」――この二つがいい例だ。学校に行きたくても事情があって進学できなかった。胸を張って「勤め先はここだ」と言えず、肩身の狭い思いで毎日、必死に働いている。そういう人たちが日本にたくさんいる。
どんな小さな会社でも、いい仕事をしていれば生きていける。良質で、値段が安く、長持ちして、後の面倒見のいい商品を作りさえすれば、あるいは、同じようなサービスを提供することができれば、お客は必ずつく。これが資本の論理というものだ。意地を張っていると言われるかもしれないが、意地というのは、人間が生きていくうえでの背骨だ。背骨があるから頭が支えられている。背骨があるから、血液のもとになる骨髄液が、日夜不断に再生産されていく。意地というものを人間から取れば、それは背骨なし、つまり、クラゲになってしまう。クラゲは潮の流れに身を任せて漂うだけだ。
世の中は、いつでもどこでも利口千人バカ千人である。本当はバカ十万人がひしめいている。だから、万事、多数決の社会では、一時は受け入れられない。しかし、今、身のこなしが軽やかで、何もかも分かっているような顔をして、人の顔色を見ては達者にスイスイ動き回っている若い人たちがたくさんいる。そういう背骨のないクラゲが群れている。その種の若者を私は好まない。
佐藤栄作は竹下登にこう語った。「政治家の世界は100メートル競争ではない。マラソンだ。最初から優勝しようと思うな。自分のペースで走れ。自分の身柄に合った早さで、自分の心臓の強さに合わせて走れ。トップランナーは、子供の投げたバナナの皮にすべって転ぶ。二番手と三番手は、あまりに競い合って、コーナーを曲がる時に身体がぶつかり、二人でひっくり返って、アキレス腱を切る。四番目の走者は下痢になって、テープの100メートル前で、もれそうになってしゃがんでしまう。そうすると、竹下君、十番目、二十番目では困るが、五番目くらいのところにぴったりつけていけば、最後に君が勝つことになる」
田中角栄が私にこう言ったことがある。「頂上を極めるために、いちばん大事なことは何だと思うか」。「むろん、味方を作ることです」。「それはちがう。無理をして味方を作ろうと思えば、どうしても借りを作ることになる。相手に愛想笑いをする。腰を引いてしまう。揉み手をする。すり足になる。そうしてできた味方は頼りにできるのか。できない。無理して作った味方は、いったん、世の中の風向きが変われば、アッという間に逃げ出していく。そうしたシロモノがほとんどだ。だから無理をして味方を作るな。敵を減らすことだ。自分に好意を寄せてくれる人たちを気長に増やしていくしかない。その中からしだいに味方ができる。そのためには、他人、とくに目下の人をかわいがることだ。誰にも長所がある。それを引き出すことだ。いばるな、どなるな、言えば分かる。手のひらを返すような仕打ちをするな。いつでも平らに人と接することだ」。
『人には馬鹿にされていろ』
人の口に戸は立てられない。人間は三人寄れば、そこにいない人の悪口を言う。バカにする。欠席裁判をする。あるいは、仲間内みんなで集まって酒の肴にする。とかく、そういう具合になりがちだ。弱い人間の最大の楽しみは、他人の悪口を言い合うことだ。上司の悪口、あの社長、部長、課長、ぶっ叩いてやる。あいつは偉そうなことを言ってるけれども、薄皮一枚ひんむけば、こんなことだ。そんなこともふくめて、欠席裁判をすることが世間にはとても多い。それは人間の本性の一つだ。
私がここで思うのは、人にバカにされてもいちいちカッカするな――ということだ。相手だって、こっちをぶち殺してやる、社会的に葬ってやるというやつを除けば、心底、ひきずりおろすために悪口を言ってるわけではない。楽しみ半分だ。それにいちいち目くじらを立てていたのでは胃を壊す。欠席裁判にされているのではないかと思ったら、一日中、悪口を言いそうなやつの側にへばりついていなければならない。そんなことは無駄なことである。
田中角栄師匠が、私に言ったことがある。「商売も政治も結局、同じことだ。大勢の人に集まってもらわなければ、話にならない。大勢の人の気持ち、お心を頂戴できなければ、吾が思いを遂げることはできない。自分だけがオレは東京帝国大学出身だ、東大だ、オレは一番賢いんだ、ほかのやつはバカだ、オレのところに寄ってこないのは、そいつらがバカだからだ。これを銀座4丁目で空に向かって叫んだところで、どうなるか。カラスが飛んできて、その開けた口の中に糞をたれて、アホウ、アホウと言って飛んでいくだけのことだ」。
人は誰でも世にスタートしたときは、右も左もろくに分からない。だが、風雪の歳月を経て経験を積み、百石もの汗を流した甲斐あって才能も花開き、時流にも恵まれて、世間が丁重に迎えるということになると、人間は普通、鼻が下を向かないで上を向くようになる。目線が高くなる。そうなれば本人の行く手に黄色の信号がチカチカ点滅する。いばりくさって世の中は渡れない。そのうち誰も相手にしなくなる。
若い者は粗相する。だが、それは当たり前だ。経験が浅いのだから、何かにつけて失敗する。しかし、経験が浅い者の失敗に、いちいち目くじらを立てることはない。自分だってそれ以上に失敗の連続だったじゃないか。叱る時には、誰もいないところでガッチリやったらいい。どんなささやかなことでも、褒めるときには、大勢のいる前でドンと褒めてやることだ。そうすれば若者は奮起する。いつか必ず知遇に応えてくれる。
田中角栄という人は、人の顔を見れば、「おい、メシは食ったか」と言っていた。口癖である。表現は乱暴だが、相手は春風のように聞いた。「メシは食ったか」。初心忘れず、この言葉は角栄の体験から発した。すきっ腹のつらさ、切なさを知っていたからである。「おい、角さん、おれが昼飯も食えないほど貧乏してると思ってバカにするのか」。こう言って怒った人は一人もいない。よほどのひねくれものでもなければ、「メシまで心配してくれるのか、うれしい。ありがたいことだ」――そう思う。この世の中は一皮剥けば義理と因縁と情実と不公正の寄席細工だ。もちろん、四つの要素がすべてではない。しかし、世間の実態はそういうものだということを、腹にしっかりたたみこんでおいたほうがいい。