| 「田中は政治家ではなく、土方だと言われる。ナニを抜かすかだッ。でも、こう言われるとここ(新潟)の人は怒るわねぇ。そうでしょう、皆さんッ(拍手)田中は入広瀬(北魚沼郡)の村長と組んで、ここばかり公共投資するとも言われた。ナニをほざくか、こう言いたいよなぁ。当たり前のことだッ。東京には水がない。その水をこっちがくれてやっている。そういうところに公共投資をしてナニが悪い(大拍手)皆さんッ、この100年は太平洋側の100年だった。しかし、これからの100年は日本海側の100年です。どんどん生活が良くなる。私はねぇ、新潟に20ヶ所のダムを持ってきている。なぜだか、分かりますか。関東が水不足になるからであります。しかし、こっちには水があるわねぇ。雪は水になり、水は力なのであります。東京の大企業は、どんどんやってくる。それが国道17号線であり、上越新幹線なのであります。もっとも、新幹線ができると、この辺の土地は値上がりするねぇ。そのときは皆さんッ、あんまり土地で儲けちゃいかんよ(大爆笑)」(1976.12月、立会演説会)。 |
| 「野党はいつも何だかんだ言っておるが、気にしなくてもいいですよ。まぁ、アレは三味線みたいなもんだ。子供が一人、二人ならいいけど、3人、4人おると、中にはうるさいのもいるもんですよ。ねぇ、おっかさん。そうでしょう(*笑)」(1978.10月、立会演説会)。 |
| 「皆さんッ、昭和60年になると、今、トン当たり60円の水が100円以上になる。東京では400円ぐれぇになるのではないですか。三越デパートの岡田茂社長は私の友人だが、この岡田君が『デパートではお客の1割が物を買ってくれればいいんだ』と言っておった。ところが、『この頃はどうも困った』と言うんです。岡田君に聞くと、『1万人の女性がデパートに入って1000人は買い物をしても、残る9000人は化粧室に入りに来る』と言うんだな。『一人当たり25円も損をしてしまう。90000人に同じことをされたら、儲けなんかフッとんでしまう』とこぼしておった(爆笑)。皆さんッ、笑っておってはダメです。いや、笑いの中に真実があるッ。いいですか。新潟には雪がある! 雪は水だ! 私の言いたいのは水ッ。水はそれだけ大事なんです。生活の基本だ。皆さんッ、雪は資源、いや財産ということなんだッ」(1980.3月、越山会総決起大会)。 |
| 「私が総理のときですがね。東京都議会で自民党が3分の1ではマズイと思ったんです。暑かったが、頑張りましたよ。田中を、アイツは選挙が大好きなんだという奴がいるが、冗談じゃないねぇ。たんぼの草取りみたいに頭下げて、ゴマすって歩くのを誰が好きかッ。まぁ、美濃部都政を倒そうと思っただけです。ところが、マゴマゴしているうちに、田中の方がひっくり返ったッ(注、タンがのどに詰まって一時、呼吸困難に陥ったこと)。戦争に負けて35年ッ。東京の道路整備は遅れた。交通マヒで物価も上がった。『物価のミノベ』た? 冗談言うんじゃねぇ! 皆さんッ、評判悪くても自民党がずっとやっているのはなぜか。まぁ、酒癖は悪いが、働き者だから亭主を代えないと思うおっかさんの気持ちと同じだねぇ」(1980.9月、越山会大会)。 |
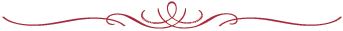
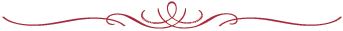
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)