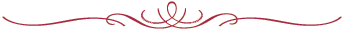
| 田中角栄政治語録 |
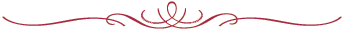
更新日/2023(平成31.5.1栄和元/栄和4).2.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、田中角栄の政治語録を採り上げる。今のところ順不同であるが、噛締めて味わいたい。下手にマルクス、レーニンに被れるよりよほど値打ちがあるのではないかと思っている。一般に誤解されているが角栄は無学なのではない。大学を出なかったと云うだけで、例えば二宮金次郎(尊徳)、松下幸之助のように土着的な日本思想を背景にした実学を真剣に学んでおり、そこから思想を汲みだしている。マックスウェーバーが激賞するところの真に英明な政治哲学者であったと評し遇するべきではなかろうか。この理合い筋合いが分からない自称インテリによる角栄批判が多過ぎて困る。 2004.11.30日、2010.06.13日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| 【角栄の政治家の原点論】 | |
戦後の代議士立候補につき、恩師の草間先生に云った言葉。
|
|
| 「政治家になると思っていなかった。日曜日に釣りに行って、ああ川の流れがきれいだし、景色もまたいい。それでついそこに住まいを構えて魚屋になってしまった。そんな感じで政治家になってしまったとも言える。議員というものは、努力、勉強すれば、大臣、幹事長まではなれる。しかし、総理総裁となるとそういうわけにはいかない。それは『運』による」。 | |
|
「住宅は一家の団欒所、魂の安息所、思想の温床。家があるならば、それからいろいろなことを考えてやっていける。働く人たちに家を与えずして、何が民主主義か。政治の仕事は、国民の邪魔になる小石を丹念に拾って捨てることと、国の力でなければ壊せない岩を砕いて道をあけること。それだけでいい」。
|
|
| 「俺の目標は、年寄りも孫も一緒に、楽しく暮らせる世の中をつくることなんだ 」。 | |
| 「何か人様の為に、社会的に意味のあることをしないと、運命に対して申し訳ない」(戸川猪佐武「田中角栄猛語録」)。 |
| 【政治家及び政治能力論】 | |||||||
角栄は、政治家たる所以の任務を次のように諭している。
1952(昭和27)念から角栄の秘書を勤めた佐藤昭子女史の「田中角栄-私が最後に伝えたいこと」は次のように記している。
角栄はかく述べ、側近の早坂茂三氏や新聞記者に常日ごろ語っていた。大衆政治家の面目躍如の言であろう。その上で次のように抱負している。
次のようにも述べている。
|
| 【政治家の能力について】 | |
角栄が政策研究に余念がなかったことを裏付ける福田赳夫の角栄評がある。
|
| 【総理の器】 | ||||
総理の器について次のように述べている。
首相になった時の次の言もある。
|
| 【首相権限、首相能力について】 | ||
自民党の加藤紘一元幹事長は、新著の「テロルの真犯人」(講談社)で、「言葉には、おそろしいほどその政治家の地金がでる」と述べ、大物政治家たちの印象的な一言をまとめている。その中に角栄語録が採り上げられている。1972.7月、田中が福田赳夫との激しい総裁選を制した直後の記者会見で、記者の一人が、「佐藤政権で幹事長などを務めたあなたは、佐藤栄作前総理とどこが違うのか」と質問した。田中は一瞬キッとなって次のように答えた。
民主党の藤井裕久前代表代行(元蔵相)は、田中政権の官房長官秘書官を務めていた時、田中が次のように述べたことを明らかにしている。
|
||
|
| 【後継指名について】 | |
後継指名をせずに辞職したことにつき、次のような後悔の念を吐露している。
|
| 【大衆政治論】 | |||||||||
新潟出身の友人に連れられて田中角栄さんの目白の家に行ったとき聞かされた話。 角栄は政治の任務について次のように述べている。
|
|||||||||
|
| 【政治家の発言について】 | |
「政治家の発言」について次のように述べている。
|
| 【政治における考え方の基本について】 | ||||
政治における考え方の基本について次のように述べている。
|
| 【議会における討論の重視について】 | ||||
角栄は、「議会討論を重視し、率先した」。角栄の議会に対する態度を物語る当人の国会弁舌がある。1947年、初めて登院した衆議院本会議で「自由討議」(フリートーキング)をテーマにしての演説である。
「自由討議」(フリートーキング)制度は、新憲法が制定された当初、国会法第78条において「各議院は、国政に携わる議院に自由討議の機会を与えるため、少なくとも、二週間に一回その会議を開くことを要する」と定められ開始された。ところが、わずか数回行われただけで、1955年の国会法改正によって実益の無い制度として削除された。このようにして、国会から自由清新な議論が消えていった。これについては、「自由討議」でもう少し詳しく見ておくことにする。 |
| 【政策論争好みについて】 |
| 角栄は、政策論争を好んだ。若手議員を掴まえては政策論争したと伝えられている。政策がおかしければ、おかしいとはっきりと口にした。発想力の豊かさに感心したと伝えられている。自然と門下生教育となった。 |
| 【野党批判論】 | ||||
次のような野党批判論、批評論を遺している。
単なる反対、反対の為の反対政治論をかく批判している。
|
| 【責任政治論】 | ||||
角栄は”舌先三寸”政治を嫌った。次のように述べている。
|
| 【現実政治論】 | |||||||
角栄は、「理想と現実」について次のようなコメントを残している。
|
| 【体当たり政治論】 | ||||||||||||||||||
日中国交回復交渉の際の角栄の言葉。台湾国府の取り扱いが揉めにもめて一頓挫していた時である。二日目の夕食は日本側の田中、大平、二階堂、外務官僚・橋本の4人だけが共にした。田中はマオタイ酒をぐいぐいと呑む。大平は交渉不調のためかシュンとなっており、食事に箸をつけなかった。田中はそんな大平に言う。
この時、橋本は角栄を凄い人だと思った、と伝えられている。この大仕事はこの人にしか出来ないと、橋本はこの時痛感したとも伝えられている。 |
| 【自民党論】 | |
角栄の真骨頂とも云うべき軽妙洒脱な自民党論に次のような言い回しが有る。
|
| 【田中派論、公約責任論】 | |||
田中派論、公約責任論について次のように述べている。
|
| 【公と私情の分別について】 | |
|
|
1980.5.16日、大平内閣不信任決議を受け、この日たまたまホテル二ューオータニで行われることになっていた田中派の「参院立候補予定者激励会」を急きょ「田中派緊急総会」に切り替え、角栄は、その席上、次のようにぶった。
|
| 【陳情政治について】 | |
「議会政治家の申し子としての角栄その2、陳情采配能力」に記す。
|
| 【議員辞職運動について】 | ||
1982(昭和57).5.17日、角栄は、日共とマスコミの一体となった政治訴追、議員辞職運動に対して次のように批判している。(「週刊現代2009.8.22-29日号」の田崎史郎の「懐かしい日本人第1回 田中角栄」より)。
1984(昭和59).8.31日、角栄は次のように批判している。(「週刊現代2009.8.22-29日号」の田崎史郎の「懐かしい日本人第1回 田中角栄」より)。
|
| 【「田中首相が外人記者クラブで記者会見】 | |
| 1974.10.22日、田中首相は、東京外国特派員協会の外人記者クラブで記者会見した。会見直前、「文芸春秋11月号」の立花論文やその関連資料の英訳版が何者かによって特派員たちに配布され、会見のテーマは「金脈問題」に関する質問攻めの場になった。記者の質問は、「文芸春秋」記事に集中し、一種査問委員会のような雰囲気となった。 この外国人記者クラブでの会見で、日本のメディアが一斉に動き出した。宮崎学氏の「民主主義の原価」には、「いわば外圧をきっかけに、日本のマスコミが一気に金脈報道に乗り出したのだ。R氏は、この記者会見を仲介したのは共同通信記者だったが、その記者はCIAのエージェントであったと話している」とある。 田中首相の予想を超える「査問会見」となり、しどろもどろの弁明となった。次のように述べている。
|
| 【田中政治の無理について】 | |||
「2チャンネル田中角栄№4」より転載する。
|
| 【宗教的倫理と教育的倫理と政治的倫理について】 | |
宗教的倫理と教育的倫理と政治的倫理について次のように述べている。
|
| 【法、法匪批判について】 | ||
法、法匪について次のように述べている。
|
| 【政治、宗教、教育について】 | |
政治、宗教、教育について次のように述べている。
|
| 【「女を味方につけろ」について】 | |
「女を味方につけろ」について次のように述べている。
|
| 【数字と統計】 | ||
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)