|
【角栄の流儀―田中元首相没後20年(中)】官僚ひきつけた操縦術
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131130/stt13113008350002-n1.htm
2013.11.30 08:24
昭和46年に53歳で通産相に就いた田中角栄は、通産官僚たちをこんな就任スピーチで笑わせた。「私は東大を出ていない。しかし、仮に東大を出ていれば卒業年次は(昭和)16年前期だ。今の次官は16年後期。私は大臣として初めて後輩の次官と相まみえることになった」。田中は尋常高等小学校しか出ていない「たたき上げ」が売りだ。その田中に東大などそうそうたる大学を出たエリート官僚たちが数多くひきつけられた。田中の持つ権力、発想力、資金力…。しかし、理由の一つは間違いなく巧みな官僚操縦術だ。
田中の通産相、首相時代に秘書官を務めた元通産事務次官の小長啓一は「就任スピーチは『役所が入省年次を重視する社会だということは、ちゃんとわかっているぞ』という意思表示だった」と解説する。田中は官僚の名前と顔をこまめに記憶していた。「顔色が良くないぞ。昨晩徹夜したのか。わるいな」などと声をかけた。せっかちで知られる田中だが、プライドの高い官僚たちに細かく指示したり、怒鳴りつけたりせず、遠回しな物言いで自発的に取り組むよう仕向けてもいた。従わない官僚がいれば肩書の上では出世させ、本省から地方に飛ばしたこともある。そんな人事が一例でもあれば、よほどのことがない限り閣僚の影響力が強まるのは当然だ。
自民党の野田毅税調会長は田中蔵相時代の39年に大蔵省に入省した。田中のライバル、福田赳夫との「角福戦争」の影響は省内にも影を落とし、「田中派、福田派があり、次官レースにも大きな影響があった」と証言する。新党大地代表、鈴木宗男は田中にこう教えられたことがある。「いいか。世の中は三すくみだ。役人は政治家に弱い。政治家が人事を握っているからだ。しかし、役人は国民に強い。国民は政治家に強い。だから世の中はうまくいっている」。
◇
小長の記憶に今も鮮やかに残る逸話の一つが、46年に通産相として臨んだ日米繊維交渉だ。米国は態度を硬化。沖縄返還交渉が大詰めを迎えた時期で早期決着が望まれていた。「事態が悪化しているが、これで良いのかね」。田中は次官らにこう述べ、複数の解決策を練らせた。輸出規制を決め、打撃を受ける国内繊維業者向けに約2千億円の対策費が必要と見定めると、すぐに首相の佐藤栄作に電話。予算折衝のため、名刺に「主計官殿2000億円よろしく頼む」と手書きし、大蔵省の担当者に届けさせた。その場に居合わせた小長は「『すごい大臣だ』とみんなが思った。米側との交渉では官僚のレクチャー以上の議論をしてくれ、誠に頼もしかったが、収拾段階のさばきも見事だった」と回想する。繊維交渉は「決断と実行」を旨とする田中の成果のひとつといえる。一方で、竹下登政権の牛肉・オレンジ交渉対策費、村山富市政権のウルグアイ・ラウンド対策費など、その政治手法は受け継がれ、財政悪化への扉を開いた。
◇
田中が47年に出版した「日本列島改造論」は90万部のベストセラーになった。人口と産業を大都市から地方に分散すべきだとし、工業の再配置、交通や情報通信のネットワーク形成の必要性を説いた。そこには田中の現場感覚から派生した都市から地方への「富」の再分配という“思想”がある。
ロッキード事件で田中の弁護団の一人だった元法相、保岡興治は「今は現場主義の政治主導より国家経営というレベルに高度化しなければいけなくなった時代。新たな事態に対処するため、政治が優秀な官僚に目標を与え、理念を認識させなければいけない」と指摘する。田中の首相秘書官だった元駐仏大使、木内昭胤(あきたね)は「今の政治家にはビジョンがない」と嘆く。ただ、こうも付け加えた。「日本は非常に良い国になった。だから中長期的なビジョンを持ちにくくなっているのではないか」。その言葉は、現役世代をかばうようにも聞こえた。(敬称略)
|
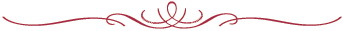
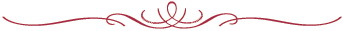
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)