| 秦野章氏逝去に関して雑感 |
れんだいこ |
2002/11/09 |
元警視総監にして法相を歴任した秦野章氏が2002.11.6日死去した(享年91歳)。秦野氏の経歴は次の通り。1937(昭和12)年、日大専門部(夜間)卒、1939(昭和14)年に高等文官試験に合格、内務省に入り警察畑を歩む。大阪府警刑事部長、警視庁刑事部長、警察庁警務局長などを経て、1967(昭和42)年私大出身者としては初の警視総監に就任した。
1971(昭和46)年自民党に担がれ東京都知事選に出馬し、美濃部亮吉知事に闘いを挑んだ。東京開発計画を盛り込んだ「4兆円ビジョン」を掲げたが、美濃部氏に100万票を超える大差で敗れた。この時「昭和元禄田舎芝居」の名ぜりふを残している。
1974(昭和49)年、参院神奈川地方区(当時)から出馬して当選、以来、2期12年を務める。自民党では無派閥を通し、一匹おおかみ的存在で、ベランメエ口調で知られた。
「ロッキード事件に関する秦野章質問」で、「コーチャン嘱託尋問は違憲」との見解を披瀝した。その論点は、①・ロッキード事件での検察の捜査手法批判、田中元首相の別件逮捕に対する批判。その弁として「嘱託尋問は違法」がある。②・過度な政治倫理要請批判。その弁として「政治家に古典道徳の正直や清潔などという徳目を求めるのは、八百屋で魚をくれというのに等しい」の名文句がある。③・マスコミのペン暴力批判。その弁として「マスコミによる巨大なリンチだ」の名文句がある。
1982(昭和57)年には、第一次中曽根内閣で法相に就任。法相時代の1983(昭和58)年10月には、ロッキード事件で逮捕された田中元首相が1審有罪判決を受けたが、元首相を擁護する立場を貫き、ロッキード事件・裁判批判発言などで物議をかもした。著書「逆境に克つ」で次のように述べている。
| 「この(ロッキード)事件で、司法・検察が日本の制度に無い刑事免責などを採用した違法な手続きを考えただけでも、一審裁判で無罪になる可能性が全く無いとは云えない。一審が仮に無罪となれば、その際、検察はむろん控訴するだろう。その時こそ検察庁法に基づく法務大臣の指揮権を行使し堂々と控訴を差し止めれば良い、と考えていた。それだけは法相の権限としてやるはらづもりでいた」。
|
この年の東京弁護士会の研修会で、自由法曹団の代表的弁護士である石原泰・氏は、秦野氏の指摘に対し次のように評価の弁を述べている。
| 「ロッキード事件の矛盾を指摘することは、本当は我々がやらなければいけないことだ。ただ、このことを一人だけ言っている人間が居る。それは秦野章だ。この件に関しては、秦野はまさに正論を述べている」。 |
1986(昭和61)年に立候補せず政界を引退した。政界引退後は、持ち前の歯にきぬ着せぬ発言で、政治評論家として活躍、雑誌「正論」のメンバーだった。1987(昭和62)年11月には勲1等瑞宝章を受章した。
産経新聞に拠れば、初代内閣安全保障室長・佐々淳行氏は≪乱世の名総監≫として次のように回顧した、とある。「学生運動が吹き荒れた昭和四十五年六月までの第二次安保闘争で指揮をとった名警視総監。秦野総監でなければ、あの警察戦国時代の修羅場は乗り切れなかった。決断力と責任感あふれる人。第二次羽田闘争や東大安田講堂事件などでは機動隊員の装備などを自らチェックし、全責任を自分で負うと突入部隊を鼓舞。さらに機動隊長や中隊長には東大出身のキャリアを配属するなど、指揮官も隊員も区別しない運命共同体というべき結束を図った。この間に負傷した警察官は一万二千人にも上ったが、離職者はゼロ。まさに『乱世の雄』。秦野総監のもとで警備課長として闘ったことを誇りに思う」。
秦野氏の生き様は非常に興味深く、後藤田氏との関係なぞもう少し触れて欲しいところだ。それはそうと、佐々淳行氏は60年代後半の労・学運動を「あの警察戦国時代の修羅場」と表現している。これが実際だったのだろうと思う。
この時、中曽根の弁を借りながら「過激派泳がせ論」をぶって火消しに懸命になっていたのがどこの党だろう。全共闘運動の個々の行動を是認する必要は無いが、今から思えばムーブメントづくりには成功していた戦後左派運動の第三ルネサンス期であっただろう。
それに対置するかのように「70年代の遅くない時期に民主連合政府構想」を打ち出したかの党は、その時期が来て実際に為したことは革新共同社共戦線、青年運動の担い手達、労働戦線、その他大衆運動全般に対する分裂策と弾圧策の強権発動であった。
こういうことを対自化させておく必要があるのではなかろうか。今又同じような念仏を打ち出しているが、それを良しとする者もかなり脳天気な御仁であろう。れんだいこは氷嚢無しには語れない。 |
| 【元警視総監・秦野章・氏の「何が権力か」について】 |
元警視総監・秦野章・氏の「何が権力か」(講談社、1984.7.20日初版)の冒頭で有益な所論が為されているので転載しておく。
私がこれまで、官僚として、あるときは警視総監として、またついこの間までは法務大臣として、いつも考えてきたことは、法治国家における法と政治の関係はどうあるべきなのか、ということだった。法と政治は性格がまるで反対だ。法の世界では、目的のために手段をきちんと選ばなければならない。難しくいえば、デュープロセス(法の適正な手続き)を守らなければならない。これに対して政治の世界では、時として、目的のためには手段を選ばない、という発想が許される。一種のマキャベリズムがある。
ちょっと見には水と油のような、この法と政治が国家の権力中枢を構成している。これが法治国家の一面の実情である。
ふだんは、法と政治はまるで一卵性双生児のように、なんの違和感も無く共存している。しかし、時折、この二つは不協和音を発することがある。たとえば、超法規問題がそうである。(中略)
政治も必死だが、遵法も必死でなければならない。超法規は法と政治の必死のせめぎあいの結果として出てくる緊急避難措置なのである。大げさにいえば、国家の存亡に関わる非常事態であるが故に、目的のためには手段を選ばない政治が法を超え、超法規措置がとられるのだ。
いいかえると、法治国家とはいつても、その大前提が国家の存続である以上、ギリギリのところでは、国家の存続を直接の任務とする政治に、それは従属せざるをえないのである。そしてこのような場合には、事後に国会の承認を得るようにするのが、事の重さからいって政治の筋道を貫くことだと思う。この点、日本のやり方はまだ未熟だ。 |
|
|
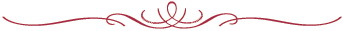
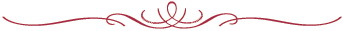
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)