|
角栄は、官僚の優秀さを認めたうえでその限界も知り、官僚に使われるのではなく、使いきろうとした。次のように述べている。
| 概要「大蔵省の役人というのはそりゃ優秀です。正しいデータさえ入れればちゃんとした結論を出してくる」(1981年「月刊ペン」) |
| 「官僚には、もとより優秀な人材が多い。こちら(政治家)がうまく理解させられれば、相当の仕事をしてくれる。理解してもらうには、三つの要素がある。まず、こちらのほうに相手(官僚)を説得させるだけの能力があるか否か。次に、仕事の話にこちらの野心、私心というものがないか否か。もう一つは、彼ら(官僚)が納得するまで、徹底的な議論をやる勇気と努力、能力があるか否かだ。これが出来る政治家なら、官僚たちは理解し、ついてきてくれる」。
|
1964年、44才で大蔵大臣に就任した角栄は、時間、局長以下、大蔵省の幹部を前に次のような挨拶をしている。
| 「私はご承知のようにし、小学校の高等部しか出ていない。しかし、世の中の経験は、多少積んでいるつもりである。まぁ、諸君は財政、金融の政治家だ。これからは、もし私に会いたいときは、いちいち上司を通して来ることは無い。こう思う、これはおかしい、これを考えてくれなんてことがあれば、遠慮せずに来てくれ。そして、国家有事の現在、諸君は思い切って仕事をしてくれ。これは局長も課長も同じだッ。私はできることはやる。できないことはやらない。事の成否はともかく、結果の責任は、全て大臣であるこの田中がとる。今日から、大臣室のドアは取っぱずす!以上」。
|
マックスウェーバーの言に、「フランスやアメリカの腐敗した官吏制度、イギリスの非常に侮辱されている夜警統治、部分的には腐敗した官吏制度をもって民主的に統治されている国は、高度に道徳的な官僚制よりはるかに大きな成功をおさめてきた」というのがあるが、まさにマックスウェーバーの言を地で行ったのが角栄政治であった。
次のように評されている。
| 「田中は、官僚をつかった。が官僚の言いなりになどなりっこない。優秀な官僚の知識を利用するが、最終的には自分が上のほうから政治的に判断する。それが、本来の政治家の在り方だと思う。今でこそ政治は官僚指導と言われているが、田中の時代は、短い期間ではあったが政治家主導でなしえた」。 |
| 「官僚の使い方がうまかった。田中は、官僚の話を聞くのがうまかった。それも、事務次官や局長など上のクラスの人だけではない。必要とあらば、例え一課長とも気軽に会った。官僚は、自分の担当については頭で整理できている。その考えを上手に聞き出し、時には政策などに活かした。その意味で、官僚の使い方がうまかった」。
|
角栄の秘書の一人早坂茂三氏は、「宝石・平成元年12月号」の「」の中で次のように評している。
| 「彼は役人をよく知っていた。自分が組む相手がどういう属性をもっているか。このメリット、デメリットは何か。役人をどう使っていけば、給料の10倍も20倍も働くか。どうすれば裏切らないか。これを良く知っていれば、役人の力をフルに引き出すことが出来る。これが、頭領の器というものでしょう。田中は、『役人は生きたコンピューターた』と、よく僕にいつていた。『役人にはハッキリした方向を示して、ガイドラインをせいかくに与えてることだ。インプットする情報、数字、ファクトが間違っていなければ、コンピューターは正確に機能して、何万人分もの能力を一瞬のうちにやってのける』と」。 |
大蔵大臣就任早々の頃の大蔵大臣室での、田中角栄と藤原弘達の会話。
| 「角さん、大蔵省というところは、一高−東大−大蔵省人脈といってね、大体頭のいい奴が集まるところなんだ。福田なんてその最たるもんだな。そういうところに、あんたのような西山町の馬喰(ばくろう)のせがれで、尋常高等小学校出が大臣になって、上から抑えようったって、到底まともにいうことはきかんぜ。どうやってやるつもりかね」。田中はニヤッと笑って、平然と答えた。「なに、たいしたことはないさ」。「どうして?」。「役人という奴は、要するに、エライ地位につきたい動物なんだ。自分のことを考えんで、日本全体のことを考えているやつなんて、本省の課長までさ。部長から局長、次官になるにつれて、大臣から何か言われて、それに反対するのは出てこれないね。だから、ちょっとお小遣いをやるとか、ちょっと出世させてやる、いいとこ連れて行ってやる。選挙に出たいといったら世話してやる---。そんな具合に、面倒見て大事にしてやれば、ちゃんと従うもんさ。角栄流の人間操縦術というのは、大蔵大臣になったって、同じだよ」。大蔵官僚の監視の中で、そのようなことを平然というものだから、さすがの私もいささか驚いてしまった---(角栄、もうええかげんにせんかい)。 |
|
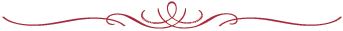
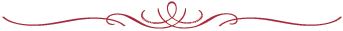
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)