| 「僕は、会議も時間通りにピシャッと片付ける。田中派の会議なら、最後は僕が一票入れて決める。リーダーなら、それくらいの見識がなくてどうする。その上で、僕の一票で決めたんだから、一週間ほど塩漬けにしておく。その間、異議が無かったら決定となる。当たり前のことだろう」(小林吉弥「田中角栄処世の奥義」44P)。 |
| 「会議の長さは出席者数の二乗に比例し、会議の成果は出席者数の二乗に反比例する」。 |
| 「だいたい日本人は無駄な挨拶が長すぎるね。時候の挨拶から始まって世間話をダラダラとしないと失礼だと思っている。そして、その後でこれこれの要件で参りましたと云って、又その不必要ないきさつについてまで話してから初めて本題に入る。これは、お互いの時間が損すると思うね。挨拶は『今日は』だけでいい。そして、今日の要件はこれこれですと話すだけでいいんじゃないかね。そうすれば私もその場で、できるとかできないとか結論を出す。これでお互いに気持ち良く用が足りるのだ」(戸川猪佐武「田中角栄猛語録」)。 |
| 「電話は、用件だけでいいんだ。馬鹿ほど長電話をするんだ」。 |
| 「話をしたいなら初めに結論を言え。理由は三つに限定しろ。世の中、三つほどの理由を挙げれば、大方の説明はつく。どんな話でも、ポイントは結局ひとつだ。そこを見抜ければ物事は3分あれば片づく」。 |
| 「オヤジの話というのは、簡潔、平易、明快が特徴だ。話に起承転結などはない。ズバッとまず結論から入る。筋道が立っているから、どう結論が出ても誰もが納得するようになっている。一度、若い政治家の相談が終わったあとにオヤジに聞いたんだ。『もう少し、ジックリ聞いてやればいいじゃないですか』と。オヤジ曰く、『どんな話でも、結局はポイントは一つだ。そこを見抜ければ、物事は三分あれば片づく。あとは結局ムダ話だ。大体、忙しいワシがムダ話をしている余裕はない。長話は奴らだって辟易するだろう』だった。真理は常に簡明であるということだな。(補足/「われ思う。故にわれあり」で知られるフランスの哲学者デカルトの言葉は「よく考え抜かれたことは、きわめて明晰な表現をとる」)」(秘書・早坂茂三の弁)。 |
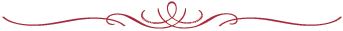
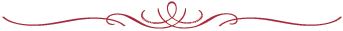
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)