| 「いいか、演説というのはな、原稿を読むようなものでは駄目だ。聴衆は、初めから終わりまで集中して聞いていない。きっちりとした起承転結の話をしても、駄目なんだ。話があっちへいつたり、こっちに行ったりしてもいい。聴衆の顔を見て、関心のありそうな話をしろ。30分か1時間の演説の中で、何か一つ印象に残るような話をもって帰ってもらえばいいんだ」。 |
| 「演説、スピーチでの真の雄弁とは、今日この話を聞けてあぁ良かった、と思わせることだ。聞き手との一体感をどう醸すかがポイントになる」。 |
| 「私の演説、スピーチは田舎のじいさんばあさん、学生、会社の経営者など、誰が聞いても分かるわようにできている。何百人いても、その一人ひとりと対話できる『一体感』が成立しているから、皆なあぁ今日は良い話しを聞けて良かった、となるんだ。真の雄弁ということじゃないかな」。 |
意訳概要「ウソはつくな。すぐばれる。わかったようなことを言うな。気の利いたことを言うな。借り物は一発で見抜かれ後が続かなくなる。何より、稚拙でもいいから自分の言葉でしゃべることだ。若い君が本当に思っていること、自分自身が体得したことを、自分なりの言葉で話せば良い。借り物でない自分の言葉で全力で話せ。そうすれば、初めて人が聞く耳を持ってくれる。相手の心に響く。百姓を侮ってはいけない。小理屈で人間は動かないことを知れ」。
(小林吉弥「田中角栄処世の奥義」82P)。 |
| 「世の中には他人様の噂話、伝聞をいつもポケットに入れ、それを放出することで一日の生活が回っているアホがいる。自分の言葉がないのは寂しいことである」。 |
| 「ワシの演説を、皆、楽しんで聞いてくれるが、じつは話に信頼感があるからだ。ここでの信頼とは何か。数字をキチンと示すことにある。数字と統計、これに優る説得力はないということだ」。 |
| 「交渉事のやり取りやスピ-チに、多くの数字と歴史にまつわる話を入れろ。説得力が増す」。 |
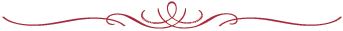
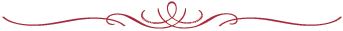
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)