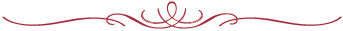
| 田中角栄式ハト派防衛論考 |
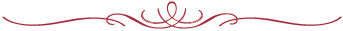
(最新見直し2007.5.19日)
| Re:れんだいこのカンテラ時評293 | れんだいこ | 2007/05/19 |
| 【田中角栄式ハト派防衛論考】 (れんだいこのショートメッセージ) 最近手に入れた「田中角栄の国会演説と各党の代表質問上下巻」(会演説調査研究会、閣文社1990.5.20日初版)所収の所信表明演説と各党代表との質疑の中から見えてくる「田中角栄式ハト派防衛論」を確認したい。今日びのタカ派式防衛論とは様相がまるで違う。このことを明らかにさせ、日本国家及び民族の自立自存に思いを馳せたい。「田中角栄式ハト派防衛論」は、現下の憲法9条改正論議が踏まえるべき今もっての基準となるべきではなかろうか。れんだいこはそう思う。 角栄の所信表明演説の最近のそれとの大きな違いは、内治外治の両面において満遍なく触れつつも、内治の方により多角的多岐精緻に言及していることである。しかも、より少なく言及されている外治のその過半が国交回復と国際友好親善と経済援助に充てられている。つまり、防衛論につき驚くべきほど寡言であるということになる。そういう事情からかどうか、四次防との絡みもあったのであろうが、各党代表は逆に「角栄の防衛論」を弱点として狙いをつけ質疑し、角栄が答弁するという構図が生まれている。これにより、奇しくも田中角栄式防衛論なるものが遺されることになったのは望外の成果と云えよう。 れんだいこは、このやり取りをれんだいこ式に整理し、「田中角栄式ハト派防衛論」として纏め、世に打ち出したいと思う。現下の国会とマス・メディアによる二頭建て牽引によるタカ派防衛論に基づく憲法改正運動に棹差してみたいと思う。最近の主流である「中曽根−小泉式タカ派防衛論」に対して、かってこの国に存在した「田中角栄式ハト派防衛論」を対置させ、後者の方が真っ当でないかと問いかけ直す機会を提供したい。 遠吠えするばかりの社共式対応で、特に日共の確かな野党論で状況に立ち向かうことは愚昧である。ああいうのは予定された反対運動であり、痛くもかゆくも無く改憲派の手の内にあり、タカ派支配に裏協力している恐れがある。 思えば、ロッキード事件で揺れた去る日、それによって利益を得たのはタカ派であった。最も激烈に反角栄闘争を仕掛け、容赦の無い政界追放運動を牽引したのは日共であった。この両者に黒い糸の繋がりを見るのは、れんだいこだけだろうか。そういう史観を持つれんだいこの、「確かな野党論」による野党分裂政策に固執する日共を見る眼は冷たい。この党はどこまで腐っているのだと云う憤然とした思いがこみ上げている。 それはともかく、ここで、「田中角栄式ハト派防衛論」を紹介する。憲法改正派に対してこれを武器にせよ、その値打ちは高い。それにしても、かような見解を保持していた角栄を極悪非道人として喧伝し洗脳し続けてきている日共の犯罪性は重い深いと云うべきだろう。日本政治の再生は、角栄の復権評価からしか有り得ない、れんだいこはそう思う。 2007.5.19日 れんだいこ拝 |
||
| 【「田中角栄式ハト派防衛論概要」】 |
| 「田中角栄式ハト派防衛論」は、日米同盟を受容している。その限りで、吉田内閣最初期の「東洋のスイスたる国際的中立」の立場には立っていない。角栄は、「東洋のスイスたる国際的中立論」に対して、それは理想であるとして却下し、我々は現実論に立つと述べている。思うに、角栄の「日米同盟受容」は、米ソ冷戦構造に於ける体制選択として、米側即ち資本主義陣営に与するという立場の表明であろう。その意義を、自由主義市場体制の擁護に求めていた形跡がある。今日の歴史は統制経済主義を志向したソ連側の体制崩壊を知らせており、「日米同盟受容」の選択の賢明さを教えている。 「田中角栄式ハト派防衛論」は、その「日米同盟受容」を受けて、それが結果的に憲法前文及び第9条違反であろうとも、日米安全保障条約及びその関連諸法、自衛隊創設及びその関連諸法を受容している。これを日米安保体制と云う。この堅持については、ハト派とタカ派の相違はない。ハト派とタカ派の相違は、この次から始まる。 「田中角栄式ハト派防衛論」は、「憲法前文及び第9条違反」の日米安保や自衛隊を認めるが、「憲法前文及び第9条」を重石として、極力整合的であるべきだとする。必然的に吉田内閣以来の解釈改憲を引き継ぐことになる。これに対して、タカ派は、「憲法前文及び第9条」を否定して、極力憲法改正すべきだとする。もはや解釈改憲を限界として、小難しい話を神学論争として一蹴していくことになる。つまり、「田中角栄式ハト派防衛論」は、護憲を前提にした軍事防衛論である。タカ派防衛論は、改憲を前提にした軍事防衛論である。一見似ているが、この違いは大きい。 国防の基本方針は具体的には次のように定められる。その1は、日米安保体制に対する対応問題となる。ハト派は、米ソ冷戦構造に於ける体制選択としての資本主義陣営仲間入りという立場からのものであり、その限りにおいて盟主米国との繋がりを重視する。が、この体制下で憲法の明示する国際法の遵守、国際協調、国際平和創造に向かうというスタンスを採る。特徴的なことは、日米安保体制のくびきに置かれつつも、極力主権国家として振舞おうとするところにある。 タカ派のそれは、米国を指導する国際金融資本の世界支配戦略に与し、日本を二等国家として存立せしめていくことが「国家百年の計」であるとする強度の日米安保体制深のめりスタンスを採る。ハト派の国防論を安保ただ乗り論として批判し、戦費の積極的負担に向かう。次に戦費のみならず自衛隊の派兵へと向かう。国際法は臨機応変のものとしてさほど重視せず、国際金融資本の論理と論法が正義だとして言いなりになる。そういう訳で、日本は隷従国家として振舞うことを辞さない。否、世界に先駆けての一番乗り支持を競う。 その2は、自衛隊及びに軍事防衛費対する対応問題となる。自衛隊をどの程度まで育成発展させるのか、自衛隊の防衛区域はどの辺りまでかを問う。ハト派は、主権国家としての自衛の為に必要とする最小限度としての防衛力の漸進的整備を目指し、今後の経済運営に支障となることのない限りに於いてという制限を設ける。軍事防衛予算の「GNP1%枠」と「専守防衛枠」で歯止めをかける。タカ派は、その「GNP1%枠」と「専守防衛枠」を取り外し、国際責任論を唱えて国際金融資本の世界支配戦略の指図のままに世界各地の紛争への積極関与を目指す。現在、自衛隊の戦地派遣に続いて前線戦闘が画策されようとしている。 その他3・米軍基地に対する対応問題、整理統合と負担問題、4・武器開発及び輸出禁止問題、5・非核三原則及び原子力開発問題、6・日米合同演習問題等々があり、それらいずれにおいても、ハト派の抑制に対してタカ派の積極という構図にあり、目下はタカ派の方針へと振り子が動いている。総じて、ハト派の目指すのは国際協調国家であり、タカ派の目指すのはネオ・シオニズム配下の好戦国家という違いになる。 |
| 【1972.10.28日の第70回臨時国会に於ける「田中角栄式ハト派防衛論発言集」】 | |||||||
|
| 【1973.1.27日の第71回臨時国会に於ける「田中角栄式ハト派防衛論発言集」】 | ||||
|
| 【1973.12.1日の第72回国会に於ける「田中角栄式ハト派防衛論発言集」】 | |||
|
| 【1974.1.21日の第72回国会に於ける「田中角栄式ハト派防衛論発言集」】 | ||||
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)