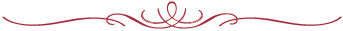
| �P�X�V�S�N���̓c���p�h���� |
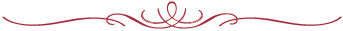
�@�i�ŐV�������Q�O�O�X�D�P�Q�D�O�X���j
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@�P�X�V�S�N���̊p�h���������^���Ă������Ƃɂ���B |
| �y�P�X�V�S�D�P�D�V���A�}���R�X�E�t�B���s���哝�̎�Ôӎ`��ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
| �@�哝�̊t���C�}���R�X�ߕv�l�C���тɂ���Ȃ̊F�l
�@�哝�̂�肽�����ܒg�����}�̂����t������������������\���グ�܂��B �@���̂��т��̔������t�B���s����K�₵�C�哝�̂���эːF�����̗ߕv�l�ɂ��ڂɂ����ꂽ���Ƃ́C���̍ł��Ӊ��Ƃ���Ƃ���ł���܂��B�܂��C�{���C�ō��̉h�_�ł��郉�W���E�V�J�c�i�M�͂�q�C���h����ɂ�������̂͂���܂���B �@���́C�}�j���ɎQ��܂��@�ォ�琼�����m�̊C�݂߂C���̊C�m�������I�ɂ������I�ɂ����䗼�������ԉ�L�ł������Ƃɉ��߂Ďv����y���܂����B�L���Ȍ�ʂ̎�i�̂Ȃ�������ɂ́C���̊C�m�́C�������𗬂̑O�ɗ����͂�����傫�ȏ�Q���ł����B����ł��Ȃ��C���ɗL�j�ȑO�Ƀt�B���s���͂��ߓ�A�W�A�̖����������ɏ�ē��{�ɂ��ǂ蒅���C�蒅�����ƐM�����Ă���܂��B����D�f�Ղ��Ő����ɒB�����P�V���I�̏����C�����킪�����R�S�N�ɘj�鍽������ɓ��钼�O�̂���ɂ́C�}�j���̓��{�l�X�ɂ͖�R�疼���̓��{�l�����Z���Ă����ƋL�^����Ă���܂��B���̒��ɂ͗L���ȃL���V�^���喼���R�E�߂���т��̈ꑰ���܂܂�Ă���C�ނ́C�t�B���s���̐l�X�̒g�������ĂȂ��̒��ɁC���̒n�ɂ����ĔӔN���߂������Ƃ́C�悭�m���Ă���Ƃ���ł���܂��B �@�M���͑哝�̂̑�z�����w���̉��ɁC�Љ�`�̎�����ړI�Ƃ���V�Љ�̌��݂�簐i���Ă����C�����C�o�ρC�Љ�̊e����Ō����Ȑ��ʂ������Ă����܂��B�������ʑ哝�̂̂����҂������ċM����K�₵�܂����̂��C������M�����̓w�͂Ɛ��ʂ��܂̂�����ɂ���ƂƂ��ɁC�M�����Ƃ킪�����Ƃ̊ԂɁC���a�Ɣɉh�Ƃ������ǂ��אl���u�̊W���琬�������悤�Ƃ̂킪���̔M�]��哝�̂ɂ��`��������������ł���܂��B �@�ߔN���䗼���Ԃ̐l�I�C�o�ϓI�𗬂��}���ɑ��債�C�F�D�e�P�W���v�X�g��E��������Ă���܂��B�Ƃ��Ɉ��N�H�����N�t�ɂ����Ă̋����{���{���ւ̔䍑�����̌䋦�́C��N�R���̃J�������ɂ�����u�䓇��v�҈ԗ��v�����̍ۂ̌�D�ӁC�X�ɂ͍�N�P�Q�����̓���F�D�ʏ��q�C���̔�y���͗����̗F�D���͊W���d������Ă���哝�̂̌�쌩�Ɠ��ʂ̌�s�͂ɂ��Ƃ����ł���C���{�����ɑ�Đ[���h�ӂ�\���܂��B �@���́C���{�ƋM�����F��������Ƃ邽�߂̒n���ȓw�͂������ނ��̂łȂ���C���䗼���̏����ɂ��đ傢�Ɋy�ςł���ƐM���ċ^���܂���B���́C�n���������Ȃ�C�����������ԋ������������Z�k�����ɂ�C�����͍ő��u���䗼���̊W�����悯��v�ƈ��Z�ł��Ȃ��ȂĂ��邱�Ƃł���܂��B �@�����̐��E�́C�����镪��ɂ����Đ[���ȕϓ��E�ϊv�̎����ɒ��ʂ��Ă���܂��B���Ƃ��Β��������̖������ƁC��S�������푈�ɒ[�������E�I�ȐΖ���@�́C�M���Ɠ��{�݂̂Ȃ炸�C�A�W�A�����S�̂̌o�ϊ����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ�����C�킪���Ƃ��Ă����E�̕��a�Ɣɉh�̂��߂Ɉꍏ�������������P�v�I�ȉ����������푈�ɂ����炳��邱�Ƃ����Ă���܂��B������������Ȏ��Ԃ̉��ɁC���͑哝�̂ƂЂ낭���ۏ�ɂ��ė����Ɉӌ����������C�M�������đ��̓���A�W�A�����Ƃ̗F�D�e�P�W���]��������w���łȂ��̂ɂ������ƔO�肵�Ă���܂��B �@���͓��䗼���̊Ԃ̂����镪��C�����郌�x���ł̌𗬂��܂��܂����i�����ׂ��ł���Ɗm�M���Ă���܂��B�Ƃ��Ɏ��̐����S�����N�̊Ԃɑ��ݗ�����[�߂邱�Ƃ́C�ɂ߂Ė]�܂����C���K�v�Ȃ��Ƃł���Ǝv���܂��B�킪�����炱�̂悤�ȖړI�Ŋ��Ɂu�N�̑D�v���M����K�₵�Ă���܂��B���͂��̌v����X�ɔ��W�����C���㖈�N�M���͂��ߓ���A�W�A�̐N���킪���ɏ��҂��C�킪���̐N�Ɛe�����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u����A�W�A�N�̑D�v�̌v����n�߂�l���ł��邱�Ƃ�\���グ�܂��B �@���̐����S�����ꓙ�����̐N�������D�̏�ŋN�����Ƃ��ɂ��Ȃ����荇���C�F��Ƒ��ݗ�����[�߂邱�Ƃɂ��C���݂̐M���Ƌ��͂̐��_��{���@�����C���̐���ւ̂����₩�ȑ��蕨�Ƃ������ƍl���鎟��ł���܂��B �@����̎��̋M���K��͐r���Z���Ԃł͂���܂����C���͑哝�̂��͂��ߊF�l���Ƃ̗����ȑΘb��ʂ��C���łɓ��䗼���Ԃɑ��݂��Ă���ٖ��ȗF�D�W����w�[�߂邱�Ƃ��ł�����̂ƐM���ċ^���܂���B �@�����Ŏ��́C���Ȃ̊F�l�ƂƂ��ɔt�������đ哝�̊t����v�Ȃ̌䌒�N�C�t�B���s�����a���̔ɉh�C���䗼���̗F�D�C�����ăA�W�A�Ɛ��E�̕��a�̂��߂Ɋ��t�������Ƒ����܂��B�}�u�n�C |
| �y�P�X�V�S�D�P�D�X���A�T�����[�E�^�C��Ôӎ`��ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@�T�����[������b�t���C�ߕv�l�C���тɌ��Ȃ̊F�l �@�T�����[������b���g�������}�̂����t�����������C�S���炨��\���グ�܂��B�^�C�����{�̌䏵�҂ɂ��C���̓x�O��̋M����K��邱�Ƃ��ł��܂������Ƃ́C���̐[����낱�тƂ���Ƃ���ł���܂��B�܂��{���ō��̉h�_�ł���M���̔��ۑ���͂�q�C���h����ɗD����̂͂���܂���B �@�M���Ƃ킪���͂��݂��ɗL�j�ȗ��̐����Ȃ��A�W�A�̓Ɨ����Ƃ��āC�܂��C�Ƃ��ɍ����Ɍh�����ꂽ�c���������������Ƃ��āC�O���I���ȏ�ɂ��킽�ėF�D���J���ێ����Ă܂���܂����B �@���͋M�����C�p���ȍ����É��̂��ƂŁC�M������b�̑�z�����w���ƋM�����e�w�̋��͂ɂ�āC���̕ϓ������鍑�ۏ�Ɍ����ɑΏ�����C�V�����̐��̂��Ƃɍ��������̌���ƍ��Ƃ̔ɉh��ڎw���ė͋����O�i���Ă���p�ɁC�[�����������ڂ�����̂ł���܂��B���͒������j�ƋP����������Ɨ��̓`����L����M�����C���̐����ȖړI����������邱�Ƃ�S����O�肵�C�܂��C�K������������̂Ɗm�M������̂ł���܂��B �@�Q�O���I�̍����C�n���͉v�X�����Ȃ�C���E�^�C�����͍X�ɐg�߂��ȗאl�ƂȂ�܂����B���݃A�W�A���Ƃ�܂����ۊ��͋}���ɕω����Ă��܂��B�����Ă���ꂪ���ʂ�����͈�w���G������ƂƂ��ɁC�����C�o�ρC�������ׂĂ̕���ɘj�鐢�E��̍L����ƂȂ�������ɓ��Ă���܂��B �@���̂��Ƃ͍ŋ߂̐Ζ���@�̉e���ɂ��Đ\���グ��܂ł��Ȃ��C�F�l�悭�䑶�m�̂Ƃ���ł���܂��B�܂��C���͓��E�^�C�����Ԃ̌o�ϊW�ٖ̋����ɔ����C��X�̖��C�������C�Ƃ��ɂ킪���̌o�ϓI�v���[���X�ɑ���뜜�̔O�������邱�Ƃ��C�悭���m���Ă���܂��B���ƊԂ̊W���ٖ����̓x����[�߂�ɂ�āC�F�M�̊Ԃɂ����Ă��������ׂ��������̖�肪�����邱�Ƃ́C����Ӗ��ł͂�ނȂ��ł���܂��悤�B �@�{���M���̎����S���w�����N�̊��}���܂������C���ڔޓ��w�����N�̕s���ɐڂ������Ƃ͎������炪���̏d�含��c�����邤���ňӖ�������ƍl���Ă���܂��B���͔ޓ��̕s���ɑ�����̌��z������Ă���܂���B������u���邱�Ƃ�������Ȃ��̂ł���܂��B�d�v�Ȃ��Ƃ́C�������_�@�Ƃ��āC�o�������ݗ����Ɩ������̂��߂̓w�͂��d�˂邱�Ƃł���C���̂悤�Ȓn���ȓw�͂�ʂ��C���ɂ���܂��悤�ɁC�J�~�Ēn�ł܂邱�Ƃ�O�肷����̂ł���܂��B���͂��̋@��ɁC�킪�����{�ƍ��������E�^�C�����Ԃ̉i���̗F�D�W��z�������Ă������߂ɁC������w�͂�ɂ��ނ��̂łȂ����Ƃ��m�M�������܂��B �@���̗l�Ȋϓ_���玄�́C�Â��F�M�ł�����E�^�C�����̊Ԃɂ����镪��C�����郌�x���ł̌𗬂��܂��܂����i����邱�Ƃ�������]�������Ă���܂��B�Ƃ��ɁC���̐����S���w���C�N�̊Ԃɑ��ݗ�����[�߂邱�Ƃ́C�ɂ߂Ė]�܂����C���C�K�v�Ȃ��Ƃł���ƍl���܂��B�킪�����炱�̗l�ȖړI�Ŗ��N�u�N�̑D�v���M����K�₵�Ă���C��N�P�O���ɂ͋M������b�ɂ��e������������������h�Ă���܂��B���́C���̍l�����X�ɔ��W�����C���㖈�N�M���͂��ߓ���A�W�A�̐N���킪���ɏ��҂��C�킪���̐N�Ɛe�����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u����A�W�A�N�̑D�v�̌v���V���Ɏn�߂�l���ł��邱�Ƃ�\���グ�܂��B���́C���̐����S���A�W�A�̐N�������D�̏�Ō�荇���C�܂��N�����Ƃ��ɂ��Ȃ���F��Ƒ��ݗ�����[�߂邱�Ƃɂ��C���݂̐M���Ƌ��͂̐��_��{���@�����C���̐���ւ̂����₩�ȑ����Ƃ������ƍl���܂��B �@�T�����[������b�t�� �@����̎��̋M���K��͐r���Z���Ԃł͂���܂����C���͋M�������͂��ߋM���̊F�l���Ƃ̊��݂̂Ȃ��ӌ��̌�����ʂ��C���łɓ��E�^�C�����Ԃɑ��݂��Ă���ٖ��ȗF�D�W������ɐ[�߂邱�Ƃ��ł�����̂ƐM���ċ^���܂���B �@���̌䈥�A���I����ɓ���C���͗�Ȃ̊F�l�ƂƂ��ɔt�������C�T�����[������b����їߕv�l�̌䌒�N�C�M���̌�ɉh�C�����ē��E�^�C�����̗F�D�̂��߂Ɋ��t�������Ƒ����܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�D�P�P���A���[�E�N�@���E���[�E�V���K�|�[����Ôӎ`��ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@���[�E�N�@���E���[�����t���C�ߕv�l���тɌ��Ȃ̊F�l�B �@���̓x���[�����̌䏵�҂��C�O��̃V���K�|�[����K��邱�Ƃ��ł��܂������Ƃ͎��̐[����тƂ���Ƃ���ł���܂��B�{�[�͂���������Ȕӎ`����Â������C�[�����ӂ��Ă���܂��B �@�{���C�u�K�[�f���E�V�e�B�v�̖��̂Ƃ���C�̑��������ȊX���݂ƁC�ɉh���Ă���V���K�|�[������̂�����ɂ��C�L���Ȋ��̒��Ƀ_�C�i�~�b�N�ɖ��i�����邻�̎p�ɐ[���������܂����B �@���[�����́C�P�X�T�X�N�ɂR�T�˂̎Ⴓ�ŏO�]��S�ĎɏA�C����C�ȗ��P�T�N�ԃV���K�|�[���̍H�ƊJ���C�����̐��������̌���ɐs����C�����̔@���ɉh�������炳��܂������Ƃ͐��Ɍh���ɂ����܂���B �@�V���K�|�[�����{���W�������n��ɑ���ꂽ���{�뉀�u���a���v�́C�O���ɂ�������{�뉀�Ƃ��čő�̂��̂ł���C���̒r�ɂ́C��������̋����̐V�����瑗���Ă����T��C�̋ь��܂�Ă���ƕ����Ă���܂��B�����̋ь�́C�V���K�|�[���̌�̐��Ƃ̌䐢�b�ɂ��C�V���K�|�[���̋C�y�ɂ悭�Ȃ��݁C���{�ɂ�������������C���h�ɐ������C�����ł͓��{�뉀��K��邨�q�̖ڂ��y���܂��Ă���Ƃ̂��Ƃł���܂��B���̓��{�뉀���C����A�W�A�ł͍ő�̋K�͂Ɗ������ق���W�������H�ƒc�n���ɑ����Ă��邱�Ƃ́C���R�ƍH�ƊJ���Ƃ��I�݂ɒ��a���悤�Ƃ��Ă�����V���K�|�[�����{�̌�w�͂̏؍��ł���C�h�ӂ�\���܂��B �@�������ʋM�����{�̌䏵�҂������C�M����K�₵�܂����̂́C�M�����Ƃ킪�����Ƃ̊ԂɁC���a�Ɣɉh�������ǂ��אl���u�̊W����w�琬�����������Ƃ̂킪���̔M�]�����瑍���ɂ��`���������ƔO�肵�����߂ł���܂��B �@�V���K�|�[���Ƃ킪���́C�H�Ɖ���ʂ������̕������i��}�邱�Ƃ���{�Ƃ��C�܂��C���Ɍo�ς̑�����f�ՂɈˑ�����Ƃ����ʂŋ��ʂ̊�Ղɗ��Ă��܂��B�]�āC���E�V�W�́C�ǂ��p�[�g�i�[�Ƃ��č���Ƃ����͂Ɣ��W���傢�Ɋ��҂�����ƐM���ċ^���܂���B �@�������Ȃ���C�����̐��E�͒P�ɓԂ̗F�D�W�̑��i�����邾���ł͍ς܂���Ȃ����ɁC���̒n��Ő����鎖�����C�����ɍL�����E�e���ɉe�����y�ڂ�����ɂ���܂��B�Ⴆ�C���������̖������Ƒ�l�������푈�ɒ[�������E�I�ȐΖ���@�͋M���Ɠ��{�݂̂Ȃ炸�C�A�W�A�����S�̂̌o�ϊ����ɑ傫�ȉe�����y�ڂ�����C�킪���Ƃ��Ă����E�̕��a�Ɣɉh�̂��߂Ɉꍏ�������������P�v�I�ȉ��������������ɂ����炳��邱�Ƃ����Ă���܂��B �@���̂悤�ȍ���Ȏ����ɍ�簂ȉp�m�Ǝ����C�����Đ[�����@�͂�L���Ă����郊�[�����ƍēx��k�̋@��āC���E����уA�W�A�����ݒ��ʂ��鑽���̖��ɂ��ė��������݂̂Ȃ��ӌ��̌������s�Ȃ����Ƃ��o���܂������Ƃ́C���ɂƂċɂ߂ėL�v�ł���܂����B �@���́C���V�����Ԃ̂����镪��C�����郌�x���ł̌𗬂��܂��܂����i�����ׂ��ł���Ɗm�M���Ă���܂��B���ɁC���̐����S���N�̊Ԃɑ��ݗ�����[�߂邱�Ƃ͖]�܂����C�܂��K�v�Ȃ��Ƃł���Ǝv���܂��B�킪���́C���̗l�ȖړI�ł���܂Łu�N�̑D�v��x�X�M���ɔh�����C�M�����̊��҂��Ă���܂��B���́C���̌v����X�ɔ��W�����C�M���͂��ߓ���A�W�A����ѓ��{�̐��N���e�����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u����A�W�A�N�̑D�v�̌v������[�����ɂ����͂��肵�C�������̌�^���܂����B���̐����S���N�������D�̏�Ō�荇���C�܂��C�N�������ɂ��Ȃ���F��Ƒ��ݗ�����[�߂邱�Ƃɂ��C���݂̐M���Ƌ��͂̐��_��{���@�����C����ꐢ��̎��̐���ւ̂����₩�ȑ����Ƃ������ƍl���鎟��ł���܂��B �@�����̎��̋M���K��͐r���Z���Ԃł͂���܂����C���̓��[�������͂��ߊF�l���Ƃ̗����ȑΘb��ʂ��C���łɓ��E�V�����Ԃɑ��݂��Ă���ٖ��ȗF�D�W����w�[�߂邱�Ƃ��ł�����̂ƐM���ċ^���܂���B �@���̈��A���I����ɂ�����C���͊e�ʂƋ��ɔt�������ă��[�����t����v�Ȃ̌䌒�N�ƌ�K�����F�O���C�V���K�|�[�������̂Ђ��Â��Ă̔ɉh�ƍK���̂��߂Ɋ��t�������Ƒ����܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�D�P�Q���A���U�N�E�}���C�V�A��Ôӎ`��ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@���U�N�t�����тɌ��Ȃ̊F�l�B �@���̂��сC���U�N�̌䏵�҂��C�O��̃}���C�V�A��K��邱�Ƃ��ł��܂������Ƃ́C���̐[����тƂ���Ƃ���ł���܂��B�{�[�C�����ɂ������g�����ӎ`����Â��Ă��������܂������ƂɌ�������\���グ�܂��B �@���͂��˂Ă��M���������̓���ƒ��a�C�n���̖o�łɂ��Љ�`�̎�����ڕW�Ƃ��āC�����ȎЉ�C�o�ϓI���W�̐��ʂ������Ă����邱�Ƃɑ��C�[���h�ӂĂ���܂������C��N�����ɂ����ċM����уt�Z�C���E�I�����ɂ��߂ɂ�����C���̕����̈�[�ɐڂ���@��C������[����������ł���܂��B�M���u�V�o�ϐ���v�̒��ŏ������Ă�����o�ϔ��W�̉ʎ��̌����ȕ��z�C���ƒ��a�����`�ł̍H�Ɖ��̐��i����э����̎����w�͂Ǝ��ȋ]���̗v�����́C�����������Ɍg���҂Ƃ��āC���̋���������Ƃ���ł���܂��B�����̂��Ƃ��������鍑�یo�ϊ����ɂ��Ă��C�M���������Ȍo�ϔ��W��i�߂Ă�����̂́C�����錫���Ȏw���ɂ�Ďn�߂ĉ\�ł���ƍl���܂��o�O13���ڃ}�}�p�B �@�����̐��E�́C�����镪��ɂ����Đ[���ȕϓ��C�ϊv�̎����ɂ���C�A�W�A�����̗�O�ł͂��蓾�܂���B���̂悤�Ȏ��ɁC�M�����ɂP�X�V�O�N�ɏ������ꂽ����A�W�A�������\�z���`�r�d�`�m�̃N�A�������v�[���錾�Ƃ��Č����������Ƃ́C�{�n��ɂ����镽�a�ƈ�������铴�@�ɕx���݂Ƃ��āC���ۓI�ɍ����]�����^�����Ă���̂ł���܂��B �@�����M�̌䏵�҂ɂ��M����K�₵�܂����̂��C���a�Ɣɉh�������ǂ��אl�Ƃ��Ă̋M���Ƃ킪���̊W����w�琬�����������Ƃ̂킪�����̔M�]���M�����ɂ��`������ƂƂ��ɁC��N�Ɉ������M�ƍL�͂Ȗ��ɂ��ĕ����Ȃ��ӌ��̌������s�����Ƃ�O�肵������ł���܂��B �@���Ȃ̊F�l���悭�䏳�m�̂悤�ɁC���{�ƃ}���C�V�A�Ƃ̊W�͋ߔN�v�X���ٖ̋��̓x����������܂��B�������Ȃ���W�̖��ډ��ɔ����V���ɒ�����v�����肪�����ė��邱�Ƃ��܂������ł���܂��B���ǂ����̐ȂɏW���҂�����Ƃ��{�[�̔@���Ȃ��₩�ȕ��͋C�̉��ɂ����Ƃ��ċ��݂𑊊J���Ă����Ȃ�C�����Ԃ̏����̒����͂͂����C�����W�͍X�ɑO�i���Ă������̂ƐM���ċ^���܂���B �@���̂悤�Ȋϓ_����C���͓��E�}�����̔@���F�M�Ԃɂ́C�����镪��C�����郌�x���ł̌𗬂��܂��܂����i�����ׂ��ł���ƒɊ����Ă���܂��B�Ƃ��ɁC���̐����S���N�̊Ԃɑ��ݗ�����[�߂邱�Ƃ́C�ɂ߂Ė]�܂����݂̂Ȃ炸�C�K�v�Ȃ��Ƃł���Ǝv���܂��B�킪�����瓯�l�̖ړI�œx�X�u�N�̑D�v���M����K�₵�Ă���C�M�����̒g�������}���ĎQ��܂����B���́C���̌v����X�ɔ��W�����C���㖈�N�M���͂��ߓ���A�W�A�̐N���킪���ɏ��҂��C�킪���̐N�Ɛe�����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����u����A�W�A�N�̑D�v�̌v������U�N�ɒ�Đ\���グ�܂������C���̌�^�������Ƃ���Ԃ��̂ł���܂��B���̐����S�����ꓙ�����̐N�������D��Ō�荇���C�܂��N�����Ƃ��ɂ��Ȃ���F��Ƒ��ݗ�����[�߂邱�Ƃɂ��C���݂̐M���Ƌ��͂̐��_��{���@�����C���̐���ւ̂����₩�ȑ����ɂ������ƍl�����̂ł���₷�o�O2���ڃ}�}�p�B �@�I��ɂ����āC���͍���̖K�₪�M�Ƃ̊Ԃ̌l�I�ڐG��ʂ��āC���ݗ�����[�߁C���E�}�����̌�������F�D�W����w���łȂ��̂ƂȂ邱�Ƃ��F�O�������܂��B �@�����ŁC���͌��Ȃ̊F�l�ƂƂ��ɔt�������C���U�N�t���̌䌒�N�C�}���C�V�A�̔Ɋy�o�O1���}�}�p�C���E�}�����̗F�D�C�����ăA�W�A�Ɛ��E�̕��a�̂��߂Ɋ��t�������Ƒ����܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�D�P�T���A�X�n���g�E�C���h�l�V�A�哝�̎�Ôӎ`��ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�́u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@�X�n���g�哝�̊t���C�ߕv�l�C�n�����N�u�I�m���哝�̊t�����тɌ��Ȃ̊F�l�B �@���̓x�X�n���g�哝�̂̌䏵�҂��C�O��̃C���h�l�V�A���a����K��邱�Ƃ��ł��܂������Ƃ́C���̐[����тƂ���Ƃ���ł���܂��B�{���͂����ɂ���������Ȕӎ`����Â��Ă��������C�S�g�܂�v���ł���C�������\���グ�܂��B �@���˂Ă���C���́C���邢���z�̉��C�L���Ȑ��ƔZ���Ɍb�܂ꂽ�厩�R�̒��ŁC������ɗ��ł�����C���h�l�V�A�����ɕ`���ĎQ��܂����B����M����K�₵�C�X�n���g�哝�̂̑씲����w���ƍ����̋��͂̉��ɁC�M���������镪��ɂ����ė͋����O�i����Ă���p��ڂ̂�����ɂ��C�[���������o��������ł���܂��B�����T�C�O�O�O�L���C��k�P�C�U�O�O�L���̍L��ȊC��ɎU�݂���P������̓��X����Ȃ�M���ɂ����āC�C���h�l�V�A�������C�����̃��b�g�[�ł���u���l���̒��̓���v�ɏے�����Ă���Ƃ���C���ꂼ��̓`���I�Ȏ��������Ȃ�����C�S�̂Ƃ��Č����ɒ��a�����Љ�肠���Ă����邱�Ƃɂ�����̌h�ӂ�\������܂���B���́C���̂悤�ȋM���̎p�̒��ɁC�����̏����̂���ׂ��p������v����v���Ă���܂��B �@�����̐��E�́C�����镪��ɂ����Đ[���ȕϓ��C�ϊv�̎���ɂ���C�A�W�A�����̗�O�ł͂��蓾�܂���B���̂悤�ȍ��ۏ�̉��ŁC�M���́C����ł͑����m�ƃC���h�m�C�����ɂ����Ă̓A�W�A�嗤�Ƒ�m�B�Ƃ����Ԑ��v�ȏꏊ�Ɉʒu����C�D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸�A�W�A�̕��a�Ɣɉh�̂��߂ɏd�v�Ȗ������ʂ��ׂ��^����S�Ă����܂��B�����M�����B�����ꂽ�����I�C�o�ϓI�������b�ɁC�A�W�A�̕��a�ƈ���̂��߂ɐϋɓI�ɍv�����Ă����邱�Ƃ́C�����A�W�A�̗F�M�Ƃ��āC�܂��ƂɐS��������ł���܂��B �@�P���R��疜�̍�����i���o�O8���ڃ}�}�p�C��������ꂽ�C���h�l�V�A�Ƃ̋��͂�[�߂邱�Ƃ́C�i������A�W�A�̕��a�Ɣɉh������킪���O���ɂƂĈ�̏d�v�Ȓ��Ȃ̂ł���܂��B�킪���́C����܂ł��M���Ƃ̐����I�C�o�ϓI�C�����I�����͂̑��i�̂��߈ꐶ�����ɓw�͂��ĎQ��܂����B���E�C�����Ԃ̐l���𗬂͍����e�w�ɂ킽�ċߔN�Ƃ݂Ɍ��݂𑝂��Ă���C�����Ԃ̖f�Ղ���N�͂Q�O���h���̑��ɏ悹�ė]�肠��Ƃ���܂Ŋg�債�܂����B���Ȃ킿�C���E�C�����͏����ɂ킽�āC���������ɊԌ����Ђ낭�C���s�����[���K�v�����ׂ��炴��p�[�g�i�[�Ȃ̂ł���܂��B�������Ȃ���C���悤�ɍ��ƊԂ̊W���Z���̓x����[�߂�ɂ�C�F�M�̊Ԃɂ����Ă��C�������ׂ�����̖�肪�����������邱�Ƃ́C����Ӗ��ł͂�ނȂ��ł���܂��悤�B���́C���E�C�����ԊW�̐[�܂�ɂ�C��X�̖��C�������C�M���̈ꕔ�ɂ����āC�킪���Ƃ̋��͊W�̂�����ɑ���ᔻ�������Ă��Ă��邱�Ƃ��悭���m���Ă���܂��B�d�v�Ȃ��Ƃ͂������_�@�Ƃ��āC�o�����݂ɑ���̗���d���Ȃ���Θb�Ƒ��ݗ����̓w�͂��d�˂邱�Ƃł���C����ɂ�Ă��������Ԃ̗F�D���͊W����苭���������̂ƐM���܂��B �@�������ʃX�n���g�哝�̂̌䏵�҂��ċM����K�₵�܂����̂��M���Ƃ킪���Ƃ̊ԂɁC���a�Ɣɉh�������^�̗ǂ��אl�W����w���łɂ������Ƃ̂����̔M�]������哝�̂ɂ��`���������ƔO�肵������ł���܂��B �@�{���P�N���U��ɑ哝�̂Ƃ̉�k�̋@��C�����̊Ԃ̐[���M���W���Ċm�F���������Ƃ́C���ɂ�����ł���܂��B���̂悤�ȐS�ƐS�̐G�ꍇ����������̏�M�ɔR����M�����͂��߂Ƃ��铌��A�W�A�����̐N����т킪���̐N�̊ԂɍL�߂čs�����Ƃ́C�����̎���ɑ���Ӗ��ł���ƍl���܂��B���͂��̖ړI�̂��߁C���������̑̌��ɍ��������𗬂̏�����Ӗ��Łu����A�W�A�N�̑D�v�v����n�߂����ƍl���Ă���܂��B������v����܂߁C�����́C���E�C�����Ԃ���ѓ���A�W�A�����Ԃ̗I�v�̗F�D���͊W��z���グ�čs���ׂ��}���w�͂��X���čs�������Ǝv���܂��B �@���́C�{���̉�k��ʂ��āC�M�哝�̂����[�_�[�V�b�v���ƂĂ����Ȃ����Ȃ�C�C���h�l�V�A�̔ɉh�C�Ђ��Ă͓���A�W�A�̈��J�̓r�́C���������y���Ɍ��������̂ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ̔F����[�������̂ł���܂��B���͋M���K����Ō�ɓ���A�W�A�����e�P��K�̗����I����̂ł���܂����C�������߂ċM�哝�̂��͂��߁C�����̎w���҂̑쌩�C�����ɐڂ��������Ƃ́C���ɂƂċM�d���̏�Ȃ��o���ł���܂����B���́C���̐Ȃ����肵�܂��āC���ǂ����{�������C���ꂩ��}����Ƃ���Q�O���I�Ō�̂S�����I���C�F�l�̂��߂ɂ��C�����̂��߂ɂ��C���a�ŏZ�݂悢�C�S�̖L����������Ȃ����h�Ȃ��̂ɂ��悤�Ƃ���ł����ӂł��邱�Ƃ���l�������Ƒ����܂��B �@���̌䈥�A���I����ɓ���C���͌��Ȃ̊F�l�ƂƂ��ɔt�������āC�X�n���g�哝�̊t����v�Ȃ̌䌒�N�C�C���h�l�V�A���a���̔ɉh�C���E�C�����̗F�D�C�����ăA�W�A�Ɛ��E�̕��a�̂��߂Ɋ��t�������Ǝv���܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�T�D�P�R���A�u�c���������܂����l�̏W���v�ɂ�������A�z | ||||||
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B | ||||||
|
�@�V�����l�̊F����I�I�@�������育���������Ă���܂��B��������A���ׂ̈ɂ��x�����ڝ����������Ă���F���A���̂悤�Ȍ`�Ŏ����܂��Ă������邱�Ƃ́A�{���ɂ��肪�������Ƃł���܂��B��������Ȃɐ��ꂪ�܂����ȂŁA���̌`�ł̌��������邱�Ƃ́A������R�T�N�O�A����͏��a�P�S�N�t�b�A�������Ƃ��ē��c�����Ƃ��ȗ��A���߂Ă̂��Ƃł���܂��B���́A�S�g�܂�ӂ邳�Ƃ̐S�ɐڂ��A���݂��݂���v���ł���܂��B �@�����F����̎x���āA���t��g�D�������܂��Ă���A��N�Ԃ̌������o�Ƃ��Ƃ��Ă���܂��B���t������b�ɏA�C�����ہA�u�O���Ɍ������ꕺ���̂悤�ȋC�������v�ƌ��������Ƃ�����܂����A����͂�����̂悤�ȋC���������܂��B�����Ă��̎��̐S���͓�N��̍������S���ς���Ă���܂���B�����̊F����Ǝ���g���ĕ��݁A�����ׂ̈̐����E�f�������Ď��s���Ă������Ƃɂ́A�ɂ߂ďd���ӔC���̂ł���܂��B���́A�߂����������ځi������j�݂Ȃ���A���̏d�݂����߂ĐS�ɍ��݂A�O�i�𑱂��ĎQ�錈�ӂł���܂��B �@���̓�N�Ԃ́A�l�ޗI�v�̗��j�̒��ɂ����ẮA�܂�������قǂ̎��Ԃɉ߂��܂���B�������b�A���E���V���ȓ]���̎�����}���Ă���Ƃ������ɁA���Ď������o���������Ƃ̂Ȃ��������A�������ŋN������������N�Ԃł������Ƃ�������̂ł���܂��B���E�́A�ْ��ɘa�̕����ɐi�݂Ȃ���A����ŐV�������ے����̊m���ɁA����ΎY�݂̋ꂵ�݂𖡂���Ă���܂��B������i�H�ƍ��͂�������]�����̍���ɒ��ʂ��Ă��܂����A�킪������O�ł͂Ȃ��A�����A���Q�A�G�l���M�[�Ȃǂ̏����̉����𔗂��Ă��邱�Ƃ͂����m�̒ʂ�ł���܂��B �@�����ɓ�����ɂԂ��낤�Ƃ��A���܂����Ɂu�V���A�肽���v�ȂǂƋ������͐\���܂���B���ݐV�����ɍݏZ����҂Q�S�O���l�b�A�S���Ɏ��Ɠ������o�҂��ɏo�Ă�������X�Q�U�O���l�b�A���v�T�O�O���l���̊F���A���Ƌ��ɂ��邱�ƂɗE�C�Â����āA�V���Ȗ��ɐ��͓I�Ɏ��g��ŎQ��܂��B�����āA���́A���z�̊������X�ƌf���A���ʂ�������������I�ɉ������A�����F����̕����ɉ����ĎQ�錈�ӂł���܂��B �@�������A�o�ώЉ���Ƃ�܂��������͑傫���ω��������܂����B����͐����݂̂�Nj�����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ���Ċg�債���o�ϗ͂Ɛ����̉ʎ����A���������̏[���ƍ��ە��a�̐��i�ɐϋɓI�Ɋ��p���Ă䂭���Ƃ������v������Ă���̂ł���܂��B�������Q�̖h���A�y�n�A���A�����̗L�����ɑ���z���A�J�����Ԃ̒Z�k�A��N�����A�Љ�ۏ��p�������R�X�g�̕��S�A�Ȏ����E�ȃG�l���M�[���̑��i�A����Ҏ匠�̑��d�A�o�ϋ��͂̐��i�ȂǁA�����̗ʎ��Ƃ��ɍ��x�������Љ�I�j�[�Y�ɂ������Ċe�ʂ̎{���W�J���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B���́A����܂ł̐����Nj��^�̘H���Nj�����߂āA�u�����ƕ��a�v�����Ƃ���o�ώЉ�̉^�c�����ɐ肩���ĎQ��܂��B����܂ł́A�������̑O�ɂ́A��i�����ɒǂ����Ƃ����ڕW�����R�Ƒ��݂��Ă����̂ł���܂��B�悤�₭�ɂ��Đ�i�����Q�̈�p�ɂ��ǂ���������A�������́A����̖ڕW���������A����Ɍ������Ē��킵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��n�ʂɗ�������Ă���܂��B����A���{�������Ǝ��̎������s�Ȃ��ׂ��Ƃ������Ă���킯�ł���܂��B���́A���{�����̂��Ă�G�l���M�[�����p���A���ݓI�G�l���M�[�������o���A�����L���ɑg�D�����A�U������A�K���₱�̎����ɐ����ł���ƐM���ċ^��Ȃ��̂ł���܂��B �@���I�����Љ�I����ցA�t���[����X�g�b�N�ցA�ʂ����ցA������S�ցA��������E�o�����X�֓��c�c�]�������߂鐺�͊e���ʂɍ����̂ł���܂��B���́u���{�����_�v�����������ɂ��āA�킪���������̎�����}�����Ƃ�����̂́A���ɂƂ��Ė]�O�̍K���ł���܂����B�����A���y�����Ɏ��g�ݎ������悤�Ɗ���Ă���̂́A�����A�j��A���ނ�������{�l�́g�ӂ邳�Ɓh��S���I�ɍČ����āA�������̎Љ�ɗ������Ə��������߂����Ƃł���܂��B�����̓��{��z�����������̃G�l���M�[�́A�n���ɐ��܂�A�s�s�ɐ��܂ꂽ�Ⴂ�͂������ɂ���A���Ɉ����ׂ��g�ӂ邳�Ɓh�̂Ȃ��ɕs�ł̌��������̂ł���܂��B �@���̂��߁A�Q�O�O�O�N�܂ł�W�]���������ɂ킽�鍑�y�����̃r�W��������������ƂƂ��ɁA����ɉ����č��y�����̏\�J�N�v��𑁋}�ɃX�^�[�g���Ă��������ƍl���Ă���܂��B���̐V�����v��́A�l���A�H�ƁA���Ȃǂ̒����W�]�̂����ɁA���������R�Ɍb�܂�A�l�Ԑ��̖L���ȁg�V�����ӂ邳�Ɓh�����x�����Љ�����݂��Ă䂭�v���O�����𖾂炩�ɂ�����̂ł���܂��B����́A������Ƃ������Ă���̂ł͂Ȃ��A�ӂ邳�ƂɏZ�ސe�̂Ƃ���֑��q�B�A���B���������A�s��ɏo�҂����Ă���l�B���ӂ邳�Ƃŕ�点��悤�ɂ��邱�ƂȂ̂ł��B�Y�ƍ\���́A������G�l���M�[����������g���d���w�H�Ƃ���A�l�Ԃ̒m�b��m������葽���g���Y�ƁA�܂�m���W��Y�ƂւƎY�Ƃ̃E�G�[�g���ڂ��Ă䂭���ƂƂȂ�܂��B�����A�_�Ƃ���т��ꂪ�c�܂�Ă���_���́A�����Љ�`���̊�ՂƂ������ׂ����{�I�Ȗ�����S�����ƂƂȂ�܂��B���ɁA�H�Ƃ�����I�ɋ����������܂��B���ɑ��z�Ɨ̂�����K�Ȑ�����Ԃ�������܂��B��O�Ɏ��R��ۑ����Ǘ��������܂��B�]���āA�_�H���S�̃o�����X�̂Ƃꂽ�J���������߂Ă䂭�ꍇ�ɂ́A���ɂ��A���ɂ��A�H��̎��ӂɂ��L���ȋ�ԂƐF�����Βn��݂��A�V��������̐X�������Ă䂫�����ƍl���܂��B �@�ӂ邳�Ƃɂ́A�Ƒ���אl��������S���c���Ă���܂��B���A�����I�ȑ����Љ��`���I�ȉƑ����x������������ꂽ�l�Ԑ��́A���ܓs�s���ƍH�Ɖ��̗���̂Ȃ��ōĂю����悤�Ƃ��Ă���̂ł���܂��B�J�T�J�T��������Љ���~���̂́A���������Ȉӎ��̏�ɗ��r�����������A�ъ��ł���܂��B���́A�ӂ邳�Ƃɉ�������Ă���A�шӎ��̗ւ��L���āA�V�����n��Љ��E������`�����Ă䂭�ׂ����̂ƍl���܂��B�g�ӂ邳�Ɓh�������A�g�ӂ邳�Ɓh��L���ɂ���^����V������L���Ă䂱���ł͂���܂��B���{�S�̂��A�l�ԂƑ��z�Ɨ���l���ƂȂ�l�ԕ����̐V���������Љ�����肩���A�S�̂ӂ邳�Ƃ���݂����炷���Ƃ��A���̐����ڕW�ł���܂��B �@�u�����̍��v�A�u���Ƃ̊�v�Ƃ������ׂ��ł��d�v�ȍ����̉ۑ�́A����̖��ł���܂��B���Ɋw���S�N���߂��A��゠�������O�\�N���}�������݁A���̋��琧�x�͒蒅���Ă��܂����B�������A�V��������ƎЉ�̗v���ɑΉ����āA��Ɂg����̌��_�h�ɗ����Ԃ��Ĕ��Ȃ���ƂƂ��ɁA���P�̓w�͂𑱂��Ă����˂Ȃ�܂���B���̈Ӗ��ŁA�Ƃ��ɍŋ߁A��������������̂́A����A�m��A�̈炪�O�ʈ�̂ƂȂ����o�����X�̂Ƃꂽ����̕K�v���ł���܂��B�m���ɒm��Ƒ̈�̓_�ł́A��O�Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��قǍ������ɒB���A�l�l�Ɉ�l�͑�w�ɐi�ޏ�ԂƂȂ��Ă���܂��B�������A���̔��ʁA���܂̋���́A�m��Ώd�̂��炢������A����u�m�b�������Ă���v����ɂ́u�����₹�Ă���v���N����Ă鋳�畗�y���蒅���Ă���ƍl�����܂��B���e���ɂ��A�Z��͒��悭�A���������̒��ɂ����ẮA�s���Ƃ��āA���{�����Ƃ��āA�A�W�A�̈���Ƃ��āA�l�ނ̈���Ƃ��Ď������S�̍l���łȂ��A��ɑ���̗���ɗ����čl����B�|�|������������{�I�ȁu����v�͐�O�A�����킸�A�܂����{��`�Ƃ��Љ��`�Ƃ��̑̐��̈Ⴂ���z�������ՓI�Ȍ������Ǝv���܂��B �@�����g�̂��Ƃ�U��Ԃ��Ă݂Ă��A�l����������l�����́A���������������i�K�ɐg�ɂ��݂����̂ł���܂��B�����A���̒ʊw�������R���w�Z�̍Z�P�u�����̐l�A�^�̗E�ҁv�́A���܂��ɔ]���ɑN�₩�ł���܂��B�w�Z�ɂ����ẮA�搶�́A�ƒ�ɂ����Ă͕�̋������A�܂��Ɏ��ɑ���u����v�ł������Ǝv���܂��B�����ŁA���́A�u�܂̑�v�u�\�̔��ȁv�������Ē������Ǝv���܂��B�`������i�K�ɂ�����q�������̐����K�͂Ƃ��āA�Ⴆ�u�l�Ԃ��ɂ��悤�v�A�u���R���ɂ��悤�v�A�u���Ԃ��ɂ��悤�v�A�u���m���ɂ��悤�v�A�u���A�Љ���ɂ��悤�v�Ƃ����u�܂̑�v�������悤�Ƃ����킯�ł��B�����Ė����̐����̂Ȃ��ŁA�u�F�B�ƒ��ǂ��������낤���v�A�u���N��ɐe�������낤���v���X�Ǝ��Ȃ���u�\�̔��ȁv��ݒ肵�Ă͂ǂ��ł��傤���B �@���ɑ�Ȃ̂́A�`�����������������u�搶�v�̖��ł���܂��B���t�A����҂Ƃ����d���́A���̐E�Ƃƈ���āA�炿����̎q����e�␢�Ԃɑ����Đ������l���ς����A��������Ƃ����l�ԂɈ�Ă�����傫�Ȏg���ƐӔC�������Ă���̂ł���܂��B���ꂾ���ɁA���E���w�Z�ɂ́A�ł��D�G�Ȑl�ށA���E�ӎ��ɔR������M�I�Ȑl����K�v�Ƃ������܂��B���̂��߂ɂ́A�g�����V�Ȃǂ����̌����������肵�A����������̂łȂ���Ȃ�܂���B�����ɁA�搶�́A�q���̐搶�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�e�B��Љ�̐搶�Ƃ��đ��h�����悤�ȑ��݂łȂ���Ȃ�܂���B�Љ�S�̂��瑸�h����邽�߂ɂ́A�搶�̋���ɑ���^���ȏ�M���܂����߂��Ă�����ׂ����̂ƍl���܂��B���̈Ӗ��ŁA����u�����l�ފm�ۖ@�v�����������̂ł���܂��B�܂��A����̎�������̂��ߋ����{����w�̐ݒu�A�g���̊m�ہA�ҋ����P�ɂ��Ă̎{��������w�g�[���i���ĎQ��܂��B �@���ɁA��w�̉^�c�Ɋւ���Վ��[�u�@�ɂ��Ĉꌾ�������܂��B���̖@���́A���N�̔����Ŋ�����ɂȂ�܂����A���͖{���Ȃ炠�̂悤�Ȗ@���͂���Ȃ��Ǝv���Ă���܂��B�����K��͂Ȃ��Ƃ͂����A��w��Ώۂɂ���Ȗ@��������Ƃ������Ǝ��̓��{�̋���s���̒p�������炯�o���Ă���܂��B�������A��w�̒��ŁA���Ƃ��ꌏ�ł��������X�ƎE���������s���Ă����Ԃ������Ă������́A���{�Ƃ��ĉ��炩�̐ӔC�������Ȃ���Ȃ�܂���B�w�Z�̊Ǘ��ɂ������āA�w��̎��R�Ɗw���̎������m�ۂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͌������܂��܂���B��������w�����t�����̂��̂łȂ����Ƃ͓��R�ł���܂����A�܂��w�������̂��̂ł�����܂���B�����S�̂̂��̂Ȃ̂ł���܂��B���̈Ӗ��ŁA����̖]�܂������������炷�邽�߂ɂӂ��킵����w�͂ǂ�����ׂ������A�^���ɍl����K�v������ƍl���܂��B���̈�Ƃ��āA�n���̍�������@�ւ̏[���́A���y�����̕����I�Ȋj�Ƃ������ׂ����̂ł���܂��B���ꂩ��́A��s�s�ɂ������w�̐V���݂̗}���ƒn���ɂ������w�̊g�[�ɂ���đS���I�ɋύt�̂Ƃꂽ��w�̔z�u���s�Ȃ��ĎQ��܂��B�����ɏ��O���̑�w�ɂ݂���悤�ɁA�n���̊��̂悢�s�s�ɑ�w�����A���邢�́A�S���V��������Ɗp�x������̂悢�ΔȁA�R�[�ȂǎR�������̒n�ɍL��ȕ~�n���m�ۂ��ĐV�w�������݂��ĎQ�肽���ƍl���܂��B���̂ق���w�����ݒu���̉����A�V�\�z�̋�����w�@��w�A������w�Ȃǂ̑n�݂����i���ĎQ��܂��B������ɂȂ����{�l���琬���鋳��̔C���͏d����ł���܂��B���ꂾ���ɁA���́A��������^�u�[�����邱�ƂȂ��A�S�����I���ꂩ������N���A�L�������̐����Ȃ���^���ʂ�����g��ł܂��錈�ӂł���܂��B �@���́A���t��g�D���Ĉȗ��A�A�����J�A�����A�����[���b�p�A�\�A�A�����ē���A�W�A�������K���A�e����]�ƃL�^���̂Ȃ��ӌ����������ĎQ��܂����B�����āA�킪���ɂƂ��čł��d�v�Ȗ��F�ł���A�����J�Ƃ̊W�̒������s�Ȃ��܂����B�܂��ɓ��̈���ɂƂ��ĕs���ȓ����̍��𐳏퉻���������܂����B����ɁA�a���ł��������B�Ƃٖ̋������͂���A�܂��Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����\�A�Ƃ̊W���P�̂��߂̑��𓊂����̂ł���܂��B�܂��{�N���߂ɂ́A����A�W�A������K�₵�āA�����̍��X�̍�����ɍv�����邱�Ƃ����߂Ė��ĎQ��܂����B���コ��ɑ�m�B�⒆��ăJ�i�_��K�₷��\��ɂ��Ă���܂��B �@�����̍��ۏ�͈�w���l���̓x�������A�킪�����Ƃ�܂���́A��ォ�ĂȂ��قǂɕ��G�����������̂ƂȂ��Ă���܂��B�ă\�́A�ˑR�R�����卑�ł͂�����̂̂��̉e���͂͑��ΓI�ɒቺ���Ă��Ă���܂��B���R�w�c���x������̂Ƃ��ẮA�č��̂ق��ɁA���[���b�p�����́A����ɓ��{���䓪���ĎQ�����̂ł���܂��B�Љ��`���ɂ����ẮA���\�̌������Η����������݂Ȃ��܂܁A���ɉ��͍P�v�����悤�Ƃ��Ă���܂��B����ɉ����ăA���u���E�́A�Ζ����O��헪�̕���Ƃ��ė���������܂����B�Љ��`���ɂ�����_�Ƃ̕s�U�́A�H�Ɗ�@�Ƃ��Đ��Ԃ𑛂����܂����B���̍��یo�ς��x���Ă����h���̒n�ʂ̉����́A���E�o�ς̐�s���ɕs�����Ȃ������Ă��܂��B�J���r�㍑�̍�����͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A�l���A�H�ƂȂǂ̔Y�݂͐[���ł���܂��B�����̖��́A��������u���������悯��v�Ƃ������ȓI�ȑԓx�ł͌����ĉ����ł��܂���B���ׂĂ̍��́A�V�����A�ъ��ɗ���������̍L�����́E�����W��ł����Ă邱�Ƃ��K�v�ł���܂��B���ɁA�����ɖR�����������y�Ɉꉭ��疜�l����������킪���́A�l���̊C�������Ď�����A�����A����ɕt�����l�������A���i�Ƃ��ĊC�H���킽���ėA�o����Ƃ����f�Ռ`�Ԃ��Ƃ��Ă���܂��B�C�m���Ɠ��{�́A���E�̕��a�Ȃ����Đ����Ă����Ȃ����A���{�o�ς́A���R�ȍ��یo�ϊ��̂��Ƃł̂ݔ��W���邱�Ƃ��ł���̂ł���܂��B���̈Ӗ��Ŏ������͉i���I�Ȑ��E���a�̑n���ƐV�������E�o�ϒ����̍Č��̂��߂ɁA�ϋɓI�ȍ��ۋ��͂𐄐i���Ă䂩�˂Ȃ�܂���B �@�Ƃ��낪�A�����Ŏ��������������̂́A�����̂��Ƃ������ł͂킩���Ă��Ă��A���ł͂܂��킩���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��B����̍��Ɍl�I�Ȑe�ߊ��������S��L���邱�Ƃ́A�D�܂������Ƃł����A�܂��K�v�ł�����܂��傤�B�������Ȃ��炻�ꂪ�����ł��Ƃ͈�܂���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ł́A���S�ȊO���ɂȂ�Ȃ��̂ł���܂��B�����Ƃ���ʓI�A�ߎ���I�ɂƂ炦�邱�ƂȂ��A�őP��s���Ȃ�������P�A�O�P�̍���l�����邱�Ƃ��K�v�ł��B���������A�삩�k���A�푈�����a���Ƃ����P���Ȏv�l�����́A���͂�ł��Ȃ��̂ł���܂��B���́A�ϔO�I�ȓƑP�����߁A���یo���̖��n�ɗR������ɘ_��r���A�����I��Ղɗ����č��C�����A���ߍׂ����A�����ɁA���ۋ��͂̎��������ĎQ�肽���ƍl���܂��B �@���́A�捠�T�U�̒a�������}���܂����B��Ђł����Β�N���߂����킯�ł����A��N�Ȃ�Č����Ă͂����Ȃ��B���ƍ����̂��߂ɉʂ����ׂ��Ӗ��́A�����A�O�𗼖ʂɂ킽���Đ������c����Ă���̂ł���܂��B�������A�������z���������A�����������܂Ō����ɗ��r���A�E�C�������Ă��Ƃ̏����ɂ�����A�����̗��z�͎����ł���̂ł���܂��B�����������́A�ꐭ�{�ꐭ�}�̂��̂ł͂���܂���B�����S�̂̂��̂ł���܂��B���ʂ���ǂ̉ۑ���Ƃ��Ă݂Ă��A�����̎Q���Ƌ��͂Ȃ����ĉ����ł�����̂͂���܂���B �@�������́A���̓��{�l�̂��߂ɁA�������̓��{�̂��߂ɁA�e���������̂��߂ɂ��������ȏ�̂��̂��������ł͂���܂��B�F����A�������̐����́A���R�Ƃ��č��������ɑ��݂���̂ł͂���܂���B���\���N�A�����N�̗��j�̏�ɍ��������邱�Ƃ�m��˂Ȃ�܂���B�����Ɏ������̍�������R�}�Ƃ��Ė����i���ɓ��{�l�̐����͑����̂ł���܂��B�������̑c�悪���{�l�̗��j�̈�R�}���Ȃ������悤�Ɏ��������A���ꂩ�疢���ɑ��������̈�R�}����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���܂��B���́A���������Ӗ��ŁA���̐ӔC���ʂ����˂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���̂ł���܂��B�V���́g�ӂ邳�Ɓh���A����ɐt���܂��ΔZ���Ȃ��Ă���܂����B�N�₩�ȐV�肪���F��V���ɂ���悤�ɁA���́A���X���ӂƊ�]��V���ɂ��A�����Ɏ��g��ŎQ��܂��B���́A���ɗ^����ꂽ���̐ӔC���ʂ������ߑS�͓����������܂��B�Ō�ɁA�d�˂Ă��Q�W�̌��l�݂̂Ȃ���̂��D�ӁA�������ɐS���犴�ӂ��A�݂Ȃ���̂����������������F�肵�Ď��̈��A���I���܂��B |
||||||
| �@���ыg��́u�c���p�h�@���̏����v���T�W�́A�u�������I���ƁA�����ق͊�������̔���ɕ�܂ꂽ�v�ƋL���Ă���B | ||||||
|
||||||
| �y�P�X�V�S�D�T�D�Q�S���A�o�c�A��O�\�܉�莞����ɂ�������A�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
| �@�o�c�A��O�\�܉�莞����ɂ����莄�̏��M�̈�[��\���ׂ̂����Ƒ����܂��B
�@����܂ł̓��{�́A��i�����ɒǂ������Ƃ�ڕW�ɁA�u�������������Ăԁv�Ƃ��������Nj��^�̌o�ω^�c���s�Ȃ��Ă܂���܂����B���{�̐�����A�d���w�H�Ɖ��𒆐S�Ɍo�ϐ����̈ێ��Ɗg��ɏd�_�������A��Ƃ��o�c�̋K�͊g��������ȖڕW�Ƃ��Ă��܂����B���̌��ʁA�킪���o�ς́A���E�L���̎��J�����ɂ�����A��Ƃ́A�o�c��Ղ��g�債�������邱�Ƃɐ������A�����̏����͂ӂ��A�������������サ�܂����B����܂ł̂킪���o�ς̕��݂́A�^�����Ȃ������̗��j�ł������̂ł���܂��B����́A�������A�����e�ʂ̓w�͂Ɖp�m�̂��܂��̂ł���A�����c�̂�����ł���܂��B �@�������A���̌��ʁA�����A���Ȃǂ̑����m�x���g�n�тl���A�Y�Ƃ��ߓx�ɏW�����A���E�ɗޗ���݂Ȃ������x�Љ���`������Ɏ���܂����B����s�s�́A�ߖ��̃��c�{�ŕa�݁A���Q�A�y�n�A�Z��A�S�~�A�����Ȃǂ̖�������Ă���܂��B�����A�_�R�����ł́A��҂������č��N����i�݁A�i���̃G�l���M�[�������悤�Ƃ��Ă���܂��B �@�������A�킪���l���́A���a�Z�\�N�܂łɈ��ܕS���l���x�����錩�ʂ��ł���܂��B��s�s�̐l���W�������̂܂ܕ��u������̂Ƃ��܂łɁA�������ŐV�݂̕K�v�ȋ���{�݂́A�c�t���O��ܕS��\�A���w�Z���Z�S���\�A���w�Z���S�A�����w�Z��S�\�ƂȂ�܂��B����ɁA��������p�������������邽�߂ɂ́A�g���b�N�����א�O�S�l�\����A���|�H���V���ɘZ�\�����K�v�Ƃ������܂��B�܂��A�Z�\�N���_�ɂ������̎��v�ʌܕS�l�\�ܖ��g���ɑ��A�O�S���\�����g���́A�������O���狟���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��A������A����ɑ�\������s�s�n��ł́A���s������ʉ����Ă���A����ȊO�̒n��ł́A�N�Ԗ�S���g���̗]�͂�����̂ł���܂��B �@���̂悤�Ȑ�������݂Ă��A����ȏ�̓s�s�W���́A�s�s�@�\�̔j��ɂȂ���̂ł���܂��B�������A��s�s����������������֗̕��������߂āA�n�����炳��ɐl�����W�܂�A�s�s�l���́A�Ƃ߂ǂ��Ȃ��ӂ������邱�ƂƂȂ�܂��B�����炱���A�s�s�W���̖z�����_�ɓ]�����āA�����A�j��A���ނ�������{�l�́g�ӂ邳�Ɓh��S���I�ɍČ����āA�n������s�s���A�Ƃ��ɐl�Ԃ炵��������������Ԃɂ��肩���邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���܂��B �@�o�ϐ�����A�����݂̂�Nj�����̂ł͂Ȃ��A�����ɂ���Ċg�債���o�ϗ͂Ɛ����̉ʎ����A���������̏[���ƍ��ە��a�̐��i�ɐϋɓI�Ɋ��p���Ă������Ƃ������v������Ă���̂ł���܂��B �@���̂��߁A���̂��ѓy�n����̊�{�@�Ƃ������ׂ����y���p�v��@�Ă���������^�тƂȂ����̂��_�@�Ƃ��āA��\�ꐢ�I��W�]���������ɂ킽�鍑�y�����̃r�W��������������ƂƂ��ɁA����ɉ����ď��a�\��N�x�����N�x�Ƃ��鍑�y�����̏\�J�N�v��̍���ɒ��肵�Ă܂��肽���ƍl���܂��B���y�����J���R�c��̏�ɂ����錟����ʂ��āA�����e�w�̈ӌ����\�������Ă܂���܂����A���̐V�����v��́A�l���A�H�ƁA���A�y�n�A���Ȃǂ̒����W�]�̂����ɁA���������R�Ɍb�܂�A�l�Ԑ��̖L���ȁg�V�����ӂ邳�Ɓh�����݂��Ă����v���O�����𖾂炩�ɂ�����̂ł���܂��B�Ƃ��ɁA�V�����ӂ邳�Ƃ̕����I�Ȋj�Ƃ������ׂ����̂́A��������@�ւ̏[���ł���܂��B���̂��ߑ�s�s�ɂ������w�̐V���݂̗}���ƒn���ɂ������w�̊g�[�ɂ���đS���I�ɋύt�̂Ƃꂽ��w�̔z�u���s�Ȃ��Ă܂���܂��B�����ɏ��O���̑�w�ɂ݂���悤�ɁA�n���̊��̂悢�s�s�ɑ�w�����A���邢�́A�S���V��������Ɗp�x������̂悢�ΔȁA�R�[�ȂǎR�������̒n�ɍL��ȕ~�n���m�ۂ��ĐV�w�������݂��Ă܂��肽���ƍl���܂��B�܂��A�g�V�����ӂ邳�Ɓh�Â���̂Ȃ��ŁA���̂��˂Ă���̎咣�ł���Z��E��n��疜�ˍ\�z���A�����̍��Y�Â���̈�Ƃ��ċ�̉����Ă��������ƍl���Ă���܂��B �@�Y�ƍ\���́A��������������g���d���w�H�Ƃ���l�Ԃ̒m�b��m������葽���g���Y�Ƃ܂�A��蓭������������A�J�����������S�Ő����ȎY�ƂփE�G�C�g���ڂ��Ă䂭���ƂƂȂ�܂��B�����A�_�Ƃ���т��ꂪ�c�܂�Ă���_���́A�����Љ�`���̊�ՂƂ������ׂ����{�I�Ȗ������ɂȂ����ƂƂȂ�܂��B�����āA�_�ƂƍH�Ƃ̃o�����X�̂Ƃꂽ���W���͂���A���ɂ����ɂ��H��̎��ӂɂ��L���ȋ�ԂƐF�����Βn��݂��A�C���_�X�g���A���E�p�[�N�ȂǐV��������̐X�������Ă䂫�����̂ł���܂��B �@�������A�ӂ邳�Ƃɂ́A�Ƒ���אl��������S���c���Ă���܂��B���A�����I�ȑ����Љ��`���I�ȉƑ����x������������ꂽ�l�Ԑ��́A���ܓs�s���ƍH�Ɖ��̗���̂Ȃ��ōĂю����悤�Ƃ��Ă���̂ł���܂��B�J�T�J�T��������Љ���~���̂́A���������Ȉӎ��ɗ��r�����������A�ъ��ł���܂��B���́A�ӂ邳�Ƃɉ�������Ă���A�шӎ��̗ւ��L���āA�V�����n��Љ��E������`�����Ă����ׂ����̂ƍl���܂��B �@�e�ʂɐ\��������܂ł��Ȃ��A�����̓��{��z�����������̃G�l���M�[�́A�n���ɐ��܂�A�s�s�ɐ��܂ꂽ�Ⴂ�͂������ɂ���A�Ƃ��Ɉ����ׂ��ւ�ׂ��g�ӂ邳�Ɓh�̂Ȃ��ɕs�ł̌��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�g�ӂ邳�Ɓh�������A�g�ӂ邳�Ɓh��L���ɂ���V�����ӂ邳�Ɖ^����S���I�ɂ���L���Ă������@���}���Ă���܂��B���́A���Ȃ��Ƃ��e���Ɉ�͏����̐V�����ӂ邳�Ɓ|��\�ܖ��l�P�ʂ̐����������ꂼ��̒n��̓��������A���肠���Ă䂭�ׂ����̂ƍl���܂��B�ӂ邳�Ƃ̑n���́A�Ȃɂ����܂��A���ꂼ��̒n��Љ�̔��ӂ̂����ɐ��i���邱�Ƃ��K�v�ł���܂��B��Ƃ���ъ�ƌo�c�҂��A������Ɠ��̌o�όv�Z�ɌŎ����邱�ƂȂ��A�V��������Ɨ���Ɗp�x����A����������ю��Ə��̑S���I�Ĕz�u���������Ă������������B���{���A�����A�㉺�����Ȃǂ̐������̐����A���H�A�S���A�`�p���̌��݁A�����̖ʂŐϋɓI�ɋ��͂��Ă܂��肽���ƍl���܂��B �@���̂悤�ɁA�g�ӂ邳�Ɓh��n�����A���x�����Љ�����݂��Ă䂭���Ƃ́A�ً}�̉ۑ�ł���܂����A�C���t�����N�������̂ł́A���̖ړI�͒B�����܂���B���������厖�Ƃ́A���ƕS�N�̑�v�Ƃ��������I�W�]�ɗ����đ����v�̓����Ȃǂ����Ă��Ȃ���A�K�x�ȃe���|�Œ����ɂ��Ƃ�i�߂Ă������Ƃ��̗v�ł���܂��B �@���ɁA���ʂ��镨�����ɂ��Ĉꌾ�������܂��B �@�����������_�@�Ƃ���Ζ��̋����팸�Ɖ��i�̑啝���グ�ɂ���ĉ������ꂽ�����̏㏸�́A�����v�̗}�����͂��߂Ƃ��銯�������Ă̓w�͂ɂ��A���É��̒��������Ă���܂��B�������A�����̗}���͑��i�K�ɂ͂����Ă���܂��B�R�X�g�̖�肪����ł���܂��B�Ζ����i���i�̈��グ�ɑ����d�͗����̒l�グ�ɂ���āA�킪���o�ςƍ��������́A�����i�G�l���M�[������}���邱�ƂƂȂ�܂����B�������A�����t���ł́A�O�Z���������钴�啝�̒��グ���s�Ȃ��܂����B �@�t���ɂ����グ�̃R�X�g�v�b�V���v���͉��������ɂ��ċ�E�܁��A����ҕ����ň�Z�����x�Ƃ������Z������܂��B�܂��A����̓d�͗����̉����́A���������ɂ��Ĉꁓ���x�̏㏸�v���ɂȂ�Ƃ����Ă���܂��B �@�����̐V�����R�X�g�v�������Ղɉ��i�ɓ]�ł��邱�ƂȂ��A�ł�����肱����z�����邱�Ƃ��Y�ƊE�̓��ʂ���ٗv�ȉۑ�ł���܂��B �@�]���A�킪���̉���������������i���ɔ�חD��Ĉ��肵�Ă����̂́A���x�����o�ς̉ߒ��ł킪���̊�Ƃ�����܂ʋZ�p�v�V�Ɛݔ������ɂ���Đ��Y�������߁A�R�X�g�v�����z�����Ă�������ɂق��Ȃ�܂���B�������A����蓙�̐���ɂ���ď]���̂悤�ȍ��x������������Ȃ����݁A��ƌo�c�҂́A���R�o�ς̃��@�C�^���e�B�Ƒn�ӍH�v�ɂ���āA�R�X�g�v���̋z���ɑS�͂��X���Ăق����̂ł���܂��B�܂��A��Ƃɓ����҂����Y�����オ�����Ă����A�͂��߂Ē����������I�ɏ㏸����Ƃ��������̗������o���邱�Ƃ��̂��݂����̂ł���܂��B �@���{�Ƃ��Ă��A�����ƒ����̈��z��f����A�������ƍ����o�ϑS�̂Ƃ̒��a���͂����Ă䂭���߂ɁA�����̏O�m�����W���Čo�ϐ����A�����A�����A���Y�����̏��W�ɂ��Č�����[�߂Ă܂��肽���ƍl���܂��B �@���{�́A�K���Ȏ����o�����X���ێ����A���v�ʂ���̕����㏸�v����}���邽�߁A�������������v�}������������Ă܂���܂��B�Ƃ��ɋ��Z�ʂɂ��ẮA�����ߐ�����p������ƂƂ��ɁA�I�ʗZ���A������Ƌ��Z�ɔz�����Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B �@�܂��A���Y���̌�����h�����A�ł����ʓI�ɐi�߂邽�߂̏����͋����̑��i�ł���܂��B�u�s��̗́v�ɂ��A���R�ȋ�����ʂ��ĉ��i�`�����s�Ȃ��邱�Ƃ��]�܂������Ƃ͌����܂ł�����܂���B���₵�����Ǘ����i�̔ᔻ�������ʂ悤�A�������i������d�����Ă܂���܂��B �@���̂悤�Ȋ�{�I�ȕ������Վ��I�ɕ⊮����`�Ő��{�́A��b��������퐶���ɑ傫�ȉe�������ꕔ�̕����̉��i�ɂ��ĕW�����i��݂�����A�s���w���ɂ�鉿�i�̗}�����s�Ȃ��Ă���܂��B�������A����́A�����܂ŋً}�̎��ԂɑΏ����邽�߂̗�O�I�ȑ[�u�ł���A�����������\�����ɂ߂Ȃ��珙�X�ɓP�p���Ă䂭�ׂ����̂ƍl���܂��B �@���R��`�o�ϑ̐��̉��ɂ����āA��Ƃ́A�����I�ȑn���͂Ɛߓx�����ƉƐ��_�����邱�Ƃ���{�ł���A���ꂪ�������Ɠ��{���x����o�ϓI�Ȋ�Ղł���܂��B��Ƌy�ъ�ƌo�c�҂́A�[�����@�ƓI�m�Ȕ��f�͂Ɋ�Â��Ċ�ƃ��x���A�Y�ƃ��x���A�n�惌�x���A���ƃ��x���̂��ꂼ��̗̈�ɂ����āA�������͂��Ƃ��A�J�g���A�g�V�����ӂ邳�Ɓh���A���������A���ۋ����̖��ȂǍL������̖��ɂ��āA�ϋɓI�ɑΉ����邱�Ƃ����߂��Ă���܂��B �@�{�����Q�W�̌o�c�Ҋe�ʂ́A���̐ӔC�̏d�傳�����o���ē��ʂ̖��ɑΏ������ƂƂ��ɁA�����I�ɂ́A���y�S�̂�l�ԂƑ��z�Ɨ���l���ƂȂ�l�ԕ����̐V���������Љ�ɂ��肩���A�S�̂ӂ邳�Ƃ���݂����点�邱�Ƃɋ��͂���邱�Ƃ�S������҂������܂��B�Ō�ɁA�e�ʂ̂����������F�肵�Ď��̈��A�Ƃ������܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�X�D�Q�T���A�g�����g��w���_�w�ʎ��^���ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@�}�N�h�i���h�����C�G���@���Y�w�����тɌ��Ȃ̊F�l �@���́C�R�N�O��U������t���ψ���ɏo�Ȃ̂��߃g�����g�̒n���ӂ݁C�u�L���ȓy�n�v�Ƃ������ɂӂ��킵�����n�̕����ɐ[���������o���Ĉȗ��C�Ăѓ��n��K��邱�Ƃ�ؖ]���Ă��܂����B�{�����̖����ʂ���C�����ėR�����邱�̃g�����g��w��薼�_�@�w���m���̉h�_�������Ƃ́C�]�O�̊�тƂ���Ƃ���ł���܂��B �@�G���@���Y�w���ق���w�W�҂̕��X�ɁC�[�r�Ȃ�ӈӂ�\�������Ǝv���܂��B �@���́C�ߋ��R��̃J�i�_�K���ʂ��C�k�Ɍ����牷�тɎ���L��ȓy�n�C���l�Ȑl��ƕ������ӑR�Ƃ��Ĉ�̂��Ȃ��C���a�̂Ƃꂽ���W�������Ă���J�i�_�̗��j�ɑ傫�ȋ��������Ă܂���܂����B�J�i�_�����ȗ����X�Ƃ��ė���鉠���ȃp�C�I�j�A���_�ɐ[���������o���Ă܂���܂����B����g���h�[�ق��J�i�_�e�E�̎w���ҋy�э����e�w�Ɛe�������b������@������āC���������R���̒��ɐ����C������������C����ɂ͐l�Ԃ̐�������̂��߂Ɏ��R�𗘗p���čs���Y�X�������͂��J�i�_���x���Ă��邱�Ƃ�Ɋ����܂����B �@�����C���̓g�����g��w��K��C���̊w��̕{���D�ꂽ�o�C�^���e�B�[�����J�i�_�����ɖ����ւ̓��������C�m���̗Ƃ�^����������ʂ��Ă������Ƃ������������܂����B�u�Ƃ��̂��肩���ƂƂ��ɐ�������̂��Ƃ��v���������ɍ����͂Ă���{��w�́C�����Ƃ������̎������ё����Ă䂭�ł���܂��悤�B �@������̍��ɂ����Ă��C���̗��j�ƕ����ɍ��������Ǝ������m�����C�����ɂƂčŗǂ̐������������悤�Ɠw�߂�ɂ�����C���̕��I�����𗘗p�������łȂ��C�����̎����ƒm�I�������ő���Ɋ��p���čs�����Ƃ��K�v�ł���܂��B���̂��ߓ��������Ƃ��C���悫�����̐��E��z�����N����Ă�ɂ����ċ���̉ʂ���������ɏd�����Ă���܂��B �@���E��Q�̍L�����ւ�C���ӂ�����̐��Ǝ����Ɍb�܂ꂽ�J�i�_�ɂ����Ă��C�܂��C�I���^���I�B�̂R���̂P�قǂ̋������y�ɁC�P���P�C�O�O�O���̐l����i���C�����̂قƂ�ǂ��C�O�Ɉˑ�������{�ɂ����Ă��C���̐���͎��Ȃ̔\�͂𑶕��ɊJ�����C�\���̒n�������L���Ă䂭�ӋC�ɔR���Ă���܂��B���́C�����W�̏�����������C�S�����ēW�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�Ă���̂ł���܂��B �@�ߋ��P�O�N�Ԃɓ����Ԃ̖f�ʂ��S�D�S���h�������R�O���h���ւƂV�{�ɂ����債�����Ƃ́C�����W�̂߂��܂������W���������̂ł���܂��B�������Ȃ���C���ƊԂ̊W�������镨�I���ʂ݂̂Ɍ�������̂łȂ����Ƃ͂����܂ł�����܂���B�������������ʂ̉^�����m�F���C�����̂���ׂ����E�̃��B�W���������āC���̎����̂��߂ɗ͂����킹�Ă䂭���Ƃ��K�v�ƂȂĂ���̂ł���܂��B �@�����������̍ő�̊�]�́C���a�Ȑ��E���������C������i�������邱�Ƃł���܂��B���̂��߂ɂ͌R���卑�Ԃ̑��ݗ}���݂̂ł͕s�\���ł���܂��B�卑�Ԃْ̋��ɘa�ւ̓����𑣂��C�����ɐ��E�e�n�ɓ��݂��镴���̉��E��ł䂭�ɂ́C���͂┭�W�i�K�̈قȂ����E�̏����̈ӎ��I�w�͂��K�v�ł���܂��B �@���{���J�i�_���C�R���͂ɂ��Ȃ��ōL�������C�o�ϖʂł̍��ۋ����ɂ��C���a�ɍv�����邽�ߌ����ȓw�͂𑱂��Ă���܂��B�����闼���̖����́C�n���Ȃ��̂ł͂���Ƃ��Ă��C���̏d�v���͑��傷�����ł���܂��B �@���������́C�����̐���Ƃ��Ċj����ۗL���ɂȂ邱�Ƃ�r���C���ׂĂ̊j�����̒�~��Nj����C�j�R�k���܂ތR�k�̑��i�ɂ��ꂼ��Ǝ��̃C�j�V�@�e�B�����ƂĂ���܂��B����ɁC�����́C�l�ނ��j�̋��Ђɂ��炳��邱�Ƃ̂Ȃ����E����邽�߁C�s�f�̓w�͂��s�Ă���C�܂��C�����ɂ킽�肱�̕���ł̍v���𑱂��čs���ł���܂��悤�B���́C�J�i�_�����E�̊e�n�ɂ����ĉʂ���Ă������a�ێ������̋M�d�Ȗ����ɑ��[���h�ӂ��ƂƂ��ɁC�킪�����܂��C���E�e�n�̕��a�̊m�ۂɒn���ȍv�������Ă䂫�����Ƃ̌��ӂ����Ă��邱�Ƃ������ɖ��炩�ɂ������Ǝv���܂��B �@�o�ς̕���ł́C��N�H�ȗ��̏����Ԃ̐i�W�ɔ����C�����̍��̓C���t���̍V�i�C�o�ϐ����̑啝�ȗ������݁C���ێ��x�̈����������̖��ɒ��ʂ��Ă���܂��B���̂����ł��C�C���t���̉����͑����̍��ɂƂčő�̉ۑ�ƂȂĂ���C�킪���ɂ����Ă��C�ډ��C���t���}���ɍŏd�_�������C�����ɍ����̕����̈�w�̌�����͂���ׂ����{���i�߂Ă���܂��B �@�������Ȃ���C�����̂��Ƃ������̖�肪���݂ɖ��ڂɊ֘A���C�������e���Ԃ̌o�ό𗬂��ٖ��ɂȂĂ���ɂ��ẮC�����̖��ɂ��Ĉꍑ�݂̂ŗL���ɑΏ��ł���]�n�͌����Ă���܂��B�e���������I�ϓ_�݂̂ɗ��Đ����i�߂�ꍇ�ɂ́C���ʂƂ��Đ��E�o�ϑS�̂ɐ[���ȍ�������������˂܂���B �@����ꂪ���ݕK�v�Ƃ��Ă���̂́C���E�o�ς��k���ύt�̓�����ނ��Ƃ̂Ȃ��悤�C�e�����{�Ԃō��܂łɂ������ċٖ��ȋ�����ۂ��Ƃł���܂��B���E�o�ς̒������Č����C����Ɣ��W�������炷���߂ɁC�����قǂ����̉p�m�Ƌ��͂�K�v�Ƃ��Ă��鎞��͂Ȃ��ƍl���܂��B �@���E�̓��������邱�̂悤�ȏ����ɑ��鋤�ʂ̔F���ɗ��āC�����W�̕��Ɛ[�݂𑝂����r��T�����邽�߂ɁC���̓J�i�_��K�ꂽ�̂ł���܂��B �@���������́C�����ꂽ������قɂ��C�o�ϓI�C���j�I�C�����I�w�i���قȂ�̂ŁC�X�̋�̓I���ɑ���A�v���[�`�́C�K��������v���Ă��Ȃ��̂ł���܂��B�������C���������̋��łȈӎv�Ƃ���܂Ȃ��w�͂����Ă���C�X�̑�������������V�����_�C�i�~�b�N�ȋ��͊W�Ƒn���I�⊮�W��K���m�����Ă䂭���Ƃ��ł�����̂ƐM���܂��B�����ł����́C�܂������Ԃ̊W���g�[���C�[�����Ă䂭�ӎv�Ɠw�͂����݂��Ɋm�F���������ł͂���܂��B �@�����āC�����W���C�����C�o�ρC�����C�Ȋw�Z�p������ɂ킽�鏔����Ŋg�[�������C�����m�����ԐV�����傫�����������\�z���Ă䂱���ł͂���܂��B����́C�����W�̐V����̖��������ے�������̂ł���܂��B���̂������́C�₪�đ����m���͂��ʂ̗��v��L���鏔���ɂ܂ʼn�������C�����m���ƊԂ̐V�������͊W���`������Ă䂭���ƂƂȂ�܂��B���̒��œ��������́C���E�̈���Ɣɉh���x���鋭�łȍ��̈�ƂȂ肤����̂ƐM���ċ^���܂���B �@���̓x�̓�����]��k�ɂ����ẮC�����̕���ŗ����̈�w�̕��݂����͂��邱�Ƃ��d�v�Șb��ƂȂ�C���̂��߂̋�̓I�[�u�ɂ��Ă����ӂ��݂��̂ł���܂��B���̂悤�ȂƂ��C�J�i�_�ɂ�������{�����̏d�v�ȋ��_�ł���C�����Ԃ̑��ݗ����̑��i�̂��߈�w�̍v�������҂�����g�����g��w��K��ł����̂́C���ɂƂ�M�d�ȑ̌��ł���܂��B �@���͐N����Ƀg�����g��w�̂��Ƃ����h�ȂƂ���ŋ������@��ɂ߂��܂�܂���ł����B���ꂾ���Ɋw��̑�����l��{�����āC�₦���w��Ǝ��g��ł܂���܂����B�l���̗��H�C�T�U�˂ɂ��ċM��w�̑��Ɛ��̂ЂƂ�ɉ����Ă����������S�V���Ȃ��̂�����܂��B �@�w��̓��́C�l�ނ̏����ɂƂĖ����̒n�������Ă䂭�������ł���C������Ȉӎu�ƁC�n�����ƔE�ϗ͂�v������̂ł���܂��B �@���́C���������W�̏������C���l�ɋ�����Ȉӎu�ƁC�n�����ƔE�ϗ͂����Đ�Ă䂭�ׂ������̉\�����߂Ă���ƐM���܂��B �@���̉��l���闷�H�Ƀg�����g��w�������ɂ킽�薾�邢���𓊂����������邱�Ƃ��F�Ď��̈��A���I��܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�O�D�Q�Q���A�O�����h������ɂ�����X�s�[�`�z |
| �@�u�f�[�^�x�[�X�w���E�Ɠ��{�x�v�i������w���m�����������c�����F������ �j�����̍��g�u����O�̉����E�����@������b�v���]�ڂ���B |
|
�@�G���A�X��A���Ȃ̊F�l �@�{���́A���{�̔��W�Ƒ����ɁA�܂��܂����]�����߂��邱�̊O�����h������ɂ����āA�F�l�Ɍ�ڂɂ�����邱�Ƃ��������v���Ă���܂��B �@�������̋���̍s���ɏo�Ȃ����̂́A�������N�O�A���{�O���j�����I�ȓ������𐳏퉻���������ꂽ����̂��Ƃł���܂����B���ꂩ���N�ԁA���E�́A�ʉ݁A�C���t���A�H�ƁA�G�l���M�[��蓙�A���܂��܂ȍ���ɒ��ʂ��ė��܂����B�킪�����܂��A���̗�O�ł͂���܂���ł����B �@���ےʉ݂̖�����Ƃ��Č��Ă��A�X�~�\�j���\�̐������N�Ă����N���o�����Ēʉݕs�����ĔR���A��ʉ݂Ƃ��Ẵh���̐؉������_�@�Ƃ��āA�킪�����܂ސ�����i�������ϓ����ꐧ�Ɉڍs����̂ł���܂��B���a�l�\���N�x�\�Z�ɂ����āA���������ƕ�������ƍ��ێ��x�̋ύt�Ƃ����O�̉ۑ�i�g�������}�j���f���A���ےʉݖ��̏����ɓ��z�����������m�呠��b���������ꂽ�̂́A�Ζ���肪�������ĊԂ��Ȃ������ł���܂����B �@��N�̏H�A���������ɒ[�����Ζ���@�ɂ���āA���E�̎�v�G�l���M�[������Ζ��̉��i���l�{���͂˂�����Ƃ����A���A���E�o�ς��o���������Ƃ��Ȃ��ő勉�̎����ɒ��ʂ���̂ł���܂��B�e���̃C���t���͍V�i���A�����}�����邽�߂̈����ߐ���̌��ʁA�������s���ɒ��ʂ��Ă��鍑������܂��B�����N�ɐ��E���P�����p�j�b�N�ɂ��C�G����s���Ƃ����҂�����܂��B�������A�l�ނ̌o���Ɖp�m�ƁA�ٖ��ȍ��ۋ����ɂ���āA���̕s�K�Ȏ��Ԃ��ŏ����ɗ}���邱�Ƃ��\�ł���Ɗm�M���Ă���܂��B �@���́A�Љ��`�̐����̌o�ς�������e�ՂɒE�p�ł��Ȃ��ł���̂Ɠ��l�ɁA���{��`�Љ��̓����ɑ������Ă�����̂ƍl����������܂���B�������Ȃ���A�l�ނɎ��R��t�^����̐��������A�l�ɐӔC�Ǝ��o�𑣂����A痂���������錴���͂ɂȂ邱�Ƃ�M���ċ^���܂���B���������āA�͂��������Ȃ����N�̌o�ς��A���N�́A��w�̍��ۊԂ̋��͂�ʂ��A��������������A��薾�邢���̂ւƒ����ȕ��݂��Ƃ�����̂Ǝv���܂��B �@���̓�N�ԁA�������𐳏퉻�̂��ƁA���́A�d�b������K�₵�A���[���b�p�Ƃ킪���Ƃ̋�������������悤�ɓw�͂��܂����B���̌�A�\�A��K�₵�A�\���N�Ԃ���������u����Ă����k���̓y�̖��𐳖ʂ���Ƃ肠�����̂ł���܂��B �@�킪���ɂƂ�A�d�v�Ȃ��Ƃ́A����A�W�A�����Ƃ̗F�D�e�P�W�̋����ł���A�߂��K�₷��r���}���܂߁A�킪���͍���Ƃ��A����珔���Ƃ̊u�ӂȂ����ݗ������͂����Ă܂���Ȃ���Ȃ�܂���B�X�ɁA����A�W�A�̈���Ɣɉh�̎����̂��߂ɂ́A�`�r�d�`�m�����Ƃ̋��͂ɉ����A��m�B�����Ƃ̘A�ы������̗v�ł���A���́A������j���[�E�W�[���\�h�A���B�K��ɑ傫�Ȋ�]������Ă���܂��B �@�킪���o�ϗ͂̔��W�ɔ����A�킪���Ƃ��ẮA���̊O���̒n�����Ђ낰�Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���L�V�R�A�u���W���A�J�i�_��]�Ƃ̘b�������A������ϓ_����s��ꂽ���̂ł���A����Ƃ�����珔���Ƃ̊W����w��ɂ��Ă܂���Ȃ���Ȃ�܂���B�����m���ǂ���A���a�Ɣɉh�̌ɂ��ׂ��A�t�H�[�h�哝�̂͂��ߊ����m�����̎w���҂Ƃ̋��͊W�𐄐i���Ă܂���܂��B �@���́A�킪�����Ƃ�܂����ۊ��̌������A���E�o�ς̒��ʂ��鏔����ɂ��ĂȂ��̌��z���������Ă���܂���B�܂��A�킪���̈ꕔ�ɂ́A�����ɗR�����鑊��̗����������l�悪��̎咣�����s���A�킪���̐��������݂̖W���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����m���Ă���܂��B�������Ȃ���A�킪���̒������j���Ђ��Ƃ��܂ł��Ȃ������̍�����̂肱���Ă������{�l�ɂ��̒��x�̖�肪�����ł��Ȃ��͂�������܂���B���{�����̂��Ă�G�l���M�[�����p�����ݓI�G�l���M�[���Ђ������A�����L���ɑg�D�����A�U�����邱�Ƃ������K�v�Ȃ̂ł���܂��B���́A���������̎x���Ɨ��������āA����̗v���ɂ������u���L���ȓ��{�ւ̓��v��O�i�������܂��B��Ò����肪�Ƃ��������܂����B |
| �y�P�X�V�S�D�P�P�D�P�X���A�t�H�[�h�哝�̊��}�ߎ`��ɉ�����X�s�[�`�z |
| �@�P�X�V�S�N�P�P���P�X���A��t�H�[�h�đ哝�̊��}�ߎ`��ɂ�����c�����t������b�̃X�s�[�` ��i�c�����t������b�����W�C�T�V�Q�|�T�V�S�Łj�B |
| �@�t�H�[�h�哝�̊t���C���тɌ��Ȃ̊F�l
�@�{�������ɁC�t�H�[�h�哝�́C���тɃL�b�V���W���[���������ق��C���s�̊��}�̉����J�����Ƃ��o���܂������Ƃ́C���̍ł��Ӊ��Ƃ���Ƃ���ł���܂��B �@�A�����J���O�����C���̌��ł��鉢�B�ɖڂ��ނ������ł��邱�Ƃ́C�e�Ղɗ����ł���Ƃ���ł���܂��B�������Ȃ���C�����̑��z�������C���E�̐����o�ςɌ���I�ȉe���͂����Ɏ������M�����C�����m�̑���������a���u������̂łȂ���C���E�̕��a��L���Ɉێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���܂��B�吼�m�̔ޕ��ɑ��鋽�D�ƁC�����m�̔ޕ��ɑ���ӗ~�Ƃ����܂��Ă����C���E�̔ɉh�ւނ��Ă̕č��̍v�����S�������Ǝv���܂��B �@���̂悤�ȂƂ��C�M�哝�̂��C�A�C��ŏ��̌����K�⍑�Ƃ��āC�A�W�A�����m�̕��a�̑b�����Ƃ��Ă���킪����K���ꂽ���Ƃ́C�܂��ƂɎ��X������ł���܂��B�܂��C�M�哝�̂����ĊW�̏d�v����g�������Ď����ꂽ���̂Ƃ��āC���{�������\���Čh�ӂ�\���鎟��ł���܂��B �@����������c�O�Ȃ��Ƃ́C�����ȂƋ��ɁC�M�哝�̌�v�Ȃ����}�����邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂����Ƃ���C�v�l���v�������Ȃ���a�C�̂��߁C�K����f�O���ꂽ���Ƃł���܂��B���̎��B��E�C�������č������ꂽ�v�l���C���炽�߂ĖK���̋@���������邱�Ƃ�S���炨�F�肢�����܂��B �@���́C�����̂����Ƃ�����k�ɂ����āC���ďC�D�j�̂ЂƂ̑}�b��z���N�����܂����B�������N�ɓ��ďC�D�ʏ����̔�y�������̂��߁C���{���č��ɔh�����ꂽ�g�ߒc�́C�č��c���K�ꂽ�ہC�]�ˏ���̑��d�ȕ]��ƑS���ΏƓI�Ɋ����ȐR�c�Ԃ�ɁC���������Ɠ`�����Ă��܂��B��s�̕��g���_�W�H��́C���̗l�q���u�킪���{���̋��s�̂��܂ɂ悭������v�Ɠ��L�ɋL���Ă���܂��B �@���̌�S�\�]�N�̕ϑJ���o�āC���ċ��s��ɂ��Ƃ���ꂽ�c��x�́C�킪���̓y��ɂ���ƍ������낷�Ɏ���܂����B�N�����l�����I�ȏ�ɂ킽��c����̎��ۂɌg���ė����M�哝�̂Ǝ��́C�����C���ė��������R�Ɩ����`�̋��ʂ̗��O�ɂ�肵�����茋�т����Ă��邱�Ƃ��m�F�������Ă���̂ł���܂��B �@�M�哝�̂̏o�g�n�O�����h�E���s�b�Y�́C�ꔪ���Z�N�Ƀt�B���f���t�B�A�ŊJ���ꂽ�C�A�����J���O�������S�N�Ղɂ����āC�u�č��̉Ƌ�̓s�v�Ƃ��čL���S�Ăɖ����͂���Ɏ���܂����B��N��̃A�����J���O��������S�N�Ղ̂Ƃ��́C�O�����h�E���s�b�Y�ƁC���ꂪ�y�o�����̑�Ȑ����ƃt�H�[�h���Ƃ��C�L�����E�Ɋm���閼����z����Ă�����̂ƁC���͊m�M���Ă���܂��B �@�����C���E�ɐ�߂���ė����̍��������Y�̑傫���C���ĊԂ̖f�Ղ̋K�͂��݂�܂ł��Ȃ��C���ė����̌��т��́C���������̂��݂��݂ɂ܂ŐZ�����Ă���C�C���������Ԃ̊W�ł͗��j�����݂Ȃ��قǂ̍L����Ɛ[�݂�L���Ă���܂��B�����̊Ԃɉ�����鑾���m�́C���͂�䂷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��r�C�ł͂Ȃ��C�����Ԃ̐l�ƕ��ƒm���̂�ǂ݂Ȃ������ۂ��łȉ�L�ł���C��邬�Ȃ��M���ƗF��̉˂����Ȃ̂ł���܂��B���́C���Ăٖ̋��ȂȂ�����C���ꂼ��O�𐭍�̎�v�Ȓ��Ƃ��闼���̓w�͂�ʂ��āC���̉�L�Ɖ˂������L�����̊����m�����ɂ܂ʼn������C�����m�����̖��̒ʂ�i���I�ȕ��a�ƈ���̑�C���Ƃ��邱�Ƃ�O�肵�Ă�݂܂���B �@���E�́C����ł͕����̍����C�����ł͌i�C�̌�ށC����ɃG�l���M�[�C�H�Ɠ��Ɖ����̋ɂ߂č���Ȗ��ɒ��ʂ��Ă���܂��B���ė����́C���ێЉ�ɂ����Đ�߂�d��ȐӔC��F�����C�M�哝�̂��t�b�g�{�[���̖��I��Ƃ��đ̓����ꂽ�`�[���v���[�̐��_�ɗ����C�����̓������̂��ߋ��͑Ώ����čs���Ȃ���Ȃ�܂���B �@����̋M�哝�̂Ƃ̉�k�͑�ς݂̂葽�����̂ł���܂��B���́C�M�哝�̖̂K�������ďC���j�ɋP���������Ղ��c���C���ėF�D�W�ɐV���Ȉ�y�[�W����������̂Ƃ��Ė����ɂ����܂���B �@�Ō�ɁC�t�H�[�h�哝�̂̌䌒�N�ƃA�����J���O�������̔ɉh���F���ĊF�l�Ƌ��Ɋ��t�v�������Ƒ����܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�P�D�Q�O���A�c��������b�ƃt�H�[�h�哝�̂Ƃ̊Ԃ̋��������z |
| �@�P�X�V�S�D�P�P�D�Q�O���A��c��������b�ƃt�H�[�h�哝�̂Ƃ̊Ԃ̋���������i�O����P�X���C�X�X�|�P�O�P�Łj�B |
| �@�t�H�[�h�哝�̊t���C���тɌ��Ȃ̊F�l
�@�{�������ɁC�t�H�[�h�哝�́C���тɃL�b�V���W���[���������ق��C���s�̊��}�̉����J�����Ƃ��o���܂������Ƃ́C���̍ł��Ӊ��Ƃ���Ƃ���ł���܂��B �@�A�����J���O�����C���̌��ł��鉢�B�ɖڂ��ނ������ł��邱�Ƃ́C�e�Ղɗ����ł���Ƃ���ł���܂��B�������Ȃ���C�����̑��z�������C���E�̐����o�ςɌ���I�ȉe���͂����Ɏ������M�����C�����m�̑���������a���u������̂łȂ���C���E�̕��a��L���Ɉێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���܂��B�吼�m�̔ޕ��ɑ��鋽�D�ƁC�����m�̔ޕ��ɑ���ӗ~�Ƃ����܂��Ă����C���E�̔ɉh�ւނ��Ă̕č��̍v�����S�������Ǝv���܂��B �@���̂悤�ȂƂ��C�M�哝�̂��C�A�C��ŏ��̌����K�⍑�Ƃ��āC�A�W�A�����m�̕��a�̑b�����Ƃ��Ă���킪����K���ꂽ���Ƃ́C�܂��ƂɎ��X������ł���܂��B�܂��C�M�哝�̂����ĊW�̏d�v����g�������Ď����ꂽ���̂Ƃ��āC���{�������\���Čh�ӂ�\���鎟��ł���܂��B �@����������c�O�Ȃ��Ƃ́C�����ȂƋ��ɁC�M�哝�̌�v�Ȃ����}�����邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���܂����Ƃ���C�v�l���v�������Ȃ���a�C�̂��߁C�K����f�O���ꂽ���Ƃł���܂��B���̎��B��E�C�������č������ꂽ�v�l���C���炽�߂ĖK���̋@���������邱�Ƃ�S���炨�F�肢�����܂��B �@���́C�����̂����Ƃ�����k�ɂ����āC���ďC�D�j�̂ЂƂ̑}�b��z���N�����܂����B�������N�ɓ��ďC�D�ʏ����̔�y�������̂��߁C���{���č��ɔh�����ꂽ�g�ߒc�́C�č��c���K�ꂽ�ہC�]�ˏ���̑��d�ȕ]��ƑS���ΏƓI�Ɋ����ȐR�c�Ԃ�ɁC���������Ɠ`�����Ă��܂��B��s�̕��g���_�W�H��́C���̗l�q���u�킪���{���̋��s�̂��܂ɂ悭������v�Ɠ��L�ɋL���Ă���܂��B �@���̌�S�\�]�N�̕ϑJ���o�āC���ċ��s��ɂ��Ƃ���ꂽ�c��x�́C�킪���̓y��ɂ���ƍ������낷�Ɏ���܂����B�N�����l�����I�ȏ�ɂ킽��c����̎��ۂɌg���ė����M�哝�̂Ǝ��́C�����C���ė��������R�Ɩ����`�̋��ʂ̗��O�ɂ�肵�����茋�т����Ă��邱�Ƃ��m�F�������Ă���̂ł���܂��B �@�M�哝�̂̏o�g�n�O�����h�E���s�b�Y�́C�ꔪ���Z�N�Ƀt�B���f���t�B�A�ŊJ���ꂽ�C�A�����J���O�������S�N�Ղɂ����āC�u�č��̉Ƌ�̓s�v�Ƃ��čL���S�Ăɖ����͂���Ɏ���܂����B��N��̃A�����J���O��������S�N�Ղ̂Ƃ��́C�O�����h�E���s�b�Y�ƁC���ꂪ�y�o�����̑�Ȑ����ƃt�H�[�h���Ƃ��C�L�����E�Ɋm���閼����z����Ă�����̂ƁC���͊m�M���Ă���܂��B �@�����C���E�ɐ�߂���ė����̍��������Y�̑傫���C���ĊԂ̖f�Ղ̋K�͂��݂�܂ł��Ȃ��C���ė����̌��т��́C���������̂��݂��݂ɂ܂ŐZ�����Ă���C�C���������Ԃ̊W�ł͗��j�����݂Ȃ��قǂ̍L����Ɛ[�݂�L���Ă���܂��B�����̊Ԃɉ�����鑾���m�́C���͂�䂷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��r�C�ł͂Ȃ��C�����Ԃ̐l�ƕ��ƒm���̂�ǂ݂Ȃ������ۂ��łȉ�L�ł���C��邬�Ȃ��M���ƗF��̉˂����Ȃ̂ł���܂��B���́C���Ăٖ̋��ȂȂ�����C���ꂼ��O�𐭍�̎�v�Ȓ��Ƃ��闼���̓w�͂�ʂ��āC���̉�L�Ɖ˂������L�����̊����m�����ɂ܂ʼn������C�����m�����̖��̒ʂ�i���I�ȕ��a�ƈ���̑�C���Ƃ��邱�Ƃ�O�肵�Ă�݂܂���B �@���E�́C����ł͕����̍����C�����ł͌i�C�̌�ށC����ɃG�l���M�[�C�H�Ɠ��Ɖ����̋ɂ߂č���Ȗ��ɒ��ʂ��Ă���܂��B���ė����́C���ێЉ�ɂ����Đ�߂�d��ȐӔC��F�����C�M�哝�̂��t�b�g�{�[���̖��I��Ƃ��đ̓����ꂽ�`�[���v���[�̐��_�ɗ����C�����̓������̂��ߋ��͑Ώ����čs���Ȃ���Ȃ�܂���B �@����̋M�哝�̂Ƃ̉�k�͑�ς݂̂葽�����̂ł���܂��B���́C�M�哝�̖̂K�������ďC���j�ɋP���������Ղ��c���C���ėF�D�W�ɐV���Ȉ�y�[�W����������̂Ƃ��Ė����ɂ����܂���B �@�Ō�ɁC�t�H�[�h�哝�̂̌䌒�N�ƃA�����J���O�������̔ɉh���F���ĊF�l�Ƌ��Ɋ��t�v�������Ƒ����܂��B |
| �y�P�X�V�S�D�P�P�D�Q�U���A�u�ސw�ɓ����āv�z |
| �@�Љ����j���u�c���p�h�@�������L�v�i���o�a�o���A�Q�O�O�Q�D�S�D�R�O�����Łj�̕t�^�Ɂu�c���p�h������b�@��v�����v�̊Y���ӏ����]�ڂ���B |
| �y�P�X�V�S�D�P�Q�D�R���A�u���ۏ����i���������āj�v�z | |
�@�P�X�V�S�D�P�Q�D�R���A����ۏ����i���������āj��i�O���ȁC������u����v���Ɋւ��钲�����ʕΏە����i�P�D1960�N�P���̈��ۏ����莞�̊j�����݂Ɋւ���u����v���֘A�j�C����1-12
�j�B
|
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)