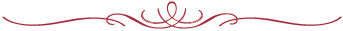
| 1973年時の田中角栄演説 |
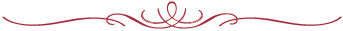
更新日/2017(平成29).5.11日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「1973年時の田中角栄演説」を確認しておく。 |
| 【1973.5.12日、故石橋湛山氏葬儀における田中内閣総理大臣弔詞】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
|
元内閣総理大臣自由民主党総裁従二位勲一等石橋湛山先生のご霊前に謹んで弔詞をささげます。 先生は明治十七年東京に生れ、早稲田大学文学部哲学科を卒業後、直ちに毎日新聞社に勤務の後、明治四十四年には東洋経済新報社に入社されました。その後,主幹となり社長となられてからは、わが国財政経済の指導者として又自由主義経済論者として、一貫して政治、経済、言論、教育等各界に於て縦横の敏腕を発揮され、斯界に多大の貢献をされました。戦後、昭和二十一年五月、第一次吉田内閣の発足にあたっては、鳩山元総裁の強い推薦により大蔵大臣に就任されました。先生は、敗戦によって壊滅的な打撃をうけたわが国経済に立ち直りのきっかけを与え、〃世界の奇跡〃といわれる復興と繁栄の緒口をつけられるなど数多くの歴史的な業績を残されました。 その後、衆議院議員として当選六回、十一年四月にわたる在職中に通商産業大臣となられ、昭和三十一年十二月、第三回自由民主党大会において総裁に選任され、内閣総理大臣の指名を受けられました。全国民は、石橋内閣に対して絶大なる信頼と期待を抱いたのでありますが、政務多忙による過労のため、健康を損われ、就任二ヵ月にして辞職せられました。これは、国家のため、党のため誠に痛恨のきわみでありました。石橋内閣の後を受けた歴代の自由民主党内閣は、先生の御意志に添い、御指導を賜りながら、時代の要請にこたえて、日ソ、日中の国交正常化の問題をはじめ数多くの問題を解決してまいりました。 いま、わが国経済は、国際収支の大幅な黒字をかかえ、流動的な国際通貨情勢のなかにあって、国民福祉の向上、社会資本の充実をめざして成長パターンの転換を行うというきわめて難しい局面を迎えております。われわれが解決を迫られている諸問題はきわめて多いのであります。このようなときに、人間性豊かなスケールの大きい得難い人を失ったことは、国家のためにも実に大きな損失であり、また、惜別の情、切々として禁じえないものがあるのであります。 このうえは、先生の残された偉大なご功績とご遺志を心の糧として、物心ともに豊かな新しい時代の創造のために、あえて困難に挑戦し、議会制民主主義の確固たる基盤にたって、全力を傾注してまいる決意であります。 ここに在りし日の先生をしのび、心からご冥福をお祈りしてお別れの言葉といたします。 |
| 【1973.6.21日、日本記者クラブにおける田中内閣総理大臣挨拶】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
|
日本記者クラブの会合にあたり、所感の一端を申しのべます。 現下の最重要政策課題は物価問題であります。最近の物価動向をみますと、景気上昇の加速度、世界的な悪天候等による海外の食糧、原材料の値上がり、海外インフレの高進に加えて、過剰流動性を背景とした一部商品に対する投機的需要等により、四十七年末以来、卸売物価が急騰しております。他方、四十七年中、比較的安定的に推移してきた消費者物価も、最近上昇を続けております。 政府は、四十八年度の経済運営の基本目標を、国際収支の均衡化、国民福祉の向上、物価の安定という相互にトレード・オフの関係に立つ三つの課題を同時に解決することに置いてきました。その結果、全世界向け輸出は、一月、一八・三億ドル、二月、二七・四億ドル、三月、三〇・〇億ドル、四月、二八・二億ドル、五月、二八・二億ドルに対し、輸入は、一月、二一・九億ドル、二月、二三・四億ドル、三月、二七・八億ドル、四月、二八・〇億ドル、五月、三二・二億ドルと推移しており、輸出は、一〜五月で対前年比二五・五%の増加であるのに対し、輸入は、四四・五%の増加となっております。この結果、二月一九〇・七億ドルに達した外貨準備も急速に減少過程に入り、五月末には一五八・七億ドルとなっております。 とくに昨年来、緊張関係にあった対米貿易は、一〜五月で、輪出三五・六億ドル(対前年同期比八・三%の増)、輸入三三・九億ドル(対前年同期比四一・一%の増)となっており、とくに五月は、八百万ドルの入超に転じておりまして、従来の予想をこえるテンポでアンバランスの是正が進んでいるのであります。 次に「国民福祉の向上」については、ご承知のように四十八年度予算において、社会保障の充実、住宅事情の改善、環境の保全、社会資本の充実等の両で、各般の措置を講じ、国民福祉の向上に努めております。 これからは、政府は、物価の安定のために全力を投入して、適時適切な対策を講じてまいります。すでに、二回にわたる公定歩合の引上げや三回にわたる預金準備率の引上げ、国債の前寄り集中発行、公共事業の施行時期の調整などを実施しましたが、今後とも財政金融政策の弾力的運用をはかるとともに、輸入の割当枠の大幅拡大、生活関連物資にかかわる特恵関税シーリング枠の弾力的運用などの輸入拡大策を強化してまいります。また、消費者に対して一般物価問題、生活関連物資の需給および価格動向等について正確な情報の提供に努めます。すでに、六月一日から四大都市において、生鮮食料品等消費者情報テレフォン・サービスを開始し、市況、在庫の状況、需給の見通し等についての情報を提供しております。 さらに、野菜の安定的な供給を確保するため、野菜指定産地を拡充整備し、農家が安心して野菜生産を行ないうるよう価格補てん事業を強化しております。また、野菜の調整保管、緊急輸送に対する助成、消費地における大規模低温貯蔵庫の設置などの事業も行なっております。 このほか、中央卸売市場の施設整備費補助、公設総合食料品センターの設置費補助などとくに大都市における流通機構の整備について、国としては、格段の予算措置を講じているのでありますから、事業の施行者である地方団体において、国と相協力して問題解決に取り組む姿勢かとくに望まれるのであります。 (公設小売市場についてみると昭和四二年度から四七年度までの補助実績五五カ所のうち、東京部は市街地の改築二、団地の新設五のみ) 物価の問題は、先進工業国に共通する現代の悩みであり、最近のOECDにおいても論議が行われたところであります。昭和四〇年から四六年までの国民総生産の平均伸び率は、わが国の一一・一%に対しアメリカ三・一%、イギリスニ・三%、フランス五・七%でありましたが、この間の卸売物価の平均上昇率は日本が一・七%に止まったのに対し、アメリカニ・八%、イギリス四・三%、フランス三・三%となっております。特に最近の動向を見ると、対前年比でイギリスは約七%、フランス一〇%台、アメリカは一一%を超えるなどスタグフレーションの様相すら呈しております。幸いにして、わが国はそのような状態にありませんし、今後もあってはならないのであります。 去る十四日、アメリカ政府は、再び物価凍結などのインフレ対策を発表しました。しかしいわゆる所得政策は、わが国において国民的合意を得られる段階にないと考えますし、政府は、そのような道を選択しないで問題解決に取り組んでおります。この点は、とくに国民各位の理解と協力をえたいのであります。 次に、勤労者の財産形成政策についてのべます。 わが国の勤労者生活の現状をみると、資金水準の向上によって所得面では一応の充実をみておりますが、資産性の貯蓄や持家などの資産保有面では、著しく立ち遅れております。さらに、すでに資産を持っている者と、これから資産を持とうとする者との間の格差は、ますます拡大する傾向にあり、これが勤労者の社会的疎外感と不公正感を助長し、一般的には豊かな社会といえるこの世の中で、生活への不満を深める大きな要因の一つともなっております。このため、勤労者財産形成促進制度を改善し、日本列島改造政策との有機的連けいを保ちつつ、勤労者のマイ・ホームの夢を実現してゆかねばなりません。 当面、健全な貯蓄を増進することは、国民の堅実な資産の形成に資するだけでなく、旺盛な消費需要を抑え、物価の安定をはかるうえで大きな意義を有します。最近、政府短期証券の公募発行を行なうことと致しましたが、更に、金融機関等が預金者に対しより有利な貯蓄手段を提供するよう新たな措置を講じたいと考えております。 次に税の問題について申し述べます。 わが国の所得税の課税最低限は、夫婦子二人の標準世帯で本年度一一四万九千円約一一五万円に引上げられました。これはアメリカの一三二万円に次ぎフランスの一〇八万円、イギリスの八四万円、西ドイツの七七万円をいずれも上回っているのであります。また、国民所得に対する租税及び社会保険料の比率を見ますと、わが国の場合二四・一%であります。これに対し、アメリカは三六・三%、西ドイツは四四・二%、フランスは四八・八%、英国は四九・四%、社会保障で有名なスエーデンは実に五三・ニ%であります。 このように、わが国の税負担率は各国に比べて決して高くはないのであります。それにもかかわらず重税感を払拭できないのは何故か。それは、わが国の租税構造が直接税中心主義だからであります。昭和四十八年度で見ても、直接税が約七割、間接税が三割であります。これに対し、イギリスは直接税のウエートが五七%、西ドイツは四八%、フランスは三三%と逆に間接税のウエートが高くなっているのであります。 わが国の直接税中心主義は、昭和二十四年のシャウプ税制以降の大原則でありましたが、この間題に抜本的なメスを入れなければなりません。四十九年度の税制改正においてその手がかりをつかもうというのが私の考えであります。所得税の課税最低限を一五〇万円以上に思い切って引上げることとし、法人税を四〇%に引上げたいと考えています。その他、自動車重量税、ガソリン税、印紙税等々についても税調の場などにおいて充分論議されることを期待しているのであります。 社会主義国の税制はどうなっているか、調べさせて見たら大体次のようになっています。ソ連邦の場合、物的生産国民所得(第三次産業の金融、保険、サービスが除かれているようですが)が一九七一年で約二九四四億ルーブル、ドル換算で約三九〇〇億ドル、円換算で約一〇〇兆円であります。(わが国の四八年度国民総生産を一〇〇兆円とすれば、金融、保険、サービスが約三割ですからこれを除くと約七〇兆円になります。) 同じく一九七一年のソ連邦政府の歳入規模は一六一〇億ルーブル、円換算で約五五兆円になりますが、このうち約三四%が売上税、国営企業に対する収益税(法人税)が同じく約三四%、個人所得税が八・六%となっております。国柄の差異はありますが、売上税のウエートが高いのは興味があります。 現在、公営住宅及び公団賃貸住宅の管理戸数は、それぞれ約百ニ十九万戸及び四十四万戸に達しております。 これらの住宅の居住者の中には、所得が相当程度向上している者もおり(長期居住者の推定家賃負担率三〜四%)、子弟の教育の面等で、同じ住宅に定着を希望している者も少なくありません。したがってこれらの長期居住者の入居している住宅が空家となる可能性は極めて小さく(空家発生率は、公営住宅の場合五・六%、十年を経過した公団住宅の場合五・五%)、これらの住宅は公的賃貸住宅としての機能を必ずしも十分に果たしているとはいえないのであります。むしろ、世論の動向もみきわめながら、居住者の希望により払い下げることも検討に値するものと考えます。勿論、公的任宅に入居できない住宅難世帯に対する適正な住宅供給は、喫緊の急務であります。とくに大都市においては、木造公営住宅の建替えによる立体化などの再開発政策を強力に推進して、戸数の増加を図ることが必要であります。 次に地価対策について申しのべます。 地価高騰の原因は、基本的には、宅地需給の不均衡にあります。(1)未利用地の活用、(2)都市立体化の推進、(3)国土の総合開発による宅地需要の分散が、地価問題解決の抜本策であります。 このため、すでに農地の宅地なみ課税は、実現いたしましたが、今後さらに都市の立体化、高層化を推進してまいります。また、交通・通信ネットワークの整備、新しい視野と角度に立脚する新都市、学園都市の建設、工業の全国的再配置等を軸として、国土の総合開発の施策を展開してまいります。当面は、本国会に提案している国土総合開発法案をはじめとする関係諸法律案の成立に全力を傾注いたします。そのなかで、士地利用基本計画の作成、特別規制地域における土地取引の規制、特定総合開発地域における総合開発を促進するための措置等を定め、国土の総合的かつ計画的な利用、開発及び保全をはかることを目的としている国土総合開発法案は、土地対策の基本法的役割をになうものと考えております。 ここで、東京の都市問題について一言いたします。 東京の魅力は、この巨大都市のもつ高度の自由選択性、便利性、快適性にあり、またそれが人間に与える刺戟の大きさ、情報の集中、文化施設の豊かさなどにあります。この魅力こそが東京の欠点を生む原因として作用し、東京の長所こそが、過密に由来する短所を生む原因となっているのであります。したがって、東京の都市問題解決の基本的立場は、東京のもつ魅力を失わせることなしに、いかにしてこれらのマイナス面を巧みに除去してゆくかということにあります。つまり、大都市対策は、国土の総合開発と平行して行なわれることによってのみ、はじめて効果をあげうるのであります。そのための一つの基本戦略と即して、都市二十三区の本格的再開発と高層化を進めて、都市の緑化、オープン・スペースの確保、居住環境の改善等を総合的に実現してゆく必要があります。 これは、零細な敷地の上に鉛筆ビルを建てて、周囲の環境を破壊することを意味するものではありません。広い敷地に、建物を高層化することによって、生み出される街路、緑地、広場その他のオープン・スペースをその建物のまわりに広々ととって、日照の問題はもとよりすべての面にわたって環境を整備しようとするものであります。 このような問題を解決してゆくためには、無責任な批判や反対ではなく、問題解決のための具体的提案を行ない、また、各種社会組織、集団相互の利害対立を調整することのできる高い次元のリーダーシップが求められております。 このような要請にこたえて、政府は、現行制度を改善するとともに、再開発促進地区制度を創設して、一定期限内に、政府の助成のもとに権利者に高層化を行なわせることとし、期限内に再開発ができないときは、公的機関が代わって再開発事業を行なうことを検討しております。また低層木造密集地域等著しく環境が悪化した地域や大震、火災の危険の大きい地域など緊急に再開発を行なう必要がある区域については、従前の権利者に対して地区内ビルへの入居を保障しながら、収用を行なう再開発事業制度の創設も検討してまいりたいと考えております。 他方、地方においては、工業、流通、学園等を計画的に誘導して、自然環境の保全に配意しながら、かつ地域住民の意思に基づき、魅力ある就業、勉学機会と良好な都市環境を備えた新都市を建設してまいります。 さらに今後の大きな問題は、エネルギー資源の問題であります。 エネルギー資源とりわけ石油問題は、(1)需給関係がタイトとなりセラーズ・マーケットとなったこと、および(2)産油国が、石油の供給者として登場してきたことにより流動的様相を示しております。 アメリカは、エネルギー教書を起点として、石油輸入の自由化をはかるとともに、国内未利用資源の開発に力を入れ、そして、核融合、太陽熱などの部門へ技術開発投資を行なうことによって脱石油政策を推進しようとしております。資源欠乏国であり大消費国であるわが国としては、まずエネルギー供給の安定確保のため、国際協調を維持しながら自主開発、共同開発を進めるとともに、供給地域の分散化、備蓄の強化、エネルギー源の多様化などに努めなければなりません。また、石油のみに依存する経済からの脱皮を目指して広範な分野における経済開発を目指している産他国に対して、わが国は、積極的に協力して、共存共栄、相互補完をはかってゆくことが必要であります。 さらに、クリーン・エネルギーの確保、省エネルギー化、および新エネルギーの開発に積極的にとり組んでまいります。私は、これらの問題を単に制約条件として、受動的態度で受けとめるのではなく、わが国経済のもつ活力を、産業構造の知識集約化、技術開発、経済協力等の面に積極的に生かしてまいりたいと考えます。とくに、増殖炉、核融合、太陽熱、地熱、潮力、波力、風力などの新エネルギー技術については、十分な研究期間をみこんで先行的に研究開発を行なう必要があります。アポロ計画のように日限を決めたビッグ・プロジェクト、目標管理方式をオーガナイズしてゆくことが急務でありましょう。 またエネルギー資源の枯渇問題に加えて、地球的な規模で拡がるようになった環境汚染の問題があります。すでに大気や水質が汚染された地域については、環境基準や排出規制を強化、拡充するとともに、総量規制方式を確立してまいります。また、不幸にして公害による健康被害をうけた人々に対する救済措置として、公害健康被害補償法案を今国会に提出しております。 さらに、美しい国土、豊かな自然は、全国民のかけがえのない資産であり、これを長く後代に守り伝えてゆくことは、われわれの責務であります。環境問題は、「自分さえよければ」という考えでは決して解決されません。山や川は日本全体の共有物であり、海や大気は世界の共有物であり、それを汚染することは、人類の危機につながるという認識が必要であります。われわれ日本人いや全人類は、「宇宙船地球号」の乗組員であり、互いに運命を分かち合って生存しているのであります。公害先進国といわれているわが国は、「公害探知のカナリヤ」となるのではなく、「公害絶滅」の先駆的役割をはたすため、官民の総力を結集して環境問題に真正面から取り組んでゆく必要かあります。 最後に国会における法案審議の状況について一言いたします。 現在の特別国会は、百五十日の会期に加えて、会期延長六十五日の約半分、合計すれば百八十日余を経過しております。ところが提出法案百二十三件のうち成立したものは、わずかに三十二件にすぎず、生活関連法案をはじめ、多くの重要法案について審議すら行なわれていない状況にあります。このような現状が、切実な要求を抱えている国民の付託に真に応えている国会運営といえるかどうかきわめて疑問であります。 議会制民主主義においては、手続問題も大切でありますが、十分な審議を尽くすことが基本的に重要であり、どうしても意見の分かれるものについては「多数決原理」に委ね、次の選挙において国民の審判を仰ぐべきであります。近く、法案の審議状況を国民の前に明らかにいたしますが、国会の良識によって、提出法案のすべてが会期中に議了されることを心から願っているのであります。 この他、「学園都市」「老人対策」「国立、青少年の家」「看護婦確保対策」等々たくさんの問題がありますが、最初のご挨拶は、この程度にとどめておきたいと存じます。ご静聴ありがとうございました。 |
| 【1973.7月、田中首相の全国勤労青少年会館の開館式での挨拶】 | |
1973(昭和48).7月、田中首相の全国勤労青少年会館の開館式での挨拶。
|
| 【1973.8.1日、ナショナル・プレス・クラブにおける田中角栄内閣総理大臣演説】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
|
(世界的視野に立つ日米関係)
ララビー会長、ご列席の皆様 ナショナル・プレス・クラブの会員の皆様にお話しできることは、私の光栄とするところであります。 このたび、私は、当地で、ニクソン大統領と実りある会談を重ね、また、議会、言論界の有力者と率直な意見交換の機会をもちました。また、明日からは、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコを訪問し、各界の指導者にお目にかかることにしております。ニクソン大統領と旧交をあたため、そして数多くのアメリカの友人をつくることができることに深い意義を見出しております。事情がゆるすなら、新しい活力に満ちた南部と南西部、更には中西部の大平原や山岳地帯までも訪問し、できるだけ多くのアメリカ国民に接したいところでありますが、限られた時間でありますので、本日は世界的に知られたこのナショナル・プレス・クラブにお集りの皆様を通じて、アメリカの国民の皆様にご挨拶を申し述べたいと思います。 第二次大戦後、すでに四半世紀余の歳月が流れました。その間、国際政治は、戦後の荒廃と冷戦的対立の試練を克服して、ようやく平和的な共存の門口に立っております。世界の経済も、ガットとIMFの体制に支えられて、史上かつてみない拡大と発展を記録することができましたが、今やその転機を迎えているのであります。かかる戦後世界の歩みに主導的な役割を果してきたのは、他ならぬアメリカでありました。私は、アメリカのこの偉大な貢献を高く評価し、かつ深い感謝の気持を率直に表明いたします。 今日、国際政治は、戦後最大の転換期を迎えています。この時期において、人類の英知に課せられた課題は、力の抑止による均衡以外に、軍備の縮小、管理。政治、経済、文化面での国際協力の強化により、真に永続する平和を創造することであります。世界が、当面する永続する平和の創造という仕事は、今や取り組むべき時がきた壮大な事業であります。また、世界的な通貨不安と慢性的インフレの克服、さらには新たな緊張をよんでいる資源や食糧問題の解決も、世界的規模をもつた難事業であります。これらの課題の解決は、アメリカがいかに強大であつても、アメリカだけの力で遂行できるものではなく、また期待すべきでもありません。世界の各国、とりわけ日米欧三者の密接な協力を必要としております。 今日、主要工業国の一員として、応分の貢献と寄与をなし得る立場にある日本国民も、平和の享受者たるにとどまることなく、平和の創造と世界経済秩序の再建にすすんで参画し、その責務を果すべきものと考えます。その意味においては、私は、アメリカ政府が日米欧を始めとする先進民主主義諸国間の協力の仕組みに新しいガイドラインを設けようとする意図を十分理解することができます。そして、それが、関係各国との十分な協議を通じて、実りある成果を生むに至ることを希望しております。私は、これからの日米関係も、そうした文脈の中で見直され検討されるべきであると考えております。つまり、単に二国間の関係という問題意識にとどまらず、「世界的視野に立つ日米関係」という新しい視角を加えて、日米の協力関係を見直す必要があるのであります。 日米二国間の関係は、両国の政府及び国民のたゆまぬ努力の結果と相互の多面的な補完関係の故に、多大の成果を生むことができました。しかし、濃密な間柄であつても、不断の注意と努力を払う必要があります。私が、日米安保体制の維持と運営に細心周到な配慮を加えているのも、そのためであります。しかるに、最近においても、繊維品の対米自主規制問題、貿易収支の大きなアンバランスの是正問題、さらには為替平価の問題等をめぐつて、日米間に緊張した空気が醸成されたことは、ご承知のとおりであります。 私は、1971年7月通商産業大臣に就任していち早く、日米関係の不協和音となつていた三年越しの繊維問題の解決に全力を注いだのであります。米国の繊維業界と同様に、強力な政治的社会的集団である日本の繊維業界の良識に訴え、私なりに政治生命をかけて深刻な日米繊維交渉に終止符を打つたのであります。私と同様に政治に携わるアメリカの上下両院の友人諸君はこの種の問題を解決することが如何に困難な事業であるかを、容易にご理解いただけるものと思います。 次に、日米間の貿易収支問題ですが、両国間の貿易収支は長い間、日本側の入超であり、1965年を境にして日本の出超に転じました。そして、昨年は、日本側の黒字が40億ドルを超えました。そこで、私は、昨年8月ハワイでニクソン大統領と会談した際、「わが国がグローバルな経常収支の黒字を、両3年の間にGNPの1%位にしてゆく考えであり、その過程で対米収支の不均衡も大巾に縮小するであろう」と述べました。その後わが国は、社会資本や国民福祉に重点を置いた大型予算と金融緩和政策により、輸出の内需への転換を進めるとともに、関税の一括引下げ等を通じて、輸入の促進に努めた結果、日本の対米輸入は激増し、わずか1年にして40億ドルという黒字が半減しようという、世界貿易史上例の少ない大きな変化が起りつつあります。本年におけるわが国のグローバルな経常収支の黒字は、GNPの1%以内に止まるものと予想されるのであります。 また、円の対米ドル相場については、ここ20カ月間に実質30%を超える切上げとなつており、わが国の外貨準備高は、190億ドルのピークから半年を経ずして150億ドルに激減しているのであります。さらに、私は、本年5月に画期的な資本自由化措置をとりましたが、これはわが国経済を一層開放化し、日米両国間で相手国への健全な投資を活発化することを意図したものであります。ところが、最近、世界の各地には、経済的、社会的分野において、閉鎖的ないし保護主義的な傾向がみられております。それは人類のために大きな損失であることを憂慮するものであります。 幸いに、自由な経済を基調として、より開放された世界経済の拡大をはかることにより、人類の平和と繁栄に貢献しようとする点で、日米間の見解は基本的には一致しております。私は、日米両国が一層の理解を深め協力を進めることによつて、永続する世界の平和の創造と経済秩序の再建に大きく寄与しなければならないし、また寄与し得るものと確信しております。その意味で、9月に東京で開始が期待される多数国間の貿易交渉は、これらの目的を達成するための絶好の機会となると考えます。 わが国産業の国際競争力と生産力は飛躍的に伸長し、労働者の賃金も欧州諸国をしのぐに至りました。しかしながら、カリフォルニア州よりもせまい国土面積の1%にすぎない東京、大阪、名古屋の三大都市圏に、総人口の32%にあたる3,300万人の人口が集中しており、公害、物価、土地、住宅等の問題が発生しております。また、社会資本の蓄積はアメリカの4分の1であります。これらの問題を解決するため、私は、地方中核都市の建設、工業の全国的再配置、及び交通、通信のネットワークの整備などを内容とする日本列島改造論を提唱するとともに、経済政策を成長第一から福祉優先へ、輸出偏重から輸入重視へ転換させております。このような政策は、日米間の補完関係を創造的に拡充することに寄与するものと確信しております。 このように今後日米間においては、政治、経済の分野での関係は益々緊密の度を加えてまいりますが、このように開けゆく両国関係の要請をみたすに十分なコミュニケーション・キャパシティーは両国間に存在しないのであります。 これは、日米両国が欧米の場合とは異なり、文化、歴史の背景を歴然と異にし、言語の障壁もこえがたいものがあるからであります。しかしながら、お互いが、共通の目的をもつて理解に努め、努力をおしまないならば、その相違を克服できないはずはありません。そのためにこそ、私は、さきに「日米の間断なき対話」の必要性を強調したのであります。そのことは、1人首脳同士だけではなく、政府、言論人、民間経済人、学者など各界各層の間に、コミュニケーションの道が広く深く定着することを念願してやみません。 私は、このような見地から、アメリカの大学における日本研究を促進するためのささやかな貢献として、国際交流基金を通じて米国のいくつかの大学に対して合計1千万ドルの基金の贈与を行ないたいと思います。 貴国の建国200年記念は3年後に迫りました。私はアメリカが、第3世紀への夜明けを前にして、その建国の理想のもとに、真の大国として引き続き全世界の平和と繁栄に寄与されることを心から希望いたします。日本もまた、自由で公正な社会の創造のため、平和と繁栄にみちた世界建設のため、ダイナミックに、かつ責任をもつて取組むことを決意しております。今や日本と米国は、新しい世界における共通の目標を目指しているのであります。相互にもつとも信頼できる盟邦として、人類の明るい未来に向つて、ともに前進して行こうではありませんか。 |
| 【1973.9.12日、ガット閣僚会議における田中内閣総理大臣スピーチ】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
|
議長、ロング事務局長、ご出席の皆様 ガット東京閣僚会議に、世界全域より政策決定の衝にある多数の指導者をお迎えし、歓迎の辞をのべる機会を得ましたことは、私の大きな喜びとするところであります。 私は、十四年前、ガット総会が東京で開催されたことを思い出します。ガットの東京総会は、その直前に実現をみたガットへの加入を通じ、日本が新しい国際経済社会の一員となった門出をしるす機会でありました。私は、再び東京で行われますガットの会合が、貿易拡大を通ずる世界の繁栄と平和への新しい出発を祝う機会となることを、強く希望したいと思います。このため、私は、この会合において、新しい多角的な交渉の開始が宣言され、これを成功に導くとの政治的意思が確認されることを心から期待するものであります。 わが国は、つとに新国際ラウンドの早期開催を提唱し、開放的な経済政策を押し進めてまいりました。私も、昨年七月、総理に就任して以来、わが国経済の、一層の開放化と自由化を指向する一連の措置を強力に推進いたしました。これら一連の措置は、保護主義への傾斜をさけ、世界経済の安定的拡大をはかるために、応分の貢けんと役割を果たそうという国民的なコンセンサスに支えられたものであります。私は、わが国が、今後とも一層開放的な対外政策を追求する方針であることを、この機会に強調したいと存じます。この開放的対外経済政策の追求は、わが国経済政策の重要課題である国民生活の質的向上、物価の安定、産業構造の高度化、国土の総合開発などの、国民的要請にも合致するものであります。したがって、わが国は、今後とも、世界に向かって開かれた経済社会を形成し、拡大を続ける市場を提供することにより、積極的に、世界貿易の拡大に貢献してまいります。このためには、過去築きあげてきた産業の構造や体制に固執することなく、国際協調の見地から、柔軟に対応しうる体制を確保していかねばなりません。 ガット設立以来、過去四半世紀の間に、世界貿易は、史上かつてない拡大と発展を記録いたしました。しかしながら、今、世界経済を更に拡大発展させることを考えるにあたり、われわれ人類は、いくつかの試練に直面しております。すなわち、貿易のみに止まらず、通貨、投資、インフレーション、資源、エネルギー、食糧、環境、開発協力などの分野において解決を必要とする問題か山積しております。これらの問題は、ここに集まっているすべての諸国にとっての共通の関心事でありますが、いずれも「自分さえよければ」という利己的な態度では決して解決できません。すべての国は、新しい連帯感に立ったすそ野の広い協力・協調関係を打ち立てることが必要であります。 私は、これから開始される新国際ラウンドの基本的目的は、ガットが基本的に志向している自由で開放的な世界経済体制の下での貿易拡大を通じて、世界の平和と諸国民の繁栄の恒久的基礎となる貿易フレームを建設することにあると確信いたします。世界経済の発展による生活水準と福祉の向上は、全世界の人人があまねく享受すべきものであります。その意味で、世界貿易の発展にかげをおとす保護主義の台頭や閉鎖的特恵的な地域主義の拡大に対しては、ガットの場を通じる多角的な話し合いによって、問題を現実的に解決する必要があります。 現代世界においては、諸国民の富と福祉は、諸国民の経済の分かちがたい相互依存関係の上に成立しております。この事実を認識した各国が、ガットの理念の下で、力を合わせ、英知をもちより、相互理解を指向した対話を行なうのが、あらゆる目的を達成するための最良の方法でありましょう。そして、このような環境の下でこそ、ガットは、今後とも生きた機能を発揮し、世界貿易発展の推進力となりうると確信いたします。 このたびの新国際ラウンドにおける重要課題に、開発途上国の貿易発展という問題があります。開発途上国が、今後の世界経済の発展から、どのような利益をどのような形で享受していくかについては、格別の配慮が必要であります。その意味で、私は、国際ラウンドの目的の一つとしてかかげられている開発途上国の「追加的利益の確保」を、全面的に支持するものであります。また先進諸国は、開発途上国に対し、今次ラウンドにおける貿易拡大のための協力とともに、その国の要請と実情に応じた本当に役立つ援助を、きめ細かく、誠実に実行していくことが必要でありましょう。開発途上国の繁栄と安定は、世界平和の必要欠くべからざる要諦だからであります。 東京会議の最大の意義は、参加国の代表者が、ステーツマンシップを発揮して、このような理想や原則を再認識し、それを実現するための行動を起こすことにあると考えます。そして、自由で開放的な世界経済体制の下での貿易拡大について、強い政治的意思を結集することが必要なのであります。各国の間には、対立する無数の利害が存在していることは否定しえない事実であります。これらの利害を調整して今次交渉の対象となる複雑、多岐にわたる問題を解決し、具体的な成果をあげることは、容易ならざる事業であります。しかしながら、わが国は、新国際ラウンドに積極的に参加し、わが国自身がなすべきことは果断にこれを実行するとともに、各国の貿易障害の撤廃を強く求めるでありましょう。ここに、私は、新国際ラウンドの成功のために、建設的かつ協力的な貢献を行うとのわが国の強い決意を表明したいと思います。また、私は、各国の代表、とりわけ従来より国際ラウンドを推進されてきた主要先進諸国の代表も、このような決意をもってのぞまれるものと確信いたします。一九七五年末までの限られた期間内に、この困難な事業を完遂するためにも、今回の閣僚会議においては、新国際ラウンドの歴史的意義が認識され、その推進のための各国の政治的意思が確認されることを、あらためて希望いたします。我々は、手をたずさえて、よりよい明日の世界経済体制の創造にとりくもうではありませんか。われわれのたゆまない努力と政治的意思の結集こそが、繁栄と安定に満ちた世界平和を支える国際経済フレームを維持、強化するために必要欠くべからざるものなのであります。 今次閣僚会議と新国際ラウンドの成功を祈り、私の挨拶を終わります。 |
| 【1973.9.12日、全国知事会議における田中内閣総理大臣説示】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
| 全国都道府県知事会議の開催にあたり、所信の一端を申しのべ各位の理解と協力をいただくとともに、きたんない意見を聴取し、国、地方を通じて緊密な連けいのもとに行政の一層の進展を図りたいと思います。
私は、昨年九月、この席においてのべた施政のめざすべき方向にしたがい、各般の施策を行ってまいりました。 (物価の安定) 特に、昭和四十八年度の政策運営にあたっては、国際収支の不均衡の是正、国民福祉の向上、物価の安定という相互にトレード・オフの関係にたつ三つの課題を同時に解決することに、全力を傾けてきました。その結果、国際収支の不均衡は、予想を上まわるテンポで是正がすすみ、二月末、百九十億ドルに達した外貨準備も八月末には百五十一億ドルとなっております。 次に、国民福祉の向上については、四十八年度予算において社会保障の充実、生活環境の整備等の面で各般の措置が講じられており、今後も昭和六十年展望に立って、着実に施策を積上げてまいりたいと考えております。 当面する最重要課題は物価の安定であります。 今日の物価騰貴は、予想を上まわる需要超過を基本的な背景とし、加えて、異常気象などによる海外の食糧、原材料の値上がり、更には国内における労働力需給のひっ迫、水不足、工場火災など供給面における制約要因が複雑に絡んでおり、問題の解決を著しく困難にしております。 政府は現在まで、去る八月三十一日に決定をみた物価安定緊急対策を含め、四次にわたる公定歩合の引上げや公共事業の線延べなど財政金融面からの対策を講じたほか、輸入拡大策の強化、生活必需物資の生産流通対策の拡充、民間設備投資の抑制や消費者信用の調整などに努めております。昭和四十へ年産生産者米価を一六・一パーセント引き上げたにもかかわらず、政府売渡価格を年度内、据置くこととしているのであります。更に、今国会で成立をみた「生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」に基づき、投機的取引に対しては、必要な措置をきめ細かく講じております。 これらの対策の効果は、漸次現われてくるものと期待しておりますが、物価問題の重大性にかんがみ、今後とも物価動向を注視しつつ、必要な施策を機動的に実施していく考えであります。 物価の問題は、先進工業国に共通する現代の悩みであります。昭和四十年から四十六年までの国民総生産の平均伸び率は、我が国の一一・一パーセントに対しアメリカ三・一パーセント、イギリス二・三パーセント、フランス五・七パーセントでありましたが、この間の卸売物価の平均上昇率は日本が一・七パーセントに止まったのに対し、アメリカニ・八パーセント、イギリス四・三パーセント、フランス三・三パーセントとなっております。特に最近の動向を見ると、対前年比でイギリスは約六パーセント、フランス一二パーセント、アメリカは一五パーセントを超えるなどスタグフレーションの様相すら呈しております。 このような事態に対処して、これら各国は、賃金、物価の凍結、ガイドラインの設定などかなりドラスティックな対策を行っております。しかし、いわゆる所得政策は、我が国において国民的合意を得られる段階にないと考えますし、政府は、そのような道を選択しないで問題解決に取り組んでいるのであります。地域の経済活動、住民生活と緊密に接触しておられる各位におかれても、これらの対策について特段の協力を切望いたします。 (土地対策・国土の総合開発) 次に土地問題について申しのべます。 土地は、憲法が認める範囲内で最大限に公共の福祉を優先する原則の下で、広く公正に国民に利用されなければなりません。現下の地価高騰の原因は、基本的には、宅地需給の不均衡にあります。(1)未利用地の活用、(2)都市立体化の推進、(3)国土の総合開発による宅地需要の分散と宅地の円滑な供給が、地価問題解決の抜本策であります。 このため、市街化農地の宅地なみ課税、特別土地保有税、土地譲渡益に対する特別課税は、すでに実現致しました。また、昭和六十年展望に立って、新幹線鉄道、高速道路、地方港湾、水資源開発ダム整備の全国的青写真を作成し、新地方都市、学園都市の建設、それと平行する大規模宅地開発の推進、工業の全国的再配置等を軸として、国土の総合開発の施策を展開してまいります。現在、国会に提案している国土総合開発法案は、土地利用基本計画の作成、特別規制地域における土地取引の規制、特定総合開発地域における総合開発を促進するための措置等を定め、国土の総合的かつ計画的な利用、開発及び保全を図ることを目的とする土地対策の基本法的役割をになうものであり、一日も早い成立が望まれるのであります。 経済企画庁は、このたび新全国総合開発計画の総点検作業の一つとして「巨大都市問題とその対策に関する中間報告」(素案)を発表し、「このまま産業と人口の集中が続けば、東京、大阪などの巨大都市圏は、昭和六十年には、国土資源の限界をこえて深刻な事態となる」と警鐘を発しております。それによると、三大都市圏は五千四百万人(現在は四千五百万人)、東京圏(一都三県)は、二千八百万人程度(現在は二千四百万人)が人口集中の限界であるが、現在のすう勢から推定すると、六十年には三大都市圏六千万人以上、東京圏は、三千三百万人以上になる可能性が強いとしております。その場合には、水、電気の不足が、慢性化し、住宅難や交通混雑は一雁ひどくなり、ゴミ処理、流通施設なども能力を突破して、環境水準や社会生活水準が、今より以上に悪化することは、明らかであります。 いまや、巨大都市において、人口や産業を抑制し、生産機能のみならず中枢管理機能を選択的に強力に地方分散するとともに、地方において、中核都市や農山漁村の整備を行って、人口や産業の定着性と収容力を拡充してゆくことが急務なのです。これこそ、私の提唱してやまない日本列島改造論なのでありますが、国民の支持と理解の下に、国家百年の大計の観点から、強力に各般の施策を展開してまいります。 (勤労者の財産づくり) 次に、勤労者の財産づくりについてのべます。 我が国の勤労者生活の現状をみると、賃金水準の向上によって所得面では、一応の充実をみておりますが、資産性の貯蓄や持家などの資産保有面では、著しく立ち遅れております。更に、すでに資産を持っている者と、これから資産を持とうとする者との間の格差は、ますます拡大する傾向にあり、これが勤労者の社会的疎外感と不公正感を助長し、一般的には豊かな社会といえるこの世の中で、生活への不満を深める大きな要因の一つともなっております。このため、私は、勤労者財産形成促進制度を改善するとともに、国土総合開発の一環として、昭和六十年までに地方に、宅地及び産労住宅五百万戸分、大都市近郊に、中高層住宅五百万戸を提供し、勤労者のマイホームの夢にもむくいてまいりたいと考えております。 本年度の給与所得は五十兆円に達しようとしております。明日の生活設計に裏付けられた健全な貯蓄の推進は、緊要な課題であります。政府としても税制その他の面で一層の工夫をこらしてまいりたいと考えております。 (社会保障) 社会保障の充実は、国民福祉向上の柱であり昭和四十八年度予算編成においても、最も力を入れた課題であります。すでに御承知のように、政府は、物価スライド制を含む画期的な給付改善を内容とする年金制度の改正や家族、高額医療給付などの給付改善と保険財政の健全化対策を内容とする健保改正案を今国会に提出し、その速やかな成立を期しているところであります。 今後の施策の重点として、老人や身体障害者、心身障害児のための社会福祉施設の整備を図ってまいります。医師、看護婦の養成確保など医療供給体制の整備をすすめてまいります。特に、原因が不明であり、あるいは治療方法が確立されていないいわゆる難病対策については、調査研究体制の強化などに特段の配慮を講じてまいりたいと考えております。 我が国の社会保障は、制度の体系としては一応の整備を終え、今後は質的な充実を図ることが必要であります。政府は現在、社会保障長期計画の策定作業をすすめているところであり、その策定をまって社会保障の総合的かつ計画的な推進に取り組んでまいる所存であります。 (教育問題) 教育は、次代をになう青少年を育て、民族悠久の生命をはぐくむための源泉であります。 政府は、教育の制度、内容の両面にわたり、総合的かつ長期的な教育改革の推進に努めているところであります。特に、人間形成の基本をなす義務教育の重要枝にかんがみ、こども心を導く先生によき人材を得るとともに、その情熱を安んじて教育に傾けられるような条件を整備するため、給与の抜本的改善を図るための特別の措置を講じることとしております。また、定年の延長についても真剣に検討いたしております。 今後高等教育の機会拡大の要請に対して、高等教育機関の計画的拡充整備を図っていくことが重要な課題であります。現在、我が国には約九百五十の大学があり、百八十四万人の大学生が在学しております。このうち、六一パーセントの学生が、東京都及び政令指定都市に集中しております。このような大学の大都市集中が学園環境を悪化させ、他方、地方における人材養成の障害ともなっております。しかも昭和六十年の段階で、大学進学率が四〇パーセントに高まると、学生教は、更に七十七万人増加するものと予想されます。このような事態に対処して、昭和四十九年度から、大都市における新増設の抑制と地方における大学特に、単科大学、工業高等専門学校等の新設、拡充を計画的にすすめてまいります。その際、新学園は、既存の都市にとらわれないで、全く新しい視野と角度から環境のよい湖畔、山麓などに広大な敷地を確保して、理想的なレイアウトに基づいて後代に誇りうる優れた教育殿堂として建設してゆきたいと考えております。 (資源・エネルギー対策) 更に、今後の大きな問題は、資源・エネルギーの問題であります。 資源・エネルギーは、急激な需要の伸びにより全地球的規模で枯渇化が懸念されております。とりわけ、国内資源の乏しい我が国にとって必要資源の供給確保は重要な課題となっております。また、国内では、資源・エネルギー消費の急増に伴い環境汚染問題が深刻化し、電力・石油精製等のエネルギー供給産業の立地は困難となってきております。 こうした情勢にかんがみ、政府は、急速に需給のひっ迫を示しつつある電力問題に対処し、環境保全と周辺地域住民への周到な配慮を払いつつ発電施設の立地の円滑化に努めてまいります。また、石油資源に対しては、国際協調をふまえた対外経済協力の拡充を通じ、供給地域の分散化、備蓄の強化、エネルギー源の多様化を推進してまいります。その他、資源・エネルギーの合理的利用、回収再生利用の促進、新エネルギーの開発、更には資源・エネルギー節約型産業構造への転換についても長期的な視点から積極的に取り組んでまいりたいと考えます。 (公害防止及び自然保護) また、エネルギー資源の枯渇問題に加えて、地球的な規模で広がるようになった環境汚染の問題があります。すでに大気や水質で汚染された地域については、環境基準や排出規制を強化、拡充するとともに、総量規制方式を確立してまいります。また、水銀汚染に関しては、大きな社会問題を引き起こし早急な解決が迫られております。このため、政府は、さきに水銀等汚染対策推進会議を設置し、汚染魚対策、工場等の排出源対策、いわゆるつなぎ融資等を実施してきたところでありますが、今後とも国民の不安を解消するための各種の対策を強力に実施してまいります。更に、不幸にして公害による健康被害をうけた人々に対する救済措置として、公害健扱被害補償法案を今国会に提出しております。 更に、美しい国土、豊かな自然は、全国民のかけがえのない資産であり、これを長く後代に守り伝えてゆくことは、われわれの責務であります。環境問題は、「自分さえよければ」という考えでは決して解決されません。山や川は日本全体の共有物であり、海や大気は世界の共有物であり、それを汚染することは、人類の危機につながるという認識か必要であります。われわれ日本人いや全人額は、「宇宙船地球号」の乗組員であり、互いに運命を分かち合って生存しているのであります。公害先進国といわれている我が国は、公害絶滅の先駆的役割を果たすため、官民の総力を結集して環境問題に真正面から取り組んでゆく必要があります。 なお、この機会に一言申し上げておきます。 このたび、我が国の公共的なシンクタンクとして総合研究開発機構が政府、地方公共団体、民間協力により設立されることになっております。ここでは特に、地域社会の問題も重要な課題として取り組むこととしており、その調査研究の成果は、地方行政の進展に大きく寄与するものと考えられます。 本機構の資金は、政府からの出資のほか、広く地方公共団体や民間からも出資を求めることとしておりますので、その設立、運営に関して、都道府県の格段の御協力をお願いする次第であります。 (地方行財政) 社会経済情勢の変貌と住民意識の変化に対応して「活力ある福祉社会」を実現していくために、地方公共団体の果たす役割が強く期待されております。 このため、今後は、福祉優先の立場に立脚した地方行政の積極的な展開、すなわち、立ち遅れた生活関連公共施設の整備や社会福祉水準の向上を図っていく必要があります。これに伴って、予想される地方財政需要の増加に対応する政府は、住民負担の合理化に配意しつつ地方自主財源の拡充、国庫補助負担制度の改善、地方債の弾力的運用等になお一層の努力を重ねてまいる所存であります。 以上、内政が当面している諸問題について所信の一端を申しのべましたが、これは、いずれも地方行政を担当される各位の協力を得て、はじめてその成果を期しうるものであります。各位におかれましても、財源の重点的な配分と経費の効率化を更に推進し、長期的な視野に立った計画的な行財政運営を行うことにより、積極的に地域社会の発展と住民福祉の向上を図られるよう十分御配意をお願いする次第であります。 |
| 【1973.10.2日、在ロンドン・プレス協会主催午餐会における首相演説】 (欧州との新しいパートナーシップ ) |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )の「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
| イングラム会長,ブラトナー会長,御列席の皆様
このたび伝統ある在ロンドン・プレス協会の午餐会にお招きいただき、会員の皆様にお話しできることは私の喜びであり、また、光栄とするところであります。ちようど一年前、ヒース首相がはじめて英国の首相として訪日され、日英交流は大きく前進いたしました。今回は、私がヒース首相の好意ある御招待により、20年振りになつかしい英国を訪問いたしましたが、まことに感慨無量であります。 私は、ロンドン到着以来、英国官民の心暖まるおもてなしに深く感謝しております。同時にこの国の整つた市街と緑おりなす山野の美しさにあらためて驚嘆しております。高度工業社会において、これだけ見事に自然と人工とが調和しているのは、この国の人達の伝統的英知によるものと考えます。 日本は、かつて英国をはじめとする西欧諸国から制度、文物をとり入れ、これに国民の勤勉と創意を加えて成長してまいりました。私どもにとつて西欧諸国は、古き良き師であり友人であつたのであります。こうした西欧との関係は、一時期相対的に稀薄になりましたが、日欧双方とも再び相互の存在価値を見直しつつ、グローバルな課題にとり組んでゆくべきときを迎えているのではないかと考えます。私は、今回の訪欧が日欧関係の転換点となることを希望しております。私は、わが国が「古き友人との新しいパートナーシップ」の確立を求めていることを皆様に訴えたいのであります。 第2次大戦後、すでに四半世紀余の歳月が過ぎました。その間、国際政治は、力による対立の時代を経て、多極化と平和共存の段階へ移行してきました。人類の英知は、明らかに力による対決の不毛を悟りつつあります。われわれは、力の抑止による均衡以外に、軍備の縮小・管理、政治、経済、文化面での幅広い国際協力の強化により、真に永続する平和を創造してゆかねばなりません。 私は、1年前、毛沢東主席、周恩来首相と会談して、アジアの平和に暗影を投げかけていた日本と中国との不正常な関係に終止符を打ち、両国間の親善友好関係の基盤を固めました。また、近く訪ソしてブレジネフ書記長と会談し、日ソ関係の改善をはかりたいと念願しております。他方、日本と米国は、政治、経済、社会、文化の各分野において深い関係をもつておりますが、この1年来両国間に存在した経済的摩擦を取り除くことに成功し、いまや日米間の伝統的友好関係は一層強固なものになつております。アジアにおいて、米国、中国、ソ連にとりかこまれた日本は、今後ともアジアにおける平和的な安定勢力としての役割を力強くになつていく決意であります。 ガットとIMFの体制に支えられて、史上かつてみない拡大と発展を記録することのできた世界経済も、いま、通商、通貨、インフレーション、エネルギー・資源、食糧、環境、開発協力などの分野において解決を必要とする問題に直面しております。これらは、われわれにとつて共通の関心事でありますが、いずれも世界的規模の難事業であります。 第2次大戦後の世界の歩みに、主導的な役割を果してきたのはアメリカでありました。しかし、いまや、欧州や日本は、重要な経済単位として、世界の繁栄の動向を左右する新たな極となりつつあります。これらの難問題は、世界の主要な経済単位の相互協力なくしては解決できないのであります。とりわけ日欧米三者の密接な協力を必要としております。こうした文脈のなかで、去る9月14日、ガット閣僚会議において、新国際ラウンドの開始をつげる東京宣言が採択され、通貨改革と並行して通商の側面から国際経済の新しい体制づくりに向つて画期的な一歩を踏みだしたことは、歴史的にも重要な意義をもつものであります。永続する平和の構造を築くためには、日欧米の三先進工業地域が相互の利益、相互の約束、および全般的な相互主義の原則に基づき、普遍的、開放的な経済秩序を建設してゆくことが必要であります。 1950年5月9日,当時フランス外相であつたロベール・シューマンは,ライン・ルーフとアルザス・ロレーヌ間の無用な競争を物理的にも不可能とするため,「西ドイツ,フランスの生産するすべての石炭と鉄鋼を共同管理機関のもとにおき,この機関は他の欧州諸国も加盟できるものとする」という提案を行ないました。この提案から2年後の52年にECSCが誕生し,その精神が発展してEECとなり,次いで拡大ECの形成となつたのであります。この歴史的発展の推移をみるとき,巨大な経済単位である欧州は,世界経済の拡大発展と繁栄の維持のためにも,世界に向つて開かれた経済社会を形成してゆくことが期待されております。 今日、主要工業国の一員となつた日本も、たんに平和の享受者にとどまることなく、平和の創造と世界経済秩序の再建にすすんで参画し、その責務を果すべきものと考えます。第2次大戦後、日本は、復興経済から高度成長経済へ、さらに国際経済へと3段とびをなしとげる過程で、ひたすら歩んできた成長の延長線上にめざす果実があるものと信じ、1日も早くそれに到達しようと努めてきました。そうした過程でわが国産業の国際競争力と生産力は飛躍的に伸長し、労働者の時間あたり賃金も1ポンド弱になり、欧州諸国の水準に達したのであります。しかし、日本の国土面積は37万平方キロメートルで、イタリーよりもやや広いのでありますが、その国土のわずか1パーセントの地域に、フランスの総人口をやや下回る数の人間が集中するに至りました。この結果、巨大都市は、過密のルツボで病み、公害、住宅、ごみ処理、物価などの問題が発生しており、半面、農山村は、若者が減つて、成長のエネルギーを失なおうとしております。他方、所得水準の上昇にともない国民の求める豊かさの質も、フローの豊かさからストックの豊かさへ、物質的豊かさから心の豊かさへと多様化し、かつ高度化しつつあります。こうした情勢に対処して、私は、生産第一、輸出優先から生活優先、福祉充実へと政策の重点を切りかえ、うるおいのある生活空間と多彩な余暇空間を積極的に創造することを内政の最大目標として、日本列島改造を提唱しております。 このように国内経済を充実させ、国民の福祉を増進させてゆくことは、世界とくに欧州の商品、資本および技術に対し、人口1億の将来性にとんだ巨大な市場を提供することを意味するのであります。しかも私は、わが国経済の一層の開放化と自由化を指向する一連の措置を強力に推進しております。この結果、わが国の輸入は激増し、本年上半期の輸入は、前年同期よりも52パーセントも増加いたしました。国際収支の不均衡は、予想を上廻るテンポで是正が進み、2月末190億ドルに達した外貨準備も、9月末には150億ドルを割つたのであります。わが国は、今後とも、世界に向つて開かれた経済社会を形成し拡大を続ける市場を提供することにより、積極的に世界貿易の拡大、とくに日欧貿易の拡大均衡に貢献してまいりたいと考えます。 飜つて日欧関係をみますと、日米、欧米の濃密な関係に比べて、不吊り合いな程に疎遠であります。日欧間の経済交流は、マージナルな規模でしかなく、日欧貿易量は日本および欧州の貿易量のそれぞれ10パーセントおよび3パーセントにすぎないのであります。また、日本と欧州との関係は、歴史的に長いのでありますが、開けゆく日欧関係の要請をみたし得ないコミュニケーション・ギャップが存在するのであります。日本の近代化は、欧州先進国の制度、文物を学ぶことによつて達成され、たしかに個々の日本人の心の中には古き良き欧州のイメージが定着しております。それだけに日本人は、古くからの知識に安住して躍進する欧州の現実の姿に目を向けることが少なかつたと言えましよう。他方、欧州人の日本に関する判断は、過去につくられたイメージの上に構築されているきらいがあり、また日本に関する知識は一握りの知日家の手に委ねられ、広い国民的基盤による交流は限られているのであります。72年に英、仏、独の3国から日本を訪れた旅行者は7万1千人にとどまつており、日本からこれら3国への旅行者も12万7千人にすぎません。たしかに、両者は、文化、歴史の背景を歴然と異にし、言語の障壁もこえがたいものがあります。しかしながら、お互いが共通の目的をもつて理解に努め、努力をおしまないならば、その相違を克服できないはずはありません。このためにこそ、ひとり首脳同士だけではなく、政府、言論人、民間経済人、学者など国民各層において間断なき、かつダイナミックな対話を行なう必要があります。私は、このような見地から、英国に対しては、英国の大学における日本研究を促進するためのささやかな貢献として、国際交流基金を通じて,3億円に相当する基金の贈与を行ないたいと考えます。 日英貿易関係は、英国政府のめざましい努力及び業界間の交流によつて最近徐々にではありますが改善の方向に向つております。ここ1〜2年における日英両国政府首脳間の交流は目を見張るものがあります。また、先般東京に英国トレード・センターが開設され、ケント公御夫妻が開所式に臨まれたことは英側の対日輸出努力を盛り上げる上で非常に印象的でありました。 歴史家アーノルド・トインビー博士の言をまつまでもなく、今日、われわれは、祖国に対する忠誠心と人類に対する新たな忠誠心の二つをあわせもつことが必要であります。地球的規模での環境汚染の拡大、エネルギー・資源の枯渇化の懸念など、人類社会に生起しつつある重要問題は、いずれも「自分さえよければ・・・・・・」という利己的な態度では決して解決できないのであります。環境問題を克服するためには大気や水が世界の共有物であり、それを汚すことは人類の危機につながるとの認識が必要であります。また資源問題も、狭いナショナリズムにとらわれず、資源の効率的活用と公平な分配をめざして協力し協調してゆかねばならないと思います。このような全人類の連帯意識は、一朝一夕には生まれるものではありませんが、いま大切なのは、そのためのあらゆる努力であります。日欧米は、国際社会におけるそれぞれの地位と責務を自覚して、21世紀に向う人類社会の前進のために、そしてまた国際社会の協調と融和のために、先駆的かつ主導的役割を果してゆく必要があると思います。私は、これこそ多極世界における日欧の新しい役割であると信じて疑いません。 御静聴有難うございました。 |
| 【1973.10.8日、ソ連側主催午餐会に於ける首相挨拶】 |
| 片岡憲男著「田中角栄邸書生日記」(日経BP企画、2002.4.30日初版)の付録に「田中角栄総理大臣 主要演説」の該当箇所より転載する。 |
| 【1973.10.12日、東南アジア開発閣僚会議における首相スピーチ】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
| 代表ならびに、ご列席の皆様
第八回東南アジア開発閣僚会議が開会されるにあたり、日本国政府及び国民を代表し、心から歓迎の意を表しつつ、一言ご挨拶を申し述べます。 まず、この会議が今回その発足の地において第八回目を迎え、しかも新たにビルマ並びに大洋州から豪州及びニュージーランドの両国の参加をも得て、更に発展を遂げようとしていることは、東南アジアの開発という共通の目的に対する認識と支持が一層深まり、かつ、強化されたことを示すものであり、私としても大きな喜びを感ずるのであります。 この機会に、私は、わが国と東南アジアとの関係及びわが国の開発協力のあり方について、私の率直な所信を申し述べたいと思います。 近年におけるわが国と東南アジア諸国との関係は、ますます増大する人的、経済的交流にも明らかなように密接の度を加えております。これは、両者が、単に地理的、歴史的に緊密に結びついているだけではなく、今日、双方の繁栄は、互いに切り離しては考えられないという特別の関係にまで発展しているからであります。 しかしながら、このような関係は、他の先進国と一部開発途上国との場合のような特定の条約や機構といった確たる法的、形式的裏付けあるものでは決してありません。それだけに高度の相互依存、相互補完の関係という強固な実質的絆をもつ両者の結びつきを更に一層強じんなものとして維持して行けるか否かは、われわれの今後の意思と努力とにかかっていると言っても過言ではないのであります。 今日、開発途上国に対する開発協力は、わが国の確立した基本政策であり、政府は、国民の強い支持の下にこれを推進しております。私は、開発協力の重要な目的は、開発途上国の国造りを助けることにあると信じます。私共は、開発途上国への援助が、自らの利益追及に傾きがちであった過去を反省し、本当に相手に役に立つ援助方式をきめこまかく誠実に実行することが必要であります。わが国は、開発途上国に対し、一九七二年において二十七億三千万ドルの経済協力を行ないましたが、うち政府開発援助は、六億一千万ドルでありました。 このような開発協力は、これまですべての点で満足すべきものではなく、量的にも、質的にも、改善をしてゆかねばなりません。現在、多くの開発途上国が歩みつつある工業化と近代化の道は、明治以来百年間にわたって、わが国が踏破してきた道でありました。その意味で、わが国こそ、これらの国に対して、自らの体験に基づく血の通った援助を実施することができるのであります。とくにその質的側面、なかんずく援助条件の改善のためには、新たな努力をみのらせてまいります。またすでに約束した案件の実施については、わが国側の事由により、遅滞することのないよう、政府としても常時注意を払ってゆくつもりであります。このように開発協力を充実してゆくことは、永続的な世界平和の創造と新しい世界経済秩序の再建に進んで参画し、その責務を果たすことともなるのであります。 最後に、私は、各国相互間の「間断なき対話」の重要性について改めて強調したいと思います。わが国とこの地域諸国間の関係は、最初に述べたように深い相互依存関係にあり、今日基本的にはきわめて満足すべきものと考えております。しかし、相互理解と信頼をより強固なものとするためには、この会議その他あらゆる機会をとらえ、官民あらゆるレベルにおいて不断の対話を持ち継続して行くことを提案したいのであります。このような対話こそ開発問題の解決のため、最も適切な方途であります。この対話の一環として、私は、出来るだけ早い時期にこの地域の幾つかの国を親善訪問することを考えております。 私は、新たにビルマ・豪州・ニュージーランド諸国からの代表の参加をえたこの記念すべき機会にあたり、閣僚会議が、過去七カ年の経験と成果の上に、一層の発展をとげ、新しい連帯感に立ったすそ野の広い協力・協調関係を打ちたてられてゆくことを心から期待するものであります。 ご静聴ありがとうございました。 |
| 【1973.10.23日、ラーマン・バングラディシュ首相歓迎晩餐会における田中内閣総理大臣スピーチ】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
| ラーマン首相閣下、並びに御列席の皆様
わが国とバングラデシュとの間に外交関係が樹立されて以来、両国国民の願望でありましたラーマン首相閣下の御来日がこの度実現を見ましたことは誠に喜ばしく、私は日本国政府及び国民を代表して、心から歓迎の意を表する次第であります。 申すまでもなく、バングラデシュ人民共和国の独立の過程及びその後今日に至る国家建設の過程において、ラーマン首相が示された卓越せる指導力と御功績は、広く世界の知るところであります。私はかねてより、ラーマン首相に深い尊敬の念を抱いて参りましたが、この度貴首相に親しくお会いする機会を得て、更にその念を強めた次第であります。 わが国とバングラデシュ人民共和国は、昨年二月外交関係を樹立いたしました。したがって両国関係は、国と国とのお付合いとしては、比較的新しい仲といわねばなりません。しかしながら、わが民族とベンガル民族との心と心の触れ合いという点になりますと、実はもっと長い交流の歴史があるのであります。すなわち、わが国の明治時代において、ベンガルの生んだ、偉大な詩人にして思想家であるタゴールに、岡倉天心、大隈重信始め多くのわが国の先覚者達との親交を通じ、わが国思想界、芸術界に大きな影響を与えたのであります。明治時代といえば、わが国の近代化の基礎を形成した重要な時期でありましたが、この時期にわが国の先覚者とペンガルの哲人タゴールとの間に深い心の交流のあったことは極めて意義深いものがあると考えます。バングラデシュの国歌はタゴール自身の作詞、作曲になるということであり、ベンガルの哲人は今なおバングラデシュ国民の心の中に生きているとの感を深くしている次第であります。 さて、一九七〇年秋以降、バングラデシュが悲劇的な全土にわたる動乱、未曽有の規模の高潮等の大惨事に相次いで見舞われましたことは、われわれの記憶に新しく、その間にバングラデシュ国民が筆舌に尽くしがたい苦難をなめられたことにつき、われわれ日本国民は深い同情の念を有しております。かかる災害の爪痕は、今日なお深く残っているとうかがっておりますが、先日ラーマン首相よりバングラデシュの官民が多くの困難にもめげず、新しい国造りに全力をもって当たられていることを伺い、感銘を新たにした次第であります。 私どもも不幸な大戦争の後、極めて困窮した状況から復興に取り組んだ経験を有しており、目下のバングラデシュ国民の御奮闘に深い共感を覚えるものであります。私はバングラデシュ国民がラーマン首相の英邁な御指導の下に一致団結して国造りに邁進されれば、将釆必ずや成果をみるものと信じて疑いません。 わが国は、これまでバングラデシュ国民に対し食糧、衣料等の人道的緊急援助を中心とする協力を行なって参りました。私は、今後ともバングラデシュの国造りに、わが国としてできるかぎり協力するつもりでありますことを、あらためて明らかにしたいと存じます。 貴首相は、日本での御日程をほぼ終えられ、明朝バングラデシュに向け帰途につかれるわけでありますが、御滞在が有意義、かつ、実り多いものであったことを心から願っております。 御列席の皆様、ここに盃をあげ、チョードリ大統領閣下及びラーマン首相閣下の御健康、ハングラデシュ国民の幸福と繁栄並びに日本・バングラデシュ両国友好関係の一層の発展を祈念したいと思います。 |
| 【1973.11.1日、物価安定政策会議第4回総会における首相挨拶】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」より転載する。 |
|
物価安定政策会議第四回総会が開催されるにあたり、一言ご挨拶申し上げます。 今般、委員の改選に際し、各位にご協力をお願いいたしましたところ、快くご承諾いただき厚く御礼申し上げます。 昭和四十四年七月に物価安定政策会議が発足以来、これまで種々のご意見や有益なご提言をいただいてまいりましたが、政府といたしましては、極力これを施策に生かすようつとめているところであります。委員各位におかれましても、引き続き政府の物価対策について適切なご助言、ご指導をいただきますようお願い致します。 (最近の物価動向) 最近の物価動向をみますと、昨年末以来卸売物価が急騰に転じ、また四十七年中比較的安定的に推移しておりました消費者物価も、本年に入ってから高い上昇を続けており、物価の安定のために、なお一層の努力を傾注する必要を痛感しているところであります。本日、委員にお集まりいただきました機会に、当面の物価問題について所見の一端を申し述べたいと思います。 (国際収支と物価) 第一に、国際収支の大幅な黒字との関係であります。昭和四十六年以降、わが国の外貨準備高は四十億ドルから、本年二月のピーク時の百九十億ドルまで、実に百五十億ドル増加しており、その結果、外為会計の外貨買入れに見合う円約四兆五千億円が市中に散布されたのであります。また国際収支の不均衡是正のため、できるたけ早く景気を回復させるとともに、輸出を内需に転換させなければならない、という観点から、金融緩和策により、景気の浮揚を図ったのであります。 景気の上昇に伴い、円の実質的な切上げの影響も加わり、国際収支不均衡の是正、特に対米貿易収支の改善は、予想以上のテンポで進み、昨年のハワイ会談から一年を経ずして解決の糸口を把むことができました。わが国の対米貿易が米国海外企業との取引を含め、わが国の全貿易量の四〇%を占めている事実を考えるならば、対米貿易収支の調整がわが国経済の発展に不可欠の課題であることをご理解いただけると思うのであります。 しかし、一方において、このような金融の緩慢現象が、いわゆる過剰流動性の発生となり、土地、株式あるいは一部商品について投機的な動きの原因となった事実は否定できません。また、西欧主要国に比し、立遅れている社会資本あるいは生活環境施設の整備のための公共投資や民間建設活動が鉄鋼、セメント、塩ビ等の需給ひっ迫をもたらした面もあると思います。世界的な規模の穀物の不作、市況商品の高騰も影響しております。およそ過度の需要超過や投機的要素によって生ずる物価上昇については、厳に抑制しなければなりません。政府及び日銀は、本年初頭以来、金融の引締め、公共事業等の執行の繰延べなど総需要の抑制を中心とした緊急物価対策を数次にわたり実施してきたところであります。その効果は市況商品等を中心にあらわれはじめており、更にその浸透が期待されているところであります。 なお、引締め政策の実施に当たって慎重な配慮を加えなければならないのは中小企業の動向であります。スミソニアン体制前に比し、円の対ドル実質切上げは三〇%を上回っており、輸出関連中小企業をめぐる環境は極めて厳しいものがありました。政府としては、中小企業の相次ぐ倒産というような事態を回避しつつ、引締め政策の浸透を図ってきたことについても国民の理解を求めたいのであります。 (国際的インフレと物価) 第二に、国際的インフレの問題であります。物価の問題は、先進工業国に共通する現代の悩みであります。先般、わたくしは欧州各国を歴訪し、各国首脳と会談し、特にこの感を深くしたのであります。昭和四十年から四十六年までの実質国民総生産の平均伸び率は、わが国の一一・一%に対し、アメリカ三・一%、イギリス二・三%、西ドイツ四・四%、フランス五・七%でありましたが、この間の卸売物価の平均上昇率は日本が一・七%に止まったのに対し、アメリカ二・八%、イギリス四・三%、西ドイツ三・〇%、フランス三・七%となっております。本年上半期の卸売物価の対前年比上昇率では、アメリカ一〇・九%、イギリス六・二%、西ドイツ六・〇%、フランス一一・五%、日本は一〇・八%となっております。一方、経済成長率について見ると、昭和四十七年度で、わが国の九・二%に対し、これら諸国の成長率は四〜五%に止まっているのであります。 これらの数字から読みとれることは、インフレ傾向がまさに国際的な問題になっているということであります。このことは、国際的な過剰ドルの存在、ドルの兌換停止、国際的な通貨不安と無関係ではありません。現在、関係国間で国際通貨制度の問題が鋭意検討されておりますが、主要国が相協力して、戦後四半世紀にわたり世界の繁栄を支えてきたIMF体制に代わる通貨体制を創造し、国際的インフレを収束することが急務であると考えます。 また、経済成長率との関係でみれば、欧米主要国のインフレ問題は、より深刻であります。これら各国は法律に基づく賃金、価格の凍結、あるいはガイドラインの設定など、いわゆる所得政策を実施しております。しかしその施策は必ずしも好結果をもたらしているとはいえず、各国とも物価問題の難しさをあらためて認識するとともに、その解決には国際協調の必要なことを痛感しているところであります。 所得政策を行なうには国民的合意が必要であります。しかし、わが国の現状においては、まだこのような国民的合意が得られる段階にないと考えますし、政府は、そのような道を選択しないで問題解決に取り組んでいるのであります。むしろ、賃金、物価の凍結のような事態に至らぬ前に国民的な自戒が必要であります。 公害費用、原料あるいはエネルギー価格の上昇等コスト面の価格上昇要因も少なくない現状において、生産性の上昇を上回る賃金の上昇や適正な価格形成を上回る安易な利潤追求が物価に悪影響を及ぼすことは明らかであります。わたくしは、この際、物価安定の見地から経営者も勤労者も等しくその社会的責任を認識し、節度ある態度をとられることを強く望みたいのであります。 (消費の動向と物価) 第三に、消費の動向についてであります。昭和四十八年度の給与所得は五十兆円に達しようとしております。本年度の百貨店の売上高が前年比三〇%に近い高水準を維持していることは旺盛な消費を物語るものであります。 わたくしは先般、昭和四十九年度の税制改正の基本構想を指示致しました。サラリーマンの負担軽減を中心とし、二兆円(初年度一兆六千億円)の大幅所得税減税を行なうこととし、特に課税最低限をサラリーマン標準世帯で百七十万円(初年度百五十万円)に引き上げます。所得税減税は消費を刺激して、物価対策上マイナスであるという意見も聞かれますが、長期的観点から減税が国民生活の向上をもたらすことは明らかであります。 ここで要請しておきたいのは消費者の節度ある態度であります。今回、西欧主要国を訪問して痛感したことは、国民の生活が堅実、質朴であり、落着いていることであります。資源・エネルギーの節約が叫ばれ、とりわけ物の豊かさとともに心の豊かさが求められている折から、国民生活のあり方において、今なお西欧先進国に学ぶべき点があると考えます。 このことは「フロー」と同時に「ストック」の厚さと無関係ではありません。政府としても住宅を含め、国民の財産づくりについて更に施策を行なう考えであります。給与水準の上昇あるいは減税による可処分所得の増加分を、できるだけ健全な貯蓄に振り向けることを期待したいのであります。 (公共料金と物価) 次に公共料金問題についてであります。いわゆる公共料金は安きに越したことはありません。現に諸物価の上昇に比し、低位に抑えられてきました。昭和一一年を一とした昭和四十七年の東京都消費者物価は六四四であるのに対し、国鉄は二六九(改訂後三二七)、消費者米価は五〇四であります。 しかし公共料金を過度に抑制することは、国民の求める適正なサービスの供給に支障を生ずることにもなります。異常な物価高に際して、一時公共料金の改訂を留保し、時期を調整することはそれなりに意味がありますが、恒常的に公共料金を低位に据え置き、このためコストの一部を財政負担により賄うことは、結果として、より優先度の高い財政支出を困難にすることにもなりかねません。 地方公共団体の公営企業についても同様であります。赤字補填のための財政負担を行なうよりも、むしろ賃金の上昇や減税の恩恵を受けることのない老人層に対する施策や、難病、奇病に悩む者、心身障害者の療養費の公費負担等に財源を配分すべきであります。このような意味で、社会保障の充実については政府としては格段の努力を致す所存であります。 (地価問題) 次に、地価の問題であります。 地価上昇の原因は、基本的には、宅地需給の不均衡にあります。 未利用地の活用、都市立体化の推進、国土の総合開発による宅地需要の分散と宅地の円滑な供給が、地価問題解決の抜本策であります。 このため、三大都市圏の市街化農地の宅地なみ課税、特別土地保有税、土地譲渡益に対する特別課税は、すでに実現しました。 先の国会に提案し、継続審査案件になっている国土総合開発法案は、土地利用基本計画の作成、特別規制地域における土地取引の規制、特定総合開発地域における総合開発を促進するための措置等を定め、国土の総合的かつ計画的な利用、開発保全をはかることを目的とする土地対策の基本法的役割をになうものであり、一日も早い成立が望まれるのであります。 (まとめ) 以上、わたくしは当面する物価問題について所見の一端を申し述べました。 先程触れましたように、政府としては物価の安定を現下の最重点課題として、財政の執行の繰延べ、金融の引締め、民間設備投資、建築投資の抑制等に全力をあげて取り組んでいるところであります。 その政策効果が末端まで浸透し、需要の堅調が一服して物価の動向に好影響を与えるまで、現在の金融引締めは堅持される必要があると考えております。国際的インフレ問題に対しては、国際協調の実を挙げるよう、引続き主要各国に働きかけてまいります。 また、住宅問題をはじめ、国民の堅実な財産づくりのための施策を行なうとともに、社会保障の充実を図ってまいります。 この機会にあらためて、国民の理解と協力を求めたいのであります。各界の指導的立場を代表される委員各位におかれては、物価安定のための国民的努力の支柱となっていただきますよう、とくにお願いするものであります。 以上、わたくしのご挨拶と致します。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)