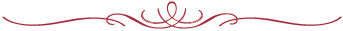
| 1972年時の田中角栄演説 |
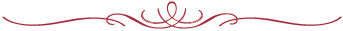
(最新見直し2008.12.23日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 1972年の田中角栄演説を渉猟する。 2007.5.9日 れんだいこ拝 |
| 【1972.3.21日、田中通産大臣の衆議院商工委員会答弁】 | ||
1972.3.21日、田中通産大臣は、衆議院商工委員会質疑の答弁で次のように述べている。
同3.23日、田中通産大臣は、衆議院予算委員会第4分科会に於いて次のように答弁している。
|
| 【1972.6.21日、田中角栄の自民党総裁選立候補声明「新しい政治を目指して」】 |
| 片岡憲男著「田中角栄邸書生日記」(日経BP企画、2002.4.30日初版)の付録に「田中角栄総理大臣 主要演説」の該当箇所より転載する。 |
| 私たちは今、内外二重の転換期に生きております。『第二の開国』とも云うべき試練に直面しております。この時に当たり、私は時代の要請をひしひしと感じ、国民の為の新しい政治を実践するために、自由民主党総裁選挙に立候補することを決意いたしました。 世界は新しい時代に入りました。力の均衡による平和の確保から、話し合いによる緊張の緩和へと、東西の関係は次第に改善の方向へ進んでおります。又世界の新しい問題の一つに南北問題があります。『北』の国々が、人類の3分の2以上を占める『南』の開発途上国に対する援助と協力を拡大することによって、南の国々の発展が生まれ、平和の維持も又約束されるのであります。東西の問題にも、又南北の問題に対しても、我が国の役割と責任は大きくなっております。 戦後27年余り、国内も又、転換と変革の時を迎えております。私たちは戦後の荒廃から立ち上がるために、精一杯働いてきました。そして、短時日のうちに今日の繁栄を確保することができました。汗を流して築き上げた実績は、日本人自らの努力の集積であり、誇りうるものであります。経済は量的に十分拡大しましたが、質的な充実はこれからであります。 又、成長の蔭に公害、物価高、過密と過疎の難題、教育の混迷、世代間の断絶など、解決を必要とする問題が数多く現われて参りました。 内外の課題が山積する中で、国民の間に、いらだち、悩み、前途に対する不安が見られます。しかし、我が国の長い歴史を紐解くまでもなく、幾多の困難を乗り越えてきた私たち日本人に、これしきの問題が解決できないはずはありません。高い理想を掲げ、しかも、あくまで現実に立脚し、勇気を持って事の処理に当れば、理想の実現は可能であります。 我が国の民主政治は、敗戦という高価な代償の上に育ちました。大事に育てて、後代の人々に引き継ぎたいものであります。 政治は国民全体のものであります。70年代のどの課題をとってみても、国民の参加と協力なくして解決できるものはありません。国民の生活感覚に基づく大衆政治を蘇(よみがえ)らせてこそ、政治不信は解消できるのであります。又、政治は国民の英知と活力を吸収できるのであります。 70年代の政治には、強力なリーダーシップが求められています。新しい時代には新しい政治が必要であります。 政治家は国民にテーマを示して、具体的な目標を明らかにし、日限を切って政策の実現に全力を傾けるべきであります。しかし、民主政治のもとでは、個々の政策がいかにすぐれていても、国民の理解と支持が無ければ、政策効果をあげることはできません。私は国民の皆様と一緒に考え、熟慮し、断行いたします。最善の為に時間がかかれば、次善をとります。右顧左眄は致しません。時には苦(にが)いものであっても、それが真実であればありのままを皆さんに訴えます。結果についての責任は私が負うつもりであります。政治責任の明らかな『決断と実行』の政治こそ、私の目指すところであります。 私は日本中の家庭に笑い声が溢れ、老いも若きも明日に希望を繋ぐことができる社会の建設に、全力を傾けて参ります。国民皆さんのご理解とご支援をお願いいたします。 |
| 【1972.7.7日、田中角栄の自民党総裁被選出時の決意表明】 | |
中野士朗「田中政権886日」のP4に「田中新総裁あいさつ」が掲載されている。これを転載する。
|
| 【1972.7.7日、田中角栄新首相談話】 | |
1972.7.7日、田中内閣総理大臣談話。(「田中内閣総理大臣演説集,4‐5頁」)
|
| 【1972.8月、田中角栄の経済審議会諮問会議での挨拶】 |
| 「1972.8月、田中角栄の経済審議会諮問会議での挨拶」。 |
| 私は、今回新しい内閣を組織、国政を担当する事になりました。内外共に多難な折ではありますが、『決断と実行』を基本として新しい政策を展開していく所存でありますので、よろしくお願い申し上げます。 政府は、昭和45年5月、『新経済社会発展計画』を策定し、我が国経済運営の指針としてまいりましたが、計画策定後の内外情勢の変化には著しいものがあり、解決を要する幾多の課題が生じてきました。 まず、対外面では、国際関係の多極化、流動化が激しく進み、過去四半世紀のあいだ自由世界の発展を支えてきた国際経済社会の構造は、大きく変化してきております。昨今の国際通貨体制の危機は、このような構造変化の一つの表われであり、昨年末の多国間通貨調整によって一応乗り越えられたかに見えますが、長期的には、なお、動揺を続けるものと思われます。我が国としては、こうした国際経済社会の構造変化を十分に見通し、国際社会の強力な一員として、我が国の基本的外交政策を確立する事が必要であります。 特に、地域主義やナショナリズムの高まりの中で、経済・文化面を含む国際交流を全世界にわたつてどのように拡大していくか、また、深刻化する南北問題の解決にどのように寄与していくか、などの課題に真剣に取り組むべき時期にきております。 次に、国内面では、昭和30年代以降の長期にわたる経済の高度成長に伴い、解決すべき多くの課題が累積し、政策体系の思い切った転換が必要となっております。このような困難な課題をもたらした基本的背景の第一は、経済成長に伴って所得や消費の水準が西欧先進国に比肩とうるまでに向上したのに対し、生活関連のストックの水準や所得の分配の面で問題が深刻化してきていることであります。住宅・生活環境の悪化、社会保障の遅れや物価上昇に伴う分配の不公平などがさの代表的なものであります。 基本的背景の第二は、生産及び消費活動の規模が巨大なものとなるに伴いいわゆる外部不経済が著しく拡大した事であります。公害の激化、自然破壊の進行、過密・過疎などの問題がその典型であります。 基本的背景の第三は、我が国の経済社会の活動とそれを取り巻く外部環境との関係で、一つの限界、換言すれば有限性に直面しているということであります。それは、自然環境の有限性、土地、水、そのほかの資源の有限性、我が国から見た世界市場の有限性などに端的に表われております。 以上のような内外両面にわたって山積している諸課題と、それをもたらした基本的背景の動きを総合的にとらえ、生活と産業の将来にわたって、今後、我が国が進むべき進路を国民の前に明らかにすることは、我が国にとって緊急の課題と考えております。 このような観点から、私は、新しい内閣の政策運営の基本として新しい長期経済計画を策定するのが適当と考え、本日個々に経済審議会におはかりすることとした次第であります。経済審議会におかれましては、これまでの調査・研究の成果を踏まえて、我が国の新しい発展段階に相応しい優れた計画を作成していただきますようお願いいたします。 新計画の内容は、今後に於けるご審議に松べきものであることは申すまでもありませんが、せっかくの機会でありますので、新計画に対する私の期待について申し述べ、ご審議の参考に供したいと存じます。 第一に、内外情勢の激しい変化に対応しつつ、既述のような山積している諸課題を根本的に解決していくためには、戦後四半世紀あるいは明治百年にわたつて保持されてきた古い制度やメカニズムを改め、新しい時代に相応しいものに作り直していく必要があります。現在、先鋭化している諸問題の要因は、既存の経済社会の仕組みに深く根ざしているだけに、包括的・長期的な視点から改革を進める必要があると思います。 このような視点から、従来の生産・輸出優先の路線を改め、福祉充実と国際協調優先の路線へ転換する事が肝要であります。そのため新しい全体的な経済社会の仕組みを描き、その実現のために財政金融、土地、地方自治、教育、医療などの諸制度やメカニズムを改革し、再編成していくことが極めて重要だと考えます。今後のご審議に拠って、どのような制度やメカニズムを創出していくか、ぜひ具体的に明らかにしていただきたいと存じます。 第二に、新しい制度やメカニズムを創出し、またこれと関連させながら望ましい資源分配や所得分配を着実に実現していくため、新計画に於いては、整合性のある政策体系をスケジュールとともに提示する必要があります。 特に、高度福祉社会の実現の基礎となる重要な項目、例えば、住宅、生活環境、公害防止、社会保障などについては、はっきりした政策目標を示す事が重要だと思います。 また、政策手段としては、これまでの財政金融政策に加えて、長期的観点から租税政策、公債政策、為替政策などを含めた新しいポリシー・ミックスの在り方を総合的に検討すると共に、社会福祉政策、環境保全政策、都市住宅政策などのきめの細かい構造政策を政策目標と対応させて、大胆に打ち出すべきだと考えます。 さらに私は、計画を作成するだけではなく、計画の実施を強力に進めることが極めて重要だと思います。そのためにも、計画の中で整合性のある政策体系を提示しておくことが不可欠の前提でありますが、私としては、このような要件を備えた立派な計画を作成していただくならば、その実行を大胆かつ強力に推進して参る所存であります。 また、経済審議会におかれましても、計画作成に続いて、計画通りの政策運営を見守る意味に於いて、常時アフターケアを行う体制をご考案いただければ幸いに存じます。 最後に、私の提唱いたしました日本列島改造案と新しい長期経済計画との関連について、一言触れさせていただきたいと思います。 日本列島改造案は、ご承知のように、工業の再配置、全国的な交通・ネットワークの結成、新しい地方都市の建設を三本の柱として、我が国の産業構造及び地域構造を改革し、日本列島の改造を進めていこうという構想が中心となっておりますが、もとより、私の考えについての建設的なご批判があればお聞かせ願いたいと考えております。その上で、もし私の考えの大筋にご賛同を得られれば、新しい長期経済計画にもこれを反映させていただきたいと存じます。 我が国が新しい発展段階を迎え、政策転換を求められている今日、皆様のご審議のもとに作られる新しい長期経済計画は、我が国の新たな発展の目標として、またそれを実現するための政策転換の指針として、大きな役割を果たすものと考えます。どうか自由な立場から十分ご審議を尽され、立派な計画としていただきますよう重ねてお願いいたしましてご挨拶と致します」。 |
| 【1972.9.11日、田中角栄の全国知事会議における首相説示】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」の「1972.9.11日、田中角栄の全国知事会議における首相説示」より転載する。 |
|
私は、本年七月、内外のきわめてきびしい情勢のもとで政権を担当することとなり、爾来国運の発展のために全力を傾け、内政・外交の衝に当たってまいりました。 本日、この機会に所信の一端を申し述べ、各位の理解と協力をいただくとともに、きたんのない意見を聴取し、国、地方を通じて緊密な連けいのもとに行政のいっそうの進展を図ってまいりたいと思います。 わが国は、長期にわたり経済の高度成長を遂げ、国民の所得水準は大幅な上昇をみておりますが、一方、国内面では過密、過疎の問題をはじめ、生活環境の悪化、社会保障の遅れ、物価問題等多くの難問題が山積し、また、対外的にも国際社会における責任の増大に加えて貿易上の摩擦増大等の事態に直面しております。 このような時代の転換期に際し、われわれは新しい時代の要請にこたえ、心をあらたにして問題の解決に取り組まなければなりません。 (長期経済計画) 近年わが国の内外情勢の変化はまことに著しいものがありますが、このような流れの変化に即応しつつ、前述の当面する多くの課題を解決していくためには、わが国のめざすべき新しい経済社会の全体像を明らかにし、長期的な観点に立ってその実現のための施策を遂行していくことか必要であります。このような観点から、政府はさきに、経済審議会に対し、「内外諸情勢の急速な転換に際し、国民福祉の充実と国際協調の推進をめざした新長期経済計画」の策定について諮問をいたしたのであります。今後審議の促進をお願いし、できれば四十八年度予算編成に間に合わせうるよう、すみやかにその答申を得て総合的な施策を展開してまいる所存であります。 (日本列島改造事業) 過密と過疎の弊害を同時に解消し、国民のすべてが誇りと愛着をもちうる国土を造り上げることは、今日の最も重要な国民的課題であります。しかしながら、これを達成するためには、産業と人口の大都市集中の流れを大胆に転換し、万全な公害対策を講じながら全国的な視野に立った合理的な土地利用を図ることがぜひとも必要であります。 このような観点に立って、政府は、昭和四十四年に策定した新全国総合開発計画について環境問題の側面から総点検を行なうとともに、合理的な国土利用の長期ビジョンの策定を急ぐ所存であり、地域開発のもととなる工業の再配置を促進するとともに、地方都市の整備拡充および総合的な交通・通信ネットワークの形成を進めてまいります。また、大都市地域においても、住宅、事務所の高層化を進めるなど思いきった都市改造に取り組み、公園、緑地の増加や道路の拡張などを図り、これらをテコとして日本列島の改造を進めてまいりたいと考えます。 以上述べたような国土改造の成否をにぎる鍵は、土地対策にあるといっても過言ではありません。このため、政府としては、国土の合理的な利用をねらった全国の土地利用計画を確立して、人口、産業の大都市への集中を抑制し、これらの地方分散を図ることとしているほか、地価対策についても地価公示制度を飛躍的に拡充し、公的土地評価体系を整備する等の措置を講ずる所存であります。このため、士地の計画的利用と調整を図るための法律や工場法等を立案し、次の通常国会に提出する予定であります。 日本列島改造事業の前途には、幾多の困難な問題が横たわっており、全国民の英知をもって忍耐強く進めなければその達成は不可能であります。政府としては、日本列島改造問題懇談会等を通じて関係各方面から幅広いご意見を承ることとしておりますか、地方行政を担当される各位の積極的かつ建設的な協力をお願いする次第であります。 (公害防止および自然保護) 公害問題は、光化学スモッグやPCB汚染にみられるように、複雑化・広域化の傾向を強めています。また、四日市判決からもわかるように、立地政策の再検討、汚染物質排出量の総量規制の導入など公害対策の拡充が強く要請されるところであります。 政府は、工場、自動車等に対する公害規制をいっそう強化するとともに、根本的には、環境保全の見地から国土利用の将来のあり方を見定め、工業と人口の再配置を推進するに当たって、環境保全の面からの配慮を十分に行なうとともに、各種の公共事業や地域開発を行なうに当たっても環境面からの事前のチェックを徹底して行ない、汚染の未然防止に努める所存であります。また、公害に係る被害者の救済の実効を期するため、損害賠償を保障する制度の創設を検討していく所存であります。 美しい国土、豊かな自然を永く子孫に伝えることは、われわれに課せられた責務であり、政府としても自然環境保全の基本方針を定める等総合的な自然保護対策を展開していく所存であります。 (社会保障) 七十年代の重要政策課題のひとつは、成長と福祉のギャップに対処して福祉の画期的充実を図ることであり、すべての国民に健康で文化的な生活を保障することであります。このため、社会保障の面で思い切った改善が必要でありますが、とくに当面緊急の課題として、社会的に保護の手を差し延べる必要のある老人や身体障害者、あるいはいわゆる難病に悩む人々に重点をおいて対策を講じてまいります。 まず、到来する高齢化社会に備えるために、総合的な老人対策は国民が一体となって取り組まなければならない課題であります。とくに老後保障の中心となる年金制度については、昭和四十八年を「年金の年」として、老後を託するに足る年金をめざし画期的な改善に努めてまいるほか、老人医療制度の拡充、老人ホームの整備、在宅老人対策の強化等について積極的に取り組んでまいる所存であります。 他方、高齢者の雇用については、現在なお一般的に不安定であるので、定年の延長の推進とあわせて高齢退職予定者の再就職促進を強力に進めてまいる所存であります。 つぎに、次代をになう児童の健全育成や社会的ハンディキャップを負っている身体障害者、心身障害児に対する保護施策、さらにこれらの施策の推進の基礎となる社会福祉施設の整備およびその職員の確保について施策の推進を図ってまいる所存であります。また、原因が不明であり、あるいは治療方法の確立されていないいわゆる難病対策についても、原因の究明、治療研究の推進等に積極的に取り組んでまいります。 さらに、医療の分野においては、医療需要の量的拡大、医療の質的高度化に対処するため、医療供給体制の整備を促進し、医師および看護婦その他医療関係者の養成確保対策をいっそう充実させてまいりたいと考えております。 なお、勤労者福祉については、国民が高福祉社会にふさわしい十分な余暇を享受することができるよう、週休二日制の普及促進に積極的に取り組んでまいりたいと思います。 (物価問題) 物価の安定は、国民生活の向上にとって不可欠の条件であります。消費者物価の騰勢は、幸い最近やや鈍化の傾向を示しておりますが、政府としては、従来から実施してまいりました低生産性部門の構造改善や輸入政策の積極的活用、競争条件の整備等の施策を一段と強力に推進するほか、とくに近年、流通費用の増大が消費者物価上昇の大きな要因となっているところから、流通機構の改善、合理化を積極的に推進していく所存であります。地域住民と不断に接触しておられる各位におかれましても、これらの対策について特段の協力と努力を期待するものであります。 (農業対策および中小企業対策) 日本列島の変化に富んだ自然条件を十分生かして適地・適作を進め、高能率・高生産の農業を展開することが農政の基本であります。このことは、同時に食料品の価格安定にもつながることであり、さらに経済の国際化に対処する方法でもあります。このため、政府は農業基盤の整備を進めるとともに、農業団地の育成、農地の流動化等を積極的に進めてまいりたいと思います。 また、農村につきましては、その恵まれた自然環境を生かしつつ豊かで近代的な社会として発展できるよう、農業生産基盤と生活基盤の一体的整備を行なう等高福祉農村の建設に努めてまいりたいと考えております。 次に、内外経済環境の変化はきわめて激しく、中小企業は、日本経済の国際化の進展、過密・公害等環境問題の深刻化、人間尊重社会への志向、産業構造の知識集約化の進展というあらたな環境変化に適時適切に対応するよう強く要請されております。 このため、政府としては、中小企業がこのような環境変化に円滑に適応していくことができるよう援助するとともに、とくに、一般的に企業体質が弱い小規模企業に対しては、一段ときめ細かく行き届いた配慮をしていく所存であります。 (教育問題) さて、本年は、「学制」が発布されてから百年の歴史を画すまことに意義深い年であります。この間、国民の強い熱意と幾多の先人のたゆまざる努力によって、わが国の教育はめざましい発展を遂げ、国際的にもきわめて高い水準に到達したのでありますが、社会経済の進展とともに教育のになう役割は今後ますます重要なものと思います。 このため、政府は、中央教育審議会の答申の趣旨をふまえ、広く関係各方面のご意見を十分承りつつ、教育の制度、内容の両面にわたり、総合的かつ長期的な教育改革の推進に当たる決意でありますが、とくに教育の根源である優れた教員の確保、生涯教育の充実、教育、学術、文化の国際交流等に力を注いでまいります。 (沖縄の振興開発) 国民の念願久しかった沖縄県の復帰が実現し、本日ここに、沖縄県知事を迎えることができましたことは、まことに慶賀にたえません。 今後は、沖縄の置かれた特殊事情にかんがみ、自治行政のための基礎的な諸条件を早急に整備し、さらには沖縄の地理的、自然的特性を生かした振興開発を図ることが重要な課題であると考えます。 また、昭和五十年には、世界最初の海洋をテーマとする沖縄国際海洋博覧会が開催されますが、これは、海洋に係る産業、文化等の各分野において、日本民族の英智と活力を世界に問う絶好の機会であります。この意義ある祭典を成功させるためには、国民各位の創造力を結集して諸般の準備をいっそう急速に進めなければなりません。 政府は、沖縄の今後の振興開発および沖縄国際海洋博覧会の準備の推進に努力してまいる所存でありますが、各都道府県におかれても、格段の協力をお願いいたします。 (地方行財政) 以上申し述べた内政上の諸問題の解決ならびに施策の推進に当たっては、地方行政の積極的な展開が強く要請されますが、地方財政の現状をみると、税収入の動向もいまだ予断を許さない状況にあり、引き続きなお厳しい環境にあります。政府としては、このような地方財政の現状に即してその充実を図るため、住民負担の合理化に配慮しつつ地方税源の充実を図るとともに、地方債の充実等についてもなおいっそうの努力を重ねていく考えであります。 (外交問題) おわりに、外交問題について一言申し上げたいと思います。 最近の国際政治情勢は、緊張緩和の方向に動き始めております。わが国としては、こうした時代の流れを的確にとらえつつ、世界の平和と繁栄のために積極的に貢献して行かなければなりません。このような観点に立って、国民的関心事となっております日中関係につきましては、目下政府の責任において両国の国交正常化を実現するため準備を急いでいるところであります。また、日ソ関係につきましても、多年の懸案である北方領土問題の解決のために、国民の支持を背景として粘り強く交渉を続けてまいりたいと考えております。 また、わが国にとって米国との友好関係の維持がきわめて重要なことは申すまでもなく、国際関係がいかに多極化したとはいえ、この事実はいささかも変わるものではないと信じます。先般のホノルルにおけるニクソン大統領との会談では相互にきたんのない意見の交換を行ない、米国との関係を地固めするために、たいへん有意義であったと考えている次第であります。 なお、わが国をめぐる国際経済環境は貿易上の摩擦が発生する等厳しさを増しておりますが、今後とも、わが国は、貿易立国の立場を貫き、保護主義の台頭を防ぎ、世界貿易の自由な拡大を推進して行かなければなりません。そのためには、自らも輸入の自由化、関税率の引下げ等を率先して実施するとともに、開発途上国への経済援助の拡充や国際収支赤字国への協力等、日本経済の成長が世界経済の拡大、発展に寄与する仕組みをつくり、これを世界に実証する努力を積み重ねる必要があります。その意味でも今後とも対外均衡の回復、維持に十分配慮した経済運営を進めてまいる所存であります。 以上内政外交上の諸問題について所信の一端を申し述べましたが、これらはいずれも地方行政を担当される各位の協力を得て、はじめてその効果を発揮できるものであります。 各位におかれましても地方行財政の効率的、積極的な運営を通じて住民福祉の向上と地方自治の進展を図られるよう格段の創意工夫をお願いする次第であります。 |
| 【1972.9.25日、田中首相の周恩来主催招宴に於ける挨拶】 |
| 片岡憲男著「田中角栄邸書生日記」(日経BP企画、2002.4.30日初版)の付録に「田中角栄総理大臣 主要演説」の該当箇所より転載する。 |
| 周恩来総理閣下並びに御列席の各位、このたび周恩来総理のご招待を受け、日本国の総理大臣として、隣邦中国の土を踏むことができましたことは、私の喜びとするところであります。本日はここに、かくも盛大な晩餐会を催していただき、まことに心温まる思いであり、関係者各位のご配慮に心から感謝いたします。 このたびの訪問に当って、私は、空路東京から当地まで直行してまいりましたが、日中間が一衣帯水の間にあることを改めて痛感いたしました。このように両国は地理的に近いのみならず、実に二千年にわたる多彩な交流の歴史を持っております。 しかるに、過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な歴史を辿って参りました。この間、我が国が中国国民に多大のご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。第二次大戦後に於いても、なお不正常且つ不自然な状態が続いたことは、歴史的事実としてこれを率直に認めざるを得ません。 しかしながら、我々は過去の暗い袋小路ないつまでも沈吟することはできません。私は今こそ日中両国の指導者が、明日の為に話し合うことが重要であると考えます。明日の為に話し合うということは、とりもなおさずアジアひいては世界の平和と繁栄という共通の目標の為に、率直且つ誠意を持って話し合うことに他なりません。私が今回当地に参りましたのは正にこの為であります。我々は、偉大な中国とその国民との間に良き隣人としての関係を樹立し、両国がそれぞれの持つ友好諸国との関係を尊重しつつ、アジアひいては世界の平和と繁栄に寄与するよう念願するものであります。 もとより日中間には政治信条や社会体制の違いがあります。私はそれにも拘らず、双方の間に善隣友好関係を樹立し、互恵平等の基礎に立って交流を深め、相互の立場を尊重しつつ協力することは可能であると考えます。 このように日中間の善隣友好関係を確固不動の基礎の上に樹立する為には、国交正常化が是非必要であります。もちろん双方にはそれぞれの基本的立場や特異な事情があります。しかしながら、例え立場や意見に小異があるとしても、日中双方が大同につき、相互理解と互譲の精神に基づいて意見の相違を克服し、合意に達することは可能であると信じます。私はこの大任を全うし、悠久にわたる日中友好の新しい第一歩を踏みしめたいと念じております。 この挨拶を終えるにあたり、私は、ここに閣下並びに各位とともに盃をあげて、毛沢東主席閣下の御清栄と、周恩来閣下のご健康とご活躍を祈念し、日中両国民の末長い友好とアジアの平和、繁栄のために、乾杯したいと存じます。乾杯 |
| 【1972.9.27(28日)日、田中首相の主催招宴に於ける挨拶】 |
| 片岡憲男著「田中角栄邸書生日記」(日経BP企画、2002.4.30日初版)の付録に「田中角栄総理大臣 主要演説」の該当箇所より転載する。 |
| 周恩来総理閣下、並びにご列席の各位。本夕ここに、周恩来総理閣下始め、中華人民共和国政府首脳、並びに関係各位のご列席を得まして、私どもの感謝の気持ちを表すための宴を催す機会を得ましたことは、私のまことに欣快とするところであります。 このたび、私をはじめ、大平外務大臣、二階堂官房長官以下随員一同、及び報道関係者に対して、周恩来総理閣下始め、中華人民共和国政府首脳並びに関係各位から、暖かい歓待と心のこもったご配慮を示されましたことにつきまして、私は、改めて厚く御礼申し上げます。 又、昨日私は、毛沢東主席閣下にお目にかかり、日中両国関係の将来、及びひろく国際の諸問題について御話し合いをする機会を得ましたが、この会談は私にとり、極めて感銘の深いものでありました。 私は、日中国交正常化という厳粛な使命を果たすため中国を訪問しました。これまで周恩来総理閣下をはじめ、貴国関係各位と親しくお目にかかり、終始友好的な雰囲気の中で、極めて率直に意見の交換を重ねてまいりました。今や、国交正常化という大事業を成就できるものと確信しております。 日中両国の首脳が、今回のように、膝を交えて友好的な話し合いをするまでには、長い歳月と茨の道がありました。私は、日中間の対話の途を拓く為貢献された両国各方面の方々に対し感謝の意を表明するものであります。 国交正常化は明日への第一歩であり、私は、歴史の大きな流れの中で、新しい展望を目指して進みたいと思います。今後、日中間には、なお解決すべき生田の問題があります。しかしながら、両国が互譲の精神と相互信頼に基づいて対処するならば、これは決して超克できない問題ではないと信じます。 かくして、これまでの両国間の不正常な状態に終止符が打たれ、両国国民の多年の願望である両国間の国交正常化が実現されるならば、これは、両国の歴史に新たな一章を開くのみならず、アジアひいては世界の平和に貢献するものと確信致します。 私は、今回の私どもの訪中が契機となって、相互の間に、多方面にわたる交流がますます促進され、両国が、強い友好の絆で結ばれるよう切望するものであります。 この挨拶を了えるにあたり、私はご列席の各位とともに、盃をあげて、中国の偉大な指導者、毛沢東主席閣下及び周恩来総理閣下の御健康と御活躍のために、中華人民共和国の繁栄、日中両国民の末長き友好、アジアと世界の平和のために、乾杯したいと思います。乾杯 |
| 【1972.12.19日、日本列島改造問題懇談会における首相挨拶】 |
| 「データベース『世界と日本』」(東京大学東洋文化研究所田中明彦研究室 )所収の左枠「国会外の演説・文書 総理大臣」の該当箇所より転載する。 |
|
日本列島改造問題懇談会の第三回会合にあたり、国土改造をめぐる諸問題について、所信を申しのべたいと存じます。 (一、総選挙後の新しい政局を担当する抱負と決意) 今回行なわれた総選挙をつうじ、いわゆる日本列島の改造問題は、今後の内政のもっとも重要な課題として、国民各位のあいだに大きな関心と議論を呼び起こしました。私はそのなかで、過密と過疎の同時解消をはかり、住みよく暮らしよい地域社会の建設を呼びかけた私の基本構想が、その大筋において国民各位の理解と賛成をえたものと確信いたしました。同時に、国民の多くか列島改造の前提条件として、地価値上がりの防止、公害の防除、生活環境の改善、物価の安定などについて、有効、かつ適切な政策の実施を求めていることを痛感いたしました。 私は、このような基本的な認識にたって、国土改造政策を総合的、計画的に進めてゆく決意であります。 (二、国土改造政策を推進するにあたっての基本的態度) この場合、私は、第一に国土改造を国土利用の再編成、施設の充実という物的な側面だけでなく、人びとが落ち着きとうるおいをもち、豊かで健康に暮らせるように配慮することが必要であると考えます。 第二に、老人や難病に苦しむ人びとのため社会保障を思い切って充実し、また民間の設備投資や輸出に偏っていた資源配分を改め、国民生活に直接、結びつく社会資本や公害防除の投資をできるだけ高めて、高度福祉社会の実現をめざします。 第三に、物価の安定をはかるため、適切な需給対策のもとで、流通部門の改善、生産性の低い農業・中小企業の合理化と近代化をすすめ、輸入政策をいっそう活用してまいります。なお最近、卸売物価の高騰がみのがせない問題になっておりますので、必要に応じ、出荷、輸入の促進などの措置を果断に実施する考えであります。 第四は、国際社会との協調、融和を促進するため、当面する国際収支問題について、この三年以内に基礎的収支の均衡を達成することをめざして、今後も総合的な対外経済政策を実施いたします。 こうした課題を解決するためには、わが国の経済社会の長期的な発展の方向を、これまでの成長追求型から、経済成長の成果を国民福祉の向上に役立ててゆく成長活用型へと大きく転換していくことが必要であります。このような観点から、わが国の産業構造の知識集約化と、社会的な責任を自覚した新しい合理的な企業活動が追求されなければなりません。また、農林漁業においても、国民にたいする食糧の安定的な供給の確保にあわせて、緑や海の保全といった面からの配慮が必要であります。さらに、財政主導型の経済運営をはかる見地から、財政の長期的かつ計画的な運営を検討するとともに、税制についても、その有効な活用をはかっていかなければなりません。 このようなわが国経済社会の長期的な発展の方向と、そのための政策体系は、近く決定される新しい長期経済計画において明らかにしてまいります。また、とくに緊急を要する施策については、昭和四十八年度予算に盛りこみ、あるいは次の国会に関係法律案を提案するため準備を進めているところであります。 (三、国土改造の方向) 以上のような基本的な態度のもとに、わが国の当面する諸問題を解決し、福祉志向型の経済社会の実現をはかるためには、これまでの偏った国土の利用を改め、国土の改造を強力に進めることが必要であります。 具体的には生活環境施設を中心とする社会資本投資の拡充、農林水産業や中小企業の近代化、教育環境の整備などを含めた総合的な施策を推進するとともに、環境の保全に万全の配慮をしながら、交通・通信ネットワークの整備、工業の全国的な再配置、地方中核都市の育成など三大施策を強力に実施することが重要であります。 このような国土の改造政策の実施にあたって、緊急の課題は土地対策と環境保全対策であります。 土地対策については、委員の皆様から多数のご意見をいただいておりますが、まず第一に、全国的な土地利用基本計画を策定し、さらに土地取引の届出制、開発行為の規制などをはかるため、国土総合開発法等の改正を命じております。また、これとあわせて、土地保有課税の強化、法人の土地譲渡益にたいする重い課税などの税制上の措置については、税制調査会の意見を十分に見きわめたうえで、結論をだしてまいります。さらに、投機的な土地の取得にかかる融資の抑制措置、また、公的な用地取得の促進措置についても結論を急いでいるところであります。 次に国土改造にあたって、わが国の豊かな自然環境を守り、国土全体を保全して、快適な生活環境をつくることは、国民に健康で住みよい地域社会をもたらすだけでなく、私たちの子孫に引き継いでいくためにも重要であります。このためにできるだけ早く環境資源の保全に関する長期的な計画を策定し、これを国土改造のための政策に反映させてまいりたいと考えております。 また、汚染物質の減少をはかるため、環境基準をきびしく改めるとともに、排出規制を強化する一環として総量規制などの導入につとめてまいります。もちろん、これらの規制強化に対応するためには、環境を保全する技術の開発が緊急の命題であります。私はとくに、無公害コンビナート技術の開発には最重点を置く考えであります。また、現代社会における広範な環境問題に対処して、実効性のある研究開発を助長し、育成するため、シンクタンクの機能をもった特別機関を設立いたしたいと考えております。 (四、国土改造の基本的施策) 次に、国土改造政策の中心となる三大施策について申しのべます。 第一は、交通・通信ネットワークの整備であります。 私はまず外国との輸送需要の増大に対処して、国際空港や国際港湾の整備、あるいは活用を積極的に推進してまいります。また、国内交通につきましては、昭和六十年までに、新幹線鉄道約七千キロメートル、高速自動車道約一万キロメートルを目標にして建設を進め、国鉄在来線の強化などとあわせ、陸海空にわたる全国的な交通ネットワークの整備と、新しい総合的な交通システムの確立をはかってまいります。なお、これらの整備にあたっては、騒音対策、施設のまわりの緑化対策などの環境保全対策にも万全を期してまいります。 一方、全国的な情報通信量の増大に対処して、郵便サービスの拡充や電話の普及率を大幅に高めるとともに、最新の技術を導入した高度な全国ネットワークの形成、電話料金制度の合理化をはかることといたします。 第二は、工業の全国的な再配置であります。 まず、その基本となる工業再配置計画をできるだけ早く策定し、雇用問題に留意しながら、再配置の目標を明らかにいたします。また、この施策の推進にあたって多くの国民から環境問題について不安があり、危険を指摘されていることも私は十分に承知しております。したがって、こうした不安をとりのぞくため、過密地域における公害発生源の総点検を行ない、住民の健康や生活環境に悪い影響がでてこないようなきびしい環境水準を確保することに全力をつくす所存であります。そのうえで、自然環境と調和した工場建設のために、工場内の生産施設用地の比率を一定の割合以内にととめたインダストリアルパークの実現と、コンビナートの公害防止をはかるため、「工場立地法(仮称)」を次期国会に提案いたしたいと考えております。 第三は、地方中核都市の整備と育成であります。 過密と過疎の弊害を同時に解消し、地域住民の福祉の向上をはかるためには、地方に、健康で、明るく、豊かな地域社会を積極的につくりだす必要があります。このため、地方都市の育成については、工業の再配置を進めるだけでなく、住民に役立つ教育や文化、福祉なだの機能をあわせもった魅力ある地方都市の整備、育成をはかることが肝要であります。 さらに、拠点的な機能をもった地方都市の育成にとどまるだけでなく、国民生活の身のまわりを整備し、国民の新しい生活パターンの変化に即応したナショナルミニマムを確立する必要があります。このため、新たに生活環境施設整備計画を策定し、市町村の生活環境施設の整備を促進いたします。 なお、大都市につきましては、人口の過度集中をさけ、森林や公園などの緑をふやし、快適な市民生活とともに、災害対策にも十分に配慮した再開発を進めてまいります。 次に三大施策に関連した問題として、教育、農林水産業、水資源、電源立地問題に関して申しのべます。 第一は、高等教育・文化機関の全国的な適正配置についてであります。 高等教育・文化機関の大都市への集中は、産業や、人口の過度集中とあいまって、国土利用や人的資源が大都市に偏在する原因となっております。これは教育全般の環境を悪くさせているだけでなく、地方に人材が還流しない大きな障害となっていることと無関係ではありません。このため、大都市にある高等教育・文化機関の地方分散をはかるとともに、自然環境に恵まれた地域に新しい学園を建設するなど、全国的な適正配置を進めてまいりたいと考えます。 第二は、農林水産業対策についてであります。 これからの農林水産業については、国民にたいして食糧を安定して供給する役割だけでなく、これらの産業が国土の保全や自然環境を守り、育てていく役割を持っていることを評価する必要があります。 農産物需給の長期的な見通しのもとに、生産目標を明確にし、これに必要な優良農地を確保しながら、土地利用の全般的、かつ計画的な調整をはかっていかなければなりません。さらに土地改良のための長期計画を新しく策定し、農業生産の基盤整備などをはかり、生産性の向上につとめてまいります。また、農村の生産と生活を一体とした環境づくりのため、農村環境総合整備対策を進めてまいる所存であります。 林業については、森林の公益的な機能と木材生産の経済的な機能との調整をはかり、また、水産業については、資源の培養と、海洋環境の保全をはかるための施策を進めてまいりたいと考えております。 第三は、水資源対策についてであります。 大都市圏を中心とする水需給のひっ迫は社会的にもみのがしえない問題であります。昭和六十年までの新しい水需要は約四百億立方メートルと推算されておりますが、この新規需要に対処するため、水資源を開発する施設の建設を積極的に進めなければなりません。その際、水源地域については、総合的な開発計画のもとに強力に水源地域対策を進めていく所存であります。 第四は、電源立地対策についてであります。 昭和六十年には約二億二千万キロワット、ないし二億四千万キロワツトの電力供給設備が必要となります。四十六年度末の供給設備は六千六百万キロワットですから、昭和六十年までに、いまの設備の二・五倍前後の開発が必要となるわけであります。 こうした電力需給のひっ迫からみて、公害対策に万全を期し、さらに地元の意向を十分にくみとりながら電源開発の立地について特別の措置を講じてまいる所存であります。 (五、国土改造推進のための体制整備) こうした国土の改造政策は、近く策定される新しい長期経済計画と新全国総合開発計画の総点検の中間報告などにもとづいて、すみやかな実行に着行いたします。 一方、長期的には、現行の国土総合開発法を全面的に改正し、新しい法律にもとづいて、西暦二〇〇〇年までを展望した長期にわたる国土改造の構想をまとめ、それにそって昭和五十年度を初年度とする国士改造十ヵ年計画を策定することといたします。この新しい計画は、人口、資源、食糧などの長期にわたる展望のうえに、美しい自然と人間性豊かな高度福祉社会の建設プログラムを明らかにするものであります。 つぎに、開発行政に関する機構について申し述べます。 現在、開発行政を所管し、開発行政に関係する省庁は、きわめて多岐にわたっております。これは、開発行政が内政全般に及ぶきわめて広範な政策分野であることを物語っておるわけであります。しかし、国土改造を強力に推進していくためには、十分な企画調整能力をもった総合的な行政機構がどうしても必要であり、たとえば国土総合開発庁というような機構の新設を行ないたいと考えております。その準備などを行なうため、本日、国土総合開発推進本部を内閣に設置いたしました。 最後に一言いたします。委員各位におかれては、この懇談会がスタートしていらい、まことに積極的なご協力を賜わり感謝に堪えません。とりわけ、文書により再三にわたって貴重なご意見をお示しいただいたことにつきましては、衷心より厚くお礼を申しあげる次第であります。申すまでもなく、国土改造は民族百年の大計であり、大事業であります。これは一政府、一政党の力だけではなく、与野党はじめ在野の英知を結集し、国民の総力を傾けてこそ、はじめて実現できる難事業であります。私は今後ともこの大いなる仕事に微力をいたす決意でありますが、こんごとも皆さま方の特段のご理解とお力添えを賜わりますようお願い申しあげて、私のご挨拶といたします。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)