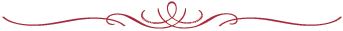
| 2009角栄ブーム考、日本が元気だった時代の象徴田中角栄を語ろう |
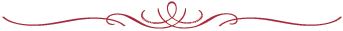
更新日/2018(平成30).11.12日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 2008年末から2009年初にかけて角栄見直しブームが起きた。これを確認しコメントしておく。 2008.3.23日 れんだいこ拝 |
| Re::れんだいこのカンテラ時評515 | れんだいこ | 2009/01/12 |
| 【産経新聞2008.12.23日付け記事「豪腕に郷愁? 今なぜか田中角栄ブーム」考】
ネット検索で角栄を拾っていたら、産経新聞の2008.12.23日付け記事「豪腕に郷愁? 今なぜか田中角栄ブーム」を目にした。これについてコメントしておく。 記事は冒頭で次のように述べている。「麻生太郎内閣の支持率低下が顕著になるなか、「平民宰相」、「今太閤」の異名をとった田中角栄元首相が、にわかにクローズアップされている。雑誌やテレビが相次いで田中元首相を取り上げ、存命ならどんな政策を打ち出すかと特集を組んだ。不況や雇用不安が続く現状を踏まえ、改めて田中元首相の手法に学ぶ視点だ。一方、清濁併せのんだ“昭和のカリスマ”の再評価を懸念する声もある。(伊藤弘一郎)」。 これは、中立公正を旨とするマスコミの立場を思えばまずまずの書き出しのように思われる。とにかく「角栄ブーム」を報道したこと自体に価値があると云うべきだろう。 記事にも書いているが、これに先立ち次のような動きがあった。「週刊ポスト」が「いまこそ田中角栄流」、「角栄政治にヒントがあった」の見出しで、田中元首相が蔵相時代の政策を例に挙げ、現在の不況対策としても通用するとの提言記事を掲載した。隔週誌「SAPIO」は計27ページを割いて特集、TBSでも情報番組で「静かなブーム」と題し、田中元首相を取り上げた。 記事はこれを踏まえて「豪腕に郷愁? 今なぜか田中角栄ブーム」 とネーミングし、「首相の座を降りて34年、死去から15年。なぜ今、スポットが当たるのか」と問うている。れんだいこに言わせれば遅すぎる問いだが、他社が採り上げない中での先乗りを評価すべきだろう。産経新聞はこのところ、かっての学生運動を問う「さらば革命的世代」でもヒットを飛ばしており、なかなかデキが良い。恐らく、新聞を通じて読者と共に思考を練るという使命に目覚めたものと思われる。読売とはひと味違う保守路線をひた走っており部数も伸びるだろう。 記事は続いて、角栄ブーム火付け役の企画者のコメントを披瀝している。興味深いのは、毎日放送プロデューサーの次の発言であろう。「田中氏が首相だったころは日本が元気だった。不況が続く今、田中氏を懐かしく思う人がいるのではと考えた」。 その通りであり、素直なコメントとして好感が持てる。産経記事は、読者や視聴者からの声として、「角栄さんならスピーディーに的確な施策を打って不況を救ってくれていた」、「政治に、ああいう力強さが欲しい」と支持する感想を紹介している。「多数、寄せられた」とも書いている。 れんだいこ的には、記事が誉められるのはここまでであり、後はどれもいただけない。三浦副編集長コメントの「安倍晋三氏以降、小粒な首相が続き、存在感を示せないことも人気復活の要因では」とあるが、「安倍晋三氏以降、小粒な首相が続き」としているのが気に入らない。ならば安倍の前の小泉は大粒なのかということになろう。れんだいこに云わせれば、彼は狂人である。日本は狂人政治を「5年5ヶ月1980日、戦後第3位、平成に入ってから初めての長期政権」を許したことになるが、小泉政治を断罪しないコメントは無意味と云うか有害であろう。この後、小林吉弥、福岡政行のコメントを紹介しているが共にくだらない。れんだいこの評に値しないのでノーコメントとする。 れんだいこが、角栄ブームの背景を素描しておく。日本は先の世界大戦で敗北し、戦勝国の分割統治の憂き目に遭う寸前であった。詳しい事情は分からないが結果的に米国の単独占領支配という形で再出発することになった。まずは戦後復興から始まり、戦前のように軍部を持たないことで国家予算の全てを民生用に振り当てていった。世界の羨む予算の配分時代となった。1950年に朝鮮戦争が始まり戦争特需が干天の慈雨となった。その後も内治主導で猛進し奇跡的とも云われる復興を遂げた。 1960年安保闘争で、日米新時代を構想し米軍支配下での再軍備化を目指していた岸政権が打倒され、池田政権が誕生した。池田政権は、戦後の国是としての経済成長政策に邁進した。この間、各種公共事業が矢継ぎ早に着手され社会基盤が整備されて行った。池田政権の後を継いだ佐藤政権時代も基本的に戦後の国是路線にシフトし世界史的に未曾有の高度経済成長時代を謳歌して行った。 この後を継いだのが田中政権である。角栄は、日本列島改造計画なるマニュフェストを打ち上げ自民党総裁選に堂々挑んだ。金権選挙と云われるが、既に歴代のものであり角栄だけが批判されるには及ぶまい。角栄の時代既に高度経済成長政策のヒズミが生まれており、インフレの波に襲われていた。そこへオイルショックが重なり、威勢の良い日本列島改造計画が相乗し狂乱物価時代へと突入した。 しかし角栄は、日本経済の底力と次に来る雄雄しい成長時代を確信していた。その後の歴史は、角栄の読みの方が正確だったことを教えている。力強く成長し続ける日本にならなかったのは、意図的に解体したからであり、その後の政治家がこれを引き受けたからである。この見解を補足しておく。 その角栄は、時代の課題にどう対処したか。まず日中国交回復を成し遂げ、その勢いは止まらず各国歴訪、遂にはソ連との経済提携にも向かい始めていた。まさに縦横無尽とも云うべき活躍ぶりを示している。その特徴は、国民生活の安定どころか実質向上を目指し、さらに戦後憲法が詠うところの国際協調友好親善の力強い推進であった。戦後日本の首相の中で、各国首脳と角栄ほど対等に渡り合った政治家は居ない。そういう意味でまさに不世出の首相であった。 マスコミ人士の世評では中曽根と小泉を名宰相と持て囃すが、何のことはないワシントンから見ての名宰相論であり、それだけ過分にワシントンの指令通りに立ち働き貢いでくれたことに対する返礼のリップサービスでしかない。それも分からず、ワシントン評をそのまま猿真似して名宰相と相槌しているに過ぎない。こういう場合には繭唾するものだが無節操が身上の低脳頭脳ゆえに直ぐに外電に飛びつく。 もとへ。現在の角栄ブームは、その角栄が今居たならどういう政治をしてくれるか、その包丁裁きを期待してのものである。それはとりもなおさず辛辣な現代政治批判となっている。かく受け止めるべきであろう。恐らく、このブームにはバイアスがかかり火消しされるであろう。だから我々がふいごで吹くようにしてそのつど燃え上がらせる必要がある。 それにしても、麻生がもう少し角栄に薫陶受けていたなら随分今と違った味を出すのだろうが、少々軽薄が過ぎる。しかし断じて小泉よりは良い。小泉チルドレンの跋扈する悪政時代に戻してはならないことだけは確かだ。これをどう切り盛りするか、ここ暫くの政治の見どころはここにかかっている。 2009.1.12日 れんだいこ拝 |
||
| 【「角」の視点から学ぶニッポン現代史/考】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「日経ビジネスオンライン 歴史を見る目のつくりかた」の2009.12.15日付け「わたしたちが「こうなった」のはなぜ?~「角」の視点から学ぶニッポン現代史」を転載し、対話する。こういう場合、著作権が煩わしいが如何せんか。 「田中角栄 封じられた資源戦略」(草思社)の著者・山岡淳一郎氏と山中 浩之(日経ビジネスオンライン編集委員)の対談形式で論じられている。れんだいこがコメント付けたい個所を抜き書きする。
|
| 【「角」の視点から学ぶニッポン現代史/考】 | |
| 2014.6.21日、週間現代の「日本が元気だった時代の象徴田中角栄を語ろう」転載。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)