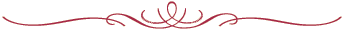
| 第2章 バビロン幽囚とパリサイ派 |
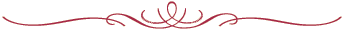
(最新見直し2012.04.06日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(1)」、「第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(2)」、「第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(3)」、「第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(4) 」、「第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(5)」を転載しておく。 2012.04.06日 れんだいこ拝 |
| 第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(1) |
| ユダヤ国民の歴史によると、彼らがその信仰する宗教に背反すると、その都度、必ず訪づれるものは他国から受ける侵略であった。そしてこの敗戦によって国民に与えられる屈辱と勝戦国への奴隷化は彼らにとって忍び難き過酷なものであった。これによって翻然として覚醒し、再び真の神への奉仕に復帰することになったのである。
今度(紀元前586年)の敗戦は、先にモアブ人、アンモニ人、シリヤ人らが、聖地の高所に陣営を設けて諸所を占領した時に比較すると遙かに大なる国難であった。今やユダヤ人は哀別離苦の涙をのんで祖国と袂(たもと)を分かれねばならなかった。征服者に引率されて遠き異教に移住することを余儀なくされたのである。俘虜として輸送されるユダヤ人に加えられる残虐は実に言語に絶したものであったとバイブルに記述されてある。 元来ユダヤ国に於てモーゼの宗教が保持されていたから、バビロン幽囚の時代に於ても、ユダヤ民はこの宗教によって自分らの精神力の源泉を汲むことができたが、アッシリヤの平野に移住せしめられたイスラエル民は、疾(と)くから既に偶像崇拝に傾いていたのでかかる精神的源泉を欠いていた。この分離した同胞なるイスラエル民が、自分の人種的特有性を喪失したのに反し、ユダヤ民は彼らの間に現われた預言者らを中心として一層密接に強固に一致団結したのである。この時代の苦難こそ、ユダヤ国民の信仰をいよいよ錬成して彼らを祖先の宗教に復帰せしめたのである。一般民衆の間に於けるこの純正信教の復興と並行して、バビロン俘囚は遺憾ながら、他の比較的幸福ならざる結果を生んだ。特にユダヤ民中の最も教育ある人々は、その宗教的観念と征服者らの信仰との接近の為に種々の誘惑を受けた。 一体バビロン人は、アッシリヤ人の如く、専ら好戦的な、他国民を奴隷化せしめることを主眼とするような国民ではなかった。彼らの性格はあまり温和ではなかったが、しかしその宿命的競争者たるアッシリヤ人ほどに残忍ではなかった。彼らが、古代の風習に従って、征服せられた国民の残余を自国の領土に移住せしめた時でも、彼らはアッシリヤ人の如くこれを奴隷にしなかった。ただ自国民の間に謂(い)はば定着せしめたのである。例えば、兵卒ならば征服前と同様に武器を持たしめ、農夫や職工ならば征服者の農耕階級に加わらしめ、祭司ならば賢人、占星術者、預言者らの仲間とならしめた。 バビロニヤには昔から哲学や史学を始めとし、天文学や神霊交通術に至るまで、当時に於て研究し得たあらゆる知識が極度の発達を遂げていた。これら当代に於ける学問の栄光を遠く世界の各地に普及せしめていた学者らの間に、ユダヤの祭司レビらは交ったのである。これが即ちバビロンに移されたユダヤ人らの運命であった。こうしてネブカドネザル王は第一回エルサレム陥落の時以来、ユダヤ国家の貴族の家庭から集めた小姓をその側近に侍(はべ)らせたのである。後世の預言者ダニエルの如きはバルデヤの神官長となった。 〔傍註〕 |
| 第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(2) |
| 移住せしめられたユダヤ人が、ハルデヤ人に接近して雑居していたにも拘わらず、特有なるユダヤ人の国民性は以上既に述べた如く全く同化滅却せられなかった。却ってかかる雑居は、征服者に対する被征服者の反感嫉視を煽って、如何にしても緩和することはできなかった。殊にユダヤ人は従来甚だしく前者を憎んでいたからである。魅力と詩情に満ちたる美妙なる詩編第137篇は、「我らバビロンの河のほとりに佇(たたず)みて、シオンを想い出でて涙ながしぬ」、「バビロンの女よ、汝らの嬰児をとりて岩の上に投げ打つものは幸福なるべし」との言葉をもって結んでいる。
しかし、この雑居によって、バビロニヤの神官とユダヤのレビとは同一の生活を為し、また同一の工作を為す義務を負っていた。それで、自然彼らの間に親交が結ばれるようになった。この時まで全然沒交渉であった二つの精神界がここに接触を余儀なくされたのである。ところが、ハルデヤの学者間に主として受けられていた哲学は、大衆の理解とその宗教的要求の満足に適応せられる迷信的通俗化を除くの外は純然たる汎神論であった。宇宙と云う広大無辺なる殿堂中からハルデヤの学者は創造した造物主を排除した。 それが為に原因と結果と混合した世界は自然に生じたものとせられ、それ自体神と認められた。神の観念それ自体はあらゆる存在を統治する宇宙の調和と、また、この調和によって統治せられたる宇宙の各部分と混合するものとされた。故に神は交々且つ同時にその乳房をもって人々を養い、その露をもってこれを潤おすところの地ともなり、これを照らして且つ温める太陽ともなり、植物の生殖作用を行う花粉を配送する風ともなった。神は人類と禽獣世界を繁殖せしめ、植物を生ぜしめ、発育せしめ、枯死せしめ、復活せしめると共に、生気なき物体の中にさえも現われる生命の源であるとされた。おのづから発生する永久なる自然の気息の如きものと同一視せられた神は、世界から生じたもので、世界が神から生じたものではない。 マッソン結社の錬金術上の労作を知っている者は、この結社の首脳者らが最も愛好している思想を直ちに了解するであろう。この思想は最初ユダヤ密教徒が創設したものであったが、中世紀の錬金術者がこれを継承し、上記結社の首脳者らが更にこれを採用しているのである。ハルデヤ人の汎神論の基礎となり、且つ古代及び現代の神秘学の根底を為したる神化人の宗教についても同様に云うことができる。 かく思考した時より初めて、文明の堅く立っていたすべての道義的基礎はその根底から覆されたのである。自然界の唯一の真の神なる人間は、最早空虚にして何らの反応もなき天に向って膝を屈する必要はない。むしろその反対に自分の性向を本能に問うて、自身の内に神を求むべきである。人間の本体にある自由意思が即ち神の意志となったので、これに反抗し、これを拘束し、これを律することは不法であるとされた。真正の宗教は、人間のすべての欲念を崇拝し、これに満足を与えることにあると云うのである。 ハルデヤの賢人らは、この学説の唯一の遵奉(じゅんぽう)者ではなかったようである。これが古代のすべての神秘学の基礎を成し立てていた。この神譜の分解と総合とを行う時、我らは、大衆の崇拝せしめられていた諸神が、人間の種々の欲念を偉大に或は頽廃的に人格化したものであり、又主としてこれら諸国民の宗教の基礎となっていたものが、萬物の母なる自然の崇拝であったことが容易に納得されるのである。この崇拝は、後世キリスト教反対の諸教説の大半、例えば諸世紀のマネス教やミトラチズムを始めとし、中世紀のユダヤ密教や錬金術、十八世紀のマルティニスト宗及び現代の神智学に至るまで、何れもその根底にこれを唱道していたのである。結局この教説と同一の結論に到着する通常の唯物主義は、単純なる思想を有する人々の為にこれを改作したものに過ぎぬのである。 ユダヤ人の間に現われた預言者らは、彼らに向って神が彼らを選民と為すが為に選抜した事、神が彼らに特別の愛をもって導き且つ保護していた事、又他の諸国民は未だ嘗て神のかかる不断の焦慮(しょうりょ)の目標となったことのないことを絶えず力説したのであった。この教旨は、必ずしも常にユダヤ人にその神の反逆に向う傾向から阻止し得なかったが、とにかく彼らをしてその人種上の優越性を確信せしめたのである。 神が彼らに対して特別の考慮を有していたと云うことの確信によって彼らの中の多くの者は、この神の選抜が彼らの人種の功績に対する公正なる褒賞であると信じていた。彼らはイスラエル民に対する神の約束を以って、彼らの忠誠の代償として彼らが他の諸国民の上に物質的に有する主権を確定する為に二つの力―神とイスラエル―の間に締結された約束と看做(みな)していた。悪憎を交えたる軽悔―これがユダヤ人が他国民を見た瞬間、その心に起す唯一の感情であった。しからばユダヤ自身は何であるかと云えば、彼らはその心に自分を神の選んだ民以上に高く考えて、自ら神なる国民と称していた。 以上が即ち俘囚によって始めてハルデヤとその賢人らとを見た時、ユダヤ国の住民が呈していた思想状態である。アッシリヤ、イラン、ミデヤ及びペルシャが専ら軍人の居住する所となっていた時、又フィニキヤ人の才能全部が商業に集中していた時、ユダヤ人とハルデヤ人は、アジヤに於ける最も文化の発達した二つの国民であった。多くの点に於て互に類似する所の少なかったこの二国民は、その教育ある社会の人々の開発に互に接近していた。ハルデヤ人を喜ばせていた人間の誇の崇拝、ユダヤ人を鼓舞しつつあった人種の誇への奉仕―これがこの二つの国民をして互に相理解せしめ、且つ互に相影響せしめた所以であった。 |
| 第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(3) |
| 最初、ハルデヤの哲学、後にペルシャの哲学が、何れもレビらから借用されたものであると云うことについての説明は、本書の主題に入っていない。だがただ次の消息を玆(ここ)に附言するに止めておこう。伝説によれば、ユダヤの預言者ダニエル或はエズラはゾロアストルの教師であった。このアジヤの哲学者の教説中に見る或る高遠なる論旨は疑いなくユダヤ教の一神論にその淵源を汲んだもので、この教師との関係に於てその理論の出発点を見出さねばならぬ。
その反対に、ハルデヤの思想は、正統的ユダヤ教に力強く影響して、イスラエルを変形せしめ、神と格闘する者とのその本来の言語の意味をその名に立ち戻らしむべき分派の起る基礎となった。この分派は即ちパリサイ派であった。パリサイ派とはヘブライ語で「特別の者」と云う意味である。この名称自体が既に異端及び分派を思わしめるものである。この意義は、多分パリサイ派自ら自分の分派の名称に附したものであったろう。しかしイスラエル民に対しては、彼らはこの名称に別の説明を加えていた。即ち彼らは他のユダヤ人から「特に別けられた」者である。その敬神の念厚き為に特別な地位に立てられたものであると云っていた。ハルデヤの哲学がパリサイ派の哲学を生んだのと同時に、この哲学は又その教義をピタゴラスに伝えた。ピタゴラスはユダヤ人のバビロン大俘囚の初め頃、バビロンで十二年間修学していたと云うことをヤンブリクが証明している。 バイブルの諸書にも、ユダヤの歴史家の書中にも、俘囚以前にはパリサイ派のことは記されていない。しかしミュンクの著書が世に公にされた後は、バビロンの俘囚の時に、ハルデヤの哲学が或るユダヤの学者、就中その大部分なるレビらに影響を与えた結果としてこの分派が起ったと云うことがもはや何人も争うことのできない定説となった。勿論このことに関するミュンクの結論は十分根拠あるものではあるが、しかし我らの見る所を以ってすれば、このユダヤの学者らが、そのハルデヤ教師らの学説から受け容れたる知識の重要さを十分に評価していない。彼らは実際啻(ただ)に万物の本体とその再生及びその初源の性質に関する迷信の一部のみならず、汎神論的教説の根源をも受け容れたのである。尤も彼らはこのすべての知識を皆ユダヤ的様式に改造し、これを選民の誇りと調和せしむるに努力した。このハルデヤ思想のユダヤ思想への寄与からパリサイ派の伝説である「カバラ」即ち神秘教が起ったのである。これが久しき間、教師から門弟へと口述によって伝えられ、爾来(じらい)八百年を経てタルムードの著述に霊感を与え、遂にその完全なる表現を「ゼフェル・ハ・ゾガル」に見出したのである。 「ゼフェル・ハ・ゾガル」とは豪華の書と云う意味である。この神秘教的著書は、ユダヤ人の間に最も重きをなしている。そして遺憾ながらキリスト教から転向して神秘教徒も同じくこれを重要視している。この書の仮想的著者は、西暦紀元50年にガラリヤで生れた祭司シメオン・ベンウォハイであったとされている。しかしその如き祭司がこの時代に実際存在しなかった。そして「ゾガル」と称せらるる書は十世紀の頃に書かれたものであると断定するに十分の根拠がある。著者として種々の人名を挙げることや、様々な著書の贋造は、ユダヤ秘密教の著者に関する問題に於ては普通の現象である。 そこでパルサイ派の人々は、同胞の信用を得る為には、宗教運動の先頭に立ち、律法の微細なる規定をも偽善的に遂行し、煩瑣(はんさ)複雑なる儀式を制定することを以って賢明なる態度であると考えた。それと同時に、彼らは秘密集会を催おし、秘密結社を組織して自分等の説教を展開した。この結社員は俘囚当時は僅か数名に過ぎなかったが、ユダヤの歴史家であるヨセフ・フラウィーの時代にはこの結社が最も隆盛を極めて六千名に達した。 この汎神論者なる学者等の集会は、忽ちにしてユダヤ民の上に指導的勢力を有するものとなった。紀元前538年にペルシャ人がバビロンを占領した時、ユダヤ人は俘囚から解放されたる一大期待をかけたところ、その後二年を経た536年に至り、ペルシャのクロス王は勅令を以って、故郷へ帰ることを希望するユダヤ人にこれを許した。この時この俘囚は終りを告げたのである。そして第一回の五千人からなるユダヤ人はゼルバベル引率の下に出発し、続いてエズラ及びネエミヤに率いられて多くのユダヤ人が帰って行った。 |
| 第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(4) |
| しかし、彼らがその神秘学の中から公表し得るものと認めていた総てのことは、国民的感情を直接に害し得るものは何も外面に露わさなかった。パリサイ派の人々は、如何に深くハルデヤ汎神論に感染しても、とにかく自分の人種的矜持(きょうじ)を固く守っていた。バビロンに於て彼らの心に浸透したこの神化人的宗教は、彼らの見る所によると、特選された最高至上の存在たるユダヤ人の利益に務むべきものであった。正統的信仰を有するユダヤ人がモーゼの律法から汲んだ所の全世界の上に王権を獲得することの約束を、パリサイ派の人々は、モーゼの神が万国民の上に王となると云う意味でなく、物質的にユダヤ人が全世界の覇権を握ると云う意味に解釈していた。 待望せらるるメッシア(ヘブライ語の救世主)は、彼らの信念から云うと、太祖の罪悪を購う者でもなく、それは連勝的戦争の血を浴びている一時的王者、イスラエル民を世界の覇王とし、自分の戦車の車輪の下に万国民を蹂躙(じゅうりん)せんとする偉大なる王者であらねばならなかった。ヨナタンのハルデヤ語で書いたイザヤ書「諸国民はメッシャ王に撃滅せられた……ユダの家より現るべき彼、メッシャ王は如何に美しき。彼は諸敵と戦を交えて諸王を殺した」と記してある。 かくのごとく諸国民の上に主権を執ることを、パリサイ派は存在せざるエホバから期待していなかった。彼らはただ国民の感情に譲歩するが為にのみ、表面的にエホバの神を崇拝することを続けていた。彼らはこの期待をイスラエル民の恒久的忍耐力にかけていた。人間的方法の適用にかけていた。彼らのこの主義が如何に驚くべきほど古きモーゼの律法と隔絶していても、しかしこれを極めて巧みに滴一滴とユダヤ人の間に注入していた彼らをして民間にその人望を失わしめる何者もその間になかった。 他のすべてのことはパリサイ派の巧妙なる秘密結社が自ら担当した。そして程なく自分らの全能をユダヤ国に強化した。西暦紀元前に於けるユダヤ社会に対する感化的行動を説明するには、現代の社会に於けるマッソン結社の活動と比較するにしくはない。パリサイ派は会員の数こそ少ないが、しかし緊密に団結し、会員をしても最も厳重に結社の秘密を守らしめて、不撓不屈(ふとうふくつ)の努力を以って二つの目的を達成するに邁進していた。第一は高級宗教職(その勢力は復興されたユダヤ国民の間に絶大であった)を獲得することによって政権を手中に収め、最高宗教評議会(シネドリオン)を牛耳ることであった。第二は国民の信念を徐々と彼等の秘密教に導くにあった。そして彼らはこの二つ目的を完全に達成した。 サドカイ派の名称は、ユダヤ哲学者サツドクから出たものである。彼らはパリサイ派に対照せらるべきような組織を有する宗派を成し立てていなかった。彼らの始めて知られるようになったのは西暦紀元前三世紀の頃であった。彼らは時としてギリシャ党と混同せられる。ギリシャ党と云う名称は、ギリシャとシリヤとを併合したセレフク王朝の主権の下にあった影響によって、ギリシャ人の風俗、言語及びギリシャ哲学の或る主旨までも受け容れたユダヤ人に附せられたのである。サドカイ派は、地上に行われるところの善にも悪にも無関心な唯一の神を信じ、霊魂の不滅を否定し、善行が霊魂のために利益なのは健康が身体の為に利益なのと同一であるとなし、善行を保持する必要は、これによって得られる個人の満足の為であると説いていた。サドカイ派は貴族の集団を成していたが、自分の理想として同胞の間に勝利を獲得せしむる目的を以って団結するようなことは決してなかった。ヨセフ・フラウィーは「パリサイ派が互に合同して生活しているに反して、サドカイ派は互に相関せざる風がある。彼らは恰も異人種の者と共にしていると同様に互に疎隔して生活している」と云っている。 他方面に於ては、パリサイ派は重要なる信仰問題に関する多くのユダヤ人の見解を何の苦もなく変革せしめていた。それは高級な宗教の職にある者の大半を占有していたこととシネドリオンに於ける大多数の発言権を有していたことによってであった。故に彼らは権力をもって律法の解釈左右する便宜を有し、なお書に録された。律法の意義をも抂げてこれに任意の解釈を加えた。この目的を達成する為に彼らはユダヤ秘密教の基礎となっていた比喩的解釈法を利用した。比解釈法は、後世あらゆる時代の異端創始者の為に、そのバイブル本文との闘争に於ける絶好の模範となり、また今日の現代主義に主要なる武器となっている。この解釈法によって、バイブルは一切直接の意義を喪失してしまった。そしてその代りに注入せられた意義は、もはや客観的真実を言い現わすものでなく、秘密教に通ぜざる門外漢から隠されている事実と理論とをカムフラジュするための仮面と認められていた。 これらの理論を自分の任意によって自由に展開していたパリサイ派は、こうしてキリストの降生前数世紀の間、既にユダヤ人をして自分の秘密教の大半の主旨を受け容れしめたのである。かくして「隣社を愛し、他国人に敬意を以って接することを命じた」モーゼの律法に反して、パリサイ派はユダヤ人ならざる総ての者に対する彼らの厭忌心は、少しでもこれに接触することをもって身心を穢(けが)すものとして、病的恐怖心に化したのであった。かくしてすべての非ユダヤ人を絶滅すべき俗世界の王なるメッシャの人間的天性についての彼らの思想は、ダビデがその神からの出生をその詩篇に讃美し、預言者らがその無睪なる栄光と極度の卑賤とを予報した超人的救世主についての思想を全然変革したものであった。終に、かくして楽園と火の地獄(グヘナ)についての正統信仰的思想は排斥されて、これに代うるにパリサイ派の人々がハルデヤ人から借用した輪廻説を以ってした。 ユダヤ古代史18章の2に於て曰く、ヨセフ・フラウィーの記す所によると、「輪廻説を信じていたパリサイ派は民間に大なる勢力を得たので、神に対する信仰と神に献ぐる盛大なる礼拝式の問題に関するすべてのことに於て国民は彼らに盲従していた」と。 |
| 第二章 バビロン幽囚とパリサイ派(5) |
| 救世主降誕の直前に於てこの進化作用は一般的となった。そしてその献祭の如きは祖先から継承したる信仰に全く離反したものであることを意識するものもなかった。しかしユダヤ国に於ける人心が、悉くパリサイ派の巧妙なる戦術に服従されたのではなかった。ユダヤ人中の頗(すこぶ)る多数者、特に比較的教育ある者、或は神の叡智に導かれていた人々は、パリサイ派がイスラエルを異端に誘導していたものであることを悟って、これに反抗しようと努めていた。その競争者らを支持していた政治的勢力からの妨害の為に、これら正統的信仰を固く守っていたユダヤ人は、正面から彼らと闘争することを避くる外なく、殆んど皆その祖国を棄つることを余儀なくされた。 死海の沿岸、荒涼たる広野に彼らは修道院を建設した。ここで彼らはキリスト降臨の時に至るまで真正の信仰の約束を守っていた。ここに約四千年のユダヤ人がモーゼの神に奉仕し、預言の応ずる時を俟(ま)ちつつ修道規則に従って住んでいた。この規則の明細はヨセフ・フラウィー及びプリニーによって我らに伝えられている彼らの高潔なる徳行生活は一般の尊敬の的となっていた。エッセイと称せられた一派の人々は、イスラエル人をしてその使命に背かしめようと努めていた人々の為に少しも心を動かされなかった。彼らはモーゼの律法のすべての規定を履行していたが、しかし献祭のためエルサレムに参拝することは差し控えていた。それは彼らがエルサレムの聖域に於ける献祭を是認しなかった為ではなく、聖殿は彼らが深く尊崇していたところであったが、しかしこの献祭が異端者なるパリサイ派の者によって執行せられたので、そこで行くことを欲しなかったのである。エッセイ派は、エルサレムの聖殿に行われた礼拝式を尊崇してはいたが、しかし自身は参列しなかった。何となれば彼らの信念によれば、献祭執行者の多くは退化したイスラエル人から成っていたからである(「ネアンデル著教会史」)。 エッセイ派の教導職は、極めて門戸閉鎖的であったが、しかしその影響するところは、修道院の四壁内に限られなかった。エルサレムその他のユダヤ国の各都市に於ける俗人の間に、彼らの教派に帰依していた者が数多かった。これは死海の沿岸に苦行を務めていた修道士らの誠実なる信徒であって、その精神的指導に従っていた。著大なる各中心地では、これら信徒中の一人に、真の神を信ずるすべての人々を団結せしめる義務が負わされていた。この真の神の教道は旧約聖書によってその霊感的内容を与えられ、既に遠き以前から新約聖書の根本義と完全に一致していたのである。 ヨセフ・フラウィー「ユダヤ人の戦争」二の一の認める所によると、エッセイは総てのユダヤ人の宗派中最も完全なるものであった。彼は死海沿岸修道士―ユダヤ人の戦争―について次のように記している。「彼らは、互に緊密なる友愛の関係を保ちつつ生活している。そして総ての快楽を以って如何なる者も避くべき罪悪とし、節制及び情慾との奮闘を以って最も尊敬すべき善行、美徳と看做している。彼らは結婚を排斥している。それは人類を絶滅すべきものと信じている為ではなく、婦人の不節制を避けねばならぬからである。しかしながら彼らは学習の為又善行の規則に於ける修養の為に委託せられる児童を引き受けることは拒絶しないのみならず、彼らの肉親者のように懇切に教育する。そして総ての児童に一様の被服を与えている。彼らは富を卑んでいる。彼らの所有はすべて共同で驚くべき程平等にしている。彼らの団体に収容せられる各人は、富による虚栄を避くる為、また他人を貧困の恥辱から救うが為に、そして兄弟として幸福なる一致団体の中に生活するが為に一切の財産と別れる。彼らは、もしその被服が十分に白ければ、それで自ら衣服に足れる者、清浄なる者と認めている。彼らは最も宗教心が強く、日の出前には信仰問題以外のことは一切口外しない。 そしてその時は、神にその光を以って地を照らさんことを願う為に、彼らが代々継承した祈祷を行う。その後各人はそれぞれ指定された業務に就く。十一時に彼らは一ヶ所に集会する。そして白衣を着て冷水を浴びる。その後各自の独房に別れて行く。房中には宗派以外の者の出入りを禁じている。かくの如くして清められた後、彼らは食堂に行く、それはあたかも聖堂に往くが如く、そこに入った後は全然沈黙して坐す。各人の前に小さい皿の上にパンと食物が置いてある。まず祭司が肉を祝福する、そして祭司の祈祷が終るまでは誰も食物に手を触れない。食事の終った後は、ただ神の恩恵によってのみ食物を得るものであることを皆感ずる。すると祭司がまたその為の祈祷を誦読する。その後、彼らは、神聖なものとされている衣服を脱いで、それぞれの職場に帰って行く。晩の食事の時も、彼らは同様に行っている。 そしてもし訪問客があればこれを歓待する。彼らの家では、誰も騒がしい音も聞かない。そこに少しの混雑もない。各人はただ自分の順番を待って物を言う。そして彼らの寡言は外国人をして自然敬意を起さしめる。こんな節度は不断の節制から生ずる結果である。彼らが飲食するのは、ただ自ら養う必要のみに限られている。窮民を救済することの外は、何事によらずいっさい長者の許可なくしては独断行為を許されない。それも同情以外の他の如何なる動機にもよらないことを条件とせねばならぬ。もしこの貧しい者が親類であるならば、許可なくしては何物をも与えることはできないのである。 この人々は鋤と、襯衣(シャツ)と白衣を受ける。この人々は同様の食物を用い、身を清める為に冷水浴を行うことを許される。しかしなお二ヶ年を経過せねば一般の食堂で食事することは許されない。その二ヶ年の間は、彼らの思想の強固さと堅忍不抜さの試験が行われる。その後始めて彼らに適当な者と認められて全く収容される。しかし、一般の食堂に入られるに先だって、神を敬い、心を尽してこれに事えること、人的関係は公平を守る事、誰に対しても、又たとえ命ぜられても意識的に悪事を行わざる事、有司特に王に対しては、神より権能を受けたる者として誠忠を守ることについて誓わねばならぬ。これになお附加して、他は彼らが権力を獲得した時、民を虐ぐるが為にこれを濫用しない事、又その時、衣服その他必要とする総ての物も、彼らはその権下の民よりも多くの物を所有しないと云うことを誓わねばならなかった」。 ヨセフ・フラウィーは、この修道士らと並んでユダヤ国の諸都市に住んで彼らの教道を信奉し、彼らの権力に服していた信徒の存在していた事をも記している。この信徒は修道士と同様に、修道規則に服していたが、ただ結婚だけは行っていた。しかし、彼らは結婚をただ人類を継続する方法と認めたのみで、これを快楽とは考えていなかった。なお、ヨセフ・フラウィーの云うには、「彼らが旅行する時は、盗賊に対して自衛する為の武器の外には何物をも携えない。彼らが往く所の町には同宗派に属する誰かがいる。その人々は同宗派の来客を接待し、宿所を提供し、衣服その他の必要品を寄附する。彼らは互に何物をも売買せず、ただその所有している物を互に交換するのみである」と。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)