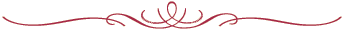
| ケルト習俗由来としてのハロウィン考 |
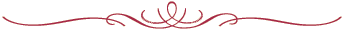
更新日/2022(平成31.5.1栄和/令和4).8.21日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「ケルト習俗由来としてのハロウィン考」をしておく。 2014.06.13日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【ケルトと日本の文化】 |
| 02. 2014年11月01日 13:57:19 : b5JdkWvGxs ケルトと日本の文化 ケルト人は、ほぼヨーロッパ全域に居住していた古代民族である。 その起源は非常に古く、紀元前2千年には、いわゆる“ケルト世界”が形成されつつあったといわれる。 紀元前8世紀頃、大いに栄え、その勢力を各地に広げていったが、ゲルマン人の進出、ローマ人のヨーロッパ制圧により、紀元前1世紀末には、ケルト人居住の大部分は失われることとなる。現在主として、スコットランド、ウェールズ、アイルランドに余命をつなぎ、フランスでは、ブルターニュ地方に、その文化の名残を留めるだけである。このように、ケルト人というと、後半の悲劇的側面が強調されがちだが、長い目で見ると、それは、栄枯衰退の歴史であった。 また、ケルトを知る上で、大変重要となってくるのが、キリスト教が普及する以前から彼らが信仰していたドルイド(Druid)教である。 この土着信仰では、太陽と大地の古い神々を信じ、生き物の中に霊的なものを知覚し、自然と宇宙と自己との一体化を試みている。また、「霊魂不滅」「輪廻転生」の信仰が中心思想として機能していた。 ドルイド教をつかさどったのは、司祭階級であったドルイド達である。(彼らの名から、宗教の名がきている)ドルイドは、常に王の側で、神からの言葉を伝えるものとして、時には王よりも強い権力を部族の中で持っていた。ドルイドには階級が存在し、地位が高い順に、ドルイド(神官、司祭、立法・裁判者など)、バード(記録者、詩人など)、ヴァート(祭儀者、占星術者、預言者など)と呼ばれた。彼らの教義は秘密裡に、人から人へと口伝えで伝授されていったので、現在、その内容を知ることは困難である。 しかし、ドルイドが行った祭儀は、ギリシャ、ローマの歴史家や哲学者達が書き残した古文献などからその内容をうかがい知ることができる。 特に驚くべき祭儀は、「火炙り」の儀式と生贄を「剣で刺す」儀式である。 彼らには、1人の人間の生命を救うためには別の人間1人の生命が必要であるという考えがあり、また、太陽の神としてのタラニスを喜ばせ、穀物の実りと作物の豊穣をもたらしてもらうために「火炙り」の儀式を行った。 「剣で刺す」儀式は、未来のことを判断し予知するために行われた。ドルイドが儀式を行う祭壇は、石舞台と呼ばれるつくりで、ドルメン(数個の支石の上に、1枚の大きな板石を乗せたテーブル形の構造を持つ墳墓遺構)のようなものであった。そして、ケルトの部落があったと思われるところには必ずドルメンがあり、ドルイドの儀式は、ある意味で、部族の信仰と習慣、生活の中心をなしていたといえる。 では、ケルトのベースとなっているドルイド教の思想が分かってきたところで、ケルトと日本の比較をしていきたい。まず、取り上げたいのが、芸術である。 ケルトの芸術は、日本の芸術と大変似たものがある。 例えば、ケルトの紐組紋と日本の縄文文化の縄文である。画家・彫刻家である岡本太郎は、ケルトの紐組紋から感じる生命美は、縄文土器の縄文から感じる生命美と信じがたいほどそっくりだと述べている。また、古代アイルランドの詩と大和の歌にも似ていると感じるものがある。和歌の詠み手は、三十一音という限られた音節の中に、その場の印象や雰囲気、感情や感動を凝縮して言い表そうとする。説明されていない部分を読み手の創造で補うことこそが、和歌の醍醐味であり、読み手の感動を深めるからである。このような詩のつくり方は、古代アイルランドの詩にも見られる。日本人と同じようにケルト人も詩的ヒントから創造を膨らませることが得意で、すべて語らぬことが最も好まれていた。「ダビデ(deibhidhe)」と呼ばれる、古代アイルランドの詩形は二十八音節からなり、頭韻法をふんだんに使うリズムある詩である。 次に、アイルランドの妖精信仰と日本の妖怪信仰について考えてみる。 現在、アイルランドは、ナショナル・シンボルとして妖精のレプラホーンを掲げており、「妖精の国」としての特色を打ち出している。それに対するなら、日本はさしずめ「妖怪の国」といえるであろう。水木しげるの妖怪画・マンガ、京極夏彦の奇怪小説、宮崎駿の劇場用アニメーション(「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」など)といった妖怪を扱った作品は人気があり、長い時間かけて育まれてきた妖怪文化の伝統を伺うことができる。 井村君江は、『ケルト妖精学』の中で、妖精が生まれてくる6つの源として (1)自然、天体、元素の精霊。(2)自然現象の擬人化 (3)卑小化した古代の神々
(4)先史時代の祖霊、土地の霊 (5)死者の魂 (6)堕天使、 を挙げているが、特に(3)(4)は、柳田国男の妖怪研究が提示したような、「妖怪変化とは、零落した古代の古き神々の姿である」という見方とも一致する。妖精と妖怪。共に不可思議な存在であるけれども、それをごく当たり前のようにうけいれている、アイルランドと日本。これらの受容には、ドルイド教や神道の思想が人々にもたらした民族性に関係しているのであろう。
このように比較してみると、地理的に、また、歴史的にもかなりの違いがあるにもかかわらず、アイルランド周辺に残るケルトと日本の文化には、通じ合うものがあるといえる。音楽、美術といった芸術や、今なお受け継がれている信仰など、さまざまである。
はじめに述べた私の疑問に答えを出すとすれば、アイルランドと日本は、自然宗教的、アニミズム的考えを国民意識の根にもっており、さまざまな芸術的類似点にもつながっているということである。 |
| 【ドルイド考】 |
| 1. ドルイド
ケルトの言葉で「ドゥル」は「オーク」、「ウィド」が「知識」を意味することから、「樫(オーク)の木の賢者」という意味です。(「ドル」は「多い」、「ウィド」が「知る」で「多く知る」という意味だという説もあり)。主にガリア(フランスあたりを中心とするヨーロッパ地方)とブリタニア(ブリテン島:イギリス)に記録が残っている「ドルイド教」の神官(僧侶と書かれている本もある)のことです。 ドルイド教の教えとは 「物質と霊魂は永遠であり、宇宙の実体は水と火が交互に支配する現象の、絶え間ない変動の下でも普遍であり、人間の魂は転生にゆだねられている」 ということでした。 現世での行いが悪いとその罰や報い・試練として、人間よりも低い段階(動物など?)への転生が行われました。 また死後には幸福の世界(マーグ・メルドやティル・ナ・ヌグ)があり、そこでは魂が生前の主体、感情、習慣を持ち続けることが出来ると信じられていました。 葬儀では死者宛の手紙や、他の死者に渡してもらう手紙などが燃やされたり、来世に行ってから返済してもらうよう、お金を貸すことさえあったということです。ドルイドはよく「呪術師」などと呼ばれますが、彼らの仕事は多岐に渡っていて、自然学者であり、天文学者であり、魔術師であり、医者でもありました。ドルイドの医学とは魔法に基づいたものであったようです。争いごとをおさめるのも、彼らの仕事だったといいます。 ドルイドの権力はたいそう強く、税金や兵役(戦争に行かなくても良い)も免除されました。この特典のためにドルイドを目指したり、一族の中からドルイドを選出したいと、家族や親戚に修行へ送り出された者もいましが、適性がないと判断されると、家へ帰されたそうです。また、ドルイドの指示に従わないと「村八分」のようにされ、これは大変不名誉なことでした。 キリスト教の伝来に伴い、ドルイドたちは迫害され、560年頃の旧都タラの放棄後にアイルランドから完全にいなくなってしまいました。 (現在はドルイドの儀式を復活させようという活動もあるようです)
首を落とすと「あの世に再生できない」という考えがあったのかどうかは分かりませんが、戦いで首を狩るというケルトの習慣は広く見られます。 狩られた頭部は貴重なものとして神殿におさめられたりしました。 イタリア北部では前216年にケルトの部族(ボイイー族)がローマの将軍ポストゥムスの頭を切り取り、それを洗った後金箔を貼り祭祀用の器として用いたことがローマの歴史家リウィウス(前59~17あるいは前64~12)によって記されています。 またボヘミアでは洞くつの中から頭蓋骨で作ったカップがその他の奉納品と一緒に発掘されています。 ドルイドは犠牲者の横隔膜の上部を突き刺し、倒れたときの姿勢、手足の痙攣、血の量と色などで占いました。 神殿の中の柱かけにしたり、死ぬまで矢と槍の雨を降らせたり、柳の枝や干し草で作った巨像を立ててその中に生きたまま人間を大勢詰め込み、ドルイドが火のついたたいまつを投げ入れるというようなことも行われました。 セクアヌでも触れていますが、金や銀を供物として聖なる湖などに投げ入れたりもしました。 2. 女魔法使い(ドルイダス=女のドルイド) 女のドルイドがいた、という明らかな考古学的資料はないようですが、ドルイドらしき女性は記録に残っています。(ドルイダスという名詞はどこにも見つからないのだ…すごくマイナーな言葉なのかも) ディオドールス・シクルス(紀元前60-30)の『世界記』に「ドルイデス」という名称が出てきますが、これは「女魔法使い」という意味ではなく、哲学者や神学者を指しています。 「ドルイダス(女魔法使い)」という言葉は「actor/actress(俳優/女優)」のように女性形になったものだと思うのですが…。 古代ローマの地理学者ストラボン(紀元前64頃~後21頃)は、著書「地理学」でキンブリー族の女祭司についてこう記しています。 「彼女らは老齢で、髪はすでに白く、白いチュニックの上に亜麻製のクロークを羽織り、青銅の腰帯をつけ、足は裸足であった。 彼女たちは剣を手にして軍の野営地に入り、囚人たちに近付き、その頭に冠をかぶせ、青銅の大鍋のところまで連れていった。 …女の一人が階段をのぼり、大釜の上に身を乗り出すと、釜の縁に押さえ付けられた一人の囚人の咽を切り裂いた。 他の女達はその体を切り開き、内臓を調べて自軍の勝利を予言するのだった」 。チュートン(ゲルマン)族の一部族であるキンブリー族は厳密にはケルト人ではありませんが、首狩り、人身御供、聖なる大釜を利用するなど、祭儀に関してはケルト人と同じ習慣を持っていました。 同時期に著作を記しているカエサル、タキトゥスなどはチュートン族の女祭司について、主な役割は占い、戦に関する予言であったと記しています。「アルスター神話群※1」と呼ばれるアイルランドの神話の中にも女性のドルイドと思われる人物が登場します。 コナハトの女王メイヴのクルーフンの宮殿には、エルネという女性の祭司が仕えていました。また、ク・ホリンは「影の国」に住む魔術に長けた女戦士スカサハに、1年の間、戦術と魔術を習い、ゲイ・ボルグという魔法の槍を授けられています。スカサハとは「影の者」という意味であり「影の国」とはアルバ(現在のスコットランド)をさしています。 ク・ホリンと一戦交えようとアルスターへ向かう途中のメイヴ女王の前に、フェゼルマ(フェデルマ)という乙女が現れますが、彼女は自分は予言者でありクロガンの妖精の墓から来たとメイヴに告げ、またアルバで詩と予言を学んだと語ります。その時フェゼルマは黒い馬がひく戦車に乗り、刺繍を施した赤いチュニックとまだら模様のクロークを身にまとい、黄金の留め金のついたサンダルといういでたちでしたが、アイルランドやウェールズの伝統では、まだら模様は異界からのしるしでした。 3. 聖なる木「宿り木」 ドルイド教では樫に寄生するやどり木は神聖なもので、やどり木自身が宿主としてる木(やどり木が生えている木=樫)に神が在ることを示していると信じられていました。やどり木自身が宿木の魂のようなもので、それが現れたものとも考えていたようです。宿り木が生えている樫は、「神から選ばれし木」のしるしでした。ドルイドたちは樫の木に生えるやどり木を特別神聖視し(樫に生えるやどり木は非常に珍しい)、それが見つかると儀式にのっとってやどり木を摘みに行きました。(冬の、やどり木の開花時であったようです) ポンペイのベスビオ火山の犠牲となったローマの博物学者大プリニウスによると、「摘み取られる日は月齢6日目で、その日は彼らの月、年、そして30年続く世の初めであり、月はまだその運行の半ばに至ってはいないが、既にその力を十分に発揮している日である。彼らはこのやどり木を「万能薬」という意味の名で呼んでいる(パナケア:panaceaと呼ばれていました)。典礼にのっとり、木の下に生け贄と食事を用意し、白い牡牛を二頭、角を結び合わせて近づける。白衣を着た1人の祭司が木に登り、黄金の鎌(おそらく青銅に金メッキだと思われる)で宿り木を切る。下にいる人々はやどり木が地面に触れないよう、白い厚地の布でそれを受ける。それから生け贄を捧げて神の慈悲を乞い、祈る。人々は、やどり木を不妊の動物に子が授かり、あらゆる毒物に効く薬になると信じているのだ」 人の首に紐でかけただけで病が癒えたと言われ、現代医学でも、不眠症、高血圧、ある種の悪性腫瘍に効くことがわかっています。 「神々との約定を結ばなかったため、宿り木は魔力を持っている」という千年のおばばの言葉については、【クリスタル☆ドラゴンに見られる北欧神話・やどり木】をご覧ください。
ドルイドになるには、長い修行が必要で、時には20年にも及んだそうです。バラーの姉エラータは12年で修行をおえた事になっていますが、これはかなり優秀だったということでしょう。 ドルイド達は軍務・税金を免除された特権階級であったため、多くの者がドルイドを目指し、また身内からドルイドを出そうと両親や親戚によって修行に出されたようです。しかし出身や家柄の良さ、高い道徳的人格を持つことなどが条件とされたために、選ばれたものにしか道は開かれませんでした。さらにドルイドの教義を受ける資格を得るためには、棺の中に埋葬され、それに耐えて生還すること、また屋根のない小舟に乗せられて、海に流されるという試練を通過しなければなりませんでした。 このような修行制度の「本場」はブリテン島で、ドルイドの術を熱心に学ぼうとする者はブリテンまで赴いて修行したそうです。修行の内容は、今日で言うと、神学を含む哲学、自然哲学、天文学、数学、歴史学、地理学、医学、法律学、詩学、演説法などを学びました。 修行の場所は人里離れた洞くつや秘密の森の中でした。 教義の伝授は全て口伝で行われ、文字に書き取られることはありませんでした。ドルイドの修行の初めは口誦伝承から行っていたようで、「語り部(フィーレやバード)」を経てからドルイドの修行へ入るという説もあります。(アリアンも「見習い」としてサガの暗唱をさせられていますね) 「文字として残す」習慣がないケルト人にとって、口伝えでの口誦伝承は重要な記録を残す手段で、宗教の教典や法律の規則、戦争の武勲の記録、家系図など部族の歴史は語り部の暗唱によって保持していたからです。 なぜ、ドルイド(ケルト人)は書物のような記録を残さなかったのでしょうか?その理由をカエサルはこう推測しています。「書き物にすることで、修行の方法や内容が外部に漏れるのを防ぐためと、書き記すことによって、記憶する力が弱まる(あるいは記憶する努力を怠る)ことを防ぐため」。 ただ、全く文字を書かなかったわけではないようです。カエサルも「すべての日常の記述にはギリシア語のアルファベットを用いている」と記していますし、19世紀末には、ブルグ近くのコリュニーで、紀元前一世紀~紀元一世紀初期のものと見られる暦が発見されました。青銅板にローマ字とローマ数字で刻まれていますが、ローマ暦とは別のもので、ガリアのドルイドによって記録されたものだと推測されています(リヨン美術館蔵の「コリニ暦」と呼ばれている物です)。 各月日を省略語でmat(良い)anm(良くない)と区別して記され、日が良いとか良くないなどを見るのに使用されたようですが、これはガリア地方(フランスを中心としたヨーロッパ)の例であり、エリン(アイルランド)では文字が記録された物は発見されていないのかもしれません。 5. ヴァテス(ヴァーティス)、フィーレ、ボエルジ、バード ヴァテス フィーレ(filidh:フィーリ) ボエルジ
|
| 【ハロウィンの由来考】 |
| ハロウィンの由来とは!?日本のお盆や節分との共通点は? ハロウィンの説明として、「日本のお盆のようなもの」という言い方を見かけることがある。確かに、と思う一方で、だがしかし、と感じる部分もある。 そこで、ハロウィンというイベントと日本の行事との類似性・相違点について考えてみたい。 まず、ハロウィンの由来について。そもそもハロウィンとは、どんな日なのか。 ハロウィンはケルト文化やキリスト教など、少なくとも3つ以上の文化習俗が混合されてできている。現在のハロウィンは、イベント、つまりお祭りとしてアメリカで花開いた。
よく言われるのが、「ハロウィンとは万聖節(ばんせいせつ)、諸聖人の日の、前夜祭だ」というもの。これはキリスト教の、主にカトリック教会を中心とした祝日の1つで、聖人や殉教者を記念する日だ。この諸聖人の日が11月1日、その前日の10月31日が前夜祭であるハロウィンとなる。ちなみに11月2日は死者の日(万霊節)で、死者の魂のために祈りを捧げる日となる。
ハロウィンのこの日は、魑魅魍魎が私たちの周りを闊歩する日だ。精霊や悪霊がそこかしこにいる。 だから、悪霊にイタズラされないように、人間だとバレないように変装する。
さて、このハロウィンだが、そもそもはキリスト教の行事ではない。キリスト教が広まる過程で、他の文化を飲み込む流れの中で合わさったものだ。
さて、このサウィン祭に、ローマの収穫祭が融合する。この収穫祭はローマで11月1日に行われていた、果実の女神ポモナをたたえる日だ。 ハロウィンにはリンゴを使った遊びや占いが多い。例えば、・たらいなどに水を入れ、りんごを浮かべる。それを口でとるゲーム・夜中に若い娘が鏡の前でリンゴの皮を向いていると、鏡に将来の伴侶が映る・真夜中に鏡の前で、後ろを振り返らずにリンゴを食べていると、鏡に(同上) これらは女神ポモナから来ているのだと思う。なぜかというと、リンゴはポモナの象徴だからだ。
さらにはキリスト教が混じり合っていく。7世紀、ローマ教皇ボニファティウス4世が11月1日を諸聖人の日と定める勅令を出した。諸聖人の日の前夜、オール・ハロウズ・イブ(All
Hallow's Eve)が後にハロウィン(Halloweem)になった。 やがてアメリカに持ち込まれ、それまでカブを用いられていたのがカボチャに変わり、現在へと至る。
ここで冒頭の「日本のお盆のようなもの」というところに戻ると、最大の類似点は③の死者の祭りである、という点になると思う。 お盆はご存知のとおり、祖霊を祀る日本の伝統行事である。このお盆の期間は、祖霊、つまりご先祖様がやってきて、私たち生者とともに過ごす。言い方を変えれば、死者があちこちにいるのがお盆であり、私たちは盆踊りを踊る。 類似点は、この死者が周囲にいる、という点だろう。 相違点は、死者に対する生者のスタンスである。 前述のとおり、ケルト人(ドルイド教)は輪廻転生を信じる。だからハロウィンの日、来るとしてもその年に死んだ者のみで、家族がくるわけではない。そして悪霊を払うためにかがり火を焚き、変装したりする。つまりシャットアウトである。 一方の日本。日本も、仏教という側面で考えると、輪廻転生である。49日を過ぎれば生まれ変わるはずなので、祖霊を迎え入れるというのはおかしい。しかし、祖霊を、というのはもともと日本古来の信仰で、後から仏教と混同・習合されたわけだ。お盆にナスやキュウリで作った馬と牛を盆棚に飾る。そして提灯に火を灯す。この火は祖霊に対する目印で、行きは馬に乗って早く来てもらい、帰りは牛にのってゆっくりと帰ってもらう。お盆の期間は食事も用意し、一緒に食す。 サウィン祭のかがり火が霊を払うに対し、日本の火は迎え入れるために使う。この霊の対象と、霊に対するスタンスが最大の違いだと思う。悪霊を払う、とうい点でいえば、それに該当する日本の行事は追儺(ついな)だろう。追儺とは大晦日の宮中行事であり、鬼やらい、鬼を払う行事である。つまり節分のことだ。 現在の節分は、立春の前日である2月3日に行う。昔のこよみでは、2月の立春近辺が新年のはじまりだった。 収穫祭という点で見たらどうだろう? もう一度、ハロウィン(サウィン)祭の特徴を再掲しよう。 ここに日本の伝統行事を照らし合わせてみよう。 ところで、ケルトのサウィン祭の説明に、動物を供えるということを書いた。動物を解体し、神に捧げる。 実はこれ、日本とも共通する部分がある。 有名なのは諏訪大社の御頭祭だろうか。これは凄い光景で、鹿の首や、うさぎの串刺しなどが供えられる。これが凄い数で、鹿の数は70~80頭はあり、うさぎのあ尻から頭にかけて串刺しにされている。もちろん現在は行われていない。こうした動物の生贄については、日本各地で見られる。詳細は別の機会に書きたいと思うが、農耕の収穫祭と生贄に強い関連性があるとの指摘もある。であれば、サウィン祭で農作物と共に動物を供えるという点と、類似する点があるかもしれない。
ハロウィンでは、「トリック・オア・トリート (Trick or Treat) 」お菓子をくれなきゃイタズラしちゃうぞ、と言って子供たちが各家庭を回ってお菓子を集める。 これの原型は、その後変質したケルト人の習慣(変装してパフォーマンスしながら各家庭を周り、その見返りとして食糧をもらっていた)やイタズラ、キリスト教の物乞いの習慣からの発展だと思われる。 子供たちにとってはお菓子の稼ぎ時だが、日本でも「子供は7つまでは神の子」と言われ、神様へのお供え物をとって食べてもしからないように、という考え方がありました。なぜ7つまでは神の子なのか。それは昔は死亡率が高かったから。昔の子供にとって、生死の境界はないようなものだったのだな。 神様に近かったわけです。 |
| 【ケルトと日本の民話の比較考】 |
| 第一章 ケルトと日本の民話の比較 第一節 ケルトとは この章では、ヨーロッパの西端にあるアイルランドなどの地域で伝承されてきたケルトの民話と、アジアの東端に位置する日本の民話にどのような共通点が見られるのか、いくつかの民話を採り上げて比較していく。 本題に入る前に、まずケルト民族について少し触れておきたい。ケルト民族は、紀元前四世紀頃には西アジアからアイルランドに至る広範な地域に広がっていた。しかし、紀元前二世紀末のゲルマン民族の大移動や紀元前一世紀頃のユリウス・カエサル率いるローマ軍の進出によって、次第に辺境に追いやられ、ついにはアイルランド、ウェールズ、スコットランド、北フランスのブルターニュの四つの地域にまで規模が縮小された[1]。(資料:地図1、2) ケルト民族は、代々伝わる伝説や信仰を文字に残すことはしなかった。むしろ、彼らの中で強い権力を持っていたドルイド教の僧たちは、教義を文字として残すことは冒?行為であり、好ましくないと考えていたのである[2]。では、なぜ無文字社会であったケルトの神話や当時の様子を現代において知ることができるのか。それは、戦いなどを通してケルト民族と交わったローマ人、あるいはギリシア人によってケルト民族に関する記述が残されたためである。例えば、ローマ軍を率いてケルト民族を辺境へ追いやったカエサルは、その記録として『ガリア戦記』を残し、その中でケルト民族について述べている。 ローマ人、ギリシア人たちの記述を見ると、ケルト民族は政治的には成功を収めたとは言えないものの、その文化は独特であり、先史時代や中世初期のヨーロッパ民族の中でも際立っていたことがわかる。 ケルト民族は、独自の霊的な信仰や自然観から優れた表現スタイルを発展させていった。そのひとつが民話である。ケルトには多くの神話や伝説がある。先に述べたように、ケルト民族は文字で記録を残すことを好まなかったため、これらの物語や詩はすべて口承されてきた。人々は語り部の口から語られる、英雄や魔物が登場する物語に胸を躍らせて聞き入った。彼らにとって民話とは、聞いて楽しむものであると同時に、過去と自分たちを繋ぐものであり、また、生きていく術を教えてくれる大切なものでもあった。 |
| 第二節 ケルトと日本の民話の比較
第一項 オシーン伝説と浦島太郎伝説 さて、第一節で述べてきたケルト民族は、私たち日本人とは明らかに異なる歴史的背景を持っている。しかし、ケルトと日本には類似した民話が存在するのである。その一つとして有名なのが、ケルトのオシーン伝説と日本の浦島太郎伝説である。第一項では、この二つの民話を紹介し、どのような点が類似しているのかを考えていく。
まずは、オシーン伝説を、以下に簡潔に示したい[3]。 ある日、オシーンとフィアナ騎士団が狩りをしていると、むこうから白馬に乗った女性が彼らのほうへ向かってきた。その女性は、オシーンがこれまでに見たこともないような美女であった。 オシーンの父親であるフィンが彼女に尋ねた。「お嬢さん、あなたの名前は何ですか。こんな所で何をしているのですか」 。「私は、常若の国、ティル・ナ・ノーグの王の娘、ニアヴです。あなたの息子、オシーンに会いに来たのです。」と彼女は答え、そして今度はオシーンに向かって言った。「私と一緒にティル・ナ・ノーグへ行きませんか」。「ええ、もちろん。あなたと共に行きましょう」。オシーンはニアヴの美しさに惹かれていたので、 彼女の誘いに快く応じた。こうして、二人はニアヴの白馬に乗って、ティル・ナ・ノーグへと旅立った。ティル・ナ・ノーグは素晴らしい国だった。一面に緑が溢れ、木々には果実がたわわに実り、そこに住む人々は不老不死であった。オシーンは、ニアヴと共に夢のような日々を過ごした。しかし、しばらくすると、彼は強い望郷の念に駆られるようになった。故郷への想いは日に日に募り、ついに、オシーンは帰郷する決意を固めた。そのことをニアヴに告げると、彼女はとても悲しみ、彼を引き止めようとした。しかし、オシーンの心は変わらなかった。そこで、ニアヴは彼が出発するときにこう言った。「もし、どうしても故郷へお帰りになるとおっしゃるのなら、私の白馬でお帰りになって下さい。ただし、決して馬から降りてはなりません。地に足が着けば、二度とここへ戻ってくることができないのですから。」オシーンは、馬からは降りないと約束し、白馬に乗ってティル・ナ・ノーグをあとにした。 彼が故郷へ帰ってみると、そこは変わり果てていた。ティル・ナ・ノーグで過ごしている間は、時間の感覚が全くなかったので、彼はどのくらいそこで過ごしていたのか分からなかった。オシーンは、自分が故郷を離れてからわずか数年しか経っていないと思っていたが、実は、あれから何百年も時が過ぎていたのだ。 故郷は荒廃していた。彼は白馬に乗ってあちらこちらをさまよった。そして、彼は遠くで数人の男が岩を動かそうとしているのを見つけた。近寄ってみると、人が大きな岩の下敷きになっている。話を聞くと、彼らはオシーンの子孫であると言う。オシーンは、彼らを助けようと、岩を軽々と持ち上げて、投げ飛ばした。すると突然、鐙がぷっつりと切れ、彼は馬から落ち、馬はあっという間に遠くへ走り去ってしまった。そして、馬から落ちた途端、オシーンは若々しい青年から、白髪の老人になってしまった。 続いて、浦島太郎伝説を以下に記す[4]。 むかしむかし、あるところに長者の息子で浦島太郎という若者がいた。太郎は海が好きで、よく海へ出かけていた。ある日、太郎が海へ出かけると、浜辺で子供が亀をつついて遊んでいた。かわいそうに思った太郎は、「子供よ、お金をあげるからその亀を私にくれないか。」と言って、子供から亀をもらい受け、海へ返してやった。
またある日、太郎が浜辺を歩いていると、大きな亀がやってきた。「私はこの間の亀です。助けてくださったお礼に私の背中へ乗ってください。海へ案内しますから。」と言うので、太郎は亀の背中に乗って海の中へ潜り、竜宮城というところへ行った。そこはとてもきれいで、美しい乙姫様が出迎えてくれた。太郎は、毎日美味しいごちそうと美しい舞を楽しんだ。
竜宮城での生活は夢のようであったが、しばらく過ごすうちに、太郎はふと故郷を懐かしく思い、どうしても帰りたくなってしまった。 太郎は、故郷に帰りたいと乙姫様に伝えた。乙姫様は、「このままずっと竜宮城でお過ごしになってくださればよいのに。」と言ったが、そういうわけにもいかない、と太郎は帰郷する決心をした。別れ際に、乙姫様は太郎にきれいな重箱をくださった。「これは玉手箱というものです。あなたに差し上げますが、決して開けてはなりません。」と言った。太郎は、くれるのに開けるなとは、不思議なことを言うものだと思ったが、有り難く頂戴することにした。再び亀の背中に乗って、陸に上がり、太郎が家に帰ってみると、自分の家がどこにもない。まわりの景色も人も見知らぬものばかり。どうしたことか、と思い、通りすがりの人に聞いてみると長者の家はとっくの昔に絶えたそうだ。太郎が竜宮城で過ごしている間に、実は何百年という時が経っていたのだった。悲しみに暮れ、困った太郎は乙姫様からもらった玉手箱を開けてしまう。すると、中から白い煙が出てきて、たちまち若々しかった太郎は白髪の老人になってしまった。
|
| 第二項 アザラシ女房と天の羽衣伝説
次に、スコットランドのアザラシ女房と日本の天の羽衣伝説を比較してみよう。 まずは、アザラシ女房である[5]。 むかし、あるところに若者がいた。彼は自分の船を持っており、夜が明けるといつも海へ出かけていった。その海の沖には無人の島があった。年に一度、夕暮れ時にアザラシたちがその島にやってくる。アザラシはそこで衣を脱ぎ、人間の姿になって一晩を過ごすのだ。 ある日、若者がこの島へやってきて、一頭の美しいアザラシを見つけた。彼は海岸の岩陰に隠れて様子を窺うことにした。すると、アザラシたちがそれぞれの皮を脱いで浜へ集まってくるではないか。その中に、彼が見つけた美しいアザラシの姿もあり、彼女は人間の姿になっても、やはり大変美しかった。その娘は脱いだ衣を岩にかけると、仲間たちの輪の中へ入っていった。 若者はその隙に彼女の衣を岩から取り、自分の船へ隠してしまった。夜明けが近づくと、娘たちはそれぞれの衣を身に纏い始めた。しかし、美しい娘だけは自分の衣が見つからず、途方に暮れていた。他のアザラシたちは娘と一緒に衣を探していたが、見つからないので、3週間後に新しい衣を持ってきてやるからと約束し、海へ帰ってしまった。 娘は、ますます困惑して岩陰に隠れて泣いていた。そこへ若者がやってきて、娘に一体どうしたのか、と声をかけた。娘は衣をなくしてしまい、海へ帰れないということを話した。すると若者は、「では、私と一緒においで。」と言って、娘を連れてうちに帰った。若者は娘を親切にもてなした。 しばらくして二人は結婚し、三人の子供を授かった。家族はいつも幸せに暮らしていた。しかし、主人が海へ出かけると、妻はいつも何かを探しまわっていた。 それから長い年月が流れたある日のこと、夫が納屋で仕事をしているとき、そばにいた一番上の子供が、納屋で見たことのないものを見つけた。それがあのアザラシの衣だったのである。子供はそのことを母親に話してしまった。 次の日、母親は子供たちにとても親切にし、夕食を作ってやった。それから、出かけてくると言い残して家を出た。主人が帰ってくると、子供たちは母親のことを彼に話した。それで、彼は全てを知り、もう妻が帰ってこないということを悟った。 続いて、日本の天の羽衣伝説を見てみよう[6]。 むかしむかし、あるところに一人の若者がいた。 ある日、彼が浜辺を歩いていると、娘たちが浜で水浴びをしていた。どの娘も本当に美しく、若者は隠れて彼女達に見惚れていた。ふと浜辺の松を見ると、ふわりとした着物がかけてあった。若者は出来心でその中の一枚を取り、自分の荷物の中へ隠してしまった。 夕方、もう一度あの浜辺へ来てみると、一人の娘が泣いていた。若者は、これはきっと自分が着物を隠したせいだろうと思い、気の毒になって娘に声をかけた。 「娘や、どうして泣いているのだい。」 すると、娘は「私は天女なのですが、水浴びをしている間に大切な着物がなくなってしまったので、天へ帰ることができなくなってしまったのです。」と嘆いた。 若者は、「それは気の毒に。帰ることができないのならば、私と一緒においで。私の妻になっておくれ。」と頼み、その天女を家へ連れ帰って妻にした。やがて年月が過ぎ、二人の間には一人の子供ができた。 ある日、若者の留守中に、天女は子供を寝かしつけようとしていた。子供に添い寝しながら、ふと天井を見上げると、何かが天井にひっかかっている。何だろうと思い、取ってみると、それは水浴びの時になくした着物ではないか。そこで、天女は、夫が着物を盗んで隠していたのだということに気づいた。 天女が子供を抱きかかえて天へ帰ろうとしたそのとき、若者が帰ってきて、それを見つけ、必死に止めようとした。しかし、天女はどうしても天へ戻りたいのだと彼に告げ、そのまま行ってしまった。 アザラシ女房と天の羽衣伝説に共通する点は、①特定の女性の衣服を、男が隠して結婚すること、②その女性が異界から来た者であったこと、である。 人間が、人間とは異なる生き物と交際し、結婚することを異類婚という。異類婚には、大きく分けて、①人間の男と異界の女、②人間の男と動物、③人間の女と動物、の三つのパターンがよく見られる。この中で、①や②はアジアに多く分布しており、③はヨーロッパにも見られる。 この二つの民話の相違点は、天の羽衣伝説では、男性と結婚する女性が天界から来た天女であるのに対し、アザラシ女房では、女性が動物だという点である。これは、天女という概念が中国から伝わったアジア特有の概念であるためだ。では、なぜスコットランドではアザラシが物語に登場するのか。これは、スコットランドやノルウェーの海にアザラシが多く生息し、そこに住む人々との生活上のつながりも深いためであると考えられる。 [1] 田中仁彦『ケルト神話と中世騎士物語 「他界」への旅と冒険』(中央公論新社)、1995
[4] 原英一 前掲書 Aurea Ovis http://aureaovis.com/index.html (05.12.05 12:00) |
| 第二章 ケルトと日本の信仰の比較
第一章で見てきたように、ケルトと日本には類似した民話が存在する。その類似の背景には、一体何があるのだろうか。私は、民話の類似が発生する一因として思想の類似が挙げられるのではないか、と考えた。そこで、今回はケルトと日本の思想を比較するために、両地域の信仰に焦点を絞って考えていきたい。信仰も民話と同じように、世界中のどの地域でも見られるものである。また、信仰も人間の思想が顕著に表れたもので、なおかつ生活に密着したものであると言えるため、これを比較の対象とすることにした。 実際、遠く離れているにも関わらず、ケルトと日本には信仰の面でも多くの共通点を見出すことができる。以下、その類似点を節に分けて紹介していく。 第一節 多神教 一つ目の類似点は、アイルランドも日本も多神教であるということだ。それは、アイルランドがカトリックを、日本が仏教を受け入れていった過程にも表れている。 今日、アイルランドの主要な宗教はカトリックであり、また、日本の主要な宗教は仏教であると考えられている。しかし、古代ケルト人はもともとドルイド教を信仰し、日本人は神道を信仰していた。カトリックや仏教は、外部からもたらされた宗教なのである。まず、アイルランドでのカトリックの受容のされ方について述べていこう。カトリックがアイルランドに入ってきたのは432年で、布教したのは聖パトリックである。彼は、キリスト教の教義である父と子と精霊の三位一体説を、ドルイド教にもともとあった教義と重ね合わせて説いた[1]。聖パトリックは、ケルトの宗教に対して決して否定的ではなく、むしろ土着の宗教とカトリックを融合させる形で布教を進めた。そのため、一人の殉教者も出すことはなかったと言われている[2]。 では、次に日本での仏教の需要のされ方について見ていこう。日本には、538年に百済から仏教が伝来してきた。仏教的世界観と古来の神道の考え方は本質的には異なるものであったが、人々は、仏教の神である菩薩や仏をも、神道の八百万の神の一部として受け入れたのである。 このように、アイルランドも日本も、土着の宗教と外来の宗教を重ね合わせる形で受容していった。なぜ、土着の宗教とは根本的に考え方の異なる新宗教を受け入れたのであろうか。それは、たんに新宗教の勢力が大きかったということだけではなく、アイルランドと日本で古くから信仰されてきた宗教が、多神教的寛容さを持っていたためではないだろうか。先ほども述べたように、ドルイド教も神道も多神教である。そのため、自分たちが本来崇拝していた神への信仰は保ちつつ、なおかつ新宗教の神をも受け入れたのである。 現在でも日本では、神道は仏教と並んで伝統的な宗教として存続してきた。これに対して、アイルランドのドルイド教は現在、民間の信仰のみにとどまっている。これは、アイルランドに新宗教として布教されたキリスト教がもともと排他的な一神教であったためだと考えられる。仏教は異教に対して比較的寛容であったため、日本古来の宗教であった神道はその地位を守り続けることができたのだ。 第二節 アニミズム では、その他の類似点を見てみよう。日本とケルトの信仰の大きな共通点と言えるのが、アニミズムである。アニミズムとは、宗教の超自然的な思想の一つで、宇宙に存在するあらゆるものには神(精霊、魂)が宿っているという考えである[3]。スティーブン・ヘンリー・ギルは、このアニミズムの精神はケルトと日本の詩の中にも見ることができる、と述べている[4]。日本人が生み出した代表的な表現スタイルと言えば、俳句、あるいは短歌である。彼は、論文の中で次の短歌を紹介している。
このように、和歌(俳句、短歌)とは、十七音、三十一音という限られた音節の中に、自然観、感情、感動などが詰め込まれた、情緒溢れる歌である。俳句や短歌を詠む際には、あまり直接的な表現は好まれない。表現の工夫で余韻を残すことによって、ある程度は作者の思いを表現し、それ以上は読み手の想像力にゆだねられる。古代アイルランドの詩にもこのように、短い音の中に詩人の思いを凝縮させたり、読み手の想像力をかきたてたりするような表現方法が見られる。 詩 意味 Scel lemm duib, dordaid dam, Snigid gaim, ro-faith sam, Roruad rath, ro cleth cruth, Ro gab gnath, giugrann guth. 鳴く鹿 積む雪 遠い夏 錆の色なる羊歯野原 今年も聞こゆ野雁の声[6] このように、詩人は短い音節の中に、自分の思いを込める。日本の作品もケルトの作品も、季節の移り変わりや風景、それに伴った人々の感情を表したものが多い。これは日本やケルトの人々が、自然とは敬うべきものであり、なおかつ自分たちの生活との結びつきが非常に強いものだと考えていたためではないだろうか。 |
| 第三節 太陽信仰
三つ目の共通点は、太陽信仰である。日本やケルトに限らず、多くの古代信仰には太陽崇拝が見られる。古代の日本でも、太陽神である女神、天あま照てらす大神おおみかみを最高神と考えることや、自分たちの国を「日ひの本もと」と称することなどから分かるように、太陽に対する信仰が厚かった。太陽は宇宙の根源であり、生命の創造、成育、豊饒のためのエネルギー源であると考えられていたのである。 一方、古代ケルトのドルイド教でも、太陽は特別な意味を持っていた。古代ケルト人は、全ての生命の源である太陽を、創造と豊饒の神として崇めていた。また、ケルトにはブリギットという女神がいる。かつて太陽が魔の雲によって闇に覆われた暗黒の時代に、その闇を払ったのが、ブリギットである。 日本でも天照大神が天の岩戸に隠れた時に、世界に暗闇の時期が訪れている。このことから、古代の人々が太陽を特別な存在と見なしており、太陽がなくなれば災いが訪れると考えていたことが分かる。そして、これらの神話は闇の世界(死)から光の世界(生)へ、という、次節で述べる輪廻転生の思想にもつながっていると言える。 第四節 輪廻転生(渦巻き模様と縄文文化) アニミズムと同様に大きな共通点と言えるのが、輪廻転生の思想である。輪廻転生とは、宇宙に生きるすべてのものは死と再生を繰り返すという考え方である。この思想によると、万物は移り変わっていくが、宇宙の実体というものは不変であり、その中で全てのものは生から死へ、死から生へと、永遠の繰り返しをしている。すなわち、肉体が死んでも、その霊魂は永遠に生まれ変わりを繰り返すのである。 このような輪廻転生の考え方が色濃く表れているのが、ケルトの渦巻き模様である。ケルトには、『ケルズの書』や『ダロウの書』に描かれているような渦巻き模様が多く見られる。(資料1-1、1-2)この渦巻き模様は、ケルト神話に登場する人間や動物、植物の自然の形態を抽象化、紋様化したものであり、生死を繰り返す永遠性や輪廻転生を象徴するシンボルであると考えられている。このケルトの渦巻き模様によく似ていると言われるのが、日本の縄文土器の模様である。たとえば、芸術家の岡本太郎は、ケルトの渦巻き模様に日本の縄文土器の紋様を重ね合わせて、こう述べている。 驚くのは、このケルトと縄文文化の表情に、信じ難いほどそっくりなのがあることだ。地球の反対側と言ってもいいほど、遠く離れているし、時代のズレもある。どう考えても交流があったとは思えない。一方は狩猟・採取民が土をこねて作った土器だし、片方は鉄器文化の段階にある農耕・牧畜の民のもの、石に彫られたり、金属など。まるで異質だ。しかし、にもかかわらず、その両者の表現は、双生児のように響きあっている。部分を写真などで比べてみると、実際区別がつかないくらいだ[7]。(資料2-1、2-2) さらに、岡本は、こうも述べている。 この極東の文化とヨーロッパ芸術の源流ともいうべきケルト。あの組紐紋に象徴される永遠に回転し、流れて行く世界観。私が西欧文化で一番惹かれるのはケルトだ。東西の両極、相離れた地域の、この古い文化に見られる不思議な同一性は、いったい何を意味するのだろう。私はこの神秘的な現象に常にうたれるのだ[8]。 また、龍村仁も、「ケルトの人々は、自然界の全ての現象が宇宙的な大霊の現れであり、自然界の全ての生命は一つの大きな命の一部分である、と考えていた。これは、神道の原点である私達の祖先・縄文人の自然観・生命観と同じだった。」[9]と述べ、ケルトと日本のつながりを強調している。 アニミズムに加え、渦巻き模様に象徴される輪廻転生の思想、これはケルトと日本の大きな共通点であると言えるであろう。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)