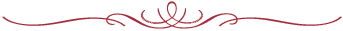
| 日本のシオニズム勢力考 |
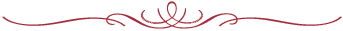
(最新見直し2014.03.23日)
| 「日本のシオニズム勢力考」をしてみたい。総花的に考察する前に「三田人脈シオニズム」から説き起こしたい。「三田人脈とは慶応大学の三田校舎からとった名前で、慶応大学人脈に形成されたシオニズムグループのことを云う」。その典型は、加藤 寛(かとう
ひろし)に見て取ることができる。 加藤 寛のプロフィールは次の通り。 1926(大正15)年、岩手県生まれ。1950(昭和25)年、慶應義塾大学経済学部卒業。昭和41年 慶應義塾大学経済学部教授。平成 2年 慶應義塾大学総合政策学部教授・学部長。1994(平成6)年、慶應義塾大学名誉教授。平成 7年 4月から 千葉商科大学/千葉短期大学学長。 経済学博士で、専攻は、比較経済体制論、.公共経済分析論。日本経済政策学会、ソ連(ロシア)東欧学会、日本計画行政学会、公共選択学会に所属。著書多数。 この間、米価審議会委員、1981年、土光臨調で国鉄(現、JR)、電電公社(現、NTT)、専売公社(現、JT)の民営化を実現。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスで教育改革を実施。前政府税制調査会会長。2004年、竹中平蔵・郵政民営化担当大臣より『郵政民営化情報システム検討会議』の座長に任命される。 しかし、これだけでは加藤寛の実像に迫れないのでれんだいこが解説する。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
中曽根康弘を中心にした臨教審・ゆとり教育人脈の研究
http://www.asyura2.com/0411/senkyo7/msg/301.html
現在、行われている「ゆとり教育」政策の源流は、中曽根臨教審にあります。なぜか、この原点が
忘れられているように感じるので、若干の研究を行ってみました。
まず、臨教審が教育版「土光臨調」に他ならないことを、他ならぬ寺脇研氏に語って頂きます。
2004年2月号 中央公論 文部科学省の教育改革を語る 「ゆとり教育」は時代の要請である
文化庁文化部長 寺脇 研(てらわき けん)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01254/contents/732.htm
>「ゆとり教育」へと進む方向は、明らかに時代の要請であり流れです。そもそも、こうした流れは、一九
>八四年に中曽根首相の主導のもとにできた臨時教育審議会(臨教審)で確立されました。いまの「錦の
>御旗」は臨教審なのです。そこで「生涯学習」という理念が決まりました。学校中心主義からの転換、教
>師による「教育」から生徒中心の「学習」への転換です。この理念の延長にいまの教育改革がある。です
>から「ゆとり教育」の枝葉については否定できても、その根本理念を否定できる人はいないはずです。
>そして、臨教審のそのまた根っこにあるのが、八一年にできた臨時行政調査会(土光臨調)です。土光
>臨調に日本の霞が関はいわばほぼ全面降伏した。事務局に出向していてその場に立ち会った私には、
>強烈な印象です。国鉄がなくなって、JRになる。電電公社がNTTになる。それまでの常識では考えられ
>ないことが起こったのです。予算はこれ以上増やさず、シーリングをかけて厳しくやっていく。公務員の権
>力はどんどん抑える・・・。
>それからの二〇年、小泉改革にいたる世の中の流れというのは、一貫して、“官から民へ”。中央集権
>から地方分権へ、大きな政府から小さな政府へ、という流れでやってきています。「ゆとり教育」もまた、
>これに沿った政策のひとつなのです。国レベルの制約をゆるめて地方や学校現場での裁量を広げる、と
>いう意味で。
この「生涯学習」自体がうさんくさいわけだが、それはまた別の話。実は「ゆとり教育」の本質とは、
教育版「土光臨調」であり、教育界の「行政改革」だったのである。
(実は、寺脇氏の話をよく聞いていると、この本音が随所に見えているのだが、みな「ゆとり教育はゆるみ
教育」「学力低下で国力低下」といった精神論に惑わされ、この本質を見抜くことに失敗した)
さて、ここで「土光臨調」とは何だったのか? 七面倒くさい行政論よりも、ここがわかりやすいだろう。
土光のメザシ:または「ウソはどれほどついてもいい」のか?
http://webclub.kcom.ne.jp/mb/imitsui/talk14.html
>この圧倒的な「土光支持」の世論の流れを受けて、80年代前半、三公社民営化が相次いで「断行」されました。まあそのうちでも、超暴利を
>むさぼっていた電電や専売を「民営化」するのはさして難しいことでもないし、その際に、しかも市価を上回る「株価」で株を売りつけちゃって、政
>府財政に多額の新財源をもたらしたのは、「財政再建」の限りで言えば、成功のうちではあるでしょう(その財源が何に使われたのか、その後
>の「バブル経済」とどうつながったのか、なんて小難しいことは、誰一人議論もしませんが)。最大の「ねらい」は、国鉄「分割民営化」にあったと
>いうことは、今日誰もが認めるところです。
>その国鉄は、確かに膨大な累積債務を抱え、政府財政に多大の負担を強いていたことは紛れもない事実です。それをどのように解決するの
>か、これは日本に限らず、古典的な輸送インフラストラクチュアとしての鉄道という「お荷物」を抱えた国々の共通の大問題でもありました。それ
>を考えるについては、単に財政問題だけではなく、運輸手段のありかたや交通政策のありかたに及ぶ、根本的な問いがあることも間違いない
>でしょう。
>しかし、そうした「マジな議論」だけではなく、ここで図られた国鉄分割民営化は、体制への抵抗勢力の最大の牙城と目された国鉄労働者の
>労働組合運動を完膚無きまでに解体粉砕することにあったというのも、今日かなり幅広く認められており、その「証言」も数々あがってきていま
>す。事実、これによって国鉄労働組合は解体に近い状況にまで無力化され、また「戦闘的」とされた組合は一挙に「御用派」に走って生き残り
>を図り、逆に抵抗労働者を威圧屈服させる先陣を争うに至りました。無数の血と涙が流され、「一人の職員も路頭には迷わせない」はずの口約
>束はたちまち反古にされ、多くの人間が路上に放り出されました。そして、90年代にはどのような企業倫理の退廃にも、リストラ攻勢と失業者
>の増大にもまったくなんの「抵抗」もできない、「労働運動」だけが残り、マスコミ諸氏にそのあまりのふがいなさを慨嘆させるほどになったので
>す。
>このとき、土光臨調の「切り込み隊長」となった加藤寛教授は、土光氏の向こうを張ってか、『国鉄労使国賊論』などというえげつない題の本
>を著し、これまたセンセーショナリズムをあおりながら、持論の「分割民営化」を一挙にすすめたのです。「労使」などという、一般の人口には膾
>炙しない「表現」は当然、「国鉄労働者=国賊」と聞こえます。いやらしいトリックです。そしてこの際には、まるで「仕掛けたような」国鉄内部の
>規律違反、不祥事、事故が続発し、「こんな国鉄はつぶしてしまえ」というマスコミの大合唱が隅々に響き渡りました。既存の労働法規は一切
>無視、まさしく国鉄労働者は「国賊」の扱いを受けたのです。
さて、臨教審のメンバーは以下の通りである。ちなみに当時(84)は、首相=中曽根康弘 官房長官=後藤田正晴 文部大臣=森喜郎
天谷直弘、有田一壽、飯島宗一、石井威望、石川忠雄、内田健三、岡野俊一郎、岡本道雄、金杉秀信、
木村治美、香山健一、小林登、齋藤正、齋藤斗志二、須之部量三、瀬島龍三、溜昭代、堂垣内尚弘、
戸張敦雄、中内功、中山素平、細見卓、三浦知寿子(曾野綾子)、水上忠、宮田義二。
現在の存命者と主な肩書きは以下の通り
石井威望(慶應大SFC客員教授) 石川忠雄(慶應義塾学事顧問) 内田健三(政治評論家)
岡野俊一郎(日本サッカー協会名誉会長) 岡本道雄(日独文化研究所理事長)金杉秀信(元同盟副会長)
木村治美(共立女子大名誉教授) 小林登(東京大学名誉教授) 齋藤斗志二(代議士)
須之部量三(杏林学園理事) 瀬島龍三(伊藤忠商事特別顧問) 溜昭代(元・千葉市立打瀬小学校長)
戸張敦雄(全国連合退職校長会
総務部長)中内功(流通科学大学・学園長) 中山素平(国際大学特別顧問)
細見卓(ニッセイ基礎研究所
特別顧問) 曾野綾子(日本財団・会長) 水上忠(獨協学園・理事長)
宮田 義二(松下政経塾相談役)
「民間教育臨調」人脈によく似ていることに気づいたアンタは偉い(笑)
http://www.kyouikukaikaku.net/
さて、土光臨調の「切り込み隊長」加藤寛は、松下幸之助のブレーンの1人でもあった。
「世界を考える京都座会」(座長=松下幸之助)
http://panasonic.co.jp/company/person/life/cl_0158.html
メンバーは(肩書きはすべて当時)
天谷直弘(産業研究所顧問)、飯田経夫(名古屋大学教授)、石井威望(東京大学教授)、牛尾治朗(ウシオ電機会長)、
加藤寛
(慶応義塾大学教授)、高坂正堯(京都大学教授)、斎藤精一郎(立教大学教授)、堺屋太一(作家)、
広中平祐(京都大学教授)、山本七平(山本書店店主)、渡部昇一(上智大学教授)
この「京都座会」は、かなり直接的に、臨教審に影響を与えている。
1985/04/25 朝日新聞朝刊「自由化」論争持ち越し 首相周辺に強い意欲 臨教審の審議経過の概要
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01254/contents/009.htm
><仕掛け> 「自由化」論が、まとまった形で臨教審のテーマに上ったのは、昨年9月27日の第3回総
>会。首相ブレーンの1人といわれる香山健一委員(学習院大教授)が「『教育改革の基本方向』について
>の提案」と題する4ページの文書を各委員に配布。そこで「今次教育改革で戦略的に重要なのは、教育
>行政改革による教育の自由化の断行だ」として、(1)教育行政分野での許認可、各種規制の見直し(2)
>教育分野への民間活力の導入(3)学校の民営化、塾の合法化(4)選択の自由の拡大と競争メカニズ
>ムの導入――など「自由化」の具体的な内容を示した。この考え方は、昨年2月の首相の施政方針演説
>でも、「教育を受ける側の選択の自由の拡大」の表現で、さりげなく顔をのぞかせていた。
>「自由化」論をいち早く組み立てたのは、松下幸之助氏が座長の「世界を考える京都座会」の面々だ。
>昨年3月、「学校教育活性化のための7つの提言」を発表、その中で自由化を改革理念の中心に据え、
>以後、マスコミなどを通じて自由化を盛んにPRしてきた。京都座会から、のちに天谷直弘(国際経済交
>流財団会長)、石井威望(東大教授)の両氏が臨教審委員に、渡部昇一(上智大教授)、山本七平(山
>本書店店主)の両氏が専門委員に任命された。
臨教審「教育の自由化論」(内実は公教育リストラ論)の急先鋒が、故香山健一(中曽根康弘のブレーン)だ
というのはよく知られているが、故松下幸之助グループの存在は忘れられているのではないだろうか?
結局、この「自由化論」は、公教育のテリトリーを失うことを恐れた旧文部省・文教族が厳しく抵抗、「個性重視」
に文案が書き換えられた(この構図は昨今の義務教育費問題にそっくり)
香山や木村治美は、文部省と日教組の双方を、「教育の自由を阻む」と厳しく批判。文部省批判には
政財界の意向が、日教組潰しには中曽根の意向が(国鉄改革における国労潰しと同じ構図)働いていた
ことは想像に難くない。
その臨教審の答申がどこに落ち着いたか、その後の教育政策はどうなったか・・・については、この2つのURLを示すに留める。
http://www005.upp.so-net.ne.jp/yosenabe/rinkyousin.htm
臨時教育審議会とは・・・
>この臨教審以降、教育政策が大きく変わりはじめた。まず、教育政策の基調が従来の保守主義から新保守主
>義に変わったことである。
>では、その新保守主義とはなにか。村上泰亮によれば「新保守主義は、ナショナリズム、経済自由主義、技術オプ
>ティミズムの三者を武器とする現状変革の試みとして要約できる」という。
>ひとつは臨教審における教育の自由化路線である。自由化論が登場した理由として、社会経済的移動の増大と
>高学歴化、生涯学習の要請、さらには国家財政の逼迫による教育費個人負担の増大等を背景に、教育を個人投
>資とみる風潮が強まったことが指摘されている。しかし、この教育の自由化も臨教審では「個性主義」に変わり、答
>申では「個性重視の原則」とされた。
>また、一方、伝統的保守の永年の主張であり、文教政策の懸案であった「道徳教育の強化」や「教員の資質向上」
>も臨教審にしっかり盛り込まれた。
臨教審以降の教育改革の主な施策の概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo1/gijiroku/001/010401c.htm
さて、話はここで、平成7(1995)年に飛ぼう。この年は、旧文部省と日教組が歴史的な
「和解」を果たした年としても知られる。同年4月、千葉市内に、ある小学校が開校する。
千葉市立打瀬小学校
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/114/gakkogaiyon.htm
この「子供は未来からの留学生である」というスローガンは、故香山健一が臨教審時代によく口にしていた
キャッチフレーズそのままである。校長の名は、溜昭代。臨教審に、日教組から参加していた人物だ。
1987/07/26 朝日新聞朝刊 現場から(臨教審の1000日・最終答申を前に:1)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/01254/contents/061.htm
>今、胸を張って言えることは、「熱意と、自分なりの言葉で話してきたこと」。そして、強い組合は、やは
>り必要だ、という。「委員には、教育基本法にも手をつけようとの声も強かった。そうならなかったのは、
>組合なり何なりの見えない影響力があったから」。そのためにも「組合は内部の派閥争いばかりせず、も
>っと変わらなくちゃ」。
溜は当然、寺脇とも親しかったはずで、この打瀬小は、いわば「ゆとり教育」の実験校である、と言っていいだろう。
松下政経塾(元臨教審の鉄鋼労連の実力者・宮田義二が深く関わっている)の人間が、ここで研修を行ったりしている。
http://www.mskj.or.jp/jukuho/9612jk3.html
23歳、2度目の小学生生活(2) 白井智子/松下政経塾第16期生
>この学校に来て何より驚いたのは、私が抱いていた日本の小学校のイメージとはまったく異なり、むしろシドニーの学校のイメージに近いこと
>だった。希望の持てるモデル校の一つになるものと感じる。
この白井は、なぜか石原慎太郎とも親しく、現在は教育関係のNPO法人を経営している。この白井と、
寺脇研・宮台真司・炭谷俊樹(大前研一の片腕・元マッキンゼー)といった面々が顔を合わせたのが、このシンポジウムだ。
第27回「J.I.フォーラム」~21世紀の国づくりを考える~「現場は待ってくれない! ~学校教育再考~」
http://www.l-net.com/lgs/mass/JIforum27.htm
このイベントを行ったのは構想日本。主宰は加藤秀樹(SFC・元大蔵省)
http://www.southwave.co.jp/swave/6_env/kato/kato03.htm
加藤秀樹は竹中平蔵(元SFC)とも親しく、竹中平蔵は加藤寛(SFC設立の立役者、現・千葉
商科大学長)と親しい。SFCを接点に「行政改革」「構造改革」論者が繋がることになる。
50年生まれの加藤秀樹も、世代的には、寺脇(52年生)と同じく、80年代の霞ヶ関で土光臨調
の影響を受けた、土光チルドレンである。
あの賢明な宮台真司が、なぜゆとり教育に賛成したのか? と訝しく思う向きが多かったが、90年代から
親しかった寺脇との関係の他にも、松下政経塾系・構想日本系の人脈の影響もあったようだ。
(宮台もゆとり教育を、「動機づけ」理論、エリート教育論の実験場ぐらいにしか思っていなかったのではないか?)
このように、ゆとり教育の「正体」とは、新自由主義・新保守主義的な「小さな政府」論の実験が、
教育界において大掛かりに進行中であることを意味する。
決して寺脇は左翼ではない(タカ派論壇は、臨教審に自分たちの身内が関わっていた一点からして、これが
嘘だと知っていたはずだ。彼らは、中曽根人脈の影を隠すために、わざと嘘をついたのではないか?)
寺脇(だけではなく、この政策の周囲に群がった人々)は過激な「小さな政府」論者そのものであり、その
意味では相当に危険な人々と言っていい。
この視点から、90年代以降の教育政策を眺めると、公教育の軽量化、「ゆとり」と裏腹の競争原理の蔓延、
大学独法化、教育特区構想、教育基本法改正、少子化危機の塾業界(ちなみに、この業界は経済産業省と仲がいい)と私学に「ゆとり」特需、
公立中高一貫(公立エリートコース)の設立、職業系高校の切り捨て(総合制は本当に優れた制度か?)、
単位制・通信制設立による「個性」「生涯学習」の奨励(美名のもとで、所詮は普通科エリートコースに乗れ
ない生徒たちを、遠回しに切り捨てているのではないか? また生涯学習の名目で、人々を「学校化」に
囲い込むだけなのではないか?)、、、
思いつつままでキリが無いが、何かが狂いだしたのではないだろうか・・・。知り合いの教師は「まるで株式会社だ、
今の学校教育は・・・このうえ教育特区が本格化したら、いったいどうなってしまうのだろう?」と呟いていた。
「学力低下」に空虚な大騒ぎをしているうちに、着々と教育界の「行政改革」は行われてしまったのである・・・。
いまや日教組も弱体化(翼賛化)。さらに政官財だけでなく、学界・ジャーナリズムも80年代以降の「土光臨調」
の洗礼を受けた世代であり、この「行政改革」の正体を見抜くことがまるでできていない。
なお、「学力低下論者」においても、ここに書き留めておこう。99年頃からメディア上で「学力低下論」
「アンチゆとり教育論」が勃興したが、タカ派論壇の身内隠しのデマ(左翼陰謀論)を除けば、
最初のURLの文中で寺脇自身が認めているように、大半は通産省(経済産業省)の仕掛けである。こんな研究会が存在した。
「グローバル市場競争時代における教育・人材育成のあり方」研究委員会(肩書きはすべて当時)
http://www.gispri.or.jp/newsletter/1999/9910-2.html
<委員長>
西村和雄(京都大学経済研究所教授)
<委員>
浦坂純子(同志社大学文学部専任講師) 岡部恒治(埼玉大学経済学部教授)
苅谷剛彦(東京大学大学院教育学研究科助教授)
倉元直樹(東北大学アドミッションセンター助教授)
子安増生(京都大学大学院教育学研究科教授)
中馬宏之(一橋大学イノベーション研究センター教授)
戸瀬信之(慶應義塾大学経済学部教授)
平田純一(立命館大学経済学部教授)
八木匡(同志社大学経済学部教授)
<アドバイザー>
飯高茂(学習院大学理学部教授)上野健爾(京都大学大学院理学研究科教授)佐野博敏(大学セミナーハウス理事長・館長)
浪川幸彦(名古屋大学大学院多元数理科学研究科教授)
<オブザーバー>
石田浩(東京大学社会科学研究所教授)
掛林誠(通商産業省大臣官房参事官・基礎産業局担当)
冨浦英一(通商産業省大臣官房企画調査官)
山田宗範(通商産業省大臣官房参事官・産業政策局担当)
横山晋一郎(日本経済新聞社編集局社会部編集委員)
ちなみに、この「地球産業文化研究所」の当時の理事長は平岩外四(経団連)。
つまりは、文部省・文教族サイドに対抗して、通産省(経済産業省)・経団連サイドから教育政策を
コントロールすることが目的であり、「行政改革」路線においては大枠ではたいして変わるところはない。
(かなりリベラルに見える苅谷剛彦氏が、文部省批判には積極的なのに、その向こうの政財官の流れ
の話になるといまひとつなのは、この委員会があったせいだろう)
いちいちは書かないが、このうち某氏などは、最近、教育産業や文教族・経産官僚と組み、怪しげな動きを
見せている。他、この委員会に入っていたメンバーではないが、和田秀樹は民間教育臨調(臨教審系人脈)に参加。
むろん、これ以外でも、純粋に土光臨調・臨教審以来の「行政改革」「構造改革」路線全体を批判していた学界人もいたようだが、こうした
状況下では、その声は小さくならざるを得なかったようだ。
これが、臨教審から続くこの国の教育界の「行政改革」の大雑把な構図であり、「学力低下論争」という
茶番劇の正体なのである・・・!
|
11. 4 |
日本商工会議所会頭・鹿島建設(株)会長 |
石川 六郎 |
|
9. 5 |
前警察庁長官 |
山田 英雄 |
|
7.13 |
経済企画庁長官 |
中尾 栄一 |
|
6.13 |
自由民主党総合農政調査会長 |
羽田 孜 |
|
5.19 |
政府税調間接税部会長・慶応義塾大学教授 |
加藤 寛 |
|
| 123-衆-予算委員会-14号
1992年03月07日 平成四年三月七日(土曜日) 午前十時開議 出席委員 委員長 山村新治郎君 理事 中山 正暉君 理事 原田昇左右君 理事 町村 信孝君 理事 村岡 兼造君 理事 村上誠一郎君 理事 串原 義直君 理事 野坂 浩賢君 理事 松浦 利尚君 理事 草川 昭三君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君 甘利 明君 粟屋 敏信君 井奥 貞雄君 上草 義輝君 小澤 潔君 越智 伊平君 越智 通雄君 奥田 幹生君 鹿野 道彦君 狩野 勝君 金子原二郎君 唐沢俊二郎君 後藤田正晴君 左藤 恵君 志賀 節君 塩谷 立君 鈴木 恒夫君 住 博司君 田澤 吉郎君 戸井田三郎君 萩山 教嚴君 浜田 幸一君 福永 信彦君 古屋 圭司君 光武 顕君 村山 達雄君 森 英介君 柳沢 伯夫君 井上 普方君 伊東 秀子君 加藤 万吉君 小岩井 清君 小林 守君 佐藤 恒晴君 新盛 辰雄君 関 晴正君 筒井 信隆君 和田 静夫君 春田 重昭君 日笠 勝之君 山口那津男君 小沢 和秋君 木島日出夫君 児玉 健次君 高木 義明君 中野 寛成君 楢崎弥之助君 出席国務大臣 法 務 大 臣 田原 隆君 外 務 大 臣 渡辺美智雄君 大 蔵 大 臣 羽田 孜君 文 部 大 臣 鳩山 邦夫君 厚 生 大 臣 山下 徳夫君 農林水産大臣 田名部匡省君 通商産業大臣 渡部 恒三君 運 輸 大 臣 奥田 敬和君 郵 政 大 臣 渡辺 秀央君 労 働 大 臣 近藤 鉄雄君 自 治 大 臣(国家公安委員会委員長) 塩川正十郎君 国 務 大 臣(内閣官房長官) 加藤 紘一君 国 務 大 臣(防衛庁長官) 宮下 創平君 国 務 大 臣(経済企画庁長官) 野田 毅君 国 務 大 臣(環境庁長官) 中村正三郎君 国 務 大 臣(国土庁長官) 東家 嘉幸君 出席政府委員 警察庁刑事局長 國松 孝次君 警察庁交通局長 関根 謙一君 防衛庁参事官 高島 有終君 防衛庁参事官 三井 康有君 防衛庁長官官房長 村田 直昭君 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 防衛庁教育訓練局長 小池 清彦君 防衛庁経理局長 宝珠山 昇君 防衛施設庁総務部長 竹下 昭君 防衛施設庁建設部長 新井 弘文君 経済企画庁総合計画局長 長瀬 要石君 環境庁長官官房長 森 仁美君 環境庁企画調整局長 八木橋惇夫君 環境庁大気保全局長 入山 文郎君 環境庁水質保全局長 眞鍋 武紀君 国土庁長官官房長 藤原 良一君 国土庁長官官房会計課長 森 悠君 国土庁大都市圏整備局長 西谷 剛君 国土庁防災局長 鹿島 尚武君 法務省刑事局長 濱 邦久君 外務大臣官房文化交流部長 木村 崇之君 外務大臣官房領事移住部長 荒 義尚君 外務省アジア局長 谷野作太郎君 外務省北米局長 佐藤 行雄君 外務省経済局長 小倉 和夫君 外務省経済協力局長 川上 隆朗君 外務省条約局長 柳井 俊二君 外務省国際連合局長 丹波 實君 大蔵大臣官房総務審議官 日高 壮平君 大蔵省主計局長 斎藤 次郎君 大蔵省主税局長 濱本 英輔君 大蔵省証券局長 松野 允彦君 大蔵省銀行局長 土田 正顕君 国税庁次長 冨沢 宏君 文部大臣官房長 野崎 弘君 文部省初等中等教育局長 坂元 弘直君 厚生省保健医療局長 寺松 尚君 厚生省生活衛生局長 玉木 武君 厚生省生活衛生局水道環境部長 小林 康彦君 厚生省薬務局長 川崎 幸雄君 農林水産大臣官房長 馬場久萬男君 農林水産大臣官房予算課長 山本 徹君 農林水産省経済局長 川合 淳二君 農林水産省農蚕園芸局長 上野 博史君 林野庁長官 小澤 普照君 通商産業大臣官房商務流通審議官 麻生 渡君 通商産業大臣官房審議官 榎元 宏明君 通商産業省通商政策局長 岡松壯三郎君 中小企業庁次長 新関 勝郎君 運輸省鉄道局長 井山 嗣夫君 運輸省自動車交通局長 水田 嘉憲君 運輸省自動車交通局技術安全部長 堀込 徳年君 運輸谷航空局長 松尾 道彦君 運輸省航空局技術部長 松本 健治君 労働大臣官房長 齋藤 邦彦君 労働省労働基準局長 佐藤 勝美君 労働省婦人局長 松原 亘子君 労働省職業安定局長 若林 之矩君 建設大臣官房会計課長 近藤 茂夫君 建設省河川局長 近藤 徹君 建設省道路局長 藤井 治芳君 自治省行政局長 紀内 隆宏君 自治省財政局長 湯浅 利夫君 委員外の出席者 衆議院事務総長 緒方信一郎君 参 考 人 (税制調査会会長) 加藤 寛君 議委員会調査 堀口 一郎君 ――――――――――――― 委員の異動 三月七日 辞任 補欠選任 相沢 英之君 森 英介君 愛野興一郎君 浅野 勝人君 池田 行彦君 福永 信彦君 越智 伊平君 金子原二郎君 唐沢俊二郎君 甘利 明君 倉成 正君 萩山 教嚴君 後藤田正晴君 鈴木 恒夫君 原田 憲君 田澤 吉郎君 松永 光君 光武 顕君 松本 十郎君 狩野 勝君 村田敬次郎君 古屋 圭司君 村山 達雄君 赤城 徳彦君 筒井 信隆君 小林 守君 水田 稔君 佐藤 恒晴君 石田 祝稔君 山口那津男君 冬柴 鐵三君 春田 重昭君 児玉 健次君 木島日出夫君 辻 第一君 小沢 和秋君 中野 寛成君 高木 義明君 同日 辞任 補欠選任 赤城 徳彦君 村山 達雄君 浅野 勝人君 塩谷 立君 甘利 明君 唐沢俊二郎君 狩野 勝君 奥田 幹生君 金子原二郎君 越智 伊平君 鈴木 恒夫君 後藤田正晴君 田澤 吉郎君 原田 憲君 萩山 教嚴君 倉成 正君 福永 信彦君 池田 行彦君 古屋 圭司君 村田敬次郎君 光武 顕君 上草 義輝君 森 英介君 住 博司君 小林 守君 筒井 信隆君 佐藤 恒晴君 水田 稔君 木島日出夫君 児玉 健次君 高木 義明君 中野 寛成君 同日 辞任 補欠選任 上草 義輝君 松永 光君 奥田 幹生君 松本 十郎君 塩谷 立君 愛野興一郎君 住 博司君 相沢 英之君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 平成四年度一般会計予算 平成四年度特別会計予算 平成四年度政府関係機関予算 ――――◇――――― ○中山(正)委員長代理 この際、山口那津男君から関連質疑の申し出があります。春田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。山口那津男君。 ○山口(那)委員 私の方からは、防衛費の削減と、それから現下問題となっておりますカンボジアの関係についてお尋ねをしたいと思います。 まず初めに、防衛費の関係ですが、既に御承知のようにポスト冷戦のもとで軍縮の傾向というものが世界の一般的な流れとなっておりまして、もはや動かしがたいものであります。そこで、我が国といたしましても、この平和の配当を要求すべき立場にあることは間違いございません。しかしながら、平和憲法を持ち、また非核三原則のあるこの我が国が、基盤的防衛力を整備しよう、こういう基本政策に立ちましてこれまでやってきたわけでありまして、おのずから他の軍事大国等とはその姿勢が違っていることも事実であります。 そこで、近年の主要な国々におけるこの防衛費といいますか、国防費の推移及び今後五、六年を見通した上で、これらの削減計画がどのようになっていくか、これについての概括的な説明をいただきたいと思います。 ○宮下国務大臣 欧米諸国におきましては、御案内のようにWPOの崩壊でありますとか、東欧の駐留旧ソ連軍の撤廃あるいはヨーロッパにおける通常兵器であるCFE条約の署名といった、欧州の安全保障環境の整備が行われていることは御案内のとおりでございます。 米国は今、戦略核兵器やグローバルに展開する兵力等の削減を内容とする兵力再編を計画いたしておりまして、先般の国防白書におきましても、地球的規模の脅威は消滅したけれども地域的な問題は依然として残ってクローズアップされてきているという認識を強く示しております。 ドイツ等は、国際公約として、統一ドイツでございますから、削減の一定の約束がございまして、兵力量を削減していることは御案内のとおりでございますが、英国、フランス等はこれまでのところ国防費を増加していると承知しております。 特に、アジアにおきましては、このアジア地域の構造がヨーロッパみたいな二極構造と異なりまして複雑で、対立の図式も非常に多様化しております。そして、未解決のいろいろ政治的な問題、民族的な問題等々もございます。中国、韓国、ASEAN等の諸国も国防費は大幅に増加をいたしておりまして、これまでのところ、私、これを調査してみたのですが、アジアにおきましては、防衛費を削減している国は一つもございません。 そういう状況で、個々のもしか国防費の総額あるいはアップ率等についで必要であればお答えを申し上げますが、全般的にはそのような状況でございますので、今軍縮軍縮ということが声高に言われておりますけれども、子細に見ますと、地域的にあるいは国によってかなり違ってきておるという状況にございます。 ○山口(那)委員 この点については、とりわけ核兵器を持たない我が国としては、通常兵器のみで防衛力を整備しているわけでありますから、この通常兵器の推移というものについてとりわけ注目をすべきであろうと思うのですが、各国の防衛費等の構造からいって、この通常兵器についての動きを分析するということが果たしてどれだけ可能なのでしょうか。現時点での御見解を承りたいと思います。 ○宮下国務大臣 ちょっと、各国の通常兵器に限定してのお尋ねでございますので、事務当局の方から説明させていただきます。 ○高島(有)政府委員 お答え申し上げます。 私どもも、各国の再編計画の中で通常兵器だけがどういう形で今後計画されていくのかといった形での分析調査はまだいたしておりません。そういう意味で、正確に現在、現時点で申し上げられる資料をここに持ち合わせておりませんが、例えば米国につきましては、今長官から御説明いたしましたように、大きな削減計画の柱の一つが戦略部門でございまして、したがいまして、通常兵器よりはむしろ戦略分野が重点の一つになっている。 それから、ヨーロッパの国々について見ますと、イギリスは一方で、例えば九〇年の三十万強の体制から、九〇年代の半ばまでには約六万ぐらいの兵力の削減計画がございますが、他方、核戦力につきましては、古くなりましたポラリス型潜水艦をトライデント型原潜に置きかえる計画が着実に実行されている。そういう意味で、防衛費は九四年までの見通しによりましても少しずつふえる計画になっております。 他方、ドイツは非核国でございますので、国際約束の一環として三十七万体制に九四年の末までに持っていくという形で、これにつきましては国防費も漸減する計画を持っているということでございますが、冒頭申しましたように、通常兵力が全体としてどういう動きにあるのかという点に焦点を当てた調査はいたしておりませんので、ひとつ御了承いただきたいと思います。 ○山口(那)委員 ぜひそういう観点からも御研究をお願いしたいと思います。 ところで、我が国は中期防衛力整備計画を持っておるわけでありますが、これが単年度の個々の予算とは異なりまして、五年の期間のお金の面と、それから人的、物的、総合力としての防衛力、これを数量で計画を決めているわけですね。この計画が果たして何を拘束するといいますか、何を決めているものなのかというところがいま一つはっきりしない点もあるわけであります。 例えば、総額明示方式といいまして二十二兆七千五百億という歳出の限度というのを決めておるわけですが、これは上限を決めたということであって、これを超えてはいけないという拘束力を持つものだろうと私なりに理解をしてまいりました。そして、個々の費目を分析した上で、例えば歳出ベースですとこの計画期間中五兆一千億になるとか、あるいは契約ベースですと総額が五兆円になる、これは正面装備だけを見た場合ですが、さまざまなそういう数量の計画を持つわけであります。これがどういう意味を持つかということ、あるいはなぜ決めるのかということについて、基本的な見解をお尋ねします。 ○宮下国務大臣 中期防は、御承知のように我が国の防衛庁がスタートいたしましてから四次防まで防衛計画でやってまいりました。しかし、非常にその当時は、今先生おっしゃっていただいたように、基盤的防衛力構想というよりも、整備途上にございましたので、脅威対抗論とまで言い切れるかどうかわかりませんが、そういう種の考え方で非常に倍増倍増でしてきたわけですね。 例えば、三次防でございますと、四次防の約半分二兆三千四百億程度だったと思いますが、四次防になりますと、これが四兆六千三百億になるということで、当時防衛費の伸び率も二〇%になるというようなごとで、際限のないことではないかという議論が当時国会で盛んに行われました。 そこで、しかし一方、国際情勢はデタント情勢になりましたものですから、この平和時における防衛力のあり方というものを問い直そうではないかということでいろいろ議論の末、我が国の基盤的防衛力構想というのがそのときに初めて出てきたわけですね。いわば平時における必要最小限度の自衛力、これはどうあるべきかということで防衛計画大綱ができたのは御案内のとおりでございます。 それ以来、一%枠の問題がございました。GNP一%の中であれば歯どめがきくということで、一%を超えるといけない、その中ならいいというような議論が国会でずっとなされてきたことも御承知のとおりです。そして、その大綱がつくられて以後は、中期防という政府レベルの防衛計画はございませんでしたけれども、防衛庁限りでは五三中業とか五六中業とか五九中業というようなことで、五カ年間の見通しのもとに防衛計画をローリングでやってきたわけでございます。 ところが一方、やはり考えてみますと、これは今先生、総額明示方式と言われましたが、各国においても、計画の長短はございますけれども、計画的にこれを整備する方がより国民にわかりやすいし、そしてまた防衛力の装備の整備等もやはり長期間を要するものでございますから、単年度単年度の今の方式でございますと、必ずしも見通しもはっきりしない、国民にも理解しにくいという点もございまして、六十一年から再び中期防衛力整備構想のもとに五カ年計画をつくったのは、前回の六十一年から平成二年度までの中期防衛力整備でございました。 これに対しまして、平成三年度から平成七年度までの中期防衛力整備計画をつくったわけでございますが、この特色は何といってもやはり世界情勢の変化というものが背景にございます。特に一昨年の十二月につくられましたものですから、東西ドイツは既に統一されておりましたし、ソビエトの状況その他も趨勢としてはもう予見できる状況にございました。しかしながら、防衛力整備というのは国際情勢が変わったから直ちにまたそれに即応してフレキシブルに即応しなければならないものでもございません。そういうことはできないわけですね。したがって、その大勢を見ながら中期防はつくられました。したがって、正面装備のお話がございましたが、前の中期防では七・七%ぐらい正面装備もふえ、今度は下降ぎみにしてあるというような点一つ見ても、非常に抑制的なものになっています。 そういう意味で、この中期防の持つ意味というものは非常に大きいわけで、この中期防の中でそれぞれの年次予算をまたその必要性に応じていろいろな角度から検討して計上してきている、こういう性質でございますので、中期防の持つ意味は非常に私は大きい、こう思っております。 ○山口(那)委員 この計画は行政内部での取り決めでありますけれども、端的に伺います。これは金額の面でもあるいは数量の面でもこれを超えてはいけないという拘束力を持つものですか。 ○宮下国務大臣 これは法律でもございませんし、また国会の議決事項でもございませんけれども、政府で決めまして、そしてそれを国会に報告をして、そしてその議論を、賛同を得る、こういう性質のもので、安全保障会議にかけ閣議決定をしたものでございますから、今度の場合、金額ももちろんシーリング上限でありますし、その中に決められております装備等もそれを超えて調達することはできないと我々は考えております。 ○山口(那)委員 さて、この防衛費、予算というのは極めて特殊な内容を持つものだと思います。平成三年及び四年度のいわば新規に契約できる部分の内訳を見ますと、これが人件糧食費以外に物件費というものがありますが、物件費の中でも後年度負担によって拘束されているいわゆる歳出化経費を除いたいわゆる一般物件費、これがその新規契約分の総額であります。その中でさらに正面装備の関係だけを取り上げてみますと、この経費というのはかなり少額ではなかろうかと思いますが、平成三年、四年、各年度ごとにその金額及び比率についてお答えください。 ○宮下国務大臣 御指摘のように本年度予算四兆五千五百十八億円でございますが、人件糧食がそのうち四一・三%を占めておりまして、歳出化経費、つまりこの以前に契約したものの支出、歳出ですね、これが三八・一%ですから、合計やはり八割程度はもうこれによって拘束を受けておる、支出を余儀なくされておるということでございます。 先生お尋ねの一般物件費につきましては、その残りで二〇・六%のシェアを占めておりますが、金額で申しますと、三年度は一般物件費が九千二百九十二億円、四年度が九千三百八十二億円ということでございまして、そのうち正面経費の歳出化はどのぐらいかというお尋ねでありますが、これは契約をした本当の初年度の支払い経費その他でございますから非常に小さいものでございます。額を申しますと、三年度に三百三十三億円、四年度に三百十九億円しか歳出化の中に含まれておりません。つまり一般物件費全体の中で四年度で申しますと三・四%、三・回ないし六%くらいしか正面装備の歳出化分はないということだと思います。 ○山口(那)委員 そういう金額でありますから、例えばこれを防衛関係費全体の中での比率を見れば、平成三年ではわずか〇・七五%、そして四年度では〇・七%にしかすぎません。しかも、この正面装備のこれだけの金額も実際には通信関係のものとかが多くて、いわゆる兵器については極めてまた金額が限られる、こういうことでありますから、この防衛費削減を考えるに当たって各年度、単年度の歳出のみをカットしようと思ってもこれはおのずから限界がある、それだけ極めて硬直的であるということであります。したがって、借金をしてどれだけ買えるかというこの契約ベース、これをいかに切り込むかということにかかっているわけであります。 そこで平成三年度、つまり昨年でありますが、これは約一千二億円を削減した、こう言われております。これはほぼ正面装備の契約ベースを中心にやった、全部契約ベースで削ったということでありますが、このうち、一千二億円のうち純粋な正面装備の関係の費用がどれくらいあるか、わかりますか。 ○宮下国務大臣 今御指摘のように、昨年の湾岸戦争の際の問題として防衛庁で千二億円削減措置を講じました。その中でほとんどが正面でございます、正面装備でございますけれども、このうち項目的には九〇式戦車、最新鋭の戦車でございますが、それのシミュレーター等の分として十六億円ございますから、差し引きやはり九百八十六億円というのが正面経費である、正面装備の経費である、このように思っております。 ○山口(那)委員 そして昨年契約ベースで削ったもののその中身、単なる金額だけではなくて物も特定されていたわけであります。例えば飛行機をどれくらいあるいは船をどれぐらい削る、こういう物も特定されたわけでありますが、契約ベースで物を削るということは、すなわちその買い物を先送りしたというだけでありまして、確定的に中期防からその兵器が削減されるという意味ではございません。ですから去年のことだけを見ているとこれは誤解を生ずるわけでありまして、これが仮に先送りされた分が後々の契約ベースの増額となってはね返ったとすれば、これは丸々復活してしまうということにもなるわけでありますね。ちなみに去年練習艦というのを削減をいたしました。しかし今年度予算で同じものが計上されておりますので、物だけを見ていると一部復活をしている、こういうことになるわけでありますね。したがって、結果として歳出がどれだけ削られたか、物がどれだけ削られたかというところを着目しなければ、これは本当の意味での削減にはならないと私は思います。 さて、我が党の市川書記長の質問に対しましてことしの予算委員会で防衛庁長官は、約一千億円をきっぱりと削ります、こういう御答弁をなさっておられますが、これはどういう意味なのか。中期防総額が二十二兆七千五百億ということですから、ここから削られるということを意味するのかどうか、念のために伺います。 ○宮下国務大臣 この点は市川書記長が総括質問で冒頭にお立ちになられた際に私の方から申し上げたわけでございますが、今、御案内のように中期防の総経費は二十二兆七千五百億円でございます。そしてこれをその期間中に一千億削減ということでございますので、当然二十二兆七千五百億円、これは価格にいたしますと、その前年度の平成二年度のマーケットプライスを基礎にいたしておりますが、それによって一千億円は削減するということをきっぱり申し上げたわけでございますから、この契約額と、それから同時にその期間内の歳出額ですね、これをきちっと減らしますということを申し上げたわけでございます。 ○山口(那)委員 したがいまして今の御答弁ですと、歳出として、二十二兆七千五百というのも歳出の総額を決めているわけですから、そこから一千億円削られる、つまり歳出として削られたということは明確になったわけであります。そうしますと、去年は契約ベースで削ったわけでありますが、ことし歳出ベースで削るということが明言されたわけでありますから、去年これこれのものを削るという物の特定というものは今の御答弁で、歳出を削るというお答えからは物が削られるということは出てくるものではありません。したがって、歳出一千億カットというこの歳出枠が今明言されたわけですから、果たしてどのものを削るかということがいずれ明らかにされなければならないわけですね。その点をちょっと指摘をしておきたいと思います。 さらに我が党の二見議員の方から質問がありまして、御答弁ですと、中期防の見直しに当たって下方修正ないし減額修正するという御答弁があったわけでありますが、それは今おっしゃった市川書記長の質問を受けての一千億歳出カットということにさらにプラスして、それを超えてさらに下方修正あるいは減額修正するという意味なのかどうか、これが答弁の文言上は必ずしも明快ではありません。御趣旨を確認したいと思います。 ○宮下国務大臣 これも二見議員に対しまして私は、千億の削減のほかに考え方としてさらに下方修正ないし減額修正の方向で検討がされるもの、そのような御答弁を申し上げてございますけれども、しかしながら中期防の修正につきましては今後種々の観点からいろいろ主要装備等について検討を加えなければなりませんので、現段階でどの程度だというようなことまではなかなか申し上げがたいということを申し上げてきたわけでございます。 ○山口(那)委員 この二見議員の質問に対して新聞報道では、一千億を超えてさらに下方修正する、こういうふうに報道されました。ですから、そういう意味なのかどうかということを伺っておるわけであります。もう一度、念のため。 ○宮下国務大臣 お答え申し上げます。 当時の議事録が、私もちょっともう一回確認をしたのですが、これは「下方修正ないし減額修正をあるいは示唆しているものというように私どもは受けとめるのが素直な受けとめ方だと存じますので、そうした方向で今後それらを含めて検討さしていただきたい、こう申し上げておるわけでございまして、これは言いかえますと、千億あるいはプラスアルファとでも言いかえれば言いかえられる可能性がある、そういうように御理解をいただいて結構だと思います。 ○山口(那)委員 確かに総額が上限として決められておる、そしてそれを見直すというからには下方修正されるに決まっているわけですね。ですから、それを単にオウム返しに言ったのでは何の意味もない。一千億削減ということを明言した後にそういうことをおっしゃったわけでありますから、プラスアルファの余地がある、こういうふうに理解するのが自然だろうと思います。そうおっしゃったからにはどの程度の減額を考えておられるのか。これは確固たる見通しがあったからこそそういう御答弁をされたのでしょうから、今どういう見通しあるいはどういう根拠に基づいてそういう修正の発言をされたのか、伺います。 ○宮下国務大臣 ただいまのところ、それでは千億のほかにどの程度の下方修正かという点につきましては、まだ検討を済んでおりませんし、申し上げる段階ではございません。早速、今防衛庁におきましては防衛力検討委員会を設けまして、前広に検討せいという総理の御指示もございますので、それを鋭意検討中である、このように御理解いただきたいと思います。 ○山口(那)委員 ところで、中期防全体で過去二カ年度の防衛費削減の位置づけがどうなるかということを考える場合に、中期防の金額というのは平成二年度の価格で示されているわけですね。ですから、各年度の価格との調整をしなければなりません。 そこで、この平成三年度及び平成四年度の正面に限って、正面契約ベースでこれを平成二年度に置きかえるとどういうふうになるか、これをお示しいただきたいと思います。 ○畠山政府委員 平成三年度の正面契約ベースの二年度価格の換算でありますが、これは八千九百億円ということになります。それから、平成四年度は八千五百億円という形になります。 ○山口(那)委員 そうしますと、今の数字を前提にして中期防全体での正面の調達額、これを歳出ベースと契約ベースで分けて考える必要があるだろうと思います。歳出ベースではこれが五兆一千億円と言われております。また契約ベースでは五兆円、こういうふうに言われております。しかしその中身は、似ておりますけれども中身は大いに異なるわけでありまして、歳出ベースの五兆一千億円というのは前中期防の後年度負担分が繰り越されてくるわけでありますから、これは既定分として差し引かなければ真の意味での今年度の新規調達という数字が出てまいりません。 それから、契約ベースで考えますと、今中期防期間中に契約をして現に歳出化するものを除いて、つまり次期防に繰り越される分というのが入っておりますので、これも明らかにしなければなりません。それぞれの数字を明らかにした上で、中期防期間中に新規に契約もし、そして歳出もされるという数字を明確にしていただきたいと思います。 ○畠山政府委員 御指摘の歳出ベース五兆一千億のうち既定分、つまり今回の中期防以前に契約をされて今回の中期防期間中に歳出に至るという部分が二兆八百億円でございます。したがいまして、五兆一千億の歳出ベースのうち、これを除いた三兆二百億円というものが、この中期防期間中に新たに契約をして、かつ支出に至る額ということであります。 それからさらに、契約ベース五兆円のうち、この中期防期間中に契約して支出に至る分が同じ三兆二百億円でありますが、後年度に、後年度といいますか、中期防以降にずれ込む歳出分というのが一兆九千九百億円ということでございます。その三兆二百億円を中心にいたしまして、それと既定分との歳出を足し算すると五兆一千億の歳出ベースになり、かつまた三兆二百億円と後年度に支出に至る一兆九千九百億円とを足し算すると契約ベースの五兆円になる、こういうことでございます。 ○山口(那)委員 今おっしゃられた数字はいずれも平成二年度価格でおっしゃられているわけでありますが、そうしますと、正面契約ベース総額五兆円ということですから、平成三年度及び四年度の平成二年度価格に置きかえた契約ベースの総額を見てみますと、先ほどおっしゃったように平成三年が八千九百億、そして平成四年が八千五百億ということになるわけであります。 しかし、中期防五年間、単純に年割りしてみますと、五兆円が、五年間ですからまあ年平均一兆円ペースで調達をしていかなければなかなか達成困難である、こういうことになるだろうと思いますが、実際にはそれをはるかに下回っているという進捗率であります。したがいまして、これがにわかに、平成五年度以降にわかにこの契約ベースの数字が大幅にアップするとは考えがたいわけでありまして、まあ常識的に言えば九千億前後で推移するのではないかと思われるわけですね。そうしますと、最終的には五兆円のうち四兆五千億程度しか達成できないであろう。つまり、大ざっぱに言えば一割程度はこれが減るであろう、このように推測されるわけであります。 こうした推定をもとにいたしましてそれを前提にすれば、新規の正面の歳出額というものがこの中期防期間中、先ほど三兆二百億円になる、こういう話でありましたから、その一割を減らすとすれば三千億円ということになるわけですね。既に一千億円歳出カットということを明言されておられるわけでありますから、残り二千億はほぼ削減されるのではないか、こういう見通しに立って、我が党といたしましてはこの中期防全体の、特に正面装備の中から現に中期防期間中歳出される金額をさらに二千億円以上削減すべきである、こういう主張をしておるわけであります。去年と合わせましてトータルで三千億円の削減を実現すべきものである、そしてこれは極めて合理的な数字である、このように私は思うわけでありますが、この点についての長官の御見解を伺います。 ○宮下国務大臣 山口先生、大変防衛費の構造に明るくて、いろいろの御試算をなさった結果につきましては敬意を表しますが、御指摘の数字は、今先生もおっしゃられたように幾つかの仮定を置いての試算だと私どもは承知いたします。そういう意味で、きょうここで私が、それがどうのこうのと適否を余りはっきり申し上げる段階ではありませんが、きょうはそういう先生の御指摘を承っておくということでとどめておきますが、既に先ほど来申し上げておりますように、また、御質問にありましたように、千億円の約束はいたしておりますから、それに幾ら上積みできるかということは今後の検討にまつということを申し上げるしかないわけでございまして、この点はひとつ御理解をいただかなくちゃならぬな、こう思います。 ○山口(那)委員 先の予算がまだ編成されてない、概算要求すらしてないという段階ですから、なかなか明言しにくいという事情はあるのかもしれませんが、今承っておく、こういう御発言がありましたので、承っだということは長官の頭の中に入ったということでありましょうから、私なりにその入ったということを前提に今後お進めいただきたい、このように私なりに理解をいたします。 さてそこで、平成四年度の正面契約ベース、これは対前年度と比べて伸び率を見ますと三・七%削減された、こういうことになるわけですね。平成三年度を見ますと、これは結果的には前年度比で一六・二%削減をされた、つまり、平成二年度の契約ベースと比べますと、この二カ年度で二割近く落ちてきている、こういう抑制傾向、削減傾向が見られるわけでありますね。しかし、まあ、過去こういう防衛費の削減というのは実現したためしかなかったわけで、平成三年度一千億というのが大規模な初めての削減の実績である、このように思われます。したがいまして、我が党が去年主張したその一千億円削減の措置が今年度にもそれが明確に反映しているということが見てとれると思うんですが、この今年度の予算について相当抑制された編成が行われたと私なりに見ておりますが、長官の見解を伺います。 ○宮下国務大臣 確かに、昨年一千億を削ったために、正面装備においては一六・二%の削減になっております。そして、今御指摘のように、私がたびたび当委員会でも申し上げておりますが、平成四年度の正面装備の方は三・七%の減になっております。今の中期防の平均で申しますと二・三のマイナスでございますが、それをはるかに上回っているもの、つまり昨年一六・二落としたものが基礎になり、さらに落としているということで、両者を足しますと二〇%の正面装備この両年で削減がされているということで、私はこれはいつか機会あったら本当に詳しく申し上げたいなと思っていたんですが、山口先生ちょうど御指摘でございますから申し上げておきますが、そういう意味では、正面装備についてこの両年で二割減少 をしたということは、これはもう今までかつてないことでありまして、私は、まあ予算の全体の額はこれは給与費その他の改善がありますからふえておりますけれども、しかし正面装備に限っては軍縮をしたというように言っても決して過言ではないというように思っております。 ○山口(那)委員 さて、先のことはなかなかわかりにくいわけでありますが、過去がいろいろと教えてくれるわけでありまして、例えば今中期防で各装備の達成率といいますか調達の状況を見ますと、陸海空それぞれ典型的な、代表的な装備というものがあるわけですね。陸でいえば戦車、これが二カ年度合わせて現在のところ三五%弱しか達成されておりません。これも、本来各二割ずつ達成して初めて全体に達するというのが単純な見方でありますから、その意味では達成状況は余りよくない、こういうふうに思われます。さらに、海上自衛隊、護衛艦、これも三〇%程度であります。さらに、航空自衛隊、F15戦闘機、これは三六%弱、こういう状況であります。したがいまして、これが今後、あと残り三カ年度、しかも三年後には見直しをする、こう言っている状況で、にわかにこの達成率がぐんぐん伸びて一〇〇%達成できるとは考えにくいわけですね。 それから、これが前中期防のときはどうだったか、こういうふうに見てみますと、今の戦車でいえば、当初の二カ年度で四四%程度達成されております。それから、護衛艦で見ますと、これは五五%程度達成されております。そしてF15、これは若干少ないんですが、それでも三八%達成されております。そして、前中期防は、後半の三カ年度でこれは歳入が大きく伸びました。それに伴って防衛関係費も非常に高い伸び率を示しております。したがって、この後半の三カ年度で調達がかなりできたという実績があるわけですね。 しかし、今回の中期防では、今なお前中期防と比べてもこの当初二カ年度の達成率は非常によくない。そして、財政状況を見れば、今後にわかに好転をして防衛関係費がどんどん伸びるという状況も恐らく予想しがたいであろう。そしてまた、国際的な環境からいっても、この正面装備をどんどん伸ばしていくということ、これもなかなかやりにくかろう。そういう状況から推定すれば、やはり正面装備を、先ほど私が申しました、一割削減せざるを得ない、こういう結論になることはほぼ明らか、むしろ私はもっとさらに低い達成率になるのではないか、こういうふうに思っております。また、そうすべきかもしれません。そんなように思っておるわけでありますが、長官、私のこの考え方について、どう思われますか。 ○宮下国務大臣 基本的に今御指摘のように、前期中期防のときの二年目、今中期防の二年目、これはもう御指摘のとおり約三五%です、両年を通じて。したがって、その限りにおいては達成率においてやや私どもそれを近づけたいということも考えましたけれども、なかなか財政事情その他もございまして、今のような形になっております。 で、今後どうしていくか。均等割で必ずしも整備するものでもございませんのでつひとつこれからいろいろ主要装備の調達量あるいは正面装備については年度年度でひとつ検討していきたいなと思っております。 ここで一つだけ申し上げておきたい点は、数量的には大綱の大体水準に達しておりまして、その更新等々でございますから、まあこれらのことも考えながら、質の高い自衛力を持つということが私は重要だと思っておりますから、そういう視点まで含めて今後検討していきたいな、こう思っております。 〔中山一正〕委員長代理退席、委員長着席〕 ○山口(那)委員 そこで、歳出カットの額が明らかにされつつあるわけですが、やっぱり最終的には何を削るかという物の側面でもこれが特定をされていかなければならないだろうと思います。その作業を明らかにしていただきたいわけでありますが、まあ今鋭意検討中というところだろうと思います。 さて、この個々の装備品といいますか、この兵器体系について、これは立法府のあり方がどうなのかということをちょっと考えてみたいんですが、この個々の装備品を一々詳細に、例えば戦車が何台要らないとか要るとか、そういう議論は、必ずしも立法府にはそういう専門的、技術的能力は備わっておらない、残念ながら。したがいまして、そういう意味では行政当局のそういう第一次的な判断というのは一応尊重する必要もあるだろうと私は思うわけであります。しかし、シビリアンコントロールの観点からいえば、やはりもっと踏み込んだ立法府のチェックというものが必要なわけでありまして、その点でこれまではその個々の装備品は予算を通じてのコントロールしか私はなかったと思います。私としては、今後この防衛計画の大綱、そして中期防衛力整備計画、こういう両者を相まって、金額の上でも、そしてまた中身の数量の上でもこれを国会がきちんと大枠を統制をしていく、こういう仕組みを確立すべきであろう、このように思っております。この点について長官、どう思われますか。 ○宮下国務大臣 個々の装備につきまして一々どうかなという、防衛庁が専門官庁でございますからという趣意の見解のようにも承れました、一面。それは私もある程度一つの見識だと思います。 しかしながら、一方、後段に述べられましたように、シビリアンコントロールということもございまして、防衛計画とかそういうものは十分国会で御議論をいただいて、そして、その中で国民的な理解を得てこれを実施していくということも、我が国の防衛上、非常に重要なことでございますから、特に後半に言われたように、防衛計画なりあるいは防衛構想なりそういったものも国会で活発な御論議をいただいて、そして、その合意形成を得た上で、きちっとしていきたいな、こう思いますので、その点は先生の御意見はよく理解できるところでございます。 ○山口(那)委員 私は委員会の所属がずっと安全保障特別委員会、そして引き続き安全保障の常任委員会に属しておるわけでありますが、残念ながら、今回の中期防計画が策定をされまして、その国会への報告はあったものの、これの中身に立ち入った十分な議論というのは国会の諸般の関係上。やっておりません。ですから、今後これはやっぱり国会の何らかの議決事項とすれば、これは当然論議を呼ぶわけでありまして、その意味でのこの国会の議決を経るようなシステムを考えるということは今後の大事な課題だろうということを指摘しておきます。 さて外務大臣、お待たせをいたしました。カンボジアの問題について若干お尋ねをいたします。 先般、私は二月十九日から二十三日までカンボジア友好議員連盟の一員として超党派で各党の皆様とカンボジアヘ行ってまいりました。シアヌーク殿下あるいはチア・シム議長あるいはソン・サン元首相、こういった方々と見解を交わし、また現地の実情も幾つか見てまいったわけであります。 さてそこで、今カンボジアを取り巻く状況は、日本が安全保障理事会の非常任理事国になった、つまり、国連の活動について安全保障面で決定をする立場にいるわけであります。そして、カンボジアPKOの代表が明石さんという日本人になった。また、もう一つの重要な活動である難民の帰還活動、これはUNHCRでありますが、この代表も緒方さんという日本人である。また、PKOのUNTACの本格的な展開に先立つUNAMIC、先遣隊、これの次長、つまり文官の最高責任者、これもまた川上さんという日本人であります。それだけ日本に対する国際的期待が高いのだろうと私は思うわけでありますが、この国際的な期待をどう受けとめ、そして我が国としてどのようにおこたえになっていくおつもりか、大臣の所信を伺いたいと思います。 ○渡辺(美)国務大臣 まさに、今ずっとお聞きをいたしましたそのとおりでありまして、日本は国際国家として大いに国連を通じて貢献いたしましょうということは、いろいろ呼びかけをしてきた手前もこれありまして、カンボジアという、日本が、おととしですか、海部内閣のときに各派を呼んで調停も試みるというようなことまでやったことでございますから、それが実を結んでやっと十数年来の内戦が終わったということですから、これは本当に定着をさせていかなきゃならぬ。 そういうような点について、さてどうするかということでございますが、口で言えば、人的、物的、最大限の貢献を、それは口だけの話でございますからね。やはり口だけではだめであって、やはり我々としては、一つはもう、人的貢献としてはぜひともPKO法案を通していただいて、それで組織的な人的協力をやらしてもらいたい。それについては、PKFの部門というようなところはとても困るというのであれば、それは話し合いのことでございますから、後方もあるでしょうし、その他のところもございましょうし、そういうようなことについてはまず若葉運転を、免許証をもらっても若葉運転というのがありますから、ゆっくりと、まず安全第一でやっていただけば、国民が見ておって、これならばまあ本当に大丈夫だと、一層賛成者がどんとふえてくると私は信じて疑わないんです、実際は。 そういうことが一つと、または、もう一つは、人的のほかに財政的な援助、これをしなきゃなりません。立ち上がりは二億ドルとかいっていますが、その後で二十億ドル以上になるのでしょうか、はっきりしたことはわかりませんが、これについては、一部は国連の分担金方式というものがあって、それで受けると。しかし、その他の部分もございますから、それはどういうふうに協力するかは、復旧その他、これはまた、これも相談でございますが、できるだけのことをやってやらないと、やっぱり口だけの国だ、調子ばかりよくてという話になっても国際信用に困りますから、ぜひとも、人様のやれることについてはできるだけ御協力をして、国際的な責任も名実ともに果たしてまいりたい、さように考えておる次第でございます。 ○山口(那)委員 PKOもさることながら、二国間でできることはほかにもたくさんあるだろうと思います。例えば農業支援、医療支援、さらに留学生あるいは文化財、アンコールワット等の文化財の保護等々、ぜひ具体的な支援を実行していただきたい、このようにお願い申し上げまして、質問を終わります。 ○山村委員長 これにて春田君、山口君の質疑は終了いたしました。 |