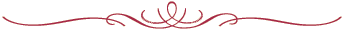
| 「日露戦争」と「日米対立」と「日中戦争」の舞台(作成 1998.3) |
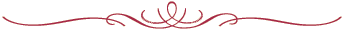
(最新見直し2011.03.25日)
| (れんだいこのショートメッセージ) | |
ここで、「「日露戦争」と「日米対立」と「日中戦争」の舞台裏〜 イギリス、ロシア、アメリカの極東戦略の実態 〜」を転載しておく。これは、副島隆彦氏のブログで教えられた。このことは感謝する。問題は、次のコメントである。
これによると、「なかなか優れた内容」で「おかしな”陰謀論者たち”の、頭のおかしな馬鹿な連中が書く、無根拠の文とは、違います」とある。れんだいこが読んでみて、写真や資料等に多少の価値は認めるが、歴史観全体が親ネオシオニズム通俗説に基づいており、とても「なかなか優れた内容」とは評し難い。「おかしな”陰謀論者たち”の、頭のおかしな馬鹿な連中が書く、無根拠の文とは、違います」は余計なセリフで、この言辞は副島氏にブーメランの如く舞い戻るものでしかない。但し、本論文が敢えて奴隷の言葉で書いているのなら、それなりの価値があることぐらいは認めておこう。その程度の駄文である。これを総評としたい。 2010.03.25日 れんだいこ拝 |
↑読みたい「章」をクリックすればスライド移動します ■序章:はじめに ●「日中戦争(支那事変)」勃発の背景(遠因)は、人によって様々な意見(見方)があると思うが、当館は20世紀初頭に起きた「日露戦争」(1904年)を抜きにしては語れないと思っている。特に「日露戦争」直後に起きた「ハリマン事件」による日米関係の悪化(日米対立)は、その後の日本の運命を決定づけた、かなり重要な事件だったと感じている。(「ハリマン事件」については第4章で詳しく紹介します)。また「アヘン」という麻薬の存在(利権争い)も、「日中戦争」の実態(深層部分)を知る上で、見過ごすことの出来ない重要な要素だと思っている。 ●当館はユダヤ研究をメインにしているので、学校の教科書では絶対に触れることのない(であろう)開国維新後の「日本とユダヤの微妙な関係」に重心を置きながら、「日本がアメリカに占領されるまでの歴史」を少し違った角度からグローバルに考察していきたい。もちろん、異論・反論あると思うが、何か参考になれば幸いである。なお、「おまけ情報」や「追加情報」が多く、内容(情報)が重複している部分が多々あるので読みづらいと思うが予めご了承下さい。 |
| ■第1章:「アヘン戦争」と「開国維新」とユダヤ人
●1971年に「第25回毎日出版文化賞」を受賞した陳 舜臣氏の著書『実録アヘン戦争』(中央公論新社)には、次のような言葉が書かれてある。「『アヘン戦争』は、単にイギリスによるアヘン貿易強行のための中国侵略戦争以上の意味を持っている。この“西からの衝撃”によって、我々の住む東アジアの近代史の幕が切って落とされたのである。」 ●「アヘン」は先述したように、「日中戦争」の実態を知る上で、見過ごすことの出来ない重要な要素だと思うので、この章では「アヘン戦争」や「アヘン商人」の暗躍について簡単に紹介しておきたい。(写真略)ケシ(芥子)の花。アヘンはケシの実に傷をつけ、そこからにじみ出てきた乳液から作られる薬である。昔から麻酔薬として使われてきた。 ●まず、有名な「アヘン商人」といえば、中東出身のユダヤ人デビッド・サッスーンが挙げられる。彼は1832年にインドのボンベイで「サッスーン商会」を設立し、アヘンを密売し始めた。イギリスの「東インド会社」からアヘンの専売権をとった「サッスーン商会」は、中国で売り払い、とてつもない利益を上げ、中国の銀を運び出した。(※ デビッド・サッスーンは「アヘン王」と呼ばれた。彼はイギリス紅茶の総元締めでもあり、麻薬と紅茶は、サッスーンの手の中で同時に動かされていたのである)。 中国では清の時代に、アヘンを薬としてではなく、タバコのようにキセルを使って吸うことが流行した。アヘンは、吸い続けると中毒になり、やがて廃人になってしまうという恐ろしい薬(麻薬)である。 中東出身のユダヤ人 デビッド・サッスーン(1792〜1864年)。インドのボンベイで「サッスーン商会」を設立し、アヘン密売で莫大な富を築く。「アヘン王」と呼ばれた。 ●やがて、清国がアヘン輸入禁止令を出したことに端を発した「アヘン戦争」(1840年)が勃発。敗れた清国は、南京条約により上海など5港の開港と香港の割譲、さらに賠償金2億1000万両を支払わされ、イギリスをはじめ列国の中国侵略の足がかりをつくることになる。 (左)清国と戦っているイギリスの商船。その頃の商船は大砲を持っていた。 学習漫画 『中国の歴史 〈9〉−アヘン戦争とゆれる中国』(集英社)は、子ども向けの本だが、アヘン戦争の実態を手っ取り早く知る上で、最適な本である。アヘン商人たちの腹黒い姿がしっかり描かれている。※サッスーン一族については、第9章で再び触れるので、頭のすみっこに記憶しておいて下さい。(このファミリーは「日中戦争(支那事変)」で重要な役割を演じます) ●ところで、鎖国時代における長崎・平戸のオランダ商館長は、すべてユダヤ系の人物だったと言われる。長崎にはシナゴーグ(ユダヤ教会堂)が作られていた。また、1853年7月8日に浦賀に来航して日本開国を迫ったペリー提督もユダヤ系だったという説がある。幕末、幕府側を援助したのはフランスであり、近代兵器を提供することなく兵制を教えた。一方、倒幕派の薩摩や長州を援助したのはイギリスであり、海援隊の坂本龍馬などを通じて近代兵器を提供した。外国人貿易商にとって、日本は武器輸出市場であった…。 1832年に「ジャーディン・マセソン商会」を中国の広州に設立したイギリス系ユダヤ商人のウィリアム・ジャーディンとジェームス・マセソン この会社の設立当初の主な業務は、アヘンの密輸と茶のイギリスへの輸出で、「アヘン戦争」に深く関わった。1841年に本社を香港に移転した。 グラバーは、1859年に英国から上海に渡り「ジャーディン・マセソン商会」に入社。その後、開港後まもない長崎に移り、2年後に「ジャーディン・マセソン商会」の長崎代理店として「グラバー商会」を設立。貿易業を営みながら、薩摩、長州、土佐ら討幕派を支援し、武器や弾薬を販売した。幕末維新期の日本では、多くの外国人貿易商が諸藩への洋銃売り渡しに関わっていたが、その中でも英商グラバーの販売量は突出していた。彼はのちに「三菱財閥」の岩崎家の後ろ盾となり、キリンビールや長崎造船所を作った。日本初の蒸気機関車の試走、高島炭鉱の開発など、彼が日本の近代化に果たした役割は大きかった。 大政奉還、王政復古、戊辰戦争、明治維新、日清戦争、日露戦争などを経験し、明治新政府の最高権力者として祭り上げられた。新政府は富国強兵、殖産興業の2つを国の重要政策とし、八幡製鉄所の建設、鉄道の敷設、輸出産業の育成など、欧米列強に対抗するため一刻も早い「近代化」を目指し、国力の邁進に努めた。また徴兵制を実施し、列強に対抗するために近代的な軍隊の創設にも取り組んだ。 ●新時代の政治体制と法制をつくったフルべッキ、民法の基礎をつくったボアソナード、大日本帝国憲法の生みの親ロエスレル、陸軍を育てたジュブスケ、近代海軍を整えたデュグラス。また、外交の功績者デニソン、貨幣制度をつくったキンドル、銀行経営の道を開いたシャンド、殖産工業の推進者ワグネル、後の東大工学部を創設したダイエル、学校制度のモルディ、生物学の基礎をつくったモース、哲学・美術の父といわれたフェノロサ……。これら日本の近代国家としての体裁を整えていった「外人お雇い教師」の多くはユダヤ人であり、日本はユダヤ人たちの力添えによって、近代国家へと脱皮をとげていったのである。 ★おまけ情報: 幕末・明治維新後の在日ユダヤ人について ●ドイツのボン大学で日本現代政治史を研究し、論文「ナチズムの時代における日本帝国のユダヤ政策」で哲学博士号を取得したハインツ・E・マウル(元ドイツ連邦軍空軍将校)は、著書『日本はなぜユダヤ人を迫害しなかったのか』(芙蓉書房出版)の中で、次のように語っている。参考までに紹介しておきたい。 「幕末には横浜にユダヤ・コミュニティーが結成され、世紀の変わり目には50家族がこれに属していた。その少し前、帝政ロシアによる迫害を逃れてきたロシア人が長崎にやってきた。このグループはまもなく解散し、700名あまりが東京・横浜や神戸に移住したといわれる。日本各地のユダヤ・コミュニティーは、第一次世界大戦後のパリ講和会議で設立されたユダヤ代表委員会の後継組織である『世界ユダヤ人会議』の傘下にあった。」 「第二次世界大戦が終わるまで、普通の日本人の中にはユダヤ人とはキリスト教の一派だと思い込んでいる者が少なくなかった。 〈中略〉横浜外国人コミュニティーの会長で『ジャパン・エクスプレス』という英字紙を発行していたラファエル・ショイヤーがいるが、彼の後任は、同じユダヤ人のウィルフリード・フライシャーで、この新聞を『ジャパン・アドヴァタイザー』と改称し、これは1940年に発行禁止となるまで最も影響力のある英字紙だった。発禁後は『ジャパン・タイムズ』に吸収される。しかし、日本で最も著名なユダヤ人は、フライシャーの友人で後継者でもあったヤコブ・シフにちがいない。シフはかつてその影響力を駆使して日本にきわめて有利な状況を作り出すのに貢献した。そして、『金持ちで影響力に富む』という日本人一般のユダヤ人についてのイメージを体現する存在となったのである。」 日本各地のユダヤ・コミュニティーは、第一次世界大戦後のパリ講和会議で設立されたユダヤ代表委員会の後継組織である「世界ユダヤ人会議」の傘下にあった 「アメリカの対日制裁は不安と怒りを呼び、日本は攻撃的になる。 〈中略〉 当時2600人を数えた在日ドイツ人の中には116人のユダヤ人がいた。日本人はユダヤ系の学者、芸術家、教育者に高い敬意を払った。その中には、音楽家で教育者のレオニード・クロイツァー、ピアニストのレオ・シロタ、指揮者のヨゼフ・ローゼンシュトックとクラウス・プリングスハイム、哲学者のカール・レヴィット、経済学者のクルト・ジンガー、物理学者のルイス・フーゴー・フランクなどがいる。日本政府は、ドイツ大使館の激しい抗議にもかかわらず、これらのユダヤ人をドイツ人同様に遇した。1941年末、ドイツ大使館は日本政府に対して、外国に居住する全てのユダヤ人は無国籍とされ、今後いかなる保護も与えられないと通告した。そして在日ユダヤ人を解職するよう要求したが、日本の外務省は無視した。 〈中略〉かくして少数ながら戦争終了まで日本で安全に暮らしたユダヤ人がいた。彼らに比べると、何年も前に上海に移住したドイツ系、オーストリア系のユダヤ人や、その後到着した東欧系ユダヤ人は、遥かに厳しい運命にさらされることになる。」※ 以上、『日本はなぜユダヤ人を迫害しなかったのか』(芙蓉書房出版)より |
|
■第2章:「日清戦争」で日本を援助したユダヤ人マーカス・サミュエル ●1894年に「日清戦争」が勃発すると、「シェル石油」の創業者であるイギリスのユダヤ人マーカス・サミュエルは、日本軍に、食糧や、石油や、兵器や、軍需物質を供給して助けた。 イギリス系ユダヤ人のマーカス・サミュエル(1853〜1927年)。世界初の「タンカー王」であり「シェル石油」の創業者である ●そして戦後、日本が清国から台湾を割譲されて、台湾を領有するようになると、サミュエルは日本政府の求めに応じて、台湾の樟脳の開発を引き受けるかたわら、「アヘン公社」の経営に携わった。日本が領有した台湾には、中国本土と同じように、アヘン中毒者が多かった。日本の総督府はアヘンを吸うことをすぐに禁じても、かえって密売市場が栄えて、治安が乱れると判断して、アヘンを販売する公社をつくって、徐々に中毒患者を減らすという現実的な施策をとった。サミュエルは、これらの大きな功績によって、明治天皇から「勲一等旭日大綬章」という勲章を授けられている。 ●サミュエルは、イギリスに戻ると名士となった。そして1902年に、ロンドン市長になった。ユダヤ人として、5人目のロンドン市長である。彼は就任式に、日本の林董(はやし ただす)駐英公使を招いて、パレードの馬車に同乗させた。この年1月に「日英同盟条約」が結ばれたというものの、外国の外交官をたった一人だけ同乗させたのは、実に異例なことだった。この事実は、彼がいかに親日家だったかを示している。(ちなみに、2台目の馬車には、サミュエルのファニー夫人と、林公使夫人が乗った)。 明治期の外交官、政治家林董(はやし ただす)。駐英公使としてロンドンで「日英同盟」に調印した。 ●サミュエルは1921年に男爵の爵位を授けられて、貴族に列した。その4年後には、子爵になった。サミュエルは「どうして、それほどまでに、日本が好きなのか?」という質問に対して、次のように答えている。「中国人には表裏があるが、日本人は正直だ。日本は安定しているが、中国は腐りきっている。日本人は約束を必ず守る。中国人はいつも変節を繰り返している。したがって日本には未来があるが、中国にはない」。●その後、ロンドンに、サミュエルの寄付によって「ベアステッド記念病院」が作られ、彼は気前のよい慈善家としても知られるようになったが、1927年に、74歳で生涯を閉じた。 |
|
■第3章:「日露戦争」で日本を援助したユダヤ人ヤコブ・シフ ●「日清戦争」勝利後、日本は、帝国ロシア南下政策と中国の権益をめぐって「日露戦争」(1904年)を行なった。しかし、日本はわずか1億7000万円の予算しか持っていないので、戦費を海外から調達しなければならなかった。 高橋是清(たかはし
これきよ) ●当時の日銀副総裁の高橋是清(たかはし これきよ)が日本の公債の買い手を求めて絶望的な気持ちで欧米を駆け回っていたとき、ロンドンで日銀創立の功労者であったシャンドと出会った。そのときシャンドは、ユダヤ系投資銀行「クーン・ローブ商会」を率いるヤコブ・シフを高橋是清に紹介し、ヤコブ・シフは当時2億ドル(現在の1兆円)の公債の引き受けをした。その動機について、高橋是清は自伝の中で、「ヤコブ・シフは、帝政ロシアのもとで、ユダヤ人は差別を受け、国内を自由に旅行すら出来ず、圧制の極に達していた。そこで、日本に勝たせ、ロシヤの政治に一大変革を起こし、ユダヤ人がその圧制から救われることを期待していた」と述べている。(※ このヤコブ・シフと高橋是清の話は、司馬遼太郎の名作『坂の上の雲』(文芸春秋)の第4巻でも紹介されているので、知っている方は多いだろう)。 ●ロシアは歴史を通じて、反ユダヤ主義が最も盛んだった国である。 歴代の皇帝はロシア正教に改宗しようとしないユダヤ人を圧迫した。19世紀末から20世紀初頭にかけて、帝政ロシアでは激しいユダヤ人虐殺(ポグロム)が進行した。ヒトラーによるユダヤ人迫害が発生するまで、帝政ロシアは、間違いなく、ユダヤ人が最も大量に殺された国であった。(当時のロシアは、世界で最も多くユダヤ人が住む国であった)。「ポグロム」はロシアから東ヨーロッパにかけて大規模に広がり、この結果、多くのユダヤ人がアメリカへ逃げることになった。
●1905年、「日露戦争」で東洋の島国・日本が勝利すると、全世界のユダヤ人が狂喜した。 今日のイスラエルの国歌「ハ・ティクヴァ(希望)」の歌詞を書いたユダヤ詩人ナフタリ・インベルは、日本勝利の報せをきいて、明治天皇と日本国民を称える詩を発表した。有名なミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』の原作者であるユダヤ人文学者シャローム・アライヘムは、1905年にワルシャワで「日露戦争」に題材をとった喜劇を発表し、日本の勝利を称えた。 このミュージカルは、帝政ロシア時代末期にウクライナで生活していたユダヤ人が、ポグロムに遭遇する物語である。この物語の原作者であるユダヤ人文学者は、「日露戦争」での日本の勝利に大喜びし、「日露戦争」に題材をとった喜劇を発表した。 ●敬虔なユダヤ教徒であったヤコブ・シフは、後になって次のように述懐している。「私はロシアにおけるユダヤ人虐殺に、深く憤っていた。ロシア帝国に対して立ち上がった日本が、ロシアを罰する“神の杖”であるにちがいないと、考えた」。「日露戦争後(1906年)、私は日本政府の招待によって、初めて日本を訪れた。明治天皇は私に親しく感謝を述べられた。皇居では完璧に西洋流の、美味な料理が供されたが、食卓の飾りつけも、西洋式にきわめて洗練されたものだった。明治天皇は健啖(けんたん)で、ユーモアに溢れていられた。ご自分の治世が始まったころの愉快だった逸話について、自由闊達に話された」。 日本政府は、「日露戦争」勝利の功績に報いるため、1906年にヤコブ・シフを日本に招待し、明治天皇が午餐会を催し、シフ夫妻を拝謁。サミュエルと同じ勲章「勲一等旭日大綬章」を与えている。明治天皇が民間人である外国人に陪食を賜ったのは、シフが初めてだった。 ●この明治天皇のユダヤ人への感謝の思いは、昭和天皇にも引き継がれていた。 外交評論家の加瀬英明氏は、次のように述べている。「もし、日本が日露戦争に敗れていたとしたら、日本はロシアによって支配されていたから、今日の日本はありえなかった。他界されてしまったが、私はイスラエルのモシェ・バルトゥール駐日大使と親しかった。大使は1966年から5年にわたって、東京に在勤された。私は大使からきいたが、着任してすぐに、皇居において信任状の奉呈式が行なわれた。その時に、昭和天皇から『日本民族はユダヤ民族に対して、感謝の念を忘れません。かつて、わが国はヤコブ・シフ氏に大変にお世話になりました。この恩を忘れることはありません』という、お言葉をいただいた。大使は陛下の思いがけないお言葉に、驚いた。ところが、ヤコブ・シフという人物について知識がなかった。そのために大使館に戻ってから、急いで調べた。昭和天皇は明治天皇を慕っていられたので、日本がヤコブ・シフとユダヤ人によって救われたことをよく知っていられた。昭和天皇は日本国民のほとんど全員が、日露戦争について関心を失っていたというのに、日本の運命を決定した日露戦争を、昨日のことのように覚えていられたのだった。私は深く感動した」。 ●昭和天皇は、その後のイスラエル大使に対しても、信任状の奉呈式が行なわれるたびに、ヤコブ・シフとユダヤ人への感謝を述べ、その上で、新任の大使を労(ねぎら)われたという。昭和天皇とユダヤ人(イスラエル)に関しては、次のような逸話もある。 ●1989年、昭和天皇が崩御された。 イスラエルのヘルツォーグ大統領は、「日本はナチスの友邦だったから参列するな」という国内の一部の反対を押し切って、大葬の礼に参列するために来日した。東京のユダヤ人協会の歓迎の宴に招かれたヘルツォーグ大統領は、こう挨拶したという。「先の大戦において、多くの国がドアを閉ざしていた頃、日本及び日本の管理地では数万のユダヤ人に避難場所が与えられました。我々は日本国民のこの行為を永遠に忘れません。ユダヤ人に対する日本の態度は、当時ヨーロッパで起きていた事とは全く対照的であり、ひときわ輝いています」。 ★おまけ情報: 「日露戦争に関与したユダヤ人」について ●20世紀初頭のロシアには全世界のユダヤ人の半分に当たる約500万人が住んでいた(これはロシア総人口の4%に当たる)が、「日露戦争」が勃発すると、ロシア軍兵士として戦ったユダヤ人がいた。ヘブライ大学の有名なユダヤ人教授ベン・アミー・シロニー博士は、「日露戦争に関与したユダヤ人」について次のように述べている。参考までに紹介しておきたい。 大の親日家で、日本に関する本を多数出している。ヘブライ大学で、毎年500人を超える学生たちに日本の歴史と文化を講義している。 「19世紀末、ロシアではポグロム(ユダヤ人迫害)の嵐が吹き荒れていた。ポグロムは、ロシア政権の奨励と黙認により、押し進められていたのが現状だった。1894年に政権を握った皇帝ニコライ2世は、彼の政権を脅かすほどの民衆の不信感に直面していた。その打開策として、彼は民衆の怒りを『内の敵(ユダヤ人)』と『外の敵(日本人)』に向けようとした」。「1904年、日露戦争が勃発すると、ヨーロッパのユダヤ資産家は、ユダヤ人を敵視していた帝政ロシアへの援助を拒否した。この資産家たちの中には、『シベリア鉄道』へ多額の援助をしたフランスのロスチャイルド卿も含まれていた。ロスチャイルド卿がロシアのために働いたのは、戦争で負傷したロシア人を援助する機関に寄付することにとどまった。ロシアに対する態度とは対照的に、他のユダヤ人資本家たちはみな日本を援助した。その中でも注目すべきは、ニューヨークの『クーン・ローブ商会』の経営者であるヤコブ・シフである」。 「日露戦争は、ユダヤ人が兵士として、また様々な物語の生みの親として大いに関係した、近代における最初の大戦である。(それまで国を失ったユダヤ民族は、戦闘経験はなかった)ユダヤ人は『シベリア鉄道』の建設に携わり、戦闘態勢を整えた点でロシアに大きく貢献し、また自らロシア軍兵士として戦った。(日露戦争に動員されたユダヤ人は3万3000人で、これは満州におけるロシア軍の約6.6%、このうち約3000人が戦死した)。しかしその一方、戦争でロシアを負かすために日本に援助を送り、日本の勝利を喜んだのもユダヤ人であった。そして、戦時中に起きた革命の過程とその結末の中で随所に登場し、それと並行して同じ頃、ロシアからパレスチナへ移住するための重要な役割を担ったのも、またロシア系ユダヤ人であった」。 「『シベリア鉄道』はロシアの軍事・経済の拡大に大きな弾みをつけ、日本との対立を早める要因となった。この鉄道は、国外から巨額の資金調達によってまかなわれたが、その中の一つがフランスの『ロスチャイルド銀行』である。ロシア政府の奨励により、ユダヤ人事業家は『シベリア鉄道』の沿線に居住した。東地域の開拓につとめ、ロシアの存在を強めるためである。中国の北東に位置する満州に、ロシアの町ハルビンが建設されたとき、ロシア政府は『シベリア鉄道』の中国部分と呼ばれる東清鉄道の地域と、その南部に当たる南満州鉄道の付近へ、在ヨーロッパユダヤ人の移住を促した。その場所に『ヨーロッパ人口』を増援するのが目的であった。1903年、ハルビンのユダヤ人コミュニティで、請負業や商業に携わったユダヤ人の数は500人を数えており、その地でもユダヤ人は町の発展に大いに貢献していた」。 「日露戦争で負けたロシアは、ヤコブ・シフが日本を援助したことを許さなかった。1911年、ロシアの大蔵大臣はアメリカの報道機関に対して、次のように述べている。『ロシア政府は、あのユダヤ人シフが私たちにもたらしたことを決して許さず、また忘れることはないであろう……彼は一個人でありながら、日本のアメリカからの資金調達を可能にした。彼(ヤコブ・シフ)は、我々に立ち向かった最も危険な人物の一人である!』」。 |
| ■第4章:「日露戦争」でユダヤ資本から「恩」を受けながら、満州の共同経営の約束を破った日本 〜 「ハリマン事件」の実態 ●ヤコブ・シフが日本を援助したのと同時に、戦後の満州経営について、日本政府とユダヤ財閥との間に秘密の取引きが行なわれていた。東郷平八郎率いる日本連合艦隊が当時、海軍力世界2位のロシアのバルチック艦隊を破って以来、延びきった戦線のための補給にも苦しくなっていたところ、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の仲介で1905年8月10日、ポーツマスで講和会議が開かれた。 ●そして、秘密取引きの内容を具体化するために、ポーツマスで日露の講和会議が開かれている最中、ロックフェラー家と関係の深いユダヤ系アメリカ人の鉄道王エドワード・ハリマンが、クーン・ローブ・グループの代表として来日したのである。当然、南満州鉄道の日米共同経営についての話し合いが目的だった。 ●「ポーツマス講和会議」では、ロシアの代表ウィッテの巧みな外交戦術により、日本の代表小村寿太郎は、赤子が手をひねられるように屈し、戦勝国でありながら日本は、領地をほとんど手に入れることが出来ず、賠償も権益も得るところわずかであった。交渉結果の知らせを聞いた国内では、「国賊小村」の声も上がっていた。 ※ この時代の日本国民の生活は増税につぐ増税で苦しいものだったし、戦死者の遺族の生活はどん底だった。ポーツマスの日露講和条約に不満を持つ人々は、1905年9月5日、東京の日比谷公園で大集会を開いた。群衆は集会を解散させようとする警官と衝突し、政府高官の家や新聞社、交番、電車を焼き打ちにしたので、日本政府は軍隊の力を借りてこれを鎮めた。 ◆◆ 焼き打ちの拡大 ◆◆ ※ この騒動により、死者は17名、負傷者は500名以上、検挙者は2000名以上にも上った。戒厳令は11月29日まで続いた。 ●桂内閣はこの要望を入れて10月23日、アメリカ側に予備協定の「破棄」を通告した。ハリマンがサンフランシスコに着いたときに、彼を待っていたのは「破棄」を通告する日本政府からの電報であった。今度はハリマンが烈火のごとくに怒り、ただちに翌年の8月に腹心のウィラード・ストレイトを奉天領事に送りこみ、徹底して日本の利権とアメリカ人の利権とを衝突させていったのである。 ●この時、ハリマンは次のような言葉を言い放った。「日本は十年後に後悔することになるだろう!」。(※ これが有名な「ハリマン事件」である。屈辱外交官として、いったんは政治生命を絶たれた小村寿太郎は、この事件後、「南満州鉄道を救った男」として名誉を回復した。しかし、歴史はハリマンの予告通りに動いていく……)。 ●この「ハリマン事件」について、テレビでおなじみの岡崎久彦氏(元・外務省情報調査局長、元・在タイ大使)は、次のように語っている。「あの時に日本がハリマンの提案を受けていたならば、20世紀の歴史はまるで変わっていただろう。アメリカの極東外交は、単なる領土保全、機会均等というお経だけでなく、日本をパートナーとして共同で満州経営を行なう形をとり、また日本では、伊藤博文が健在だった時でもあり、第一次世界大戦の国際情勢の中で、対露、対支政策について、日米英の協調路線ができていた可能性は小さくない」。 「日露戦争が終わった1905年10月、アメリカの鉄道王エドワード・ハリマンが来日し、日本がポーツマス講和条約によって獲得した南満州鉄道の経営に参加したいという申し出をした。このとき、ハリマンと会ったのは首相・桂太郎、元老・井上馨、同じく伊藤博文、財界の渋沢栄一らであったが、彼らはみな『ハリマン構想』に賛成し、合意の覚え書まで作られた。日本側が『ハリマン構想』に同意したのは、今日から見ても正しい判断であった。 そもそも戦争でロシアに勝ったとはいえ、シナ大陸からロシアの勢力が消え失せたわけではない。ロシア軍はなお北満州に展開し、南下の機会を狙っている。そのような状況下において、日本一国が南満州鉄道を維持するのは、軍事的に見ても、また財政的に見ても非常な負担であったから、日米合弁で鉄道経営をするということは、日本にとって一種の安全保障にもなるのである。もし、ロシアが南満州を狙って南下しようとすれば、アメリカ政府はただちにロシアに圧力をかけるに違いないからだ。 また、日米外交という面から見ても、『ハリマン構想』は意義あるものだった。当時、シナ大陸に進出していたのはイギリス、フランス、ドイツ、日本といった国々であり、シナに利権を有していなかったアメリカは切歯扼腕していたのである。ここで日本が南満州鉄道の利権を半分譲れば、アメリカも満足を覚え、日本との友好関係を重視するであろう。こうした点を踏まえて、日本のトップ・リーダーたちは挙げて『ハリマン構想』に賛成したのであった。 ところが、そこにただ一人の、そして頑強なる反対者が現われた。それはポーツマス講和条約を無事締結し、意気揚々と帰国した外務大臣・小村寿太郎である。小村は『わが国の将兵が血を以て獲得した南満州利権をアメリカに譲り渡すとは何事か』と唱え、ついにハリマンとの覚え書を破棄させるに至った。もし、『ハリマン構想』がそのまま実現していたら、その後の日本の運命は大きく変わっていたであろう。 戦前の世界において日米間に緊張が高まり、ついに大東亜戦争に至ったのは、結局はシナ利権問題であった。西部地方の大開拓時代が終わり、その膨張欲を満たす対象を失ったアメリカにとって、広大なシナ大陸の利権はひじょうに魅力的に映った。だが、そのシナ大陸の主要な利権は、他の国々に握られ、アメリカが新たに獲得できる可能性はない。そこで彼らは『ハリマン構想』を日本に持ちかけ、シナ大陸進出の橋頭堡(きょうとうほ)にしようとしたのである。だが、その『ハリマン構想』は土壇場で覆された。 この事件は、その後の日米関係に決定的な亀裂をもたらすことになった。というのもアメリカは自分たちの欲求不満を『日本叩き』に向けたからである。彼らはアメリカがシナ大陸に進出できないのは、すべて日本人のせいだと考えるようになった。戦前のアメリカ人が抱いていた日本に対する憎悪は、いま考えてもぞっとするほどである。まず標的にされたのは在米の日本人移民であった。日本人移民を徹底的に迫害する法律が諸州で作られたばかりか、『絶対的排日移民法』と呼ばれる連邦法までが成立し、日本人がアメリカの市民権を得ることはできなくなったのである。 〈中略〉歴史に『イフ』を持ち出すのは慎重でなければならないが、『ハリマン構想』が実現していれば、アメリカは日本移民をあれほどまでに敵視することはなかったろうし、それどころか満州国建国をもアメリカは支持したと考えられるのである。」 (渡部昇一著『まさしく歴史は繰りかえす〜今こそ「歴史の鉄則」に学ぶとき』クレスト社より) ◆ ◆ ◆ ※ 追加情報: 「ハリマン事件」に関する記事(リンク集) ◆エピソード 『小村寿太郎と桂・ハリマン覚書』 (野澤道生氏の『日本史ノート』解説より) ◆桂・ハリマン覚書 (クリック20世紀より) |
|
■第5章:太平洋をめぐる日米両国の覇権争いが激化 ●アメリカは「日露戦争」(1904年)の数年前に、ハワイに海兵隊を奇襲上陸させて、当時、独立国であった「ハワイ王国」を占領して滅ぼし、アメリカの領土としていた。当時ハワイでは、日本人が人口の半分(2万2000人)を占めていたので、女王は明治天皇に援助を依頼してきたが、当時の日本にはアメリカと戦う力はなく、みすみす事態を見過ごすしかなかった。 彼女は音楽を愛好したことでも知られ、ハワイ民謡として有名な 「アロハ・オエ」は彼女の作である。 ●ちなみに、彼女の兄であるカラカウア前国王は、世界で初めて日本を訪れた外国の国家元首だった。彼はハワイ王国の安泰のため、明治天皇の甥に縁談を申し込んだことで知られている(1881年)。もし、この縁談が実現していたら、「ハワイ王国」はもっと長く存続していたかもしれない…。 彼はアメリカのハワイへの進出を阻むため、同じような状況にあったアジア諸国と連合を組み、立ち向かうための構想を持っていた。そして、それを実現するためアジア諸国を回り、その一番最初の訪問国であり絶対同盟を組みたいと思っていた国が日本であった。(この構想は「大東亜共栄圏」構想の先駆的なプランだった)しかし、このプランは、維新まもなく国力増強優先の日本が取り組めるほど余裕がなかった事もあり、実現しなかった。 ●「ハワイ王国」滅亡後、ここにアメリカの大軍事基地が築かれ、「太平洋艦隊」の根拠地として発展した。それが「パールハーバー」である。そして、イギリスのシンガポール、ロシアのウラジオストクと呼応して、三大軍港が日本を三方から牽制するように取り囲む体制が次第に整っていくのである。 ↑当時作られたこの風刺画は、列強がパイにみたてた中国を分割しているところを描いたものである。左からイギリスのヴィクトリア女王、ドイツのヴィルヘルム2世、ロシアのニコライ2世。ななめ後ろがフランスで、右端の武士が日本である。背後で両手をあげている男性は清の大臣で、「やめてくれ!」と悲鳴をあげている。 ●開国維新後の日本にとって、最大の脅威はロシア帝国であった。ロシアは軍事力を傘に東アジア南下戦略を目指していた。日本にとって「日露戦争」は、国家予算の6倍以上の戦費をつぎ込み、継戦不可能というギリギリで掴んだ“薄氷の勝利”であった。その戦費の約40%を調達したのが、第3章で紹介したユダヤ人金融業者ヤコブ・シフだった。この男の助けがなければ日本は「日露戦争」に勝てなかった、と言っても過言ではなかった。 1847年、ドイツのフランクフルトで生まれる。1870年にアメリカに帰化した。シフ家の祖先は、ドイツのフランクフルトの旧ユダヤ人街区にある一軒の家をロスチャイルド家と共有して住んでいた。シフ(schiff)家の側には「船(schiff)」が、ロスチャイルド(Rothschild)家の側には「赤い盾(roter Schild)が描かれてあり、両家の姓は、そこに由来しているという。 ★おまけ情報: ヤコブ・シフの「クーン・ローブ商会」とエドワード・ハリマンについて ●歴史研究家の田畑則重氏(東京大学新聞研究所修了)は、ヤコブ・シフの生涯(素顔)や日本支援の動機、そして叙勲のために招待された際の『シフ滞日記』を紹介した面白い本を出版した。本のタイトルは『日露戦争に投資した男 〜ユダヤ人銀行家の日記〜』(新潮社)である。 『日露戦争に投資した男〜ユダヤ人銀行家の日記〜』田畑則重著(新潮社) ●田畑則重氏は、この本の「まえがき」の中で次のように書いている。「日露戦争は紛れもなく近代日本の大きなターニング・ポイントだった。この日露戦争を論ずる際に看過されがちな視点は、あの戦争は日本とロシアが戦っただけでなく、日本の同盟国イギリスや、ロシアに対する最大の債権国フランスはもとより、1898年の米西戦争でキューバとフィリピンを手に入れて大西洋と太平洋の覇権を狙うアメリカ、さらに戦場となった清国と韓国、それにドイツや北欧諸国までが絡んでの一大国際戦争だった事実である。最近になって、これら関係国の合従連衡、巨額の戦費、兵器のレベル、大軍の動員、陸海軍の連携、情報・宣伝戦などが第一次世界大戦のミニチュア・スケールながら、これ以前の戦争とは大きく様相が異なることから、日露戦争を『第0次世界大戦』(World War
Zero)と呼ぶ視点が欧米の研究者から出てきている。〈中略〉日露戦争を国際的視点で理解するための地図の空白を埋めるキーパーソンが、以下に紹介するドイツ生まれのアメリカ人銀行家ヤコブ・シフである。日本はもとより、今ではアメリカでさえ忘れられかけているが、当時、彼はウォール街を代表する投資銀行家であり、ヨーロッパの一大金融帝国・ロスチャイルド家とも緊密な関係を持ち、またアメリカ大統領にも直言する立場にあった」。 ●参考までに、この本の中から興味深い部分をピックアップしておきたいと思う。以下、抜粋。※ 各イメージ画像は当館が独自に追加 ◆ ◆ ◆ ◆「クーン・ローブ商会」の創業者エイブラハム・クーンは、1839年にアメリカに来て、他のドイツ系ユダヤ人同様、行商人から身を起こし、10年後、インディアナ州で衣類の卸売業を経営していた時に、遠縁のソロモン・ローブを呼び寄せた。ソロモンは、エイブラハムの妹と結婚し、すぐに共同経営者となった。クーンとローブがシンシナティに移って、総合小売業に転じると、南北戦争の軍用毛布需要が利益を生み、1867年、2人はニューヨークに移り、国債とのちには鉄道債券を取り扱う「クーン・ローブ商会」を設立した。クーンが早くに引退し、ローブの息子たちも金融界で働くことを嫌ったが、1875年にヤコブ・シフが加わった。この年、シフは「クーン・ローブ商会」の共同経営者ソロモン・ローブの娘テレーズと結婚した。 1867年、ドイツ系ユダヤ人によってニューヨークに設立された ◆1885年、ソロモン・ローブの死去に伴い、シフが「クーン・ローブ商会」の代表となった。この正直で若き銀行家は、地味ながら評価される「クーン・ローブ商会」の名声を築き上げていったが、社名に自分の名を冠しようなどとは考えもしなかった。シフの時代のユダヤ人投資銀行家たちの結束は固く、血縁関係で結ばれた同族集団を形成していた。「クーン・ローブ商会」も例外ではなかった。
◆20世紀に入る頃には、「クーン・ローブ商会」は、アメリカでは「モルガン商会」に次ぐ地位を占めるようになっていた。その原動力は、鉄道事業への投資だった。欧州資本と組んで、1875年以降、国の大動脈に投資しているうちに、鉄道会社の再編を通して、「クーン・ローブ商会」自体が鉄道の経営に参画するようになった。鉄道会社の再編と投資事業に先鞭をつけたのは、のちに日露戦争後の南満州鉄道買収をめぐって対立するJ・P・モルガンだったが、シフは数年遅れて追走することになる。シフと「クーン・ローブ商会」は、この過程でエドワード・ハリマンのパートナーとなった。アメリカの東部と北西部の鉄道を縄張りとした「モルガン商会」に対抗して、ハリマンと「クーン・ローブ商会」は、南西部の鉄道を支配する立場に立った。「モルガン財閥」に加え、鉄道界の大立者のジェームズ・ヒルおよびエドワード・ハリマンを巻き込んだノーザン・パシフィック鉄道の再編劇は、シフの名を一挙に全米にとどろかせることになった。 ◆政治と距離を置いたJ・P・モルガンと違って、ヤコブ・シフはアメリカの政府部内に味方を増やす必要があった。日露戦争の直前、シフはロシアとルーマニアでのユダヤ人迫害に対してアメリカ政府が公式に抗議するよう嘆願していた。ビジネスマンとしては、ルーズベルトの反トラスト姿勢には同意しかねたが、ユダヤ人の指導者のひとりとしては、そんなことは言っていられなかった。ルーズベルトも、ユダヤ票を獲得するために、シフの意見に耳を傾けた。「全米ユダヤ人協会」会長も務めるシフという人物が、ユダヤ同胞に圧政を敷くロシアに打撃を与えたいと考え、日本を支援したことには疑いを入れない。しかし、フランクフルトからアメリカに来たドイツ系アメリカ人でありながらアメリカ金融界の頂点にたどり着いた男が、日本に肩入れすることにビジネス・チャンスを見出したとしても矛盾しない。 ◆(日露戦争後)そこに現れたのがアメリカの鉄道王エドワード・ハリマンだった。彼には世界一周鉄道網の夢があり、南満州鉄道を1億円で買収し、シベリア鉄道経由でヨーロッパにいたるアジア大陸横断鉄道を構想したのだった。彼は「ポーツマス講和会議」が始まった8月10日に息子のアベレルとローランドを伴ってニューヨークを発ち、16日にサンフランシスコを出港、31日に横浜に着いた。事前に駐日公使グリスコムが動いて、日本政府は首相桂太郎はじめ、ハリマン提案に傾いており、閣議での反対者は逓信大臣大浦兼武ただひとりだった。背景には、莫大な戦費と賠償金を得られなかったことによる財政難があった。元老井上馨などは、グリスコムに「この好機会を逸せしむるようでは愚の極である」とまで語った。財界も大御所の渋沢栄一が支持した。 裸一貫からアメリカを横断する鉄道網を作り上げた。1905年8月、クーン・ローブ・グループの代表として来日。(満鉄の経営についての話し合いが目的) ◆ハリマンは戦時公債500万ドルの引き受け手でもあったから、話はとんとん拍子に進み、10月12日には、南満州鉄道に関する日米シンジケートを組織する予備協定覚書を交換し、意気揚々と帰国の途についたハリマンだったが、太平洋上ですれ違ったのが「ポーツマス講和会議」の日本全権小村寿太郎だった。〈中略〉こうした背景があって、小村も強硬にハリマン案に抵抗、葬り去ることができたが、その結果、南満州鉄道が日本の独占経営となったことで、ルーズベルトのあとを襲ったタフト政権が期待した満州の門戸開放は実現されず、日米関係は悪化したまま、アジア太平洋戦争へと突入していく大きな端緒となった。 ◆1905年の「ハリマン構想」は挫折し、日本政府の恩を仇(あだ)で返すような態度にヤコブ・シフは激怒し、その怒りを高橋是清にまでぶつけた。しかし、シフはほかの取り引きで見せたように、決してあきらめなかった。 ◆1909年春、ハリマンは再び動いた。3月、ルーズベルトに代わってウィリアム・タフトが大統領に就任すると、アメリカの対日政策は、反日に変わった。タフトは、ハリマンの娘婿ウィラード・ストレイトを東アジア部長に任命した。タフト政権の東アジア政策に中心的役割を果たしたのは国務次官のウィルソンとストレイトだった。ウィルソンは、満州の門戸開放を持続させるための唯一の方法は日本に対し、強圧をかけるほかないと確信していた。ストレイトは、旧来の政策では、満州でのアメリカの未来は暗く、アメリカ製品の市場拡大には満州に鉄道建設と資源開発の大規模投資をすることが必要だと主張した。ハリマンは自己の経済的目的のため南満州鉄道を支配しようとしたが、ストレイトの場合はさらに、国際戦略の見地から、アメリカ資本を満州へ投入する図を描いたのだった。◆タフトは、国務長官にノックスを選任した。1909年12月、ノックスは、満州における列強の鉄道権益を清国に返した上で列強の共同管理にするという南満州鉄道中立化を提案したが、戦後に協調に転じた日本とロシアの反対で成立しなかった。敗戦により目を東から西に転じたロシアと日本の協商体制が進むなかで1910年、アメリカは5000万ドルの借款を清国に与え、英独仏と4ヶ国借款団を組織、強力なドル外交で日本に対抗し、太平洋をめぐる日米両国の覇権争いが激しさを見せはじめる。 ◆ ◆ ◆ ※ 以上、『日露戦争に投資した男 〜ユダヤ人銀行家の日記〜』(新潮社)より |
| ■第6章:「日露戦争」後にアメリカで広まった「黄禍論」
●「日露戦争」は、国際社会のほとんどが大国ロシアの勝利を予想していたにもかかわらず、アジアの小国・日本が勝利した戦争だった。
※ 「奉天会戦」=1905年3月に行なわれた日露戦争最後で最大の陸上戦。
●しかし、欧米人の間では、日本人に対する警戒心が噴出し始めた。いわゆる「黄禍論」(こうかろん)である。 ヴィルヘルム2世の母親はイギリスのヴィクトリア女王の娘だった。そのため彼は生涯、イギリスには好意的だった。しかし、その旺盛な海軍力増強姿勢はイギリスの警戒心を刺激し、イギリスをフランス陣営に追いやることになった。ちなみに、彼の立派な口ひげ(端がピンとはね上がった口ひげ)は「カイザー(皇帝)ひげ」と呼ばれた。彼は科学技術の進歩に大きな関心を持ち、学術団体「カイザー・ヴィルヘルム協会」を設立して科学者を援助したことでも知られる。 ●このドイツ皇帝は1908年、『ニューヨーク・タイムズ』とのインタビューでこう語っている。「ロシアが白色人種の利害を代表して日本と戦ったことは、誰もが認めている。しかしロシアの戦い方はひどくまずいものであった。ドイツ軍なら日本軍を撃破していたであろう。ロシアが黄色人種に弱点をさらけだした今、今度はドイツが黄禍の拡大に歯止めをかける番になったのだ。我がドイツはアメリカと協力して中国を応援する取り決めを行なったが、これは日本の進出を抑え、極東における勢力均衡を保つためである」。 『黄禍論とは何か』ハインツ・ゴルヴィツァー著(草思社) ●ところでアメリカは、日本が「日露戦争」に勝った直後に、日本を第一仮想敵国とした「オレンジ計画(対日侵攻戦略)」を作成した。(のちの日米戦争におけるアメリカ側シナリオは、すべてこの「オレンジ計画」によるものである。既に日米開戦の30年以上も前から、アメリカは日本を第一仮想敵国と考え、日本打倒のプランを練っていたのだ)。「黄禍論」はアメリカでも広がり、日本人労働者の就職妨害や排斥、学童の隔離教育、太平洋沿岸州議会のハワイからの転航移民禁止などとして具体化し、「排日気運」を激化させていったのである。(=「太平洋戦争」の遠因) 『人種偏見 ─ 太平洋戦争に見る日米摩擦の底流』ジョン・ダワー著(TBSブリタニカ) ★おまけ情報: アメリカの対日圧迫政策について ●この時期の日米関係(摩擦)について、帝京大学教授の高山正之氏は次のように鋭く述べている。参考までに紹介しておきたい。 「セオドア・ルーズベルトを多くの日本人は親日家だと信じている。ホワイトハウスに畳を入れて柔道をやったとか、『日露戦争』では継戦能力のない日本のために講和の労を取ってくれたとか。しかし彼の本音は全く違い、日本を叩き潰すことにあった。そのきっかけは1893年、米国のハワイ王朝乗っ取りだった。米戦艦ボストンがリリウオカラニ女王の宮殿に砲口を向け、彼女を退位させた直後、日本の巡洋艦『浪速』と『金剛』がホノルルに入り、米戦艦をはさむように錨を下ろした。米国の横暴を牽制したもので、米国はハワイの併合を断念、ハワイ共和国という体裁を取った。巡洋艦の艦長は東郷平八郎といい、彼は翌年もホノルルにやってきたが、同共和国の建国1周年を祝う礼砲要請を『その要を認めず』と断った。『錨泊中の他国の艦船も彼に倣(なら)いホノルル港はあたかもハワイ王朝の喪に服したようだった」と地元紙が報じている」。 「共和国は報復に日系移民の帰化を拒否した。東郷の行動を見た米海軍省次官ルーズベルトは1897年3月、友人に『できることなら今すぐにハワイを併合し、ニカラグア運河を完成させ、日本を凌ぐ軍艦を建造したい。私は日本の脅威をひしひしと感じている』と書き送っている。そのために彼は新聞王のハーストと組み、世論を焚きつけて翌98年に『米西戦争』を起こし、グアムとフィリピンを手に入れた。大統領に就任するとすぐパナマを独立させ、運河建設に取りかかった。脅威の日本人を米国から追い出す作業も始めた。その1つが、米国に併合を済ませたハワイの日系人の本土移住の禁止措置だ。ハーストの新聞も一役買って反日キャンペーンを展開する。『日本人は怠け者で売春や賭博にふける』とか『白人の知恵を盗む』とか『貯蓄して米社会に還元しない』とか思いつく悪口をすべて並べ立てた。結果、日系人の子弟は学校から締め出され、土地所有を禁じられ、市民権の取得も拒否された」。 「しかし駐米大使の珍田捨己は米国人の善意を信じることから始めた。 〈中略〉 『まず相手を信じ、反省する』──この珍田方式が以降、日本外交の基本姿勢となる。そんな馬鹿をしているからロシアから一銭の賠償も取れない講和を押し付けるルーズベルトを本気で『恩人』と思ったりする。ルーズベルトの思いは一つ。米国にとって脅威の日本が賠償獲得でより強力にならないようにすることだった」。 「彼を継いだウッドロー・ウィルソンは日本を弱体化するために国際社会からも締め出そうとした。彼は第一次世界大戦の『パリ講和会議』で五大国委員会を解散し、日本を追い出して英米仏伊の四ヶ国委員会にして日本の発言力を弱め、彼の後を継いだハーディング大統領は『ワシントン会議』で日英同盟を破棄させ、日本を孤立に追い込んだ。しかし当の日本は、ウィルソンはいい人で、この会議も海軍の軍縮会議だと今でも信じている。 〈中略〉 『相手国の善意』を信じた珍田外交が、日本を滅ぼしたことを忘れてはなるまい」。 1919年、第一次世界大戦の戦後処理を行なうために開催された「パリ講和会議」で、日本は「人種差別撤廃」を強く提案した。人種平等の理想論には表向き反対できないので、投票の結果、過半数の賛成を得られた。ところが、議長のアメリカ大統領ウィルソンは、イギリスと組んで、このような重要な決定は、全員一致でなくてはならないと難癖をつけ、可決したはずの提案を否決してしまった。植民地を多く持つ白人列強に都合が悪いからであった。日本の提案の成功を心待ちにしていた、世界中の多くの植民地民族は、「否決」と聞いて、改めて白人の横暴を非難し、日本に同情した。この「パリ講和会議」において盛んに強調された「人権」「民族自決」という考え方自体がそもそも「白人」を対象としたものであり、有色人種は始めから埒外に置かれていた当時の状況を伝えるエピソードである。 ●「ハーバード大学国際問題研究所」の研究員で、現在、国際政治学者として活動している藤井昇氏は、次のように述べている。「アメリカが国際政治に、一人前のプレーヤーとして登場するのは、セオドア・ルーズベルトが日露戦争の仲介を買って出た『ポーツマス講和会議』(1905年)をもってである。これ以前のアメリカは、ヨーロッパ各国から国際政治上の一人前のプレーヤーとは見られなかった。そして、第一次大戦で疲弊したヨーロッパを横目に、第一次大戦後の世界でアメリカは大国の地位を揺るぎのないものにしていく」。 「日露戦争直前に結んだ『日英同盟』(1902年)は、戦争に実に有効に機能した。バルチック艦隊の長路の日本遠征では、途中のイギリス領関係の港での寄港を拒否、妨害され、食料補給、給水などに支障をきたした。これは、ロシア軍にとっては大変な痛手となった。日露戦争後、日本を仮想敵国とする戦略を明確にしていたアメリカは、友邦のイギリスを日本から切り離しておかねばならないと考えた。そこで『ワシントン会議』を機に、『日英同盟』の廃案を両国に迫った。日本政府は反対したが、イギリスはすでにその使命が終わったとして、アメリカの提案に賛成した。その頃から、米英は協力して日本の勢力拡大を抑える反日の姿勢を明らかにしていったのである」。 「アメリカの日本叩き、日本いじめ政策の第一弾が、1924年の『排日移民法』の制定である。元来移民歓迎を国是とする移民受け入れ大国が、日本移民だけを締め出したのである。さらに日本の在米資産を凍結する挙に出た。後に昭和天皇は後日談の中で、この『排日移民法』の制定が大東亜戦争の第一の遠因であると述懐されておられるほどである」。 第一次世界大戦後の1921年、アメリカのハーディング大統領の提唱で ワシントンで開かれた国際会議。この会議によって「日英同盟」が破棄され、東アジア太平洋地域での新たな国際秩序となる「ワシントン体制」が発足した。この会議により形成された体制は、ヨーロッパの「ヴェルサイユ体制」と並んで、第一次世界大戦後の国際秩序を確立することになった。この会議を主催し指導したアメリカは外交的勝利を収め、国際的指導者の地位についた。★この会議は国際社会の主導権がイギリスからアメリカに移った会議であった。 |
|
■第7章:ヤコブ・シフと高橋是清の死 ●「ハリマン事件」後、少しギクシャクする時期があったが、ヤコブ・シフと高橋是清の交友関係は続いた。ヤコブ・シフは終生、高橋是清と家族ぐるみで親しく交わった。高橋是清の長女のわき子を、ニューヨークの自宅で、3年間にわたって預かったほどだった。 ●高橋是清は82歳の時(1936年)に「2・26事件」で青年将校達に射殺(暗殺)された。ヤコブ・シフはその16年前(1920年)に、73歳で没していた。この2人の死によって、日本とユダヤの関係は“新たなステージ”を迎えることになる……。 ●参考までに、前出の渡部昇一氏(上智大学名誉教授)は、高橋是清の死について次のような興味深い意見を述べている。「明治の日本が日露戦争のときに得たユダヤ・コネクションを、もしも上手に活用していれば、日本には重要な情報がたくさん入ってきただろうし、またユダヤ資本と協力してさらに産業も大きくできたかもしれない。たとえば満州の重工業にユダヤ資本を参加させていたら、イギリスやアメリカの満州国に対する態度は、別のものになっていたはずである。だが、現実はまったく逆であった。戦前の軍部は、ユダヤ人を迫害したナチス・ドイツと同盟を結んでしまった。これでは日本の運命が悪くなるのも当然と言わざるをえない。 1940年(昭和15年)9月、日独伊三国同盟が締結された。この年の終わり頃、クーン・ローブ銀行の紹介状を持った2人のカトリック神父がやってきた。その目的の一つは、ユダヤ排撃を政策として打ち出しているヒトラーと日本との同盟に関係したものであったに違いない。その時、もし高橋是清が生きていたら、シフの銀行の紹介ということで対応も違っていたであろう。しかし、高橋はその4年半前に2・26事件で青年将校に殺されていたのである。嗚呼(ああ)。 事実、三国同盟締結と時を同じくしてアメリカは蒋介石の重慶政権に1億7500万ドル、イギリスも1000万ポンドの借款を与えているのだ。このカネがユダヤ人と関係しているのは明らかである。蒋介石は外貨に不自由しなくなったのである。対米戦争を始めることになったのも、もとはといえば日本がアメリカから石油禁輸を受け、にっちもさっちも行かなくなったからだが、アメリカ経済に隠然たる力を持つユダヤ人を味方に付けていれば、そこまでアメリカは日本をいじめることもなかったのではないか──今さら悔やんでも仕方のないことだが、私には残念でならないのである。」 (渡部昇一著『まさしく歴史は繰りかえす〜今こそ「歴史の鉄則」に学ぶとき』クレスト社より) ヤコブ・シフの「クーン・ローブ商会」は、1977年に同じドイツ・ユダヤ系の投資銀行「リーマン・ブラザーズ社」と合併した |
|
|
■追加情報 2: 中国戦線のアメリカ軍総司令官は語る 「米国は敵を間違えた」 ●アメリカの孤立主義の指導的代表者だったハミルトン・フィッシュ(元下院議員)は、著書『日米・開戦の悲劇 ─ 誰が第二次大戦を招いたのか』(PHP文庫)の中で、次のような日本を擁護する言葉を残している。「アメリカ国民の85%は、第二次世界大戦はもとより、いかなる外国における戦争に対しても米軍を派遣することに反対していたという現実にも関わらず、ルーズベルトは、欧州戦争の開始当初から、米国は同戦争に参戦すべきであると確信していた。この大戦は、結果として、30万人の死亡者と70万人の負傷者、そして5000億ドルの出費を米国にもたらしたのである。〈中略〉日本はフィリピンおよびその他のいかなる米国の領土に対しても、野心を有していなかった。しかしながら、ひとつの国家として、日本はその工業、商業航行および海軍のための石油なしに存立できなかった。 非常な平和愛好家である首相の近衛公爵は、ワシントンかホノルルに来てもよいからルーズベルト大統領と会談したい、と繰り返し要望していた。彼は、戦争を避けるためには、米国側の条件に暫定協定の形で同意する意思があったが、ルーズベルトは、すでに対日戦および対独戦を行なうことを決意していたというだけの理由で、日本首相との話し合いを拒否した。駐日米国大使であったジョセフ・グルーは、日本がどれだけ米国と平和的関係を保ちたいと希望していたかを承知しており、かかる首脳会談の開催を強く要請した。しかしルーズベルトおよびその側近の介入主義者たちは、策謀とごまかしとトリックを用いて、全く不必要な戦争へ我々を巻き込んだのである」。 ※ ハミルトン・フィッシュ自身は「孤立主義者」という言葉は、ルーズベルトがプロパガンダのために捏造した、不正確な表現で、本当は、自分は「不干渉主義者」だと言っている。 ◆ ●ところで、第二次世界大戦の「中国戦線」のアメリカ軍総司令官で、蒋介石の軍事顧問を兼任したアルバート・ウェデマイヤー大将は、戦後に出した『回想録』の中で「米国は敵を間違えた」と述べている。参考までに紹介しておきたい↓ 「ルーズベルトは中立の公約に背き、日独伊同盟を逆手に取り、大日本帝国に無理難題を強要して追い詰め、真珠湾の米艦隊をオトリにして米国を欧州戦争へ裏口から参加させた。 〈中略〉米英は戦閾には勝ったが、戦争目的において勝利者ではない。英国は広大な植民地を失って二流国に転落し、米国は莫大な戦死者を出しただけである。真の勝利者はソ連であり、戦争の混乱を利用して領土を拡大し、東欧を中心に衛星共産主義国を量産した。米国は敵を間違えたのだ。ドイツを倒したことで、ナチス・ドイツ以上に凶悪かつ好戦的なソ連の力を増大させ、その力は米国を苦しめている。また日本を倒したことで、中国全土を共産党の手に渡してしまった。やがて巨大な人口を抱える共産主義国家がアジアでも米国の新たな敵として立ちふさがるであろう」。 |
|
■追加情報 3: アメリカも第二次世界大戦の敗戦国 (勝者は毛沢東とスターリンだけ) ●『新・文化産業論』や『失敗の教訓』など数多くのベストセラーを世に出している日下公人氏(東京財団会長)は、日中戦争の実態について、著書『人間はなぜ戦争をするのか』(三笠書房)の中で、次のように鋭く述べている。参考までに紹介しておきたい。 「日本と中国は1937年以降、戦火を交えていたが、大日本帝国も中華民国もお互いに『宣戦布告』をしていなかった。なぜか?あまり人の知らない事情を言うと、当時アメリカには『中立法』があって、交戦国に対する融資や武器輸出を禁じていた。交戦国の旅客船にアメリカ人が乗船することも禁じていた。第一次世界大戦の時、ドイツ潜水艦が撃沈したイギリス船ルシタニア号にアメリカ人の乗客が数百人いて、その被害が戦争参加原因になったという反省から議会が設けた“しばり”である。したがって、日中両国はもしも宣戦布告をすると、アメリカから武器を輸入できなくなる。同様に、日中両国からの大量注文で大不況からの立ち直りを果たしつつあったアメリカの武器メーカーも困る。実際、ボーイング、ロッキード、ダグラス、カーチスなどの航空機メーカーは日中戦争のおかげで倒産寸前を助かっている。だから、アメリカは支那事変を戦争とは認定せず、武器輸出を続けた。しかし、アメリカは戦後の東京裁判ではこれは『侵略戦争』だと日本の責任を追及した。アメリカは矛盾していると中村粲氏は『大東亜戦争への道』(展転社)に書いておられる。そのようにアメリカは日本の軍備拡張を援助することで利益を上げながら、他方、日米交渉では日本が飲めないような強硬条件を突きつけて、日本が対米戦に立ち上がることを期待していた。そして1941年が暮れる頃、ついに12月8日がやってきて、日本はパールハーバーを急襲し、その日以降、アメリカは晴れて戦争ができるようになったのである。 〈中略〉ちなみに、イギリスのチャーチルは、日本がパールハーバーを攻撃したとの報を受けて大喜びした。これでアメリカはイギリスの側について戦ってくれることがハッキリしたから、この戦争は勝利でイギリスは救われたと思ったのである。その夜、チャーチルは感謝に満ちて眠ったという」。 「ところで、1937年の時点で、世界で最もファシズム路線の国は中華民国である。蒋介石が一番ファシストだった。ヒトラーもムッソリーニも、その当時の蒋介石に比べれば、ファシストとしてはまだまだ可愛いものだった。だから、アメリカの上下両院は、蒋介石を連合国陣営に加えることに大反対した。この戦争は軍国主義に対する戦いなのに、蒋介石はファシストではないか、というわけだ。蒋介石はそれを知って、宋美齢夫人を派遣して、『日本のほうがもっと軍国主義である。弱い中華民国を助けてくれ、私の夫を助けてくれ』とPRした。その費用は、アメリカからもらった対中国援助の中から払った。宋美齢はPRのためのパーティーで、参加者に中国の高価な書画骨董をはじめ、いろいろなものをプレゼントした。アメリカの税金で、アメリカの国会議員を買収していた。日本にしてみれば、宋美齢一人にやられたようなものである。ロビーイングの元祖はマダム・チャンなのである。 〈中略〉 」。 「……アメリカもまた、第二次世界大戦で国益を見失っていた。ドイツと日本に勝つことに執着したが、勝利の結果は、かえって大きな負担を背負いこむことになった。アメリカは、日本を占領して初めて、日本が明治時代からしていたのは南下してくるソ連(ロシア)を食い止めることだったと知った。日本は、中国大陸や朝鮮半島がロシア化または共産化することを懸命に防いでいた。そのおかげでフィリピンがアメリカのものになった。その日本をアメリカは後方から攻撃したのだから、これほど愚かなことはない」。 「戦争が終わり、アメリカは日本を武装解除して“平和第一主義”を教えたところ、日本人は大喜びして、日本は本来の平和愛好国になった。その結果、ソ連の南下を食い止めるのはアメリカの仕事になって、朝鮮戦争では日本の代わりにマッカーサーが38度線で戦って、200億ドルの戦費と3万5000人の損害を出した。さらにマッカーサーは38度線を確保するため、北上して平壌を陥とし、鴨緑江まで進出するが、これはかつて日本がしたことと同じである。アメリカは日本に対して、それを『大陸への侵略』だと言ったが、自分も同じことをするハメに陥った。アメリカが中国国境に迫るのを見た中国は、“抗美援朝、保家街国”(アメリカに対抗し、朝鮮を援助し、家や街や国を守る)のスローガンで18個師団を送り、米軍を押し戻してソウルを奪還した。そこで頭にきたマッカーサーは、『原子爆弾約20発、中国とソ連の都市に使いたい』と言ったら、トルーマンに解任されてしまった。このように、昔は日本がやっていたことを、アメリカが引き継がなければならなくなったので、『ルーズベルトの戦争目的は、日本の代わりにソ連と戦争することだったのか』という批判が出てしまった」。 「アメリカが日本と戦争したのは、実は中国貿易の利権を手に入れるためだった。戦争が始まる前、中国にモノを売っている国は、イギリスと日本だった。そこへ参入したかった。当初は、門戸開放・機会均等のスローガンを主張していたが、やがてエスカレートして、日本は中国から手を引け、ということになった。そこで日本を追いつめて全面戦争をしたが、この戦争目的は達成されなかった。戦争が終わって中国を手に入れたのは、アメリカが支援した蒋介石政権ではなく、ご存じのとおり毛沢東政権だから、アメリカは日本との第二次世界大戦ではくたびれもうけの惨敗である。この意味ではイギリスも負けている。中華民国も同じで、第二次世界大戦で勝った国は、毛沢東の中国共産党とスターリンのソ連だけだったと言える」。 ※ 以上、『人間はなぜ戦争をするのか』日下公人著(三笠書房)より |
|
■追加情報 4: ホロコーストに匹敵するスターリンの「国家犯罪」 ●ソ連のヨシフ・スターリン(グルジア人)は、一応、有能なユダヤ人を将兵として重用してはいたものの、他方では虐殺や粛清の手をゆるめようとはしなかった。ユダヤ人であろうと非ユダヤ人であろうと、スターリンにとって自分を否定するものは誰もが敵となった。スターリンの粛清は1934年の党幹部の暗殺をきっかけに始まった。「狂犬は殺せ」のかけ声のもと党の幹部たちが次々に刑場へ消えていった。共に戦ってきた同志を次々に抹殺していった。スターリンは自らの偉大さをアピールし、正当化することが仕事となった。モスクワはいたるところ、スターリンの肖像画、彫像で覆われていった。自分の前に神があってはならなかった。宗教儀式は禁止された。
●粛清はクレムリンからロシア全土に広められ、ユダヤ人、外国人、知識人たちが次々と「敵」の烙印を押されていった。全土に200もの「強制収容所(ラーゲリ)」が作られ、無差別に大勢の人間が逮捕され、理由もなく処刑された。助かったものには強制労動の生き地獄が待っていた。全土に監視と密告制度が、網の目のように張りめぐらされていった。知らないうちに人が消えていった。家庭の中でさえ密告が横行し、人々は疑心暗鬼になった。 ●ポーランドで生活していたユダヤ人メナヘム・ベギン(のちのイスラエル首相)は、1940年9月、リトアニアのビリニュースにいたところをソ連の秘密警察に逮捕され、ルキシキの牢獄から極北ペチョラの収容所へと辛苦の遍歴生活を送った。(1941年に独ソ開戦にともなって、その冬、ポーランド市民に特赦が発せられ、彼は釈放された)。彼が書いた『白夜のユダヤ人──イスラエル首相ベギンの手記』(新人物往来社)という本は、彼が「ラーゲリ」で体験したことを赤裸々につづった自伝的回想録である。興味のある方は一読を。 ●第二次世界大戦中、ソ連在住のユダヤ人のうちほとんどはシベリアに連行された。15%以下がドイツ軍の手に落ちた。赤軍中で、あるいは「強制収容所」で少なくとも100万ものユダヤ人が死亡した。最近の研究によって、スターリンもまたヒトラーと同じように、ユダヤ人問題の「最終的解決」を図ろうとしていたことが明るみに出ている。つまり、スターリンはユダヤ人たちの集団流刑の計画を立てていたのである。トルストイの子孫である作家ニコライ・トルストイは、その著『スターリン』の中で次のように述べている。「1953年には、各大学からユダヤ人の徹底的な追放が行なわれた。そしてとどのつまり、スターリンはユダヤ人問題の最終的解決を準備していたのであった。ロシアのユダヤ人は、すべて北カザフスタンの荒野に放逐されるはずであった。スターリンの死によって、初めてこのヒトラーばりの課題の完遂は妨げられたのである」。◆ ●第二次世界大戦中、占領されたドイツや東欧諸国の捕虜や市民も、スパイ容疑で無差別に根こそぎ連れ去られた。ソ連軍に占領された地域は、ソ連兵によるレイプ・略奪の地獄絵図となった。レイプはソ連軍が1944年に東プロシアとシレジアに入った時に始まった。多くの町や村では10歳から80歳までの全ての女性がレイプされた。女性はソ連兵に見つかり次第レイプされた。町のいたるところにレイプされ斬殺されたドイツ女性の死体がころがった。進軍するソ連軍部隊は、強制収容所においても、ドイツ女性と同様、ものすごい数のロシア女性、ポーランド女性をレイプした。スターリンと彼の司令官たちは、レイプをドイツ女性ばかりか、同盟国のハンガリー、ルーマニア、クロアチアの女性に対しても許すか、正当化さえしたのだ。 ●ソ連軍がベルリンに突入して制圧した際、スターリンは兵士に対し「ベルリンはおまえたちのものだ」といい、3日間の“祭り”を許可した。ベルリンのドイツ女性のほとんどがソ連兵によってレイプされ、連合軍に届けられたものでも10万件を越えた。また暴行による自殺者は6000人を数えた。レイプの規模は、1945〜48年の間、毎年200万のドイツ女性が非合法に妊娠中絶した事実から暗示される。ドイツ全体で少なくとも200万のドイツ女性がソ連兵にレイプされた。ソ連軍の強姦率は80%だった。ソ連当局が病気のまん延を心配し、敵との親交に対し、東ドイツにいるソ連軍兵士に重罰を課すようになったのは、1946年から47年の冬になってからのことであったという。 ●1945年8月9日、スターリンは突如「日ソ不可侵条約」を破って日本に戦争を仕掛け、北方領土を奪い、満州に侵入した。この満州でもソ連軍はレイプしまくった。日本の連合軍への降伏により、日本軍は38度線を境に、南鮮はアメリカ軍、北鮮はソ連軍へ降伏するように指令された。南鮮の日本人は終戦の年の暮れまでにほとんどすべて引き揚げたが、北鮮では31万の日本人がそのまま残っていた。もともと北鮮に住んでいた27万と、満州から戦火をさけて逃げてきた4万人である。北鮮にはいってきたソ連軍は、満州におけると同様、略奪、放火、殺人、暴行、レイプをほしいままにし、在留日本人は一瞬にして奈落の底に投じられることになった。白昼、妻は夫の前で犯され、泣き叫ぶセーラー服の女学生はソ連軍のトラックで集団的に拉致された。反抗した者、暴行を阻止しようとした者は容赦なく射殺された。虐殺・餓死・凍死などで無念の死を遂げた民間人は20万人にも達した。
●また、ソ連は60万人にものぼる日本人を捕虜にして連行し、極寒のシベリアで強制労働をさせ、7万人近くを死亡させた。(※ 最近の研究によれば、シベリア抑留者は100万人を超え、そのうち40万人が死亡したという)。 ●1997年11月6日、モスクワ放送は「10月革命の起きた1917年から旧ソ連時代の1987年の間に6200万人が殺害され、内4000万が強制収容所で死んだ。レーニンは、社会主義建設のため国内で400万の命を奪い、スターリンは1260万の命を奪った」と放送した。旧ソ連のノーベル文学賞作家アレクサンドル・ソルジェニツィーンは、この膨大な「強制収容所(ラーゲリ)」の群れをいみじくも「収容所群島」と呼び、その恐るべき実態を明らかにしている。ソルジェニツィーンによれば、囚人の総数は1500万人に達する。もっとも4000〜5000万という説もあるが、実数はもはや確かめようにない。規模の大きさからいって、ドイツのホロコーストに匹敵する「国家犯罪」であることは確かだ。だがホロコーストへの糾弾に比べてスターリンの「強制収容所」の犯罪が追及されないのはなぜだろうか。理由ははっきりしている。アメリカの原爆投下の犯罪が糾弾されないのと同じで、ロシア(旧ソ連)は“戦勝国”だからである。 ■関連記事(リンク集) ◆日米開戦の真相 ── 歴史学の権威であるチャールズ・ビアード博士は語る。「戦争責任を問われるべきは日本ではなく、ルーズベルト大統領だ」 ◆反日の「民主党」のF・D・ルーズベルト大統領は日本へ18発もの原爆投下を承認していた。しかし「共和党」は日本との戦争にも反対し、分割占領にも反対していた。http://www.geocities.jp/tqovopy/TORAshi.htm ◆1941年・幻の東京空爆計画 〜日本を敗戦に導いた宋美齢の生涯〜 ◆アジアにおける最新の侵略国は「英・米・仏・蘭」の諸国
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)