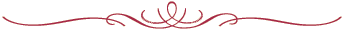
| 第7節、「世界の新聞統制」(国際ユダヤ祕密力の世界新聞統制) |
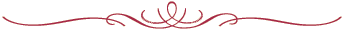
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 愛宕北山氏はここで、「世界の新聞統制(国際ユダヤ祕密力の世界新聞統制)」の考察に向っている。様々な角度からこれを論じており、傾聴に価する話が満載でありそういう意味でも貴重である。 2006.1.17日 れんだいこ拝 |
| 新聞の使命 |
| 新聞は言うまでもなくあらゆる国民の言葉の拡声機であり、世界の眼ないし耳であり、またいわゆる輿論の担い手であり、世界に於ける出来事の焦点を成すのみでなく、空間を超えて人間と人間の間を仲介する役目をもつ。それは政治的地平線にかかっている雲の動きを記すと共に、諸国民の日光を録するが故に、一つの大きな権力と認められねばならない。新聞は単に国民生活に於てばかりでなく、国際的生活に於ても亦前代未聞の有力な政治的機関と認められざるを得ない。総ての大事件に対する諸国民の政見は、新聞を通じて発表されるので、今日ではそれは、世界政治界のバロメーターと呼ばれることが妥当であろう。即ちこれなくしては全然政治を行い得ないし、このバロメーターの針位と振幅とは、世界中の最近二、三十年にわたるあらゆる内閣に対して、世人のよく察知し得ない程に大きな影響を及ぼして来たのである。
そもそも世界の政治家の中で新聞界から出た者が如何に多いことか! また今日新聞を読まない政治家が何処にあるか? 果して彼らのうちで新聞の影響を脱し得るものが幾人あるであろうか? 今日新聞の持つ意義は、人が欲すると欲せざるとに拘らず、どうしてもそれを認め且つ尊重せざるを得ないところにあり、また新聞自身もこの点を大いに誇としているのである。しかしながら新聞がこの意義ある地位を保ち続け得るのは、言うまでもなくそれが、自分自身面目を汚さず、また醜汚な仕事によって自己の名誉を損傷しない時に限るのである。それ故に新聞は、何よりも先づ真実の報道を以てその生命としなくてはならない。不真実は常に必ず新聞の最大の恥辱である。新聞の力は一にかかって真実という地盤の強弱に存するのである。 ところが新聞に與えられているこの力こそは、実はそれに極めて困難な責任を課しているのであって、その故は、この真実といい真理というものが決して善悪の彼岸にあるものではないからである。この力は必ず国民の安寧と幸福及び人類の福祉の為に利用さるべきものであり、万一にも間違って用いられるならば、たちまち国民と人類との不幸と破滅とを招来する恐るべき力に変ずるのである。従って私的のものであれ、超国家的なものであれ、ある祕密力が、ジャーナリズムの精神的威厳を支配するに至るや、新聞はそれに応じて世界の危険物となり、一国民人民の内政生活のみならず、結局のところ世界平和にとっても一大危険物と化するのである。 新聞がそのうちに内蔵しているこの危険は、実に今日に於ては世界政治的意義を有する大問題と化しつつあり、その解決が遲れれば遲れる程、この危険も増大して来る。なるほどこれまでも責任感ある政治家や新聞人が、この危険について多く書いたり語ったりしなかった訳ではない。しかし遺憾ながら彼らの声は聞き逃され、単なる沙漠の説教に終ったのである。世界新聞界はこの問題になると多くは沈默を守るし、「輿論の政府」と自称する民主主義国家も新聞の有するこの危険に対して戦いを挑む勇気は持たないのである。それは新聞界そのものがある国際的祕密力に依って支配されている上に、いわゆるデモクラシー国家に於ては政府自身がその新聞界に依存しているからである。 かく見て来ると、これら諸国の政府及びこれら新聞の読者は、少くともこれまでの所では、真の平和の敵でありまた現代に於て最も危険な戦爭煽動者でありまた世界輿論の毒薬処方者であるところの新聞背後の祕密力というものに対しては、全然盲目であったと言われねばならないのである。 我々もまたかかる危険力に対して口を緘(とざす)べきであらうか? 否、世界新聞界の破壞力が人類の災厄となった今日に於ては、我々はこの暴状に対して敢然と戦わねばならない。そしてそれは単に国民又は平和の為のみではなくて、責任感を持つ新聞とその当事者とに途を拓き與へ、その勇気と道義力とを鼓舞し、且つ一般に真理の伝播を容易ならしめんが為である。しかもこの困難な課題を解決し得るのは、あらゆるユダヤ及びフリ−メイソン祕密結社の迫害に抗しつつ人類の新時代の為に戦いつつある防共諸国のみである。防共とは実に反ユの別名であり、排フリ−メイソン結社の異名であるからである。 上述の事情は、言うまでもなく、日本に於ては多少とも異ったところがある。しかし現代に於ては、通信交通機關の発達の結果として我が国の新聞界が世界のそれと全く絶縁状態にあることは不可能である。殊に日本の新聞にも、毎日外国電報が現われるのであるから、真に国を思う者は、新聞当事者たると否とを問わず、充分の反省と自覚が必要であると思われる。 |
| 新聞検閲の歴史 | ||||||||||||
| 1479年と言えば、かのグーテンベルグが印刷機械を発明してから間もなくのことであるが、この年にケルンの大僧正はローマ法王に申請して、一定の出版物の発行人・印刷者・著者及び読者に対して教会上の刑罰及びその他適当の方法によって干渉を加える特権を得た。更に1486年にはマインツのベルトホルト大僧正が自分の教区を取締る特別の検閲委員を任命したし、1501年には、法王アレキサンデル第六世が、爾後「厳格なる信仰に背馳し、神をなみし、人心を怒らす如き」言葉を印刷に附することを禁止するという布告を出した。かくて新聞の検閲なるものは、初めは俗界からではなく教会側から提起されたのであり、之が俗界側の政治的檢閲に法律的根拠を齎(もたら)したのは、1524年のニュルンベルグの国会の時のそれを以て嚆矢とする。そしてその条文には、「当局は必要に応じて印刷物その他を検査し、爾後誹謗文及び誹謗畫等を悉く駆逐し、その伝播弘布を抑止すべし」とある。
古い文書に徴すると、既にトルコ戦争の頃、無道な物語作家の類が跋扈し、毒筆を揮って既成秩序の破壞を企てたので、彼らは町から町に逃げ廻らねばならなくなったそうであるが、その際には教会団体は何れも密告者の役を引受けていたらしい。フリードリヒ大王が「新聞紙は面白きものたる限り、妨害されてはならぬ」と言った言葉はよく彼の自由主義を示す材料として引かれるが、しかし同じ大王が、その三年後即ち1743年7月9日に、新聞の自由を内閣条令によって撤回したことはもっと重大に取扱われねばならないであろう。その条例には、「ベルリン諸新聞の発行者達は、検閲用見本刷を要せずという自由権を悪用し、諸種の虚報を載せ、外国に不快の感を與へたるを以て、王は命を下して、檢閲用見本刷なしに新聞を印刷する自由を撤廃し、予め有識の権威者をして檢閲をなさしめ、その裁可を経ざれば発行するを得ざらしめんとし給う」と書かれているのである。 これによれば、フリードリヒ大王は如何に巧に新聞を行政のために利用し、又それに干渉を加えたかが察知せられる。大王は、1767年、ベルリン市に新しく戦争の噂が流布した時、ベルリンの新聞に命じて、ポツダムを襲うた強烈な暴風雨に就いて次の如き報道をなさしめている。
実際の所、ポツダムでは風も吹かず、雹も降らなかった。そしてベルリン人は兔に角新しい噂の種を得て戦争の恐怖を忘れてしまった。とにかく老フリードリヒ大王は、上掲の内閣条令によっても解るように、言論の自由に就いては苦い経験を持っていたのである。1772年4月7日に彼はフランス人ダラムベールに宛てて次の如くに書いた。
ところが、かく新聞に批判的態度をもって当ったのはフリードリヒ大王だけではなく、当時の有名な国法学者クリスティン・フリートリッヒ・ダニエル・シューバルトの如きも言論の自由(彼によればむしろ言論の厚顏無恥)の乱用に反対した一人である。彼はしばしば報道の信用し難き点と矛盾を難じ、いわゆる「……なる由」なる言葉を嘲笑して、それはつまり風評と虚僞との境目が明かでなくなったとき新聞記者が縋り付く尻尾であり、百口ある怪物に他ならない、と言っている。また新聞の虚僞は物語の国に篭っている真っ黒な渡り鳥にも比すべきである、と彼は言い、オランダのパンフレットや小册子や新聞雜誌がこの国に起った暴動に大きな関連を持つことを指摘し、更には、パリの書籍検閲が頗る厳重に行われているのを喜んで、次の如くに総括している。
以上二人の言葉によって我々の知り得ることは、デモクラシーが声を大にして、人類の神聖な財であり又新聞の発展のためのかけがへのない原動力であるとして讚美する「言論の自由」なるものが、しばしば事実に於ては有恥有害なる空辞の最たるものであり、自由なる美名の下にかくれて輿論を毒する恐るべき害物であることである。 而してこの言論の自由の出発点は、1789年のフランス革命に外ならない。同年8月26日のいわゆる「人権宣言」の第6條には、
と書かれている。 同樣の考は少しく制限を受けているが、1791年のフランス法第12条にも規定されている。
このような立派な公告があるにも拘わらず、仏国では、法律上言論の自由が保証されていた時代に、政治的権力者の嫌う新聞には重い圧迫が加えられた事実がある。1789年にマレー・デュ・パンはその主宰する「メルキュール・ド・フランス」誌に次の如く書いている。
1793年3月8日の憲法会議で一人の議員が、「ジャーナリストには決して全権を與へてはいけない。彼等は立法者が仕事をする空氣を毒するだけである」と主張したことがあるが、之が言論の自由の本場と称せられるフランスの出来事である。更に4年後パリで起った補欠選挙では、ジャーナリストは候補者となり得ない、とされたその時の憲法会議で或る演説家は、「世人は須らくジャーナリストを淫売婦と同視すべきであって、その故は、彼等はこの女達と同じく周旋人を有し、買手を探すために道路を駆け拔け、また公の健康を毒するからである」と言っている。 それ故にナポレオンが、クーデターをやった後に出版界にも手を下したのは、別に怪しむに足りないことであらう。
彼がセント・ヘレナ島で最後を遂げる直前に語った後人への戒めには、「新聞をそのままにして置くことは、危険の側で寢を取るにも等しい」という語があったと云われている。 しかし彼の時代はこの戒めを余り省みなかった。新聞は政治的立憲主義と工業的経済の進歩とにつれて大きな躍進をとげ、遂にその黄金時代に達したのであった。 かくて新聞が無限な経済的自由をモットーとして、正規の取引業に発展するに至ったので、ことにユダヤ人は民衆の安寧のために戦ういう仮面の下にかくれて大役を演じるに至った。新聞は政治的党派の奴隸、その背後に隱れている黒幕たる祕密力の奴隸に墮してしまった。編輯部には今や、一番多くの報酬をくれる者のために筆を用いる器用な多筆家が登場し来たり、仏国政治家ネットマンの如きは既に前世紀の始めにあたって次の如く難じている程である。
1835年8月22日に仏人ラマルティーヌは下院で論じて曰く、
文豪バルザックはもっと鋭犀に当時のの新聞界の状況を描いている。
またフランスの新聞人エミル・ドゥ・ジラルダンは1827年に、彼の新聞「ル・ヴォルール」の発刊を予告した文の中で、率直に次のように書いている。
以上は何れも当時の人々が、いわゆる言論の自由に就いて懷いていた見解を並べて見たものである。 |
| 新聞の商業化 |
| 新聞の商業化といふ現象はユダヤ人の仕事として18世紀の末から19世紀の初頭にかけて始まって来たのであるが、その結果として新聞は二重の役目を演ずることになり、精神的政治的要素であると同時に一種の商品と化したのであるが、この事情は、新聞をして諸国民を結合する力としての位置から転落せしめて、人類の災厄にまで下落せしめるに至ったのである。
近代新聞の動向を規定するのは報道と広告との二つである。そしてこの二つの入口から、かの恐るべきユダヤ及びフリ−メイソン結社の祕密力が「言論の自由」なる仮面を被って侵入し来たり、世界新聞界をば今日の如き精神的並びに道徳的危機に追い込むに至ったのである。前世紀の中葉に於て広告税と公用広告機関が撤廃せられた結果として、殆ど凡ての国に於て政治新聞に広告を載せ得るようになったし、従って国民の商業的関心と精神的政治的要求とを新聞によって結合しようという傾向が著しくなって来た。また広告依頼者の信用を得るために読者層を増大しようとしてあらゆる手段が講ぜられ、新聞の購読料は印刷代以下に引下げられるに至った。1836年7月1日に仏人ジラルダンは「ラ・プレス」紙を発刊したが、その購読料はその当時の相場の半値であった。では、かくして出て來る欠損が如何にして埋められるかと言うに、それは広告を殖やす他に道はないのである。 ジェームス・ゴルドン・ベネットは1835年に米国に於てニューヨーク・ヘラルド紙を創刊したが、彼はそれを只の1ペニで売った。しかし実際には、一部3ペンスないし4ペンスかかっていたのである。英国では1855年に、新聞税と広告税との撤廃後のこと、ヨーゼフ・モーゼス・レヴィが最初の「1ペニ新聞」たるロンドン「デーリー・テレグラフ」を発刊したが、他方ヴィーン市でも既に1848年にアウグスト・ツァングが「ディ・プレッセ」紙を発刊して、ジラルダンの例に倣って、相場の半値で売った。爾後新聞の讀者は印刷用紙代だけも支払っていないことになり、従って文字通りの不払い所得として贈られる通信や報道の部分は、匿名の金主が新聞を支えてくれるのでなければ、広告代によって経済的に補填される外に道はないのであった。 |
|
新聞の買收 |
| かくて遂には色々の方面から買收の可能性が生じて来たが、これはかの国際ユダヤ人及びその支配下にあるフリ−メイソン結社に取っては誠にお誂え向きの活躍舞台であった。ユダヤ人の破壞力が新聞に侵入した第二の門は近代の通信機関の発展である。新聞が資本主義に従属するに至ったが為に輿論もまた金力で動かされ得るものとなり、通信組織は乱用されて、新聞のデマ記事が国民生活の中に食い入るようになった。現代に於ける世界通信網の歴史を辿って見る時、我々は驚くべき連絡と組織とに当面するのである。
現代の新聞通信機関の起源はかのユダヤ人の取引所であるから、現代の組織化された虚報通達による新聞の悪用というものはすべてユダヤの商売根性の発現したものである。現代の通信組織は、自分に都合のよい通知によって競争者や顧客から出来るだけ物質的な利益を搾取しようとする商業本位のユダヤ人の手に握られている実験室である。 その好例をあげれば、ロンドンのユダヤ人ネイサン・ロスチャイルドのあの歴史的な「ワーテルローの勝利」である。彼は正に現代新聞虚報の父である。彼の父でフランクフルトにいたマイエル・アムシェル・ロートシエルトもまた相当の腕前があったらしく、郵便局を買收して取引上の敵の手紙を祕かに手に入れ、それを儲け仕事に利用したそうであるから、その息子ネイサンのやり方はつまり父親のやり方を現代化したに過ぎないとも言えないことはない。とにかくネイサンは伝書鳩郵便を使ったり、船長や旅行者を手数料で買收して色々な報道を集めるに役立てた。そしてこの世界中から集まった報知を勝手に利用したり、祕密にしたり、ほのめかして、兔に角彼の取引事業に都合よいやうに細工したのであった。彼の「ワーテルローの勝利」もまたその一例であった。彼は逸早く誰も知らぬうちにワーテルローの決戰の結果を知ってゐて、丁度ロンドンでは未だ一般に半信半疑でいたのを奇貨として、英国及び普魯西がナポレオンに敗戦したとの虚報を伝えた。相場はがたがた落ちた。ロスチィイルドは仲買人を使って出来るだけ株を買込ませたので、ワーテルロー戦勝の正しい報知がロンドンに到着した時には、彼はもう巨大な金を儲けていたのであった。 |
| 虚報の勝利 |
| ユダヤ的資本主義的貪欲に奉仕する新聞虚報は、世界通信網を握っている政治的電線工夫の手にかかると忽ち諸国民の平和を脅かすものに化する。最近百年間に亙って戦時平時共に世界通信網を牛耳っているヨーロッパの通信社は殆ど皆なユダヤ人の創立である。先づ大きい所でアヴァス通信社は1835年にロイ・アヴァスの創立に係るが、その父はポルトガルからフランスに移住したユダヤ人である。彼は1832年にドイツ系ユダヤ人ベルンシュタインの「色刷通信」紙を買取って、之を改組した。彼には二人の共働者ベルンハルト・ヴォルフとヨザファト・ベールとがいたが、この両ユダヤ人は1848年にアヴァス社を去ってヴォルフの方はベルリンに自分の通信社を開き、カッセル出のユダヤ僧の子なるベールの方は50年代に英国に渡り、ロイテルと改称して英国の大通信社となった。
この三大ユダヤ系通信社は数十年来、全欧州新聞通信界を支配していたのみではなくて、殆ど全世界の報道陣を占領していた。ドイツも前大戦前に於ては言う迄もなくこの三社独占から殆ど逃れることができず、ドイツ系の通信社が僅かに北方諸国を通信で繋いでいる間に、アヴァスやロイテルは全世界を分割して支配していたのであった。 |
| 大戦の通信状態とその後 |
| かくして世界大戦が1914年に勃発するや、恐るべき結果が招集され、全世界は仏英通信社のデマ宣伝で塗りつぶされてしまい、ドイツは僅かに近隣中立国数国に真実の叫びを聞いて貰えたに過ぎない。デマ宣伝がどんなに有效だとしても、それがアヴァスやロイテル等の国際的通信組織の力を借りなかったならば、決してドイツをたたき伏せる程の力を持つことはできなかったであろう。 ナチスドイツは政権掌握後ヴォルフ通信社と電通連合社とを統合して「ドイツ通信社」を創設して、地球上枢要の各地に自派の代理者による自己の世界通信網を設置したが、ドイツは歴史上ここに始めて他の先進大通信社に劣らぬ近代科学の粹を尽した客観的且つ急速果敢な通信網を全世界に敷くことを得たのである。大通信社が何れもその背後の祕密力の庇護を受けていることは上述した通りであるが、その結果として、国際通信組織が蔵している巨大なる危険は時とともに増大し、新聞の虚報は益々危険な隱蔽方法を考案して、大通信社の看板を下してまでも悪質のデマを飛ばすようになった。 多くの場合には誰も責任を負わぬ報知を虚構するのが主眼であり、誰が委託したか、誰が背後にいるのかを全く気づかれないように仕組むのである。虚構は又次々に他の新聞にも引用されて尾鰭が附き、また互に引用し合ったりなどしているうちに何れが元のものか解らなくなってしまう。これら通信社のモットーは、新聞虚報が常にその取消よりも迅速に広まること、一度書かれた以上、結局何かが後に殘るということである。假令取消その他のいざこざがあっても、報道の迅速と競争という理由のために事件の真偽を確める暇はないので、自由主義的な新聞は無批判にこれらの通信社の通信を掲載してしまう。 また多くの場合には、外国新聞中に見られる虚報、傾向的通信の類は、新聞自身の通信員から出るのではなくて、却って新聞の編集部員自身が通信員に傾向的なものや新聞社の政治的経済的従属関係に沿うような報道を強制するのである。通信員の意図などは全く顧みられることはない。かくて「言論の自由」という看板を掲げて新聞を支配しているのは、決して精神でも真理でもなく、金錢であり、それを払う人である。立派なジャーナリストと雖もここでは自主権を持たない。立派な新聞を毎日検閲する匿名の背後人達は、厚顏にも常に「自由」を叫び乍ら、この空辞に隱れて諸国民を毒する贋作をどしどし広めようとしている。「自由」なる語は西欧民主主義国家に於ては頗る高く謳歌されているので、「自由」を踏付けにするためにインチキ者流に用いられるような場合でも「自由」とさえ言えば喝采を博するのは、真の「自由」のためにも歎かわしいことである。 |
| フランス新聞界 | |||||
フランス衆議院議員エルネスト・ベゼは、フランスの宣伝力増大のために議院内に特殊の一派を結成している人であるが、彼は1935年にその著「世界の眼の下に」に於て次の要求を漏らした。
仏国の有名な出版者ヴラヂミール・ドルメソンは1928年に「ドイツへの信頼」なる書で言っている。
仏国掌璽官アンリ・シェロンは1934年11月13日に新聞について次の如く語った。
以上は何れもフランス人自身の告白であって、之は疑う余地のない資料であるが、序に仏国新聞が大戦前に於てそれ程迄に買收し易いものになっていたかを示す材料を一つあげて見よう。それは当時ロシア財務大臣のパリ駐在代理として仏国新聞を親露派に傾けようという任務を帶びていた枢密顧問官ラファロヴィンチュの手紙である。彼は、1904年8月30日に当時ののロシア財務大臣ココヴィッツェフに宛てた手紙の中で、買收金の分割法に関して次のように報知している。
今日の何の国でも、政治と商売とを新聞で結合する企てが、フランスに於ける程にうまく行っている国はない。即ちこの國では、フランス新聞全体の生命線をアヴァス通信社が独占しているのである。この通信社は各新聞に報道を供給するだけでなく、同時にその広告及び販売にも手を出すのである。この先頭に立って一切を切り廻しているのは、アヴァス社の総取締にして最大の広告社の社長でもあるレオン・ルニエルである。なほ彼は、仏國新聞全体の販売組織であるアシェト社の監査役をも兼ねている。またパリのロスチャイルドと並んで財界に有力な地位を占めているユダヤ人ホラース・フィナリイがこの全能なアヴァス社の首席監査役におさまっていることを見れば、実状が尚お一そうよく解る。如何なる新聞もこの全能な通信社に刃向かう勇気と力を持ちえないのは当然ではなからうか。 かくフランスの新聞界に於ては政治と商業とが混和しているので、経済団体や財団の類が新聞の一年の予算を支払ってやる代りに、その新聞の本欄全部を買切ることも出来る。編集者の意見に従って、背後の全権者の供給する通信や論説がそのまま新聞に載せられることも大して珍しい現象ではない。それ故に、如何に良い意志を持っている記者も、この事情を如何ともし得ない程であり、かのヴラヂミール・ドルメソンはこの点に関して次のやうな意見を述べている。
|
| 英国の新聞 | ||||
フランス新聞の方は多少に拘らず決まった精神的並びに経済政策上の潮流に従い、特定の党派乃至財閥とか言ったものに仕えているが、英国の新聞の方は、少数の例外を除けば、殆どその全部が大衆のセンセイション欲を滿たすことを主眼としている。英国新聞の完全なる商売化をジェラルド・バリーはよく描いているが、1932年2月19日の「余は新聞を訴える」に於ては次のように言っている。
今日英国ではロード・ロザーメーア・コンツェルン、ビーヴァブルック・コンツェルン、ベリ団、ウェストミンスター団、スティーマー団、オガームス団等の他には、極く少数の新聞が存するだけである。中でもドイツを比較的客観的に見ているのはロード・ロザーメーア位のものである。英国では言論の自由ということが、伝統的になっているが、その実施はなかなか困難である。かかる自由は公衆の眼を蔽う目隱しであり、目潰しの砂に過ぎない。この事実をよく喝破した人に「タイムス」の主筆ケネディがあり、「19世紀とその夜」誌の1937年8月号にこう書いている。
このやうな批判をやっているのは敢えてケネディだけに止まらず、大英新聞連盟長ハムフレイは1937年3月22日に総会の席上次の如き言をなした。
1934年5月9日にに故総理大臣マクドナルドは「英国新聞連盟」の前で左の演説をなし、大衆新聞の無軌道振りを責めている。
|
| 合衆国の新聞 | ||||
| 北米合衆國の新聞界を掌握している大物は、ウィリアム・ランドルフ・ハーストであり、自分のインタナショナル・ニュース・サーヴィス(I・N・S)とユニヴァーサル・サーヴィスといふ二大通信社の他にも無数の自社系新聞を支配して、全国発行部数の三分の一を占めている。その殘りはアソシエィテッド・プレス(A・P)とユナイテッド・プレス(U・P)が分有している。しかしながらこんなに有力なハーストの如きでも、一度ユダヤ人の顧客達が彼の主要新聞ニューヨーク・アメリカンに広告依頼を拒み、ハーストの共産主義排除とソ連攻撃とを封じようとした時には、止むなくこの新聞を廃刊せざるを得なかった程である。他の新聞王と雖も同樣の支配から脱れ得ない。
例えば1939年4月17日附けウァールド・プレス・ニュースの論文で、ラムゼイ・ムイルという人がこの事を言っている。
新聞組織の中央集権、その商業化、広告大衆のセンセーション欲とによる制約等は、合衆国に於ては極端に發達している。或る有力な発行者が1929年に7百人程の一流商人を前にして米国新聞を論じたが、その中にはこういう言葉がある。
ある米国発行人は、個人的にはドイツ総統ヒットラーを崇拜しているに拘らず、その新聞では総統の悪口をする文章や絵画を平気で載せているので、それを或る人が難詰すると、こう言ってゐる。
既に1913にジョン・スウィントンは、「アメリカン・プレス・アソシエイション」の総会席上でこう言っている。
|
| 言論の自由 |
| スウィントンの指摘している通りが、いわゆる「言論の自由」の正体である。かくて「言論の自由」はそれを所有していると自称する人々自身の言葉によって正体を暴露されたか、新聞はその成立の当初から今日に至るまで、決して一度も真の自由を所有したことがなかったのであって、自由が最も讚美された時代こそ最も悲慘な時代であり、最も多く金力と権力とによって圧迫れ買收された時代であったのである。「言論の自由」とは要するに歴史上最も巧緻な細工を施した僞造概念であり、諸国民の道徳も、政治的良心も、輿論も、このインチキ概念の背後に於て凌辱され、破廉恥極まる商売に悪用されるのである。 新聞は本来から言って諸国民の生活に於ける一つの権力であるから、これは充分に支持されるべきものである。之を愛そうが憎もうがそれは人の勝手であるが、但しどうしても無くては済まされない機関である。前仏国大使ガブリエル・アノトウが言ったように、新聞は「ヱソップが最善にして最悪のものと言った舌」に他ならない。その最善な点とは、新聞がその真の功績によって獲得した読者の盲目的信頼であって、これは新聞に真実の報道の責任を負わせるものである。またその最悪の点とは、それば僞の「言論の自由」を押しつける無恥である。この言論の自由こそは現代の盜賊達や、戦争煽動者達や、人類の掠奪者達がその背後に隱れている仮面である。彼等は一般的利益の公共施設たる新聞を下劣な本能の競爭場と化し、「真理よりは虚僞の方が容易に金錢を儲けさせる」という主義を以て輿論を毒している。 ファッシズム及びナチズムは今日に於てかかる「言論の自由」を撤廃し、新聞をばかの虚僞の「自由」から「自由」にしてやったのは、実に精神史上に於ける一大事業であると言わなければならぬ。日本に於ける新聞雜誌統制も端緒に就いてはいるが、前途は今なお遼遠の感がある。我々は速かに従来の危険なる「自由」の崇拜から醒めて、真実に真理に立脚する言論出版の国を建設せねばならぬ。 |
| 新聞と戦争 |
| 世界の新聞は今日実際に於て戦争と平和の鍵を手中に握っているのであって、この事は最近数十年の歴史を繙けば直に判明するのである。実に無数の戦争は、かの新聞の作った業であった。弱力な政府が戦争を煽る新聞に容易に屈してしまうことは、かの第二フランス帝国が如実に示している。ビスマルクは1870年に繰返して新聞の強力なること及び新聞の與える損害を大なることを述べている。1864年、1866年、1870年の三戦役を惹起したのも新聞である。1898年から1903年まで続いて合衆国のキューバ島保護統治を以て終を告げた西米戦争は、明らかに米国の二大新聞連盟の競爭から起ったのである。1912年から13年に亙る第二バルカン戦役、即ちトルコ征服者相互の戦争は、もし新聞が絶えず煽動しなかったならば、爆発しなかったであろう。
米国大統領リンカーンは、「筆は剣よりも強し」と言った。かの世界大戰でドイツは武力で負けたのてはなくて、結局世界の新聞の虚僞宣伝に敗れたのであって、リンカーンの言葉の真実なることをドイツは身を以て体験したのである。国際新聞界とその背後勢力とが世界大戦を惹起したことは好個の研究材料である。無数の政治家の言葉によってもこの事実は闡明せられる。連合軍側の筆陣の本部はパリではメイゾン・ド・ラ・プレス、ロンドンではクルー・ハウスにあって、盛にデマ宣伝を飛ばしたのであった。 アルトゥール・ボンゾンビイはその著「大戦時の虚言」に於て国際デマ宣伝の実状を述べているが、その中から一例を引いて見る。1914年にアントワープ市が占領された後に、ケルン新報は左の如く報じた。 「アントワープの占領が周知となるや、教回の鐘が鳴った」。ところが仏国新聞ル・マタンはこの報知を次の如くに受け取っている。 「ケルン新聞によれは、アントワープの僧侶達は城塞占領後教会の鐘を打つように強制された」。 更にタイムスには翌日になってこう出た。 「ル・マタン紙がケルンから聞いた所によると、アントワープ占領後鐘を打てとの命令を拒んだ僧侶達はその職を追われた」。 それがイタリーのコリーレ・デラ・セラ紙にはこう載った。 「タイムス紙がパリを経てケルンから聞いた所によると、アントワープ占領後鐘を打つことを拒んだ憐なベルギー僧侶達は強制労働を課せられた」。ル・マタン紙は更にこの虚報リレーに結末をつけて全然のデマを書いている。 「コリーレ・デラ・セラ紙がロンドンを経てケルンから聞知したところによると、アントワープの野蛮な占領者は、教会の鐘を打つ命令を拒んだ憐なベルギー僧侶達の英雄的行爲を罰するため、彼等を生きた鐘鐸として頭を下に鐘に吊り下げた」。1937年11月2日の「ニュース・クロニクル」で政治的宣伝の問題に触れたカミングスは、戦時デマ宣伝の競爭に於ては英国が第一位を占めたと書いている。 またド・マルシァルはその著「良心の動員」中で、平和が危険に陷るのは外交家の手によるよりも良心のない新聞による方が大である、と語っているし、仏国ジャーナリストのウルバン・ゴイエも次のように言っている。「世界平和は、世界の新聞が金力の奴隸である限り許されるであろう」。前英国内務大臣ウィリアムス・ジョンソン・ヒックスは、1927年10月29日に記者協会ロンドン支部総会の席上、新聞人に向って語った。「諸君は内閣の運命を規定する。諸君は政府を作ったり、滅したりする。諸君は政府を強いて宣戦布告でも平和宣言でも勝手に出さしめる力を有する。それ故にこそ諸君は常に諸君の重大な責任を銘記していなけれはならない」。前フランス首相カイヨーも次の如く公言した。「平和を脅かす危険は新聞にある。・・次の戦争は新聞によって布告される」。 |
| 国際連盟の悪業とユダヤ人 |
| このようにして世界平和の真の大敵が新聞であることが解ったが、実際、国際新聞が協同して悪宣伝をするならば、どんなに強固な平和工作も立ちどころに崩れてしまうのであって、その悪業たるや誠に恐るべきものがある。その例としては我々に直接の関係のある日支事変に於ける各国の新聞乃至通信社の悪意に滿ちた無責任なデマのことは問題にしないとしても、例えばかのスペイン問題に関係してドイツが蒙った悪宣伝の如きも著しいものがある。
ドイツが如何にも占領の意図を以てモロッコに上陸をなしたかの如く書いたのはパリ新聞の大部分であったし、又英国はバスク地方のゲルニカ市でドイツ人が大虐殺をやったと悪宣伝をしたが、実はボルシェヴィスト達が故意にあの殺戮を犯して罪をドイツ人に稼したに過ぎないのである。それからドイツの飛行機や戦艦が非行を犯したような宣伝も無数にあるが、これもまたボルシェヴィストが意識的に世界を第二の大戦に追い込もうとした手段なのである。 それからドイツ合併問題に関するデマも相当にひどいものがあり、またドイツはヒットラー総統自身の選抜にかかる特殊訓練修了の男子五百人をロンドンに送って英国の軍備計画を探索せんとしている、という記事さえも新聞によって作られたのである。かような例はいくらあげても際限がないが、しかしここで深く注目すべきことは、これらのデマ宣伝、悪宣伝の背後には常に、ユダヤ人乃至ユダヤ人支配下のフリイ・メイスン祕密結社の手が動いていることである。 世界各国の大都市に所在するモスカウの出店にはユダヤ移民とその買收された記者達が出入して、盛にナチズムやファッシズム打倒のための悪宣伝の指令を受けている。世界新聞界に及ぼすユダヤ人の影響というものは実に巨大なものであり、彼等が完全に実権を掌握しているソヴィエト新聞では、彼等の思うことで行われないことはないのである。他の新聞界でユダヤ人がどれ程の勢力を扶植しているかを示す一例をあげるとすれば、最近出た1937年度ハンガリー新聞年鑑に依れば、ハンガリーの新聞編集者総体の56%がユダヤ人であると言われる。「言論の自由」を振りかざしているいわゆる民主主義の国々の事情がこれ以上であることは自明のことである。而して前述した悪宣伝の要素がユダヤ人が世界新聞に振っている影響力の大小に比例して増減することは言うまでもない。 世界ユダヤ王国の政治的中心たるモスカウから新聞の戦争煽動は発火せられ、それかニューヨーク、ロンドン、パリ等のジャーナリズム的贋造所で見透しのつかないデマ通信の衣を着せられ、そこから地球上のありとあらゆる電線を伝わって、最後の政治的センセーションとして新聞読者の眼前に広げられ、わが国土の中へさえも堂々と伝わって来て来るのである。数日後になって嘘がばれたとて、それが何にならうか。悪宣伝の筆者は何時も背景に隱れているし、取消記事が退屈で面白くない一方では、新しいデマが次々と出て来るので、取消は全く無效である。 かくて政治的虚言は思うままに暴威を振い、国民生活と国際関係を崩してしまう。世界の輿論は責任ある政治家の手から滑り落ちて、国民の知らぬ間に恐ろしい結末に国民を追い込んでしまう。目を醒ましたときは、もう後の祭りであることが極めて多い。 |
| 新聞組織の改革 | ||
|
ヒットラー総統は既に1936年5月に全世界に向って声明を見して、世界輿論の無責任なる要素による害毒を先づ十分に除かぬ限り、世界の国際的緊張は決して解消され得ないと言ったが、イタリーのムッソリーニも亦同樣の考えを発表して次の如く言った。
ユダヤ勢割の支配下にあると称せられるフランスのアルベール・ルブランでさへも、1937年2月9日のパリ共和主義ジャーナリスト大会に於て、言論の自由が利己的憎悪の私情に引廻されるとき大きな危険を惹起する、と戒めた。
しかし、今日まで世界の民主主義国家は一つとして人類の紙上敵を迎え討つ準備をしていないで、徒に国際協調とか国際的連帯関係を以て平和保持の手段と考えている。そして世界平和の最も近道である新聞改革の問題には目を向けていない。それには何よりも先づユダヤ人と不潔なる無国籍的な商売人を新聞界から追放しなければならない。新聞に於てもユダヤ人は、過去に於ては恐るべき癌腫であったし、現在及び将来に於てもそうである。この癌を除去すれば、そこには真に責任ある「言論の自由」が打ち樹てられるであろうし、真の世界平和も拓かれるに至るであろう。安価なるユダヤ同情論が、わが国に於てさえも、ともすればジャーナリズムその他の方面から出現し易いのは、その直接の原因が奈辺にあるかは兔に角として、ユダヤの新聞界に於ける強力さを意味深く物語るとも考えられる。それ故に以上主として欧米の事情を中心として述べられたことは、決して単に他所事ではないのである。国際資本主義、国際共産主義、国際的祕密結社、国際的言論通信機関、誠にユダヤの張り巡らす十重二十重の世界支配の網は精緻にして堅固である。幾千年の訓練を経たタルムード的詭弁と虚僞の精神の結実であるとは言え、実に驚歎すべきものではないか。(昭和14.8月) |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)