|
ユダヤ問題が単なる宗教問題でないことは言うまでもないことであるが、しかしユダヤ民族の場合に於てもその特質がその宗教に於て最も本質的に現われていることは、他の民族の場合と同一であって、ユダヤ民族の過去・現在・未来を知るためには、何よりも先ずその宗教をよく理解しなくてはならない。勿論、或る宗教を真に理解するためには、その祭式の実際を詳細に知る必要のあることは言うまでもないが、しかしそれと同時に、否、それよりも一層重要なのは、その宗教の聖典を充分に検討することである。この意味に於て我々は、第一にトーラと称せられる旧約聖書の最初の五巻、次にはタルムード、次にはシュルハン・アルフ、そして最後にはシオンの議定書にまで及ぶところがなくてはならない。
勿論この他にも、旧約聖書の残部、ユダヤ諸法師あるいはマイモニデスの著作等は考慮されねばならないであろうが、しかし前の四つを問題とすることで、充分ではなくとも、大体に於ては事足りるのである。それ故にここでは、これら三つをその成立と内容とに亙って極めて簡単に述べて見ることにしよう。殊に我が国に於けるユダヤ問題研究の最大の欠点は、現在の問題に眼を向けることに急なる結果として、その根拠を充分に明らかにせざる所にあり、従って、しばしば余りにも早急に「八絋為宇」の大理想を持ち出すなどして、ユダヤに関する相当の知識を有するにも拘らず、極めて容易にユダヤの張り巡らす陥穽に陥るのである。無知から来る傲慢さと同じく、原理の確立せぬ知識が如何に危険であるかは、この場合にもよく窺われるのである。
さて、トーラであるが、それは「教」を意味するものであって、ユダヤ教の原典をなしている。旧約聖書の始めの五書がそれであることは(広義には旧約全部を指すこともある)既述の通りであるが、ユダヤ人のそれに対する尊敬の念は極度に深く、それが「意味」の点から神の言葉であるばかりでなく、その一語一語、その一綴り一綴り、その一文字一文字が、そのまま神の言葉であって、今伝わっているままの姿で神より直接にシナイ山上でモーゼに伝えられる前に、更に正確に言えば、この世界が神によって創造される前に、現在のものと一言一句の相違なしに創造されてあったというのである。
自分の宗教聖典に対するこの強烈な信仰は宗教的信念の表現としては尊敬すべき熱意を帯びているのであるが、しかしここに既に見られる物質的文字への執着は、ユダヤ民族に於ける唯物主義の深さを暗示していないとどうして言えるであろうか。殊に創世紀の宇宙創成史その他の内容が、インド乃至バビロンよりの輸入品であることを考慮し、またその中の神観乃至道徳観がそのままの言葉であるというユダヤの信仰を問題として考えるならば、かかる言葉をモーゼに伝えあるいはそれ以前にそれを創造した神エホバは、決して民族神とさえも言い得ない程度の妖怪乃至悪魔と見做されても差し支えないのである。
真のキリスト教に生きんとする者は、キリスト教とユダヤ教の差を知らなくてはならないし、従って新約と旧約との根本的差異をも知らなくてはならない。旧約の名に欺かれてユダヤの世界政策の手先となることは、「我らの父なる神」の御旨にも叶う筈はなく、況んや身を捨ててもユダヤの不正を矯めんとしたと称せられるキリストその人の意志に副う筈はないのである。例えば、米国のブルックリンに本部を有する「万国聖書研究会」という看板の陰謀団体及びそれに類似のものの如きは、何れもキリスト教の名に於けるユダヤ帝国主義の一機関たるに過ぎない。
ユダヤ民族自身が「神の選民」たることを主張するのに対して、その歴史が果してそれを証しているか否かを見ることもせず、ユダヤ聖書を旧約とする信仰に属することが人を「高等民族」にするという如きお目出度い迷信を抱いて、真の信仰の本質と自己の本質とが何であるかを反省することを忘れる者が如何に多いことであるか! 例えばカンタベリー僧正の如くにユダヤ教会のみを保存しているソ連を反宗教ならずとして感激し、また米国のブラウン僧正の如く幾百万ドルの遺産を共産党に寄贈する程度の盲信者は我が国にはないであろうが、しかし「戦争と真理」という如き三歳の童子と雖も正気ではなし得ぬ相関概念を作製する無教会派「人工ユダヤ人」の如きがキリスト教者であるというに至っては、キリスト教の為にも遺憾この上もない事であろう。
ここでユダヤ聖典そのものに帰ろう。さてユダヤ人のトーラに対するかくの如き唯物主義的盲信は、健全な常識を持つ程度の人に取ったならばトーラの到るところに存することの明らかな無数の矛盾に面しても、ユダヤ人をして矛盾を矛盾として認めるだけの余裕を許さなかった。即ち、神の言葉に矛盾があると認めることが神を冒涜することと感ぜられるのは尤であって、ここに、その成立史から見ても存在し得ない筈の統一をかかる矛盾のうちに認めようとする努力が生れて来る。神の言葉に矛盾が見えるのは、いまだ神の心に徹しないからだというのである。かくていわゆる「解釈」又は「註釈」の必要が生じ、極めて牽強附会な無数の説が生れて来るが、しかしこれらの解釈が単なる解釈と認められる限りはそれらに強制力がないので、かかる解釈に従事するユダヤ法師達は、彼らのなす解釈は単なる解釈ではなくて、モーゼが神より伝授された神の言葉の一部が口伝によって彼らに伝えられて来たのである、と説くようになったのである。
かくして成立したのが「解釈」を意味するミトラシュであるが、時代と共にそれがまた整頓され、解釈されて、やがて「繰返し」を意味するミシュナが生れた。旧約聖書と並んでユダヤ人によって尊崇されている上に、ユダヤ人の本質を知る為にはあるいは旧約よりも一層適切であるかも知れない。タルムードは、このミシュナと、更にこれに加えられた解釈の集成で「完成」を意味するゲマラとから成っているのであって、これは後にも論及したいと考えるが、ユダヤ聖典として重要なタルムードは、その成立史から見る時には、解釈の解釈であるのである。このタルムードが現在の形に於て完成したのは西暦4百年から五百五十年に至る頃であるが、現在ではパレスティナ系の小部のものと、バビロン系の極めて大部のものとがあり、欧米に於て普通タルムードと称せられるのは後者を指すのである。細字大型書十幾冊と称せられているから、その大部であることは容易に想像がつくであろう。
しかしこの大部の書は、現在のキリスト教徒の全部があらゆる神父達の書を読破することはなく又現代の仏教徒があらゆる仏教経典を通読することのないのに照応して、決してユダヤ教信者によって全部が読まれることはないのである。しかしながら、ユダヤ人がアジアの西部から欧州へと黄金を追うて流浪するようになってからは、個人的乃至団体的の一々の重大事に際してパレスティナの大法師の裁断を受ける暇がなくなったので、ここにより簡便な律法の書を必要とするに至ったのであるが、西暦千年頃にスペイン・フランス・西部ドイツの地方に於て書かれたユダヤ哲学者マイモニデスの著、ヤコブ・ベン・アシェルの著、及びヨゼフ・カロの著等は、その使命を持っていたのである。いづれもタルムードを抜粋し、それにユダヤ的「解釈」を加えたものである。
そのうち最後の書が最も広く読まれたが、これがまた既に大部の著であったので、更に著者自身によって抜粋が作られ、1564年から翌年へかけて始めてヴェニスで出版されるに至った。「シュルハン・アルフ」(「用意の出来た食卓」の意)と称せられるものがこれであるが、しかしユダヤの他のあらゆる場合と同じく、この書もまた直ちに「解釈」を生んで、現在「シュルハン・アルフ」として我々の手に入るものは、クラカウのユダヤ法師モーゼ・イツセルレスの書いた部分の加えられたものである。かくてこの書もまた相当大部のものとなっているが、この程度ならば実用的であるので、現年も盛んに活用されている。四部から成っていて、日常生活の諸般の事を規定した巻、祭事を規定した巻、民法乃至刑法の巻、婚姻の巻となっている。
唯物論者マルクスが常に懐中して、人目を避けては読み耽ったというのも、恐らくこの書か、それの抜粋であるらしく、改宗ユダヤ人で表面的には宗教排斥の元祖であるマルクス(本名モルデカイ)に於てすら既に然りであるから、他のユダヤ教ユダヤ人に於てはこれらのユダヤ聖典が今に於ても如何なる拘束力を持っているから、到底吾人の想像を許さぬところである。しかしこの事情は、大部のユダヤ史の著者ユダヤ人グレッツ教授や日本に於ても一時渇仰随喜の対象となったユダヤ的「純粋」派のユダヤ哲学者コーエンらが、あるいは著書の中で、あるいは法廷の前で、ユダヤ教とその聖典とが現在のユダヤ人にとっても唯一絶対の価値の標準であり、実行の規矩である、と公言しているのを見れば充分に明瞭になるであろう。
既に論及したように、これらのユダヤ聖典乃至法典はすべて解釈であり、解釈の解釈であり、そのまた解釈であるが、これは我々がユダヤ人の本質を知る場合には極めて興味深い事実を暗示しているのであって、ユダヤ人は「創造的でない」とされるかと思えば、同時に他方ではユダヤ人は「頭がよい」とされるという、一見しては矛盾と見える事柄が、決して真の矛盾でないということも、ユダヤ聖典の成立史に見られる上述の事実を知る者には直ちに明らかになるのである。つまりユダヤ人の「頭のよさ」とは、トーラ又はタルムードの解釈の場合のように、本来の矛盾であるものに統一を見出すことであり、勇猛な詭弁によって対象を無視しても或る種の「解釈」を成立せしめるだけの大胆さを持つという事に外ならない。
それ故にユダヤ人の頭のよさとか解釈のうまさは、ユダヤ人の実生活の殆ど全部を形成していると称せられる「嘘言・詐欺・裏切り・暗殺」等の諸傾向が頭の仕事として発現したものに外ならぬことが判明する。タルムードの成立そのものが既にトーラに対する虚言であり、詐欺であり、裏切りであり、暗殺であることは、タルムードには既にトーラの面影が殆ど全くないと称せられていることによっても判明する。ユダヤ精神の本質が「技術的」であると称せられるのも、真の創造力がなく、解釈のみに終始するが為であらう。
一体に解釈的精神は非創造性の一面であって、これは個人的に見ても、民族の歴史を見ても、よく理解のできることである。ゲーテの言う創造的批評が如何に稀であり、解釈のうまさという技術の点に捉われない真の創造的解釈が如何に少ないかということが、これを証する。ユダヤ精神の以上の側面を我々は「ユダヤ的論理」と呼びならわして来ているのであるが、この技術的精神が技術の世紀である唯物主義の19世紀に支配的地位を占め得たのも、蓋し偶然ではないであらう。とにかく、ユダヤのトーラ崇拝は、表面的には宗教的熱意を帯びているが、実際に於てはトーラは、その解釈者、即ち、ユダヤ法師の「頭のよい」解釈によって、口伝もまた神の言葉なりという詭弁の下に、如何とも変更され得ることになっているのである。
宗教聖典に対してさえもかような態度であるから、他の解釈の場合が如何であるかは容易に想像し得られるであろう。いわゆる「純粋法学」、「形式社会学」等と呼ばれるユダヤ系の思想がすべてそれであって、例えばユダヤ法学が国家をも「純粋」化して××機関説に及び、また偉人天才の研究に於ては対象の本体をユダヤ化し、それによって解釈者の「頭のよさ」を誇示するのも、同じ「嘘・詐欺・裏切り・暗殺」的精神の一表現に外ならない。(昭和16・5月)
|
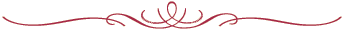
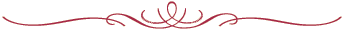
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)