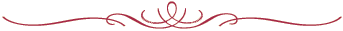
| 蔵田計成氏の問題提起、ウラン研究その1 |
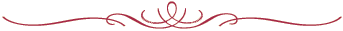
(最新見直し2011.03.21日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ウラン放射能問題、原発問題を考える際の格好なテキストが入手されたのでここにサイトアップしておく。(了解は得ていないが、文全体をれんだいこ表記、文法で構成し直した。文言は変えていない) 2007.7.28日 れんだいこ拝 |
|
人類史におけるウラン=核原子力の根底的意味を問う 惨劇の教訓=人形峠ウラン残土、原発、劣化ウラン弾、放射能被曝 蔵田計成 |
||||||||||||||
| 第一部 核・ウラン | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
2,放射性核物質の危険な素顔 ウランという放射性核物質の素顔については、余り正確に知られていないのが、実情ではなかろうか。私自身も、過去3年間にわたって反核・反原発市民運動などに深く関わってきたが、いまだに妥当な認識水準の域にまで到達し得ていない。その実践的経験を通じて痛感したことは、ある程度の基本的知識がないままに、どんなに丁寧な説明を受けても、妥当な認識回路は、知識の隙間を素通りしてしまうという事実であった。そこで,核問題を論考するための最小限必要な前提として、取り敢えず文系の筆者と共に、百科事典等の知識を参考にしながら、ウランの正体、ウランに関する基本的物性、危険な毒性の実態、劣化ウラン、生命体を冒すミクロ世界の被曝メカニズム等の基 本的知識と認識を共有することから、記述をはじめたい。 (1)「燃えるウラン」と「燃えないウラン」 天然に存在する核物質の中で、もっとも重い元素はウラン=Uである。そのウランも他の物質と同様にあらゆる物質のもとになる原子からできている。その中心に原子核があり、原子核は「陽子」と電気的に中性な「中性子」からできている。その陽子と中性子からなる原子核の周りを「陽子」と同数の「電子」が回っている。このうちウランの「陽子」の数はすべて92個の同数であるが、「中性子」の数は異なっている。142個、143個、146個の3種類の中性子がある。ウラン原子核の分量=質量数は、これらの異なる3種類の中性子数と、92個の陽子数との和によって表わされている。このウラン原子核の分量=質量数の違いよって、ウラン原子核を識別し、それぞれ、U-234,U-235,U-238と呼んでいる。だからウラン元素=Uはこれらの3種類の原子核からできている、ともいえる。 このようにウラン元素は三種類の原子核をもち、陽子数がすべて同数(92個)なことから、三種類の原子核を「ウラン同位体」「ウラン同位元素」と称している。さらに、放射能を帯びているので「放射性同位体」「放射性同位元素」(ラジオアイソトープ)とも称している。また、この陽子数92個がウラン同位体の原子番号にもなっている。さらに、このウラン同位体の化学的性質は三つともすべて同じであるが、核分裂するのは「燃えるウラン-235」だけであり、残り二種類のウラン同位体は「燃えないウラン」、つまり「核分裂しないウラン」である。 さらに、自然状態で存在する天然ウランを構成する元素は、「燃えるU-235」と「燃えないU-238」の二つの同位体からできている、といっても差支えない。この天然ウランの組成比率では、後者の核分裂しないウラン(燃えないU-238)が99.3%である。だから、前者の核分裂するウラン(燃えるU-235)はわずか0.7%に過ぎない。つまり、天然ウランに含まれている「核分裂するウラン」は微量に過ぎないことになる。 この二つの同位体の他に、天然ウラン中に存在する三つ目のウラン同位体がある。「燃えないU-234」である。天然ウラン中の含有率は、0・0054%と微量である。 |
||||||||||||||
|
(2)崩壊(壊変)するウラン ウラン同位体の共通な現象として、崩壊=壊変という現象がある。ウラン原子核のようにある程度以上に重い原子核は、核内の陽子と中性子の結びつきが不安定なので、安定した原子核へと自然に変化する性質を持っている。そのために、「放射線」の形で余分なエネルギーを放出しながら、連続的に崩壊していく。この放射性崩壊現象をそれぞれ、α線を出すα崩壊、β線を出すβ崩壊、さらにγ線やX線などの電磁波を出すγ崩壊と呼んでいる。この自然崩壊過程において放射性同位体は変化して別の崩壊生成物、つまり別な原子番号をもつ元素や、同位体(まとめて核種)へと変質していく。たとえば、天然ウランの主成分「燃えないU-238」は、いわば「始源元素」であり、これを「親核種」(おやかくしゅ)と称している。この「親核種」は単独で崩壊し、トリウム、ラジウム、ラドン…等14種の「娘核種」「子孫核種」と呼ばれるウラン系列放射性元素へと崩壊=変化していく。 この崩壊・変化過程において、最初の原子核の個数が二分の一個に半減し、放射能力も半減する。この半減までに要する時間を「半減期」と称していることは、よく知られている。このようにウラン放射性同位体(親核種)は、長期間にわたる崩壊という放射能半減期を経て、その後は4分の1、8分の1という具合に原子核や放射する能力や総量を減少させながら「崩壊生成物」となる。最終的には放射する能力や総量もゼロに近くなり、鉛の同位体(鉛-206)になって安定・成仏する。 これらのウラン系列に属する放射性元素(娘核種)の放射能半減期はさまざまである。例えば、天然ウラン中微量の「燃えないU-234(娘核種として扱われている)の半減期は24万5千年という長期間である。逆に、後述するが、あの岡山県・鳥取県境の人形峠で主役の一角を演じることになったラドンのような希ガス(気体元素で他の元素と化合しない)の半減期は、わずか3・8日に過ぎない。この事実だけから、ラドンが危険をもたらすのはわずか3・8日間に過ぎないと思い勝ちであるが、そうはいかない。その理由は、①毒性は半減期に反比例して強烈であること。②新顔のラドンが次々と押し寄せ、一瞬も途絶えることはないということ。 例えば、崩壊に向かって突き進む二つのウラン親核種の放射能半減期は、「燃えないU-238」が約45(44.8)億年、「燃えるU-235」が7億年である。前者の数値は、半減期が地球の寿命ほど長いということを意味している。それだけではない。ウラン放射能の毒性は半減期の長短にかかわらず、絶えず後続の「娘核種」に引き継がれ、再生し続けることになる。その崩壊現象は半減期を経て最終的には放射する能力が無化するまで続く。だから、地中のウランが危険な毒性を保持し続ける歳月は,人類史的時系列とは桁違いであり、太陽系の寿命に等しく、現存する人類にとっては、「未来永劫」である。その意味で、ウラン放射能は妖しい輝きを永遠に出し続ける「危険な毒物」なのである。 |
||||||||||||||
|
(3)臨界と原子炉 天然ウランの中に0.7%含まれている「燃えるU-235」を濃縮(濃化)して得られたウラン物質を、一定の質量以上に加工し、一定の形状容器に集めて、これに向けて自然界に存在する中性子をゆっくりと反応・減速させる。その結果、電気的に中性である中性子はそのまま電子軌道を通り抜けて「燃えるU-235」の原子核に到達する。その結果、元々が不安定な状態の原子核に新しい中性子が入りこむとバランスを崩して、「燃えるU-235」の原子核は最初の核分裂を起こす。この核分裂反応が、人類が最初に試みた人工的な「核分裂」である。 この人工的核分裂の過程において、原子核は大きなエネルギーを出しながら二つに分裂し、新しい2個~3個の中性子を放出する。さらに、この新しい中性子は他の原子核に反応する。その後は、同じような仕組みと原理によって、次々と連鎖的に核分裂を起こす。このような連鎖的な人工的核分裂反応を「臨界」という。その際に大量のエネルギーと共に中性子線、α線、β線、γ線等の放射線を出す。さらに、放射能を含んだ粒子、揮発性蒸気、希ガス等の人口放射性物質を排出する。 原子力発電のシステムは、この臨界反応を原子炉の中に封じ込めて、人為的に制御しながら作動させ、膨大な放射熱エネルギーを発生させ、その際に発生する全エネルギーの30%強のエネルギーを取り出して電機タービンを回し、電気エネルギーに変換する、という発電システムである。 このように、原子力発電では、残り70%弱の放射エネルギーを無価値な温排水として廃棄しているが、この大量な廃熱を前提とした発電システムこそ、「非効率な原発」を象徴しているともいわれている。なお、原子力発電用の燃料(燃えるU-235)を1グラム(米粒大)だけ燃やして得られるエネルギーは、一般家庭用3年6ヶ月分の電気エネルギーに相当する。さらに、99年の東海村JCO臨界事故で主役を演じたウランの重量は、さらにその千分の一(Ⅰミリグラム)という目に見えないほどの極微量であった。にもかかわらず、被害者は死者2名と認定被曝者663人以上という事態をもたらした。 |
||||||||||||||
| (4)太古の眠りを覚まされたウラン
天然ウランの主成分である「燃えないウラン-238」を元祖にした14種のウラン系列放射性核種がもつ放射能濃度は、生み出されたままの自然状態の下におかれている限り、放射線の総量はすべて等しい状態で、地中深く眠ったままであり続ける。いわば土の蓋をかぶせられた自然制御維持の状態にある。この状態を「放射平衡」という。 ところが、天然ウランが過去(地球誕生から1000万年・新第三紀中新世)の平穏な眠りから覚醒させられて、はじめて人為的に地中から地上に引きずり出さてしまうや否や、その瞬間から「放射平衡」は崩れてしまい、生物環境に晒されて危険な相貌を剥き出しにする。例えば、第2部の稿で詳細な現地ルポをふくめて論考するが、あの岡山・鳥取県境人形峠のウラン鉱石採掘跡地やウラン残土からは、いまも地表に吹き出したラドン放射性希ガスが空気中に拡散し、人の呼吸を介して体内被曝を拡大させている。ラジウムも水に溶け出して河川を汚染し、食物連鎖の危険性を増大・加速させているわけである。その意味で、あの人形峠付近のウラン鉱山から掘り出された膨大な「土砂の山」は、浅はかな人知がもたらした「修羅」を象徴しているといえるだろう。 勿論、自然界に存在しているラドン希ガスは自然放射能として地中から大気中に放出している。同様に水溶性ラジウムも地下水や河川に溶け出して自然放射能の一部となり、「自然放射能値」として、カウントされている。だが、このような大自然の営みはいうならば「神の領域」の出来事である。だが、愚かにして不幸にも、いまや人類はこの領域を超えてしまったのである。しかも、いまなお地球生命体への背逆という愚昧を演じ続けている。 |
||||||||||||||
| (5)核開発における軍事目的、その非人間的な究極の邪悪
人類が本格的にウラン開発を始めた初発の動機は、邪悪な軍事目的にあった。つまり、人類が初めて開発した原子炉第一号は、発電のためではなかった。原爆用プルトニウムをつくり出すことが直接の目的であった。 広島型原爆をつくるには、天然ウラン中の「燃えるU-235」(天然中の含有率0・7%)から、一挙に濃縮度93%以上の高純度ウランに濃縮=濃化しなければいけない。しかも、その濃縮のためには膨大なエネルギー消費を必要とする。そこで開発されたのが、原爆用濃縮材を効率よく作るための原子炉であった。こうして、人類史上最初に作られたのが、広島型ウラン原爆、長崎型プルトニウム原爆であり、人類の頭上で炸裂した。 この原爆開発システムを概括しておこう。 原子炉のなかで原爆材料のプルトニウム(Pu)を精製するには、「燃えないU-238」が原材料となる。「燃えないU-238」を毛布状のブランケット炉内に装着して、中性子をあてて「燃えるU-235」を燃やすだけでよい。後は装着した「燃えないU-238」が「燃えるPu-239」へと見事に変身してくれるだけである。ただし、このプルトニウム変身過程で必要な操作は、普通の「軽水炉型」の原発用原子炉では「燃えるPu-239」をすぐ取り出さないと「燃えないPu-240」に変質してしまい、その分だけ、作業は厄介になる、という点である。 この軽水炉型の原発用原子炉から出る、変質した高レベル放射性物質についても、再処理して高純度のPuを抽出することは技術的にも、容易に可能である。また、遠心分離装置でも濃縮できる。さらに、その技術上の不便さを解消するために、いくつかの「改良型原子炉」が開発された。「ガス冷却炉」「重水冷却炉」「黒鉛炉」「高速炉」「高速増殖炉」等である。これらの改良型原子炉の開発目的は、名目上は発電用とされているが、実質的には、軍事用プルトニウム精製という目的に容易に転化可能であるという意味で、軍事目的に直結しているのである。むしろ、表面的には平和利用のための原子力発電発という技術的なシステムをとっているに過ぎない。この事実は公然の秘密というよりも、公知の事実というべきである。この技術論上ギャップが表面化しないのは、メディアを含めた原発タブーであり、政治的に露呈しないのは、日米間の経済的、政治的、軍事的盟友関係が安定しているからである。ひとたび安保条約破棄などの矛盾が顕在化したならば、日本原子力政策を直撃するのは必至である。 |
||||||||||||||
|
6)日・朝の核兵器開発における潜在的能力 日本の核開発の現状についてふれておこう。日本では52基の原発用の軽水炉型原子炉と大小10基の研究炉がある。そのうち、発電ではなくて、実質的にはプルトニュウム=PU抽出だけを目的にした実験用原子炉としては、「東海1号炉」(ガス冷却炉、老朽解体中)、「ふげん」(重水冷却炉、故障停止中)、「常陽」(高速炉)、「もんじゅ」(高速増殖炉)がある。これらの実験用原子炉開発の目的は、名目上は原発用の燃料=PUの抽出となっている。これらの実験用原子炉のうち、実用型を目指す高速増殖炉「もんじゅ」は、95年重大なナトリウム火災事故を起こして故障停止中だったが、05年最高裁判決により、事故から10年ぶりに運転再開の目途がついた。だが、欧米は技術的ネックを理由に高速増殖炉から完全撤収している。にもかかわらず、日本だけが計画を断念していないのが現状である。 これらの原子炉から取り出したPUは、国内保有分だけで「常陽」約40㎏、「もんじゅ」約60㎏、合計100㎏以上保有していることが知られている。原爆一個製造に必要なPUを2キロ前後(技術的には1キロでも可能)とすれば、約50個の原爆製造が可能である。たとえ、日本のPUが国際機関(IAEA)の監視下におかれているからとはいえ、PUを製造することは、現在の原爆製造技術を用いれば、核燃料廃棄物の再処理によって通常の軽水炉型原子炉でも十分可能である。 単純に計算して日本のPu保有分はすでに国内に7トン(原爆3500個分)、海外貯留分を合計すると40トン(合計2万個分)に達すると指摘する専門家もいる。 それに比べて、朝鮮民主主義人民共和国の核保有問題は、政治的に誇大視されているのが実情である。使用済み核燃料の全量を再処理してPUを取り出したとしても、その量はせいぜい20キログラムに過ぎない。「仮に超優秀技術を駆使して核兵器を製造したとしても、その数は長崎型原爆(8キログラム)3個分に過ぎない」(「朝鮮の核問題をめぐって」小出裕章、技術と人間、03年6月号)という。この事実こそは、ブッシュ政権によって喧伝されている「悪の枢軸、核脅威論」に基づく核先制攻撃論が、如何に底の浅い欺瞞とペテンの論理であるかを如実に示している。 その理由を補足すれば単純明快である。政治主体のイデオロギー性や政治性を口実にして、自らの世界支配への野望を隠そうともしない傲慢さにある。一方では、後述するように自ら行う核兵器の実験、行使、核自体がもつ残虐な絶対的凶器性を不問にしておきながら、他方では、それを開発・保有しようとする新参国家意志を、断罪・排除しようとする自分勝手な理屈は、「核拡散防止」を大義名分に装っただけの、「ヤクザ親分衆」のご都合主義的外交そのものである。 その身勝手な屁理屈の日本流の極め付きの一つを、さらに補記しよう。英語のNuclear Developmentは「日本国用」に邦訳されると「原子力開発」となる。ところが、「悪の枢軸国」を断罪するための翻訳では「核開発」に意訳されている。このように「原子力開発」と「核開発」という二枚舌を平然と使い分けているのが、日本の「核的状況」である。このような欺瞞を許している事実は情けないほどに、腹立たしい。 「怪しからん国だから経済制裁をするという。ならば問う。日本には原子炉はないのか?ウラン濃縮はしていないのか?再処理をしていないのか?」(前出小出裕章) |
||||||||||||||
| (7)猛毒人工放射性物質
原発を稼働させ、ウランを核分裂させることによって各種の放射性同位体(プルトニウム、セシウム、ストロンチュウム、各種ヨウ素)等、おおよそ自然界では存在し得ない、否!存在を許すべきではない人工核分裂生成物質がつくり出されている。とくに、核実験や原発事故によって生じた放射性微粒子が対流圏や成層圏に吹き上げられ、いまも上空から徐々に降下して地球上にばらまかれている。90年代半ば、日本産科学会は「流産急増」という統計数値を発表した。原因を辿れば、95年中国核実験にたどり着いたという。このように「放射性降下物」(フォールアウト)を含めた人工放射性物質の毒性が、地球の全生命体に与えるダメージは深刻である。実験や事故による放射性降下物は、50年代~60年代には大気中の放射能数値を長期間にわたって増大させたことがある。その結果残された痕跡は、たんに「微量」として片づけられる代物ではなかった。セシュウムのように、自然界には決して存在しないはずの最悪の毒性人工放射性物質が、地球上のどこからでも検出されるという事態を生み出したのである。 「燃えるPu-239」は「燃えないU-238」の毒性の約2〇万倍(18・8万倍)と記憶しておけばよい。天然ウラン放射性同位体を親核種にした、猛毒人工放射性物質の半減期は、「プルトニウム-239」2万4千年、「セシウム-137」30年、「ストロンチウム-90」29年、「ヨウ素-131」8日、「ヨウ素-138」7時間、「ヨウ素-137」4分である。その毒性の特徴は、先にもふれたが、半減期が短いほど強烈な放射能を出すという点にある。つまり、半減期の長短と、その毒性の強弱は反比例の関係にある。だから核自体が強い毒性を持つと思えばよい。 ついでに補足しておくべきは、突如、核災害に出くわしたときの身の処し方である。既述したような放射能の危険性を考えると、東海村JCO臨界事故のような、事故災害から「身を守る心得」を知っておくのも、無駄ではないだろう。たんぽぽ舎・柳田真さんは以下のように警告する。 1, 臨界事故の際は、突発した瞬間から臨界が止まるまで、有害な放射線が大気中に放出され続ける。事故直後は、揮発性ヨウ素群が放出される。半減期が4分~7時間、8日間という短半減期であるとはいえ、事故が突発すると被曝は不可避である。 2, 猛毒の放射線被曝から可能な限り我が身を守る手段があるか。答えは「否!」と考えるべきである。敢えて避難と防御手段の原則をいえば、「ひたすら現場から遠ざかることしかない」。放射能被害は、無風状態を前提条件にして距離に反比例するから、間違っても、現場で解毒剤配布の行列に並んではいけない。 3, この二点を前提にして幾つかの点を補足する。
|
||||||||||||||
|
(8)放射線被曝症候群、被曝回路 広義の放射線とは電子、中性子、陽子などの原子核から出る粒子線と、X線、γ線、紫外線、赤外線、可視光線などの電磁波の総称である。一般に放射線障害といえば、高エネルギーをもつ中性子線、陽子線、電子線、α線、β線、γ線、X線、などによる障害を指す。低エネルギーの紫外線、赤外線、可視光線等による障害、例えば白内障、皮膚ガン、日光皮膚炎、角膜炎などの障害は、放射線障害の範疇から除外されている。しかし、後にみるが人形峠ウラン鉱山で働いた女性労働者は全員が低線量被曝特有の白内障の手術を余儀なくされた。この例からも分かるように、放射線障害はエネルギーの高低にかかわらず、多岐にわたっていることは疑いの余地がない。 放射線障害は身体的障害と遺伝的影響に分かれる。そのうち、身体的障害は症状の出現時期によって、短期の「急性放射線障害」と長期の「晩発性放射線障害」に区分されている。 前者の急性放射線症候群のうち、重篤な症状は、広島原爆の爆心地から1・5キロ以内にみるような、即死状態である。また、東海村JCO臨界事故の犠牲者のように、現場室内の至近距離で透過力の強い中性子線やγ線などを一度に大量に浴びると、生還不能である。 臨界発生直後は瞬時にして中性子線被曝がはじまり、発生源(線源)からの距離が数十メートル以内でも、被爆して数日後から数週間以内で放射線や放射性物質を浴びて、身体の自覚的異常が知見される。例えば、事故現場の隣接地で被爆した作業員や住民の体感異常は、すでに十数時間後(事故当日の夜中)から始まった。さらに、空気中に放出された短半減期の揮発性蒸気・ヨウ素群は、まず皮膚に付着して「日焼け」「皮膚炎」を起こす。それを吸い込むと呼吸器系の鼻腔に付着し、やがて脳もダメージを受け、最初の自覚症状「頭痛」「下痢」が短時間ではじまる。 体内に入り込んだ放射能は、消化器系の食道や胃にダメージを与え、「吐き気」「食欲不振」になる。さらに肺に入り込み血液とともに全身を駆けめぐり、「脱力感」に襲われるという。これらの被曝症状は、JCO臨界事故の1週間後に報道された「ゴルフ中に頭痛」「強い吐き気」「気だるさ」「下痢」等の症状が示す典型的な急性放射線症候群である。(名城大、槌田敦) これに対して、「晩発性放射線症候群」の例は、広島、長崎の症例である。まず、「低線量被曝」では数ヶ月から長ければ7年~8年後に発症する。次に、長い発症例は、固形ガン(例えば大腸ガン)の症状で、その潜伏期間は平均25年という長い年月である。とくに、晩発性放射線障害は、統計学的・疫学的な数値における有意差によって所見が確認されるまで、超長期間にわたる調査や検診を必要とする。そのために、病変の解析、因果関係の特定、疫学的立証をますます困難にし、患者に犠牲・苦痛を強いる要因となっていく。 晩発性障害の発症様式は、被曝放射線の量だけではない。被曝放射線の被曝態様によっても異なる。放射線の発生源(線源)が外部の場合は「外部被曝」(体外被曝)、身体内部の場合は「内部被曝」(体内被曝)である。また、原爆のような爆発的な被曝を「混合被曝」と称している。外部被曝の場合でも、エネルギーが強くて、透過性も強い中性子線、γ線、X線の方が、殺傷力は強くてダメージも大きい。その中性子線を利用した中性子爆弾は、その強い透過力を利用して建物の破壊を最小限に抑え、相手の人的殺傷だけを目的にした特殊爆弾として開発された。 逆に、内部被曝ではα線やβ線のように、透過力は弱いが、高エネルギーをもつ放射線の方が影響力は大きい。人体に吸収された放射能が、多くの細胞に付着してエネルギーを与え、長い時間を経て緩慢に生体細胞を破壊し続けるからである。同じことが、「劣化ウラン」についてもいえるが、この詳しい実態は後にみる。 これらの放射能被曝における唯一ともいえる共通点は、放射線に敏感な胎児、幼児、小児の被曝が成人の被曝に比べて大きなダメージを与えるという点である。また年齢・性別・個体差によっても発症に差異があることも知られている。 |
||||||||||||||
|
(9)被曝障害発生メカニズム(機序) ミクロ世界における生体破壊の病理学的メカニズムについても、概括しておかなければいけない。 周知の通り、生命体は原子によって構成され、その原子が集まって分子となり、その分子は互いに分子間をつなぐ結合エネルギーをもっている。人体はこのような分子結合をもつ細胞によって構成され、その数は約60兆個である。その内の2%(約1兆2000億個)が日々新しい細胞と入れ替わっている。この細胞の交代(細胞分裂)で重要な役割を果たしているのが細胞のDNA(核酸)である。放射線という異物が固い防護壁(細胞膜)を通って細胞原形質内に進入すると果たして何が起きるか、ここから生命体内における死闘のドラマが始まる。 放射線は数十万~数百万電子ボルトという桁違いに高いエネルギ-をもっている。これらの放射線はまず分子内の結合エネルギーに作用して分子結合を破壊し、電離作用を起こして細胞を傷つける。それに続いて致命的なダメージを受けるのがそのDNA分子である。破壊の度合いによって、その生命体はさまざまな異変をきたす。その結果、誤った情報がDNA分子に組み込まれ、正常細胞が変質細胞に取って代わり、ガン細胞や異常生殖細胞が発生する。 細胞損傷順位は三段階あることが知られている。細胞が受けるダメージの大きさは、細胞分裂=細胞再生機能が活発で高度な細胞ほど大きく、細胞再生機能が低いほどダメージは小さい。 第1、増血組織(骨髄)、生殖器官、粘膜、皮膚等の細胞活動が活発な細胞再生系。 第2、肝臓、腎臓などの緩やかな条件付き細胞再生系。 この他に、被曝障害には「即発性瞬間被曝」ともいうべき地獄絵図がある。JCO東海村臨界事故で「多臓器不全」で亡くなった大内久さん、篠原理人さんのように、血液や皮膚の細胞再生機能が瞬時に破壊され、身体が内部から溶けていくような壮絶な苦痛とともに、早くて3ヶ月後~半年後には臓器の生命活動が力尽きてしまうような場合もある。 |
||||||||||||||
|
(10) 時系列でみる放射性廃棄物 核・原子力開発(以下核開発)に伴う低レベル・高レベル廃棄物は、ウラン産出→精製→実用・使用→再処理に至るまで、各段階の、しかも全課程において例外なく排出する。そればかりではない。稼働中の原発からも、生活環境に向けて、間断なく「放射性投棄物」を垂れ流している。例えば、原発敷地の沖合の海洋放出管からは、トリチウム、ヨウ素、コバルト、ストロンチウム、セシウム、プルトニウムなどあらゆる種類の放射能が、廃液に混ざって海に捨てられ、海域を汚染し続けている。また、再処理工場の巨大な排気筒からは、例外なくクリプトン、トリチウム、ヨウ素、炭素などの気体状の放射能を大気中に放出し、小児白血病を多発させている。 このように、進歩という名を冠した核開発の全課程は、文字通り徹頭徹尾危険な毒性にまみれている。まさに反文明、反生命体、非的存在そのものである。以下、廃棄物の毒性排出の全過程を、最初の入り口ともいうべき、ウラン鉱山採掘過程にまでさかのぼって、時系列を追って整理してみよう。
|
||||||||||||||
| (11)核・劣化ウランの危険な毒性
上記工程①②③で排出される廃棄物の危険な毒性に関しては、第2部で実証的かつ詳細にみていくことにする。ここでは、④で示した「劣化ウラン」に関してみていこう。なお、工程⑦で示した「再生ウラン」も、米軍によって劣化ウラン弾と混用されているが、このことは別項で触れるにとどめる。 劣化ウラン=DUは、上記の排出過程では主に「六フッ化ウラン」の濃縮加工過程で排出される「第4番目の廃棄物」である。このDUは、それまでは二束三文の値打ちしかないウラン廃棄物として捨てられてきた。ところが、比重が鉄の2・5倍、鉛の1・7倍であるために、弾丸や砲弾の弾芯として廃物利用されることになった。弾丸の貫通力や水平飛行距離が長いという、単純な理由から軍事用に転用された。 弾芯に使用される劣化ウランの重量は、30ミリ砲では約300グラム、一番大きい120ミリ 砲では約4・7キロある。その半分が大気中に飛散する事実をもってすれば、その自体が正真正銘「危険な核兵器」であることが分かる。 その他の転用先としては、航空機の部品をはじめ、ガラスエナメル、写真フィルム、セラミックス食器用の上薬、ネガとプリント、義眼等の民生用にも利用され、ときには道路の舗装用に敷きつめられたという。このような安易きわまりない汎用の危険性については、劣化ウラン弾が大量に使用されたコソボ戦争以来ようやく指摘され始めた、というから驚くほかはない。その軍事的使用は野蛮な犯罪行為というべきである。 DU=劣化ウランの毒性に関しては評価が大変難しい、という説が流されている。先に触れたように、放射能半減期の長さと、放射能の毒性の強さは反比例の関係にある。半減期が短ければ、その短い分だけ強い放射線を出し、半減期が長ければ、その長い分だけ弱い放射線を出し続ける。例外を除いて、放射能は「太くて短い人生」か、または「細くて長持ちする人生」にも似ている。したがって、DUの毒性=危険性も、ウランの組成上の変化に微妙に対応している。そのために、曖昧模糊の口実となっている。 毒性の度合いを大雑把にみれば、DU=劣化ウランは陽子2個と中性子2個で構成され、他の放射線よりも重いアルファ粒子線を放出するから、きわめて厄介な潜在的発ガン性放射性物質ということになる。 先にみたように、DUは④の廃棄物であり、その生成過程は以下のようなものである。 天然ウランを濃縮加工して、②の廃棄物、③の廃棄物を経て、④の廃棄物を分離して原子炉用燃料の「濃縮ウラン」を取り出す。その際に残るのが、④の廃棄物=DUである。この濃縮過程では、半減期が短くて強い毒性をもつ「燃えるU-235」の含有率が天然の0・7%→3%~5%へと数倍になるまで濃縮し、製品化される。この製品化された濃縮ウランの毒性は、「燃えないU-238」にくらべて放射能が20万倍も強い「燃えるU-235」を濃縮=取り出した分だけ、毒性が強くなる。逆に、残存廃棄物の毒性は、毒性が強い「燃えるU-235」を取り出した分だけ微減することになる。結局、DUに関しては、この二種類のウラン組成のプラス・マイナスの出入り分が、毒性の強い「燃えるU-235」の含有率を、計算上では6分の1だけ「劣化」「枯渇」(depleted)させたことになる。 ところが、ここで注意すべきは厳密な意味で劣化したのは「含有率」であって、この劣化現象は必ずしもそのまま「毒性の劣化」には結びつかないという点である。つまり、劣化ウラン=DUの名称は、毒性の強い「燃えるU-235」の、いわば「含有率の劣化」に由来しており、この微量な「含有率の劣化」が、「毒性の劣化」(減化)へと、用語化されることによって、概念だけがすり替えられたに過ぎないのである。この事実からも分かるように、「劣化」という言語表現は、劣化ウラン=DUという名の実体を表していないばかりか、逆に乖離させている。 結論的にいえば、その毒性は「同質」にちかい。だから、疑いもなく「劣化ウラン弾は核兵器」と規定すべきであり、断罪すべきなのである。 既述したように、劣化ウラン弾はあたかもナイフでバターを切るように、戦車の装甲を切り裂くほどの優れた装甲貫通力をもっている。それだけではない。激しい燃焼性を兼ね備えた徹甲焼夷弾というにふさわしい。高速で戦車に衝突した瞬間に炎を上げて炸裂し、車輌を爆破炎上させて兵員を瞬時に殲滅させる。さらに、弾芯の重金属DUは、その半分以上が酸化性であり、5ミクロン以下の浮遊する微粒子(エアロゾル)となって大気中に放出される。風が吹けば、大気中に巻き上げられて広範囲に拡散する。飛散距離は40キロに達する。すぐ後でみるように、その浮遊粒子は呼吸を介して人体に入り込み、長期にわたって重い体内被曝をもたらす。地下水や食物連鎖を通じて、生体環境を汚染する。 劣化ウラン弾による被曝の経緯・実態については余り知られていなかったが、最近では、徐々に明らかにされつつある。皮肉なことに、この実態の解明は被曝現地ではなくて、加害本国の帰還兵の追跡検査という、意外な顛末を辿って解明される結果になった。戦場で被曝し、体内に劣化ウランの破片を残したまま帰還した兵士たちが、その被害者であった。 彼等は、被曝後7年が経過した後でも、通常よりも高い濃度の放射能ウランを、尿、精液から検出している。肺に入り込んだDUの微粒子が、血液に流入して体中に拡散し、慢性的に常時体内組織を汚染したものと考えられる。従来の知見では、ウランは腎臓および骨に蓄積することから、その化学的毒性による腎・骨障害のみが問題にされてきた。しかし、最近の動物実験の結果、ウランは身体のあらゆる組織(睾丸、胎盤、リンパ節、脳髄)にまで蓄積し、免疫の低下を引き起こし、脳活動に影響を与える可能性が指摘されている。また、被曝現地イラクからは、胎盤を通して胎児にも蓄積し、骨変形の奇形児が続出していることが、ネットでも報告されている。 90年代以降の、細胞レベルの放射線影響のメカニズムに関する研究の進展は著しい。劣化ウランが出すアルファ線は、到達距離は短いが、高エネルギーをもっており、細胞に当たると深刻な影響を及ぼす。アルファ線のような、高エネルギー放射線の与える生体影響は、従来考えられていたよりもはるかに大きいという事実が明らかにされつつある。92年におこなわれたイギリスの医学者グループの研究によると、たった1個のα粒子を細胞に当てただけでも、ほぼ確実に突然変異が起こるという事実が突き止められた。この研究は、アルファ放射能の内部被曝が引き起こす発癌の危険性についての、これまでの知見の変更を迫る、重大な意義を持っているとされている。 直径5ミクロン(μm)の劣化ウラン微粒子が細胞に付着すると、この微粒子は1年間に約500回のα粒子線を放射する。その際の、アルファ粒子線の到達距離から推定すると、粒子線の影響を直接受けるのは、微粒子の周辺にある数十個の細胞という。したがって近傍の細胞は、1年間に数回から十数回程度のα粒子線の放射を受け、確実に遺伝子の変異を引き起こすことになる。破壊された細胞はやがて死滅するが、生き残った細胞は、前癌細胞へと変化する可能性が高い。このような事実は、いまようやく明らかにされようとしている。(『劣化ウラン弾による被害の実態と人体影響について』アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会、公開ネット) |
||||||||||||||
| (12)衝撃的な証言、暴かれたペンタゴンの三百代言
証言Ⅰ:真実の報道を世界に向けて発信し続けているサウジアラビアのTV局アルジャジーラは、03年4月、米国軍人ダグラス・ロッキーとのインタビューを放映した。その経歴は以下の通り。 67年:原子物理学博士号をもつ軍医として入隊。 71年:ベトナム戦争でB52パイロット。 94年:1年間、国防総省劣化ウラン・プロジェクト最高責任者。 彼は、やむを得ず米軍が敵と見なすメディアを選んで、以下のような勇気ある告発を行った。 「米国防総省は、91年湾岸戦争以前からウラン兵器が戦闘にきわめて有効な兵器として使用することを決めていた。それは接触するすべての人を殺し、すべてを破壊する。私が湾岸戦争に際して『ウランの汚染を除去せよ』という特命を受けたとき、ロスアラモス国立研究所の大佐から『ロスアラモス・メモ』というべき1通のメモを受け取った。そのメモには『われわれは健康と環境に影響があることを知っているが、劣化ウラン兵器はきわめて有効であり、つねに戦闘で使用可能な状態にしておかなければいけない。従って、戦闘におけるウラン兵器の使用による健康と環境への影響については真実を語ることがないように。』というものであった。 エイブラムス戦車が発射するウラン弾は、すべてがプルトニウム、ネプツニウム、アメリシウムで汚染された10ポンドの固体ウランである。着弾時に最初のウラン弾量の約半分が放射性微細粉末になって飛び出し、環境中に放出されて人体に吸収されていく。私達が気づいた最初の重要な影響は呼吸器障害で、気管支炎が悪化したように呼吸困難に陥り、やがてひどい発疹が始まった。まるで1リットルもの有害重金属を服毒したようなものである。さらに重大な事態は、8ヶ月~9ヶ月以内にチームのメンバーがガンを発症したこと。しかも、2年以内に増え続けてやがて全員亡くなったことである。戦場で故意に身体に埋め込まれた弾片は、体内の周囲を放射能で冒し、腫瘍をつくる。(註、丁度、このインタビュ-が世界に放映される1ヶ月前に、国防総省の退役軍人医療責任者マイケル・キルパトリックは“退役軍人90人の追跡調査の結果、彼等が病気で苦しんでいる兆候はないという事実が証明された”と記者会見で明言した。) どう考えても、それは事実に反する。退役軍人援護局が確認した統計では、02年5月までに現地に滞在した経験を持つ米軍100万人のうち、4分の1(25万人)が回復不能の障害者であり、そのうちすでに1万人以上が死亡し、現在の死亡率は毎月140人以上に達しているという。 国防総省の責任者がウソをつく理由は、イラク、サウジアラビア、クエート、バルカン、そして米国のすべての場所で、ウラン兵器を故意に使用したことの責任を回避するためである。」(明治大学、生方 卓、ネット公開掲示板) 劣化ウラン弾被曝の実態は、以上のような迫真の事実暴露をはじめとして、秘匿のベールを脱ぎつつある。これまで米軍当局は帰還兵士の被曝の実態や因果関係の容認を峻拒してきた。だが、もはや事態は黙殺することが不可能なほどに、限界値を超えてしまったようである。軍当局者は、「米軍帰還兵士の30%が苦痛に悩まされている。影響は思ったよりも大きい。再調査が必要である。」(米軍放射性生物調査研究所、A・ミラー、ガーディアン紙) という深刻な事態の容認を余儀なくされた。この期に及んで、否応なく劣化ウラン弾の犯罪的危険性を追認したのである。すぐ後でみるように、ペンタゴンの重大なウソも明らかになった。 証言Ⅱ:アメリカ政府国防総省は、戦場で初めて劣化ウラン弾を使用した湾岸戦争のはるか以前から、その危険性を知り尽くしていた。表向きは、これまでも劣化ウラン弾の放射能毒性を終始一貫否定してきたが、この演出は全くのウソであった。政府と軍は、劣化ウランの危険性を知りながら、味方に対してすら、何らの防護措置も危険告知も行わないで核兵器を使用したのである。米欧の帰還兵支援団体や、反核団体は、粘り強い取り組みのすえ、米政府のウソを裏付けるいくつかの軍事報告書の存在を暴き出した。 メリーランド州ボルティモア市近郊30キロにある陸軍専用の兵器開発研究所内の試射場(設立1917年)では、50年代半ばから劣化ウラン弾の試験が続いていた。79年までの25年間に、何の遮蔽もなしに、戦車や装甲車用に使う金属を 標的に実射試験を繰り返してきた。 90年、湾岸戦争の半年前に米軍兵器弾薬化学司令部に提出したSAIC報告書(応用科学国際研究所)は、「低摂取量の長期影響は癌を引き起こし、高摂取量の短期影響は死をもたらす」「戦場の兵士に対するエアロゾルとなった劣化ウランの被曝は、放射線と化学的な影響の可能性の点で重要になるであろう」と述べている。 別な研究報告は「劣化ウラン弾に撃たれた装申車輌の内部、あるいは50メートル近傍に存在する人員は、劣化ウランの著しい内部被曝を受ける」「標的となった車輌の風下で測定されたウラン粒子の平均79%が、呼吸によって吸入されやすいサイズであり、吸入されれば肺の中に永久に捉えられたままとなるであろう。」(米軍弾道学研究所報告) 英国原子力公社(UKAEA)の秘密文書では「湾岸戦争で使われた戦車砲弾だけで、劣化ウランの総量は約22・5㌧を超えるだろう。・・・.戦車砲弾に含まれる劣化ウランを吸入した場合、最新のICRPのリスクファクターで.計算すると、これは50万人を死亡させる能力を持つことになる」「実際の使用量320㌧では700万人の死亡」(英インディペンデント紙) |
||||||||||||||
|
(13)帰還兵士症候群の被曝実態 91年湾岸戦争後の米軍やNATO軍帰還兵等を襲った一連の「帰還兵士症候群」では、40種近い被曝症状がみられ、その症状は身体の全部位にわたっている。主なものを列挙すれば、ガン、白血病をはじめとして、慢性倦怠感、記憶障害、神経障害、無気力症、気管支障害、関節痛、皮膚の斑点、脱毛、白内障、激しい頭痛、下痢、性交障害、激しい生理痛、死産、未熟児、新生児の先天 的欠損等。 わき道にそれるが、このように、残虐な凶器は味方帰還兵士やその家族をも深刻な障害に晒し、殺傷するという悲劇的なパラドックスを演じることになった。(山崎久隆、劣化ウラン研究会) この戦史に残る蛮行は、敵の殲滅、味方の保存という戦争の軍事目的・法則を越えて、軍事の暴走が引き起こした無差別殺戮であった。このような「軍事法則への背理」「究極の野蛮」を大前提にした軍事作戦と、その背後に隠されている薄汚れたネオコンの戦争観こそは、虚偽をねつ造して侵略戦争の口実にするという、邪悪な政治目的と相まって、自らの墓穴を用意するだけであった。その意味からも、イラク侵略戦争におけるビュッシュの敗退は必定であった。 |
||||||||||||||
|
(14)放射線被曝症候群 以下の数字は何を物語っているだろうか。その統計は、戦場に出向いて被曝した加害側の兵士達の数字である。その統計数値が物語る事実は、戦争の残虐性にみる、彼我二面性のうちの「裏面」を示しているといえるかも知れない。
加害側の数値とは逆に、十字砲火に晒された相手国側コソボ、アフガン、イラク等の住民や兵士達の被曝者数は、10倍をはるかに超えるだろう。現地の救援に入ったユニセフは、統計システムも破壊され尽くしたイラクから、想像を絶する地獄の惨劇を伝えている。それによれば、湾岸戦争以来の兵糧攻めと戦争によって98年までに50万人、03年までには70万人もの幼い命が奪われたという。これほどまでに夥しい数の「一回性の命」を奪い去り、「人間の尊厳」を傷つける正義は、はじめから地上に存在し得るはずがないだろう。 |
||||||||||||||
|
(13)プルトニウム(Pu)検出、「再生ウラン弾」 先の衝撃的な証言を裏付けるかのように、ボスニア・コソボ空爆で投下された劣化ウラン弾から、天然には存在しない猛毒の人工放射性物質Pu=プルトニュウムが実際に検出された。この事実は重大かつ深刻な意味を持っている。
|
||||||||||||||
| (14)廃棄物毒性の危険性を隠蔽し、犯罪性の告発を認めないことの意味
核開発の全過程では、先にみたようにさまざまな放射性廃棄物が排出される。それにもかかわらず、その廃棄物毒性がもたらす最悪の結果に対する警告は、軍事機密を口実に、徹頭徹尾かき消されてきた。おそらく、その背後には巨大な政治的力学が存在していたはずである。核開発においては、戦争=軍事が最優先する。その軍事目的を妨げるような軍事への否定的な要素、一切の可能性、戦争犯罪への告発に結びつくようなあらゆる要因は、あらかじめ根絶しなければならない。このような作為性の介在は、容易に想像できる。そのために、放射能がもたらす最悪の結果を口外したり、公表したり、警鐘を鳴らすことも、すべて軍事の目的外として封印されてきた。さらに、核兵器開発の後を引きうけた原発開発においても、徹底した秘密主義、隠蔽体質はそのまま、悪しき伝統のごとく受け継がれてきた。いまだに後を絶たないデータ改ざんなどは、日常茶飯である。 この核開発における秘密主義や隠蔽体質を考えるとき、それを許した側の核廃絶運動における問題点も、敢えて付記しなければいけないだろう。 この問題に関しては、問題提起にとどめるほかないが、例えば、冷戦時代においては、核兵器に関してさえも、イデオロギー的正当化が運動内部にも存在していた。「帝国主義侵略戦争に勝つための核武装」「平和を実現し、保持するための手段としての核兵器」「戦争廃絶のための戦争」という論理である。さらにこの正当化の論理は、軍事核開発から民生利用への転用を口実にした、「核の平和利用=原発」という虚構として、社会的に広く追認されることになった。過去における不屈の努力にもかかわらず、政治的にも、イデオロギー的にも、理論的にも、実践的にも、その根強い虚構を打ち破ることができないままに、無為な歳月を重ねてきた。その結果が、過去、現在の核廃絶運動における、彼我の力関係の低迷をもたらしたというべきではなかろうか。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)