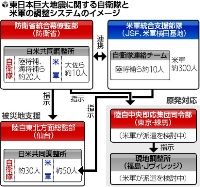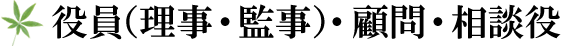東京電力福島第1原発の高濃度放射能漏れ・爆発事故で、東電側が14日夜、同原発の職員全員を退去させる方針を政府に打診していたことが分かった。現地での作業継続は困難と判断したとみられ、自衛隊と米軍にその後の対応を委ねる構えだったという。菅直人首相は打診を拒否し、東電側も一部職員を残すことになったが、東電はその時点で高濃度の放射線被ばくが避けられない原子力災害に発展する可能性を認識していたことになる。
複数の政府関係者によると、東電側が14日夜、「全員退去したい」との意向を枝野幸男官房長官と海江田万里経済産業相にそれぞれ電話で申し入れた。両氏は認めず、首相に報告した。首相は15日午前4時過ぎ、清水正孝・東電社長を官邸に呼び、「撤退はあり得ない。合同で対策本部をつくる」と通告。その後、東京・内幸町の東電本店を訪れ、「東電がつぶれるということではなく、日本がどうなるかという問題だ」と迫ったという。
政府当局者は14日夜の東電側の打診について「全員を撤退させたいということだった」と明言した。
一方、東電側も首相への不満がくすぶる。東電によると、同原発では協力会社と合わせ計4000~5000人が働いているが、現在、現地に残っているのは約300人。発電所の制御や復旧などの作業にあたっている。
東電関係者によると、15日早朝に首相が東電本店を訪れた際、事故対応に追われる社員が会議室に集まったが、首相は「こんなに大勢が同じ場所にいて危機管理ができるのか」と非難した。東電関係者は「『撤退は許さない』というのは『被ばくして死ぬまでやれ』と言っているようなもの」と漏らした。
東電幹部の話 (必要最低限の作業員を残し、あとは退去する)部分的な撤退を検討したのは事実だが、全員撤退を検討した事実は絶対にない。
【三沢耕平、小山由宇】