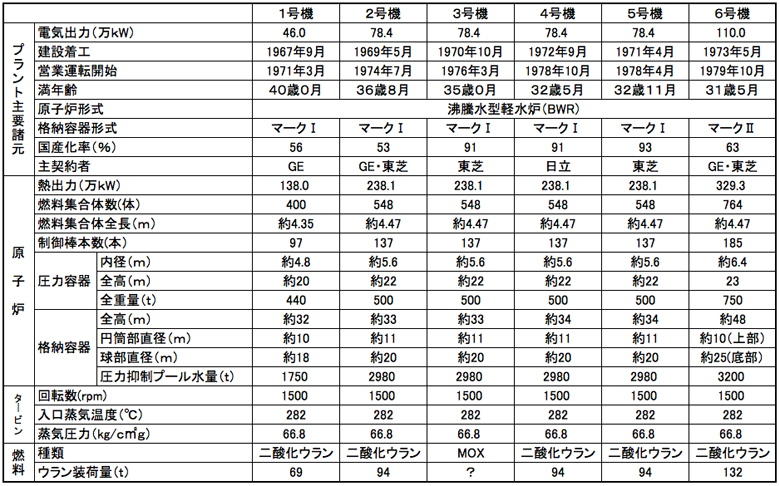経済産業省原子力・安全保安院は22日、福島第1原発の放水口付近の海水から規制値の100倍を超える濃度の放射性物質、ヨウ素131が検出されたことについて、原子力安全委員会から「周辺住民に直ちに影響はない」と回答があったことを明らかにした。
会見した西山英彦審議官によると、第1原発の半径20キロが避難区域に指定されていることや、ヨウ素の半減期が8日間と短く、魚などに取り込まれても、人が食べるまでには濃度が低くなることなどを理由としている。
西山審議官は「まずは原発の各号機を安定させ、放射性物質が出ないようにすることが重要。その上で水の処理を考える」とした。(2011/03/23-00:52)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-7c39.html
2011年3月20日 (日)
原発最悪事故収束可能性浮上だが三つの重大問題
大地震と大津波により激しい損傷を受けて、重大な放射能漏れ事故を発生させた福島原子力発電所が、自衛隊および東京消防庁、ならびに福島原子力発電所関連の電源復旧作業員たちの決死ともいえる尽力により、最悪の事態を回避する方向に転回しつつある。放射能線を浴びて国難に対処する、勇気ある末端の従事者に心よりの敬意を表したい。事態を改善させているのは、安全な場所で命令を下すだけの者ではない。危険な現場で、危険を承知の上で、重要な任務にまい進する人々である。安全な場に身を置く幹部職員は、せめてもの責任として、危険労働を行う労働者の生命と健康を確実に守らねばならない。
放水作業により使用済み燃料プール等の水位が増大し、冷却効果が観察され始めているように判断される。今後、電源復旧作業が順調に進み、1号炉から4号炉までの冷却システムが回復すれば、事態は収束に向かう。しかし、まだまだ予断は許されない。事態収束に向けて、関係者の更なる尽力に強く期待したい。事態は最悪の状況を回避する方向に転回しつつあるが、このことによって、今回の重大事故の評価が歪められることは許されない。三つの重大問題について、十分な検証と対応策が示されなければならない。
第一は、原子力発電そのものについての見直しが必須であることだ。今回の事故は、原発反対運動を展開してきた人々が懸念してきた通りのことが生じたもので、完全に予測された事故である。その意味で、「人災」であると言って差し支えないと思われる。日本は大地震国であり、大津波国である。広瀬隆氏が指摘するように、三陸海岸では、わずか100年前に38.2メートルの大津波に襲われたとの記録がある。今回の大津波による災害は、この意味で、完全に「想定しておかなければならない範囲内」のものであり、そのことによって発生した事故は、「人災」と呼ばざるを得ないのである。
政府・電力会社・原子力産業・関連学界は、すべて、原発推進によって利益を受ける立場にあり、これらの勢力が自らの利益を追求するために、原発を推進してきた。反対側にあるのが、日本国民の生命と安全である。産・学・政のトライアングルが国民の生命と健康を犠牲にして原子力政策を推進してきた結果として、国民の生命と健康が重大な危機に晒されている。
この図式を解消するには、原子力に頼らない電力の確保に注力してゆくほかにない。世界では、チェルノブイリ、スリーマイル島、東海村、美浜原発、柏崎原発などの事故の経験から、脱原子力の運動が拡大してきた一方で、原子力推進によって巨大な利益を得る勢力による原子力推進の活動がせめぎ合いを演じてきている。日本は世界で唯一の被爆国として、脱原子力の方向に舵を切るべきであると思われる。