| 私の手元に、旧日本海軍のいくつかの戦友会から託された資料がある。「戦友会」といってもいろいろあって、親睦が主目的の集い、戦没者慰霊を主とする会もあれば、毎回、講師を決めて、戦中戦後の体験や裏話を語ってもらい、それについてディスカッションするような、「勉強会」に近い集いもあった。「勉強会」の代表的だったものが、東京・銀座の交詢社で隔月で開催されていた「交詢社ネービー会」と、関西で毎月開催されていた「関西ネイヴィクラブ」だ。それらの講演のほとんどが文字に起こされ残っているが、ここでは前回(靖国神社)に引き続き、8月にふさわしい話題を紹介したい。1985(昭和60)年8月12日に起きた、死者520人、未曽有の航空機事故となった日航ジャンボ機墜落事故。その墜落現場の村長・黒澤丈夫氏の講演録である。 |
| 日航機墜落事故対応に尽力した名村長 |
| 1985(昭和60)年8月12日、午後6時56分頃、乗員乗客524人を乗せて羽田空港から伊丹空港に向かった日本航空123便ボーイング747SR機が、群馬県多野郡上野村、長野県との県境にほど近い御巣鷹の尾根に墜落。女性4人をのぞく全員、520人が死亡するという、航空史上最大最悪の事故が発生した。翌8月13日、事故現場が発見されると、空陸より現地入りしたマスメディアによる報道合戦が繰り広げられたが、そのなかで、現場となった上野村村長の事故への対応の鮮やかさ、救難指揮の見事さが話題を呼ぶようになっていた。村長の名は黒澤丈夫。その昔、太平洋戦争中は零戦隊を代表する指揮官として、開戦劈頭、台湾・高雄基地からフィリピンの米軍基地空襲に出撃したのを皮切りに、おもに南西方面(インドネシア~オーストラリア北部~西部ニューギニア)を転戦。日本軍が優勢だった大戦初期のみならず、敗色濃厚となった戦争末期にいたるまで、精鋭部隊を率いて出色の戦果を挙げ続けた人である。終戦時の階級は海軍少佐。戦後は郷里・上野村に帰り、村長を10期40年、さらにその間、全国町村会会長を4年にわたりつとめた。 私は、1996(平成8)年春、永田町の全国町村会で初めてインタビューして以来、上野村にも何度か通い、2011(平成23)年に亡くなる直前までの15年間、取材、交流を続けたが、「日航機の墜落事故に際会して」と題する、今回紹介する講演は、事故の記憶もまだ新しい1987(昭和62)年10月14日、大阪証券会館で行われたものだ。 |
| 「それなら自分の村ではなかろうか」 |
| 〈私は戦闘機乗りだ。つねに八方破れで荒っぽく、人様の前で円満な話ができる性質ではないが、こういう仕事(村長)で多少は角が取れてなんとか今日まで選挙をくぐり抜けてきた。今日は日航機事故と私が感じたことをお話したい。私の村は、群馬県の西南端で三国山がある。昭和60年8月12日、私は国道整備促進の陳情で東京に行き、帰って孫たちとくつろいでいるとテレビが飛行機の墜落を報じた。どこか遠いところの話だと思ったら、しばらくして長野県川上村(西南に隣接する村)の主婦が、「県境を越えて群馬のほうに入って見えなくなり煙が出てきた」と話すのを聞き、「それなら自分の村ではなかろうか」と思って、私はテレビを食い入るように見つめた。やがて、現場は長野県北相木村の御座山(2000メートルぐらい)の中腹と報道されたが、その周辺一帯は標高が高く、人は1200メートルぐらいのところまで住んでいるから、すぐ目の前で火も見え音も聞こえたはずだ。また私たちの村と北相木村を結ぶブドウ峠(1500メートル)にはたくさんの人が詰めかけており、捜索の飛行機は燃えている火を確認しているのに一向に現場が確定できない。私はどうも川上村の主婦の話が気にかかる。発見できないのは、墜ちた場所の地形が複雑だからだ。長野県側は高いがなだらかで発見しやすいから、発見されないのは私の村か埼玉県の大滝村に墜ちたのではないか。
夜11時頃、群馬県警の河村本部長から、「明朝4時に1500人以上を投入するから受け入れを頼む」という電話。県警では群馬らしいという情報を掴んでいるなと感じた。悶々のうちに夜は明け4時ごろに役場に行くと本部長はもう来ていた。村長室でテレビをつけっ放しで救難の準備に心を砕いた。5時過ぎに墜落現場が映し出されると、私は「あっ」と思った。村でも県境に近い国有林。私は植林に2回ほど行っている。愛林組合の友人に電話すると、「スゲノ沢だ」と教えてくれた。
しかしそこの地理を知る者は村でも少ない。ましてや警察や自衛隊ではむずかしい。私どものすべきことはまず現場への道案内だ。消防団のほかに、いちばん山奥の集落の人たちに案内するよう指示した。植林のころには沢の入口までついていたトロッコ道もこの時期には撤去され、橋も道もくずれ放題だから現場まで4時間くらいかかった。帰ってきた消防団員に聞くと、沢に入るにしたがい、上の方で黒煙が上がっているのが見える。しばらく進むと人の手がある、足がある。木の枝には腸がぶらさがっている。鬼気迫る状況のなか、飛行機はスゲノ沢に折れて落ち、尾翼に近いところで女の子の手が少し動いた。皆はハッと思ったが声が出ない。また動いた。「生きてるぞーッ!」という声になって皆が集まって助け出した。結局、女性4人が助かった。 |
| ちぐはぐな指揮命令系統 |
| 現場に行くだけで警察も自衛隊も疲れ切ってしまう。しかも惨憺たる光景のなかで救助、救難が始まったが、遺体の収容は大変な苦労だった。バラバラで誰が誰だかわからない。じっさいにご遺族のもとに帰った方は192名、残りの328名は多かれ少なかれ身柄を現場に残された。1本の歯の歯形とか、肉片がついたパンツの柄で氏名が確認されたりしたが、お骨の大部分を上野村に遺した人がきわめて多かったのである。
そういうなかで私どもは救難、救助活動に移り、13日の朝、遺体の収容のために体育館やお寺を手配し、血が流れるから農協からビニールシートを全部もってこさせたが、県警は上野村にはご遺族を泊める場所がなく遺体確認ができないから、遺体は藤岡に運ぶという。どうも指揮命令系統が一本化されていない。以後、われわれは県警の仕事の裏方に徹することにした。その後、村には多くの対策本部(県、県警、上野村、陸上自衛隊、運輸省、日航、事故調査委員会)ができたが、全部縦割り行政で横の連絡はまったくない。これでは県警はやりにくい。日本国に災害に対する態勢づくりのルールが確立しているかどうか、私は疑問に思うようになった。 |
| 総理や大臣も視察に来たが…… |
夏の盛りで、遺体はにおいを発する。においを防ぐのに自衛隊はマスクを持ってこいといい、機動隊はタオルがほしいという。自衛隊と機動隊が協力して山の急斜面に応急のヘリポートをつくると、自衛隊は往復ともにヘリだが警察はバスと徒歩だ。都道府県でよくやる災害救助訓練は事前によく話し合って実施するが、現実の災害や飛行機事故に予定はない。訓練では想定だけ関係の市町村に渡し、時間を決めて開封させて発動させる方がよいと思う。なにより先に指揮統率の構えを整えることが絶対に必要だ。それがバラバラではとんでもない、こんな感慨を強くもった。この忙しい最中に防衛政務次官が来るという。出迎えてくれというから行ってみると、連絡なしに別のところに着いて勝手なところへ行く。運輸大臣がきて、「銭のことは心配せず、救助救難に全力を尽くせ」と。ところが後始末になると、費用の3分の2は日航に出させ、3分の1は地方交付税のなかの特別交付税(地方自治体で分けて使う地方の金)で賄え、と。結局国は出さない。
中曽根総理大臣は11月4日にきて調子のよい挨拶をし、感謝状を乱発して帰った。総理は8月15日に軽井沢でゴルフをしていた。なぜその日に、あるいは落ち着いてからでもこなかったか。聞けば支持者からの忠告で、次の参院選で息子を出す都合上きたらしい。そして(尾根までの)「道はつくる」と言明したがなにもしない。道をつくるのは結局、日航とボーイング社に10億出してもらった。貧乏村からも何千万円も出した。知事も1千万円出してくれた。
|
| 「慰霊の園」の設立 |
身元の分からないご遺体の葬送の責任は法律上は上野村の村長にあるから、年末までに県下の火葬場で荼毘に付し私の村で永久に供養することになった。そこで問題は納骨堂の場所と資金の工面だ。そこに通じる山道は国有林の中だから、国から土地を借りる手続きがいる。急がないと翌年8月に一周忌がくる。救難作業の渦中に霊を慰めに行って落岩で亡くなった人もいる。もし来年お参りに来られたご遺族に事故でも起こしたら、これこそ村の恥、私の責任だ。また、葬送の法律上の責任があるとはいえ、村の予算で直接に実行すれば将来必ず、
「村に直接関係のない遭難者の葬送は丁寧にやりながら、なぜ戦没者に対しては一般会計で処置できないのか」 という疑問が残る。靖国神社の公式参拝はいけないとか、市が忠霊塔を建てた費用を返せという裁判が起こる中では私どもはそれができないから、一般会計から社会福祉協議会に補助を出し、協議会の名で慰霊祭を行ってきた。それとの比較で村民に疑問や不満が起これば、日航機事故の方々に対する慰霊行事もやり難くなる。それを長続きさせ、かつ戦没者とのバランスがとれるようにしておくことが私の務めだと思って、別に財団法人「慰霊の園」を設立することにした。これらの問題が12月にかけて表面化した。そこで日航の社長と話し合い、供養に万全を期する主旨から10億出していただいた。道については、観光地にされることを恐れるご遺族の強い要望から、自動車が通るほどの道にはしないことにしたので、10億で道と墓所ができる。永代供養の基金には村からの拠出金や浄財を集めて2億円ぐらいをつくった。
ところが、財団法人をつくるのに県との折衝に時間がかかった。国有林から土地を借りる問題もスムーズには進まなかった。3月の雪解けには工事にかからないと8月に間に合わない。県のほうはようやく許可がおりた。国有林のほうはもっと面倒だった。下っ端の役人がちっともハンコを押さない。営林局長に、「間に合わなかったら林野庁長官が国会で吊し上げられ世論に叩かれるぞ」と言ったらその日のうちにすんだが、切る木の対価が高いということを言う。「あんな雑木に値打ちがないことは上野村の住民ならよく知っているぞ」と言ったら10分の1ぐらいになった。墓所の土地は所有者からわりあいスムーズに買い取った。
こうして昭和61(1986)年3月には御巣鷹の尾根への道づくりと納骨堂を中心とする墓所の造成がはじまり、なんとか8月3日に完成式典を挙げることができた。3日にしたのは、その月の12日ではおそらく各家庭で法要が営まれるのでご迷惑になるだろうと思ったからだ。式典を済ませ、これで責任が果たせたような感じをひそかに持った。 |
| 村長の心残り |
その頃、私が良心の呵責に耐えなかったのは、戦没者への処遇があまりにも疎漏なことだ。これでいいのか。遭難者の霊を祀ることは上野村民できるだけのことをして、世に生きる者の務めを果たしたい。同時に、こんにちの日本の礎となって亡くなられた戦没者に対する祀りを忘れてはならない。この人たちの犠牲の上にこんにちの日本が築かれている。村の忠霊塔に祀られている人たちはわが村民であり身内だった。私の弟もいる。それをきわめて軽く扱う、というのでは村民感情が納得しえない。これは私の村政で片をつけておかなければならない。そこで、昭和62年度予算で忠霊塔を慰霊の園と同じ山の別の面に移設し、10月17日に竣工とともに追悼祭をやる。同時に私は、もうこれ以上、上野村は一般会計の金を追悼会や慰霊祭に出すことを遠慮する必要はない、堂々と戦没者の霊を祀り慰めるとともにたくさんの人にお参りしていただき、「ただ平和、平和と唱えていても平和はこない。これを繰り返さないよう反省し、民族間の対立を力で解決しようとする態度を改めるよう悟りを開かないとダメだ」ということを皆さんにも伝え、永くそのことを書き残したいと思っている。忠霊塔の周囲は、質素ながら霊園らしく飾るようにつくった。形だけでなく祀りの精神を塔のように高くもち、戦没者、日航機事故どちらの霊も祀り慰めつつその教訓を語り継いでもらいたい。
私の村は「日本のチベット」と言われるが、山奥の人間は隣人と協力しなければ生きてゆけない。他人のありがたさをしみじみと感じつつ生きているのが、農山村の住民だ。そのよさを今後も持ち続け、そこにお入りになった人の霊を慰め、残った人たちを守り応援しながら務めを果たしたい。それを通じて、ともすれば俺さえよければいい、他人のことは構わないという人間が多くなった日本社会に、戦争を生き残った人間のひとりとして、多少なりとも光をかかげてまいりたい。〉
黒澤村長の講演は以上である。いざ、未曽有の大事故が起きたら対策本部が乱立し、しかもそれらが全部縦割りで横の連絡がないこと、自衛隊と県警の機動隊が協力して造ったヘリポートも県警は使えない、忙しいなか村上正邦政務次官がやってきて、出迎えを要請しながらそこには現れずに勝手に行動する、「銭のことは心配するな」と威勢のいいことを言いながら結局、金は出さなかった山下徳夫運輸大臣……。現場の村長の立場で指揮を執りながら、縦割り行政の弊害や政治家に翻弄されたいらだちが伝わってくるようだ。 |
| 「国民のかたまりが天皇と思えばいいんだ」 |
| 事故処理も峠を越えた昭和60年10月30日、黒澤村長は天皇主催の秋の園遊会に招待された。「『事故のあとはどうなっているか』というようなお言葉だったと記憶しています。私は、答える前に涙が出そうになってね、かろうじてお答え申し上げたんですが。陛下(昭和天皇)は、われわれにとっては、命がけで日本の将来を救ってくれた方ですよ。戦争中、私は軍人だったが、天皇は神であるというような考え方にはついていけなかった。これは、海軍の軍人ならみんなそうだったと思います。要は、国民のかたまりが天皇と思えばいいんだ、と。その国家という、依存すべき社会を守るためにわれわれは戦うんだと。陛下は、ほんとうに『私』ということをお考えにならない。接してみるとその人格が伝わってきて、尊敬の念が自然と湧いてくるし、畏れさえ感じます。指揮官にしても、政治家にしても、人の上に立つ人の条件は『無私』ということですよ。もちろん、私心が全くゼロでは生きられないし、昭和天皇のようにはなかなかいきませんが、身を捨ててでも周囲をたすける気持ちがないといけません。ひるがえって、昨今の自治体首長や政治家をみると、やれ賄賂だ選挙違反だと、あんなのが社会のリーダーだというのは情けないですよ。国会議員なんてクズ中のクズだ。財界のほうが頼りになる。なんたって、死ぬか生きるかの自由経済のなかで勝ち残っていく人たちだから……。私自身の目標として、首長に必要なのは、私心がないこと、やる気があること、指揮統率力があること、その3点だと思っています」。 |
| 村長を引退した理由 |
| そして2005(平成17)年、91歳の黒澤氏は、6月の任期切れを最後に村長を引退、後進に道を譲ることを宣言した。村長としての在任期間は10期40年におよび、日本の地方自治体首長として最高齢だった。
黒澤氏が、引退を決意した理由として私に話したことの第一は、高齢となり、足腰が弱って、日航機事故の慰霊祭が行われる御巣鷹の尾根へ自力で登ることができなくなったことだった。「いかにも黒澤さんらしいな」と、私はそのとき思った。黒澤氏は以後、いっさいの公の場から身を引くが、それでも最後まで、上野村では「村長」と親しみを込めて呼ばれていた。2011(平成23)年12月22日、死去。享年97。98歳の誕生日を翌日に控えていた。黒澤氏の訃報は、24日付の新聞各紙やテレビニュースでいっせいに報じられたが、亡くなってから1日おいての発表は、23日――この日は黒澤氏の誕生日でもあるのだが――の天皇誕生日の祝賀気分に水を差さまいという、黒澤氏らしい配慮なのでは、と、近しい人は噂しあった。黒澤氏の葬送は近親者のみで行い、翌2012(平成24)年1月22日、上野村立上野中学校の体育館で、改めて黒澤家・上野村合同葬が盛大に執り行われた。上野村は、現在も鉄道のない交通不便な山村だが、それでも降りしきる雪のなか、村人総出で道案内にあたり、体育館は500名を超える参列者であふれた。焼香の列に並んだとき、私の真後ろにいた村の人が、「これで、上野村の一時代が終わってしまったということだな」としみじみ話していたのが心に残った。 |
| 黒澤氏が遺したもの |
| 日航機123便墜落事故から38年――。遺族の高齢化が進み、いまやJALグループでも、事故当時を知る社員はほとんど残っていないという。だが、上野村に「慰霊の園」があり、慰霊追悼式典が行われている限り、ここで起きた悲劇が忘れ去られることはないだろう。恒久的な追悼施設の建設は、自らが亡きあとも永久に事故の記憶を風化させまいという、黒澤氏の強い意志によるものでもあった。犠牲者への哀悼とともに、自らのパイロットとしての戦争体験を胸に、後半生をかけてこの事故と誠実に向き合い、遺族に寄り添い続けた地元の村長がいたことも、記憶にとどめておきたいと思う。 |
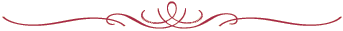
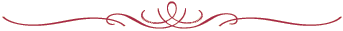
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)