1985.9.14日、中間報告が出され、これを境に事故調の委員長及び委員の半数が、任期で交替している。
1987.6.19日、事件から2年後のこの日、運輸省航空事故調査委員会が、橋本運輸大臣に事故の原因に関する報告書を提出し公にした。事故原因について次のように結論づけている。
| 運輸省航空事故調査委員会の報告書考 |
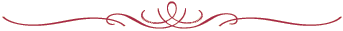
更新日/2023(平成31. 5.1栄和元/栄和5).2.10日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、当事故事件を調査した運輸省航空事故調査委員会の報告書の中身を確認しておく。何故、ブラックボックスが公開されないのか? 何故、無編集のボイスレコーダーが公開されないのか? 2010.08.16日 れんだいこ拝 |
![]()
|
【運輸省航空事故調査委員会の報告書考】
|
||
|
事件後、航空管制を監督する運輸大臣直属の常設機関である航空事故調査委員会が設置された。委員は委員長を含め定員5名。武田峻委員長は前宇宙技術研究所長だが、委員には航空局OBが2人入っている。航空機事故調査委員会はいわば身内を裁く委員会となるから、事故原因調査にあたってその独立性を保持せねばならぬところ、独立性に大いに疑問がある構成となった。
1985.9.14日、中間報告が出され、これを境に事故調の委員長及び委員の半数が、任期で交替している。 1987.6.19日、事件から2年後のこの日、運輸省航空事故調査委員会が、橋本運輸大臣に事故の原因に関する報告書を提出し公にした。事故原因について次のように結論づけている。
これによると、JAL123便は、ハイドロプレッシャーダウン(油圧系統のダウン)により機体後部の圧力隔壁が破壊されたのが原因で垂直尾翼が3分の2損傷し、墜落したと推定されている。即ち、「後部圧力隔壁の破壊に伴う、垂直尾翼を含む機体後部の破壊」としている。これを仮に「圧力隔壁破壊説」とする。しかし、航空機の垂直尾翼は非常に頑丈なものであり、機内与圧空気の急激な噴流などで壊れたとする報告書に疑問が投ぜられている。生存者の落合由美氏は、「乗客は降りてきた酸素マスクは当てているが、混乱はなかった」と証言しており、機内に急減圧が起きているフシはない。我々は単刀直入に垂直尾翼が破壊された原因を考えねばなるまい。これを常識的に考えると、何らかの飛行物体が尾翼にぶつかったのではないかということになる。事故調査委員会は、外部原因説の可能性に一切言及せず、内部原因説の「後部圧力隔壁破損説」を固持し続けている。その癖、相模湾に落ちた垂直尾翼や 尾部胴体 、その他多数の部品についても解析と調査を まったく行っていない。 |
| 【日航乗員組合連絡協議会の報告書考】 |
| 日航の従業員組合の組織、日航乗員組合連絡協議会は「急減圧はなかった」と結論したレポ―トを発表している。 被害者の遺族たちは、1999年1月に事故原因再調査要求を提出した。しかし、事故調査委員会はこれを完全に無視し今日に至っている。それどころか、1999年11月、情報公開法施行を前にして、JAL123便墜落事故関係の全書類をにすべて廃棄処分にすると云う挙に出ている。その重量は1160キログラムであったと云う。一体何の為に証拠書類をすべて廃棄処分にしたのだろうか。既に多くの識者が、「高度高度24000フィート(7200メートル)の上空で飛行機の垂直尾翼に飛行機かミサイルのような謎の飛行物体が激突した」可能性について言及している。一体誰が何の為にと云う「もう一つの推理」までは避けているが、外部原因説は既に衆知の事実のように思われる。 |
|
|
| 雫石事故とは71年、全日空機のジェット機727型機に航空自衛隊のF86F戦闘機が衝突した事件である。この時、自衛隊は全日空にも管制にも訓練を報せていなかった。この時、ある疑いがもたれた。自衛隊機が民間機の全日空機を敵機に見立てて戦闘訓練をしていて誤って衝突したのではないかという疑惑である。乗客乗員162名が死亡。この時は航空幕僚長の辞任で収まっている。運輸省管轄の航空事故調査委員会はこの事故をきっかけに誕生している。 |
2021.8.11日、「日航機墜落 事故調査官100ページの手記に書かれていたこと」。
|
「★阿修羅♪ Ψ空耳の丘Ψ9」の「一刀斎 日時 2000 年 8 月 12 日」「日航ジャンボ機 御巣鷹墜落事故 事故調「圧力隔壁説」と食い違い本紙入手ボイスレコーダ記録で判明(赤旗)」。
|
|||||
| 「隠された証言 日航123便墜落事故」(藤田日出男)によれば、事故調報告書・資料は「情報公開法」が施行される前に廃棄されたが、関係者がその一部を持ち出して同氏のところへ届けた。藤田氏は日航のジャンボ機の元パイロットの経験を元に圧力隔壁破壊説を否定している。例えば事故機の機内で撮られたカラー写真、破壊で垂直尾翼吹き飛ぶ程の風圧があったのなら、乗客や機内の物が機外に吹き飛ばされても不思議ではないが整然としている。当日非番で事故に搭乗していたキャビンアテンダントの落合証言によると、急激な減圧は一切なかったと発言している、パイロットは全く酸素マスクを装着してないと思われる。垂直尾翼の方向舵は上下2枚あるが、擦れたような跡がある。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)