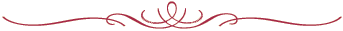
| れんだいこのイエス教・キリスト教論 |
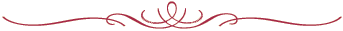
更新日/2018(平成30).2.25日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、れんだいこのイエス論、イエス教論、キリスト教論を書きつけておく。何事も奥深き真実は言葉や文字にしにくいように、本稿のテーマを書き記すには隔靴掻痒の感がある。何度も何度も書き換えて次第に真に云いたいことに近づけようと思う。 2006.8.21日、2006.11.1日再編集、2013.2.1日再編集 れんだいこ拝 |
| 【はじめに】 |
| いよいよイエス/キリスト考に入る。初めにお断りしておくが、れんだいこは、キリスト教については門外漢である。思えば、中学生時代に聖書を読んだ。小さな字でびっしりと書かれたものを読み、何やら半分判ったようで分からない読書体験であった。それから以降はマルクス派になったので敢えて読まなかった。 ところが、50代半ばの今2004年、折からの「9.11米国同時多発テロ事件」、タリバン政権懲罰アフガン戦争、フセイン政権懲罰イラク戦争、イスラエルによる残虐非道のパレスチナテロの流れと仕掛けを思うにつき、否応なく現代世界を牛耳る国際金融資本に目が行かざるを得なくなった。その表出権力体「米英ユ同盟」を眼前に据え、如何に闘うべきか問わざるを得なくなった。 現代史を理解する為に「シオンの議定書」に注目し、その歴史的流れを追わざるを得なくなった。「シオンの議定書」の流れは存在する、そう思うようになったからである。そこで気づいたことが、かってのイエスは、当時におけるネオコン族であったと考えられるパリサイ派と律法学者同盟の悪魔主義的選民論理に徹底対決し、論駁でもって彼らを徹底的に震え上がらせた稀有な超能力者ではなかったのか、ということである。そういう訳で、ならば、イエスが具体的にどう弁証していたのか行状も含めて知りたくなった。 当時のパリサイ派と律法学者同盟、後の「シオンの議定書」派、そして今日のネオコンに至る系流は歴史的に一貫してサタン思想に被れている。今日ネオコン一統が世界で為している残虐非道ぶりを見よ。これは昨日今日始まったことではない。深い歴史的な伝統を持ち続けていることが判明する。本当にそうなのかは別として残念ながら、この流れが人類智の最高の頭脳を形成しているようにも思われる。彼らは現代社会の全分野で支配権を確立し栄耀栄華をほしいままにしており、今や、この連中のものの見方、説教がメディアを通じて不断に流され続け、人は容易にこれに汚染され、マインドコントロールされている。人類はこのまま彼らの頭脳、仕掛けに誰も太刀打ちできないのだろうか。 れんだいこは、天理教開祖中山みきについてはそれなりに研究してきた。その成果を生かしつつ、こたびイエス論/キリスト論を書いてみようと思う。興味深いことに、イエスとみきはかなり思想的に近接している。歴史的風土及び伝統に規制されてと思われるが、双方の御教えには若干の差があるが、本質的には同類の共生思想を福音していたように見える。みき論の時にも述べたが、だがしかしみきがみきのままに論ぜられてはいない。イエスについても然りではなかろうか。そう思う故に、れんだいこの観るイエス論を綴ってみたいと思う。れんだいこは、キリスト教については門外漢であるが、キリスト教団公認イエス論より案外イエスの実像に迫っているのではなかろうかと自負している。どこがどう違うのか以下創書する。以上前置きしてれんだいこ式イエス・キリス論の考察に入る。 2004.10.27日 れんだいこ拝 |
| 日本は今、確実に滅びの道に誘われつつある。それを促す裏政府権力の強さと彼らの狡知による仕掛けを思えば、もはや抗う術はないのかもしれない。しかし、不思議の神州国日本はやはり再生するだろう。その時の心強い史実に「かの時のイエスの格闘」がある。刻まれているこの歴史を学ぶべしであろう。歴史上のイエスを極力実像で捉え返してみたい。そういう思いから、「イエス論、キリスト論」をサイト化することにした。 サイト名称を「イエス教論、キリスト教論」としたのは、イエス教とキリスト教が大きく異なるためである。れんだいこは、イエスの御教えを画然とさせ、それが現代につながる「パリサイ派サタ二ズムに対する神の側からの駁論」であることを伝えたいと思う。あまた神父が居るが、何らかの規制があるだろう、こういう風には問いかけられないみたいである。そこで自由人れんだいこが斬り込むことにする。 この問題で最初に留意すべきは、イエス教論とキリスト教論の差異であろう。これまでのキリスト教学は、イエスをキリストになぞらえ、キリスト論に傾斜してきたきらいがある。れんだいこは、それは違うと思う。我々は、イエス教論にこそ熱中すべきであり、ユダヤ教パリサイ派の教説を取り入れた故のキリスト教論に深入りすべきではない。歴史は、この逆のことばかりをやってきた。お陰で、キリスト教はイエス教の真実を曇らし、これが為に本来はユダヤ教が負うべき偏執性を身につけさせられ、本来ユダヤ教が負うべき教義批判をユダヤ教に代わって引き受けさせられるという損な役回りをさせられている。この虚構の解体とイエス教の再生こそ目指すべきだろう。 2004.11.14日、2010.06.21日再編集 れんだいこ拝 |
| れんだいこのカンテラ時評№1100 投稿者:れんだいこ 投稿日:2013年 2月 2日 |
| キリスト教の親ネオシオニズム性考 2012総選挙の八百長性に関心を持って以来、その後の政治に同様の臭いを嗅ぎまともに論評する気になれない。こういう時には原理的な問題に関心を寄せることにする。先にマルクス主義の「労働者は国家(祖国)を持たない」に端を発する愛国民族主義問題を検討したが、ここでは世上で云われているキリスト教のそれについて解析してみる。 その実践的意味は、キリスト教信仰者(キリスト教徒。これを俗にクリスチャンと云うので以下クリスチャンと記す)が日本の国家中枢各機関に進出することの危険性を危ぶみたい故である。彼らには特有の売国的傾きが見られるからである。「彼らに特有の売国的傾き」は他の出自分野でも認められる。これらは現代史の第一級課題となっているのではなかろうか。 れんだいこのこの危惧を裏付けるかのような次の一文に出くわした。2012.7.7日付けブログ「保守派政治家にクリスチャンが多い理由」が次のような問いを掲げている。
上記文に登場している政治家はごく一部でしかない。精査すればもっと多くの与野党問わずの政治家が確認できよう。上記文は現首相の安倍、次期首相の呼び声の高い石破をクリスチャン政治家として挙げているところに意味がある。このことは実は怖い話しである。 もとより信教の自由は認められるべきであるから政治家のキリスト教信仰自体に非はない。問題は、クリスチャンがこぞって日本の伝統習慣法律を軽視しあるいは反逆するように意識づけされていることにある。これは、日本史上の戦国時代の宣教師(バテレン)渡来時にも発生したことである。かの時、キリシタン大名下の軍兵が各地の神社仏閣を焼き打ちしたことは知る人ぞ知る史実である。結果的には神社仏閣側が反撃し、良し悪しは別として鎖国に至る過程でキリシタン狩りが数度となく行われ、その動きが封殺されたことは衆知の通りである。この問題は、近代以降の西欧列強の世界分割植民地化の先兵として宣教師(バテレン)が活躍した史実と照らし合わせた時、深刻になる。 キリスト教問題はその親ネオシオニズム性にある。しかしてネオシオニズムは歴史的に見てユダヤ教パリサイ派特有のものである。クリスチャンも又通俗マルキストと同様に国家(祖国)を持たない。代わりにユダヤ教パリサイ派的世界秩序理念に従い、その国際センターの指導に一元的に服する傾向が強い。代わりに出世登用が約束されており、その餌を求めて魂を売るクリスチャンが多い。非クリスチャンに比べてクリスチャンには何重にもサロンへの誘惑が多く結社加入の機会が敷かれている。これによる組織盲従性が政治問題化されねばならないと考える。その昔、イエスがその誘惑のワナから逃れたのは「荒野問答」で知る人ぞ知る逸話である。 理論的に見て、どうしてこういうことになるのだろうかと問いたい。結論を先に述べれば、キリスト教は開祖イエスの御教えを部分的に取り入れながらも構図的にユダヤ教化されたキリスト教であり、開祖イエスの教えに基づくキリスト教ではない。むしろキリスト教はユダヤ教パリサイ派教義に取り込まれており、ユダヤ教パリサイ派の系譜をひく国際金融資本全盛の現代ではなおさらその傾向を強めつつある。これ故に学べば学ぶほどネオシオニズム化されたクリスチャンが生まれることになる。こうなるとクリスチャンと云うより新たにシオ二スタンと命名した方が適切であろう。そういう意味で新たにシオ二スタンなる呼び名を造語した。この謂いの妥当性はキリスト教教義の解析により判明する。これについては「イエス伝福音書考」で論述している。 要するに、キリスト教教典の第一章が旧約聖書として天地創造から始まるユダヤ教の教典を掲げているところが臭い。イエス教教義であれば、ユダヤ教教典は参考資料にはなってもイエス教教義として取り込まれる筋合いのものではない。そもそも独善的な選良意識を基底に形成されているユダヤ教教義に最も厳しく対決したのがイエスなのではないのか。そういう意味でイエス教であるならばその教義にユダヤ教教典の入り込む余地はない。本来ならイエス教祖伝が編成され、キリスト教教典第一章の地位に治まるべきところである。実際はイエス教祖伝が隠され、その代わりに旧約聖書が拝戴されている。そういうすり替えが行われている。 しかして、このことを誰も訝らず今日まで通用している。これによりキリスト教徒は不断にのっけからユダヤ教教育を余儀なくされている。この不正を糺さねばならない。その旧約聖書の解釈を廻ってキリスト教新派が数多く生み出されているが、本来確立されるべきのイエス教の見地からすれば何の意味もないことである。宗教的音痴の為せる技でしかない。 キリスト教をかく解析したのは、既に為されているのかも知れないが少なくとも流布されていないので、れんだいこの功績だろう。キリスト教渡来より数百年、ようやくキリスト教が何者なのか解析し得たと自負している。「れんだいこのキリスト教論」が成るほどのものだとすれば、開祖イエスの御教えに基づかないものを基づいているとして奉じていて良いものだろうかと根本疑惑せねばならないことになる。既に数千年来そのようなキリスト教が流布されているのであるが、ならば本当のイエス教とはどういうものなのか、かく関心が進むべきであろう。これが自然な論理の流れである。 この作業はさほど為されていないように思える。そこで、つたないながられんだいこが挑んでいる。一応の書き上げが「別章【イエス教論・キリスト教論考】」である。今後は誰しもこれを下敷に論を更に精緻にして行くが良かろう。 |
| 【週刊ポスト記事の日和見論評考】 | ||||||||
上記文の補足をしておく。いずれも週刊ポスト記事である。日本政界におけるクリスチャンの進出ぶりを日和見的に評論している。もっとも、こういう問題を取り上げたことに意味を見いだすべきだろう。
|
| 【最近のイエスの聖像否定の動き考】 | |
2006年、幻の書と云われる「ユダの福音書」公開、ダン・ブラウン著「ダ・ヴィンチ・コード」発刊、映画「ダ・ヴィンチ・コード」封切り、「イエスの王朝」、「イエスの血統」、「聖母マリアをめぐる沈黙の陰謀」等々、イエスないしは初期キリスト教への関心が高まった。2006.8.19日付け日経新聞文化欄は「イエスの物語、異端に脚光 初期キリスト教見直す」(編集委員・河野孝)の見出しの記事を掲載し、次のように記している。
その通りである。イエスを実像に合わせて捉え返さねばならない。問題は、キリスト教に関する2006年の動きが正しい理解の方向に向かおうとしているのや否やにある。れんだいこの見るところ、イエスの聖像否定に主眼を置いており、それはそれで構わないのだけれども方向が怪しい。ユダヤ教のタルムードに記されるイエス像に向かおうとしており、その結果却ってイエスの実像からますます離れるのではなかろうかと危ぶむ。この流れを「現代パリサイ派による謀略的イエス聖像剥離の動き」とも読み取ることが可能で、そうなると対抗上「れんだいこのイエス論」を更に練り上げねばならない。 思えば、1911(明治44).1月、当時の日本左派運動随一のイデオローグであった幸徳秋水が大逆罪で死刑に処せられたが、幸徳は獄中で遺稿集となる「基督抹殺論」を書き上げていた。これが刊行されたのは処刑の翌月2月であった。以来、日本左派運動のイデオローグがキリスト論を書く作風は継承されていない。覚束ないながら、れんだいこが受け継ぐことにする。 イエスとキリストの関係は「イエスとキリストの関係考」で考究しつつある。それを踏まえて思うことは、我々はイエスの足跡とイエスの教義をこそ究明すべきで、生身のイエスをないがしろにしたキリスト論は神学的迷路に誘われるだけなのではなかろうか。ところが、史上為されていることは意図的にキリスト論の方であってイエス論ではない。それはイエス隠しであり不正である。れんだいこはむしろ、イエス論、イエス教義論こそ追求していくべしと考えている。 キリスト教的神学研究は相当程度為されている。反してイエス教義の研究は覚束ないように思われる。れんだいこにはなしてこうなるのか分からない。その優秀な頭脳をなしてあらぬ方向に費消しようとするのかが分からない。この現象はイエス教義のみではない。世に有益な思想は殆どそのような運命を辿る。マルクス思想も然りで、いわゆるマルクスも辟易したマルクス主義の研究が進む割にはマルクス思想そのものの研究が深められない。そういう事例に似ている。中山みきの例にも似ている。みきの御教えそのものが信仰されず、本部教理が一人歩きしている。世の中にはこういう事例が溢れているが、なぜこうなるのだろう。 もう一つ疑問がある。その結果、本来に於いては明解に語られていることが次第に難しくされている。その難しさを廻って解釈が始まり、その解釈を廻っての更なる解釈が始まる。気がつけば、事情に疎い者は参加資格がなくなり敬遠するしかなくなる。お定まりはいつも、創始者の最初期の生命力のある諸言説が曖昧模糊にされてしまう。いわゆる著作権がこの傾向に更に輪をかけ、議論の通交を妨げる為に一役買っている。自称知識人が著作権にことのほか執着している。れんだいこは、そういう不毛を質したいと思う。 もう一つ言い添えておきたい。我々は、イエスの何を知ろうとするのか。福音書その他外典から学ぶのに、人はイエスの1・神性、2・予言、3・奇跡、4・人品骨柄を知ろうとして熱心なように思える。本当はそれさえ曖昧なのだけれども。れんだいこ観点は違う。知るべきはイエスの足跡であり教義であり問答であり、主としてパリサイ派に対する論難の仕方の方ではなかろうか。 パリサイ派の末裔ロスチャイルド一派が近世になりシオンの議定書を創案し、これに基づく世界支配構想で世界を席巻していった近代、更にその末裔が今日ネオコンとして立ち現われ、ネオシオニズムによる世界支配最終戦争に打って出ている狂気のアジェンダ時代に突入している現代、彼らネオシオニストが世界各地に戦争を強いている今日、2千年昔にこの流れの起点者と最も果敢に闘ったイエスの戦いザマこそ知るべきではないのか。 このように立論する時、不思議なことに市井のイエス・キリスト論は膨大な量を数えているにも拘らず何の役にも立たない。むしろ意識的に余り意味をなさないイエスの1・神性、2・予言、3・奇跡、4・人品骨柄にばかり耽溺しているように思われる。れんだいこは、イエス教義、問答、論難の解明に向かわないイエス論はイエス・キリスト論のねじ曲げだと思う。そろそろそういう時代に断を下したい。 2004.11.13日、2007.2.26日再編集、2013.2.1日再編集 れんだいこ拝 |
| Re:れんだいこのかんてら時評261 | れんだいこ | 2007/02/26 |
| 【解せないいつまで経っても参考書、解説本、その又参考書の繰り返しについて】
これもいつか云いたかったことだけれども、原文もしくは本人にいつまで経っても当たらず、その参考書を読み、その解説本を読み、又もや参考書を欲するという、原書ないしは本人不在のこの現象は何なんだろう。これは単に性分の差なのだろうか。 仮に、イエスの場合なら、少なくとも4種の福音書がある。イエスを知ろうとするならそれらの福音書を読むことから始めねばならない。それぞれのイエス像があるなら、本当のイエス像を訪ねればよい。それは結構楽しいことだ。そんなに分厚い分量ではないのだから読めばよいのに。まずここができてから、弟子の著作に精通すべきだろう。イエスを知らぬままに弟子の膨大な資料に頭でっかちになっても、どっか違んだな。たいして意味はないと思うのだけれども。 マルクスの場合なら自身の著作がある。それを読めばよいのに解説本ばかり読もうとしている。なぜそういい切れるか。それは、和訳本の場合、恐らく故意にだと思うほど意味が通じにくくされており、そんなものを読んで分かったつもりになっていること自体が臭いから、結局読んでないんだ。れんだいこは、共産主義者の宣言、資本論のほんの前半部、その他数点を訳してみたことで自信を持ってそう言い切れる。 本当に読んでたら、既成の訳本のオカシサが事件にされている筈だから。にも拘らず、原書ないしは適訳書を求める声は少ない。もっともらしい解説本は多いが、これも分かったつもりにされるだけで、本当は小難しくされているだけである。原文の方がよほど論理的でリズムがあってすっきりしてらぁ。とにかく、原書不要にされ過ぎている。そういうオカシサが通用している。 中山みきの場合、自筆のお筆先と側近が聞き取りしたみ言葉がある。まずは何でもこれに目を通せば良いのに、どこまでが教祖みきの本当の言葉なのか判然としない。しないまま信徒形成だけが進んでおり、結果的に停滞している。この間任意なみき像が勝手に一人歩きしている。イエスもマルクスもみきも、れんだいこは当の人の本当のところの発言、意味、意思を尋ねてみたい。その吟味なら努力を惜しまない。これって真っ当なごく自然の欲求なんだけれども、どういう訳か研究が進んでいないように見える。関連書はあまた有り過ぎるほどだというのに。この現象って何なんだ、性分の差かなぁ。 2007.2.25日 れんだいこ拝 |
||
| れんだいこは今再びイエスの門を叩きたくなった。直接の契機は著作権法と苦闘し始めたことによる。著作権法とイエスと何の関係があるのだろうと訝る向きもあろうが、れんだいこはあると考えている。れんだいこが、現代強権著作権者の全方位全域著作権論と抗する時、それがいわゆるネオシオニズム派の狡知に基くものであり、彼らの典型的な論法、商法であることを見て取っている。そうであれば、かの時、そういうパリサイ派の思惟様式と最も徹底的に闘ったイエスの論難弁舌、思惟方式を学ぼうとするのは当然であろう。そういう意味で、再度イエスの論理論法が知りたくなった。著作権論と直接的には関係しないが思惟作法は普遍的であり、これを深く学ぶことで著作権論にも応用が効くと考えているからである。れんだいこのイエス学にはそういう意味と意義がある。 イエスとパリサイ派の最大の違いを確認しておく。れんだいこは、思惟様式を共生志向させるのか=イエス派、選良志向させるのか=パリサイ派にあると考えている。この打ったての違いが、我々の処世法、学の違いとなる。打ったて論はそれほど重要な意味を持つ。イエス派とパリサイ派は互いに抗争、混淆しつつそれぞれが膨大な学的体系を構成している。両者は、打ったての違いにより交わらない。れんだいこには、そう見える。 れんだいこは、学生時代のようにマルクス的階級闘争論に耽るのも良かろうが、イエス対パリサイ派の抗争論の方がもっと大事と考え始めている。ここに目が行かない思想は二級品以下のものでしかないと考えている。目下、著作権論に関心を深めているが、この問題で云えば、パリサイ派式強権著作権論に抗する為にイエス派式解放式著作権論を早急に打ち立てねばならないと考えている。この面が細いので、人民大衆の頭脳域が非常に狭められ、生活逼迫に加えて思惟空間までが非常に抑圧させられつつあると見立てている。著作権論にはそういう重要性がある。そういう理由から、再々度本稿を手掛けることにする。 2008.3.11日 れんだいこ拝 |
||
| 【イエス論理とパリサイ派論理の根源的対立考】 | |
| 「シオンの議定書」派の現代嫡出子であるブッシュ派は、やること為すことの全てがそうで、かなり強烈且つ特殊な宗教に被れているに相違ない。紛れもなく歴史的な意味でのサタン思想に捕囚されている。現在アメリカを本拠地として新種キリスト教が瀰漫しつつあり、俗にキリスト教原理派ないしは福音派と総称されているようである。が、何で原理派であるものかは。彼らは2004年の大統領選でもブッシュを肩入れしたようであるが、サタン被れのブッシュ支持に向うキリスト教原理派なぞあり得て良い訳がない。それは存立矛盾だろうに。 それというのも、キリスト教の何たるかを廻ってその理解が滅茶苦茶で、本末転倒事態が起こっているからであろう。そう考えないと理解できない現象である。しかし、用語の不正確さは意図的に撹乱されている可能性が濃厚で、現代サタン派によるマインド・コントロール攻勢が仕掛けられていると読むべきかも知れない。そこで、れんだいこは、元々の原義において、キリスト教とはそもどういう教義なのか、その開祖イエスとはどういう人物であったのか検証してみることにする。 2004.11.11日現在のことであるが、イラクのフセイン政権を強権的に打倒した米英ユ連合軍が依然続くイラク人民のレジスタンス活動に業を煮やし、イラク中部の都市ファルージャに総攻撃を仕掛けている。これを命令するブッシュの言い草はこうである。
我らが小泉君は一の子分の存在証明出番と心得て、又もやこれに逸早く追従し、概要「成功させないといけない。治安改善がイラク復興支援のカギだから」と述べ、盲目的に支持する見解を表明した。彼の論法を聞いてみたまえ。「イラクの為に」と云うところを「ブッシュ御一統の為に」と云いかえれば実に理解が容易になる。「苦しい時に手助けするのが真の友」だと。それはそうだが、迷路に入って苦しむのは自業自得と云うべきで、時には苦口を云ってあげるのも真の友だろうに。 考えてみれば、ブッシュの言い草は典型的なかのパリサイ派の論理そのものである。彼らは悪知恵の限りを使って強引に全てを逆に描き出し、強弁する。「イラク暫定政府の要請による」とは例の得手勝手に仕立て上げた錦の御旗論理の持ち出しであり、「罪なき人々を殺し、イラク国民や有志連合を脅迫し、民主主義を妨げようとする者たちを処断する」とは、己の悪行を他に転嫁しそれをもって攻める口実にする例の転錯サタン論法の典型であろう。 このサタンは、上述のような詭弁を弄しながら、昔から残虐非道な悪の限りを尽くすことで知られつつある。他には厳しく指弾するがおのれらはやりたい放題で一切免責という訳だ。現代軍事兵器の最高性能で爆撃を繰り返し、禁止兵器の戦術核兵器と毒ガスを意図的に使用し、無差別殺傷を何ら意に介さず、国際法違反の病院、学校、教会攻撃、市民殺戮を無慈悲に遂行し、投降兵の即時射殺、捕虜虐待を常習としている。 その手加減のなさ、確信犯的悪行ぶりは常人の域ではなく、可能な限りの残虐さを追求し、更に徹底しようとしている。彼らは常々堂々と「目的が是なら手段は無制限、否むしろあらゆる手段を使って徹底的に遂行すべし。中途半端がより悪い」論を唱える。これら全てがサタン論理であり、サタン被れを証左している。 これほどまでの非道さを傲然と為しえるのは、歴史上あの連中以外にはいない。当時も今もやっていることが何ら変わらない。彼らは、テロを口実にするが、歴史上テロの専門家はかの連中の方ではないのか。それは彼らの共同体内部でも血で血を争い、「主の怒り」を買うほどであった。そのテロリズムが外部の者に対して向うのも必然で、当然のごとく多くの犠牲者を生んできた。歴史にはその事例であふれている。その昔、「ユダヤの民の所払い」、「流浪の歴史化」、「ゲットー化」は案外と、その当時おいては故あることであり、それほどの怒りを買っていたせいかも知れない。 れんだいこはそう思うようになった。ユダヤの民が全てそうなのだとは思わない。れんだいこの敬愛する近世ドイツの哲学者フォイエルバッハはラビの家系の者であったが、この狂信論理から抜け出し改宗している。マルクスもこの系譜である。ルネサンス機運の高まりと共にかなりな改宗派ユダヤ人が誕生した。但し、偽装転向派と真性転向派に分かれるようである。だがしかし、近世から現代に至る過程でますます影響力を強めてきたのは原理派とも云うべきネオシオニストの方である。 それを思えば、ユダヤの民達は、彼らの信奉するユダヤ教、律法、タルムード、その他悪知恵言い伝えの中に潜むサタン論理を掣肘するものを持っていないのではなかろうかと見抜きたい。彼らの信仰の中に現下のネオコン的論理を生み出すものがあり、ユダヤの民の穏健派は急進主義的強硬派に対してそれを掣肘するものを持っていないのではなかろうかと見抜きたい。彼らは「勝てば官軍」で、威勢の良い間は栄耀栄華しようが、局面が変われば再々度「所払い」されることになるだろう。れんだいこは、どうか、その時、我が日本に大挙して押しよせてこないことを願う。 思えばかの日、イエスが登場した。ここにイエスの歴史的意義がある。この時、イエスは彼らにどう切り込んだのか、論難したのか。その鮮やかな切り口こそがイエスの魅力である。概要は「山上の垂訓」で知られている。イエスないしその御言葉がどのように受け止められたのか。イエスこそ真の神の聖者であり、イエスの言葉は永遠の命の言葉であるとして、感嘆と畏敬をもって受け入れられたことが伝えられている。 れんだいこが思うに、イエスの論証は一つ一つがもはや人智を超えた神の域の御言葉であった。サタン思想に打ち勝つ神の智恵の授けでもあった。つまり、イエスは、歴史上唯一サタン派思想の頭脳に打ち勝った稀有な頭脳の持ち主として登場したことになる。これが、イエスが占める史上の地位である。新約聖書各書はそれぞれのイエス伝を伝え、イエス教義はそれぞれの立場からそのことを明らかにしているが、必ずしもイエスのこの面の輝かしい功績を称揚し切れていないように思われる。むしろ、詰まらない方向への神学的議論に誘っているように見える。 イエスは、サタン派の論法と行いに対して徹底的に論難した。そしてこれを誰にも聞き分けできるように例えを用いて説法した。人民大衆は、それまでパリサイ派によって教えられてきた教義とイエスの教義の差に驚き、イエスの教えの方こそ真性の神の御言葉であるとして覚醒し、熱狂的に支持し始めた。当時の律法学者、パリサイ派らのサタン同盟はこれを見捨てておけず教義問答を挑む。しかし、そのたびに煮え湯を飲まされた。イエスの反論がことごとく彼らの臓腑を抉ったからである。 それは、サタン論理がイエスの精霊論理に勝てなかったことを意味する。そこでサタン派は遂に、イエスを捕捉し、あらん限りの辱めを施した後十字架磔刑で処罰殺害した。しかし、イエスは、このことを事前に予告していた。処刑後三日目に復活することも予告していた。 これがイエス・キリスト教創教の伏線となる。キリスト教は、そういう栄誉を持つイエスに端を発している。あぁ何と歴史は凄いのだろう。 2004.10.27日、2005.10.22日再編集 れんだいこ拝 |
| 【その後の宗教戦争史概括】 |
| イエスの磔処刑後の西欧宗教史を概括しておく。 イエスの死後、イエスの使徒達がイエスの行状と弁証を想起し、イエスをキリストとして再認識しつつ再結集した。そして、イエスの御教えを伝道して行った。次第に教義形成され、ユダヤ教に対抗する新教が生み出されていった。これがいわゆる原始キリスト教と称せられるものである。原始キリスト教時代にあっては、彼らは引き続きユダヤ教神殿派の律法学者、パリサイ派らのサタン同盟から迫害され続けた。 しかし歴史は面白い。各国の支配者が原始キリスト教団を取り込みし始める。それを、ユダヤ教義に対抗し得るイデオロギーとして利用し始める。各国の支配者は、それほどユダヤ教のイデオロギー攻勢に手を焼き続けていたことになる。しかし、イエス教義をそのまま受け入れる訳にはいかなかった。イエスの御教えからその革命的要素を骨抜きにし、それを応法的に改造する必要があった。キリスト教団は数次にわたる会議を通じてこれを上手く導き、カトリック教義を生み出していく。そういう意味で、カトリック教義の本質は、世俗の王権と神学的聖権との弁証的整合化にあるように思われる。カトリック教義はやがて国教的地位を勝ち取っていき、カトリックの本拠地バチカンが中世西欧諸国を律していくことになった。こうして、西欧中世期は宗教が政治を支配する時代となり、キリスト教は体制支配イデオロギーとして利用されつつ君臨していくことになった。 この間、ユダヤ教は社会の表舞台から遠ざけられ、長い雌伏の時代に入っている。キリスト教とユダヤ教のバランス関係は、その後数百年間にわたって、キリスト教優位のままに推移していく。このバランスに変化を兆すのがプロテスタント教義の誕生によってである。ルター派とカルビィン派は、あまりにも体制イデオロギーとして馴致されたカトリック教義に対して、原始キリスト教時代の御教えへの復帰を求めて抗議し始める。 この流れが、並行して開始されたイタリア・ルネサンスと結合し、歴史的転換を促し始める。イタリア・ルネサンスは西欧各国に飛び火していく。この経緯は同時に、雌伏を余儀なくされていたユダヤ教に再台頭の機会を与えることになった。以降歴史は、カトリック・キリスト教、プロテスタント・キリスト教、ユダヤ教の三者鼎立時代へと向い始める。 この三者鼎立時代が次第にユダヤ教の一強時代に傾いていきつつあるのが現代史のように見える。これを指導したのがユダヤ教内ロスチャイルド派であり、「シオンの議定書」で大指針を打ち出し、以降怒涛の世界革命に向うことになる。凡そこういう風に概括できるのではなかろうか。(以下略) 2006.3.20日再編集 れんだいこ拝 |
| 【キリスト教の「愛の思想」について】 |
| 東洋の我々からすれば、キリスト教もユダヤ教も同種の流れに有るように見える。しかし、イエスの生涯を検証すれば、同じ土俵では有るが、ユダヤ教義の選民思想、拝金祭壇主義、戒律主義、懲罰主義、報復主義に対して徹底的にそれを否定した新たな御教えであることが分かる。こうなると、土俵が一緒というのも変であるが、旧約聖書上の神の国思想、神と人との契約信仰という意味では同じ系譜であるように思えるので、同種の流れと見られても致し方なかろう。だがしかし、ことごとくが全く正反対の御教えである。このことが、イエス・キリスト教を理解する為のカギとなる。 イエス・キリストが歴史に占める評価を如何に確定すべきだろうか。れんだいこは、やはりその後の歴史に最大の影響力をもたらした最大の人と評したい。彼が人か、精霊の宿りし御方か、天の父の子か、主そのものかについては詮無い議論だと思うので避けようと思う。興味深いことは、その後形成されるに至ったキリスト教団は、こちらの方を廻って喧々諤々し、イエスが何を語り、何とどう闘い、後世の者に何を示唆したのか、肝心のここが問おうとしない。仮に問うたとしても、去勢された上での汎平和的愛の御教えのみ問いたがる。 一見、イエス・キリスト教は、いわゆる「愛の哲学」を説いているように思える。それは間違いない故にそう理解しても忽ちは支障ない。しかし、「愛の哲学」をそのまま字句通りに受け取って、闘う者に対して「武器を捨てよ」なる「のべつくまなき平和の思想」を説きまくるのがイエス・キリスト教だと捉えると違うのではないのか。イエス・キリスト教の「愛の哲学」は、イエスを取り巻いていた当時の世界の支配的思想であった「パリサイ派の偏狭なユダヤ選民思想の果実である報復哲学」と鋭角的に対峙して打ち出された「闘う武器」としての思想、宗教論理であり、そういうものとしての「繰り返す報復主義を超える愛の哲学」として解するべきではなかったのか。こう理解しないと、イエスの行状の真相が見えてこない。 にも拘らず、のっぺら棒な「愛の哲学」を説くのが神父の役目として受け取る教養主義的キリスト教のみが伝道されているような気がしてならない。あるいは又最近の新種キリスト教のように「パリサイ派の偏狭なユダヤ選民思想」と和合させたキリスト教がもてはやされつつある。これでは、キリスト教という名を被せているが、少しもイエス・キリストを理解していないのではなかろうか。キリスト教という名を被せているが骨抜きイエス論であり、少しもイエス・キリストの歴史的位相を理解していないのではなかろうか。れんだいこは、そういうイエス・キリスト教論を排斥し、イエスの生涯の軌跡と御教えの素晴らしさを赤裸々に明らかにしたいと思う。 2004.10.27日 れんだいこ拝 |
| 【キリスト教の「革命的精神」について】 |
| では、れんだいこから観て、イエスはどういう御方であったのか。分かりやすく云えば、「高山批判、谷底救済、金持ち後回し」の回天運動家であったのではなかろうか。それは多分に「人はかくあるべし、人の世も又かくあるべし」の政治的理想主義に根ざしていた。そういう意味では、紛れもなく真紅の革命者であったと拝察する。だがしかし、この流れはその後一千五百年間堰止めされ、社会は保守化した。近世になってルネサンスが胎動し、やがてフランス革命をエポックとして革命の時代に突入する。この時代に再び「高山批判、谷底救済、金持ち後回し」の回天運動が始まった。 しかし、今度はイエスは現れなかった。代わりに、社会主義者、共産主義者、無政府主義者がイエスの旗を振ることになった。この流れがロシア革命、中国革命へと続いていくことになる。これにユダヤ教的選民主義に裏付けられた「シオンの議定書」派が絡む。彼らは、イスラエルの建国運動と中世期ゲットー化されたユダヤの民の社会的解放を掲げて諸革命と関わる。よって、事態はかなり複雑化する。あるいは、「シオンの議定書」派こそが近代の革命と戦争時代の真の牽引者とみなすこともできよう。 それはともかく、「新高山批判、谷底救済、金持ち後回し」運動に、キリスト教徒の覚醒派が与していき、その中から社会主義者、共産主義者、無政府主義者(アナーキスト)が生まれることになったのもむべなるかなと推察している。社会主義者、共産主義者と理論ないし教義は違ったけれども、精神がかなり似通っていたからだと拝察する。れんだいこは、実践上の手引きについてはむしろイエスの非凡さとその後の長い歴史を持つだけにイエス派の組織作りの方が勝れていたのではないかと思っている。この辺りを説く力が欲しいが、れんだいこの筆力が及ばない。 2004.10.27日 れんだいこ拝 |
| 【キリスト教の「ヒューマニズム」について】 |
| 「キリスト教のヒューマニズム」についても言及しておかねばならない。イエスの時代に「ヒューマニズム」という言葉自体あったようには思われないが、後の時代に発生した「ヒューマニズム」の精神はイエス教義に通底しているように思われるので、敢えて「キリスト教のヒューマニズム」としてこれを考察する。 「キリスト教のヒューマニズム」イデオロギーは如何なる意味を持っているのか。これを知るには、「ユダヤ教的ヒューマニズム」の反対概念として捉えた方が分かりやすい。「ユダヤ教的ヒューマニズム」とは、「選民たるユダヤ教徒の為のヒューマニズム」であり、「目的のためには手段を選ばないヒューマニズム」であり、「目的達成の為には反モラル、陰謀的なものも含め全てを是とするヒューマニズム」であると考えられる。イエスは、これに徹底して異議を唱え、「神の国を唱えることで宗教的に装うが、一事万事で神の国思想とは正反対を実践している」と批判し、悪魔思想であると論難し、「本来の神の国信仰」の福音を宣べた。 こうして、「キリスト教のヒューマニズム」は「ユダヤ教的ヒューマニズム」に対抗して生み出された。この史実は案外大事で、西欧精神にある二大底流として知っておく必要があるように思われる。思えば、イラク懲罰戦争の際に演ぜられた米英ユ同盟と仏独の対立の背景にあるのは、この種のイデオロギー的な差かも知れない。 2004.12.5日 れんだいこ拝 |
| 【キリスト教批判の視角考】 |
| イエス教のキリスト教化に当っての教義の変質の検証の次に為さねばならないことは、キリスト教の不当批判に対する弁護でもある。れんだいこは、イエス教のキリスト教化に当っての教義の変質の検証の際には、イエス教を弁護した。その為に「イエス伝」まで作成し、イエスの履歴と理論を確認してみた。そのことによって、キリスト教がイエス教の核心を改竄し、その値打ちを落としこめていることを検証した。だが、そうはいうもののキリスト教の不当批判に対する弁護をもせねばならない。この一連の作業はかなり高等なものであるので、どれほ能く為し得るかは分からないが、やらねばならない。 れんだいこが、キリスト教の不当批判に対する弁護をなぜ為さねばならないのか。それは、主としてユダヤ教側からの攻撃に対して弁論する為である。今日キリスト教は、まさに左から右からサンドバッグにされている感があるほど批判されている。新種の動きとして、キリスト教のユダヤ教化が目論まれており、入り口はキリスト教を学ぶ格好にして、中に入ればユダヤ教義満載と云う隠れユダヤ教的キリスト教も隆盛している。 それやこれやで、キリスト教の不当批判は目に余る。良く似た例としてマルクス批判の構図も然りであるが、どちらの場合も当の本人が言ってもいないことを批判され、だからその教義ないしは理論は間違いなどという安逸批判に晒されている。れんだいこは、そういうみえみえの批判が嫌で堪らない。批判するなら、一応は批判される当のものを正確に客体化させ、その上で批判しないと申し訳ないと思う。こういう拘りは昨今では流行らないのかもしれない。 さて、どこから論ずるべきか。たくさんあり過ぎて困るほどである。とはいえ、一神教批判から入ろうと思う。論者が多神教との比較で一神教を論ずる場合、キリスト教を俎上に乗せる事例が多い。れんだいこは、それはオカシイと思う。一神教教義は、キリスト教で云うところの旧約聖書の創世記の項で開陳されているものであるが、本来のキリスト教即ちイエス教に於いては、旧約聖書の比重は非常に低い。故に、多神教と一神教の関係を論ずるならば、ズバリ本家本元のユダヤ教義をこそ対象にせねばならない。ところが一神教の責めをなべてキリスト教に負わせようとする傾向がある。これはどういう精神よってそうなのであろうか。ユダヤ教を軽々に論ずことができないような仕掛けがあるのであろうか。 本来のキリスト教であるイエス教の価値は、ユダヤ教神学とそれを奉戴するユダヤ教内諸派とりわけ当時のパリサイ派の論理と論法批判にある。ヨハネの洗礼を受けた後のイエスの布教活動の軌跡は、終始一貫パリサイ派との徹底した論争である。イエスの最後は、使徒と共にエルサレム神殿に乗り込み、最後の論争を交えた後に捕縛され十字架刑に処せられた。その復活を問うところからイエス教、後に転じてキリスト教か始まるのであるが、これらの教義の本来の教えは、イエスの行状と弁論を学ぶことである。 これを思えば、キリスト教に一神教の責を負わせるのは不当と云うべきで、真に教義論争するのであれば、ユダヤ教神学を相手にせねばならないということになる。このことがわかって貰えれば良い。ただそれだけのことである。しかるに、何故にユダヤ教に向かうのではなくキリスト教批判になるのかという仕掛けが問われねばならない。人は、それは偶然と云うのかも知れない。昔のれんだいこなら、そうかもと思っただろう。今は違う、意図的故意にキリスト教批判が世界各地で演ぜられていると思っている。 何故にそれほどキリスト教批判が為されるのか。それがもっと問われねばならない。ここには深い歴史の表には出ない裏真実があると思っている。れんだいこが判ずるところ、キリスト教はその昔、主として中近東から西欧の時の為政者が、それまで非合法化させ取り締まっていたイエス教を、手前たちの政権護持イデオロギーとして利用するに至ったことに起源する。その為に、イエス教の舌鋒鋭い面を穏和化させ、どうでも良いような宗教行事に熱中するよう改編した上で取り込んだ。れんだいこが、「イエス教のキリスト教化に当っての教義の変質」を指摘するのはその為である。 本当の問題は次のことにある。時の為政者が何故にイエス教をキリスト教化させて取り込んだのか。その理由は何なのか、このことが詮索されねばならない。れんだいこの判ずるところ、どうやらユダヤ教が大きく関係しているらしい。どう関係しているのかと云うと、ユダヤ教は元々極めてイデオロギッシュな宗教で、ユダヤの民は「宗教の輸出」に長けていた。その宗教を受け入れた国々は不思議なほどに栄耀栄華を誇った挙句に国家破産させられていた。それを歴史的に見て取った時の為政者が、ユダヤ教の輸出を断る為に対抗的にキリスト教で精神武装する必要が生まれ、こうしてキリスト教国家が生まれていくことになった。 西欧中世はこの時代であり、キリスト教大隆盛であった。このことを逆に言えば、ユダヤ教は逼塞させられ、この頃ユダや人は流浪の民となり、彼らの住むゲットー内で命脈を保っていた。この期間がほぼ一千年間続く。この一千年間の過程でキリスト教王国も徐々に変質し、キリスト教内諸国家となり、キリスト教カトリック法王の方が王よりも強い権限を持つに至った。そういう牢とした秩序が生まれ、やがて変革の時代に向かう。 十字軍、プロテスタント、ルネサンス、大航海による新大陸の発見、産業革命等々の時代となり、新秩序形成の動きが強まり、やかで革命と戦争の時代に向かう。この時のキリスト教批判は、聖と俗を併せ持ったカトリック支配に対するものとなり、体制批判=キリスト教批判となったのは致し方ない。そこにはそれなりの正義があったと見て取るべきだろう。 問題はこれで終わらない。中世一千年のキリスト教支配の時代に代わって、今我々はどういう時代に向かおうとしているのかが問われねばならない。科学時代、無宗教の時代に向かおうとしているなどと云う者も居るだろう。しかし、漠然とそう思うだけでは真実にはならない。れんだいこは、一千年間雌伏せしめられたユダヤ教が復権しつつある時代と見る。それも、かってイエスが最も激しく闘ったパリサイ派がネオシオニズム的理論武装したユダヤ新教が世界を席巻しつつある時代と見る。 現代パリサイ派ユダヤ新教は、イエスが喝破したように御神体が金であり、金貨を稼ぐことと宗教が一体となった拝金教であり蓄財主義であり、金の保有に応じた序列を作る聖俗混交教であり、モーゼの教えは建前に過ぎず、故に聖書よりもタルムードを重んじ、権謀術数は当たり前であり、暗殺テロはお手の物であり、戦争ビジネスを常用している。あるいは金融支配を得意としている。 ここまでならまだしも勝手かも知れない。問題は、彼らは、シオンの議定書で漏洩したように、最終的に世界中の非ユダヤ教徒をゴイム畜生視し、そのゴイム畜生諸民族を平定することを正義とし、これに基づき彼らの新秩序観に基づく世界を創り出そうとしており、それが世界秩序であり平和だとのたまっていることにある。イエスはかって、この種の当時のパリサイ派教義を悪魔に身売りしている最も危険にして背徳の教えと指弾している。これを歴史に警鐘乱打する為に十字架刑をも引き受けた。 れんだいこには、イエスの教えが正しいのか、現代パリサイ派ユダヤ新教の説く世界平和論が正しいのか、論ずるまでもない。世界平和は、世界各地の伝統と文化に根ざした諸国民の共同によって創出するものであって、現代パリサイ派ユダヤ新教徒を頂点にした強権政治のくびきに繋がれるものではない。人にはそれぞれ寿命があり、寿命内をそれなりに充足する世の中で過ごすのが生き甲斐であり、そういう世の中を世代継承によって漸次創出していけばよい。この弁えを通り越して、絶対真理的世界を妄想して殉ずるには及ばない。とか考える。 2007.2.18日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)