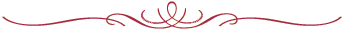
| ルターの宗教改革の史的意義 |
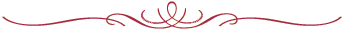
(最新見直し2007.5.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ルターの宗教改革の意義は殊のほか大きい、れんだいこはそう思う。日本の仏教史に比すると、法然−親鸞のそれに匹敵するか、それ以上のものがあるように思われる。ルターの原書に接してないのではっきりしたことは云えないが、「聖書に帰れ」は起こるべくして起きたキリスト教革命ではなかったか。しかし、それは、キリスト教カトリックが、政教一致体制化で腐敗しきるまで時を待たなければならなかった。 ルターの時代、教皇の免罪符発売と云う、かってイエスがエルサレム神殿に乗り込んだ時、激しく批判した「宗教のユダヤ的商売利用」が公然化しており、その正当化説法に我慢ならなかったものと思われる。実際には、ルターが所在していたドイツ北部のヴィッテンベルク地方の支配者ザクセンの選帝侯のローマ・カトリックとの一定の確執という政治的背景があり、これに庇護されていたという事情もあったものと思われるが、いずれにせよ公然と叛旗を翻したことになる。 こうして、ルターは、中世的キリスト教支配システムに闘いを挑み、今で言う政教分離の先駆けを主張する身となった。ここに、ルター派の史的意義が認められると思う。ルター的宗教改革にはもう一つの意義があり、この頃より勃興し始めたユダヤ教の歴史的反攻にも鋭い目線を保持していたことである。 「ユダヤ人と彼等の嘘」を著し、今日的にも有意義なユダヤ教並びに教徒の生態批判を繰り広げている。 ルター的宗教革命の意義は、この二点で問われるべきであろう。それは、ドイツ的知性の真骨頂と云うべきだろう。してみれば、宗教対立の根は深いということになる。もう一方のカルビン派の宗教革命との相似と差異を比較すればなお有意義と思われる。これについては、後日の検討課題とする。 2007.5.24日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
|
1524〜1525年、農民の不満を背景に、急進派トマス・ミュンツァー率いる武装農民が蜂起し、これに対してルター派の諸侯らと激く衝突、いわゆるドイツ農民戦争を勃発した。これで多くの犠牲が生じた。1529年にルター派の諸侯や都市が神聖ローマ帝国皇帝カール5世に対して宗教改革を求める「抗議書(プロテスタティオ)」を送った。以降、この派は「抗議者(プロテスタント)」と呼ばれるようになった。 以後、宗教抗争は政治権力抗争ともからみ、内乱状態は30年間続いた。内乱終結のアウグスブルグの和議(1555年)により、プロテスタントもカトリック教会と同等の信教の自由の地位を保証されることとなる。ルター派は北方に広まり、デンマーク・スウェーデン・ノルウェーで国教となった。 ドイツ改革とほぼ同時期に、スイスでも宗教改革運動が起こった。カトリック司祭のウルリッヒ・ツヴィングリは聖書のみ、信仰のみという教理を展開し、彼の弟子たちから幼児洗礼を否定し再洗礼を認めるアナバプテスト派が生じ、後に改革派からも排斥されることになる(ウェストミンスター教会会議)。また、ツヴィングリは、聖餐論においてルター派と対立することになる。 内乱状態の後を受けて、ジャン・カルヴァンが登場し、彼はツヴィングリを受け継いでスイスにおける宗教改革の指導者となる。カルヴァンは新しい教会の組織制度として長老制を提唱した。大陸におけるカルヴァン派の教会が改革派と呼ばれ、英国系のカルヴァン派の教会が長老派(その後アメリカへ)と呼ばれる。また、カルヴァンは予定説(二重予定説)を提唱し、カルヴァン派で受け継がれ、カルヴァン主義とも呼ばれる。予定説も、ルター派と同じくトリエント公会議で排斥の対象となる。カルヴァン派は、混乱から社会を救うため、宗教と政治、教会と国家を明確に機能区分することを提唱する。また一般市民の信仰生活に対して、世俗職業を天職(神の召命)とみなして励むこと、生活は質素で禁欲的であること等を説き、プロテスタント精神を確立させた。カルヴァン主義は、西方のフランス・オランダ・イギリス・アメリカへ広がった。後に、オランダ改革派から、カルヴァン主義の予定説に反対し、ヤコーブス・アルミニウスとその後継者によってレモンストラント派(アルミニウス派)が現れる。1610年、改革派はドルト会議にて、アルミニウス派を異端として排斥する。このアルミニウス派の思想は、後にメノナイト派、ジェネラル・バプテスト派(普遍救済主義のバプテスト)、メソジストのウェスレー派などに継承されることになる。 16世紀末頃、英国国教会の内部において、ピューリタンと呼ばれる改革派教会の方向へ改革を求める者らが現れた。更にこの改革運動を急進的にし、国教会から非合法に教会を建てようとする者らが現れ、彼らは分離派と呼ばれる。ピューリタンおよび分離派は、国教会の特に監督制に反対し会衆制を主張した。分離派は、国教会から分離せずに内部から教会改革を志すピューリタンに対しても、偽りの教会に属するとして相互聖餐を拒否していた。英国の分離派の思想は、ロバート・ブラウン(Robert Browne)に始まったとされる。これがやがて、ジェネラル・バプテスト派の母教会の牧師ジョン・スマイス(John Smyth)に受け継がれる。スマイスはジェネラル・バプテスト派の創始者トマス・ヘルウィス(Thomas Helwys)に恩師として影響を与えた。ただし、当時ウォーターランド派メノナイトとの合併を考えていたスマイスが、ヘルウィスに対して具体的にどれだけの影響を与えたかは、教理史的議論の決着がなされていない。またパテキュラー・バプテスト派は、元英国国教会司祭であったヘンリー・ジェイコブ牧師により発足した非分離派会衆主義教会から、より分離派的教会を求めて離脱した者ら数十名が、再洗礼を行って教会を新設したことにはじまったとされる。 18世紀、英国のオックスフォード大学内でジョン・ウェスレーが指導するグループから始まった運動が、英国全土にメソジスト(方法論者)という名で広がるようになった。そして、この運動はアメリカに渡ったが、独立戦争が始まる際に一部英国に帰国することとなった。1784年アメリカに残ったメソジスト宣教師らを監督教会として認める25箇条のメソジスト憲章が定められる。1845年、米国のパティキュラー・バプテスト派は、奴隷問題と国外伝道政策に関する見解の相違で北部バプテスト同盟(現在の米国バプテスト同盟)と南部バプテスト連盟とに分裂する。この頃、米国メソジスト教会にも同様の分裂が起こるが、やがて分裂は終結する。19世紀後期のアメリカのメソジスト系統からホーリネス派が起こり、これを基盤にペンテコステ派が起こる。さらにペンテコステ派によるペンテコステ運動は他教派におよび、聖霊派として知られている。また、カリスマ派はペンテコステ派から起こるが、WCCに加盟したことにより、エキュメニズムに反対するペンテコステ派から排斥される。同じく18世紀、アメリカで再臨運動が起こり、エレン.G.ホワイトらが活発に活動し、日曜ではなく、旧約律法通りの土曜を礼拝日とするSDA(セブンスデー・アドベンチスト教会)が組織化される。 |
||||||||||||||
|
1520年、「ドイツ国民キリスト者貴族に与える書」「教会のバビロニア補囚」「キリスト者の自由」という三大書著をあらわす。特に、「キリスト者の自由」において「人は信仰によってのみ義とされる」という信仰義認説を主張した。レオ10世は、60日以内に自説を撤回しなければ破門に処すと教書で通告したが、ルターは公衆の面前で破門状を焼き捨て、結果翌1521年に破門された。同年ヴォルムス国会に召還され、ここで皇帝カール五世の前で福音主義信仰を表明する。皇帝は彼をドイツ帝国の罪人と断じて法律の保護外に置いた。そのため、ザクセン選帝候の好意によりヴァルトブルク城にかくまわれ、ここで新約聖書をドイツ語訳する。またエラスムスと自由意志論争をめぐって論争し、「奴隷的意志について」を書く。
|
||||||||||||||
宗教改革の政治化、そして改革の限界この頃までに、ルターの教えは、教皇や皇帝に反感を抱く諸侯・没落しつつあった騎士・自由を求める都市の市民・封建制の重圧に苦しむ農民に受け入れられていた。しかし、その受容は身分や階層の利害と関わっていたので、宗教改革は単に信仰の問題には留まらず、政治化へと向かっていった。一方、ルターの福音主義に対して再洗礼派が台頭して来ていた。ルターはこれを知って1522年にヴィッテンベルクへ戻り、警告の説教を行った。そして9月、翻訳した新約聖書を出版した(いわゆる「9月聖書」)。同年、騎士階級が宗教動乱に乗じて教会諸侯領の撃破を唱えてケルン大司教領・トリエル大司教領で蜂起したが、諸侯軍によって鎮圧された(騎士戦争)。 1524年、トマス・ミュンツァーらを中心としたルター支持派の農民たちが領主の過酷な支配に対し反乱を起こす(「ドイツ農民戦争」)と、ルターはミュンツァーを最初は支持した。しかし、ミュンツァーが再洗礼派の影響を受けて次第に過激化、教会の襲撃などを行うようになると、ルターは彼を「悪魔の手先」と非難し、領主の側に立って反乱鎮圧を支持した。そのため、ミュンツァーはルターを「嘘つき博士」と激しく非難することになる。最終的に、ルターの支持に力を得た諸侯軍によって反乱は徹底的に鎮圧された。 ここから分かることは、ルターの改革が領主の利害と密接に関係していたこと、そして社会の改革ではなく内面的な信仰の改革に止まったことである。後に、この点において彼の改革の限界が指摘されることになる。 この結果、南ドイツの農民はルター派から離脱する。その後、ルター派の支持者はおもに北ドイツの諸侯や豊かな市民・農民に移っていく。その後、ルター派の諸侯は領内の教会の首長として領内の教会の支配権を握り(領邦教会制)、修道院の解散などの改革を進めていった。 す(はっきりいってボロい)。以後、農民戦争の指導者ミュンツァーや人文主義者エラスムスとの対立・論争を行いつつ、ルターはドイツにおけるプロテスタント教会の組織化に努力し、また最後まで大学教授として講義と著作活動を続けました。1546年、ルターは紛争を調停するために旅行した生まれ故郷のアイスレーベンで、心臓発作のためその生涯を閉じました。 |
プロテスタント出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』プロテスタントは、宗教改革運動を始めとして、カトリック教会(または西方教会)から分離し、特に福音主義を理念とするキリスト教諸派の総称である。ただし、聖公会(英国国教会)は教義上はプロテスタントだが、儀式・礼拝はカトリックという独自の立場から特に教会一致運動に寄与している。 カトリック教会や東方正教会は基本的にはそれぞれ統一された組織をなし、教義を共有する。これに対し、プロテスタントは神学や教義解釈がそれぞれ異なる多数の教派の集合体である。 なお、現在のキリスト教の女性観は基本的には男女平等だが、カトリックは男女ともに不完全で合わせて十全になるものとし、 プロテスタントは男女それぞれが完全な人格として女性の独立を前提とする傾向がある。 |
社会学などで研究、議論の対象となるヨーロッパの近代化は、プロテスタントによって担われたものだとする説がある。
その最も有名な説はマックス・ウェーバーによる『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に展開されたもので、清教徒など一部のプロテスタントが労働者としては合理的に効率性、生産性向上を追求する傾向を持っていたことを指摘している。ウェーバーによれば、プロテスタントの教義上、現世における成功は神の加護の証であるということになり、プロテスタントは与えられた仕事を天職のように考えてそれに打ち込むことで自分が神に救われる者のひとりである証を確認しようとしたという心理があるという。
また、ダニエル・ベルは『資本主義の文化矛盾』で、このような合理主義の精神が、芸術におけるモダニズムの運動と共に、近代社会のあり方を規定した主要因であったとする。また、1960年代以降、消費社会と結びついたモダニズムの影響力が拡大し、プロテスタンティズムに由来する近代の合理主義を脅かしているとも診断する。
プロテスタントと近代の関わりについてはもうひとつ、異なる側面を扱った説があり、やはり広く知られている。教会に赴いて他の教徒と一緒に説教を聞いたり、歌うことによって信仰を実践していたカトリックに対して、プロテスタントは当初、個々人が聖書を読むことを重視した。集団で行う儀式に比べて読書は個人中心の行動であるため、一部の論者はこれを近代社会に特有な個人主義と結び付けて考える。
*聖公会は本来プロテスタントとは自称しないが、西方教会における諸教派の一つとして挙げておく。
ルーテル教会は、マルティン・ルターによりドイツに始まる、キリスト教の教派または教団で、ルター派とも言われる。「ルーテル」という邦訳は、北欧訛りに由来する。
信条として
が採用されている。ただし、シェマルカルド信条については採用しない教団もある。
| 作品について: | 『マルチン・ルターの小信仰問答書』(1529年)は、宗教改革を行なったマルチン・ルターがキリスト教の教義のエッセンスを問答形式でまとめたものである。学者や教育程度の高い人に向けたものではなく、一般の民衆、特にあまり教育を受けていない人向けに書かれている。宗教改革後、ルターは各地の教会を巡視した。しかし、多くの人がキリスト教の教義を知らずにおり、また牧師にも指導力が不足していることを見て、ルターは大きなショックを受けた。そこでルターはまず牧師向けに『ドイツ・カテキズム』(後に『大信仰問答書』)という大きな信仰書を著し、そしてその後、一般の信徒向けに短くまとめた信仰書を編纂した。それがここで紹介する『マルチン・ルターの小信仰問答書』である。 『マルチン・ルターの小信仰問答書』は、キリスト教における十戒、使徒信条、主の祈り、洗礼、罪の告白、聖餐式などの意味を問答形式で簡潔・平明にまとめており、キリスト教の全体像をとらえるためのよきテキストになっている。(結城浩) |
| 仮名遣い種別: | 新字新仮名 |
1 ルターの宗教改革
1517年にドイツでおこった宗教改革は、単に宗教面のみならず、政治・経済・社会のあらゆる面に大きな影響を及ぼした。
宗教改革がおこった背景としては、(1)教会大分裂(シスマ)などの出来事によって教皇や教会の権威はさらに衰え、教会の世俗化や腐敗が進んだために教会を批判し、教会の革新を主張するウィクリフやフスによって先駆的な運動が行われたがカトリック教会内部での革新が進まなかったこと。(2)エラスムスの『愚神礼賛』やドイツのロイヒリンやメランヒトンなどにより聖書の文献学的研究が進んだことなどルネサンスのヒューマニストの影響が広まるなかで、人々が教会の世俗化や腐敗に疑問を抱くようになったこと。(3)国王の中央集権化が進むなかで、国王は教会の束縛を離れようとする傾向を強めていたことなどがあげられる。
ルネサンスの保護者として知られるメディチ家出身の教皇レオ10世は、サン=ピエトロ大聖堂の改築資金を調達するために、当時のマインツ大司教にドイツでの贖宥状(免罪符)販売を許可した。
カトリック教会では、罪を告白し、悔い改めた者に、祈りや巡礼、金銭の喜捨などの償いを課した。罪の償いを金銭の喜捨で免除できるとしたのが贖宥状であるが、中世末には贖宥状は教皇庁の財源をまかなう手段として乱用され、贖宥状を購入すれば罪そのものが許されるという考え方が広まっていた。
レオ10世が、ドイツでの贖宥状の販売を許可したのは、当時のドイツが「ローマの牝牛」と呼ばれていたように、ドイツは分裂を続け、皇帝権力が弱く、教皇に対する抵抗がほとんど見られなかったからである。しかも、この時のドイツでの贖宥状販売には、ドイツにおける教皇庁財政の独占的管理者でもあったアウグスブルクの大富豪フッガー家が協力していた。
マインツ大司教は、贖宥状販売をドミニコ派修道会の説教僧であるテッツェルに委ねた。テッツェルは、教皇の紋章をつけた十字架を先頭に行列をつくって町をねり歩き、「お金が賽銭箱のなかでチャリンと音を立てさえすれば、魂は煉獄の焔の中から飛び出してくる」などという露骨で巧みな説教により、身分や収入に応じて寄進の額を定めて贖宥状を売りまくり、人々からお金を集めていた。テッツェルの一行はザクセン選帝侯領内のヴィッテンベルクの近くでも贖宥状を売りまくった。
この時、修道士でヴィッテンベルク大学の神学教授でもあったマルティン=ルター(1483〜1546)は、1517年10月31日に、ヴィッテンベルク城教会の扉に、贖宥状の悪弊を攻撃する「九十五カ条の論題」を発表した。この出来事が宗教改革の発端となった。
ルターは、中部ドイツのテューリンゲンの鉱夫の家に生まれ、エルフルト大学で学んだが、友人の死や落雷体験をきっかけに修道院に入った(1505)。後にヴィッテンベルク大学の神学教授となり(1512)、1517年に「九十五カ条の論題」を発表して、宗教改革の口火をきった。
ルターは「九十五カ条の論題」のなかで、『第一.われわれの主にして師たるイエス=キリストが、「汝ら悔い改めよ」というとき、信徒の全生活が、改悛であらんことをのぞんでいるのである。
第二十七.かれらは人に説教して、金銭が箱になげいれられて、音がするならば、霊魂は(煉獄から)とびにげる、といっている。
第二十八.箱のなかで金銭が音をたてるとき、財貨と貪欲とがいやますことは、確かではあれ、教会の(赦宥の)援けは、ただ神の意思のうちにのみよっている。
第八十二.もし、教皇が教会をたてるというような瑣末な理由で、いともけがらわしい金銭をあつめるため、無数の霊魂をすくうのならば、なぜ、あらゆることのうち、もっとも正しい目的てある、いとも聖なる慈愛と霊魂の大なる必要のために、煉獄から(霊魂)をすくいださないのであろうか。』(山川出版社、世界史史料・名言集より)と述べて、魂の救済は善行や儀式によるのでなく、悔い改めと福音への信仰によってのみ人は救われるとして、贖宥状の販売を激しく攻撃した。
「九十五カ条の論題」は、神学上の論争を求めたものであり、教皇の権威を否定するものではなかったが、たちまちドイツ中に広まり、大反響を呼び起こした。
教皇は使節を派遣し、ルターに説の取り消しを求めたが、ルターは応じず(1518)、神学者エックとのライプチヒの公開論争では教皇権を否定し(1519)、『キリスト者の自由』(1520年刊)を著し、「人は信仰によってのみ義とされる」という信仰義認説を主張した。
教皇は、ルターが60日以内に自説を撤回しない場合は破門に処すとの教書を発したが、ルターは破門状を公衆の面前で焼却し(1520)、破門された(1521)。
教皇は、神聖ローマ皇帝カール5世(位1519〜56)に、ルター破門の実行を要求した。イタリア戦争を有利に展開するために教皇との緊密な関係を必要としていたカール5世は、ルターを弾圧するためにヴォルムスの帝国議会への出頭を命じた。
ルターの友人達は、ルターに出頭は危険だから中止するように勧告したが、ルターは「ヴォルムスの屋根の瓦ほど多くの悪魔がいても、私は行くつもりだ」と答えて出頭した。
カール5世から自説の撤回を求められたのに対し、ルターは聖書に明らかな証拠がある以外は取り消さないと拒否し、「我ここに立つ、神我を助け給え」という言葉で答弁を終わったと言われている。カール5世はルターを法律の保護外において帝国追放に処し、ルター派を禁止して彼の著書の購買や頒布を禁じた(1521)。
その後、ルターは突然人々の前から姿を消し、行方が分からなくなった。ルターはザクセン選帝侯の居城ヴァルトブルク城にかくまわれていたのである。そこで彼は『新約聖書』のドイツ語訳を完成し、一般の人々にも聖書が読める道を開いた。
その頃、ルターが聖書中心主義を唱えたのに対し、聖霊による神秘的な体験を重視し、聖書を軽んずる教派がおこり、広まっていた。この教派は、自覚のない幼児期の洗礼を無効として、成人の「再洗礼」を主張したので、再洗礼派と呼ばれている。
ルターは、このような動きを知り、ヴァルトブルク城からヴィッテンベルクへ戻り、警告の説教を行った(1522)。
この頃までに、ルターの教えは、教皇や皇帝に反感を抱く諸侯・没落しつつあった騎士・自由を求める都市の市民・封建制の重圧に苦しむ農民に受け入れられていたが、その受け入れられ方は身分や階層の利害と関わっていたので、宗教改革は単に信仰の問題には留まらず、政治化の方向をたどっていった。
没落しつつあった騎士達は、宗教動乱に乗じて教会諸侯領の撃破を唱えて蜂起したが諸侯軍によって鎮圧された(騎士戦争、1522〜23年)。
教会や諸侯の圧迫に苦しんでいた農民達は、ルターの思想的な影響を受けて、1524年に南ドイツを中心に大規模な反乱を起こした。この出来事はドイツ農民戦争(1524〜25)と呼ばれている。彼らは農奴制の廃止や封建的地代の軽減などを求めて「十二カ条の要求」を掲げて戦い、一時は南ドイツの3分の2を制圧した。反乱はさらに各地に広がり、特に再洗礼派の代表者であるトマス=ミュンツァー(1490頃〜1525)が指導した中部ドイツでは激しい暴動が起こった。
トマス=ミュンツァーは、初めルターの福音主義を支持したが、再洗礼派の人々に出会い、次第にルターから離れて急進化し、教会の腐敗・堕落を激しく攻撃するようになった。後にドイツ農民戦争に参加し、信仰を社会改革に結びつけて徹底した社会改革を求め、中部ドイツのチューリンゲンで一時市当局を打倒したが、後に諸侯軍に敗れて斬首された。
ルターは、初め農民を支持したが、ミュンツァーに率いられた農民達が財産の共有や神の前での平等を主張して教会を襲撃するなど過激な行動をとるようになると、彼らを「殺人強盗団」とののしり、諸侯に「狂犬同様に絞め殺し、打ち殺してしまえ」と過激な鎮圧を勧告した。これに対してミュンツァーはルターを「嘘つき博士」と呼んで激しく非難した。ルターがこのような行動をとったのは、彼が問題としたのは内面的な信仰のあり方であって、社会の現状を変革することまでは考えていなかったためである。
装備に勝る諸侯軍は、ルターの支持に力を得て結束して反撃に転じ、反乱側の分裂・不統一に乗じて農民軍を徹底的に鎮圧した。農民の犠牲者数は10万人にも達したといわれている。
ドイツ農民戦争後、南ドイツの貧しい農民達はルター派から離れ、以後ルター派の支持者は、おもに北ドイツの諸侯や豊かな市民・農民に移っていった。ルター派の諸侯は、領内の教会の首長として、領内の教会の支配権を握り(領邦教会制)、修道院の解散などの改革を進めていった。
その頃、神聖ローマ皇帝カール5世は、フランス王フランソワ1世とイタリアをめぐって争っていたが(イタリア戦争)、フランソワ1世はカール5世に対抗するためにドイツのルター派諸侯を援助し、またオスマン=トルコ帝国のスレイマン1世と結んだ。
スレイマン1世はハンガリーを攻略してオーストリアに侵入した。孤立したカール5世は、第1シュパイアー帝国議会(シュパイエル国会、1526)でルター派を認めて、ルター派諸侯の支持を取りつけて危機を脱した。
その後スレイマン1世は再度オーストリアに侵入し、1529年にはウィーンを包囲した。カール5世はウィーン包囲をかろうじて撃退すると、第2シュパイアー帝国議会で3年前の決定を取り消し、再びルター派を禁止したため、ルター派諸侯は抗議書を提出した(1529)。このため彼らはプロテスタント(抗議する者の意味)と呼ばれるようになった。
ルター派諸侯・都市はシュマルカルデン同盟を結成して(1530)、皇帝に対抗し、両者の争いは後にシュマルカルデン戦争(1546〜47)と呼ばれる内戦となったが、同盟側は内部分裂によって戦いに敗れて瓦解した。
しかし、国内の混乱を恐れた両者は妥協して、1555年にアウグスブルクの和議を結んだ。この和議によって諸侯にはカトリック派(旧教)とルター派(新教)のうちいずれかを選択する権利が認められ、都市では両派の存在が認められた。
しかし、アウグスブルクの和議では、個人の信仰の自由は認められず、領民の信仰は諸侯のそれと一致することが要求され、領民は諸侯が選択した派を信仰しなければならなかった。また当時各地に普及していたカルヴァン派は除かれるなど問題が多く、後に三十年戦争(1618〜48)が起こる原因となった。
ルター派はやがてデンマーク・スウェーデン・ノルウェーなどの北欧諸国にも広がった。
| マルチン・ルター (1483〜1546) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聖書は古いものでもなければ、新しいものでもない。聖書は永遠のものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツのアイスレーベンに生まれる。エルフルト大学で法律を学んだのち、ローマカトリックの修道僧となる。その後、教会の腐敗と善行による救いに疑問を持ったルターはヴィッテンベルグの教会に95ヶ条の抗議文を貼りつける。信仰によって義とされるという信仰義認を明確にした。また、聖書をドイツ語に翻訳し、だれにでも聖書が読めるようにした。宗教改革のさきがけとなった人物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ルネッサンス期の人々は、なお古い世界に属しつつも、それが自然の流れでもあるかのようにして合理的思考を始め、そこから、いろいろなことを求めました。
そこから、数々の「天才」と呼ばれる人々も出てきました。「求めること。」これが近代を支えます。そして、「求めることに限界があることを知る。」これが現代です。
彼らのほとんどは、観察と実験によってこの世界を知ることをを求めました。それは、「ありのままの世界をありのままに知ること」を前提にして進められました。
ミケランジェロは立体的で肉感的な人間を描き、天才ダビンチはあらゆる分野に渡って、リアリティーを追求し、可能性を探り続けました。
それまでキリスト教会が指し示してきた神中心の世界観から、人間が経験することができる人間中心の世界観への移行が始まったのです。
ガリレオがピサの教会の礼拝堂で、天上からつり下げられていたランプの揺れをじっとみつめて、振り子の原理を発見したのは象徴的な出来事です。
教会堂に座っていながら、彼は、揺れるランプを見つめていたのです。そして、「天」にいると教えられていた神を見出すために、望遠鏡で宇宙を観察し、神ではなく、見ることができる天体の動きを見つめたのでした。
数学的な、つまり合理的で、計算可能な思考をし、宇宙が数学的なものであり、その宇宙が地球を中心に動いているのではなく、太陽を中心にして動いていることを主張しました。
やがて、ニュートンがこの説の正しさを物理学的に証明し、今日では、もちろん、その太陽でさえ動いていることが認識されていますが、ガリレオの「地動説」は、当時の教会からは拒否されました。
それは、神中心から物質中心の世界観へと世界についての理解が移行していくことの象徴です。政治的・社会的権力に寄りかかることだけを考えていた当時のキリスト教会は、この事態にきちんと対応することができませんでした。
このルネッサンス期の世界観の変動は、ルネッサンスが古代ギリシャを手本にしたのですから、当然といえば当然ですが、神話から経験、経験から数学、数学から哲学へと動いていった古代ギリシャ思想の動きに似ています。
ルネッサンス期には、あのデモクリトスの「原子論」やピタゴラス学派の数学的世界観といったものと同じような、ジョルダーノ・ブルーノの「単子(モナドと呼んだ)論」やトマス・ホップスの「運動論」が生まれ、やがて、すべてを数学的合理性で説明しようとしたルネ・デカルトが登場しました。
ブルーノは、宇宙は無数の単子(モナド)からできており、モナドは創造されたものではなく、初めから存在し、完全で不滅のものであると主張しました。そして、その単子が様々な方法で結びついていると考えたのです。
また、ホップスは16世紀から17世紀にかけての人ですが、世界を運動する物体として理解しようとしました。
西洋史全体の流れからいえば、これ以前に、キリスト教の側でも、16世紀の初めにM.ルターが「宗教改革」を引き起こし、社会全体が大きな変革期を迎えていきますが、ルターの世界観は、思想的には神中心の世界観に他なりませんでした。
しかし、宗教改革によって、キリスト教会の中にも世俗化、つまり、合理的思考と人間中心的世界観が浸透していきました。しかしまた、プロテスタントであれ、ローマ・カトリックであれ、一般的な人々にとっては、以前として、世界は神中心の世界に他なりませんでした。
そして、これらに道筋をつけたのが、16世紀後半から17世紀の初めに生きたフランシス・ベーコンでした。
ベーコンは、近代的思想の道筋をつけた人で、人間的にもおもしろい人生を送った人ですが、彼については、次回触れることにします。
| 宗教改革の背景(2)─免罪符を買えば救われるか? 近代ヨーロッパ史08 |
[キェルケゴールの『畏れとおののき』におけるディレンマの問題]
http://66.102.7.104/search?q=cache:Wb5Bt78wW1QJ:web.kyoto-inet.or.jp/people/namaste/ronbun/kft3.htm+%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC&hl=ja
第三章 ディレンマの問題
第一節 ルターのアブラハム解釈
19世紀の神学者は、哲学者や歴史家よりもルターから遠いところにいたと言われ(1)、キェルケゴール自身がルターを読み始めるのは、1847年以降のことである(2)。キェルケゴールの生きたデンマークでは、ルター派プロテスタント教会を国教会としていたがゆえに、キェルケゴールにも何らかのルターの影響があったことは確実であり、その影響を無視する訳にはいかない。
そこでまず、ルターの『ガラテア書講義』(3)を見れば、アブラハムによるイサク供犠の物語についてのごく簡単な言及が見られる。それによれば、アブラハムがその子イサクを犠牲として捧げるよう命じられたのは、律法であり、アブラハムの行いは神を喜ばせ、他の儀式上の行ないと同様に神を喜ばせたというのである。そして、アブラハムはこの行いによって、義とされたのではなく、信仰によって義とされたとして、『ローマ書』第4章3節の「アブラハムは神を信じ、それが神の義と認められた」が引用されている。つまり、ルターは、信仰と行ないを区別して、アブラハムの行ないではなく、信仰に重きを置いているのである。この点は、信仰と行為の一致を考えるキェルケゴールと対称をなしている。
また、ルターは、『創世記講義』(4)において、『創世記』の一文一文に詳細で膨大な注釈を施し、語源的な探求や行為の解釈、登場人物の心的状況の推測など、多岐にわたって追求している。そしてルターは、人々が『創世記』に対して抱くであろう疑問を想定し、それへの反論を試みて、人々を信仰に導こうと企てている。そこで想定される疑問は、人間が理性的に考えれば不可解と思える神の行為についてや、アブラハムの行為についての言及が多数見られる。これを見ると、『畏れとおののき』に先行して、人々がアブラハムの行為をどのように捉え、どのように解釈していたか、これに対するルターの批判や解釈を伺い知ることができるのである。
例えば、ルターは、神はアブラハムにイサクを約束の子として授けながら、どうして今度は燔祭として捧げよと命じたのだろうかという我々が通常思いつくような疑問を想定している。そこにおいてルターは、神は自分の約束を後悔したからイサクを燔祭として捧げよと命じたのか、それとも、アブラハムが神を怒らせるような罪を犯してしまったのかなどという理由が考えられている。また、なぜアブラハムが神を怒らせてしまったのかというアブラハムの側に立った考察もなされ、イサクを授けられることを誇りに思い過ぎて、神への感謝が足りず、それによって神が後悔してしまったのだろうかと、アブラハムの心情が想像されている(5)。
さらに、アブラハムと、エレサレムで息子を失ったマリアとの対比も行われている。マリアの場合は、息子が生きてかえってくるという希望を持てたが、アブラハムの場合は、息子を授けてくれた神自身が殺せと命じたので、息子が戻ってくるという希望が持てるだろうか(6)というのである。
ルターは『創世記』の記述から踏み込んで、サラは何も事情を知らなかったのだろうと推測している。その理由としてルターが挙げているのは、彼女はこの大きなショックに絶えるにはあまりに弱いので、アブラハムは事情を隠していたのだろうというのである(7)。さらに、アブラハムが、三日目に同行の供の者を置いて、イサクと二人で山へと入って行ったが、その理由としてルターが考えているのは、もし供の者を同行すれば、彼らはアブラハムが息子を捧げようとすることを止めるかもしれないし、気が狂ったと疑うかもしれないからだというのである(8)。
これらをみると、ルターの批判はおくとして、あたかもアブラハムが神によって本当にイサクの命を取られてしまうと思っていたかのごとくである。つまり、アブラハムは神を信じていたので、イサクを燔祭として捧げよという命令を受けても、必ず神はイサクを助けてくれるという逆説を信じていたとされる一方で、アブラハムは、神によって生け贄の羊が差し出されることを知っていたのでもなければ、イサクの復活を信じていたのでもなく、本当に自分の子どもを殺そうとしていたと読めるのである。
しかし、他方、ルターによれば、確かに人間の理性では、神の約束(約束の子としてのイサク)が嘘だったのか、イサクを捧げよという命令が、神ではなく悪魔によるものだったのかと結論づけざるをえないという(9)。しかし、ルターは、アブラハムが復活によって矛盾が解決すると理解していたともいうのである(10)。それは、今日、息子を持ち、明日には死んで灰となったとしても、いつか必ず復活するという考えである。もし、このようにアブラハムが考えていたとするならば、アブラハムは神がイサクを必ず生き返らせてくれると確信していたことになるのである。
この物語は神による試練として読まれるが、もしこのことをアブラハムが知っていたら、不安は少なかっただろうとルターは主張している(11)。ここで考えられるのは、アブラハムが単なる試練だと了解していたのなら、彼は何のディレンマを感じることもなく、たかをくくってモリアの山へ出向いたであろうということである。そして、アブラハムは、イサクやサラにも自分の行為を説明することが出来ただろうし、供のものを何のためらいもなく山頂まで同行できただろうと考えることもできるのである。
さらに、ルターはアブラハムの心境を問うている(12)。それは我々がアブラハムに深い葛藤を見てとることを彼が予測しているからである。例えば、イサクがモリアの山で犠牲の子羊はどこにいるかと尋ね、神が与えてくださるだろうとアブラハムが答える場面では、そこには深い感情と力強いパトスがあるという(13)。ここで考えられるのは、もしアブラハムがイサクの復活を単純に確信していたのなら、そこには深い感情やパトスなどは必要なく、神が子羊を与えてくれるというおそらく事実となるだろうことを語るだけであるか、また、イサクの生命が何らかの形で保証されていると確信していたのなら、取りたてた感情の動きなどないだろう。大きな心的な運動を見るのは、アブラハムが真に息子を愛していると同時に、殺さねばならないというディレンマをみるからであり、アブラハムが息子に嘘をついていると考えるからなのである。アブラハムは「お前が羊なのだ」と答えるべきだったが、そうとは言わずに「神が与えてくださる」とだけ付け加えたのである。少なくともルターはアブラハムのその答えのうちに我々がディレンマを読みとることを想定しているのである。
キェルケゴールの『畏れとおののき』では、アブラハムが語ることが出来ない点に苦悩と不安があるとされる[p.113]。その一方で、『創世記』では、アブラハムはイサクに神みずからが燔祭の子羊を備えてくださるであろうとのみ語ったとされている。我々は、アブラハムがあらゆる瞬間に背理なものによる信仰の運動を信じ、神によってイサクが復活させられると信じていたのなら、アブラハムは嘘を言ってイサクを騙したのではないと考えることができる。この場合、アブラハムは淡々と神の命令に従っただけであり、イサクを燔祭とすることに深い倫理的な罪意識を感じる必要がなかったということもできよう。その一方で、アブラハムは、不安と苦悩をもって、イサクを犠牲に捧げようとしていたとするならば、イサクに気休めの嘘を言って、イサクを燔祭として捧げようとしたと考えることが出来る。もしそうでないならば、アブラハムはイサクに「実はお前が燔祭の羊なのだが、神は背理なものの力で羊を与えてくださるかもしれないし、そうでなかったとしても、いつか必ず復活させてくれるだろうから、安心するがよい」などと、説明することも可能であったはずである。それにもかかわらず、アブラハムはイサクが死ぬべき運命にあることを明らかにせず、イサクの喉にナイフを突きつける瞬間まで「神みずからが燔祭の子羊を備えてくださる」ということ以外は何も言わずに、イサクを捧げようとしたのである。キェルケゴールによれば、もしアブラハムが「私は何も知らない」とイサクに説明しても、それは非真実を言ったことになるという。アブラハムが語ることが出来た唯一の言葉「神みずからが燔祭の子羊を備えてくださる」によって、アブラハムは、何ら非真実を言っているのではなく、しかしまた、何かを言っている訳でもないというのである[p.118]。
『畏れとおののき』では、「調律」の章において、詳細なアブラハムの心理描写を付け加え、創作を交えた四つの物語が提示されている。ここでまずはじめに提示される物語は、イサクを燔祭として捧げることをアブラハムがイサク本人に説明する場合が想定されているのである。そして、いくら説明しても燔祭とされることを諾としないイサクに対して、アブラハムは「これが神の命令だと思っているのか? そうではなく、これはわしの望みなのだ」と、イサクの胸ぐらをつかみ、地面に投げつけて叫ぶのである[p.10]。次の物語では、神から子羊が与えられた後、モリアの山から帰宅したアブラハムがイサクに対して顔向け出来ずに老けこんでしまうという話が想定されている。さらに、アブラハムが、イサクを捧げようとしたことを、父としての義務を忘れていたとして罪を許すように神に嘆願する話、そして最後には、燔祭となったイサクが、アブラハムの拳が絶望に握りしめられて、全身がわなないているのを見てしまったことによって、信仰を失ってしまったという話が創作されているのである。以上のようにみれば、このようなキェルケゴールによるアブラハム描写は、内容的にルターの『創世記』解釈に対応しているのである。
第二節 「信仰」の優位と「信仰の騎士」
『畏れとおののき』において、アブラハムは驚嘆に値する信仰の騎士とされるのであるが、それはアブラハムが神に対して個別者として絶対的な義務を遂行した信仰ゆえであるとされる。しかし同時に、必ずしもアブラハムの狂信的な側面のみが取りあげられているのではない。例えば、信仰の騎士は、普遍的なものに属することが素晴らしいことであるのを知っていると同時に、普遍的なものよりも高いところに、孤独な小径が、狭く、そして険しく、うねりくるっているのを知っているというような記述がみられる[pp.75-76]。信仰の騎士は、単なる個別者であることから、普遍的なものを知った上で、再び信仰という名の個別者への道を見つけた者なのである。つまり、倫理と信仰との間に何のディレンマの余地がない単純な信仰優位と異なるのである。
『畏れとおののき』には、アブラハムの物語に見落とされているのは不安なのであるという記述[p.28]や、人は結果を知りたがるが、不安や苦難、逆説には少しも耳を貸そうとしないという記述が見られる[p.63]。さらに、これは恐ろしいことであると見えない人は信仰の騎士ではないということや[p.77]、苦悩と不安とが、およそ考えられうる唯一の資格であるということなども語られている[p.113]。こうして、アブラハムの苦悩や不安を見落としてはいけないことが繰り返し語られているのである。『創世記』のアブラハムは、何の躊躇もなく、ただ淡々と神の命令に従ったかのように書かれているが、『畏れとおののき』で描かれたアブラハムには、深い葛藤があるのである。また、キェルケゴールは、アブラハムの物語を単なる試練として解釈する俗説にも反対している[p.52]。そして、モリアの山への行程が三日あったという記述に注目し、アブラハムにとって、如何に旅の時間が長かったかを強調している[p.53]。この物語をただ単にアブラハムが神の試練を淡々と忠実にこなしたのだと考えるのならば、彼の物語は表面的な物語となってしまうのである。アブラハムがモリアの山へ向かい、イサクを縛り、燔祭として捧げようとするまでの時間を語ることは、その時間にアブラハムが味わったであろう葛藤を自分の問題として受け取り直すことである。つまり、アブラハムが如何に悩んだかという試練の苦痛を描写する必要があるのである。
もう一度、『ルカ伝』第14章26節(「誰でも、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分自身の命までも憎んで、私のもとに来るのでなければ、私の弟子となることは出来ない」)を取り上げることにする。キェルケゴールは、「あの箇所は文字通り解釈されねばならない。神は絶対的な愛を要求するものである」としつつ、ある夫が妻に父と母を捨てよ要求する話をそれに対比させている[p.73]。キェルケゴールはそのような夫を利己主義者であると同時に愚か者と見なす。父と母を捨てることを自分に対する妻の愛の証拠であると夫が考えるならば、そのような夫は愚かものなのである。夫が愛とはどのようなものであるかを知っていたら、彼は自分の妻が、娘として、姉妹として、愛において完全であることを見出したいと願うであろうと、キェルケゴールは考えるのである。
『ルカ伝』の場合と、自分への愛を確かめるために妻に父母を捨てろという男の場合における相違は、神への愛と夫への愛のあり方の違いである。この夫の例においても、単に妻が父母を憎むために、要求したのではない場合も考えられるが、少なくともアブラハムの場合、彼はイサクを犠牲に捧げようとする瞬間でもイサクを愛していたのである。もし、アブラハムがイサクを憎んでいたのなら、神は犠牲としてイサクを捧げることを要求しなかっただろうと考えられる。絶対的な義務は、倫理学なら禁止するようなことを行わせることができるけれども、絶対的な義務も信仰の騎士をして、愛することをやめさせることは出来ないところに、逆説があり、ディレンマの意味を見なければならないのである。
ある人が、悲劇的英雄への道を歩みだそうとする時、多くの人が忠告を与えることが出来るが、信仰の狭い小径を行く者には、誰も忠告を与えることは出来ないし、誰も彼を理解することが出来ない。信仰は奇蹟であるが、如何なる人も信仰から閉めだされていない。なぜならすべての人間の生活を一つにつなぐものは情熱であり、信仰とは情熱だからである。しかし、同時に、逆説を容易だと思う人は、信仰の騎士ではなく[p.113]、信仰は困難な道であり、誰にでもまねができるものではない。個別者が個別者として振る舞うことを得意がるようになったが最後、最悪のことが起こりかねないという恐れや[p.75]、個別者が本当に誘惑におちいっているのかどうか、あるいは彼が信仰の騎士であるかどうかは、ただ個別者が決定しうるばかりであるという事実[p.79]など、我々はアブラハムによるイサク供犠の物語を前にした時、極めて難しい問題に直面する。それにもかかわらず、個別者が個別者としてあるような信仰がないならば、人生は虚しいものとなるのである。信仰は殺人をさえ神聖な行為と考える一方で、アブラハムの偉大さは殺人によるのではなく、信仰によるのである。信仰の騎士は、普遍的なものに属することが素晴らしいことを知っているのであり、それと同時に、普遍的なものよりも高いところに、孤独な小径が、狭く、そして険しく、うねりくるっているのを知っているのである。そして、倫理的なものと宗教的なもの、普遍的なものと個別的なものの間にあるディレンマには、深い葛藤に伴う不安や苦悩が存在するのである。「個別者が個別者として、絶対者に対して絶対的な関係に立つという逆説が現実に存在し」「アブラハムが空しく」ないというならば、そこには深い葛藤にともなう不安や苦悩が存在し、このような不安や苦悩のうちに信仰への道が存在しているのである。まさに、このことが『畏れとおののき』におけるディレンマの意味なのである。