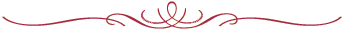
| ルターの生涯の概略履歴 |
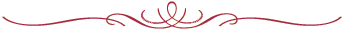
(最新見直し2007.5.24日)
「講義ユダヤ・キリスト教史」その他参照
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、ルターの生涯履歴を確認しておく。 2007.5.24日再編集 れんだいこ拝 |
| 【マルティン・ルター】(Martin Luther)(1483.11.10日-1546.2.18日) |
| 16世紀ドイツの宗教改革者、牧師、説教者、神学者。キリスト教宗教改革を主唱し、プロテスタント派を打ち立てた。カルビン派も誕生しており、並立している。ルター派教会は北ドイツ中心にドイツ語圏の国々や北欧諸国(オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノールウェイなど)に発展していった。新約聖書をギリシャ語からドイツ語に訳した。農民戦争では領主方の立場をとった。 |
| 【ルターの出生と家系】 |
| 1483.11.10日、ハンス・ルターの次男としてドイツ中部のザクセン地方のアイスレーベン(EISLEBEN)に生まれた。ルター家は代々、ザクセン領内チューリンゲンの森の西北端、メーラー村の農民であった。この地方はドイツでも有数の銅の鉱山地帯で、父ハンスはマンスフェルトの銅鉱山の炭坑夫であった。やがて溶鉱炉3基をもつ小企業家となっていた。生後数か月の頃、一家はマンスフェルトに移住した。マンスフェルト、マクデブルク、アイゼナハで初等・中等教育をうけている。父の教育方針は峻厳をきわめ、マルティンはこの、厳しい父に裁き主としての神の姿を描いたといわれる。 この時代、日本では室町末期、戦国時代に当たる。当時のドイツは、神聖ローマ帝国(IL SACRO ROMANO IMPERO)のもとに諸領邦が分裂しており、ローマ教皇庁(IL VATICANO)が巧みにコントロールしていた。 |
| 【ルターの入信】 |
|
1501年、エルフルト大学に入学、文学部で法律を学ぶ。これは当時のエリートコースであった。1502年、教養学士、1505年、法学で修士号を取得し修士となる。修士過程を17人中2番で卒業したルターは、法律家としての将来を嘱望されていた。 1505.7.17日、この出来事を契機として彼は修道士になる決心をする。父親の反対を押し切ってエルフルトにあるアウグスティヌス修道会(聖アウグスチノ修道会)に入る。 この経緯から判明することは、ルターの宗教的契機は「死の問題」を通じての神との対話にあったということになる。これが彼の第一回心の真相である。 |
| 【ルター司祭に叙される】 |
|
1507.4月、司祭に叙階され、神学の勉強を本格的にはじめる。1508年、新設のヴィッテンベルク大学に講師として招かれ、以後ずっとエルベ川がわったりと流れるドイツ北部のヴィッテンベルクに住むことになる。ルターの住んでいた家は現在も保存されている。ルターは、キリストを中心にした聖書講議とそれを民衆の言葉で説教、御言の分かち合い、アリストテレスの「ニコマコス倫理学」を講じた。かれの講義は明快で魅力があり、学生だけではなく、町の人びとも聴講に来たという。 1510.11月から翌年の4月にかけて、アウグスティヌス会の7つの修道院を代表してローマを訪問した。教会の世俗化と道徳的荒廃を目の当たりにし、衝撃を受けた、と伝えられている。 |
| 【ヴィッテンベルク大学神学部教授となり、聖書注解の講義を開始する】 |
| 1512年、アウグスティヌス派修道会の会議に出席し、神学博士に推薦され学位を授けられる。そしてヴィッテンベルク大学で神学博士号を取得した。 1513年、ヴィッテンベルク大学神学部教授となり、聖書注解の講義を開始。神学教授として活動し始めた。1513年から1515年までは「詩編」、そのあと1516年の暮れにかけて「ローマ人への手紙」を、続いて「ガラテヤ人への手紙」、「へブル人への手紙」、「テトスへの手紙」を講義した。 この頃のルターは、神秘主義者タウラーなどの書物の影響もあって、神は人間を、その人間の懐(キリストへの信仰)だけで受け入れて下さるという、信仰だけで罪人のまま義人として、神によって取り扱われるという信仰義認の立場に立ったように思われる。1516年頃には、ルターのこの立場は確固としたものとなっていた。 |
| 【ローマ教皇の免罪符販売について】 | |
| 1514年、ローマ教皇レオ10世(メディチ家出身)が、ローマのサン=ピエトロ聖堂(LA BASILICA DI SAN PIETRO)再建の資金にする目的で、当時のマインツ大司教に現世的処罰を免れさせる効力があるとする証書「贖宥状」(免罪符、Ablassbrief)の販売を許可し、ドイツにおける教皇庁財政の独占的管理者でもあったアウグスブルクの大富豪フッガー家の協力によりドイツ国内で大々的に販売が進められた。当時のドイツは「ローマの牝牛」と呼ばれ、ローマ・カトリックの有力な財源になっていた。 マインツ大司教は、贖宥状販売をドミニコ派修道会の説教僧であるテッツェルに委ねた。テッツェルは、教皇の紋章をつけた十字架を先頭に行列をつくって町をねり歩き、「お金が賽銭箱のなかでチャリンと音を立てさえすれば、魂は煉獄の焔の中から飛び出してくる」などという露骨で巧みな説教により、身分や収入に応じて寄進の額を定めて贖宥状を売りまくり、人々からお金を集めていた。テッツェルの一行はザクセン選帝侯領内のヴィッテンベルクの近くでも贖宥状を売りまくった。こうして、人々は我先にそれを買い求めた。 「宗教改革の背景(2)─免罪符を買えば救われるか?」は次のように記している。
この背景には十字軍(LA CROCIATA)遠征や教皇の華奢な生活が引き起こした経済難もあった。もともと免罪符は元来、ゆるしの秘跡において罪のゆるしを受けた者に課せられる償いが、教会の保証によって免除されることを記した証書で、例えば十字軍の際、従軍者に罪の許しが与えられるとしたのがその始まりであった。後には病院や橋、教会堂などの公共事業の建築費用調達のためにも販売されるようになっていた。当時ドイツは政治的に分裂していたため、教皇による政治的干渉や税制上の搾取を受けやすく、免罪符の販売にも好都合であった。 但し、庶民の信仰感覚としては金銭を払えばあらゆることが免罪されるものと受けとめられ、さらには極端になるとそれは煉獄の魂の救いにも効力のあるものとされたり、罪の償いのみならず罪そのものの許しまでも得られると吹聴される始末となった。それは明らかにイエスが最も激しく批判したユダヤ教パリサイ派の信仰姿勢であり、ルターはこれに立ち向かっていくことになる。 |
| 【ルターの「95箇条の提題」】 | ||||
1517年、ルターは、「七つの悔い改めの詩篇」、「ヘブル書の講解」、「スコラ神学に対する97箇条の提題」、続いて10.31日、「免罪符に対する95箇条の提題」をラテン語で発表し、ローマ教皇の免罪符乱発を批判した。次のように述べている。(山川出版社、世界史史料・名言集より)
その中でルターは、人は免罪符によってではなく神を信ずる信仰によってのみ救われることを主張していた。「聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ」という三大原理を説き、聖書に記されている神のことばに絶対的な権威があり、神の前にすべての人は平等であり、神の恵み、イエス・キリストの十字架と復活によってのみ、人は救われる、と主張していた。すべての人間は原罪のために罪人であって悪の力に束縛されている。自分自身の力では自由になれない。神によってのみ義化(義認)される、信仰とは神の不変の愛を信じることであり、信仰こそが神の救いの働きかけに応える唯一の道である、と説いていた。救いは人間の行いによらず、信仰のみによるという「信仰義認論」を唱えて、カトリック教会の聖職位階制度、修道制を否定した。 |
| 【ライプチヒで公開大論争】 | ||||||||
|
1519.6.27日、ライプチヒで、ルターと教会側の神学者エックとの公開大論争が始まった。次のような遣り取りが為された。
この時、ルターは、法王の権威を否定した為教会と完全に対立することになった。 |
| 【ルターの「宗教改革の三大論文」と審問】 | ||
| 1520年、ルターの宗教改革の三大論文といわれている「ドイツ国キリスト教貴族に与う」(An den Christlichen Adel deutscher
Nation von des christlichen Standes Besserung)、「キリスト者の自由」(Von der Freiheit
eines Christenmenschen)、「教会のバビロン捕囚」(De captivitate Babylonica ecclesiae
praeludium) が発表された。「バビロン捕囚」だけがラテン語で書かれていた。 ルターは、「ドイツ国キリスト教貴族に与う」で、カトリック教会の司祭を仲介して初めて信者は神の前に出ることができるのではなく、すべての信者一人一人が直接神の前に出ることができるし、信者は皆一人一人が神の前に司祭であると主張した。「教会のバビロン捕囚」で、サクラメント(秘跡)の問題を論じて、聖書で認められているサクラメントはバプテスマと聖餐の二つだけで、告解の実施も幾分は価値があるけれども、堅信礼、婚姻式、聖職者任命式、終油式はサクラメントとしては聖書に全く根拠がない、と言い切った。「キリスト者の自由」で、「人は信仰によってのみ義とされる」という信仰義認説を主張し、真のキリスト者はイエス・キリストとの霊的で神秘的な交わりを通して、罪をキリストの力で清めて頂き、キリストの義を頂戴して、隣人に対しては自分自身が一人のキリストになって行かねばならないことを説いた。 この3大論文を刊行したのちルターは、主君であるザクセン選帝侯の庇護のもと聖書のドイツ語訳に着手する。 1520.6.15日、ローマで教会審問がおこなわれ、ルターの教えを非難する勅書が出された。レオ10世は、60日以内に自説を撤回しなければ破門に処すと教書で通告したが、1921.1月、ルターは、法王が出した破門状を公衆の面前で焼き捨て破門宣告された。しかし、ルターの主張に耳を傾ける者が増大し、1530年ごろには、ルター派はドイツの主張を二分する政治勢力にまで成長していくことになる。 「講義ユダヤ・キリスト教史」は、次のように述べている。
1521.4.17日、ルターはドイツ皇帝カール5世(在位1519−56)からウォルムスの帝国議会に召喚され、自説を撤回するよう求められた。ルターの友人達は、ルターに出頭は危険だから中止するように勧告したが、ルターは「ヴォルムスの屋根の瓦ほど多くの悪魔がいても、私は行くつもりだ」と答えて出頭した。 審問された彼の前には、自分が書いた書物が置かれていた。それらがルターの書いたものであるかどうかの確認を求められたルターは、一日の猶予を願い出た。これでルターも屈服するのだろう、と多くの人々は思ったであろうが、翌日また法廷に立った彼は、それらが自分の書いたものであることを認め、次のように述べた。
|
| 【ルターのドイツ語訳聖書】 |
| 怒った皇帝カール5世はルターに対する法律の保護を停止し、ルターを帝国から追放した。ルター派を禁止して彼の著書の購買や頒布を禁じた。領主のザクセン選帝候フリードリヒが彼を助け、ヴァルトブルク城にかくまった。約9カ月の間身をかくした。城内にはルターが住んでいた部屋が残されているが、ほかの絢爛豪華な部屋と比べるといかにも質素なものである。そこでルターは著作活動に専念する。 1521.11月〜1522.9月、ルターは、エラスムスが世に送り出した新約聖書の当時一番立派なギリシャ語原典をドイツ語に翻訳した。これをルター訳と云う。この翻訳聖書は、標準的なドイツ語の確立にも重要な役割を果たすこととなった。 ルター訳は、パウロの言葉「信仰によって義とされる」(「ローマ人への手紙」 3:28)を「信仰によってのみ義とされる」と訂正翻訳したり、序文で「ヤコブの手紙」を藁(わら)の書簡と呼ぶなど、聖書に含まれている書物にも価値的に低いものがあるとして、ルター的価値判断で独自に編集している。ルターは、「ヘブライ人への手紙、「ヤコブプの手紙」、「ユダの手紙」、「ヨハネの黙示録」などを重んじなかった。 ルターの教えは、教皇や皇帝に反感を抱く諸侯・没落しつつあった騎士・自由を求める都市の市民や封建制の重圧に苦しむ農民に受け入れられていた。しかし、その受容は身分や階層の利害と関わっていたので、宗教改革は単に信仰の問題には留まらず政治化へと向かっていった。 1522年、ルターは、許されて、ヴィッテンベルク大学の教授に戻った。この頃、ルターの福音主義に対して再洗礼派が台頭して来ていた。再洗礼派は、ルターが聖書中心主義を唱えたのに対し、聖霊による神秘的な体験を重視した。この教派は、自覚のない幼児期の洗礼を無効として、成人の「再洗礼」を主張したので、再洗礼派と呼ばれている。ルターは、これに対し警告の説教を行った。 同年−1923年、騎士階級が宗教動乱に乗じて教会諸侯領の撃破を唱えてケルン大司教領・トリエル大司教領で蜂起したが、諸侯軍によって鎮圧された(騎士戦争)。 |
| 【賛美歌の整備と出版】 |
| ルターは、ドイツ語訳聖書の出版が宗教改革への多くの賛同者を得たのと同様にドイツ語による聖歌の編纂に意欲を燃やし、9月、翻訳した新約聖書を出版した(いわゆる「9月聖書」)。2年を要して1524年、「エルフルト提要」(家庭集会用)、「ヴィッテンベルク讃美歌集」(J.ヴァルター編の聖歌隊用)と立て続けに讃美歌集を出版する。(それまでラテン語以外での讃美歌集は、1501年にフス派がチェコ語で出した他、1522年にブラウンシュヴァイクのN.デツィウスにより低地ドイツ語で出されていた)。 シュトラスブルクでもルターの讃美歌は礼拝にすぐさま取り入れられ、それに感化された結果1525年、シュトラスブルクの讃美歌集が生まれた。その影響を受けてカルヴァンが1539年に詩篇歌集を編纂し始めることになる。 |
| 【ルターの信仰制度改革】 |
| ルターの唱える福音主義運動は信徒の信仰生活に大きな変革をもたらした。洗礼とミサを残して教会の諸秘跡はすべて廃止され、ミサの神学も変えられた。典礼はラテン語に代わってドイツ語でなされ、説教中心となった。また、一般初等義務教育という考えを導入して新しい教育制度を打ち立てた。こうして、教会、家庭、学校の三つが信仰の養成の場として新たに意味づけられたのである。(「カトリック教会の歴史」参照) |
| 【ドイツ農民戦争とルターの対応】 | |||
| この時代、ドイツでは農民一揆が多発していた。1524〜25年、南ドイツのバイエルンで農民反乱が起こった。彼らは農奴制の廃止や封建的地代の軽減などを求めて「十二カ条の要求」を掲げて戦い、一時は南ドイツの3分の2を制圧した。反乱はさらに各地に広がり、特に再洗礼派の代表者であるトマス・ミュンツァー(1490頃〜1525)が指導した中部ドイツでは激しい暴動が起こった。 これは、「ドイツ農民戦争」と云われる。 トマス・ミュンツァーらは、初めルターの福音主義を支持したが、再洗礼派の人々に出会い、次第にルターから離れて急進化し、教会の腐敗・堕落を激しく攻撃するようになった。後にドイツ農民戦争に参加し、信仰を社会改革に結びつけて徹底した社会改革を求め、中部ドイツのチューリンゲンで一時市当局を打倒した。 ルターは、ドイツ農民戦争に初めは同情的協力的だった。ところが、ミュンツァーに率いられた農民達が財産の共有や神の前での平等を主張して教会を襲撃するなど過激な行動をとるようになると、彼らを「悪魔の手先」、「殺人強盗団」とののしり、諸侯に「狂犬同様に絞め殺し、打ち殺してしまえ」と過激な鎮圧を勧告した。
これに対してミュンツァーはルターを「嘘つき博士」と呼んで激しく非難した。ルターがこのような行動をとったことに対して、次のように評されている。
装備に勝る諸侯軍は、ルターの支持に力を得て結束して反撃に転じ、反乱側の分裂・不統一に乗じて農民軍を徹底的に鎮圧した。1525年、ザルツブルクが陥落して農民一揆が終結した。ミュンツァーは諸侯軍に敗れて斬首された。農民の犠牲者数は10万人にも達したといわれている。 ドイツ農民戦争後、南ドイツの貧しい農民達はルター派から離れ、以後ルター派の支持者は、おもに北ドイツの諸侯や豊かな市民・農民に移っていった。ルター派の諸侯は、領内の教会の首長として、領内の教会の支配権を握り(領邦教会制)、修道院の解散などの改革を進めていった。 |
| 【ルターの結婚】 |
| この頃、ルターの改革に共鳴して修道院から逃げてきて、ルターの家に何人かの尼僧が匿まわれていたことがあった。1525年、ルター42歳の時、そのうちの一人のカタリーナ・フォン・ポーラ(26歳)と結婚した。それは、聖職者の妻帯を禁じていた教会への反抗の実践でもあった。家庭は、ルターに大きな慰めを与えた。2人の間には3男3女の6人の子どもが生まれている。家庭は至極円満であり、しばしば旅に出たルターが子供たちに送った手紙は子供と妻への愛情あふるるものであった。 |
| 【ルターとエラスムスの論争】 |
| ルターは、農民戦争以降、人文主義者エラスムスと自由意志論争し、「奴隷的意志について」を書く。その後、ドイツにおけるプロテスタント教会の組織化に努力し、また最後まで大学教授として講義と著作活動を続けた。 1526年、「ドイツ語ミサ」(礼拝式文)を出し礼拝改革のための一通りの体裁を整える。 |
| 【プロテスタントと呼称される】 |
| その頃、神聖ローマ皇帝カール5世は、フランス王フランソワ1世とイタリアをめぐって争っていたが(イタリア戦争)、フランソワ1世はカール5世に対抗するためにドイツのルター派諸侯を援助し、またオスマン=トルコ帝国のスレイマン1世と結んだ。スレイマン1世はハンガリーを攻略してオーストリアに侵入した。孤立したカール5世は、第1シュパイアー帝国議会(シュパイエル国会、1526)でルター派を認めて、ルター派諸侯の支持を取りつけて危機を脱した。
その後スレイマン1世は再度オーストリアに侵入し、1529年、ウィーンを包囲した。カール5世はウィーン包囲をかろうじて撃退すると、第2シュパイアー帝国議会で3年前の決定を取り消し、再びルター派を禁止したため、1529年、ルター派の諸侯や都市が、神聖ローマ帝国皇帝カール5世に対して宗教改革を求める「抗議書」(プロテスタティオ)を送った。この為、め彼らはプロテスタント(抗議する者の意味)と呼ばれるようになった。 |
| 【聖書のドイツ語全訳】 |
| 1530年、アウグスブルク国会において、最初のプロテスタント信仰告白書「アウグスブルク信仰告白」が提出される。この頃、ルター派はドイツの主張を二分する政治勢力にまで成長した。
1534年、旧約聖書を含めた聖書全巻のドイツ語訳を完成し出版した。これが、ラテン語の解らない一般の大衆に聖書を読む機会を与えたばかりでなく、結果的に各地の方言に分かれていたドイツ語を統一するのに大きな貢献をすることとに寄与した。この聖書が、後世聖書の各国語訳成立に多大な影響を及ぼした画期的な書物であったことは、「西洋をきずいた書物」(1977年、雄松堂出版より刊行)に述べられている。 この独訳聖書は、グーテンベルクにより発明されて間もない印刷術によりドイツ国内に急速に広められていった。聖書を自らドイツ語に翻訳したルターの業績は大きい。 ルターの唱える福音主義運動は信徒の信仰生活に大きな変革をもたらした。洗礼とミサを残して教会の諸秘跡はすべて廃止され、ミサの神学も変えられた。典礼はラテン語に代わってドイツ語でなされ、説教中心となった。さらに、修道生活や聖職者の身分は廃止され、彼自ら妻帯に踏み切った。また、一般初等義務教育という考えを導入して新しい教育制度を打ち立てた。こうして、教会、家庭、学校の三つが信仰の養成の場として新たに意味づけられたのである。 また彼はコラール歌唱を奨励し、自身も作詩・作曲にあたり、「我らが神は堅き砦」、「深き悩みの淵より」などのコラールを残した。4部合唱への編曲はヴィッテルベルク教会の楽長ヨハン・ヴァルターが多くを手がけている。また、これらを編纂した讃美歌集を出版して信徒の礼拝への直接的参加・積極的参加の手段、そして慰励のためとした。ルターの賛美歌は、イエス・キリストの福音を人々に分かりやすく、また身近なものとした。 ルターは晩年まで大学での聖書講義、著作活動、改革の指導や牧会活動を続けた。これにより、ルター派が形成されていくことになった。但し、ルター自身はルター派という名称に批判的で、教会も当初は「アウクスブルク信仰告白の福音主義教会」、あるいは単に「福音主義教会」と名のっていた。今も一般にエヴァンゲリスト(福音主義)と呼ばれている。 |
| 【ルタ−派に対抗してイエズス会が創設される】 |
| こういった宗教改革の動きを重く見たローマ教会からは、若者たちが立ち上がった。反宗教改革である。1534年にはイグナティウス・ロヨラらによりイエズス会が発足した。イエズス会はローマ教会の巻き返しを図り、キリスト教未到達の国への布教を試みた。 |
| 【ルターの晩年】 |
|
1537年頃、ルターは健康が衰え始めた。
1539年、最初のルター全集であるウィッテンベルク(Wittenberg)版は、ルターの晩年の1539年に刊行が開始され、完成したのは彼の死後12年もたった1558年であった。その後、イエーナ(Jehna)版、アイスレーベン(Eisleben)版全集が出版された。 1545.2.18日、ルターは紛争を調停するために旅行した生まれ故郷のアイスレーベンで、心臓発作のためその生涯を閉じた。遺体はヴィッテンベルクの城教会に埋葬された。 |
| 【ルター派の公認】 |
| 1955年、国内の混乱を恐れた両者は妥協して、宗教戦争と云われる内乱終結のアウグスブルグの和議により、諸侯にはカトリック派(旧教)とルター派(新教)のうちいずれかを選択する権利が認められ、都市では両派の存在が認められた。プロテスタントもカトリック教会と同等の信教の自由の地位を保証されることとなった。ルター派は北方に広まり、デンマーク・スウェーデン・ノルウェーで国教となった。
しかし、アウグスブルクの和議では、個人の信仰の自由は認められず、領民の信仰は諸侯のそれと一致することが要求され、領民は諸侯が選択した派を信仰しなければならなかった。また当時各地に普及していたカルヴァン派は除かれるなど問題が多く、後に三十年戦争(1618−48年)が起こる原因となった。 |
| 【ルター派のその後】 |
| 18−19世紀の宣教運動の結果、ルター派教会は世界各地に広がったが、その多くはルター派系の新しい教派として形成されていった。信者数は現在、約8000万人を数えるといわれる。 ルター派教会は、キリスト教の文化や学問に大きな影響を与えてきた。特に音楽と哲学の発展に大きな力となった。作曲家としてはプレトリウス、シュッツ、ブクステフーデ、バッハなどがあげられる。また、ルター主義出身の思想家にはカント、フィヒテ、ヘーゲル、キルケゴールらがおり、彼らはルター派の伝統に対する問答として、またしばしばルター主義に対する反論を通じて自分たちの思想を展開した。さらに、ルター派系教派からは著名な聖書学者や神学者も輩出している。シュトラウスやシュヴァイツァーらの聖書学者やリッチュル、ハルナック、オットー、ブルトマン、ティリヒらの神学者が有名である。 |
|
(以下、出典不明となってしまった。転載しておく) 内乱状態の後を受けて、ジャン・カルヴァンが登場し、彼はツヴィングリを受け継いでスイスにおける宗教改革の指導者となる。カルヴァンは新しい教会の組織制度として長老制を提唱した。大陸におけるカルヴァン派の教会が改革派と呼ばれ、英国系のカルヴァン派の教会が長老派(その後アメリカへ)と呼ばれる。また、カルヴァンは予定説(二重予定説)を提唱し、カルヴァン派で受け継がれ、カルヴァン主義とも呼ばれる。予定説も、ルター派と同じくトリエント公会議で排斥の対象となる。カルヴァン派は、混乱から社会を救うため、宗教と政治、教会と国家を明確に機能区分することを提唱する。また一般市民の信仰生活に対して、世俗職業を天職(神の召命)とみなして励むこと、生活は質素で禁欲的であること等を説き、プロテスタント精神を確立させた。カルヴァン主義は、西方のフランス・オランダ・イギリス・アメリカへ広がった。後に、オランダ改革派から、カルヴァン主義の予定説に反対し、ヤコーブス・アルミニウスとその後継者によってレモンストラント派(アルミニウス派)が現れる。1610年、改革派はドルト会議にて、アルミニウス派を異端として排斥する。このアルミニウス派の思想は、後にメノナイト派、ジェネラル・バプテスト派(普遍救済主義のバプテスト)、メソジストのウェスレー派などに継承されることになる。 16世紀末頃、英国国教会の内部において、ピューリタンと呼ばれる改革派教会の方向へ改革を求める者らが現れた。更にこの改革運動を急進的にし、国教会から非合法に教会を建てようとする者らが現れ、彼らは分離派と呼ばれる。ピューリタンおよび分離派は、国教会の特に監督制に反対し会衆制を主張した。分離派は、国教会から分離せずに内部から教会改革を志すピューリタンに対しても、偽りの教会に属するとして相互聖餐を拒否していた。英国の分離派の思想は、ロバート・ブラウン(Robert Browne)に始まったとされる。これがやがて、ジェネラル・バプテスト派の母教会の牧師ジョン・スマイス(John Smyth)に受け継がれる。スマイスはジェネラル・バプテスト派の創始者トマス・ヘルウィス(Thomas Helwys)に恩師として影響を与えた。ただし、当時ウォーターランド派メノナイトとの合併を考えていたスマイスが、ヘルウィスに対して具体的にどれだけの影響を与えたかは、教理史的議論の決着がなされていない。またパテキュラー・バプテスト派は、元英国国教会司祭であったヘンリー・ジェイコブ牧師により発足した非分離派会衆主義教会から、より分離派的教会を求めて離脱した者ら数十名が、再洗礼を行って教会を新設したことにはじまったとされる。 18世紀、英国のオックスフォード大学内でジョン・ウェスレーが指導するグループから始まった運動が、英国全土にメソジスト(方法論者)という名で広がるようになった。そして、この運動はアメリカに渡ったが、独立戦争が始まる際に一部英国に帰国することとなった。1784年アメリカに残ったメソジスト宣教師らを監督教会として認める25箇条のメソジスト憲章が定められる。1845年、米国のパティキュラー・バプテスト派は、奴隷問題と国外伝道政策に関する見解の相違で北部バプテスト同盟(現在の米国バプテスト同盟)と南部バプテスト連盟とに分裂する。この頃、米国メソジスト教会にも同様の分裂が起こるが、やがて分裂は終結する。19世紀後期のアメリカのメソジスト系統からホーリネス派が起こり、これを基盤にペンテコステ派が起こる。さらにペンテコステ派によるペンテコステ運動は他教派におよび、聖霊派として知られている。また、カリスマ派はペンテコステ派から起こるが、WCCに加盟したことにより、エキュメニズムに反対するペンテコステ派から排斥される。同じく18世紀、アメリカで再臨運動が起こり、エレン.G.ホワイトらが活発に活動し、日曜ではなく、旧約律法通りの土曜を礼拝日とするSDA(セブンスデー・アドベンチスト教会)が組織化される。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)