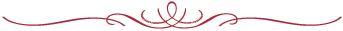
| フランシスコ会 |
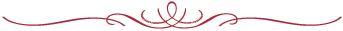
(最新見直し2013.10.26日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| フランシスコ会(「フランチェスコ修道会」)について見ておく。「フランシスコ会」、「聖フランシスコ」、「修道会」、「パドヴァのアントニウス」等々を参照する。 フランシスコ会とは、フランチェスコによってはじめられたカトリック教会の修道会を云う。フランチェスコとは「フランス風」の意味である。アメリカ合衆国のサンフランシスコは彼の名前にちなんでいる。 |
| 【フランシスコ会】 | |
| 1182年(1181年とも云われる)、聖フランチェスコは、父はイタリア人のピエトロ・ベルナルドーネという裕福な織物商、母はフランス人のピカ。その長男としてイタリア中部ウンブリア地方のアッシジに生まれる。最初ヨハネと名付けられたが、フランスでの商用から帰った父のピエトロは、フランスに因んでフランシスコという名前に変えた。弟にアンゼロがいたことが知られている。 成長すると、持ち前の快活さと父の財力で、町の青年たちの中心となって、青春を謳歌した。当時アッシジでは貴族と一般市民たちが町の政治の主導権をめぐって争っていた。市民たちが、これまでアッシジを支配してきた封建領主の城塞を攻撃し、破壊した時、フランシスコもこれに参加した。やがて貴族たちは隣の町のペルージアに亡命し、これがきっかけとなって、アッシジとペルージアの間に戦端が開かれる。フランシスコも参戦した。アッシジは敗れ、フランシスコは捕虜となり、父親が身の代金を払って釈放されるまで、ペルージアの捕虜収容所で1年余を過ごした。捕虜生活の間に病気に罹ったため、アッシジに帰った後も、しばらくは療養に時を過ごすことになる。 イタリア半島の南部にあるプーリアでローマ教皇と神聖ローマ皇帝の間の戦いが起こった。フランシスコは教皇軍に加わった。プーリアへ赴く途中、フランシスコは他になすべきことがあると言う心の奥深く囁きかける不思議な声に促されて、故郷アッシジへ帰った。20歳の時、信仰に目覚め、隠修士となり、教会堂の修復などを行った。 1206年の或る日、フランチェスコが祈っていた時、サン・ダミアーノ教会の十字架像から「私の家が壊れているのが見えないか。早く行って私の壊れかけた家を建て直しなさい」との主の声を聞く。また、ハンセン病患者との出会いもあり、宗教的回心を経て、それまでの裕福な生活を捨てて、無一物になり、神と人々に奉仕する生活に入った。 古い教会堂を修理し、人々に神の言葉と回心を告げ、労働をして生活の糧を得、それが得られない時には托鉢をする、という生活を行なう。やがて、フランシスコの周りには、かれと志しを同じくする若者たちが集まるようになった。1208年、3つの戒律を定め、活動を始めた。かれらは、短い会則に基づいて全ての財産を放棄した厳しい貧しさのうちに生活し、祈りに時を過ごし、神の言葉と回心の福音を説き、平和について語り、病人の看護と労働に従事する。当時のベネディクト会則とはまったく違う独自の会則に従い従順・清貧・貞潔に生きた。 そうして弟子たちとともに各地を放浪し、説教を続けた。マザー・テレサは彼の人生を聞き、修道女を目指したと言われる。次第に互いに兄弟と呼ぶ同志が増え、この小さな共同体が12人になった時、フランシスコはローマに赴き、1210年、ローマ教皇インノケンティウス3世に謁見し、修道会設立の認可を求める(教皇は口頭で認可を与えたとされる)。「原始会則」と呼ばれる会則の認可と修道会設立の許可を得る。こうして、「小さき兄弟会」(Ordo fraterorum minororum)という修道会が創立された。 フランシスコ会の組織的特徴が次のように説明されている。
1215年、キアラ(日本ではクララとして知られる)を中心に第2修道会(女子修道会)が創設された。1221年、在俗の「償いの兄弟姉妹の会」(第3会、略称OFS)が承認された。1517年、「小さき兄弟会」は「コンベンツァル小さき兄弟会」、1619年、「カプチノ小さき兄弟会」が分かれ、主流派となった「小さき兄弟会」(改革派フランシスコ会)と共に3つの男子修道会がある。 そういう訳で、フランシスコ会は、広義には第1会(男子修道会)、第2会(女子修道会)、第3会(在俗会)から成る。狭義には第1会に当たる3つの会の事を云い、特にその中の主流派である改革派フランシスコ会のみを指す事もある。この3つの会はいずれも「小さき兄弟会」Ordo Fratrum Minorum (OFM)の名で知られる。聖公会でもフランシスコ会が組織されている。 小さき兄弟会は急速に発展し、ヨーロッパ全土に広がり、パレスチナおよび北アフリカに活動の場を伸ばして行く。1219年、フランシスコ自身エジプトに赴いてイスラムのスルタンと交誼を結び、聖地パレスチナおよびシリアを訪れている。会員たちは宣教、司牧、学問、社会福祉に携わって、神と人々への奉仕を行なう。 1223年、新しい会則が起草され、教皇庁によって「勅書によって裁可された会則」が認可された。小さき兄弟会の三つの修道家族はこの会則に従って生活する。グレチオで、牛や驢馬を入れた小屋を作り、そこで「キリストの降誕祭」(クリスマス)を祝う。この時から教会の中に小さな「馬小屋」をしつらえてキリストの誕生を記念する習慣が生まれた。1224年、ラヴェルナ山でキリストの五つの傷をその身に受けるという恵みに浴す。フランシスコはいくつもの書き物を残しており、「兄弟太陽の歌」が特に良く知られている。 1226.10.3日、アッシジのポルチウンクラで44歳の生涯を遂げた。遺骸はアッシジの聖フランシスコ大聖堂(バジリカ)に安置されている。2年後には聖人の列に加えられた。 |
| 【フランシスコ会のその後】 |
| 小さき兄弟会はイタリア半島ばかりでなく、ヨーロッパ全土、北アフリカ、パレスチナおよびシリアへと広がる。会員たちは、宣教のために、中国にも赴く。活動も福音宣教、信徒の司牧、学問、教育、福祉活動の分野に及ぶ。神学・哲学の分野で貢献した小さき兄弟会員としては、ヘールスのアレキサンダー、ボナベンツラ、ヨハネ・ドゥンス・スコートゥスなどが知られている。 時代とともに小さき兄弟会は発展し、種々の活動に伴って、初期の素朴さや厳しい貧しさは徐々に姿を変えて行く。生活も緩やかになってゆく。このような経過の中で、初期の素朴な生活と厳しい貧しさへ戻ろうと言う動きが芽生え、改革運動が始まる。こうして、14世紀には小さき兄弟会にはコンムニタス(コンベンツアルとも呼ばれた)という「共同体派」とオブセルバンテスという「改革派」の二つの流れが生まれる。 共同体派は大きな修道院に住んで、共同体生活を大切にし、主に都市部で人々の奉仕にあたった。改革派は初期の頃は小さな修道院や山の庵に住んで、観想生活を主とした。時代とともに、改革派も大きな修道院共同体を作り、都市部でも活動するようになった。また、改革派のほうが会員の数においても活動の面でも、主流派である共同体派を凌駕するようになった。 1517年、教皇レオ10世は、小さき兄弟会を共同体派の流れを汲むコンベンツアル兄弟会(コンベンツアル聖フランシスコ修道会)と改革派の流れを汲む小さき兄弟会(フランシスコ会)とに分割し、こうして小さき兄弟会は独立した二つの修道会となる。 間もなく小さき兄弟会(フランシスコ会)からはカプチン小さき兄弟会(カプチン・フランシスコ会:1619年に独立した修道会となる)が分かれ、小さき兄弟会は三つの独立した修道会となる。 16世紀から17世紀にかけて、「フランシスコ会」、「コンベンツアル聖フランシスコ修道会」、「カプチン・フランシスコ会」の三つの独立した修道家族に分かれる。三つの修道会ともアッシジのフランシスコが書いた同じ会則に従って生活するが、それぞれ異なった会憲を持っている。 小さき兄弟会の分割後、コンベンツアル聖フランシスコ修道会は一時期困難な歩みをたどるが、その後活力を取り戻し、18世紀には会員2万5千名を数えるようになる。しかし、フランス革命とナポレオンの施政および西欧社会における修道会廃止令によって大きな打撃を受ける。多くの国々で修道院は没収され、会員たちは教区司祭になるか、個人で修道生活を送るか、または還俗するかの道を選ばなければならなかった。 |
| 1549(天文18)年8月15日、イエズス会員聖フランシスコ・ザベリオの鹿児島渡来によって、わが国におけるカトリックの宣教が始められたが、その後続々とイエズス会、フランシスコ会、ドミニコ
会、アウグスチノ会等の会員がインド・フィリピン等から相次いで来日し、各地に教会、修道院、学校、病院等を設置して熱心に宣教に当った。 1593年、フィリピン総督の使節としてペドロ・バプチスタが到着。 |
切支丹迫害、 <次へ : ユートピア社会主義者の夢>、 オカルト百科、キリスト教伝来、「シンドラーのリスト」。
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
フリードリッヒ2世は、神聖ローマ帝国の皇帝であったが、歴代の皇帝と異色だったのは彼が「法王は太陽、皇帝は月」としてきたそれまでの教権と王権の関係を疑惑し、「神のものは神に、皇帝のものは皇帝に」としたことであった。いわば、政治と宗教の分離の先駆け思想を唱えていたことになる。フリードリッヒ2世はこのような観点から、官僚機構の整備、税制の整備、通貨の整備、学術芸術分野の改革。法王庁の管轄から外れたナポリ大学、研究所、図書館の新設、サレルノ医学校の改編。ちなみにこの頃パリ、オックスフォード、ケンブリッジ大学が作られており、13世紀前半は相競うかのように各地に「ユニバーシティ」が設置されていったことになる。
但し、フリードリッヒ2世の統治が善政というのではない。教権に変わって王権を優位にさせようとの国家管理の強化でもあり、今日的なブルジョア民主主義の観点から単純に評価し得る性質のものではない。実際、商人層は法王派となったり皇帝派になったりしている。「ライコ」的な国家モデルを構想していたということになる。