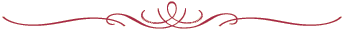
| キリスト教史その1、原始キリスト教から東方教会の成立まで通史 |
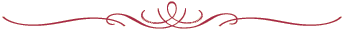
(最新見直し2007.1.26日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「ウィキペディア、キリスト教の歴史」、「近代以降のキリスト教の歴史」、「(2)キリスト教の発展」その他を参照する。 |
| 【皇帝ネロの迫害】 | |
| 紀元50年頃既にイエス教は「ヘレニスト」によってユダヤに隣接するサマリアを初めとする地中海沿岸の諸地方へも布教され、各地で教会が設置されていた。これら各地での信仰はエルサレム教会側からみれば逸脱に当たるものもあり、一部はパウロによって軌道修正されたようである。 イエス教は、ディアスポラを通じてローマ帝国内に広まっていった。しかし、ローマ帝国政府当局により迫害を受け、多くの殉教者を出した。これにはローマ帝国が元々多神教国家であった事や東方の影響によって発生した皇帝崇拝にキリスト教徒が従わなかったことなどいくつかの理由がある。 64年、ネロ皇帝の時代、「ローマの大火」が起る。ローマは数日間燃え続け、当時人口100万人と言われたローマの市街の大半が消失した。ネロは、イエスキリスト教徒を犯人と嫌疑し、多くの信者を捕え、十字架の刑にしたり、火あぶりの刑にしたり、獣の皮をかぶせて猛犬にかみ殺させたり手の込んだ罰を与えていった。ヤコブの処刑、続くペトロやパウロの刑死。 「(2)キリスト教の発展 」は次のように記している。
セネカ(紀元前4〜紀元後65)は、この時代の哲学者である。セネカは、ネロの幼少期の個人教授を勤め、親交していた。ネロは、結婚相手ポペーァによってユダヤの金貸し業者を侵入させ、それと共に暴君化していった。セネカは、ユダヤ系金貸し業者の排除に向かおうと営為した為、自殺を強要されることになった。 |
| 【第一次ユダヤ戦争とその余波】 |
|
第一次ユダヤ戦争(66-70年)の結果としてエルサレム神殿が崩壊した後で、(現在のユダヤ教主流派に近い)ファリサイ派がヤムニア会議で(旧約)聖書正典を決定するプロセスにおいて、ギリシア語の七十人訳聖書を主要テキストとしたキリスト教と完全に袂をわかつことになった。ここにおいてユダヤ教とキリスト教の信条の相違は決定的となる。これ以降「キリスト教」としての歴史が始まったといえる。 |
| 【「福音書」】 |
| 紀元70年頃より福音書が作成されていった。これについては、「福音書の相関考とれんだいこ記イエス伝の特徴について」に記す。 |
| 【「使徒行伝」】 |
| 続いて、「使徒行伝」(しとぎょうでん。ギリシア語はΠρ?ξει? των Αποστ?λων)が作成され、新約聖書中に所収される一書となった。「ウィキペディアの使徒行伝」その他を参照する。 |
| 「使徒行伝」は、新約聖書の中で、伝統的に四つの福音書のあとにおかれる。かって日本のカトリック教会では『使徒行録』とも呼ばれていたが、現代では新共同訳聖書の表記にあわせ、プロテスタントと共通の『使徒言行録』という呼び名が用いられている。新改訳聖書では『使徒の働き』と訳され、日本ハリストス正教会では『聖使徒行実』という訳語をあてている。 使徒行伝の内容は、一口で言えばキリスト教の最初期の様子である。特に二人の使徒ペトロとパウロの活躍が中心に描かれている。さらにエルサレム教会と初期のユダヤ人のみのキリスト教コミュニティーがコルネリウスの洗礼をへて異邦人(非ユダヤ人)の間へと広がっていた様子が記録されている。 本文によれば、使徒行伝は『ルカによる福音書』の続編として(伝承によればルカの手で)書かれたものであるという。どちらも「テオフィロ」(ギリシア語で「神を愛する者」という意味)なる人物に献呈されている。もともとは一冊の書物だったという説もあるが、現代の研究者たちがさかのぼれる最古の資料の時点では、すでにルカ福音書と使徒行伝は別々の本になっていた。使徒行伝はこの時代に書かれた作品としては他に類をみない非常にユニークなものであり、初期キリスト教の研究は本書なしには成り立たない。また、パウロの書簡集も使徒行伝の存在によって価値あるものになっており、使徒行伝なしにパウロの手紙を読んでも理解できない部分が多いことを忘れてはならない。 使徒行伝の構成とルカ書の構成には共通点が見られる。たとえばルカ福音書はローマ帝国(の人口調査)に関する記述から始まる。物語はイエスが故郷ガリラヤを出て、サマリアからユダヤへゆき、エルサレムで十字架にかけられるところへと展開していくが、そこで復活し、昇天して栄光を受けると結ばれる。 使徒行伝はこれと呼応するかのように、エルサレムから使徒の活動が始まり、ユダヤからサマリアへと広がり、やがてアジア地方をへてローマ帝国の中枢にいたるという構成になっている。このような文章の組み立てをキアスムス構造(X字構造、交差法)という。キアスムスでは構成の中心に位置する部分が重要なのでこの場合は、中心にある「エルサレム」および「イエスの復活と昇天」が著者にとってもっとも重要なものであることを示している。 このような使徒行伝の地理的展開は冒頭におけるイエスのことばであらかじめ示されている。つまり 「あなたがたはエルサレムだけでなく、全ユダヤとサマリア、さらに全世界にいたるまで私の証人となる」という記述である。これがエルサレム(1章〜5章)、ユダヤとサマリア(6章〜9章)、全世界(10章〜28章)という使徒行伝における物語の舞台の展開に対応している。 また使徒行伝はペトロとパウロという二人の使徒の活躍が中心であるが、それによって全体を二つに分けることができる。つまりペトロの活躍(1章〜12章)の部分とパウロの活躍(13章〜28章)の部分である。 使徒行伝は2世紀の頭にはすでに存在していたことが他の資料から確認できる。すくなくともマルキオンの活躍した時代(120年〜140年)に存在していたことは間違いがない。またポリュカルポスやアンティオキアのイグナティウスの書簡からも使徒行伝の存在が伺われることや、使徒行伝13章22節の記述と『コリントの信徒への手紙一』18章1の引用する詩篇89:20が(本来の詩篇にはない)同じ文章であることが偶然ではないと考えられることなどから、使徒行伝は96年にはローマで、115年までにはアンティオキアとスミルナで広く読まれていたことが明らかである。 成立時期が70年より前ということは考えにくい。ルカ福音の序文はイエスを直接知る世代がいなくなったという事実をほのめかしているからだ。研究者たちの間でもっとも可能性が高いといわれているのが80年ごろである。75年から80年の間に成立したという説の支持者もいるが、70年から75年という説はほとんど支持されない。使徒行伝にはフラウィウス・ヨセフスの著作との共通点があることから著者はヨセフスを参照していると指摘するものもいるが、それが正しいとすると100年以降の成立になってしまうため、説得力は弱い。使徒行伝が他の記録で言及される最古の例は177年を待たなければいけないが、これは成立時期を示すものでなく、ただ使徒行伝という名前がついていなかっただけなどいくつかの説明ができる。 |
| 【キリスト教の発展】 |
|
イエス教は、特にネロ、ドミティアヌス、デキウス、ディオクレティアヌスといった皇帝のもとで大々的な迫害が行われた。しかし、イエス教の広まりは衰えることなく、殉教者の地理的広がりから、2世紀末には、ローマ帝国全域に教会は組織を広げていたと推測される。また3世紀にはエジプトから砂漠での隠修修道が広まり、独居あるいは集団で荒野で修道生活を行う者(修道者)が多数出た。 1世紀後半から2世紀までの教会内文献(使徒的教父文書)などからの推測によると、この頃、エルサレムのヘブライスト(ユダヤ系)教会と、シリアやエジプトのヘレニスト(ギリシア系)教会とで異なる文化圏の教会が形成されていたが、使徒たちがそれぞれの文化圏を認めていた。カトリック教会によれば、ヘブライスト教会は使徒(司教)と長老(司祭)、ヘレニスト教会は監督(司教)と執事(助祭)と、組織体型(ヒエラルキ)が異なった特徴を持っており、やがて全土の教会において司教、司祭、助祭というヒエラルキが普及するようになる。 |
| 【古代異教由来の事物の取り込みと一神教の変容】 |
| 使徒パウロの活動拠点のアンティオケイア教会では異邦人への柔軟な文化適合を重視していた。そのため、その後のローマ帝国と辺境各地への布教でも、現地の異教の風習や祭礼がキリスト教的再解釈されて積極的に利用された。有名な例では、ミトラ教由来の冬至の祭礼クリスマスがある。また禁教下で日付の問題が争われていた復活祭(復活大祭)の日付が正式に確定するのもこの頃である。 さらに多神教世界に布教する際、キリスト教は他の宗教の神殿の場所に教会を建立することを奨励した。この結果、多く女神の神殿が聖母マリアに捧げられる教会に変えられた。そのような女神の例としてミネルヴァ・イシスなどがある。時には異教の神像をそのまま流用することもあった。その例として、イシスとオシリスの像をマリアとイエスの聖母子像へ転用したことなどが指摘される。 禁令解除以後は弾圧の際の殉教者を積極的に称揚することが行われ、諸聖人の記念日や聖像(イコン)が使用されるようになった。 異教の多神教的世界観に慣れた古代人にはキリスト教の一神教的世界観を理解することが困難であるが、これらの一種多神教的な事物を内部に取り込むことは彼らへの布教を推進させる力となった。 また東ローマ帝国において、キリスト教の布教は帝国に親和的な環境を作ることにつながるため、東ローマ帝国皇帝は積極的に他民族への布教を後援した。 |
| 【神学論争勃発と頻繁な公会議開催】 |
|
古代の神学の中心は主に東方のギリシア教父によるものであった。アレクサンドリアのオリゲネス、アタナシウス、カッパドキアの三教父のバシリウス、ナジアンゾスのグレゴリオス、ニュッサのグレゴリオスなどである。やがて西方のラテン教父のアウグスティヌスなども影響を与えている。こういった神学の発展にともない教理論争が激しくなる。そのため、しばしば地方教会会議や普遍公会議が行われるようになった。 2世紀以後、マニ教の流入や、モンタノス派やアリウス派が起こり、教会内での意見の統一が難しくなった。とくに4世紀以降、キリストの位置付けをめぐる一連の神学論争が教会の分裂を招くまでになった。キリストの位置付けをめぐるアリウス派とアタナシウス派の論争は、暴力を伴う争いを招くまでに加熱していった。 |
| 【イエス教がキリスト教化により初の国教的地位を獲得する】 |
|
歴代皇帝の数次にわたる迫害にもかかわらず、4世紀にはキリスト教を公認する国が現れるようになった。 311年、ガレリウス帝が大迫害の後に寛容令を出した。 |
| 【コンスタンティヌス1世とリキニウス帝によるミラノ勅令でキリスト教が公認される】 | |
313年、コンスタンティヌス1世とリキニウス帝によるミラノ勅令によって、他の全ての宗教と共に公認された。「もはやキリスト教徒を敵としてはローマ帝国の統一は困難であるとさとり、キリスト教徒の団結を帝国の統一に利用しようとした」とされている。「(2)キリスト教の発展 」は次のように記している。
|
| 【日曜日安息日令】 |
| 321年、初期キリスト教徒たちはユダヤ教徒のように土曜日を安息日としていたが、ユダヤ教との対立の中で、徐々にキリストの復活した日とされる日曜日を祝日とするようになった。コンスタンティヌス帝は、日曜日強制休業令を強制した。このとき反対者への弾圧により死者が出たともいわれている。364年、ラオディキア教会会議により日曜日の安息日化が正式に決定され、現在に至っている。 |
| 【「ニカイア公会議」、アタナシウス派教義の正統化、アリウス派追放】 |
|
325年、ローマ皇帝コンスタンティヌスは、キリスト教の教義論争による抗争を解決するため、小アジアのニカイアで全教会の司教、長老など約300名を集め公会議を開いた(「ニカイア公会議」)。ローマ皇帝がキリスト教に介入したのはこのときが最初である。コンスタンティヌスは公会議の時点はキリスト教徒ではなかった(洗礼を受けたのは死の直前)。あくまでもローマ帝国の求心力低下の課題解決に図るためキリスト教の勢力を利用することがコンスタンティヌスの意図であった。 ニカイア公会議は激しい論争の末、「父なる神と、子なるキリストおよび聖霊とは、三つでありながらしかも本質的には同一である」という三位一体説を唱えたアレクサンドリアの助祭のアタナシウス(259頃〜373)の説を正統とし、アレクサンドリア教会の長老のアリウス(250頃〜336)のキリストの神性を否定し、人性を重んじる、いわゆるアリウス派を異端としローマ帝国から追放した。アリウス派は以後ゲルマン人の間に広まって行く。 |
| キリスト教では「天なる神」「キリスト」「聖霊」の三位(さんみ)は一体とされます。この「三位一体(トリニティ)説」は、キリスト教を公認したコンスタンティヌス大帝(270-337)のもとで開かれた宗教会議(ニケーア公会議 325年)で正統とされた。 |
| 【キリスト教の更なる国教化】 |
| 350年、アクスム王国(現在のエチオピア)でも国教化された。 |
| 【キリスト教の更なる国教化】 |
|
キリスト教を公認したコンスタンティヌス帝の甥に当たるユリアヌス(在位361〜363)はギリシア文化に心酔し、ミトラ教などの密儀宗教にひかれ、即位後異教に改宗し、キリスト教を弾圧したため「背教者」と呼ばれた。 |
| 【テオドシウス1世がキリスト教をローマ帝国の国教宣言】 |
| 380年、イエス教はその後もユリアヌス帝などの抑圧を受けたが、379年に皇帝となったテオドシウス帝が、アタナシウス派キリスト教をローマ帝国の国教と宣言した。 392年、帝国内の他の宗教を厳禁し、異教信仰を禁した。 |
| 395年、ローマ帝国が東西に分裂。 |
| 【「エフェソス公会議」で、ネストリウス派追放】 |
|
431年、皇帝テオドシウス2世により開かれたエフェソス公会議が開かれ、コンスタンティノープルの総大司教であったネストリウス(?〜451頃、在位 428-431)は、キリストは「神」でありかつ「人」であると主張しました。すると、聖母マリアも人の母であったことになる。イエスと聖母マリアの神性説に反対し、イエスについては神・人両性説をマリアについては非聖母説を唱えた。ネストリウス派も異端と宣告され、国外追放となった。 |
| 【教父アウグスティヌスがキリスト教教義を確立】 |
| この頃までに教会の組織化が進み、聖職者身分が成立するとともに、「教父」と呼ばれるキリスト教の正統教義の確立に努めた多くの学者が現れた。特にアウグスティヌス(354〜430)は最大の教父・神学者であった。彼の母は熱心なキリスト教徒であったが、彼は放縦な生活に溺れ、肉欲に苦しみ、一時マニ教に帰依したが、後に母の祈りに心を動かされ、回心を決意し、回心してからは異教や異端との激しい論争を通して正統教義の確立に努めた。彼の著書「神の国」(神国論)はアラリックのローマ荒掠をキリスト教の責任と非難したのに対して擁護したものでキリスト教歴史哲学のもととなった。また「告白録」は三大告白録の1つとして有名である。 |
| 【「カルケドン公会議」で、単性論を排斥】 |
|
451年、皇帝マルキアヌスがカルケドン公会議を開き、キリスト単性論と両性論が争われ、一時は単性論が有利な様相を呈したが最終的に単性論が異端とされた。しかし、シリアやエジプトを中心に単性論を支持する教会が多くあったため、各教会で対立司教が立つほどの分裂が生じた。単性論は、エジプトのコプト正教会や、その姉妹教会エチオピア正統教会、シリアのシリア正教会(ヤコブ派)や、元小アジア(現在はコーカサス地方)のアルメニア使徒教会など現在東方諸教会と呼ばれる教派につらなっている。 このように異端説を切り捨てることにより、正統派のキリスト教は自らの教義を洗練させ確立していった。言い換えると排除するべき異端の対比として、この時代に「正統」信仰が誕生したといえよう。 |
| 【東方諸教会の成立】 |
| 公会議による教義の確認は正統教義の確立を促したが、その一方で異端とされた教説の保持者が教会から分離することにもつながった。異端とされた説には消えていったものも多かったが、正統派の勢力が及んでいない地域で活路を見出すものや、自派の勢力の強いところで独自の発展を遂げたものもある。アリウス派は、最終的には消滅したものの、一時はゲルマニアを中心に布教し、それなりの期間にわたり勢力を保った。またネストリウス派はペルシアを経て中央アジアへと勢力を広げて、更には唐代の中国にも三夷教の一つ景教として伝来した。景教は大秦寺が建立されるなど、唐代では栄えており、仏教の浄土信仰等に与えた影響も指摘されている。単性論教会はシリア・エジプト・アルメニアでは多数派として残り、イスラム教化する以前の東方では、数において他を圧していた。現在も単性論教会はシリア・エジプト・アルメニアに相当数の信者を持っており、またカトリックや東方正教会とも一定の交流を保っている。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)