|
イエス教からキリスト教へ転換する時代において、最も難しい神学が「イエスは神か人か」という問題であった。「父なる神、子なる神、聖霊」に於けるイエスの「神性」の位置づけを廻る論争がその後4世紀に亙って続いた。
313年、ローマ帝国のコンスタンティヌス大帝がミラノ勅令でキリスト教を公認した。
320年頃、アレキサンドリアの司祭アリウス(アレイオス)が、キリストの神同一的神格化に疑問を呈し、概要「キリストは万物の中で、最も神に近い人であった。イエスは神ではない。父なる神だけを唯一の神である。御父と御子は決して同格ではなくて、御子は、あくまでも御父に従属する被造物である」と主張した。これを従属説と云う。この見解を支持する者達を仮にアリウス派と云う。以下、「雪ノ下通信ONLINE」の「ニカイア信条を学ぶ」その他を参照する。
325年、小アジアのニカイアで全教会会議(公会議)が開かれ(ニケイア宗教会議)、アタナシオス派とアリウス派(アレイオス派)が論争した。結果、アリウス派の主張は退けられ、「御子が人となった神であること、その本質は父なる神と同じであること」、「イエスを父と本質を一つにする神の子」と宣言した。この時制定された信条が、「原ニカイア信条」と呼ばれる。これにより、キリストの神同一的神格化に反対していたアリウス派は正統の座を失った。
「原ニカイア信条」は次の通り。
われらは信ず。唯一の神、全能の父、すべて見えるものと見えざるものとの創造者を。われらは信ず。唯一の主、イエス・キリストを。主は神の御子、御父よりただ独り生まれ、すなわち御父の本質より生まれ、神よりの神、光よりの光、真の神よりの真の神、造られずして生まれ、御父と同質なる御方を。その主によって万物、すなわち天にあるもの地にあるものは成れり。主はわれら人類のため、またわれらの救いのために降り、肉をとり、人となり、苦しみを受け、三日目に甦り、天に昇り、生ける者と死ねる者とを審くために来り給う。われらは信ず。聖霊を。
御子が存在しなかったときがあったとか、御子は生まれる前には存在しなかったとか、存在しないものから造られたとか、他の実体または本質から造られたものであるとか、もしくは造られた者であるとか、神の御子は変化し異質になりうる者であると主張するものを、公同かつ使徒的な教会は呪うものである。(関川泰寛訳) |
「原ニカイア信条」は、「御父と御子が同一の本質を持つ」ということを、「同質」と訳される「ホモウーシオス」というギリシア語で明確に表明していた。この言葉は新約聖書の中には出て来ない言葉であった為、教会の信仰箇条の中に入れるかどうかで大きな議論が起こった。会議は大きく揺さぶられた。最終的に「原ニカイア信条」が制定されることになったが、問題が決着したわけではなかった。その後も揺り戻しがあり混乱が続いた。アリウスに対抗して論陣を張ったアタナシオスはニケイア宗教会議で勝利したが、その後何度も追放の憂き目にあっている。会議において正当信仰と認められたにも拘わらずその強引な裁定が教団内にしこりを残し続けていたことになる。
381年、コンスタンティノポリス公会議が開かれた。この会議において制定されたのが、「ニカイア・コンスタンティノポリス信条」と呼ばれる信条である。通常、「ニカイア信条」と言うと、この会議で採択された信条の方を指す。325年の「原ニカイア信条」と381年の「ニカイア・コンスタンティノポリス信条」の違いは、ただ単にニカイア・コンスタンティノポリス信条が原ニカイア信条の改訂増補版として制定されたのみでなく、原ニカイア信条で規定されたキリスト論、そのキリスト論を含む三位一体論に基づく教会の礼拝作法を確立したことに認められる。
次に、コンスタンティノポリスの司教ネストリウスとアレクサンドリアの司教キュリロスの論争が発生する。イエス・キリストはどうやって神性と人性を、一つの人格の中で統合し得たのかを廻る論争が繰り広げられた。この問題は、カルケドン宗教会議で決着付けられるまで続いた。
451年、カルケドン宗教会議が開かれ、「イエス・キリストは神であり人である」(「イエス・キリストは真の神にして真の人であり、一つの人格の中に二つの性質を持つ」)とする「カルケドン信条」を採択することになった。これにより「イエスは人間でありながら、なおかつ完全な神である」と云うことになった。これを「カルケドン信条」と云う。カルケドン宗教会議以来、「カルケドン信条」がキリスト教の正統的理解となった。
但し、「カルケドン信条」は「一応の決着」でしかなく、カルケドン宗教会議以前の古くからの教会の一部は、その発祥地域(ペルシャ、シリア、エジプト、小アジア)や進展地域(エチオピア、南インド)に於いて現在に至るまでカルケドン宗教会議以前の規定を保持し、イエスの神性と人性を明確に区別し続けている。
この間併行して、「三位一体」教説が確立された。「三位一体」とは、第1神格=父なる神、第2神格=子なるイエス、第3神格=聖霊は、三つの位各(ペルソナ)でありながら、一つの実体であるとする「等質不可分説」である。キリストに強く神聖を認め、神そのものともするこの主張は、325年に開催された二ケーア公会議以来のキリスト教論争に於ける正統教義となった。
当時、コンスタンティノポリスを首都とするビザンティン帝国が形成されつつあり、キリスト教は、ビザンティン帝国下に教会を設けていった。ビザンティン帝国には、五つの総主教区が設けられていた。1・ローマ総主教区、2・コンスタンティノポリス総主教区、3・アレキサンドリア総主教区、4・エルサレム総主教区、5・アンティオケ総主教区がそれである。
その後、政治的な分裂によって文化圏が切り離される中で、西方ローマを中心とするラテン語文化圏キリスト教(仮に西方教会とする)と、東方のコンスタンティノポリスを中心とするギリシア語文化圏キリスト教(仮に東方教会とする)へと別れていく。8世紀頃から次第に、ビザンティン帝国の五つの総主教区のうちで、ローマ総主教区が、独立した一つの教会のように活動を始めるようになっていく。ローマ総主教区に於いては、ラテン語に翻訳したニカイア信条が定着していき、信条だけではなくて礼拝全体がラテン語を用いるようになった。この伝統は、1960年の第二ヴァチカン公会議で、礼拝が現地の言葉で行われるよう転換されるまで続くことになる。
ところで、ローマ総主教区がラテン語の「ニカイア信条」を用いるようになった際に、ラテン語本文に「フィリオクエ」という小さな言葉を付け加えていた。直訳すれば、「子よりもまた」という意味の言葉になる。381年のギリシア型ニカイア信条においては、「聖霊は父から出て、父と子と共に礼拝され、あがめられ」となっていたが、ラテン語版においては、「フィリオクエ」という言葉が加わったことによって、「聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝され、あがめられ」となった。この言葉を巡る論争を「フィリオクエ論争」と呼ぶ。
東方教会は、このラテン語の「フィリオクエ」を含まない元来のギリシア語の「ニカイア信条」を用い続けた。そして、勝手に信条の言葉に加筆した西方教会を非難し続けた。このことがやがて、東西教会の分裂を決定的なものとする一因ともなる。そのようにして、東方教会と西方教会に分かれて、ギリシア型とラテン型と、二つの版のニカイア信条が存在することになった。1054年、ローマの総主教とコンスタンティノポリスの総主教がお互いを破門し合った。これにより東西教会へと分裂した。
西方教会は、カトリック教会と呼ばれるようになり、全ヨーロッパに広がった。
10世紀中葉、オットー1世はイタリアを支配した。当時イタリアではローマ教皇権は衰退して、教皇はその他の豪族に意のままにされる有様だった。ドイツ王のオットー1世は苦境にあった教皇ヨハネス2世を助けて、教皇の立場を強化するのに尽力した。教皇はこの恩義に報いるために、オットー1世に加冠して神聖ローマ皇帝とした。こののちドイツ王は神聖ローマ皇帝を兼ねるようになり、こうして神聖ローマ帝国と云われるキリスト教国家が生み出された。「ドイツ王は列国の国王より一段上位にいるという精神的優越感を与えられることになった」(洛陽社「世界史の新研究」より。
11世紀後半、イスラム勢力によって奪われた聖地を奪還するという御旗を立てて、十字軍が組織された。ローマ教会は、独立した地位を確保し、本来は東方教会の教区であるところに、ローマ教会の枝教会を建てることを強引に認めさせるというようなことも起こった。十字軍による西方教会の東方教会に対する攻勢も見過ごすことが出来ない歴史的史実であったと思われる。
ローマ・カトリック、ギリシア正教、ロシア正教、プロテスタント各派は共通して、カルケドン信条と三位一体教説に依拠している。カトリックとプロテスタントもこの点では一致している。
唐の時代、中国に渡ってきた景教は、ネストリオス(382〜451?)派であって、カルケドン信条を否定する。景教は日本には上陸しなかっただ。
|
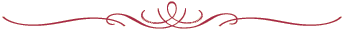
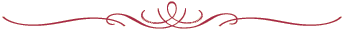
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)