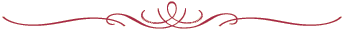
| 外伝福音書各書考(トマス福音書、死海文書、ユダ福音書他) |
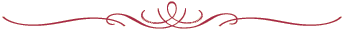
更新日/2018(平成30).12.9日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)トマスによる福音書」(荒井献『トマスによる福音書』講談社学術文庫#1149、1994)その他参照する。 四福音書のほかに幾つかのその他福音書が存在することが判明している。20世紀の半ばには、新約聖書学にとって重要な二つの貴重な発見がなされた。一つは、1945年の「ナグ・ハマディ写本(文書)」(Nag Hammadi Codices)の発見で、「トマス福音書」(「フィリポ福音書」)が世に知られるようになった。いま一つが1947年の「死海文書」の発見である。他にもユダ福音書が挙げられる。これらの福音書の意義は、四福音書とは又違うイエス像及び教義を記していることにある。「その他福音書」の方がより正確かどうかの判定は容易ではないが、無視できない記述が一部認められる。「その他福音書」の意義はここに存する。以下、これを考察する。 他に「新約聖書外伝」がある。正統派キリスト教は、群雄割拠していた数多くの新約聖書の中から27の文書を「正統」とした。この選抜から漏れてしまったものを「新約聖書外伝」と呼ぶ。 2006.10.30日 れんだいこ拝 |
| 【「フィリポ福音書」】 | |
ナグ・ハマディ文書の一つ「フィリポ福音書」は、次のようなイエス像を伝えている。
ここで述べられているマグダラのマリアがイエスの妻だっとの説も生まれている。正典福音書は、「パウロのイエス像」に依拠して聖像化しているが、「フィリポ福音書」はそれらとは明らかに違う「生身のイエス像」を示している。 |
| 【「ナグ・ハマディ写本(文書)」】 | |||||||
| 「ナグ・ハマディ写本(文書)」は、1945.12月、上エジプト(エジプト南部のナイル川の中流域の河畔の町)のナグ・ハマディ村のとある田んぼから発見された。アラブ人農夫は、肥料に使う軟土を掘り出すためにナグ・ハマディ郊外へと出かけた。そこは150以上の洞窟がある山で、エジプトの長い歴史の中で、墓場や修道院に使われた場所だった。そこを掘っていると偶然、赤い素焼きの壺(甕)が出てきた。好奇心に駆られた彼らがそれを割ったところ、中から出てきたのはボロボロになったパピルスで作られた写本冊子(本)の束だった。 これが現在「ナグ・ハマディ文書」と命名されている。「ナグ・ハマディ文書」は、発見時の様子からして謎に包まれている。発見された場所が土中の壺の中というのも奇異であり、意図的に隠されて埋められた可能性が強い。最も有力な説は次の通りである。
発見した農夫は、その本を知人のキリスト教神父に預けた。その神父の友人の歴史教師が、この写本の価値に気づいた。写本はそのまま古美術品のブラックマーケットに流されてしまい、転売に次ぐ転売をされ、さらに一部の学者の独占欲により死蔵されるなど、恐ろしく複雑でやっかいな経緯を経て、発見から実に30年以上もたって、ようやくその全貌が明らかになった。 現存する写本は13のコーデックスより成り、それぞれの写本(コーデックス)は、皮で綴じられ装丁されており、各々が3から7の独立した文書を含み、全体で断片も含め、52の文書より成る。次のことが判明した。
「ナグ・ハマディ文書」は、「創造神話」、「福音書」、「説教・書翰」、「黙示録」などに形態的・内容的に分類されており(この分類は、岩波書店版ナグ・ハマディ文書全4巻に使用されているものである)、グノーシス派文献の体裁を示している。「アダムの黙示録」、「セツの3つの教え」等の旧約聖書絡みのグノーシス文書もある。旧約とも関係のないものも含まれており、キリスト教的な加筆が成されている。「雷・全きヌース」、「シェーム釈義」、「マルサネース」、「ヘルメス哲学関係文書」、宇宙の流出による創造を説いた「アスクレピオス」の他、「第八のものと第九のものに関する講話」や「感謝の祈り」などが含まれている。他にもプラトンの著書も含まれ、「国家」の断片なども写本されている。格言集もある。 文書には、タイトルのないもの、原題の記されているもの、グノーシス主義名称が冠せられた文書が含まれる。救済神話として、「ヨハネのアポクリュフォン」、「アルコーンの本質」、「この世の起源について」。福音書として「トマス福音書」、「フィリポ福音書」、「エジプト人の福音書」、「真理の福音」、「三部の教え」。説教・書翰として、「魂の解明」、「闘技者トマスの書」、「イエスの智慧」、「雷・全きヌース」、「真正な教え」、「真理の証言」、「三体のプローテンノイア」、「救い主の対話」、「ヤコブのアポクリュフォン」、「復活に関する教え」、「(聖なる)エウグノストスの書」、「フィリポに送ったペトロの手紙」。黙示録として「パウロ黙示録」、「ヤコブ黙示録一」、「ヤコブ黙示録二」、「アダムの黙示録」、「シェームの釈義」、「大いなるセツの第二の教え」、「ペトロ黙示録」、「セツの三つの柱」、「ノーレアの思想」、「アロゲネース」。(第十三コーデックスは、纏まった写本の形では存在せず、第六コーデックスの中に、八枚分が紛れ込んでいた)。 コプト語原典写本には、最初ファクシミリ版が造られたが、現在では、複数の言語で「写本文庫」の翻訳が行われている。英語版の全訳は、「The Nag Hammadi Library in English」(San Francisco, Harper and Row,1988)がある。これは最初、オランダで初版が出版されたものであるが、現在、英国・アメリカ両方の出版社から入手できるはずである。 日本の翻訳は、岩波書店が発行している「ナグ・ハマディ文書」であるが、これは、52の文書の裡の保存状態の良かった33の文書の訳を収載している(34文書を含むように見えるが、3文書は、異端反駁論者の著作からの抜粋翻訳で、また、「マリヤによる福音書」は「ベルリン写本」に所収の文書で「ナグ・ハマディ写本」中の文書ではない。 更に、「ヨハネのアポクリュフォン」の異本2文書が、一つの文書として、他の異本(「ベルリン写本」文書)と共に、対照形で訳出されており、また「(聖なる)エウグノストスの書」の異本2文書を、同じく対照形で一文書として示しており、「エジプト人の福音書」も同様2異本で一つの文書としているので、実質33文書となる)。 |
| 【「グノーシス主義」】 | ||
ナグ・ハマディ文書は主としてグノーシス派のものであることが判明した。ここでは、グノーシス派について考察する。グノーシスとは、ギリシャ語で「知識」を意味する。グノーシス派は、紀元2世紀半ばから後半に最盛期を迎えている。そのグノーシス派は後に正統派となるカトリック系キリスト教から異端呼ばわりされているが、れんだいこの見るところ、古代原始イエスーキリスト教時代に於いてはむしろグノーシス派の方が正統派であった可能性がある。「グノーシス」を著した筒井賢治・新潟大学助教授は、次のように述べている。
グノーシス派と後の正統派となるキリスト教の間には次のような教義上の違いが認められる。 ユダヤーキリスト教では、神と人間は、全くの他者と規定されているが、グノーシス派は次のように主張する。
グノーシス派の教義によれば、自己認識は神の認識であり、究極人間と神は実は同一なのだと説く。かく認識するグノーシス派の教義には原罪意識が無く、故にキリスト教的「罪と悔い改め」を説かない。 このようにグノーシス派は、人間を神の下僕とみなす正統派のキリスト教とは、根本的に異なる。神は人間の内部にも存在する。人間は、覚醒することによって、神と合一し得る存在と考えている。人間を下僕とみなし、逆らう人間は容赦なく皆殺しする恐ろしい存在は、実は「神」ではなく、デミウルゴスと言う堕落した天使にすぎないと考える。 |
||
| 思うに、イエス教はキリスト教化されるに従い、そのキリスト教がユダヤ教的神学的に読み取られて行くに従い、イエスの言説から離れて行った。その点、「ナグ・ハマディ文書」から判明するグノーシス派は、キリスト教化する以前のユダヤ教的神学化される以前のイエス教の真実を伝えている可能性が強い。興味深いことは、古代ギリシャ思想と調和していたことである。これらの観点からの考究は今後の課題であろう。 2007.2.27日 れんだいこ拝 |
| 【トマス福音書の白眉的記述】 | |||||||||||||||||||
以下、トマス福音書の他の福音書と違うイエス像の箇所を確認する。
|
| 【死海文書】 | |||||
「ウィキペディア死海文書」。
死海文書(しかいもんじょ、しかいぶんしょ、英語: Dead Sea Scrolls)あるいは死海写本(しかいしゃほん)は、1947年以降、死海の北西(ヨルダン川西岸地区)にある遺跡ヒルベト・クムラン(英語版) (Khirbet Qumran) 周辺で発見された972の写本群の総称。主にヘブライ語聖書(旧約聖書)と聖書関連の文書からなっている。死海文書の発見場所は1947年当時イギリス委任統治領であったが、現在ではヨルダン川西岸地区に属している。「二十世紀最大の考古学的発見」ともいわれる。なお、広義に死海文書という場合、クムランだけでなく20世紀後半の調査によってマサダやエン・ゲディ近くのナハル・ヘベルの洞窟から見つかった文書断片なども含むので、文書数には幅が生じる。 死海文書はヘブライ語聖書の最古の写本を含んでいて、宗教的にも歴史的にも大きな意味を持ち、第二神殿時代後期のユダヤ教の実情をうかがわせるものでもある。文書は大部分がヘブライ語で書かれており、2割ほどのアラム語文書と、ごくわずかなギリシア語文書およびアラム語の方言であるナバテア語の文書を含んでいる。多くは羊皮紙であるが、一部パピルスもある。文書の成立は内容および書体の分析と放射性炭素年代測定、質量分析法などから紀元前250年ごろから紀元70年の間と考えられている。死海文書を記したグループ(以後、クムラン教団と呼ぶ)については、伝統的にエッセネ派と同定する意見が主流であるが、エルサレムのサドカイ派の祭司たちが書いた、あるいは未知のユダヤ教内グループによって書かれたとする意見もある。
死海文書の内容は大きく分けて3つに分類することができる。第1は「ヘブライ語聖書(旧約聖書)正典本文」(全体の4割)、第2は「旧約聖書外典」と「偽典」とよばれる文書群(エノク書、ヨベル書、トビト記、シラ書などでユダヤ教の聖書正典としては受け入れられなかったもの、全体の3割)、第3に「宗団文書」と呼ばれるもので、クムラン教団の規則や儀式書、『戦いの書(英語版)』(1QM(オランダ語版)、1Q33、4Q285(オランダ語版)、11QSM)と呼ばれる書など(全体の3割)である。 1946年の終わりから1947年の初めのいずれかの時期に、ベドウィンのターミレ族の羊飼いムハンマド・エッ・ディーブ(Muhammed edh-Dhib、「狼のムハンマド」の意)とその従兄弟が、ヒベルト・クムランと呼ばれる遺跡(遺跡自体は19世紀から知られていた)の近くの洞窟の中で、古代の巻物の入った壷を発見した。最初の発見に関しては、「子ヤギを追いかけていて、洞窟の中に石を投げ入れたところ、何かが割れる音がしたので入ってみた」などさまざまな逸話が語られるが、どこまでが真実かは、もはやわからない。ベドウィンたちは、最初に見つけた4つの写本をベツレヘムの靴職人で古物も扱っていた「カンドー」ことハリル・イスカンダル・シャヒーン (Khalil Eskander Shahin) の元に持ち込んだ。自身もシリア正教徒だったカンドーは、古代シリア語の文書かと思い、これを聖マルコ修道院の院長で、シリア正教会の大主教だったアタナシウス・イェシュア・サミュエル (Athanasius Yeshue Samuel) に見せた。アタナシウスは、4つの写本(『イザヤ書』 (1QIsa)、『ハバクク書註解』、『共同体の規則』、『外典創世記』)を24パレスチナポンド(現在の価値で約100ドル)で買い取った。 同じころ、ヘブライ大学考古学教授エレアザル・スケーニク (Eleazer Sukenik) とビンヤミン・マザール (Benjamin Mazar) も、ベドウィンが発見した写本(続けて発見した3つの写本)をカンドーが入手したことを知り、命の危険をおかして(当時アラブ人地区だった)ベツレヘムに赴き、1947年11月29日にカンドーから『戦いの書』、『感謝の詩篇』と『イザヤ書』断片 (1QIsb) の三つを買い取った。ここで、スケーニクは、あと4つの写本をアタナシウスが持っていることを知る。 1948年1月、スケーニクとマザールはアタナシウスと接触し、4つの写本の購入を図ったが話はまとまらなかった。アタナシウスは、第三者の評価によって写本の真価を知るために、アメリカ・オリエント学研究所 (American Schools of Oriental Research, ASOR) の研究者だったジョン・トレヴァー (John C. Trever) に写本を見せた。トレヴァーは、写本の書体や語法がナッシュ・パピルス(1898年にエジプトで発見された紀元前1世紀のものと思われる十戒を含むモーセ五書の抜書きの断片)のそれと非常によく似ているとアタナシウスに告げた。1948年2月21日、トレヴァーは、アタナシウスの持っていた写本(イザヤ書、共同体の規則、ハバクク書註解)を撮影したが、原本はその後インクの変質によって見にくくなり、トレヴァーの写真のほうが読みやすくなっている。 1948年4月、トレヴァーとスケーニクによって、世界に「死海周辺で古代の写本発見」の第一報がもたらされた。当時知られていた旧約聖書の最古の写本(レニングラード写本)を約1000年さかのぼる写本の発見は古代における旧約聖書の実情を示すものであり、イエス時代のユダヤ教の実態を知ることで、キリスト教誕生に関する新事実がわかるのではないかという期待が生まれた。 1948年5月に第一次中東戦争が勃発したが、アタナシウスは、写本を安全のためレバノンのベイルートに移していた。この後、アタナシウスは、写本をベイルートからアメリカ合衆国に移し、各地の大学や博物館などに買取りを打診してまわった。しかし、そもそも本物かどうかわからないという点と、もし本物だとしたら国宝級のものであり、所有権をめぐって国家間トラブルの招来が予想されることの二点を理由に、各地の施設が購入に二の足を踏んだ。最終的に、アタナシウスは、1954年6月1日のウォール・ストリート・ジャーナル紙に写本売り出しの広告を出した。そこには、「売りたし。四つの死海文書。少なくとも紀元前200年ごろにさかのぼる聖書テキスト。個人・団体を問わず教育機関や宗教施設に最高の贈り物」と書かれていた。写本は、匿名の購入者によって25万USドル(現在の価値で200万ドル以上)で購入された。「匿名の購入者」は、実はイスラエル政府の意を受けたマザール教授とスケーニクの息子イガエル・ヤディン (Yigael Yadin) であった。こうして、イスラエルは、最初の七つの写本を全て入手することに成功した。ヤディンは、1967年の第三次中東戦争時には、ベツレヘムのカンドーの自宅から第11洞窟から出た『神殿の巻物』を回収している。 最初に出土した7つの写本は、エルサレムのパレスティナ考古学博物館(ロックフェラー博物館)に入った。同博物館は、当時フランス・アメリカ・イギリスの各国政府が共同で運営していた。ところが、1961年になって、ヨルダンが、死海文書はヨルダンの財産であると宣言、1966年には考古学博物館も国有化した。イスラエルは、1967年の第三次中東戦争の後で考古学博物館にあった死海文書を回収し、イスラエル博物館内に新しく作られた「死海写本館」 (Shrine of the Book) に移した。ヨルダン政府による死海文書返還要求は、以後も繰り返されている。 死海文書研究の開始とその進展1947年の写本発見から2年がたっても、研究者たちは、写本の出所である洞窟の発見にすら至っていなかったが、国連休戦監視部隊のベルギー人将校フィリップ・リッペンス (Phillip Lippens) 大尉らが、ベドウィンから情報を得て洞窟(第1洞窟)を発見した(1949年1月28日)。委任統治領時代にイギリスによって設立されたヨルダン考古局 (Jordanian Department of Antiquities) の長官ジェラルド・ランケスター・ハーディング (Gerald Lankester Harding) は、同地域の考古学遺跡を管轄していたため、このニュースを聞いてクムランの洞窟探索を企画し、エルサレム・フランス聖書考古学学院 (École Biblique) の所長で、ヘブライ語聖書の専門家のドミニコ会司祭ロラン・ド・ヴォー(英語版) (Roland De Vaux) を誘った。1949年2月から3月にかけて二人の指揮のもと、アメリカ・オリエント学研究所も協力して第1洞窟が調査され、残っていた数百の写本断片が回収された。 その頃、ベドウィンたちも周辺の洞窟の探索を続け、考古学者たちを出し抜くようにさらなる写本を発見する。1952年に新たな写本が市場にでたことから、ド・ヴォーの指揮下でフランスとアメリカの考古学者たちが共同で周辺の洞窟群を調査、新たに5つの洞窟(第2〜第6洞窟)から写本を回収した。第3洞窟から発見された異色の発見物は「銅の巻物」と呼ばれるもので、その名のとおり薄い銅版に文字を刻んで巻物のように丸めたものであった。(銅の巻物には金を含む財宝の隠し場所が記されていて話題となったが、巻物に記された「財宝」は一つも発見されていない。)また第4洞窟からは膨大な量の断片が発見され、それらをつなぎあわせて600の巻物が復元された。これは死海文書の実に4分の3にあたる。以後、ヒルベト・クムラン遺跡を含めて、周辺の調査が続けられたが、洞窟からの写本の発見は1956年の第11洞窟の発見が最後になった。 死海文書の研究は、特定の教派によらない超教派による国際的な委員会によって行われることになった。ド・ヴォーが委員会のリーダーになり、ヨゼフ・タデウス・ミリク(Josef Tadeus Milik、ポーランド、カトリック司祭(後に還俗)、文献学)、パトリック・スキーハン(Patrick Skehan、アメリカ、カトリック司祭、聖書学)、ジャン・スタルキー(Jean Starcky、フランス、カトリック司祭、アラム語研究、パリ国立科学研究センター)、モーリス・ベイェ(Maurice Baillet、フランス、カトリック司祭、パリ国立科学研究センター)、フランク・ムーア・クロス(Frank Moore Cross Jr、アメリカ、プロテスタント長老派、後にハーバード大学教授)、クラウス・フンツィンガー(Klaus Hunzinger、ドイツ、プロテスタント(ルター派)、ゲッティンゲン大学)、ジョン・アレグロ(英語版)(John Marco Allegro、イギリス、メソジスト派(のちに無神論者)、オックスフォード大学)、ジョン・ストラグネル(英語版)(John Strugnell、イギリス、英国国教会、後にハーバード大学)、そして後にド・ヴォーの後継者に指名されるピエール・ベノワ(英語版)(Pièrre Benoit、フランス、カトリック司祭(ドミニコ会))といった気鋭の学者たちが集結した。委員会の研究成果は『ユダの荒野の発見物(英語版)』(Discoveries In The Judaean Desert、DJDと称す)叢書としてオックスフォード大学出版局から出版されることになった。 1951年にはド・ヴォーの指揮によるヒルベト・クムランの本格的な発掘調査も開始された。(簡単な調査に限っていえば1949年に一度行われている。)調査チームはそこで洞窟にあったものと同じタイプの壷を発見し、ド・ヴォーは死海文書を作ったのがクムラン教団であることを確信した。調査は1956年まで断続的に続けられたが、第二次中東戦争の勃発(1956年10月29日)によって中止された。遺跡の最後の調査は1958年に行われている。 写本への疑義死海文書の価値に関して学者たちは当初から認めていたわけではなく、調査の結果を待って静観の姿勢をとるものが多かった。研究の初期に死海文書への疑義を積極的に表明したのは、フィラデルフィアのドロプシー大学教授ソロモン・ザイトリン (Solomon Zeitlin) であった。彼はラビ文献の専門家であったが、写本が偽作で金目当てに捏造されたものだと訴えた。またイギリス人学者のゴドフリー・ドライバー (Godfrey Driver) も写本が紀元5世紀のものであると判断したが、後にこれを撤回し、紀元1世紀のものであるという説に同意している。写本の研究が進むにしたがって1世紀ごろの成立ということに関しては多くの学者たちの認めるところとなっていった。 最初の出版と委員会の「停滞」早くも1950年には最初の死海文書の公刊が行われた。ジョン・トレヴァーと2人のアメリカ人研究者ミラー・バロウズ (Millar Burrows)、ウィリアム・ブラウンリー (William Brownlee) の名義で『イザヤ書』、『ハバクク書註解』、続けて『共同体の規則(英語版)(宗規要覧)』が出版された。さらにスケーニクの監修した『イザヤ書』の第二の巻物、『感謝の詩篇』、『戦いの書』が(スケーニクの死後の)1955年にヘブライ語版と英語版で出版された。『外典創世記』もスケーニクの息子イガエル・ヤディンの努力によって1956年に出版された。ド・ヴォー率いる委員会もDJD(『ユダの荒野の発見物』叢書)第一巻を1955年に世に問うた。こうして1956年までに第1洞窟から発見されたすべての写本の内容が明らかにされた。最初に発見された写本群が迅速に出版されたのを見て、世の研究者たちは残りの写本に関しても国際委員会が迅速に公刊してくれるだろうと期待を抱いたが、その期待は完全に裏切られることになる。 委員会によるDJD(『ユダの荒野の発見物』叢書)は第1巻(1955年)、第2巻(1961年)、第3巻(1962年)、第4巻(1965年)、第5巻(1968年)と続けて出版され、第6巻(1977年)と第7巻(1982年)が思い出したように出版されたが、その作業は1960年代以降、遅々として進まなかった。その最大の理由は、第1洞窟から発見された写本がほぼ完全な形を保っていた(ので公刊もスムーズに行われた)のに対し、それ以外の洞窟から発見された写本は(第11洞窟から出た『神殿の巻物』を唯一の例外として)ほとんどが膨大な量の断片であり、再構成にかかる時間が膨大なものであったことによる(特に第4洞窟からは大量の文書が出たが、ほとんどが断片であったため、第4洞窟の文書の内容はなかなか明らかにされなかった)。また、リーダーのド・ヴォーが「委員会による公刊まで写本の内容を明かさない」よう委員たちに求めたことが、国際的な非難を受けることになった。 肝心の委員会の中からも不協和音が聞こえるようになる。1956年に委員のジョン・アレグロ(英語版)がBBCの放送で「銅の巻物」の内容に言及し、ヨルダン考古局と共同して『銅の巻物の宝物』という著作を1960年に委員会の許可を得ずに出版した。後にアレグロはこの「財宝」探索に乗り出す。さらにアレグロはソルボンヌ大学教授アンドレ・デュポン・ソメール(英語版) (André Dupont-Sommer) の感化を受けて「死海文書の内容がキリスト教の起源に関する重大な発見をもたらす」ものだと主張するようになる。1956年1月BBCのラジオ放送でアレグロは「死海文書の中に「義の教師なる人物がアレクサンドロス・ヤンナイオスによって捕らえられ、十字架にかけられ、弟子によっておろされ、その遺体が再臨の日まで守られること」が書かれており、これこそがキリスト教のルーツである」と述べ、大反響を巻き起こした。3月16日にド・ヴォーと委員会はタイムズ紙に反論を掲載、そのような記述が死海文書にはないことを明らかにした。後にアレグロ本人も「自分の推論」と認めている。アレグロは1970年にはユダヤ教やキリスト教が幻覚剤であるベニテングタケの効果によって生まれたことを述べた『聖なるきのこと十字架』を出版して以降、学者として認められなくなった。しかし、アレグロの主張はその後の死海文書をめぐる「カトリック教会の陰謀論」の原型として利用されることになる。 1967年の第三次中東戦争によって中東の政治情勢が大きく変化したことが、死海文書の研究継続に打撃を与えた。エルサレムとクムラン周辺がイスラエルの勢力下に入り、アメリカやイギリスの外交筋がエルサレムにおける紛争解決の日まで、一切の考古学的調査を控えるようにという要請を行った。これを受けてド・ヴォーのチームは活動を休止し、1971年にド・ヴォーが世を去ると(報告書の出版が細々と続けられたが)死海文書の研究が著しく妨げられることになった。 死海文書研究の転機1972年に死去したド・ヴォーに代わってピエール・ベノワ(英語版)が委員会のリーダーになると、作業の遅れが公然と非難されるようになる。1972年8月9日付のニューヨーク・タイムズは死海文書を特集し、その中で新しい編集主幹は公刊の遅れによる「民衆の怒りを避けるよう」努力することを薦めた。しかし、ベノワが委員会の代表をつとめていた12年の間に出版されたのはわずかDJD2冊に過ぎなかった。ベノワは健康上の問題を理由に1984年に辞任、ジョン・ストラグネル(英語版)が後を継いだが、その頃には委員会はメンバーが亡くなったり、辞任したりで人材が枯渇しており、委員会の実務能力はないに等しかった。 1987年は死海文書発見40周年の記念であったため、各国から死海文書研究と原典公刊の遅延を非難する声が再び巻き起こった(特に第4洞窟の文書の内容がまったく明らかにされていないことに世論の不満が高かった)。これを受けてフランス聖書・考古学研究所はジャン・バッティスト・アンベール(英語版) (Jean-Baptiste Humbert) をリーダーにした調査チームを立ち上げ、ド・ヴォーが残した死海文書とクムラン遺跡に関する膨大な調査記録の編纂を開始した(ド・ヴォーはクムラン遺跡発掘の報告書をまったく出版できずに世を去っていた)。 さらに死海文書を管理していたイスラエル古代遺跡管理局 (Israel Antiquities Authority, IAA) が、不適任という理由で1990年にストラグネルを委員会から外し、ヘブライ大学教授エマニュエル・トーヴ(英語版) (Emanuel Tov) を新しい委員長に任命した。トーヴは手始めに委員会の人数を60名に増員し、世界中から優れた学者たちを招聘した。トーヴの強力なリーダーシップのもと、世界が待ち望んでいた死海文書の公刊は急速に進展することになる。一方でトーヴはド・ヴォーの「公刊されるまで委員会以外に文書の内容を示さない」というルールを継承しようとしていた。しかし、1991年9月4日にアメリカのオハイオ州シンシナティにあるヒブル・ユニオン・カレッジに保管されていた死海文書の写真が『死海巻物未公刊本文予備版』と題して出版された。これを受けて、9月22日にはカリフォルニア州パサデナにあったハンティントン・ライブラリーも保管していた死海文書の写真版の公開を決定。イスラエル古代遺跡管理局 (IAA) は当初法廷闘争を企図したが、世論に配慮して方向転換し、9月25日に「死海文書の写真の自由な利用を認める」旨を発表した。最初の発見から44年をへて、初めて死海文書の全容が世界に示された(これらの死海文書の写真は、中東戦争時に損傷を恐れてアメリカで保管されていたものだった)。 「カトリック教会の陰謀」論の虚偽1991年にイギリスの作家マイケル・ベイジェント(英語版)とリチャード・リー(英語版)が『死海文書の謎(英語版)』(英語: The Dead Sea Scrolls Deception)を出版し、死海文書の出版が進まないのはカトリック教会(バチカン)の陰謀であると主張した。同書によれば委員長のド・ヴォーはバチカンから「写本の年代を紀元前2世紀として新約聖書の成立年代から極力離すこと」と「カトリック教会の教義をおびやかす内容がある場合、決して公表させないこと」という2つの指令を受けていたとしている。 「カトリック教会の陰謀」というテーマで一般受けした同書ではあるが、学術的にはまったく意味のないものである。オックスフォード大学の死海文書研究者ゲザ・ヴァーメシ (Geza Vermesh) は成立年代に関しては非カトリックの学者たちによっても広く認められていること、委員の中にはカトリック教会と無関係の者も多く、ド・ヴォーのそのような指示があったとしても従う義理のないものが多いこと、最終的にすべての写本の内容が公開されているが、キリスト教もユダヤ教もどちらに関してもその土台をゆるがすような記述は何もないことなどをあげて、まったくのナンセンスと論破している。ノートルダム大学の教授で死海文書の研究家ジェイムス・ヴァンダーカム (James VanderKam) もベイジェントとリーの著作について「死海文書のすべての巻物を利用することのできる今、誰もそこにキリスト教にダメージを与えたりするものや、バチカンが隠蔽しようとしたものを見出すことはできないでいる」と述べ、2人の陰謀説が「根も葉もない」もので、同書は「学問といかがわしさがこれほど奇怪に合体した書物を想像することは難しい」と切り捨てている。ベイジェントとリーは1982年にも『レンヌ=ル=シャトーの謎』 (The Holy Blood and the Holy Grail) を出版してカトリック教会の陰謀論を展開した(同書は後に『ダヴィンチ・コード』の原案となった)。 1991年、ロバート・アイゼンマン (Robert Eisenman) とジェームズ・ロビンソン (James Robinson) の監修によってハンティントン・ライブラリー所蔵の写真が『写真版死海巻物』 (A Facsimile Edition of the Dead Sea Scrolls) として公刊され、1992年には新委員長のトーヴによって全てのクムラン資料のマイクロフィルム版が出版された。1997年にはオックスフォード大学出版局が全死海文書の写真デジタル版CDを出版、さらに2010年10月19日にはイスラエル考古学庁がグーグルと共同で全死海文書のデジタル写真をインターネット上で公開する計画を発表し、作業を進めている。(40年間でわずか7冊のみと)ド・ヴォー及びその後継者の下で遅々として進まなかったDJDの刊行は、トーヴのもとで劇的に進行し、1995年から2000年までに第8巻から第38巻(5年間に30冊)が一挙に刊行された。第39巻は2002年、第40巻が2009年に出版されてようやく全作業が終了した。洞窟と発見された写本の一覧死海文書が発見されたクムラン周辺の洞窟群には発見順に番号がつけられている。第4洞窟と第7〜9洞窟はクムランに非常に近いが、第1、第3、第11洞窟はクムランから遠い場所にある。クムラン周辺には100以上の洞窟があるが、写本が発見された洞窟は全部で11である。以下に概要とそこからの出土品を示す。死海文書には断片にいたるまでほとんどすべてに整理記号がつけられている。たとえば「1QIsaa」とあれば、「クムランの第一洞窟 (1Q)」から出土した「イザヤ書 (Isa)」の「一つ目 (a)」という意味である。断片には整理番号がつけられている。たとえば「1QGen」(クムラン第一洞窟から出た創世記断片)は「1Q1」でもある。 1947年に発見された最初の洞窟。七つの写本が発見された。二つの『イザヤ書』 (1AIsaa, 1AIsab)、『共同体の規則(英語版)』 (1QS、1QSa(英語版))、『ハバクク書註解』 (1QpHab)、『戦いの書(英語版)』 (1QM(オランダ語版))、『感謝の詩篇』 (1QH)、『外典創世記』 (1QapGen)。そのほかに巻物を保管していた陶器の壷(クムランから出土したものと同型)、布切れ、写本の断片などが発見されている。 |
|||||
「★阿修羅♪ > カルト19」の仁王像 氏の2018 年 12 月 09 日付投稿「エルサレムの東の 死海のクムラン洞窟から発見された「死海文書」は、偽造された古文書らしい/副島隆彦」。
|
| 【ユダ福音書】 |
| 2006.5.28日付毎日新聞「今週の本棚」の辻原登・氏の「ユダの福音書を追え」評参照。 |
| トマス福音書の衝撃に続いて新たに「ユダの福音書」が出現した。「ユダの福音書」は、紀元180年にリヨンの司教エイレナイオスが有害な異端の書として批判したもので、「トマスによる福音書」などのグノーシス文書と同系列に属し、写本成立は4世紀初頭と看做されている。「イスカリオテのユダとの対話でイエスが語った秘密の啓示」であるとされている。イエス物語のクライマックスであるゴルゴタの丘の磔刑(たっけい)に於けるユダの裏切りが知られている。この逸話がユダヤ人迫害に一役買っているが、この定説を覆す逸話が登場したことになる。それによると、弟子のユダは、イエスを裏切ったのではなく、イエス自らが指示し密告させたと記されており、従来のユダ像を覆す内容となっている。 「最後の晩餐」の下りでのイエスの次の言葉が知られている。「マタイ福音書」は次のように記している。「特にあなたがたに言っておくが、あなたがたのうちの一人が、私を裏切ろうとしている。人の子を裏切るその人は、禍である。その人は生まれなかった方が、彼のためによかったであろう」。ユダが言った。「まさか、私ではないでせう」。イエスは言われた。「いや、あなただ」。イエスはローマ総督ピラトに渡され、十字架に架けられる。裏切ったユダは、代価の銀貨30枚を投げ捨てて、首を吊って死ぬ。 「ユダの福音書」が世に出るまでには曲折があった。1970年、中部エジプトのナイル川の岸辺近くで、農民が地下墓から崩れかけた石灰岩の箱を見つけた。中に革張りのパピルス紙の書物が入っていた。古代エジプト語のコプト語で書かれていたパピルス古文書であることが判明した。但し、内容が分からず骨董品として転売され、その経緯で破損した。 ハンナ・アサビルという名のカイロの古美術商が売込みを図り、かつての死海文書やナグ・ハマディ文書に匹敵する古代キリスト教関係の重要な資料ではないか、という見方が芽生えた。後に「ユダ福音書」と命名されるが、その後約25年間解読されないままアテネ、ジュネーブ、ニューヨークへと移管され、途中で窃盗団によって行方が分からなくなったりの騒動の末、再び最初のハンナの手に戻った。ハンナは、ニューヨーク郊外の小さな銀行支店の貸金庫に預けたままカイロに帰る。その後16年間、貸金庫に眠ったまま2000.4月、コプト語の専門家、パピルス古文書の専門家チームによる解読が始まる。そして、「ユダ福音書」と命名される。ナショナルジオグラフィック協会の支援を得て、専門家が粉々の断片を最新技術で復元し、解読、英訳された。 2006.4月、映画「ダ・ヴィンチ・コード」が公開された。続いて、2006.5月、日本で、「ユダの福音書を追え」(ハーバート・クロス二ー、日経ナショナル)、6月、「原典ユダの福音書」の題で出版された。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)