
| 隅の詰め碁例題/石の下の筋 |

更新日/2024(平成31、5.1栄和改元/栄和6).2.4日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、「隅の詰め碁例題/石の下」の筋を確認する。 2014.10.27日 囲碁吉拝 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 |
| 自分の石を取らせたあとに手が生じる石の捨て方を「石の下」と呼ふ。「石の下の筋」は、捨て石跡を手段するという高度なテクニックである。実戦では気づかないことが多い。石の下にはダンゴ型や集四型、稲妻型がある。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||
|
| 1(正解初手) | |
| 1(正解初手)/。 | |
| その後図 | |
| 黒がBと白2子を抜くと、白△、黒×、白Aと打たれて欠け目で黒死。ところが、黒Aと打つと、白はBで黒4子を取る。そのあと黒が□に打つと隅の白3子が取れて活きとなる。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||
|
| 1(正解初手) |
|
| 1(正解初手)/当り。 | |
| その後図1 | 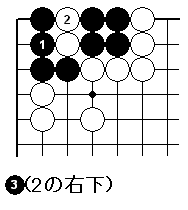 |
| 2/黒4子取り。 | |
| その後図2 | 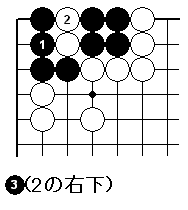 |
| 3/2子当りとなり「石の下の手筋」で生きている。 |
| 【隅の詰め碁例題/集四型の石の下の筋】 | ||||
「ウィキペディア石の下」参照。
|
| 1(正解初手) | |
| 1(正解初手)/白2子取り。この黒1は後で取らせる捨て石として活用する。 | |
| その後図1 | |
| 2/放り込み。黒aと取れば白bで欠け眼にしようとする狙いである。四角形の黒4子がアタリになっているが、どうするか。 | |
| その後図2 | |
| 3/ツギ。構わずに黒3と打つ。4/黒4子取り。取らせた四角形の黒4子の形を集四またはダンゴと呼ぶ。 | |
| その後図3 | |
| 5/キリ当り。白2子を取って一眼、隅の一眼で二眼の生きとなる。以上の黒1、黒3、黒5の一連の手段を石の下の手筋と呼ぶ。特に黒5は「取られた跡の切り」なので跡切りと呼ぶ。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】(石の下の筋) | ||||
|
| 1(正解初手) | 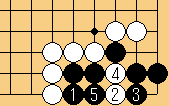 |
| 1(正解初手)下がり。この手が石の下の始まりの好手。 | |
| その後図1 | 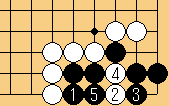 |
| 2/ノゾキ置き。 | |
| その後図2 | 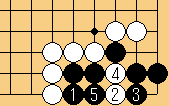 |
| 3/眼づくり押え。4/突込み。5/白2子抜き。 | |
| その後図3 | 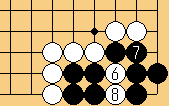 |
| 6/打ちかき。7/ツギ(決定打)。この手が「石の下の手筋」を用意している。8/黒4子取り。 | |
| 決定打 | 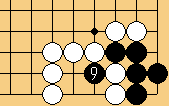 |
| 9/取り跡切り。この手で2目を取り返す。これを「石の下の手筋」と云う。 |
| 【隅の詰め碁例題/稲妻型の石の下の筋】 | ||||
「ウィキペディア石の下」参照。
|
| 1(正解初手) | |
| 1(正解初手)/ノビ。 | |
| その後図 | |
| 白2、黒3、白4、黒5、白6、黒7、白8。黒1から黒3で捨て石を4子に増やす。この4子の形を稲妻形と呼ぶ。白4から白8で稲妻形の黒4子を取らるが、 | |
| 決定打 | |
| 黒9。白6子を取って生きることになる。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||
|
| 1(正解初手) | 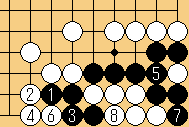 |
| 1(正解初手)/ノビ。これが「石の下の手筋」を見通した手である。 | |
| その後図1 | 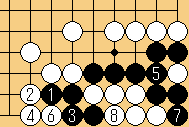 |
| 2/。3/。4/。 | |
| その後図2 | 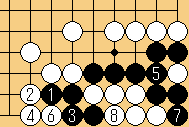 |
| 5/。6/。7/。8/まで黒4子が取られる。 | |
| 決定打 | 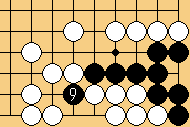 |
| 9/取り跡切り。この手が石の下の手筋になっている。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||
|
| 1(正解初手) |  |
| 1(正解初手)/。 | |
| その後図1 |  |
| 2/。3/。4/。1から3のとき4がオイオトシ狙いです。 | |
| その後図2 |  |
| 5/。6/。7/。黒はかまわず5と大きくして6目を取らせに向かう。 | |
| その後図3 |  |
| 8/ウチカキ。9/トリ。10/。11/。 | |
| その後図4 |  |
| 12/。13/取り跡キリ。12が取られ隅の眼がなくなっている。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||
|
| 1(正解初手) |  |
| 1(正解初手)/この1の所を白につがれるとセキだから黒1と切るよりない。 | |
| その後図1 |  |
| 2/。3/。4/。黒4子を捨石にする。 | |
| その後図2 |  |
| 5/眼欠き。ここが急所である。5で5の左は白5の所で逆転の石の下という面白い形になっている。 |
| 【隅の詰め碁例題/石の下の筋】 | ||||||
「NHK杯で石の下出現!」( 2010/08/01 )参照。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)