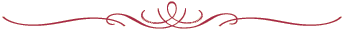
| 囲碁将棋由来と思われる用語、諺考 |
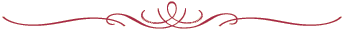
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).3.26日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、「囲碁将棋由来と思われる諺考」をものしておく。 2018(平成30).10.6日 囲碁吉拝 |
![]()
| 【囲碁将棋由来と思われる諺考】 | |||
「論語」の「学而編」の中に次の句がある。
これを、学問的問答を求めての知者の交遊を描写した格言と受け取るのが普通である。私も否定はしないが、ただしだ、囲碁愛好家が碁仇を求めて来訪した時の、された側の者の喜びの気持ちを綴ったものとして受け取る方が、よりビビッと来る。 |
|||
「論語」の「学而編」の中に次の句がある。
孔子は、学びについて、「知る」、「好む」、「楽しむ」の三段階で説いている。最初は「知る」の段階である。これを自発的に自ら学ぶ意志が働く段階である「好む」の域にまで高めれば大いに上達していることになる。さらにその上に「楽しむ」の域があるという。これを最上達域にしている。仕事も趣味も楽しむ者には敵わないという譬えであり、碁の習熟に比すれば能く分かる。日本の諺「好きこそものの上手なれ」もこれら通じていよう。 |
| 【囲碁将棋由来と思われる諺考】 |
| こういう例は他にもある。普段何気なく諺一般の文句として受け取られているが、碁の局面描写として受け取る方がよりスッキリ理解できるので、由来を囲碁からとした方が良さそうなものが結構ある。例えば、以下の通り。 |
| 「駄目」(だめ) |
| 「駄目」は一般に「してはいけないこと」、「できないこと」、「良くない状態」を表す言葉として使われるが、囲碁でとは、「両者の地又は勢力の境にあってどちらの地(所有)にもならない、打ってみるだけの価値のない場所(目)」を指す。「目」とは「碁石を置く場所」のことで縦横の直線の交差点を指す。 |
| 「駄目押し」 |
| 「駄目押し」は、日常的に「念のためもう一度確かめておく」という意味で使われる。スポーツの試合では「ほとんど勝敗は決しているのに、さらに点を取ったり攻撃を加えて勝利を決定的にする」の意味に使われている。 |
| 岡目八目(おかめはちもく) |
| 「岡目八目」の「岡目」とは、他人がしていることをわきで見ていることを云う。「傍目」とも書く。「岡目八目」とは、「打っている者よりも、そばで見ている人の方が形勢とか局面、打った手の良し悪しなどを正しく判断できること」を云う。八目ぐらいの差がつく手が見えるところから生まれた用語と思われる。「八目先まで手を見越すことができる」と解する説もあるが、そこまで読める打ち手は少ないので意訳し過ぎのように思われる。 余談/「岡」の付く言葉としてはほかに、「岡惚(ぼ)れ」、「岡焼き」、「岡評議」がある。岡惚れは、わきから密かにその人に恋をすることで、岡焼きは、直接自分に関係がないのに、わきから他人の仲のいいのを妬(ねた)むことです。岡評議は、局外者の無用で無駄な評議のことです。「岡吟味」とも言う。 |
| 一目置く(いちもくおく) |
| 「一目置く」とは、「自分より相手が優れていることを認め、敬意を払うこと」です。強調して「一目も二目も置く」という場合もある。
囲碁では、対戦者間に実力差がある場合、「置き碁」というハンデ戦ができる。弱い方が2子から9子まであらかじめ碁盤に石を置いて対局するもので、下手が強くなるに従い置き石を減らしていくことになる。 囲碁は通常、「黒が先手」と決まっているが、置き碁では白が先手となる。一目置いただけでは通常の碁と変わらないため、置き碁では、弱い方が対戦が始まる前に二目以上の碁石を置く。将棋でも、上手の人から飛車・角行の大駒を取り除いて行う「二枚落ち」、あるいは角行だけを取り除く「角落ち」というハンデ戦がある。 |
| 白黒(しろくろ)つける |
| 「白黒つける」とは、「物事の是非・善悪・真偽などを決める、決着をつけること」。「黒白(こくびゃく)をつける」とも言う。囲碁が白石と黒石で勝負をつけることから来た言葉である。
|
| 布石(ふせき)を打つ |
| 「布石を打つ」とは、「将来に備えてあらかじめ手はずを整えておくこと」。囲碁では「対局の序盤で要所要所へ石を配置する陣形づくり」のことを云う。 |
| 捨て石(すていし) |
| 「捨て石」とは、「将来、または大きな目的のために、その場では無用とも見える物事を行うこと」や「大きな目的を達成するために見捨ててしまう事柄」、「将来のためにあえて犠牲になること」。囲碁では、「大局的見地から、あえて相手に取らせるように打つ石」を「捨て石」と云う。 |
| 目論見(もくろみ) |
| 「目論見」とは。「物事をしようとして考えをめぐらすこと」。 |
| 「目算(もくさん)」 |
| 囲碁で、「対局中に自分と相手の地を数えて形勢を判断すること」を云う。 |
| 活路(かつろ) |
| 「活路」とは、「苦しい状況から生き延びる方法を切り拓くこと」を云う。 |
| 死活問題(しかつもんだい) |
| 「死活問題」とは、「死ぬか生きるかの重大な問題のこと」です。囲碁では、二眼持って治まるのを生き、二眼できず殺されるのを死にと云う。例題的に石の生き死にを問うのを「死活」と呼ぶ。 |
| 玄人(くろうと)・素人(しろうと) |
| 「玄人」とは、「ある分野での技能者、専門家」のこと、「素人」とは、「専門的な知識や技術を持たない初心者」のこと。囲碁では、現代では上位者が「白石」、下位者が「黒石」を持つ。昔は上位者が「黒石」を持った。 なお、素人・玄人の語源については次のような説もある。平安時代には、「白塗りをしただけで芸のない遊芸人」を「白人」(しろひと)と呼び、それが室町時代に「しらうと」、江戸時代に「しろうと」に変化したという。「白人」が「素人」の漢字表記に変わった理由ははっきりしないが、「素」には「ありのまま」という意味のほかに「平凡な」、「みすぼらしい」という意味もあるので、そこから来たとも考えられる。「素人」の対義語「玄人」は、「白人」に対して生じた言葉で、もともとは「黒人」(くろひと)と言ったその「くろひと」が音便化して「くろうと」になったもの。「玄」も「黒」という意味。「黒」よりも「玄」の方が奥深く容易ではない意味合いが強いので「玄人」と書くようになった。 |
|
||
|
||
|
||
| 「人のふり見て我がふり直せ」も然り。 この諺は諺一般の文句として通用するが、碁の教訓として受け止めた方がよりピッタリするように思える。 |
||
| 「八百長」(やおちょう)然り。 「八百長」とは、「真剣に勝負を争うように見せかけ、実は前もって約束しておいた通りに勝負の結末をつけること」をいう。語源は明治時代の八百屋の長兵衛さんの物語から始まる。長兵衛さんは皆から「八百長」と呼ばれていた。彼には伊勢ノ海五太夫という囲碁仲間がおり、本当は長兵衛さんの方が強かったのだが、八百屋のお得意さんなので時々わざと負けて機嫌をとっていた。ところがあるとき、本因坊秀元という強い碁打ちと互角の勝負をしたことで、長兵衛さんが本当は滅法強いということがばれてしまった……という故事に由来する。これより、何か魂胆があってうまく負けることを「八百長」というようになったと云う。 |
| 「急いては事を仕損じる」。これもそう。 |
| 「能ある鷹は爪隠す」。これもそう。 |
| 「虎穴に入らずんば虎児を得ず」。これもそう。 |
| 「狙った獲物は外さない」。これもそう。 |
| 「二兎を追う者は一兎をも得ず」。これもそう。 |
| 「命あっての物種(ものだね)」。これもそう。 |
| 「肉を切らせて骨を断つ」。これもそう。 |
| 他にも気づき次第確認しておくことにする。 |
| 【囲碁将棋由来と思われる言い回し考】 |
| 白黒付ける |
| 駄目 |
| ダメ押し |
| 一目(いちもく)置く |
| 先手 |
| 先手を打つ |
| 先手を取る、先手必勝 |
| 後手 |
| 後手に回る |
| 手を打つ |
| 下手を打つ |
| 打つ手なし |
| 手抜き |
| 手順前後 |
| 手筋 |
| 筋がよい |
| 筋違い |
| 玄人(くろうと)・素人(しろうと) |
| 八百長 |
| 定石 |
| 布石 |
| 捨石 |
| 死活問題 |
| 結局 |
| 局面 |
| 大局観(だいきょくかん) |
| 傍目八目・岡目八目(おかめはちもく) |
| 目論見(もくろみ) |
| 活路(かつろ) |
| 目算(もくさん) |
| 必死/必至(ひっし) |
| 詰めが甘い |
| 大詰め |
| 地合いがいい、地合いが悪い |
| 味が良い |
| スキがない |
| 咎(とが)める |
| 待った |
| 投了 |
| 形作り |
| 最後のお願い |
| 角番(かどばん) |
| 王手 |
| 逆王手 |
| 成金 |
| 成り上がる |
| いぶし銀 |
| 高飛車 |
| 持ち駒 |
| 手駒 |
| 捨て駒 |
| 詰み |
| 将棋倒し(しょうぎだおし) |
| 歩兵 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)