
更新日/2019(平成31→5.1栄和改元).6.8日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
ここで「日本囲碁史考2」として武士の時代になる鎌倉時代から江戸時代初期の徳川政権誕生前夜までの囲碁史を確認しておく。
概要「囲碁は、鎌倉時代(1192~1333)までは二子ずつ対角の星に置き合って打ち始めていた。安土・桃山時代になって第一着手から自由にどこを打ってもよい手法に変わった。日蓮宗の京都寂光寺の僧・日海上人に初めてみられたと云われている」。この謂いのどこまでが本当のことか分からない。
2005.4.28日 囲碁吉拝 |
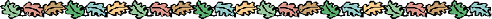
| 1180(治承4)年から1235(嘉禎元)年までの56年間、鎌倉時代の公家藤原定家の日記「明月記」に囲碁に関する記事が散見する。囲碁が原因の喧嘩で揉める話もある。 |
1182年頃、81代安徳帝の寿永年代、源廷尉(義経)門下の壮士相集まりて囲碁。駿河、亀井、相当り。武蔵坊弁慶、伊勢三郎側にあり。武蔵坊。駿河に助言し、亀井怒り、武蔵坊を打つ。武蔵坊直ちに三郎を打ち曰く輪次也と。(「永富独嘯の*光秘録」)
1184年頃、文治年代、碁盤忠信の伝説。義経の都落ちの時、「陸象山、奕を観て曰く、河図洛書まさにこのうちにあり。堯舜の作豈徒然ならんやと」。(「坐隠談叢」)
| 源頼朝に追われる身となった義経の忠臣佐藤忠信が碁盤を持って戦ったと言う(伝説碁番忠信)がある。これは浄瑠璃で脚色されたもので有名となった。義経関連では弁慶が愛用したと伝えられている碁盤、碁石、碁笥が現存している。 |
| 源頼朝にも碁会の逸話が爛柯(らんか)堂棋話に載っている。ただ、この記事を伝える吾妻鏡は、「建久元年…、栄中双六御会有り」と、碁ではなく双六とする。吾妻鏡には和田義盛、北条時房、北条時頼などの鎌倉武人にかかわる囲碁逸話が記されている。(「囲碁史研究家・増田忠彦の囲碁研究」) |
| 【西行法師の囲碁逸話】 |
西行法師/著「山家集」(1180年頃成文)巻3の条は次のように記している。
| 「雑、伊勢のたふしと申す島には、小石の白のかぎり侍る浜にて、黒は一つも混じらず、むかひてすが島と申すは、黒のかぎり侍るとなり」。 |
すが島や 答志の小石 わけかへて 黒白まぜよ 浦の浜かぜ
鷺島の小石の白をたか波の たふしの浜に 打ち寄せてける
島崎浜の 小石と思ふかな 白もまじらぬすが 島の黒
あはせばや さぎとからすと 碁をうたば たふしすが島 黒白の浜 |
|
| 【鎌倉時代】 |
| 1185(文治元)年11月、源頼朝が守護地頭を設置し、鎌倉に幕府を置いた時代より鎌倉時代が始まる。1192(建久3)年、源頼朝が征夷大将軍に任命され名目的にも時代の支配者の地位に就いた。 |
1186年頃、82代後鳥羽院の文治建久年代、後鳥羽院、囲碁に賭け物を下賜。御碁打たせ給うついでに、若き殿上人ども召して、これかれ心の響きに挑み争はさせ給えば、あるは、こゆみすごろくなど云うことまで思ひ思いに勝ち負けをさうどきあへるをいとおかしう御らむじて云々。(「二中歴」)
囲碁名手道範阿闍梨あり(後鳥羽帝の帰依浅からざる人)
| 鎌倉幕府の時代、囲碁が再び盛んになった。宮廷、貴族に広まった囲碁は、武士、僧侶などの知識階級へ、さらに農業、商業の人々の間にも広まっていった。源義家も頼朝も碁を好んだと伝えられている。当時の文学として歴史書「吾妻鏡」(あずまかがみ)、「太平記」(たいへいき)、吉田兼好の随筆「徒然草」(つれづれぐさ)などにも囲碁に関わる記述がある。 |
| 「通ひ路の中へ碁盤の関を据え」。これは、人妻のもとへ忍び通う、若い八幡太郎義家を詠む雑俳(川柳)である。原話は古今著聞集にある。源義家には別の囲碁逸話も伝わる。「うちうたず君が手並みを知らぬ間は浜の真砂ぞあやぶまれける」。これは少し下って源三位頼政の「囲碁」と題した和歌である。 |
| 1190(建久元)年、。 |
ランカ堂棋話が次のように記している。
| 「ある時、頼朝が碁会を催し、諸士伺候して終日碁を楽しんだ。その時、佐々木盛綱が頼朝の相手をした。北条時政、大江広元らがそれを見物していた。(以下略)」。 |
|
|
| 1190年、西行の山家集に、志摩国答志島及び菅島を、碁石の産地とする記録あり。 |
| 1191(建久2)年、。 |
「玉葉集」(摂政藤原(九条)兼実の日記)。
| 「(1191(建久2)年)七月廿七日、癸酉、大将(藤原良経)来る[布袋也]。今日、囲碁上手二人を召して、その興を催す。[舞人好方、越前公実暹等なり。好方定先を得、猶算二を負け(負二を算して)了んぬ。懸け物扇十二本]」。 |
九条(藤原)兼実は九条家の祖とされる鎌倉初期の公家、頼朝の知遇を得て摂政・関白に昇った(日記の当時は摂政)。大将・藤原良経は実子。囲碁の上手、舞人好方と越前公実暹を招いて賭物に扇を供して対局させた。人の内、越前公実暹は、越前の斎藤氏の人物と思われるが詳細不詳。舞人好方は吾妻鏡にでてくる宮舞曲・神楽曲の名人、右近将監多好方(おおのよいかた)と推定されている。 |
| この頃、藤原定家の「明月記」に囲碁の記事多し。 |
1192(建久3)年、源頼朝が征夷大将軍となり、鎌倉に幕府を開く。
| 1198(延喜元)年、。 |
世紀末に編まれた人文関係の百科事典「二中歴」が編纂されている。寛蓮以下、平安から鎌倉期にかけての囲碁の上手の名前を列挙している。
| 「囲碁、碁聖、寛蓮・賀陽・祐挙・高行・実定・教覚・道範・十五小[少]院・長範・天王寺冠者(欠文)説云、碁聖は囲碁上手之称也。賀陽は外記賀陽宣政[正、手]也、祐挙は石見守平祐挙也、高行は右衛門入道也、実定は豊後守中原実定也、教覚は三井院人也、道範は嵯峨闍梨、十五少院者」。 |
|
| 1199年、。 |
| 玄尊(げんそん) |
| 1199(正治元)年6月、鎌倉時代の玄尊(げんそん、生没年不詳)が「囲碁式」という棋書を著す(「群書類従」に収められている)。それによれば、碁盤の正式な大きさ、礼儀作法、取り決め、心構えに始まり、定石、手筋などの解説書であり、当時すでに相当に碁の技術があがっていたと思われる。「囲碁式」は平安の上手・寛蓮が醍醐天皇に命じられて勅撰した日本で最古の囲碁の解説棋書といわれている「碁式」を踏まえての焼き直し書「囲碁口傳」(「群書類従」に収められている)の一部を転載編述したものといわれている(「綜合囲碁講座
別巻」】)。囲碁式は現存する最古の棋書とされ、その編者・玄尊もこの当時の上手である。「囲碁口傳」の中に、広定・天王寺冠者・公安といった碁打ちの名がみえる。 |
「囲碁式」(いごしき)には対局のコツや、先人から伝わってきた囲碁の本質を表すような次のような言葉が記されている。 例えば、ハンデなしの対局をする場合には、四方に目を配って慎重に相手の間違いを見つけなさい、ハンデをつけて対局する場合は、あちこちに石をまいておいて後にそれを利用して戦いなさい、特別な碁会の際には、落ち着いた場所に畳を並べ敷いて立派な碁盤と石を置くこと。強い相手と対局するときは、前日の夜はよく眠るべきである。酒はとくに慎み、鹿の肉を食べることなどは避けるべきである。負けそうもない敵に負けることがあっても年のせいにしてはならない等々。体調の整え方や耳が痛くなるような心得まで事細かに記されている。
| 「凡そ囲碁肝心この式にすぐべからず。少々所抄出也。先達の口伝並私の意楽。為未練注之。広定説云。[天王寺冠者]如法の上手の碁は面白き手なし。心得ざることできるこそ興ある手にもあれ。あやまり有るまじき様に兼ねて打をきたるは、目をおどろかす事なしと云う。又曰く、上手は幼少より打つ。成人の後に打出るは逸なる物にはなるべからず。…公安説云。[秦五]碁は所詮只能々案ずるにはしかず。いそぎて打たば必ず後に悔あり」。 |
|
「旧坐隠談叢」が次のように記している。
| 「当時、源右府(頼朝)を初め、将士の棋をよくしたる者多く、(中略)日蓮の棋をよくしたると、意雲老人と云える名人ありし等、枚挙にいとまあらず」。 |
|
| 1200(正治2)年、。 |
玉葉(関白藤原(九条)兼実の日記)。
| 「二月四日、庚申。天晴る。この日春日祭なり。祓を修め遥拝す。南の極み山峰に迫り一星あり。蓋しこれ老人星か。瑞と謂ふべきか。中将(記者兼実の男・良輔)の小舎人童、生年十二歳、囲碁の上手の由を聞きこれを召見す。実に以つて不思議なり」。 |
|
| 1200(正治2)年、。 |
明月記(藤原定家の日記)。
| 「二月四日、天晴る。風雪、甚だ寒し。午の時ばかり、召しに依り八条殿( 子御所)に参る。中将殿(良輔)、九条殿(兼実)に参り給ふ。御共すべき仰せなり。未の時ばかり御共し参入す。中将殿の小童、囲碁の上手なり。件の碁、御覧ずるの料なり。御前に召し了んぬ。其の後大臣(良輔)殿に参る。未だ見参せざる間に、腹病忽発り、苦痛術なし。仍て退下す。辛苦極りなし」。 |
関白・藤原(九条)兼実(当時、関白)に召しだされて技を披露、藤原定家も兼実の第に伺候して対局を見物した。 |
1205(元久2)年、畠山重忠讒(ざん)せらる。平賀武蔵守と六郎重保と碁を争いたる結果に出づ。(「坐隠談叢」)
1205(元久2)年頃、時政の後妻牧方の女婿、武蔵守朝雅、京都の守護職として常に京にあり。牧方の陰謀のため反逆者として幕府方より討手を受く。朝雅、この日、仙洞に伺候して碁を囲み居たりしも、急と聞いて少しも騒がず徐に局を終り、石を*めて後、挨拶して打って出でたり。(「吾妻鏡」)
1213年、84代順徳帝の建保元年、和田義盛挙兵の時、三浦胤義変節し密かに急を北条義時に告ぐ。義時、この日、囲碁の会を催ほし対局中なりしも、少しも騒がず、目算をした後、徐に局を収め急に応じたり。(「吾妻鏡」)
1217(建保5)年、「7月21日、今日上皇御発心地落し令む。すなわち御験者阿闍梨道範、御剣御馬御衣等を賜い権少僧都に任ず。先に律師に任被られ云々。上皇は後鳥羽院、道範は囲碁の名手」。(「百錬抄」)
1221年、85代仲恭帝の承久3年、吉備大臣入唐絵詞出る。作者は参議雅経。かって藤原の定実と新古今集を撰す。(「碁誌、安藤如意記」)
1233年頃、87代四条帝の天福元年頃、「金田府時光と云う笙吹と市允茂光と云ひ**吹きあり。常に寄り合いて囲碁を打ち、世間のこと公私ににつけて心入らざる折節、内裏より時光に急のお召しあり。いつもの癖なれば、時光耳にも聞き入れず。皆々騒いで如何に如何にと勤めけれども終に聞かず。御使力及ばず内裏にこの由を奏聞す。何計らいの勅勘にてかあらんと思けるところに、主上仰せありけるは、勅命を顧みず万事を忘れて心を澄まし、面白かるらん、やさしさよ云々」。(「源平盛衰記」)
| 【北条義時、北条時頼などの囲碁逸話】 |
「吾妻鏡」には北条義時、北条時頼などの囲碁逸話などが残されている。第39、1248年8月が、北条時頼(鎌倉幕府第5代執権で北条時宗の父。執権在職1246-1256年)に関連して次のように記している。
| 「一日乙亥 左親衛(時頼)、甲斐前司(長井泰秀)が亭に渡御す。下野前司(宇都宮)泰綱・出羽(二階堂)前司行義等参会す。囲碁の勝負を決せらる云々」。 |
北条時頼が囲碁愛好家であったことが分かる。武士の博打を禁止している。「但し囲碁、将棋者は非制限」とした。これにより武士の囲碁熱が高まった。 |
| 【兼好法師の随筆「徒然草」の囲碁記述】 |
鎌倉時代後期から南北朝にかけての歌人/兼好法師の随筆「徒然草」にも囲碁に関して触れられている個所があり、囲碁に対して兼好独特の評価をしている。かなりの愛棋家だったことが知れる。
| 「碁を打つ人、一手もいたづらにせず、人に先立ちて小を捨て、大に就くが如し。それにとりて三つの石を捨てて、十の石につくことは易し。十を捨てて十一につくことは難(かた)し。一つなりとも勝らんかたへこそつくべきを、十までなりぬれば惜しくおぼえて、多く勝らぬ石にはかへにくし。これをも捨てず、彼をも取らんと思う心に、彼をも得ず、これを失うべき道なり」(「徒然草第188段)。 |
| (三つの石を捨てて十の石を取るのは容易(たやす)いが、十の石を捨てて十一の石を取るのは難しい。一つでも得がいけばいいのだから、十の石を捨てて十一の石を取るべきなのに、十となると惜しくなって捨てきれず、捨てないで十一の石を取ろうとすると、石は取れないどころか我が石の十の石を失うことになるのが道理である) |
| 「拙き人の、碁打つ事ばかりにさとく、巧みなるは、賢き人の、この芸におろかなるを見て、己れが智に及ばずと定めて万の道の匠、我が道を人の知らざるを見て、己れすぐれたりと思はん事、大きなる誤りなるべし」(「徒然草第193段)。 |
| (知力の乏しい人が自分が碁を巧みに打てるからといって、碁の技芸には劣っている賢い人を見て、こいつは自分よりも知力が劣っていると決めつける。それぞれの道に通じた専門家(職人)が、他人が自分の専門分野のことを知らないのを見て、自分のほうが優れていると思い込むのは大きな誤りである) |
| 「囲碁双六(すごろく)好みて明かし暮らす人は、四重五逆にもまされる悪事とぞ思うと、ある聖の申ししこと、耳にとどまりて、いみじくおぼえ侍る」。 |
|
| 【僧・道元の著「正法眼蔵」の囲碁記述】 |
| 僧・道元の著作正法眼蔵にも囲碁のくだりがある。道元は1253年に53歳で没した曹洞宗の開祖である。 |
| 【北条時頼の囲碁愛好】 |
2016.02.26 「北条時頼と囲碁」。
|
鎌倉の明月院に鎌倉幕府第5代執権・北条時頼の墓があります。時頼は晩年、出家して、この地に「最明寺」を建立し暮らしていたそうです。有力御家人、三浦泰村一族を滅ぼすなど、北条氏による執権政治を強固にした時頼は、数々の善政を行った名君でもあったと言われています。鎌倉幕府は、大事件が起こると諸国の武士を鎌倉によび集めていましたが、「鉢木」という謡曲(能の曲)では「いざ鎌倉」という言葉が使われています。謡曲「鉢木」は北条時頼が執権を退いた後、僧となって諸国を回ったという伝説から生まれたもので、次のような物語です。上野国
(群馬県)の佐野(高崎市内)に、佐野源左衛門常世という貧しい武士が住んでいました。ある雪の夜に常世の家に旅の僧がやってきて一晩泊めてくださいとたのまれます。常世は僧を泊めることとし、粟のご飯でもてなし、マキがなくなると、大切な鉢植えの梅・松・桜の木を囲炉裏にくべ暖をとったそうです。常世は僧に、一族に領地を取られ、今は落ちぶれてしまったが、「いざ鎌倉」というときには鎌倉に一番にかけつけて戦う覚悟だと語りました。その後、鎌倉幕府から、集まれという連らくが来たので、常世は、やせ馬に乗って、鎌倉に駆け付けますが、そこには、雪の夜に泊めた旅の僧がいて、前執権・北条時頼であったとわかりました。時頼は、常世の言葉に嘘がなかった褒美として、奪われた領地を取りもどし、大切な木をくべたもてなしのお礼として、梅田・松井田・桜井の三ヶ所の土地が更に与えられたと言われています。
ところで、北条時頼は囲碁の愛好家であったと言われています。当時、博打を行う武士が多かったため時頼は武士による博打の禁止令を出します。この時、「但し囲碁・将棋者は非制限」とした事から、武士の間で囲碁が更に広まっていったそうです。
|
|
1251年、89代後深草帝、建長3年、「正月17日、すけやすが元にゐきのふのある参らせよといふ心、歌に詠みてやれと仰せごとありければ、少将内侍折々に、こけのむすの山の奥のふもとにてこれを*みをへて帰りけん。返し中将 ふるさとのはなの盛りをもろともに**みまし昔なりやと。なほせめにやれと仰せごとありしかば、弁内侍 ふる里の花よりもげにおもひやれ。それより奥のしがの山越え」。(「弁内侍日記」)
| 1253(建長5)年 |
| 正月、僧侶・日蓮32歳、弟子・日朗(吉祥丸、11歳)が鎌倉の松葉谷の草庵で打った棋譜が残されている。「僧侶・日蓮-弟子・日朗(吉祥丸)(2子局)」。181手まで
ジゴ。三神松太郎(江戸時代後期井上家十一世幻庵因碩の弟子、井上家二段)が1819(文政2)年に発刊した古棋に掲載され、「現存するもっとも古い棋譜(ゲームレコード)」と云われている。本物かどうかは不明。ただ自筆の教本にも碁の記事がみえるところから日蓮が囲碁を打ったことは間違いない。 |
| 【如仏の判決】 |
1253(建長5)年12.29日、古今著聞集の中に「両コウにかせう一つ」の話しが記されている。それによると、僧侶同士の法探坊と刑部坊の打った碁で「両コウ仮生(かせい)一つ」と云われる形の両コウ問題が起き、1眼半の石団の生死につき、法探坊が「囲碁の二眼生きルールは全局の絡みによって時に変じるものなり。実際に取りようがないではないか」(全局的死活論)として生きを、刑部坊は「囲碁の二眼生きルールに照らして単独で生きられる石団ではない」(局部的死活論)として死を主張し争いになった。
当時、上手(じょうず)と云われていた備中の法眼俊快のところに持ち込まれ、俊快は「両劫にかせう一つとは是なり。目一つといえども、両コウのあらむには死石にあらず」と判じて、全局的死活論に軍配を上げ、法探坊の主張を認めた。次に如仏の意見を聞いたところ、「目一つなりと雖も両コウのあらむには死石には非ず」と同じ判定が下った。この件の審議が江戸期の文政4年に復活する。
| 問題事例 |
|
| 図における左上の両コウゼキがある中で、同じ盤面上の右上のように一眼とコウを持つ白石がある場合の、右上の白石の生死に関して裁定に二つある。一つは、部分死活論(両コウに関わらず、右上隅の白石を死とする)と、全局死活論(
右上のコウを黒から取られても、両コウのところに無限のコウ材があるため、常にコウを取り返せるので生とする)という考えの、どちらが正しいかが問題となる。
|
| それを当時の囲碁の上手と言われた備中法眼俊快に尋ねたところ、「両劫にかせう一つとは是なり」。さらに如仏に尋ねたところ、「目一つといえども、両コウのあらむには死石にあらず」と裁定した。これを「如仏(にょぶつ)の判決」と云う。この時の「両劫に仮生一つ」が後々の判例となった。但し、この問題が燻りながら詮議され続けることになった。 |
|
| 1253(建長5)年、。 |
古今著聞集(1254年成立説話集)。巻十二、博奕第十八[法深房と刑部房囲碁の勝負に付き争論の事](本文省略、以下概要)。
| 「建長年( 年)師走日に僧侶人が碁を打って両劫に仮生一つという局面ができて生か死かを争う。当時の僧で囲碁の上手、如仏、俊快、珍覚の人に石の生死を問いに使者を走らせた」。 |
|
1274年、文永の役。
| 【楠木正成に纏わる囲碁物語】 |
「太平記」(たいへいき)の楠木正成に纏わる囲碁物語は次の通り。
1332年、96代後醍醐帝の元弘2年、北条高時を征討すべく楠木正成が天下の兵を千早城に集めた時、「大将の下知に随って、軍勢皆な戦を止めければ慰む方なかりけん。或いは碁、双六(すごろく)打ちて日を過ごして」( 「11月、楠正成千早篭城中、士卒に碁双六を打たせて時を過ごさしむ」)と、囲碁、双六(すごろく)で退屈を慰めたと記している。 |
1333年、鎌倉幕府滅ぶ。1334(建武元)年、建武の中興。
|
| 南北朝時代を舞台とした軍記物語「太平記」は正確な史実とは言えないものの碁について記されており、一般の兵卒にも碁が打たれていたことがわかる。 |
1335年、「楠正行、11歳にて囲碁に秀で、耽るなかれと侍臣を戒む」。(「らんか堂棋話」)
| 【室町時代】 |
1338年、足利幕府開く。
囲碁が庶民に本格的に浸透しはじめるのは室町期以降のようである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| これを「宋銭の流入で貨幣経済の概念が産まれてから。要するに賭博として広まった」とする見方があるが如何なものだろうか。ごく普通に囲碁の魅力、社会的有用が認められ愛好の裾野を広げていったとみなせば良いのではなかろうか。 |
|
| 1347年、中国宋代の晏天章、厳徳甫により「玄々碁経」が大成され、元の至正7年(虞集)によって再編された。論説、定石、布石、詰碁を含む古代の囲碁全書の地位にある。 |
| 【「玄玄碁経」が刊行される】 |
| 中国元代の1349(至正9)年、現存する棋書のうち二番目に古いといわれている「玄玄碁経」が刊行されている。囲碁の哲学が語られる序文と、定石や詰碁などから成っている。「玄玄碁経」は日本でも改編されながらたびたび翻訳出版された。1753(宝暦3)年の「玄玄棊経俚諺抄」巻。これを元にし、囲碁棋士の雁金準一、関源吉(1856-1925)の意見に基づいて図が改められた1913(大正2)年の「玄々棊経」などがある。
|
| 【帝王編年記()】 |
| 14世紀くらいに成立したらしい年代記「帝王編年記」()には弘法大師こと空海(774~835)の「碁と琴は禁止するものでない」という言葉が記録されているという。 |
1350(観応元)年、吉田兼好が、囲碁双六について説諭す。(「徒然草」)
| 【希代神変の者としての小松法師】 |
1377(永和)年、洞院公定公記(洞院公定の日記)。
| 「二月五日、癸丑、天晴る。今日園中将基明朝臣来り、同道し北辺に遊行す。土筆・水芹を取り、聊か之を賞翫す。彼羽林多々須辺に於て張行し一興す。帰宅の次即ち彼の朝臣を招引し、また小一盞を勧め了んぬ。散所小松法師を召し、碁を打たしむ。希代神変の者也」。 |
日記の記者・洞院公定は北朝の公家で尊卑分脈の編者。小松法師を希代神変者とは囲碁の腕前をいうのであろう。小松法師は外に記録が見当たらず履歴などは不詳。 |
| 【碁石の祖/大坂商人・笹川祐右衛門】 |
| 1400年頃、足利中期のこの頃、大坂の商人・笹川祐右衛門が貝から白石を、那智の石から黒石を作製し、今日に伝わる碁石の祖を作った。 |
1418年、101代称光帝の応永25年、回碁(まわしご)あらわる。「5月11日、囲碁回し打ちあり。予、椎野長資朝臣と之を打つ」(「看聞御記」)。
| 【幕府の碁会に呼ばれた上手たち宗勝(式部)・昌阿(性阿)・大円】 |
1431(永享3)年、満済准后日記(足利将軍家護持僧・満済准后の日記)。
| 「六月十二日、晴る。室町殿参り、御対面す。…晩頭に及び寺に入る。関東管領より上杉安房守方への状、上覧に備ふべき由管領申入るの間、今日御目に懸け了んぬ。この状を門跡に預け置くべき由仰せらる間、その儀也。宝池院へ預申す也。雨止みて御祈結願し了んぬ。東寺同前。新造御厩七間に於て、囲碁これあり。洛中の上手を少々召さる。大円北野周防法眼・宗勝(式部)・昌阿・一色・吉原等以上七人と云々。懸物に盆香合、御劔一腰を打勝に為すべきと云々。今日は勝負決せずと云々」。 |
満済は醍醐寺の僧で、代将軍・義満とその子の代・義持、代・義教の信を得て黒衣の将軍と評された人物。記事は代・義教の治政、洛中の上手を集めて開かれた幕府の碁会の様子。参集した京の上手七人のうちの宗勝(式部)と昌阿は看聞御記の囲碁記録にも名がみえる。また、大円は、後に掲載する連歌師・心敬のひとりごとのなかに囲碁の上手として同名が載る。 |
| 【「看聞(かんもん)日記」の賭け碁記述】 |
伏見宮貞成親王(1372-1456)によって書かれた「看聞(かんもん)日記」1431(永享3).2.17日条、囲碁の対局に金品が賭けられたという記述が見られる。
| 「其の後囲碁を打つ。余、中納言、持経、廻し打つ。持経勝ち、予、懸物(茶垸瓶(ちゃわんびん))を出し、これを取る」。 |
中世の記録類を見ると、公家や武士たちが集まって優劣を競ったり勝負事を行う場面では「懸(賭)物」が頻繁に登場している。囲碁の対局で賭けが行われたこともそれらのうちの一つといえよう。 |
1432年、102代後花園帝の永享4年、「5月10日、囲碁廻し打ち。予、前宰相持経等と打つ。己に晩に及ぶの間、勝負着かず退出せんと欲す。しかして今一番勝負、持経、負くれば今夜祇候、一献沙汰申すべく、予負くれば重宝下被べき由申す。その興極まりなし。すなわち祇候すべき由申し、しかして持経以外沈酔の間、先に退出すべき由仰罷り出る」。(看聞(かんもん)日記)
| 【将軍義教と関白持基の対局】 |
1435(永享7)年、「看聞御記」(伏見宮貞成親王の日記)が、将軍義教邸にて、将軍対関白等の碁界開催。
| 「八月廿二日。暁雨降る。天明以後に晴る。日出以前門を出て乗車(一族揃って上洛のこと、中略)予は室町殿直に参ず。…三献了りて盤上の御遊有るべき之由にて、主人(将軍義教)張行す。則ち囲碁打を二人召し出さる。式部[三宝院侍法師]・性阿[遁世物]が参る。懸物に段子一反、珪璋盆一枚、練貫二重を出さる。式部は上手と云々。性阿先を以て打つ。又主人と関白少将と碁を遊さる。三番を関白が負けられ了んぬ。三条と日野と囲碁を一番打つ。日野が負け了んぬ。按察と源宰相と双六を五番打つ。源宰相勝つ。予は何をか御沙汰の由を源宰相に尋ねらる。囲碁を遊ばるの由を申す。三条と参るべきの由仰せられ。則ち打つ」。 |
| 「初番は三条勝ち。次いで予が勝つ。式部・性阿三番を打つの間、数剋三つ時許りなり。見物退屈す。性阿が三番ながら負け了んぬ。懸物を式部拝領し退出す。眉目なり。囲碁之間一献退転なし。役送無人之由仰せらる。明豊俄に召されて参ず。但し遅参す。武家近習輩役送に召さるべき之条、如何之由を申さる。関白申され談ず。内々儀苦しからざる歟之由申さる。猶日野三条御談合同前。猶雖有猶予無人之間三人召し出さる。一色五郎・山名小次郎・畠山七郎、[各若俗也]公卿之役送を懃仕す。[但し関白左大将は懃仕せず]数献之間、予両度御酌に立つ。関白例之当座之会数ヶ度也。太逸と、式部、囲碁を三番了んぬ。[于時酉の下、]その後両三献畢りて主人座を起つ。予も同じく座を起ちて休所に帰す」。 |
| 「九日、雨降る。陽明局二行有盃酌。その後、予、三位、長資朝臣囲碁打つ」。 |
| 「十一日、雨降る。囲碁有廻し打ち。予、椎野、長資朝臣之を打つ」。 |
日記の記者・伏見宮貞成親王は持明院の嫡流で崇高天皇の孫に当たり、後花園天皇の実父。看聞御記は1416(応永23)年から晩年の1448(文治5)年の、足利将軍4代義持から8代義政までの年代を書き綴っており、碁好きの親王だったことから連日の日記に囲碁の記録がみえる。記事の永享年には、将軍足利義教の援助によって洛中に伏見御所が建築された。朝廷・公家と幕府とが融和の関係にあった一時期であった。親王が上洛し、方違えで足利義教の第に滞在し歓待を受けた。関白以下の公家も参会し、上手を招いた囲碁の興行でもてなされた。親王の囲碁好きに対する将軍のもてなしということであろう。主人と関白少将と碁を遊さるとあり、将軍義教と関白持基が対局した様子。記者の親王は三条と二番打分けている。 |
1437(永享9)年、「8月5日、行豊、持経朝臣等重仲候、囲碁廻し打ち。予、懸け物両種出る。皿十、檀紙十帖。碁勝負つかざるの間、目勝打ち。持経朝臣勝之を取り、聊か盃酌あり」。(看聞(かんもん)日記)
| 【日親上人が八諌勢の珍ろう(詰め碁)を作成】 |
| 1440年頃、日親上人が八諌勢の珍ろう(詰め碁)を作成している。 |
1444(文安元)年、「6月10日、伝え聞く。細川九郎(惣領なり13歳)去る月26日、囲碁を覧る。(香西子、荷田子共に15歳)香西子碁手、九郎助言。*ち荷田子怨み言を出す。云々」。(「建内記」)
| 【囲碁上手としての一宮大炊】 |
1451(宝徳3)年、師郷記(大外記中原師郷の日記)。
| 「五月十九日、丁巳、今日前右府(三条公冬)に参る[出雲路の第、]。内府(三条実量)に坐を令し給ふ。囲棊の上手一宮大炊これに参り[初参也、]、囲棊の会あり。希代の上手也。掃部頭(中原師富)も同じく之に参る」。 |
|
| 【囲碁上手としての一宮大炊】 |
1452(享徳元)年、師郷記。
| 「四月十日、癸酉、今日、予前右府に参る。内府・三位中将殿をして座をせしめ給ふ。碁の上手一宮大炊参り、掃部頭も参る」。 |
|
1456(康正2)年、後崇光院没。室町中期の囲碁記事が多い「看聞御記」を遺す。
| 【囲碁の名手としての意雲老人】 |
爛柯堂棋話が次のように記している。
| 「意雲老人は後土御門帝の世、囲碁の名手なり。庵を泉南に結びて居す。みずから可竹と号す」。 |
後土御門(ごつちみかど)天皇は1442(嘉吉2)年7.3日(陰暦5.25日)-1500(明応9)年10.21日(陰暦9.28)。第103代天皇で在位は1464(寛正5)年8.21日(陰暦7.19日)-1500(明応9)年10.21日(陰暦9.28)。諱は成仁(ふさひと)。 |
1467(応仁元)年、「応仁の乱」が始まる。これ以降、戦乱の世に突入する。その戦国時代にあっても武将たちは碁盤と碁石を手から離さなかった。
| 【囲碁上手としての大円と三浦民部】 |
1468()年、ひとりごと(連歌師・心敬の歌論随想書)。
| 「一三[諸道の名匠たち] およそ、天下に、近き世の無双の人々、愚僧見及び侍りしは、平家物語語りしには、千都検校といへる者、奇特無双の上手といへり。…碁をうち侍りし近き世の無上の上手には、大山の衆徒大円といへる者なり。同じ比、東に三浦民部といへる上手、たがひに勝負なきばかりなり。この二人の人の手合ひ、昔より今に生まれぬばかりの者なり。かれら失せて後も上手とて侍れども、二人に及ぶべきにあらず」。 |
諸道の名匠と題する中に、大円と三浦民部という囲碁の上手人の名をあげている。大円は先の満済准后日記に上手として同名がある。三浦民部の方はほかの書に名をみない。心敬は、晩年戦乱を避けて相模国大山山麓石蔵の古寺に入り、そこで没した。大山の衆徒大円とあるところから、大円はこの相模国大山の僧だろうとする連歌研究家の説もある。しかし、一方の対の人に東に三浦民部といへる上手とあるところから、西の伯耆の国の大山(だいせん)とするのが自然だろう。なお、この心敬には歌論書「さゝめごと」にも諸芸、囲碁に関する論考があり、また連句付合にも幾つかの囲碁句がみえる。 |
1473年、103代後土御門帝文明5年、「7月7日、今日種のことある裡、囲碁に就いて一、*曲、人々故障により之無*改めて囲碁畢ぬ。云々」。(「親長卿記」)
| 【仁和寺の大僧正・真乗院覚遍/左大臣・西園寺実遠の対局】 |
1485(文明17)年、「お湯殿の上の日記(禁裏女房の日記)」。
| 「二月廿九日、さいをんし(西園寺実遠)、しんせう院(真乗院覚遍)めして、ごうたせられて御らんぜらるゝ、そろそろにて御まいり」。 |
|
| 【宮中碁会で、仁和寺の大僧正・真乗院覚遍/左大臣・西園寺実遠の対局】 |
1485(文明17年)年、実隆公記(左大臣三条西実隆の日記)。
| 「二月廿九日、辛巳、陰り、雨時々降る。朝の間梳髪、午後参内す。左府(西園寺実遠)・覚遍僧正(真乗院)等を召され、黒戸に於て囲碁有り。夜に及び尤其の興有り。勝負の躰、絶へて神変の者也。筆端に述べ難し」。実隆公記。「閏三月十七日、戊辰、晴る。…召し有り、(欠字)直衣を着し参内す。左府(西園寺実遠)・真乗院僧正等を召され、囲棊これ有り。両竹園御参り、聊か一献の事有り」。 |
いずれも宮中御前で催された碁会の様子。仁和寺の大僧正であった真乗院覚遍が招かれていて、実隆公記では勝負の躰、絶へて神変の者也、筆端に述べ難しとある。相手をつとめている西園寺実遠は当年52歳で左大臣、こちらも相当の上手だったのであろう。なお、この時の天皇は後土御門で、お湯殿の上の日記には天皇自身が碁を囲んだ記録も多い。 |
1487年、103代後土御門帝文明19年、「11月29日、番匠を召し、碁盤を作り令む」。(「親長卿記」)
1488年、日親上人が、八諫勢の珍ろうを作る(「坐穏談叢」)。
| 【同朋衆重阿弥とその相手如西、西園寺公藤、増位】 |
1489(延徳元)年、宣胤卿記(参議中御門宣胤の日記)。
| 「三月一日、己未、天晴る。安禅寺殿に参り、御盃を賜はる。次いで都護許に向ひ、相伴して飛鳥井大納言入道亭に向ふ。毎年の庭花の賞翫を、今日為すべきの由、姉相公昨日の音信之故也。一桶一種を所持し向ふ也。勧修寺亞相・按察・飛鳥井中納言入道[号二楽軒、]・冷泉中納言・同新中納言・民部卿・姉小路園等宰相・通世・基春・雅俊等朝臣・壽官等座に在り。その外武家輩一両人・宗祇、[連歌宗匠]・重阿[碁上手、]など也。先日、各々に短冊に花一首を詠ましめられ、今日披講す。読師は予」。 |
実隆公記(左大臣三条西実隆の日記)。
| 「六月四日、辛卯、天霽る。今日当番也、午の時に参内す。小御所馬道に於て重阿、[禅衣を著す、本来時衆也、]・伊予法橋泰本[青蓮院坊官、]など棊局を囲む。簾中に於て叡覧有り。親王御方・伏見殿・連輝軒・万松軒・予・民部卿・園宰相大貳三位・菅原(欠字)棊局は妙々玄々、筆端に勒し難し」。 |
碁の上手・重阿弥の名が日記に見える最初の記録。宣胤卿記は、飛鳥井の花見の宴の様子で、招客の中に重阿、碁上手とある。実隆公記は、宮中での碁会の様子で、重阿弥を禅衣を著し、本来時衆也と割注をしている。幕府に芸能で抱えられた同朋衆は僧体で阿弥号を称し、かつ時宗の僧侶が多かったとされる。重阿も重阿弥と記されるものも多く、この同朋衆の一人だったと想像する。なお、このお抱え芸能団体同朋衆は室町幕府がしいた制度だが、その走りは鎌倉の代執権北条泰時( 年御成敗式目を制定し執権体制を完成させた人物)の時代で、幕府の小侍所の結番ごとに芸能に秀でた者を加え、武家も一芸を持つように心掛けるべしといった役所の触れが出されている。この碁打重阿弥は当時よく知られた囲碁の上手だったようで当時の日記類ほかのものに数多く名前をみる。対局相手の碁打の名もみえる。 |
|
1491(延徳3)年、蔭涼軒日録(相国寺の寮舎蔭涼軒の公用日記)。
| 「四月廿九日、参らず。天快晴。…景甫往常喜同じく途月江来る。待つの間、皆厩中に在りて馬を看る。啜茶し打話。時に棊の者重阿弥を招き、栗田と二番之を囲む。栗田が石三ヶ置き之に勝つ。又石三ヶ置き、又之に勝つ」。 |
|
| 【碁打ち重阿】 |
兼載雑談(連歌師猪苗代兼載の談録)。
| 「物の上手にならむこと大事なり。碁打ち重阿に、ある人兄弟ながら先にてうてるなり。勝負なし。又、人、重阿に兄弟碁の事を問ふに、兄まされりと答ふ。人皆云う、いつれも先にてうつに、兄のまさるといふは如何。といひしに、重阿云う。弟は打手さだまりて、はや我流と見えたり。其流と見えば、はやすぐるゝ事あるまじき。といふなり。面白き詞なり」。 |
兼載雑談は1510年に没した連歌師・猪苗代兼載の談録で、弟子の編んだもの。打手さだまりて、我流は進歩が望めない、と重阿がいった、というのであろう。 |
|
多胡辰敬家訓(戦国武将・多胡辰敬の家訓書)。
| 「一、万の事に付てれうけん(料簡)なくては叶まじき也。…くはう(果報)能芸きよう(器用)なりとも此ごとし。碁といふ物は目の前にてかちまけ(勝負)あればひいきへんば(贔屓偏頗)も入ず。しかれば天下一の上手といふは近代極楽寺の重阿弥といふ碁打なり。されば世上に此人よりまして打人なし。上もなきとやをもはれけん。いづくとも知らぬ客僧来て碁を打て帰りしなり。それより重阿弥心うかうかとなりしといへり。小国といへども日本ひろし。一里二里の間、一郡二郡の間に我程の者なしと思事、まことにあかりも知ぬをかしき事也。左様の事をや井の内の蛭と申べき。日月の御めぐりあるよりもたかき天あり。大海の底より下に世界有り。何ともわかち申されざる世の中也。(狂歌略)」。 |
多胡辰敬家訓は尼子家に仕えた戦国武将・多胡辰敬の家訓書。ここでは重阿弥を極楽寺の僧としている。この極楽寺は広島廿日市のそれかと思われるが、重阿弥晩年の居所だったのだろうか。 |
| 【重阿弥と同時代の意雲】 |
半陶文集(彦龍周興の詩文集)。
| 「[皓隠斎説]意雲老人、泉南の庵に居す、自ら可竹と号す、又皓隠を以て寝に扁す、従容余に謂て曰く、昔巴園の人大橘を収む、之を剖るに二叟有り、対碁曰、橘中之楽と、(賛など、後略)」。 |
半陶文集は1491年に34歳で没した相国寺僧・彦龍周興の詩文集。文中にみえる意雲も、重阿弥と同時代の打ち手と思われるが、当時の記録の中には他に名をみない。重阿弥が同朋衆として京師の間に有名だったのに対し、泉南の隠者だったためであろう。 |
|
1493(明応2)年、後法興院記(前の関白太政大臣近衛政家の日記)。
| 「閏四月十八日、壬午、晴る。雅俊朝臣・碁上手重阿弥、并びに如西など召し具す。来りて前に於て碁を打つ。重阿弥と如西が三盤之を打つ[重の二三也]。又重阿と雅俊朝臣が一盤之を打つ[重の二四也]。次いで盃酌の事有り、晩に及び各帰る」。 |
割注の重の二三也重の二四也はいわゆる手合割であろう。 |
1493(明応2)年、「蔭涼軒目録」。
| 「人あり。予に告げて曰く、院内の衆、近年碁将棋を以て業と為す云々」。 |
|
1495(明応4)年、後法興院記。
| 「五月十五日、戊申、晴て風吹く。鷹司前関白父子来らる。楊弓・鞠の興有り。勧修寺黄門・雅俊朝臣など来る。重阿・如西など来りて、碁を弾ず。土岐民部大輔・妙瑞寺来りて、鞠足也」。 |
|
|
1495(明応4)年、後法興院記。
| 「八月廿一日、辛未、晴陰り、暁に雨下る。雅俊朝臣・重阿など来りて、終日碁を囲む。晩景に鞠の興有り」。 |
|
1500(明応9)年、「意雲老人輩出す。後土御門帝の世、囲碁の名手也。庵を泉南に結びて居り、自ら可北と号し、又こう隠を以てその庵に扁(しる)す(渋谷春楼の碁話中)」(坐隠談叢)。
|
1501(文亀元)年、言国卿記(公家山科言国の日記)。
| 「癸丑、天曇り、時々雨下る。一、今日時に弘願院来臨す。予しやうばん畢んぬ。其の時分に彜首座西園寺(公藤)より使に来られる間、中酒を分ち畢んぬ。西園寺へ、ぢう阿ごをうちに来るべき由の間、予も見物に来るべき由申さる間、則ち用意す。首座を同道し行き畢んぬ。一、西園寺内府とぢう阿と碁をうたれ畢んぬ。近比の見事也。五番うたれ畢んぬ。二つにて西園寺うたるゝ也。其の後一こん之れ在り。しやうばんの衆、予・洞院御僧・不動院・ぢう阿・彜首さ・師富朝臣(大外記)父子也。さうめん其の(他)種々にて酒これ在り。一こんの後、洞院御僧とぢう(重阿)又一番うたれ畢んぬ。手あひ内府と同じ。首勝たれ了んぬ。その後予・各、帰り了んぬ。…」。 |
西園寺邸の碁会。この年の当主は公藤で歳で内大臣、先に上手として名をあげた西園寺実遠の子。同朋の上手に二つとは相当な打ち手のようで、父と並んで公家の上手だったようである。 |
|
1502(文亀2)年、元長卿記(公家甘露寺元長、歳の日記)。重阿弥が十歳の弟子の小法師を連れたとある。子どもの碁打であろう。
| 「二月十八日、晴る。聯輝軒(就山永崇)に参る。齋あり。江南院・親就朝臣(和気)同道し、象戯有り。また碁の上手重阿弥並びに弟子の小法師[十歳]参る。暁陰に退出し蓬屋に帰る」。 |
|
|
1502(文亀2)年、「宣胤卿記」。記者は中御門宣胤で、先の年の日記にも重阿弥の記事を記している。
| 「囲碁名手、重阿弥あり」 |
| 「四月三日、又住彼寺(誓願寺)中、重阿弥碁を打つ。天下第一の上手也。[相手は増位、細川政元朝臣被官、]見物の輩、奇異の思ひ成り。二条殿より笋を賜る(宰相方前之を給う)」。 |
重阿弥の相手を増位、細川政元の被官とする。当時の有力大名も幕府の同朋衆にならって芸能者を抱えていたようである。 |
1504~(永正年間)、鷲尾隆康「二水記」が、室町末期の碁界を記す。
1506(永正3)年、「正月23日、今夜月待也。隣松軒と碁を戦わしむ。暁鐘の後、閨(ねや)に入る」。(「菅見記」)
|
1506(永正3)年、後法成寺関白日記(左大臣近衛尚通の日記)。
| 「七月廿五日癸卯、晴る。女中(尚通室維子)清水へ参詣す。晩に及び左衛門督[為広卿](冷泉)・中山中納言[宣親卿]・小原判官・重阿弥の師弟子など来りて、碁をうつ。一盞を勧む」。 |
|
|
| 6代足利将軍義教の時、碁の名手であったのは日報上人と伝えられている。 |
| 【「言継卿記」、】 |
| 1506(永正3)年、戦国時代の公家・山科言継(1507-1579)の「言継卿記」日記が、散逸部分もあるが、1527(大永7)年から1576(天正4)年の期間にわたって記録している。天正4年7月2日の日記に「碁打之仙也」という記述がある。この頃、碁打ちとして認識される人物が登場し、衆目の一致する囲碁の上手が現れ始めたことがうかがえる。 |
| 「言継卿記」のほかにも、同時代やその後に書かれた「舜旧記」(しゅんきゅうき)、「兼見卿記」などに、「碁打」と認識されている人物の名前が散見されるようになる。 |
| 【大碁盤奉納故事】 |
2023.11.26日、丹波新聞「日本一の大碁盤 囲碁で領地争い解決の故事 連載”まちの世間遺産”/兵庫・丹波市柏原町大新屋」参照。
1992(平成4)年、石見神社を管理する新山管理組合が、兵庫・丹波市柏原町大新屋の石見神社の祠の前に、大きさ縦2メートル5センチ、横1メートル91センチ、重さ約4トンという通常の碁盤の23倍の大碁盤を奉納した。裏話は次の通リ。
1509(永正6)年、「新山」(石戸山)では、米百俵を銭百貫で、同村の挙田、大新屋、鴨野、北山、田路に永代売渡されていた。隣村とたびたび山境を巡って対立していた。地元の新井村誌に、この問題の解決を巡る「故事伝説」が記されており、昔話本「柏原の民話とうた」(グループふるさと発行)で紹介されている。谷垣石見守は、隣村との領地争いを、隣村の領主との囲碁勝負で解決を試み、「未曽有の対局に深遠な智謀を発揮し活殺自在、遂に石見守の勝利」した。
囲碁勝負に同行した囲碁名人の若者が、傘に小さな穴を開け、穴から射す光を碁盤に当てて、次の手を石見守に教えた。領民に平穏な生活をもたらした云々。 |
1517(永正14)年、「8月29日、御揚弓あり。夜に入り、御三間に於いて勝負の御碁あり。云々」。(「二水記」)
1523(大永3)年、「越年は薪酬恩庵傍、捨密下炉辺、人集まりて、田楽の塩噌のついで、俳諧たびたびに、(中略)碁盤の上にはるは来にけり。うぐいすの巣ごもりといふつくり物、朝が隅々までは立ちいらで、是も愚句つけまさりはべらんかし」。(「宗長日記」)
1526(大永6)年、「7月29日、午刻参内。竹内卿御祇候御碁あり。懸物予(藤原隆康)拝領尤も祝着也」。(「二水記」)
| 【「適情録」20巻】 |
| 1530年頃、中国の明の林応竜が囲碁の本を作成した(「適情録」20巻)。その中に、虚中(きょちゅう)という日本の僧侶がつくった碁の図が384余り入っている。虚中という人物は誰なのかわかっていないが、日本の碁が中国と同じくらいのレベルまでに達していたと推定される。室町時代に入ると囲碁が武家や有力者にも広がり、「碁打ち」、「上手」と呼ばれる半専業の者を抱えて競わせるようになった。その中には同朋衆や出自不明の者も少なくなかった。(幸田露伴記「碁と将棋」) |
| 【秀吉履歴/秀吉の誕生】 |
ここで、格別な関心をもって後に天下人の豊臣秀吉となる人物の生涯履歴を確認する。なんとなれば、その人こそ、実は知られていないが、否、意図的故意に隠されているように見えるが、若くして囲碁の才が認められ、その知恵者ぶりが認められて織田信長の臣下に採用され、採用されるや否や囲碁的才知能力を発揮し始め、これにより織田信長に引き立てられ、順次出世街道を驀進し遂には一兵卒から国持ち大名になるという戦国一の出世頭となった。本能寺の変で主君の織田信長が討たれるや、討った側の明智光秀を成敗し、その勲功を元手に遂に天下人となった稀代の出世頭である。我々は、秀吉の他人を魅了する「人たらし」の才と、囲碁的才智と思われる柔軟な発想力から学ばねばならないと思う。戦後史学は、真に有益なこの辺りの考究をなおざりにし、さして有益でもない事象に誘う癖があり、これも敗戦後遺症の為せる技かと今にして思う。そういう意味で、豊臣秀吉の生涯履歴を検証したい。
ちなみに、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は共に初代本因坊算砂に対し5子の手合いとされているが、正しくは秀吉のみがプロ棋士的な5子手合いで、信長は着手を評する審美眼があるものの棋力不明、家康は晩年に覚えて以降滅法愛好した経緯からして忖度手合いだったと思われる。
2019(栄和元).6.10日 れんだいこ拝 |
| 1536(天文5)年2.6日、「甫庵太閤記」によれば、後の豊臣秀吉が尾張国愛知郡(愛知県名古屋市)中村郷の下級武士にして足軽をしていた(農民とも)/木下弥右衛門の子として生まれた。母は美濃の鍛冶関兼貞の娘なか。 いつどこで生まれたのか、父や母は誰だったのかについて諸説あり不詳。幼名は「日吉丸」。母なかは、日輪が懐中に入った夢を見て妊娠し、元旦に生まれたので日吉丸と名づけたと云う。実は、これは太閤記の作者小瀬甫庵のフィクションといわれている。 |
| 木下弥右衛門となかの子供として姉の"とも"、秀吉。"なか"が再婚した筑阿弥との間の子供が秀長、朝日姫と云われている。 |
| 【秀吉履歴/行商時代】 |
| 1542(天文11)年、日吉丸7歳の時、父の木下弥右衛門が病死。 |
| 1543(天文12)年、日吉丸8歳のとき、光明寺に預けられる。 |
| 母のなかが織田信秀の同朋衆だった竹阿弥と再婚する。 |
| 日吉丸は義父(竹阿弥)との折り合いが悪く家を出る。父の遺産永楽銭1貫文(銭1000枚)を受け取り、それを元手に針売りの行商などしながら各地を流れ歩いていたと云われている。太閤素生記では秀吉の幼名を「猿」とし、また秀吉の父が亡くなったとき、秀吉に金を遺した一節に「父死去ノ節猿ニ永楽一貫遺物トシテ置ク」とある。 |
宣教師のルイス・フロイス「日本史」次のように記述している。かなり悪意的な書き方であることが分かる。
| 「(秀吉は)貧しい百姓の倅として生まれた。筵(むしろ)で身を覆うしかなかった。若い頃には山で薪を刈り、それを売って生計を立てていた」。 |
| 「身長が低く、また醜悪な容貌の持ち主で、片手には6本の指があった。目が飛び出ており、シナ人のようにヒゲが少なかった」。 |
日本教会史には、秀吉は「木こり」出身と書かれている。 |
| 【秀吉履歴/松下加兵衛之綱(ゆきつな)に仕官】 |
| 1551年、日吉丸14歳のとき、やがて遠江(静岡県西部)に流れ着き、今川義元の家臣/飯尾氏の配下である陪臣の頭陀寺城(ずだじじょう、静岡県浜松市)城主/松下加兵衛之綱(ゆきつな)に仕官。藤吉郎は、能力のある藤吉郎は松下之綱に目をかけられた。松下之綱は「猿ヲ見付、異形成ル者也、猿カト思ヘバ人、人カト思ヘバ猿ナリ」と語っている。 |
| この頃「木下藤吉郎」と改名する。これは父親から受け継いだ姓とも、妻・ねねの姓とも云われている。 |
| 1553(天正22)年、藤吉郎は、同僚との折り合いが悪くいじめを受けるなどしたため、ほどなくして辞去し、全国各地放浪の生活に入る。藤吉郎は後に、松下之綱を大名の身分にまで引き上げている。その後、松下家は江戸時代に5万石の大名にまで成長している。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここまでの履歴のどこかの段階で、秀吉は読み書き算盤、そのほか囲碁も習ったと考えざるを得ない。 |
1543年、種子島にポルトガル船漂着。この頃、鉄砲伝来。
| 【了本】 |
1544()年頃、東国紀行(連歌師宗牧の東海道下りの紀行文)。
| 「(旅中の表敬訪問の条) 観音寺登城。去夏御参詣。毎日御気も尽されし名残。その年の御不例。并発蘭軒召し下されて、祈療の残る所なくて、この日いささか御快気とて、澄玄さへ下さるべき。折よく罷り下りたるよし。進藤山城守御内儀聞かせられたり。宿老面々にさへ御対面なき頃なれば、御礼も憚り多くて、さたにも及ばざるに過分の事也。誠に御相伴とても、左右大夫殿、中務大輔殿、永田備中守、碁打了本。猿楽一両輩。次の間に伺候したる計なり。座敷は二階尤も眺望をいはゞ老曾森。麓の松原に続きて、板倉の山田。蒲生野の玉のをやま。さながら磨ける砌なるべし」。 |
観音寺城に六角定頼を表敬した記事である。参会者の芸人の中に碁打了本の名がみえる。相当の打ち手だったと思われる。 |
| 【虚中】 |
| 野上彰の小文に虚中のことが記されている。それによると、虚中は足利時代に明に渡った僧侶で、渡明の折に自著「適情録」10巻を携えている。それは、「玄々碁経」の打ち方に新手法を考案したもので、中国囲碁史に重要な地位を占めている。 |
| 【秀吉履歴/織田信長に仕官】 |
1554年、藤吉郎17歳のとき、地元の尾張の領主/織田信長に仕官し採用され、小者(こもの)として仕えた。
この経緯が不詳である。一説に、「知人で織田信長の小人頭をしていた一若という者の紹介で、織田信長に仕えた」と記されている。異説として、「織田信長と豊臣秀吉の関係はどうやって出来たの?」に「織田信長が若い頃出入りしていた郡(こおり)村の生駒家の記録『武功夜話』に豊臣秀吉との関係が出ています」として次のように記述されている。
| 「この人、弘治乙卯年の夏越方の出会いと承るなり。そもそもの因縁は、尾州郡村に生駒屋敷雲球宅に候。蜂須賀小六殿、彼の者雲球屋敷にて見知り、色々不審の儀もこれあるにより、乱波の類にては候わずや。その風躰は無頼の輩の如く、小兵なれども武芸あり、なりに似合わず兵法の嗜みも深く初めは得体知り難し。さる程に仕切りに懇願して蜂須賀の桛好み候なり。やむなく小六殿、宮後屋敷へ伴い出入り御用に足し候ところ、才智を働き、機転は人に勝れ、胆力殊に英で、遂には小六殿閉口すれども、彼の者桛多太凡人を超え、日を追って調法を感じなされ候由に候なり。かの者、信長公に奉公の濫觴は、郡村生駒雲球屋敷の久庵様御口添えあるによるところ多太あり。小六殿の使い走りに郡村雲球屋敷へ往来。久庵様の御前少しも憚らず長談義もしばしば、生来の利口者なれば、久庵様の御機嫌取る事たくみなり。当時久庵様は、信長公御手付きとなる事よくよく承知仕りての所行、あきれ果てたる御仁に候。よくよく一同、藤吉郎の厚顔恐れ入りたる仕業に候。
(引用:吉田蒼生雄全訳「武功夜話 <一> 巻三 木下藤吉郎因縁の事の条」1995年 新人物往来社)
大意は、”豊臣秀吉とのそもそものきっかけは、弘治元年(1555年)の夏頃(秀吉18歳)の尾張国郡(こおり)村にある生駒家長(いこま いえなが)の屋敷(雲球屋敷)での出会いだったと聞いている。その時、蜂須賀小六は、秀吉が雲球屋敷に出入りしているのをみつけて、見たところ怪しい奴ではあるが、野盗の仲間ではなさそうだが、ならず者のような風体である。小柄だが武芸が達者で、見かけによらず兵法の知識もあり、どうも得体のしれない奴だと感じた。ところが、しきりに蜂須賀党の仕事が好きだとせがむので、仕方なく小六は、秀吉を屋敷に連れ帰って、小者の一人に加えた。すると、知恵があり機転は利くし、胆力もあり、遂には他の者を超える働きぶりで、小六は閉口しているが、徐々に重宝するようになって行った。秀吉の織田信長公への奉公の始まりは、郡村生駒雲球屋敷の生駒類(吉乃)の口添えによるものである。当初蜂須賀小六の使い走りで雲球屋敷に頻繁に出入りし始め、周囲を憚らずに吉乃を捕まえては、話上手で吉乃の機嫌をたくみにとり結んでいた。聞くところによると、秀吉は当時吉乃が信長公の愛人であることを承知の上で近づいていたと云い、全くあきれ果てたる人物である。その厚顔無恥には、一同恐れ入った。”位の意味です。
つまり秀吉は、身分によらず有能な人材を登用すると言う織田弾正忠家の嫡男三郎信長の噂を聞きつけ、最初から信長狙いで、先ず信長が通う郡村の生駒雲球屋敷に出入りする大物蜂須賀小六の所へ入り込み、次に雲球屋敷で信長の愛人吉乃(生駒類)に目を懸けてもらうように取入って、最後に吉乃から信長へ推薦してもらう形で、清須城での信長奉公を勝ち取った訳です。
因みに、この”生駒類”(いこま るい)は織田信長の側室(後に正室になったとの説もあります)で、”吉乃(きつのー吉法師の側室の意か)”とも呼ばれ、信長の嫡男信忠・次男信雄・長女五徳のお袋様(お腹様)です。
秀吉は自分の卑賎の階級出身者であることを自覚し、出自によらず知恵と実力で勝負をさせてくれる織田弾正忠家の跡取り織田信長に目をつけました。そして、その信長が吉乃を訪ねるために小折の生駒屋敷に通っていることを突き止め、近づくために知恵を絞って、先ず同じような境遇で野武士の親分として既に名を成していて、生駒屋敷に出入りしている蜂須賀小六に取り入ることから始めたものと思われます。織田信長がいかに出自によらず人材を登用すると言ったところで、武士階級でもない卑賎の身の秀吉がその織田信長に近づくために、どれだけ知恵を絞ったことでしょうか。とにかく、ここから、豊臣秀吉の未来が開けて行ったのです。
|
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 藤吉郎が当初より織田信長の身辺に仕えて雑用などをする「小者」として仕えたことにつき、「藤吉郎は体格が小さく、戦闘には向いていなかったので足軽になることを避けたのでしょう。あるいは、大名である信長自身の目にとまる仕事につくことで、立身出世のきっかけをつかもうとしたのかもしれません」との評があるが違うと思う。今のところ史料に出て来ないが、信長が、「囲碁に長ける知恵者」の評がある藤吉郎に興味を覚え、将来の知恵袋になるかもしれぬと召抱え、当初は主人の身のまわりの世話をする雑用係の「小者」として採用された節がある。そいう「碁縁」繋がりが考えられるのではなかろうか。この線は初見かもしれないが引き続き洗いたい。秀吉論に「戦国一の出世頭。他人を魅了する「人たらし」の才と、常識にとらわれない柔軟な発想力を武器に、次第に頭角を現す。主君・織田信長から絶大な信頼を得て、一兵卒から国持ち大名に出世を果たした。信長没後、怒濤の勢いで天下人への道を駆け上がる」との評があるが、「碁智碁縁」で考えれば得心が行く。 |
| 【秀吉履歴/草履取り】 |
藤吉郎は期待に違わず、あだ名をつけるのが好きな信長から「猿」と呼ばれるようになり目をかけられた。信長の草履取りをしていた時、懐に草履を入れて温めておき、これを信長に差し出して気に入られたという有名な次のような逸話がある。
| ある寒い日、信長は小物の日吉丸に言った。「サル!出かけるぞ」。「はっ、かしこまりました。どうぞ」と、殿の履物(はきもの)を揃えて差し出した。信長は、日吉丸がきれいに並べた草履(ぞうり)に足を入れるや怪訝な顔をした。「うむむっ、なぜ草履が温かい。さてはサル、わしの草履を履くなり尻に敷くなりしていたな。この無礼者!」。「殿、そんな、めっそうもない」。「では、なぜ草履が温かい?」。日吉丸は待ってましたとばかりに言った。「はい!殿のおみ足に冷たくならぬよう、この懐(ふところ)で温めておきました」。日吉丸が自分の胸元を開くと、草履の跡がくっきりと残っていた。信長は、日吉丸の気配りに、他の者とは一味違う才覚を感じた。生まれ持っての地位やコネがない日吉丸は、この様に細かい事にまで知恵を働かせながら信長に懸命に仕えた為、信長の信頼を次第に得ていった。 |
|
| 【秀吉履歴/薪奉行、普請奉行、台所奉行】 |
秀吉の手腕が買われ、薪奉行、普請奉行(建築の責任者)、台所奉行に任じられるなど内政面で活躍し出世していった次のエピソードがある。(「偉人の先見性⑦ 豊臣秀吉の仕事ぶり 」その他参照)
| 最初に信長に認められた大きな仕事は「薪」のコストダウンだった。信長が薪奉行に、「どうも薪の金額が大きいがどうなっている?」と問いただしたところ、薪奉行は「今まで通り行っているだけです、特にこれといったことはしていません」と返答したところ、信長の逆鱗にふれ薪奉行は更迭された。後任に誰にしようか考えていたときに秀吉が手をあげ、「殿、ご覧あれ。私が適正にして見せます」と自薦したので信長は秀吉に託した。秀吉は現場へ入り、1・燃料が城へ入ってくるルートにつき無駄がないか、2・購入量が適切なのかに焦点を当てて調べた。薪のルートは実は様々なルートがあり、1本1本に利ざやがあることが分かった。購入量の適正については、薪に無駄がないかを徹底的に調べた。竈(かまど)、暖房用、風呂などの使用量を調べ上げ、工夫の余地があることが分かった。秀吉は考えた。仕入れルートでは仲介業者を省いた形で進めてみようという考えに至った。村々を歩いてけっこう枯れ木があることに気づき、村長に「あの枯れ木もらえるか?」と提案し、さらに「その分税金を安くする、それか、木の苗10本と交換するか?」どちらか選ぶ方法を提案していった。このように村々へ説きに廻った。これによって、減税で多少収入は落ちるが薪代が薪代が今までの10分の1にまで下がった。さらに苗木が増えて村々の環境整備にも役立った。この成果を聞いた信長は「さすがサルはやるわ」と喜んだ。 |
| 信長の居城であった清洲城がある年に大きな台風に見舞われた。修理奉行が100人の人夫を使って取り組むも怒鳴り散らすばかりで中々はかどらずにいた。それを見ていた秀吉が「こんな調子じゃ、いつになるか分からない」と信長に聞こえるように呟いた。信長が、「おまえなら何日でできるか」、秀吉は「3日でやって見せます」と答えた。信長は修理奉行を更迭し、秀吉に修理奉行で直すように命じた。秀吉はまず、壊れた箇所を年位置に調べて全体を10箇所の区分に分けた。これを「割普請」と云う。そして人夫にいった。「これから10組に分かれろ!誰と誰が組むかは自分達で決めろ。俺にはみんながだれが好きだ、嫌いだということは分からない。嫌いなやつと一緒にやっても面白くないだろう。気も使うしな。さ、早くきめて責任者をきめろ」。その上で、「一番先に終わった組には殿が格別な褒美を出してくれるそうだ」。そういって競わせたところ、城の修理を瞬く間に終わらせた。 |
| 秀吉は台所に関することを取り仕切る台所奉行になり、そこでも評価を高めている。 |
|
後々のことであるが、「乗数の法則」を語る歴史的な逸話として次のような話がある。ある時、戦国時代の武将豊臣秀吉の寵臣、頓智で名高い曽呂利新左衛門が知恵比べに勝ち、「何でも欲しいものを所望せよ」と秀吉から云われた。新左衛門は、「今日は米1粒、翌日には倍の2粒、その翌日には更に倍の4粒と、日ごとに前日の倍の量の米を100日間お与えくださいませば本望です」と答えた。秀吉は、「欲のないやつだ」と承知した。ところが、秀吉は、この方式で1カ月間も続ければ途方もない数字になることに気づき、急きょ前言を翻し、かぶとを脱いだと云われている。
数列には、等差数列や等比数列などがある。等差は前の数と次の数の差が一定(例えば、2、5、8、11、14....というように前の数字に3を足したもの=算術級数)の数列を云う。等比は、前の数と次の数の比(公比)が一定である(1,2,4,8,16,32....二つの比の等しいこと=幾何級数)数列を云う。「人の乗数梃子の法則」とは等比数列のことであり、凄い威力となる。
ちなみに、初代(先代)曽呂利 新左衛門とは、豊臣秀吉の御伽衆として仕えたといわれる人物で、落語家の始祖とも言われ、ユーモラスな頓知で人を笑わせる数々の逸話を残している。元々、堺で刀の鞘を作っていて、その鞘には刀がそろりと合うのでこの名がついたという(「堺鑑」)。本名は杉森彦右衛門で、坂内宗拾と名乗ったともいう。大阪府堺市堺区市之町東には新左衛門の屋敷跡の碑が建てられており、堺市内の長栄山妙法寺には墓がある。没年は1597(慶長2)年、1603(慶長8)年、1642(寛永19)年など諸説ある。架空の人物と言う説や、実在したが逸話は後世の創作という説がある。また、茶人で落語家の祖とされる安楽庵策伝と同一人物とも言われる。茶道を武野紹鴎に学び、香道や和歌にも通じていたという(「茶人系全集」)。「時慶卿記」に、曽呂利が豊臣秀次の茶会に出席した記述がみられる。他にも「雨窓閑話」、「半日閑話」ほか江戸時代の書物に記録がある。 |
| 【弘化から永禄に改元】 |
| 1558(弘化4、永禄元)年、2.28日、永禄に改元。 |
| 【戦国時代/天才的な碁打ちの続々登場】 |
日本最初の商業都市・堺に仙也や林利玄といった伝説的、天才的な碁打ちが登場する。爛柯堂棋話が次のように記している。
| 「意雲老人は後土御門帝の世、囲碁の名手なり。庵を泉南に結びて居す。みずから可竹と号す」。 |
|
| 【加納與三郎(後の本因坊算砂)誕生】 |
|
1559(永禄2)年5月、加納與三郎(後の日海、本因坊算砂)が加納与助を父(舞楽宗家)とする加納家の三男として京都(長者町)に生まれる。父の弟(叔父)の学僧にして堺・妙国寺にも関連する僧侶にして法華宗寂光寺開祖/初代住職の日淵上人(
1529-1609)が、甥の日海をまず堺(大阪)の伝説の碁師の仙也に弟子入りさせて修行させたところ抜群の才を示す。8才で日蓮宗僧侶に出家させ本行院日海を名乗り顕本法華宗寂光寺塔頭本因坊に住む。後に織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三代に仕える。「碁なりせば劫を打っても活くべくに死ぬる道には手もなかりけり」の辞世で知られる。
|
| 【「碁は武将の嗜み」時代到来】 |
| 室町期になると幕府に同朋衆がおかれ、武家自身が芸能の担い手となった。囲碁が戦のシミュレーション用の教養として好まれ「碁は武将の嗜み」として隆盛した。足利義教、細川勝元、北条早雲、武田信玄、その家臣の高坂弾正、細川幽斎、真田昌幸、浅野長政、黒田如水、伊達政宗などの戦国武将が囲碁を愛好し囲碁逸話を遺している。これを数え上げれば枚挙にいとまがない。信長、秀吉、家康の天下人の三人共が碁を愛好し、それぞれが逸話を残している。(「囲碁史研究家・増田忠彦の囲碁研究」) |
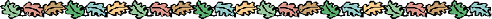



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)