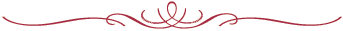
| 創業者・経営者名言 |
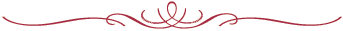
| 吉田忠雄 | 『勝負の決め手は引く手にあり』 | ||
| 早川種三 | 『何もやらないうちからクヨクヨするな』 | ||
| 豊田佐吉 | 『まずやってみよ、失敗を恐れるな。障子をあけよ、外は広いぞ』 | ||
| 松永安左衛門 | 『岩は割れる。スジを見つけよ』 | ||
| 奥村綱雄 | 『勝負は”間”と”スピード”の結合で決まる』 | ||
| 西沢潤一 | 『マツタケはとられる前に千人の股の下をくぐる』 | ||
| 野村徳七 | 『なんでも命がけでやれ』 | ||
| 出光佐三 | 『活眼を開いて、眠っておれ』 | ||
| 松下幸之助 |
| 企業の公器について 「一般に、企業の目的は利益の追求にあるとする見方がある。しかし、根本は、その事業通じて、共同生活の向上を図るところにあるのであって、その根本の使命をよりよく遂行していく上で、利益というものは大切になってくるものであり、そのあたりを取り違えてはならない。そういう意味において、事業経営というものは、本質的に私の事ではなく、公事であり、企業は社会の公器なのである。例え、個人企業であろうと、その企業のあり方については、私の立場、私の都合で物事を考えなくてはならない。常に、その事が人々の共同生活にどのような影響を及ぼすか、プラスになるかマイナスになるかという観点から、ものを考え、判断しなくてはならない」。 |
| 経営学と経営の違いについて 「経営学は教えられても、経営は教えられるものではない」 |
|
経営責任について |
| 不況について 不況といい好況といい、人間が作り出したものである。人間がそれをなくせないはずはない。不況は贅肉を取るための注射である。今より健康になるための薬であるから、いたずらに怯えてはならない。不況は物の価値を知るための、得がたい体験である。不況の時こそ、企業はのびる。かってない困難、かってない不況からは、かってない革新が生まれる。それは技術における革新、製品開発、販売、宣伝、営業における革新である。そして、かってない革新からは、かってない飛躍が生まれる。不況、難局こそ、何が正しいかを考える好機である。不況のときこそ、事を起こすべし。政府もまた、勇猛果敢に政治の大転換をはかり、徹底的に積極政策をとるべきである。 |
経団連会長・土光敏夫
「トップというのは大変な役目だ。それを知ってか知らずにか、『社長になりたい』などとぬかす奴の気が知れない。なりたくてしようがない奴を社長にするものだから、いつも、あとでゴタゴタが起きる」
堤康次郎西武鉄道創業者・衆議院議長
「ごまかし、曖昧さ、ウソというものは一度は通じても、二度三度は通じない。仮に、相手を騙す気が無くても、騙されたと思わせるような曖昧な態度だけは、断じて取ってはならない」。
ジャック・ウェルチ
「私は大組織に適応する『企業人間』ではなかったし、儀礼的な手続きなどほとんど無視した。ちゃんと仕事しない者にはがまんができず、無遠慮に文句を言った。『建設的反対』を好んで、素直な議論こそが最適の決断をもたらすと信じていた。当時はよく『うちの6歳の息子だってもっとうまく出きる』、『評論家など要らん。対案を出せ』と絞り上げ、それが出来ない者には辞めて貰った。偉そうにしている者、口先だけの者も長続きはしない。業績の悪い者をどんどん解雇し、成績のいい者には大幅に給料を上げ、ボーナスも弾んだ。蹴り飛ばす一方、抱いてなでる。それが今日まで続く私のやり方だ」、「辞めさせたい管理職には必ず事前に二、三回、個別面談し、私が何に不満かを伝え、挽回のチャンスも与えた。業務報告のたびに私の意見をメモに書いて渡した。だから最後通告の時にショックを受けて取り乱す例はただの一件もなかった」(2001.10.14日経「私の履歴書⑭」)
パウエル長官「マイ・アメリカン・ジャーニー」
「何事も思っているほど悪くない。朝になれば状況は良くなっている」
「まず怒れ、そしてその怒りを乗り越えよ」
「やればできるはずだ」
「常に冷静に、且つ親切であれ」
「ビジョンを持ち、自分に対してより多くを求めよ」
「常に楽観的であれば、力は何倍にもなる」
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)