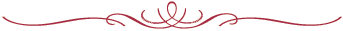| 【武田信玄(1521~1573年)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武田信玄(1521~1573年)は言わずと知れた戦国大名の1人で、「風林火山」の軍旗を使い、「甲斐の虎」として知られ、上杉謙信との五度にわたる川中島の戦いが有名である。現代でも「部下の力を引き出し、チームの力を高められる」として、戦国武将の中の「理想の上司№1」に選ばれたこともある。信玄は身分を問わず、部下の意見をよく聞き、部下が活躍すると高い評価を与え、モチベーションを高めることに常に配慮していた。功績を上げた部下にはボーナスとして金を与えることもあり、慕われるリーダーの見本としても名を残している。その人となりが「甲陽軍鑑」に書かれている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武田信玄は、領民を大切にし、大変親しまれていた。例えば「信玄堤」という堤防をつくり(今でいう公共事業)、長年苦しめられていた洪水による水害を防いでいる。人間にとって生命に等しい「水」を調達しやすくしたため、民の暮らしは飛躍的に向上した。信玄堤は当時としては画期的なことで、家康の利根川東遷事業にも大きな影響を与えた。戦国時代を生き抜いた武将たちは戦に次ぐ戦で心が休まる暇がなかったが、多くの武将たちが心と体の健康を維持するために独自の健康法をこっそり実践していた。信玄の場合は温泉だった。隠し湯だけで30ヵ所もあった。心と体をリラックスさせて、ストレスが蓄積された体を癒しながら英気を養っていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「武田信玄の名言」。
|
| 【上杉謙信(1530~1578年)】 | ||||
|
上杉謙信(1530~1578年)は越後(新潟県)の戦国大名で、「越後の龍」、「軍神」と称された。武田信玄とのライバル関係が有名で、信玄没後に衰退した武田家を攻め入ることはせず、私利私欲のための戦はしない、義に忠実な武将として知られる。謙信は越後で作られる布を「越後上布」というブランドにして専売制を実施。その布を自ら足利将軍家に売り込むなど経営者としても優れていた。 |
||||
「上杉謙信の名言」。
|
| 【織田信長(1534~1582年)】 | ||||
| 織田信長(1534~1582年)は最も有名な戦国武将の1人である。奇抜なエピソードもあるが、その一方で目標設定を上手く活用した戦術家でもあり、非常に優れたカリスマリーダーであった。有名な戦に「桶狭間の戦い」がある。日本三大奇襲の1つで、2万5000の兵を擁する今川義元をわずか2000の軍勢で強襲し討ち取った。(数字には諸説あり) | ||||
「織田信長の名言」。
|
| 【豊臣秀吉(1537~1598年) 】 | |||||
豊臣秀吉(1537~1598年) は低い身分から叩き上げで出世し、天下統一まで成し遂げた戦国武将であり、智将としての要素が人気の理由です。秀吉が信長へ行った、冬の寒い日に懐に草履を入れて温めたエピソードはあまりに有名ですが、他にも象徴的なものが数多く残っています。
例えば、増え続ける薪代のコストを下げるよう信長から指示された秀吉は、流通過程から調査し、問題のあった仕入れルートを排除。代わりに城下の村にあった枯れ木を薪として利用しました。その上で、この無料同然の薪代を「苗木代」、すなわち植林のための費用として徴収し、城下に植林を行い、自前で薪を賄えるようにしました。まさに、そのまま現代のビジネスに通じるエピソードといえます。 |
|||||
「豊臣秀吉の名言」。
|
| 【長宗我部元親(1539~1599年) 】 | |||||||
| 四国の戦国大名として、部下思いな一面だけでなく、山が多く米の収穫量が少ない四国を経済的に救ったリーダーとして知られます。元親は弱みである山の多さを逆に強みと捉え、木材を管理し、職人たちの力で商品化を進めて経済難を回避しました。地元産業の活性化に力を注ぐことで経済力をつけた政治家としてだけでなく、名経営者ともいえるでしょう。 | |||||||
| 【名言】 | |||||||
|
| 【徳川家康(1543~1616年) 】 | |||||||||
| 戦力の差がない関ヶ原の戦いにおいて、味方だけでなく敵軍をも上手く動かして戦局を有利に進め、江戸幕府を築いたのが徳川家康です。自身の失敗はもちろんのこと、味方の裏切りや秀吉の失敗、最終的には部下からも学ぶ家康の「学習能力」と「柔軟性」の高さが受け継がれ、江戸幕府は260年以上も繁栄を続けました。 | |||||||||
【名言】
|
●黒田官兵衛(1546~1604年)
秀吉の天下統一を支えた軍師です。本能寺の変で信長を裏切った明智光秀を討つ秀吉の活躍をお膳立てしたのが官兵衛であり、上司を立てて信頼・評価を高め出世しました。
【名言】
「その職にふさわしくない者はすぐに処分したりするが、よく考えてみると、その役を十分に務めてくれるだろうと見たのはその主だ。目利き違いなのだから、主の罪は臣下よりもなお重い」
「自分の上司に読ませたい」と思った人もいるかもしれません。仕事を任せたのは上司であって、部下がその仕事を完遂できなかったことは、部下の責任もありますが、上司にも責任があります。いや、むしろ上司の責任のほうが重いというのが官兵衛の意見です。自分が上司になって部下を持ったときも忘れないようにしたい名言です。
【名言】
「上司の弱点を指摘してはならない」
どんな人にも弱点はあります。しかしその弱点を部下から指摘されると、上司としては気分が良いものではありません。表面上は納得してくれても、信頼関係を築くことは難しいでしょう。
上司の弱点に気づいたときは、そこを部下として補完することが大切です。そのことで上司から信頼され、良い評価を受けられるでしょうし、責任のある立場に取り立ててもらうこともできるでしょう。
●真田信繁(真田幸村)(1567~1615年)
NHK大河ドラマ『真田丸』でもお馴染み、織田信長と並んで人気の戦国武将です。天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いの際に、亡き豊臣秀吉に恩義を感じていた信繁は、莫大な報酬で徳川家康率いる東軍から誘いを受けますが、これを断ります。義を大切にしたリーダーです。ちなみに「幸村」の名前が広く浸透していますが、正しくは「信繁」です。
【名言】
「部下ほど難しい存在はない」
褒めて育てると甘やかすことにならないか、厳しく指導すると辞めてしまわないか――人材育成というのは今も昔も難しいもの。「笛吹けども踊らず」とならないよう、部下の能力を最大化して、チームとして結果を出すにはどうすれば良いのか?上司としての力量が問われるところです。
【名言】
「いざとなれば損得を度外視できる、その性根。世の中にそれを持つ人間ほど怖い相手はない」
ビジネスは損得勘定をベースに動きます。しかし、人間関係において損得勘定のみを優先する人の周囲には同じような人ばかりが集まり、その人物と付き合っても損だとわかると潮が引くように皆去っていくものです。信繁が日本人の心を捉えて離さない理由の一つは、損得勘定よりも義を優先した彼の姿勢にあることは間違いありません。
●伊達政宗(1567~1636年)
伊達政宗は後に仙台藩の初代藩主となる戦国大名です。23歳で奥州を制圧し、乱世の時代には勇猛果敢な若き武将として活躍。その後は抜群の行動力で仙台藩を統治しました。幼少時に患った天然痘の影響で右目を失明したことから「独眼竜」という呼び方でも知られています。また、政宗の身につけるものは弦月の兜など特徴的でセンスの高いものばかりでした。このことからオシャレな男性を「伊達男」と呼ぶようになったという説が流布されていますが、真相は不明です。
【名言】
「時を移さずに行うのが勇将の本望である。早く出立せよ」
競合他社より出遅れてしまうと、機会損失の影響は後々大きく響いてきます。いざ勝負と思ったときは、時を移さず行動すること。つまり、戦略立案から決断→実行をスピーディに行い、ライバルに先んじることが勝利のカギを握ると解釈できるでしょう。
【名言】
「大事の義は、人に談合せず、一心に究めたるがよし」
重大な選択をする際、他人に相談して意見を求めたり、さまざまな情報を調べることは大切ですが、最終的な判断は自分でするべきだという言葉です。自ら決断したことは、腹をくくって進むことができますが、他人の意見に流されて失敗してしまえば、相談した相手を憎んだり、後悔が生じてしまいます。