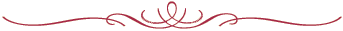
| 検索エンジンと著作権考 |
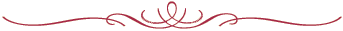
(最新見直し2005.12.3日)
| グーグルとかヤフーの検索はとても重宝であるが、この検索機能についても「誰の断りしてサイト紹介しているのか」てなクレームを付ける者が居るのだろうか。逆に、グーグルとかヤフーの検索が認められるとすれば、承諾無しのその行為が広く支持されていることを意味する。全方位四角四面の著作権推進論者はこの点どのようにお考えか、聞いてみたい。 2004.9.2日、日本経済新聞は、「グーグル、日本語ニュース検索を開始」なる見出しで、次のような記事を掲載している。
れんだいこは、この流れを支持するが、日本新聞協会編集委員会はどのようにその著作権理論を整合化しているのだろう。「社会的有益論」で合意するのなら、いっそのこと元に戻ってかの偏狭な「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」の見直しまで踏み込めばよいのに。 2004.9.2日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)