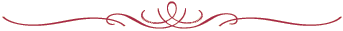
| 「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考 |
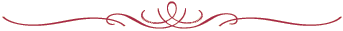
(最新見直し2008.3.12日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものがある。新聞記事を利用する際には「事前通知、要承諾制」であることをしきりに説いている。果たして、著作権法に照らしてこれが正論なりや。れんだいこは、現代マスコミ人の知性の大いなる貧困と利権体質を認める。以下、これを検証するが、するにつけ胸糞が悪くなる代物でしかなかった。 2008.3.12日 れんだいこ拝 |
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 現代の新聞メディア諸君に告ぐ。君たちが記事著作権を生硬に主張するのなら、新聞1面の然るべきところに「本紙には著作権有り。勝手な引用転載をご法度とする」云々を表記すべきではないか。君達の著作権理解に拠ると、ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶという。それほど後生大事なものならば、明記しておくのがマナーではないのか。 れんだいこは、政党の場合と同様に記事著作権の振りかざしは「自絞殺」と思う。活字離れの遠因になっているのではないかと思う。それは、識字率の高さを誇りにしてきた日本の伝統に対する背徳ではないかと思う。そう思わない君達はならば、信ずるところに従い看板に偽り無きように然るべき前書き告知をせねばならぬ。今のままでは卑怯姑息である。 ついでに述べておくが、君たちが予防法的に記事著作権を振りかざせば振りかざすほどプレス特権を剥奪せねばならなくなる。でないと釣り合いが取れないだろう。特権の上に胡坐(あぐら)をかいて、その特権から生まれた権利を独占的に主張するのは余りに虫が良すぎよう。職務の社会的負託という公益性概念を欠如させているところに、かような戯画的権利姿勢が立ち現われているのではないのか。 君達の関心はむしろ、誤報、虚報、記事改竄、悪解釈に対してこそ真摯で無ければならない。この姿勢を怠惰にさせて、記事著作権を振りかざすのは二重の痴態であろう。もっとも、誰かが音頭を取っているのではあろうが。れんだいこにはナベツネの悪行が見えてくる。それに引きずられた言論人の見識の低さが見えてくる。 2006.3月現在もう一つ問題が発生した。新聞は、他の業種業界では禁じられている同一価格での新聞販売協定トラスト是認という「特殊指定」の保護に与っている。この価格トラストが廃止されると、「競争激化で販売店の寡占化は避けられず、宅配制度も危機にひんする」との理由に拠っている。なるほど新聞の果たしている社会的役割からすれば是認されるべきであろうが、他方で生硬な著作権を主張していることを勘案すれば、虫のいいエエトコ取り発想であることが透けて見えてくる。 れんだいこは、日本新聞協会編集委に尋ねたい。君達が「特殊指定保護継続」を云うなら、著作権主張を見直すべきではないのか。少なくとも、著作権法第10条第2項で概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作物に該当しない」との規定にも拘わらず、色々理屈を付けて「ニュースは無論のこと死亡記事さえ著作権が及ぶ」とする態度を改め、規制緩和せねばなるまい。 与野党問わず、この辺りを不問にしたまま「新聞の特殊指定制度の存続を求める」のはむしろ不義と云うべきではなかろうか。 2006.3.15日、2006.4.6日再編集 れんだいこ拝 |
| 日本新聞協会編集委員会より「ネットワーク上の著作権について―新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に」として「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」なるものが出されている。れんだいこはこれを「歴史的暗愚声明」ではないかと思っている。我等がマスコミ人の現段階的インテリ教養度とええとこ取り精神と頑迷ぶりが分かって興味深いのでこれを本サイトで考察する。 本文リンク先で確認いただくとして、れんだいこ見解を逐次つけてみる。文意分け、文№付け、ゴシック文字、句読点、「」、『』の使い分け等読みやすくするため、れんだいこが任意に措置した。 蛇足ながら、日本新聞協会説に拠れば、こうやって日本新聞協会編集委員会見解をリンクすることも転載で披瀝することも、逐条検討していくことも無断では出来ず、著作法違反になる。しかし、そんな馬鹿なことがあるだろうか。一般に、情報の作用には、1・伝達、2・周知徹底、3・議論の叩き台としての要素があると思われるが、日本新聞協会の著作権見解は情報のそういう本能的使命をことごとく圧殺した上で公然と居直っている。 れんだいこが一例をもって諭す。外電で2004.4.8日、「民間日本人3名人質、殺戮予告事件」が報ぜられてきた。我々は、こうした情報をマスコミを通してしか入手できない。外電ならずともその他政府要人の記者会見然り。これらの記事に著作権を被せることにどういう意義があるというのだろう。法理論的には、著作権網からの解放を意味する何らかの受託委任行為論が生み出されるべきであろう。日本新聞協会編集委員会はそういう営為の労を採ろうとせず、「(著作権非適用は)死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています」などとのたまっている。 思うに、彼らは官報式のこうした一方的伝達で事が足り、知らぬは民の勉強不足としていつでも罪科を被せられるよう罠を仕掛けている。「口コミと議論の錬成に資する」観点を端から放棄しているが、知的教養人としてはかなり野蛮な精神に依拠していることを証左しているように思われる。マスコミはいつからかような偏屈知に汚染されたのであろうか。その歴史は案外浅く新しい。ここが事態を理解する際のポイントだ。誰かが意図的に仕掛け、イエスマンたちが合唱しているに過ぎない。特に読売系が酷い。あらゆる記事に「無断転載禁止」なる断り書きをつけ、記事見出しのテロップ紹介にさえ告訴介入し、その他方でサブミナル効果を楽しんでいるが、その真意は奈辺にありや、狂人の所為ではないか。ナベツネよ聞いとるか。 2003.4.20日、2004.4.12日再編集 れんだいこ拝 |
| 【総論(要約)】 | ||||||
|
||||||
| 「1997.11月付け日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」は、冒頭から「電子メディアで発信する記事・写真利用に於ける事前通知要承諾制」を振りかざしているが、著作権法のオーバーラン解釈ではなかろうか。れんだいこにはあたかも、憲法9条規定にも拘らず自衛隊合憲論を詭弁する論法に似ている気がする。 2008.3.12日 れんだいこ拝 |
||||||
| 新聞、書籍などの著作権と電子メディア上のそれとは「基本的に同一」とあるが、果たして正論だろうか。れんだいこには決定的な違いがあるように思われる。その一つは、新聞、書籍などは基本的に有料物であり、電子メディアは基本的に無料物であるという違いが認められること。二つ目に、新聞、書籍の記述は変更不能的であるが、電子メディアは容易に記述変更されるという違いが認められること。三つ目に、電子メディアは本来、著作権に馴染まない向きのもので、相互閲覧及び利用のし合いを目的として市場形成してきたという違いが認められること。 これらの差違は、「基本的に同一」視する方向ではなく、逆に「違いを際立たせる」方向で理論形成すべきでは無かろうか。電子メディアは「人民的共有サイト」にこそ眼目があり、これをプライベート化するのなら会員制パスワード方式にすれば良いということであって、電子メディアに著作権適用させようとするのは本来馴染まないと考える。この観点に立って、どういう要件が揃えば著作権を被せるのに値するのかを検討した方が生産的では無かろうか。 |
||||||
| 該当条文は著作権法10条2項の概要「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、著作権法上の著作物に該当しない」規定である。この規定は本来文字通り「著作権非適用」を意味している。ならば、「原則として利用する際には承諾が必要なのです」は逆理解で、「原則として利用する際には承諾は不要なのですが云々」と特殊例を述べるのが正当な立論の仕方というものだろう。 法文がかように人民的利益を優先的に担保しようとしていると云うのに、敢えて法文に従わずこれを空洞化させるロジックこそ邪にして曲者であろう。思えば、官僚の見識のほうが高く、民間のそれの方が低いというままある実例の一つであろう。 2006.4.6日再編集 れんだいこ拝 |
| 【日本新聞協会の対インターネット見解】 | ||||||||
|
||||||||
| こういう物言いが流行しているが、れんだいこには不快極まりない。日本新聞協会が、インターネット空間に著作権規制を控える法文に違背してまで新聞・出版物並に著作権を適用せんとする時の論理が、その経済的利益狙いという本音を隠して「情報の信頼性を確保するため」なる美名を掲げて恫喝しようとしているだけのことではないのか。この論法は、国家権力の公共秩序論と寸分違わない。 | ||||||||
| 全くの暴論だろう。以上述べたように、「インターネット上での著作物の利用と印刷刊行物やテレビなどの利用との違い」を確認する作業が望まれているのであって、それを「変わりありません」などと云い為し推敲を放棄せんとするなどというのは全くの逆対応でありナンセンスでは無かろうか。 |
| 【各論】 | ||||||||
| 1・記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります。 | ||||||||
|
||||||||
| 新聞協会のこの弁「個人的なページだからといって、私的使用にはなりません」は暴論ではなかろうか。個人の社会的繋がりを考えれば当たり前の事を述べ、それがあたかも不正であるかのごとく云い為すロジックは正気ではなかろう。 | ||||||||
| 私的使用を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とする規定がそもナンセンスであろう。かく狭めた上で、それ以上の私的使用について要通知要承諾制にしようとする魂胆が明け透けである。私的使用とは、個人の営為でありそれ以上でも以下でもなかろう。敢えて識別するなら、営利を目的とするか非営利なのかの垣根を作ることも出来ようが、さほど意味は無かろう。求められるべき基準は、社会的有害行為か無害行為かが問われるべきで、無害であれば開放されるべきであろう。 | ||||||||
|
インターネット上のホームページが世界中のどこからでもアクセスすることができるのは当たり前であろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません」なるロジックは何なんだろう。「多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、その目的が達成されるよう導かれねばなりません」となるところ、「私的使用とは言えません」なる方向へ捻じ曲げている。「私的使用であろうが公的使用であろうが」多数の人に読んで貰う為にどうするのかが問われているのだろう。従って、結局肝心なことを何も云っていないことになる。 |
||||||||
| 「公衆送信権」や「送信可能化権」を認めるにせよ、「多数の人に読んでもらうことを目的」にしてさてどうするのかが問われており、「公衆送信権」や「送信可能化権」があるというだけでは何も云っていないことになる。「インターネット時代の著作権法」の項で説明するとあるが、どういう説明するのだろう。 | ||||||||
|
|
||||||||
| 2・LANやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です。 | ||||||||
| 企業や学校などのネットワークの中で新聞・通信社が発信する情報をニュース・クリップなどとして無断で利用することはできません。 企業や団体などがLAN(企業内または構内の通信網)やイントラネットといった内部ネットワークを構築するケースが増えています。こうした内部ネットワークに、経済や社会全体の動向、業界や自分の会社のことなどが取り上げられたニュースをクリッピングして社員などに周知させたい、という希望も新聞・通信社に寄せられるようになりました。こうした利用の場合でも、限定された企業内で社員の一人ひとりが自分で見るだけだからといって私的使用だということにはなりません。 大学などで、「研究や教育を目的としているから」という理由で、情報を無断で利用するケースも散見されますが、やはり著作権法に触れます。研究者や学生が利用しやすいよう、一般に公開しているホームページに転載すれば、世界中どこからでもその情報を見ることができます。企業や大学で、ID・パスワードを使ってアクセスできる人を制限したとしても、私的使用の範囲を超えることになります。必ず著作権者に連絡し、承諾を得ることが必要です。 |
||||||||
どうやら、私的使用なら認められ、私的使用ではないから「著作権者の承諾が必要」と云っているようだ。しかし、「著作権者の承諾が必要」は、著作権法何条のこういう規定によって云々と説明すべきではないか。ならば示してみよ。 インターネットが情報の世界同時的開示に勝れた性能を持つ利器だというのに、それを否定して自己都合的に利用させようとする魂胆の方が咎められるべきだろう。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 3・ニュース記事には、著作権が働いています。 | ||||||||
| 著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。 「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・著作物に該当しない」と規定しているため、「新聞記事には著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは、「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。 著作権法は1971年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い、「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。 「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や、「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。 しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。 解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。 |
||||||||
| マジかよう。何と、死亡記事にも著作権を平然主張し、死人からもテラ銭稼ごうという魂胆が見える。概要「死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したもの』と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます」と云う。 しかしねぇ、それが大衆的に利用されたとして何の不都合があるのかいなぁ。そこまで云うのなら、事前に死亡者の了解とっておいてくれよなぁ。あなたが万一死亡した際にはあなたのことを記事にいたします。その際、著作権を頂くようになるのですがご了解のほどを、てなもの一筆取っておいてくれよなぁ。 ニュースも然りだ。誰が使おうと却って名誉だと思わなくっちゃ。何をひねくれて「無断利用は認められません」なぞとするのだろう。だったら、許可する場合の基準を明確にしておかないと法の公平に反するでせうが。ついでに記者クラブ制などの閉鎖的特権的制度も廃止して、記者会見、聴聞会、裁判傍聴なぞ入札制度にしていただかないとなぁ、虫が良すぎるわ。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 4・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります | ||||||||
| カギかっこを付け、出所を明示すれば引用になる、と安易に考えていませんか。引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」でなければならないなどの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません。 著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。 しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。 この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。 つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。 表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。 |
||||||||
| ここの理解も全く違う。れんだいこは、「引用基準のルールとマナー」を遵守さえしていれば、それは無条件で認められるべきと思っている。「質量の主従関係」は、その方が望ましいという程度のものではなかろうか。仮に新聞社の記事を引用するとして、それを主的に紹介したとして何の咎があろう。むしろ、その記事ないし新聞社の評価を高める訳で、無償の宣伝役を引き受けている故に褒められるべきであろう。 一体全体、自称知識人の狭量さは目に余る。著作権法第32条の「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」は文字通りに解釈されるべきもので、「引用基準のルールとマナー」を遵守し、「目的上正当な範囲内で行われる」ものであるなら無条件に認められるべきではないか。ここでも著作権法第1条の「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」の縛りが適用されるべきで、文化の発展に寄与する行為であれば何の咎めを受けることがあろうに。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 5・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります | ||||||||
| 原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要です。利用が認められるのは、作品自体の存在だけを紹介するごく短い要旨程度のものに限られます。 「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することは認められるだろうか」と相談を受けることがあります。 一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。 見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫がこめられており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。 新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提供しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、1面、2面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。 |
||||||||
| ここの下りも日本新聞協会の狭量さは目に余る。「原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の『翻案』に当たり、著作権者の承諾が必要です」とあるが、本当だろうか。引用、転載、要約による紹介が「ルールとマナー」に沿って紹介されるならば、当然に著作者あるいは情報元の紹介も為される訳だから喜ばしいことであって、宣伝にもなることであるし、それが「承諾無しの紹介は相成らん」というようになるだろうか。 日本新聞協会は、「見出しの紹介も相成らん」と云う。無茶では無かろうか。れんだいこには、そのような規制が著作権法第一条の「「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」という趣旨に合致しているとはとても思えない。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 7・インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました。 | ||||||||
| 大勢の人を対象とする双方向の送信(インタラクティブ送信)が「自動公衆送信」と定義され、著作権者の権利が「公衆送信権」として明確になりました。 インターネット時代に対応するための著作権法改正が1997年6月に成立し、1998年1月1日から施行されます。これは、世界知的所有権機関(WIPO)が、デジタル・ネットワーク時代に対応した国際的な著作権のあり方を検討し、「WIPO著作権条約」「WIPO実演・レコード条約」の二つの新条約を採択したのを受けたもので、インターネットなどを通じて行われるインタラクティブ送信を「自動公衆送信」と名付け、インターネットに接続しているサーバーに情報を記録・入力したり、情報を入力したサーバーをネットワークに接続したりする行為を「送信可能化」と呼ぶことにしました。そして、著作者やレコード製作者・実演家に「送信可能化権」という新しい権利を与えたのが特徴です。 文化庁は、インターネットなどへの著作物の利用については「これまでも複製権などで著作権者の権利が保護されていた」としていますが、理論的には著作権者の権利にわずかなすき間ができていました。今回の改正はこのすき間を埋め、インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にしたものと言えます。 |
||||||||
| 1997.6月に著作権法が改正され、「公衆送信権」が認められたことにより、「インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にした」と云う。1997.6月の著作権法改正文については今後精査して見るが、果たして日本新聞協会の理解する内容通りであろうか。仮にそうだとすれば、その改正内容に疑義がある。 「どのような形でのサーバー入力でも著作権者の承諾が必要」ということになると、リンク紹介も承諾事項ということになろう。だとすれば、そのような規制はインターネット空間の通行往来機能を著しく弱め、問題大いにあり、というべきではなかろうか。文化庁の見解を質したいところである。 |
||||||||
|
|
||||||||
| 8・新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください | ||||||||
| 転載だけでなく、インターネット上のリンクについてもご連絡をお願いします。 新聞・通信社は、日々の情報発信に当たって、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載するだけでなく、公正を旨として、より適切、より正確な記事とするよう創意・工夫を重ねていますが、メディア環境は、新聞製作など出版業のコンピューター化が進み、ネットワークを通じての情報発信への傾斜が強まるとともに、放送のデジタル化と合わせて通信と放送の融合も進むなど急激な変容を続けています。その中で、新聞・通信社のホームページが日本における代表的なサイトに成長するなど、各社とも技術進歩の先頭に立って一層の努力を重ねています。 一方、新聞は公共的な使命を負った報道機関としての立場から、各種記事を印刷物や放送素材として利用したいとのご要望に対しては、できるだけこたえるようにしてきました。しかしながら、デジタル化された情報は、簡単に複製でき、何回複製しても品質は劣化しません。ネットワークに載せることで、情報は瞬時に世界中からアクセスできるようになり、また受け取った情報を加工して送り出すことも可能となるなど、情報のインタラクティブなやりとりができるようになります。 著作物の転載を認めた場合、2次、3次、4次と情報がどのように波及していくのか具体的な像は描きにくく、著作権者としてどう考えたらよいかの明確な基準もまだできていません。 このため、新聞やインターネット上などに掲載したニュース記事や報道写真などを、インターネットや企業内ネットワーク(LAN)などに転載したい、という要望が出た場合、どう対応するかについての考え方は、新聞社によってまちまちです。 新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。 利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやLANの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。以上 |
||||||||
| 新聞・通信社による「連絡、ご相談要請」は、「お上意識丸出し」では無かろうか。元々情報とは伝達されるべき本姓があることを踏まえ、可能な限り認め合う方向で対応することこそ望まれているのではなかろうか。日本新聞協会の要請は逆方向甚だしいと云わねばならぬ。仮に、日本新聞協会にそのような権限が与えられるなら、第一次情報の公正な取得システムが詮議されねばならず、現行記者クラブ制を見直し、その都度の入札制度へと向かわねば不公正だろう。エエとこ取りは虫が良すぎように。 |
| 【新聞各社の具体的な対応の状況】 |
| 上記の観点から、新聞社各社は次のような【著作権・リンクについて】断り書きをしている。ここでは最も熱心に詳述していると思われる朝日新聞社、読売新聞社を代表例として取り上げ、続いてその他参考例を見てみることにする。 |
| 【朝日新聞社の著作権見解】 | ||
「朝日新聞社の著作権・リンクについて、プライバシー・クッキーについて」は次の通り。
|
| 【読売新聞社の著作権見解】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
読売新聞社の見解は次の通りである。「著作権」
|
| 【日経新聞社の著作権見解】 | |
|
日経新聞社も次のようなお知らせをしており、ほぼ同様観点から【著作権・リンクについて】の断り書きをしている。日本経済新聞社からのお知らせ (2002.7月付け)
|
| 【産経新聞社の著作権見解】 | |
産経新聞社の見解は次の通りである。
|
| 【毎日新聞社の著作権見解】 | |
毎日新聞社の見解は次の通りである。
|
| テレビ局も同様見解を声明している。フジテレビの例を見てみる。 | ||
|
| 各図書館も同様の観点から制限声明をしている。ここでは、早稲田大学図書館の例を見てみる。 |
|
早稲田大学図書館 |
|
【ドキュメントの著作権ならびに使用許諾条件】
【URL の公開】
【掲示責任者】
【謝辞】 このページは「早稲田大学メディアネットワークセンターの掲 示するhtml ドキュメントに関する著作権・使用許諾条件・掲示責任者の表示」の文面を修正利用して作成しました。 Copyright (C) Waseda University Library, 1998-.All Rights Reserved.First drafted 1998 sobun@wul.waseda.ac.jp |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)