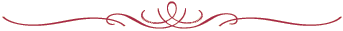
| 朝日新聞社の「ネット掲示板阿修羅」への記事無断転載に対する警告考 |
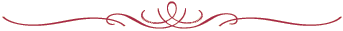
(最新見直し2007.6.4日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| れんだいこが情報源として愛用している希少ジャーナル「阿修羅」が何と、朝日新聞知的財産センターから無断転載警告と刑事告訴の恫喝を受けていることが報ぜられている。早くもこの警告を当然とする論調が為されているようであるが、れんだいこは闘うべしと考える。以下、この問題を考察する。 結論から言えば、著作権法もまたイエス派とパリサイ派の思想性に関わるものであり、旧著作権法には何がしかイエス派の精神が見られているが、新著作権法となるとユダヤ教パリサイ派のものであり、それが為に何かと軋轢を生みつつあるという認識が欲しい。要するに、ユダヤ商法との闘いということになる。我々は、文の世界へまでの聖域無き資本主義化を断じて許すべきではなかろう。 朝日新聞知的財産センターは既に現代パリサイ派の権益思想に篭絡されている。革命でも起こして指導する者を変えない限り、これからもそうであり続けるだろう。これを結論としておく。 2007.6.4日 れんだいこ拝 |
| 【朝日新聞知的財産センターの通告】 | |
「阿修羅管理運営13」の管理人さん氏の2007.5.31日付け投稿「朝日新聞東京本社で著作権などを担当する部署の知的財産センターです」によれば、5.30日18時49分に、下記のメールが届いたとのことである。これを転載する。
|
| 【朝日新聞知的財産センターの見識考】 |
| 我々はこれにどう対応すべきだろうか。極力理論的に反応してみたいが、その前に直感的な見解を記しておくことにする。 れんだいこが思うに、産経、読売が名うての御用新聞化し憲法改正世論の盛り上げに躍起になっている折柄、朝日、毎日、日経は既に五十歩百歩の差でしかないほどの差にまで接近してきているものの、辛うじて「中立性」を保持している面があり、これが評価されて購読に結びついているのではなかろうか。特に、朝日については、右翼から「アカ新聞」呼ばわりされてきた歴史があるが、これを逆に云えば左派系の支持を得ているということでもあり、朝日のこの特徴は評価されることではなかろうか。 但し、著作権法の強権適用となると別の話となる。読売、朝日が双璧の強著作権者として立ち現れており、「記事の無断転載罷りならん」と云う。読売となると、ついこの間まで、記事と云う記事の末尾に「無断転載禁止」を付しており、大方の顰蹙を買っていた。読売の著作権実態については、「読売新聞社のライントピックス提訴考」で言及する。 朝日はそこまでではないと思っていたら、今やネット空間の人気サイトにしてれんだいこも愛読している「阿修羅」に恫喝をかけていることが判明した。両者に見られるは権威主義であり、読売がこれを為すのはらしさであきらめもあるが、朝日には不似合いなように思われる。本当のアカ新聞なら、こったら野暮なことは云わないのだが。 しかし、朝日の知的財産センターのこたびの通告はかなり確信犯的に為しておるようなので、れんだいこは、同社の狙いはどこにあるのかまで含めて分析せねばならないと考える。以下、論じてみることにする。 |
| 【天下の往来物情報を囲い込みする朝日の思想考】 |
| れんだいこは早い話が、新聞記事は政党機関紙記事も然りだが、ある種の公共情報だと思っている。公共事業は周知されることが使命であり、規制されることは好ましくないと思っている。だが、各新聞社、政党はいつの頃からかはっきりしないが、私的営利企業的側面を強く主張し始め、いわばその商品である記事に対する著作権を発動させ始めた。この歴史的転換期をはっきりさせたいが、今のところ分からない。判明することは、1997.11月、「日本新聞協会編集委員会のネットワーク上の著作権に関する協会見解」(以下、「新聞協会の著作権見解」とする)なるものが出されており、各社は以降この申し合わせに基き記事著作権論を主張し始めた形跡が認められることである。これについては、「日本新聞協会編集委のネットワーク上の著作権に関する協会見解」考」で言及する。 れんだいこが思うのに、各新聞社、政党が馬鹿げた記事著作権を主張して止まないのなら、主張しない新聞社、政党を創出する以外に無い。政党の場合なら直ぐにできるが、新聞社となると容易ではない。そこで、願うらくは、第二NHK的な官営的新聞事業を創出することである。これにより、公共情報の任意伝達、回し読みができるようにした方がより良い社会になるのではなかろうかと思っている。 こんなことなら、そもそもNHK放送局が出来たとき、同時にNHK新聞社をも創っておくべきだった。記事そのものに公共性を持たせ、国民が大衆的に回し読みすることに何ら制限しないとの約定を付けてNHK新聞社をも創っておくべきだった。当時、このアイデアがなぜ湧かなかったのだろう。恐らく、その時点では、各新聞社が今日の如く記事著作権を弄ぶようになるとは夢には思えず、むしろ官営の新聞を起こせば、戦前の大本営発表的な時の政府御用化新聞に堕し易いことを危惧して阻止されたのではなかろうか。 国策新聞社創出の時機があったのかどうか判らないが、仮にあったとして、その阻止の過程が実証されたなら、民営新聞社が国策新聞社機能を代替する公共性が確認されるだろう。恐らく、「社会的負託に応える公共性理論」が吹聴され、これに基き記者クラブ、その他ある種ギルド的な排他的独占的な取材環境が保障されている経緯が見えてこよう。 れんだいこは、新聞社にはこういう歴史があると仮定している。戦後から1970年代までは、これはこれで何ら問題は無かった。問題は、1980年代に入り、中曽根政権の登場と共に読売のナベツネグループが政権中枢に入り込むと同時に、それまでのハト派的著作権抑制政策が放棄され、今日的タカ派的著作権強権化政策へとシフト替えされた。 その狙いは、情報に対する天下の往来物的性格から統制的性格へ転換することにあった。もう一つは、聖域無き著作権の全方位全方面適用化であり、それは社会的性格から金銭対価的性格へと転ずることにあった。俗に言えば、情報界に於けるユダヤ・ロスチャイルド式商法化であろう。これにより著作権論はすっかり性格を変えてしまった。このことに気づく必要が有るのではなかろうか。 しかし、この転換は、解けないジレンマに陥っている。つまり、上述した「社会的負託に応える公共性理論」に基く特権化と、「資本主義的情報利用対価及び規制理論」が並立し得ないからである。にも拘らず並立させている現下メディア界は、濡れ手に粟のエエトコ取りの得手勝手理論に酔いしれていることになる。 手前のところがそういう体質であると云うのに、官僚の天下り規制を主張しているのは無様と云うより滑稽でしかない。メディア界の天下りも相当程度に為されていると云うのに、官僚の天下り規制を主張して正義ぶっているのも右同じである。 朝日の知的財産センターよ、君たちがこういう風に考えたことは無いとしたらかなり病膏肓であると考えるが如何かな。 |
| 【朝日の知的財産センター思想と音楽著作権ジャスラック思想の通底性考】 |
| 朝日の知的財産センター思想及びそれを支える「新聞協会の著作権見解」は、、音楽著作権に於けるジャスラック思想と通底している。ここに認められるのは、業界協会が、それぞれの著作物が人民大衆的に利用され享受されることを願って促進させることに営為するのではなく、利用享受に対する承諾と課金制を取り入れ、民間警察的取り締まりに営為する傾向である。この姿勢により、本来ならそれぞれの業界著作物の普及功労者として表彰されねばならぬ者に対して、警察に逮捕を要求し、懲り懲りするようヤキイレをお願いすると云うテイタラクぶりを見せている。業界が、本来期待されているものと全く反対の働きをするところに意義を見出していることになる。 現在、多くの自称インテリが、手前達の駄文にもいつの日か課金され収入にならないかと願う気持ちとハーモニーさせてか、マスコミ著作権、音楽著作権のタカ派的強権適用を支持している。れんだいこは云っておく。僅かな手当てをあてにするより、君たちの言論稽古として市井情報を無料享受した方が、よほど賢明であろう。情報享受はお互いがやればオアイコなのよ。下手な欲張り思想に染まるから同調してしまうのさ。 君たちの情報が評価されるからこそ市井に出回る。それを光栄とすべきではないか。そうして知名人になれば、仮に本を出版した時、良く売れるのではないかな。そう思えば、民間企業なら売り出そうとすれば高い広告費を払って宣伝している訳で、それを無料で販促してくれている訳だから感謝すべきではないか。それを小難しく云う手合いの論文にろくな物はありゃしないって。これが法理というものさ。 当然このことは音楽著作権にも云える。人が口ずさんでくれたら、有り難いと思うべきではないか。それが回りまわってヒット曲になるのではないかな。ヒット曲に恵まれれば、食うていけるではないか。その日まで辛抱と稽古の毎日でよいではないか。その芽を双葉のうちに摘むようなみっともない手を出してくれるな。れんだいこはそう思う。 |
| 【マスコミ著作権思想と日米安保思想の親疎性考】 |
| 著作権法問題は、「憲法と日米安保の絡み」と酷似している。これについて愚考する。戦後日本は、憲法体制と日米安保体制の二元支配から成り立っており、両者は調和しつつ抗争している。著作権法も、旧著作権法と新著作権法が並立し、調和しつつ抗争している。こう認識する必要がある。こう認識すれば、新著作権法信奉派にして護憲を説くインテリの弁はウソ嘘しいことになる。君たちは、著作権に於いては既に改訂派であり、その意味で既に改憲派ではないのか。 れんだいこ理解によれば、旧著作権法は、新聞記事、政党機関紙記事等々は極力著作権規制せず、天下に往来することが望ましいとされているように読み取ることが出来る。はっきり断定できないのは、アバウトに表現されているからである。しかし、史実は実際に「新聞協会の著作権見解」が出される前までは、「情報は天下の廻りもの」と弁えて、特段の権利主張したことはなかった、と、れんだいこは理解している。ちなみに、この頃の政治を主導していたのは、戦後与党を形成した自民党ハト派である。ハト派の天下の時には、こういうみみっちぃことは云わなかったということである。 ところが、そのハト派が駆逐され、タカ派が支配権を握り始めると、社会の強権規制が押し進められていくことになった。治安、防衛強化然り、著作権然りである。現下の著作権規制は、この過程で浸潤させられてきているとする歴史的認識が欲しい。これのどこが問題かと云うと、れんだいこに云わせれば、日本が国家的自律を失い始め、それに応じて歴史的なユダヤ商法が満展開し始めたというところに認められる。 歴史的なユダヤ商法に対して、これをどう受け止めるのか、この是非が問われている。かの昔、イエスがサタニズム思想であるとして厳しく批判したのは承知の通りである。イエスは、「人は世の為人の為生きるよう」導いた。しかし、当時のユダヤ教パリサイ派は、「選民である自分達の民族の為、己のため、全ては金貨の蓄財次第」とする教義を打ちたて、信仰さえもその教義に基づき秩序づけていった。両者の思想のいずれが正しいのかが問われているのではないのか。 れんだいこが見立てるところ、「新聞協会の著作権見解」思想は、現代パリサイ派の思想に列なるものであり、その真の狙いは情報統制に導こうとするものである。これを立証するのは難なくできるが、ここでは触れない。問題は、「新聞協会の著作権見解」は漠然と打ち出されたものではなく、極めてイデオロギッシュなものであることにある。これは、名うてのネオ・シオニストである中曽根−ナベツネ派の主導で発せられたものであることからしても分かるところである。「新聞協会の著作権見解」の政治性については、「『ヒトラー古記事問題』で見えてくる著作権の本質」で言及する。 そろそろ話を戻す。朝日新聞知的財産センターは、現代パリサイ派の観点から著作権を主張し、「阿修羅」に恫喝していることを認識すべきである。れんだいこが思うに、朝日新聞がそのように振舞うのなら、我々は購読せず同盟で対抗すればよい。但し、それだけでは防衛的なので、記事転載天下往来当然論の新聞機関を創出せしめねばならない。テレビメディアも然りであろう。 とりあえず以上書き留めておく。 2007.6.3日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)