 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| ほ |
む |
た |
の |
す |
と |
め |
ら |
こ |
み |
二 |
十 |
と |
せ |
に |
、 |
|
|
|
| 誉田のすとめらこみ(天皇)20年に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
れ |
こ |
の |
く |
に |
に |
い |
た |
り |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 我この国に至りて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| め |
く |
り |
み |
る |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廻り見るに、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| つ |
ち |
い |
と |
あ |
し |
く |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土いと悪しくして、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| た |
な |
つ |
も |
の |
み |
の |
る |
や |
と |
お |
も |
ほ |
ひ |
て |
、 |
|
|
|
| たなつもの(穀物)実るのやと思いて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| さ |
と |
の |
お |
さ |
を |
め |
し |
て |
と |
わ |
せ |
た |
ま |
ふ |
に |
、 |
|
|
| 里の長を召して問わせ給うに、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| そ |
の |
か |
み |
よ |
り |
た |
な |
つ |
も |
の |
み |
の |
ら |
さ |
り |
し |
を |
、 |
| その神より穀物(たなつもの)が実らざりしを、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| さ |
き |
に |
お |
を |
す |
の |
み |
こ |
と |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 先におおす(小碓)の尊(日本武尊)、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| ひ |
む |
か |
し |
の |
ま |
つ |
ろ |
わ |
ぬ |
ひ |
と |
と |
も |
を |
、 |
|
|
|
| 東(ひむがし)のまつろわぬ(服従しない)人どもを、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| こ |
と |
む |
け |
や |
わ |
し |
に |
い |
て |
ま |
し |
の |
と |
き |
、 |
|
|
|
| 言向けやわし(平和)に出でましの時、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| う |
み |
に |
う |
か |
ひ |
て |
わ |
た |
ら |
む |
と |
し |
た |
ま |
ふ |
と |
き |
に |
| 海に浮かびて渡らむとし給う時に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| そ |
の |
わ |
た |
り |
の |
か |
み |
な |
み |
を |
お |
こ |
し |
て |
、 |
|
|
|
| その渡りの神(渡る所の神)浪を起こして、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
ふ |
ね |
た |
ゆ |
た |
ひ |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 御船たゆたいて(ゆらゆらと揺れ動いて)、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| え |
す |
す |
ま |
さ |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| え進まざりき。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| こ |
こ |
に |
た |
ち |
は |
な |
ひ |
め |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ここに橘媛、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
こ |
と |
に |
か |
わ |
り |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 尊に代わりて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| う |
み |
に |
い |
り |
た |
わ |
む |
と |
す |
る |
と |
き |
に |
、 |
|
|
|
|
| 海に入り給わんとする時に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| も |
ろ |
の |
う |
ね |
め |
み |
と |
も |
せ |
む |
と |
て |
、 |
|
|
|
|
|
| 諸の采女(うねめみ)供せんとて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| と |
も |
に |
う |
み |
に |
い |
り |
、 |
た |
ま |
へ |
は |
、 |
|
|
|
|
|
| 共に海に入り、給えば、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| な |
き |
て |
み |
ふ |
ね |
え |
す |
す |
み |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 凪(なぎ)で御船はえ進みき。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| か |
れ |
、 |
な |
と |
り |
ふ |
ね |
と |
も |
を |
つ |
と |
ひ |
て |
、 |
|
|
|
| 彼、な(魚)取船どもを集(つど)いて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| み |
ま |
を |
、 |
ま |
き |
た |
し |
か |
と |
も |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| みまを、まきたしかども(意味不明)、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
ま |
を |
ま |
き |
い |
つ |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| みまをまきいつして(意味不明)、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| と |
み |
と |
い |
ふ |
ひ |
と |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| トミと云う人、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| ひ |
め |
の |
み |
く |
し |
を |
い |
て |
た |
て |
ま |
つ |
り |
し |
か |
は |
、 |
|
| 姫の御櫛を出で奉りしかば、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| ゆ |
ふ |
ひ |
の |
ひ |
て |
る |
こ |
ろ |
と |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 夕日の日照るころとて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| み |
つ |
か |
つ |
く |
ら |
し |
み |
た |
ま |
ひ |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
| 御塚造らし御給いき。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| そ |
こ |
よ |
り |
い |
て |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| そこより出でまして、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| こ |
の |
う |
ら |
の |
な |
と |
り |
ふ |
ね |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| この浦の魚取船に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
え |
く |
を |
の |
せ |
て |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 御えぐ(?)を乗せて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
た |
ら |
せ |
た |
ま |
ふ |
と |
き |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 渡らせ給う時に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| そ |
の |
ふ |
ね |
の |
と |
ほ |
く |
つ |
つ |
き |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
|
| その船の遠く続きしかば、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| ふ |
ね |
の |
を |
な |
か |
し |
と |
の |
た |
ま |
へ |
け |
ろ |
。 |
|
|
|
|
| 船の尾長しとの給えけろ(る?)。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| み |
こ |
と |
の |
み |
ふ |
ね |
を |
お |
さ |
め |
し |
や |
ま |
、 |
|
|
|
|
| 尊の御船を納めし山、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ふ |
ね |
の |
か |
た |
ち |
を |
な |
せ |
り |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 船の形をなせり。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| こ |
れ |
を |
ふ |
な |
つ |
か |
い |
ひ |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| これを船塚と言いき。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| み |
こ |
と |
く |
ぬ |
か |
に |
あ |
か |
り |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 尊、くぬが(陸処)に上がりて、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
へ |
り |
み |
た |
ま |
ふ |
と |
き |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 返り見給う時に、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| み |
つ |
と |
り |
の |
さ |
わ |
に |
つ |
と |
へ |
お |
り |
し |
を |
、 |
|
|
|
| 水鳥の沢に集へおりしを、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
そ |
な |
わ |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 見そなわして、 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| は |
た |
に |
し |
る |
し |
あ |
る |
か |
こ |
と |
し |
と |
|
|
|
|
|
|
| 旗に印あるが如しと |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| の |
り |
た |
ま |
ひ |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| のり給いて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| こ |
わ |
す |
め |
ら |
お |
ふ |
か |
み |
の |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| こはすめら(皇)大神の |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| み |
お |
し |
え |
の |
み |
し |
る |
し |
と |
こ |
そ |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 御教えの御印とこそ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| よ |
ろ |
ほ |
ひ |
つ |
つ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 喜びつつ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ま |
つ |
す |
き |
の |
お |
へ |
し |
け |
り |
し |
や |
ま |
に |
の |
ほ |
り |
て |
、 |
| 松杉の生え茂りし山に登りて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| み |
ち |
く |
ら |
や |
ま |
と |
の |
り |
た |
ま |
へ |
て |
、 |
|
|
|
|
|
| 道暗山とのり給えて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| す |
き |
き |
の |
う |
ろ |
に |
か |
か |
み |
を |
か |
け |
て |
、 |
|
|
|
|
| 杉木の洞(ウロ)に鏡を掛けて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| い |
せ |
の |
お |
ふ |
み |
か |
み |
を |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伊勢の大御神を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お |
ろ |
か |
み |
た |
ま |
ひ |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| おろか(拝み)み給いき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
こ |
の |
か |
か |
み |
を |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 彼、この鏡を、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
か |
め |
ま |
つ |
れ |
は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 崇め祀れば、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| こ |
め |
む |
き |
お |
の |
れ |
に |
み |
の |
る |
と |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 米麦(コメムギ)おのれに(自然に)実ると、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| の |
ら |
し |
め |
た |
ま |
ひ |
て |
、 |
い |
て |
ま |
し |
き |
。 |
|
|
|
|
| のらしめ給いて、出でましき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
、 |
み |
お |
し |
え |
の |
ま |
ま |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 彼、御教えのままに、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
か |
め |
ま |
つ |
り |
し |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 崇め祀りしに、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ま |
こ |
と |
に |
の |
ら |
せ |
ま |
ふ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| まことにのらせ給う |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| か |
こ |
と |
な |
り |
き |
と |
き |
け |
り |
と |
え |
ひ |
き |
。 |
|
|
|
|
| かことなりきと聞けりとえひき(誠に告げられたごとくになったと聞いたとおっしゃった)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| か |
れ |
、 |
こ |
こ |
に |
い |
は |
の |
く |
に |
た |
ま |
お |
き |
つ |
、 |
|
|
| 彼、ここに岩の国魂置きつ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
か |
み |
と |
あ |
か |
め |
つ |
り |
て |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鏡と崇め祀りて |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| お |
ふ |
み |
や |
は |
し |
ら |
ふ |
と |
し |
り |
た |
て |
て |
、 |
|
|
|
|
| 大宮柱太しり建てて(どっしりと建て)(大宮柱太敷立て→中臣祓・伊勢祝詞参照) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| い |
わ |
ひ |
ま |
つ |
り |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 祝(斎)い祀りて |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| あ |
ま |
て |
ら |
す |
わ |
か |
ひ |
る |
め |
の |
お |
ふ |
か |
み |
と |
、 |
|
|
| 天照らすわかひるめ(稚日霊)の大神と、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
た |
ひ |
ま |
つ |
り |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 称え祀りしかば、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| く |
す |
し |
き |
か |
な |
、 |
お |
ふ |
み |
え |
つ |
も |
ち |
て |
、 |
|
|
|
| 奇すしきかな、おふみえつ持ちて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| あ |
ま |
き |
あ |
め |
ふ |
り |
、 |
あ |
ま |
き |
み |
つ |
わ |
き |
、 |
|
|
|
| 甘き雨降り、甘き水湧き、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| い |
て |
し |
に |
や |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出でしにや。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
つ |
く |
た |
も |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| みつく田も、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| く |
か |
た |
も |
ひ |
に |
つ |
き |
に |
い |
や |
ま |
し |
に |
ひ |
ら |
け |
、 |
|
| くが田(畑)も日につきに(日に日に)いやましに(益々)開け、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| い |
や |
た |
わ |
に |
み |
の |
り |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| いやたわに(はなはだ多く)実りしかば、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
み |
よ |
ろ |
こ |
ほ |
ひ |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民悦んで、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| お |
ふ |
か |
み |
を |
い |
と |
う |
や |
ま |
ひ |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
| 大神をいと敬いき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
、 |
お |
ほ |
み |
か |
み |
の |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 彼、大御神の |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| わ |
れ |
に |
お |
し |
へ |
し |
へ |
た |
ま |
わ |
く |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 我に教えしへ給わく、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ろ |
き |
の |
し |
た |
に |
た |
ま |
あ |
り |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 洞木の下に珠あり。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ほ |
り |
|
て |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 掘り出して、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| わ |
か |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
を |
ま |
つ |
れ |
と |
|
|
|
|
|
|
| わかむすび(稚産霊)の神を祀れと |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| お |
し |
へ |
た |
ま |
へ |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教え給えき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| か |
れ |
ゆ |
め |
の |
お |
し |
へ |
の |
ま |
ま |
に |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
| 彼、夢の教えのままにして、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 七 |
つ |
の |
た |
ま |
を |
と |
り |
|
て |
あ |
わ |
せ |
ま |
つ |
り |
て |
、 |
|
| 七つの珠を取り出して合わせ祀りて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ま |
か |
た |
ま |
の |
お |
ほ |
か |
み |
と |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勾玉(まがたま)の大神と |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| い |
わ |
ひ |
ま |
つ |
り |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 祝い祀りしかば、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| あ |
め |
の |
ま |
し |
ひ |
と |
ら |
い |
や |
ま |
し |
に |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
| 天のましひとらいやましにまして(人々は増えに増えて)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| と |
み |
も |
た |
す |
わ |
し |
す |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 富もたすわしすき(満ち足りた)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
こ |
こ |
に |
す |
め |
ら |
み |
こ |
と |
の |
|
|
|
|
|
|
|
| 彼、ここに、すめらみことの |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
な |
か |
の |
お |
ほ |
み |
よ |
わ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| たなか(?)の大御代は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
め |
つ |
ち |
ひ |
つ |
き |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 天地日月と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| と |
こ |
は |
に |
ま |
も |
り |
た |
ま |
へ |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| とこは(常盤)に守り給えて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さ |
き |
く |
に |
は |
ひ |
ろ |
く |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| さ(狭)き国は広く、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
し |
き |
く |
に |
は |
ひ |
ら |
け |
く |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| かしき(険しい)国は開けく、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| 五 |
く |
さ |
の |
た |
な |
つ |
も |
の |
ゆ |
た |
か |
に |
、 |
|
|
|
|
|
| 五種(くさ)のたなつもの(穀物)豊かに |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| む |
く |
さ |
か |
に |
み |
の |
ら |
し |
め |
た |
ま |
へ |
と |
、 |
|
|
|
|
| むくさかにみのらし給えと(豊かに益々栄えよと)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| わ |
め |
な |
の |
つ |
き |
つ |
き |
に |
え |
た |
り |
て |
も |
、 |
|
|
|
|
| わめなの次々にえたりても(子孫の継々に至っても)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ね |
き |
ま |
を |
す |
こ |
と |
な |
せ |
よ |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ねぎ申すこと為せよ(祈りせよ)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ほ |
む |
た |
の |
す |
め |
ら |
み |
こ |
と |
二 |
十 |
ま |
り |
七 |
と |
せ |
に |
、 |
| ほむた(誉田)のすめらみこと(天皇)二十まり七年に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| わ |
か |
こ |
う |
ら |
な |
か |
た |
つ |
の |
み |
こ |
と |
、 |
|
|
|
|
|
| 我が子、うらなかたつ(浦長多津)の命、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| や |
ま |
ひ |
に |
ふ |
し |
て |
や |
み |
こ |
や |
せ |
り |
。 |
|
|
|
|
|
| 病に伏して病みこやせり。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
、 |
お |
ほ |
か |
み |
の |
み |
ま |
え |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 彼、大神の御前に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひ |
は |
ひ |
の |
く |
る |
る |
か |
き |
り |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 昼は日の暮るる限り(暮れるまで)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| よ |
は |
よ |
す |
か |
ら |
や |
ま |
ひ |
い |
や |
し |
た |
ま |
ひ |
|
|
|
|
| 夜は夜すがら(夜通し)、病癒し給い(病気を癒して下さい)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| な |
を |
し |
た |
ま |
ひ |
と |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 治し給いと(直してくださいと) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ね |
き |
ま |
を |
し |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ねき申ししかば(お祈り申し上げたら)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一 |
や |
ゆ |
め |
の |
こ |
と |
く |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一夜の夢の如くして、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ふ |
み |
か |
き |
た |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文を書きたりき(書き上げた)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
| さ |
え |
て |
み |
る |
に |
、 |
こ |
の |
ふ |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
| 覚めて見ると、この文なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| か |
れ |
、 |
お |
ほ |
み |
か |
み |
の |
み |
こ |
こ |
ろ |
も |
ち |
て |
、 |
|
|
| 彼、大御神の御心持ちて、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
か |
て |
に |
か |
か |
せ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 我が手に書かせ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| お |
し |
へ |
た |
ま |
へ |
し |
ふ |
み |
と |
こ |
そ |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 教え給へし文とこそ(であると)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| よ |
ろ |
こ |
ほ |
ひ |
つ |
つ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 悦びつつ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| ふ |
み |
の |
お |
し |
ひ |
の |
ま |
ま |
に |
、 |
せ |
し |
か |
は |
、 |
|
|
|
| 文の教えのままに、せしかば、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| く |
す |
し |
き |
か |
な |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奇すしきかな(不思議にも)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| や |
ま |
へ |
ひ |
に |
ひ |
に |
い |
や |
た |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
| 病いが日に日に癒(いや)されたりき(回復して行った)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
れ |
、 |
こ |
こ |
を |
も |
ち |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 彼、ここをもちて(これを持って)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| た |
み |
お |
も |
さ |
わ |
に |
す |
く |
へ |
し |
、 |
ふ |
み |
そ |
。 |
|
|
|
| 民をもさわに救えし(民をたくさん救った)、文ぞ。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| を |
み |
の |
な |
ら |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| をみのなら(?)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
み |
を |
さ |
わ |
に |
す |
く |
へ |
よ |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 民をさわに救えよ。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| こ |
の |
ふ |
み |
八 |
も |
を |
し |
る |
す |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| この文、八方(よも)を記すに、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
め |
の |
ま |
な |
か |
は |
一 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天のまなか(ま中)は一に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| に |
し |
き |
た |
の |
あ |
わ |
へ |
を |
二 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
| 西北のあわへを二に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| き |
た |
を |
三 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 北を三に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| ひ |
む |
か |
し |
き |
た |
の |
あ |
わ |
へ |
を |
四 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
| 東北のあわへを四に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひ |
む |
か |
し |
を |
五 |
に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東を五に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| ひ |
む |
か |
し |
み |
な |
み |
あ |
わ |
へ |
を |
六 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
| 東南のあわへを六に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| み |
な |
み |
を |
七 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 南を七に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| に |
し |
み |
な |
み |
の |
あ |
わ |
へ |
を |
八 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 西南のあわへを八に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| に |
し |
を |
九 |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西を九に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| し |
る |
し |
を |
く |
も |
の |
そ |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 記しおくものぞ(ものである)。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
め |
の |
み |
な |
か |
ぬ |
し |
の |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天の御中主の、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| か |
み |
は |
一 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 神は一をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
ま |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| あれますひとこまとに、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| な |
か |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中はらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
か |
み |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| たかみむすび(高皇霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| う |
わ |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上はらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
し |
か |
ひ |
ひ |
こ |
ち |
の |
か |
み |
は |
|
|
|
|
|
|
|
|
| あしかひ彦ち(葦茅彦遅)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
そ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎にぞ、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| は |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ははらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給へる神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
ま |
る |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
は |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| たまるむすび(玉留産霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| あ |
め |
の |
み |
な |
か |
ぬ |
し |
の |
か |
み |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
| 天の御中主の神と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| な |
か |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| なかはらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| い |
く |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
わ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| いくむすび(生産霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| き |
も |
の |
み |
た |
ま |
を |
わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
| きもの御魂を分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| た |
る |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
わ |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 足産霊(たるむすび)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六をうしはきまして(支配しまして)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| い |
く |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 生産霊(いくむすび)の神と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| き |
も |
の |
み |
た |
ま |
を |
わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
| きもの御魂を分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
か |
ひ |
る |
め |
の |
か |
み |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| わかひるめ(稚日霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
| お |
も |
ひ |
は |
か |
り |
の |
み |
た |
ま |
を |
わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
|
|
| 思いはかりの御魂を分け給える |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| か |
み |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| かみむすび(神産霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八 |
を |
う |
し |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 八をうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| あ |
め |
の |
み |
な |
か |
ぬ |
し |
の |
か |
み |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
| 天の御神主の神と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| な |
か |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中はらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
か |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
は |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| わかむすび(稚産霊)の神は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九 |
を |
う |
は |
き |
ま |
し |
て |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九ををうしはきまして(支配して)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| あ |
れ |
ま |
す |
ひ |
と |
こ |
と |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| た |
か |
む |
す |
ひ |
の |
か |
み |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
| 高産霊の神と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| う |
わ |
は |
ら |
の |
み |
た |
ま |
を |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| うわはらの御魂を |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| わ |
け |
た |
ま |
へ |
る |
か |
み |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 分け給える神なりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| か |
れ |
、 |
こ |
の |
九 |
の |
は |
し |
ら |
の |
か |
み |
た |
ち |
、 |
|
|
|
| 彼、この九の柱の神等(たち) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| と |
し |
こ |
と |
、 |
つ |
き |
こ |
と |
に |
、 |
み |
め |
く |
り |
ま |
し |
て |
、 |
| 年毎、月毎に、御めぐりまして、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ひ |
と |
と |
も |
に |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日と共に、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
| よ |
こ |
と |
さ |
わ |
に |
た |
ま |
へ |
る |
も |
の |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
| 夜ごとさわに給えるものなりき。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| し |
か |
あ |
れ |
と |
、 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| しかあれど(そうではあるが)、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| そ |
の |
み |
め |
く |
り |
を |
あ |
や |
ま |
ち |
お |
か |
す |
と |
き |
は |
、 |
|
| その御廻りを過ち冒す時は、 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| ま |
か |
こ |
と |
あ |
る |
も |
の |
な |
り |
き |
。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 禍事(まがごと)あるものなりき。 |


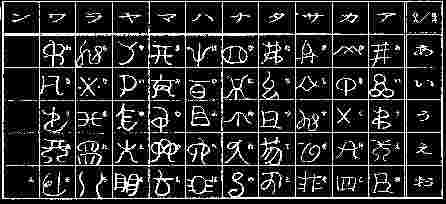
 。さ(サ)のカタカナは出雲文字の
。さ(サ)のカタカナは出雲文字の 、カタカムナ文字の
、カタカムナ文字の 。の(ノ)のひらがなは出雲文字の
。の(ノ)のひらがなは出雲文字の 。へ(へ)は出雲文字の
。へ(へ)は出雲文字の 。ほ(ホ)のカタカナはカタカムナ文字の
。ほ(ホ)のカタカナはカタカムナ文字の 。わ(ワ)のひらがなは出雲文字の
。わ(ワ)のひらがなは出雲文字の![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)