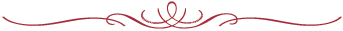「安」をくずして「あ」が生まれたように、漢字の音だけ借りて、形をくずして書いて生まれたのが平仮名です。明治33年(1900年)に「小学校令」が制定され、一つの音に対して一つのひらがなが決まるまで、ひらがなにはたくさんの種類がありました。たとえば、「阿」をくずしたもの、「愛」をくずしたもの、「悪」をくずしたもの、これらはすべて「あ」という音を示していました。現在、我々が普段使っているひらがなと異なる形の平仮名を「変体仮名(へんたいがな)」と言います。昔の戸籍には変体仮名が使われている場合がありますので、読めなくて困っている方に向けて、ひらがなの「くずし字の一覧表」をお見せします。ぜひ、この表で崩し字の読み方を確認してください。
※変体仮名の右に字母(じぼ)を示しました。字母とは平仮名のもとになった漢字のことです。